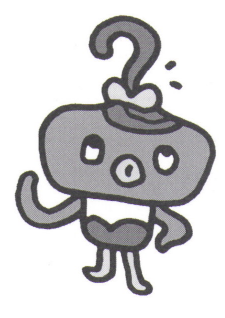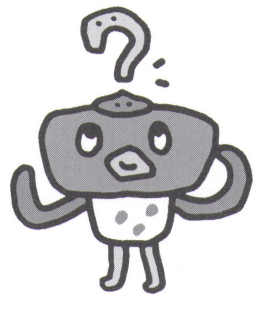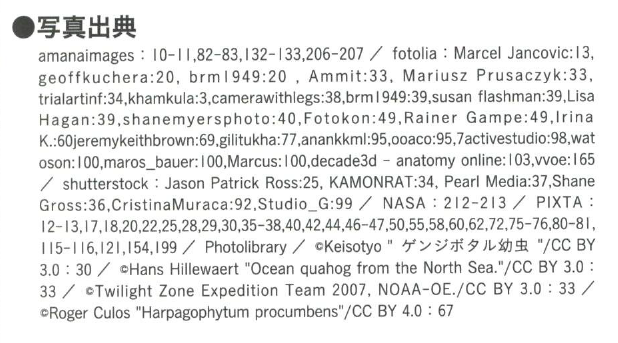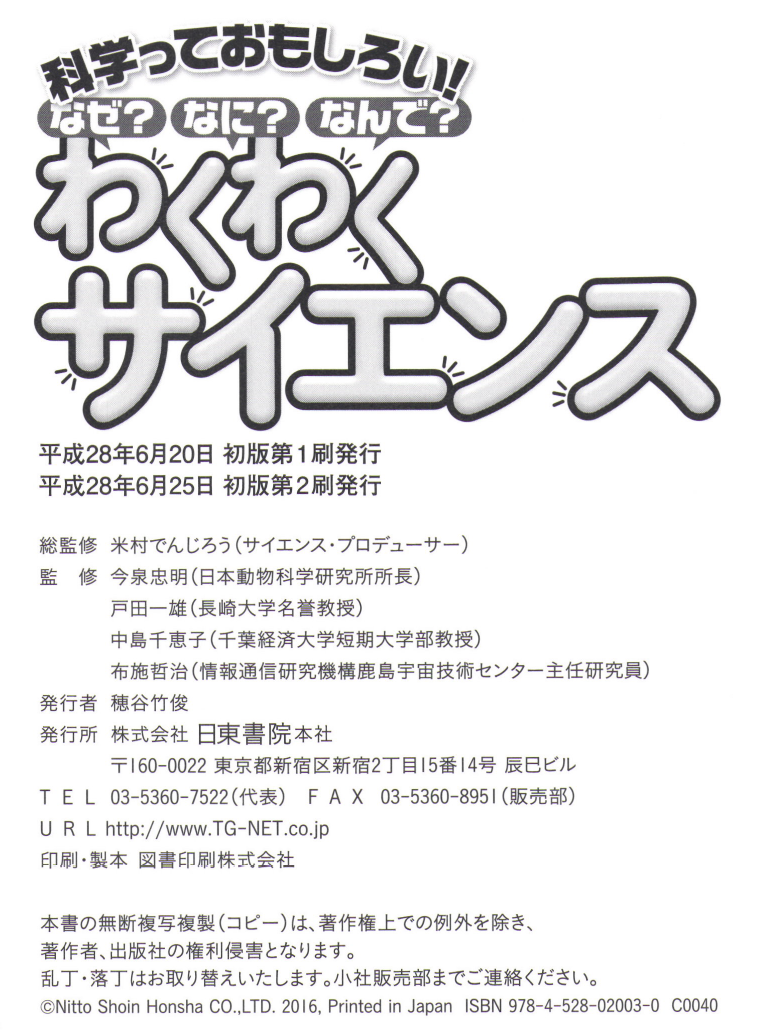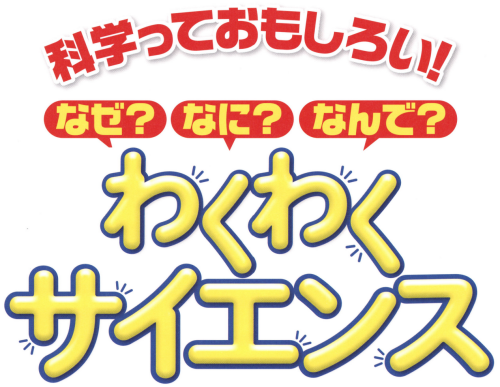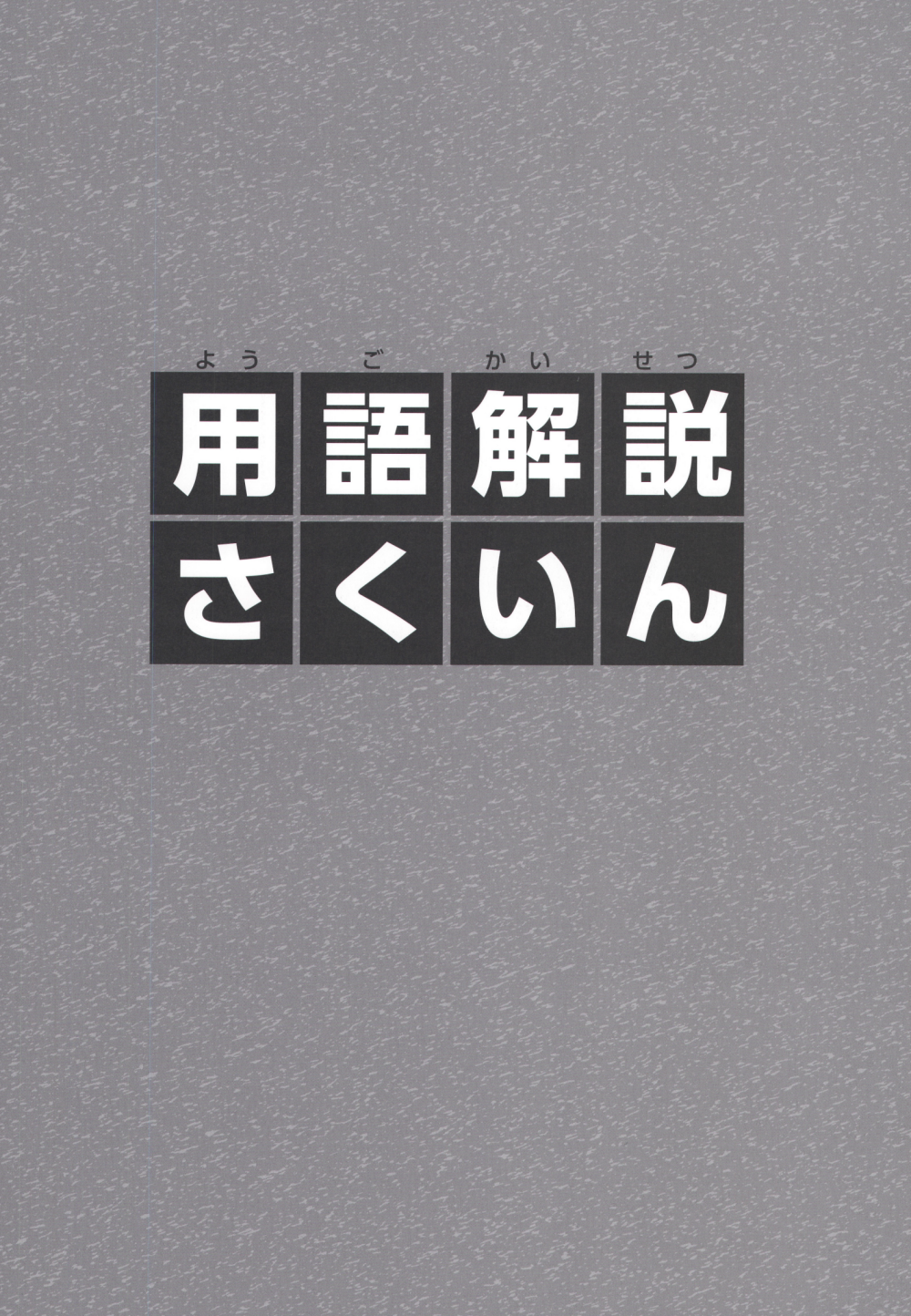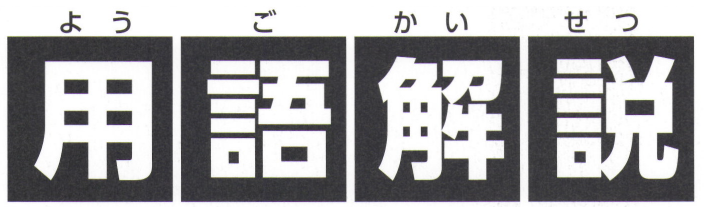科学っておもしろい! なぜ?なに?なんで?
わくわくサイエンス
子どもたちの疑問に答える…学びから体験へ…
総監修 米村でんじろう

『生き物』(動物・植物)、『体』、『地球・宇宙』、『身のまわり』(生活・命・心)の4つのジャンルから
子どもたちの身近な科学の疑問を取りあげ、解き明かす!!

米村でんじろう
(サイエンス・プロデューサー)

今泉忠明
(日本動物科学研究所所長)
戸田一雄
(長崎大学名誉教授)
中島千恵子
(千葉経済大学短期大学部教授)
布施哲治
(情報通信研究機構鹿島宇宙技術センター主任研究員)

2
遊びから体験へ!
米村でんじろう(サイエンス・プロデューサー)
遊びの中にも科学がいっぱい!!
科学というとむずかしくて苦手だなとかんじる人が多いとおもいます。でもじつは身近なところにたくさんの科学がかくれています。たとえばシャボン玉遊びをしていると、こんな疑問がわいてくるかもしれません。「シャボン玉はどうして色がつくのだろう?」「どうしてすぐにわれないのだろう?」このように、子どもたちの遊びの中にたくさんの科学の不思議がみつかります。
科学の実験を成功させるためには、たくさんの試行錯誤や工夫が必要です。同じように、あそんでいるときも、うまくいかずに「ああでもない。こうでもない」とかんがえ、工夫することでうまくできたり新しい発見があったりします。このようにかんがえたり工夫したりすることが、十分に科学の体験になっているとおもうのです。手をつかったり体をつかったり、一見科学とは関係のないような遊びの中で、科学と同じ体験をしているといえるのです。
科学をむずかしくおもわずに、あそびながら「科学ってとても身近なもの」と、楽しんでもらえればいいですね。
「なぜ?」「どうして?」 いつも疑問をもちつづけよう!!
今ではあたり前のようにしられていることも、さいしょはだれもしらないことでした。答えをしらない昔の人は「なぜ?」「どうして?」と疑問をもち、たくさんの失敗をかさねて答えをみちびきだしてきました。さいしょは、疑問をもつことからはじまったのです。そんな疑問の答えを、長い年月をかけて少しずつみつけだして現代の科学へと進歩してきたのです。
昔の人と同じように、子どもたちも「なぜ?」「どうして?」と疑問におもうことがたくさんみつかるでしょう。でも、その答えをしらないことをはずかしいとおもうかもしれませんが、そんな必要はありません。さいしょはだれもがわからないし、わからなくてあたり前なのです。それよりも「なぜ?」「どうして?」といつも疑問をもち、答えをさがしつづけることが大切なことなのです。それが、子どもたちの成長につながっていきます。ぜひ、たくさんの科学の不思議にチャレンジしてみてください。
3
学ぶこと、体験する楽しさを!!
現代では「なぜ?」「どうして?」の答えがすぐにしらべられてしまいます。しかしそれだけでわかった気にならないようにしてください。学んだ知識だけが答えではないのです。実際に体験することで、はじめてわかることがたくさんあります。
たとえば、料理のレシピをみただけで同じようにおいしい料理をつくれるようになるでしょうか? 本のとおりに上手に包丁やフライパンがつかえないときもあるとおもいます。火加減がわからないときもあるとおもいます。レシピだけではその料理の味はわかりません。実際につくってみないとわからないことがたくさんあります。
この本をよんで興味をもったもので、実践できるものはぜひやってみてください。実際にやってみるといろんな発見があるはずです。もちろん、うまくいかないこともたくさんあるでしょう。そんなときは「どうしてうまくいかないんだろう?」とかんがえて、また挑戦してみてください。
何度も何度も失敗をかさね、自分で工夫し成功したとき、それがとても楽しい体験になるはずです。そういった体験をかさねることで子どもたちが大きく成長していってくれればとおもいます。

4


「遊びから体験へ!」……2
この本のつかい方……8
 第1章 生き物のなぜ?
第1章 生き物のなぜ?
ミツバチの巣はなぜ六角形なの?……12
アメンボはなぜ水にういていられるの?……14
アリの行列はどこへいくの?……16
オンブバッタはどうしておんぶしているの?……18
カにさされると、かゆくなるのはどうして?……19
カメムシはどうしてくさいの?……20
クモは自分の巣にくっつかないの?……21
ゴキブリはどうして家の中にいるの?……22
ダンゴムシはどうしてまるくなるの?……23
セミはなぜとぶときにおしっこをするの?……24
チョウの口はどうしてまるまっているの?……26
ナミテントウにはどうしていろいろな模様があるの?……27
トンボの目はなぜ大きいの?……28
トンボの幼虫はなぜ水中でくらすの?……29
ホタルはどうしてひかるの?……30
秋になるとなく虫が多いのはなぜ?……31
昆虫には骨がないの?……32
一番長生きする生き物は何?……33
キリンとゾウのうんち、大きさがちがうのはなぜ?……34
地球上には何種類の生き物がいるの?……35
一番強い生き物は何?……36
動物は虫歯にならないの?……37
カバの口はどうして大きいの?……38
カンガルーはどうしておなかのふくろで子そだてするの?……39
クジラの赤ちゃんは海の中でどうやってお乳をのむの?……40
ゴリラがむねをポコポコたたくのはなぜ?……41
シマウマの模様は何のためにあるの?……42
パンダは竹しかたべないの?……43
イヌはどうしてあちこちにおしっこするの?……44
ネコのひげは何の役にたつの?……46
ヤギはどうして紙をたべるの?……48
ホッキョクグマはどうして氷の世界でも平気なの?……49
キツツキはどうして木をつつくの?……50
小鳥はどうしてよくなくの?……51
鳥はどうしてとべるの?……52
鳥はどんなところに巣をつくるの?……53
渡り鳥はどうしてわたってくるの?……54
カメレオンはなぜ体の色がかわるの?……55
イルカは頭がいいの?……56
イカやタコはどうしてすみをはくの?……57
ヤドカリがひっこすって本当?……58
サケがうまれた川にもどるのはなぜ?……59
ピラニアはこわい魚って本当?……60
魚もねむるの?……61
魚にも耳や鼻があるの?……62
田んぼにはなぜ水をはるの?……63
キノコは植物なの?……64
帰化植物って何?……65
木の実に赤い実が多いのはなぜ?……66
くっつき虫とよばれる実はなぜくっつくの?……67
葉はどうして緑色なの?……68
バラのとげは何のためにあるの?……70
5
サボテンにはどうしてとげがあるの?……71
マツヨイグサはどうして夜にさくの?……72
レンコンにはどうして穴があいているの?……73
カミキリムシは、髪の毛をきれるの?……74
チョウとガのちがいはどこ?……74
鳥は夜に目がみえないの?……75
オウムはなぜことばをまねるの?……75
フラミンゴはなぜかた足でたつの?……76
ニワトリはどうして朝になくの?……76
ウシはなぜ口をもぐもぐさせているの?……77
ゾウがよく水あびするのはなぜ?……77
ラクダのこぶには何がはいっているの?……78
タヌキは本当にたぬきねいりするの?……78
ヘビはどこからがしっぽなの?……79
ヤモリはどうしてかべにはりついてあるけるの?……79
パイナップルにたねはあるの?……80
落花生は土の中に実がなるの?……80
食虫植物は虫をどうやってつかまえるの?……81
植物にもオスとメスがあるの?……81
 第2章 体のなぜ?
第2章 体のなぜ?
はしると胸がどきどきするのはなぜ?……84
人の目とほかの生き物の目、どっちがすごいの?……86
目の錯覚って何?……88
耳は音をきくためだけにあるの?……90
鼻がつまると、なぜ味がわからなくなるの?……91
皮膚の色はどうしてちがうの?……92
悲しいと涙がでるのはなぜ?……93
赤ちゃんはどうしてよくなくの?……94
赤ちゃんはどうしてうまれてすぐにたてないの?……95
人はどうして2本足であるけるの?……96
あくびがうつるって本当?……97
からい物をたべると汗がでるのはなぜ?……98
子どもが親ににるのはなぜ?……99
人にはどうしてしっぽがないの?……100
どうして、人にはへそがあるの?……101
どうしてかぜをひくの?……102
予防接種って、なぜするの?……103
血液型が4種類あるのはなぜ?……104
血がでても自然にとまるのはなぜ?……105
どうして頭には髪の毛がはえているの?……106
しゃっくりがでるのはなぜ?……107
虫歯はどうしてできるの?……108
爪の根元にある白い部分は何?……109
すっぱい物をみるとつばがでるのはなぜ?……110
ぐるぐるまわると目がまわるのはなぜ?……111
1日にどのくらい息をするの?……112
自分でくすぐってもくすぐったくないのはなぜ?……113
どうしておふろにはいるの?……114
右利きと左利きは、いつ決まるの?……115
人は水がないといきられないの?……116
どうして、たべないといきられないの?……117
どうしておならがでるの?……118
指紋はみんなちがうの?……119
どうして野菜をたべないといけないの?……120
どうして人はねむるの?……121
ゆめをみるのはなぜ?……122
おなかの中には細菌がいるの?……123
どうしておねしょをしちゃうの?……124
男女の声はどうしてちがうの?……124
としをとるとはげたり、しらががはえたりするのはなぜ?……125
たんこぶはどうしてできるの?……125
どうして鳥はだがたつの?……126
6
ほくろはどうしてできるの?……126
まばたきをするのはなぜ?……127
大声をだすと力がでるって本当?……127
熱中症ってどんなもの?……128
日やけをするとはだが黒くなるのはなぜ?……128
おなかがすくとグーグーなるのはなぜ?……129
たべた後にはしるとおなかがいたくなるのはなぜ?……129
おふろで指がしわしわになるのはなぜ?……130
花粉症って何?……130
正座をするとどうして足がしびれるの?……131
かき氷をたべると頭がキーンといたくなるのはなぜ?……131
 第3章 身のまわりのなぜ?
第3章 身のまわりのなぜ?
セーターをぬぐとパチッとするのはなぜ?……134
乾電池には電気がはいっているの?……136
電気はどうやってできるの?……138
LEDと蛍光灯はどこがちがうの?……139
電子レンジでものがあたたまるのはなぜ?……140
ガスはどこからはこばれてくるの?……141
鉄でつくられた大きな船がしずまないのはなぜ?……142
すべり台をすべるとなぜおしりがあつくなるの?……143
紙はどうやってリサイクルされるの?……144
ジェットコースターはなぜさかさまでもおちないの?……146
自転車はどうしてたおれないの?……147
ブーメランはなぜもどってくるの?……148
ボールはなぜはずむの?……150
おふろのお湯はなぜ上からあつくなるの?……151
水はどうしてこおるの?……152
磁石がくっつくのはなぜ?……154
アニメーションがうごいてみえるのはなぜ?……155
ガラスはどうしてすきとおっているの?……156
望遠鏡でとおくのものが大きくみえるのはなぜ?……157
録音した声がちがってきこえるのはなぜ?……158
新幹線の先頭車両は、どうして細長いの?……159
ダイヤモンドはどうやってみがくの?……160
タイヤにみぞがあるのはなぜ?……161
花火はどうしていろいろな色があるの?……162
クレーンはどうやってビルの上にあげるの?……163
野球の変化球はなぜまがるの?……164
鉄はどうしてさびるの?……165
消しゴムでえんぴつの文字がきえるのはなぜ?……166
方位磁石はどうして北をさすの?……167
どうしてふとんをほすの?……168
布や道路がぬれると色がかわるのはなぜ?……169
お湯がわくとなぜシューシュー音がでるの?……170
冷たいコップに水滴がつくのはなぜ?……171
雪はどうしてふるの?……172
飛行機雲はどうしてできるの?……173
空気にも重さはあるの?……174
紅茶にレモンをいれると色がかわるのはなぜ?……176
たまごをゆでるとかたまるのはなぜ?……178
タマネギをきると涙がでるのはなぜ?……180
うどんの「こし」ってなに?……181
納豆はどうしてねばねばするの?……182
野菜に塩をかけると水がでてくるのはなぜ?……184
きったリンゴを塩水につけるのはどうして?……185
水と油はどうしてまざらずにわかれるの?……186
食べものは何でも冷凍できるの?……188
カビはどうしてはえるの?……189
7
ゼラチンとかんてんはどうちがうの?……190
ジャムはどうしてくさらないの?……192
人前で緊張してあがっちゃうのはなぜ?……193
暗いところや高いところがこわいのはなぜ?……194
おばあちゃんにもおばあちゃんがいたの?……195
寿命って何?……196
人は死んだらどうなるの?……197
電車でジャンプしても同じ場所におちるのはなぜ?……198
なぜリモコンでテレビがうごくの?……198
鳥はどうして電線にとまってもへいきなの?……199
さむい日に息が白くなるのはなぜ?……199
おもちはどうしてかたくなるの?……200
ポップコーンはなぜはじけるの?……200
シュガーレスの砂糖はどうしてあまくかんじるの?……201
スイカに塩をかけるのはなぜ?……201
カニやエビをゆでると赤くなるのはなぜ?……202
パンはどうしてふくらむの?……202
お医者さんはどうして白衣をきているの?……203
ウイルスって生き物なの?……203
線路にしいてある石は何のためにあるの?……204
あつい日に水をまくのはなぜ?……204
こんにゃくは何でできているの?……205
昔の人はどうやって大きな石をきったの?……205
 第4章 地球・宇宙のなぜ?
第4章 地球・宇宙のなぜ?
月の形はどうしてかわるの?……208
月食や日食がおこるのはなぜ?……209
太陽はどのくらいあついの?……210
流れ星はどうしてできるの?……211
流星群って何?……212
土星にはなぜわがあるの?……213
星はどうして夜だけひかるの?……214
星の明るさがちがうのはなぜ?……215
雷がおちるのはなぜ?……216
夕焼けが赤いのはなぜ?……217
にじはどうしてできるの?……218
梅雨って何?……220
朝日や夕日はなぜ大きくみえるの?……221
雲は何でできているの?……222
天気予報はどうやってするの?……224
夕立はどうしておこるの?……226
一番深い海はどのくらい深いの?……227
酸性雨って何?……228
台風はどうしてできるの?……229
春夏秋冬があるのはなぜ?……230
南極と北極どちらが寒いの?……231
地球の温暖化って何?……232
化石はどうやってできるの?……233
恐竜って本当にいたの?……234
恐竜の名前はどうやってつけているの?……245
天の川って何?……236
宇宙はいつできたの?……236
ブラックホールって何?……237
宇宙人はいるの?……237
しんきろうはどうしてできるの?……238
うずしおって何?……238
海の水はどうしてしおからいの?……239
オーロラって何?……239
オゾン層って何?……240
温泉はどうしてわくの?……240
用語解説……242
さくいん……246
保護者のみなさんへ……254
8
9
この本のつかい方
この本では、くらしの中で「なぜ?」「ふしぎだな?」とかんじる身近な科学の疑問の答えを紹介しています。疑問にかかわる科学実験や自然観察なども解説していますから、実際に体験してみましょう。
この本では、身近な疑問を4つのジャンルにわけています。

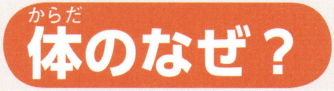

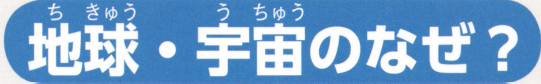


実験・観察の注意
 実験は、一度でうまくできないこともあります。あきらめずにちょうせんしてみましょう。
実験は、一度でうまくできないこともあります。あきらめずにちょうせんしてみましょう。
 実験につかう材料や道具は、最初に全部そろえてからはじめましょう。
実験につかう材料や道具は、最初に全部そろえてからはじめましょう。
※「用意するもの」では、主にそろえるものを表記してあります。必要なものがあれば、工夫して準備してください。
 はさみやカッターナイフ、包丁などの刃物をつかうときは、けがをしないように注意しましょう。むずかしいときは、おとなの人にてつだってもらいましょう。
はさみやカッターナイフ、包丁などの刃物をつかうときは、けがをしないように注意しましょう。むずかしいときは、おとなの人にてつだってもらいましょう。
 火や熱湯をつかう実験は、かならずおとなの人と一緒にやりましょう。
火や熱湯をつかう実験は、かならずおとなの人と一緒にやりましょう。

この本にでてくる単位のあらわし方です。
 長さ・大きさ
長さ・大きさ
(ミリメートル)
(センチメートル)…
(メートル)…
(キロメートル)…
 重さ
重さ
(グラム)
(キログラム)…
(トン)…
 体積
体積
(ミリリットル)
(リットル)…
 温度
温度
℃(度)…摂氏
 割合
割合
%(パーセント)…全体をとした場合に、その中にしめる割合。
10
11
第1章 生き物のなぜ?
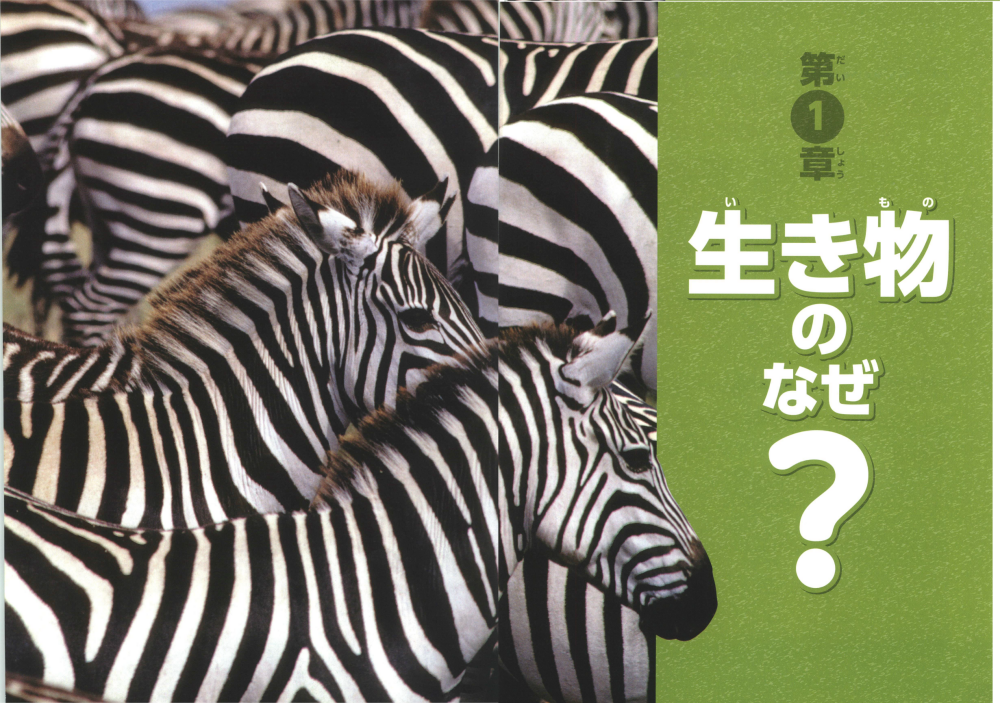
12
ミツバチの巣はなぜ六角形なの?
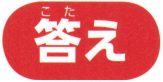 軽くがんじょうで、たくさんの部屋がつくれる形だから
軽くがんじょうで、たくさんの部屋がつくれる形だから
 ミツバチの巣のような、たくさんの六角形をすき間なくならべたつくりのことを「ハニカム構造」といいます。ハニカム構造は、いろいろなすぐれたところをもっています。
ミツバチの巣のような、たくさんの六角形をすき間なくならべたつくりのことを「ハニカム構造」といいます。ハニカム構造は、いろいろなすぐれたところをもっています。
まず、おされる力に強いことです。六角柱は上からの力ははねかえし、横からの力は吸収しやすい形です。そのため、巣ががんじょうにつくれます。
つぎに、上手に空間をつかえることです。同じ形をたくさんしきつめたとき、六角形は、むだなすき間ができません。つまり、たくさんの部屋がつくれます。
それから、巣につかう材料が少なくてすみます。巣をつくる作業がらくになるうえに、軽い巣をつくれます。
 ミツバチの巣。
ミツバチの巣。

 円形だとすき間ができるが、六角形ならすき間ができない。
円形だとすき間ができるが、六角形ならすき間ができない。
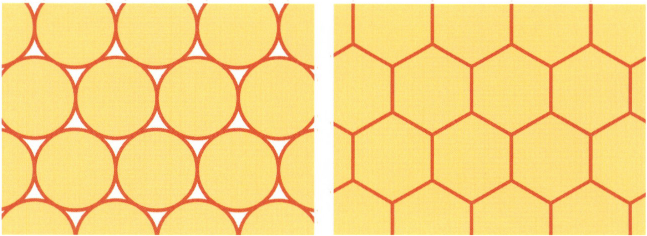
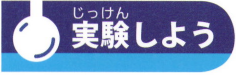 シャボン玉で六角形をつくろう
シャボン玉で六角形をつくろう
シャボン玉をたくさんくっつけて、ハニカム構造がどんなふうにできるかをみてみよう。
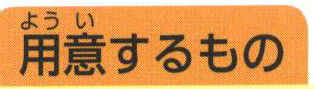
台所用洗剤、水、ストロー、食品トレイなどの底がたいらであさい容器
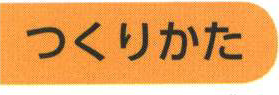
①台所用洗剤と水をまぜて、シャボン液をつくる。
②食品トレイにシャボン液をいれ、ストローで息をふきこみ、シャボン玉をつくる。なるべく同じ大きさになるようにつくろう。
③くっついた真ん中のシャボン玉は、どんな形になっているかな?
 シャボン玉に六角形がみえる。
シャボン玉に六角形がみえる。
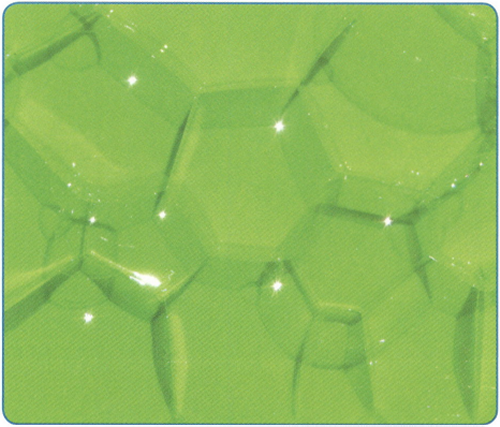
 どうして六角形になったの?
どうして六角形になったの?
シャボン玉がまるくなるのは、「表面張力」という、できるだけ表面をへらそうとする力がはたらくからです。この実験のシャボン玉もまるくなろうとしますが、となりとくっつきあい、その部分にかべができます。シャボン玉が7つくっつきあった場合、真ん中のシャボン玉のかべは六角形になります。また、シャボン液をつけた透明な板を上からかぶせると、シャボン玉がつぶれて、より六角形になります。
3
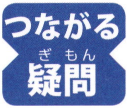 ミツバチは何をつかって巣をつくるの?
ミツバチは何をつかって巣をつくるの?
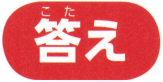 ミツロウをつかいます
ミツロウをつかいます
 ミツバチは、おなかにある8つの分泌腺から、うすい紙のようなミツロウをだします。それをあしで口まではこび、さらに口でかみながらこねます。これが巣の材料になります。
ミツバチは、おなかにある8つの分泌腺から、うすい紙のようなミツロウをだします。それをあしで口まではこび、さらに口でかみながらこねます。これが巣の材料になります。
ミツバチはみんなで協力して、六角形の部屋をたくさんつくります。ミツロウはかわくととてもじょうぶになります。
 ミツロウをこねるミツバチ。
ミツロウをこねるミツバチ。

 花にきたミツバチをみてみよう
花にきたミツバチをみてみよう
 ミツバチはふつうの胃のほかに、花のみつをはこぶための「みつ胃」をもっています。花にきたミツバチは、長い舌をだして花のおくにあるみつをすいこみ、みつ胃にためています。
ミツバチはふつうの胃のほかに、花のみつをはこぶための「みつ胃」をもっています。花にきたミツバチは、長い舌をだして花のおくにあるみつをすいこみ、みつ胃にためています。
また、同時に花粉もあつめます。花粉は、後ろあしのまわりにまるくつけられます。
ミツバチはこれらを巣にもちかえり、みんなの食べ物や、冬にむけてのたくわえにします。
 花粉は後ろあしにまるくつき、「花粉だんご」とよばれる。
花粉は後ろあしにまるくつき、「花粉だんご」とよばれる。

 ミツバチはさします。おしりのはりは産卵管が変化したもので、女王バチ以外のメス、つまりハタラキバチがもっています。はりは、さすとぬけないしくみで、さしたハチはおしりがちぎれて死んでしまいます。
ミツバチはさします。おしりのはりは産卵管が変化したもので、女王バチ以外のメス、つまりハタラキバチがもっています。はりは、さすとぬけないしくみで、さしたハチはおしりがちぎれて死んでしまいます。
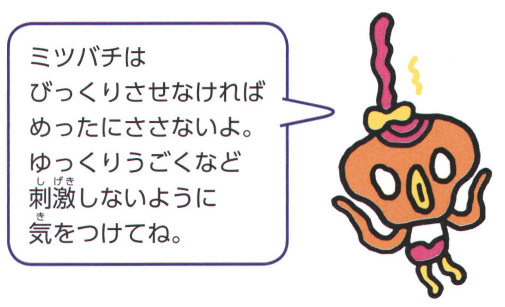
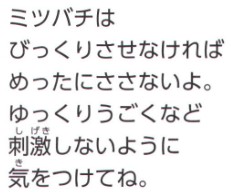
 ミツバチの天敵はスズメバチです。ときにオオスズメバチはミツバチの巣をおそい、ミツバチやその幼虫を食料にします。
ミツバチの天敵はスズメバチです。ときにオオスズメバチはミツバチの巣をおそい、ミツバチやその幼虫を食料にします。
もともと日本にすむニホンミツバチは、オオスズメバチをむかえうつことができます。巣の偵察にやってきたオオスズメバチを、ミツバチたちは集団でボールのようにとりかこみます。そして羽をうごかして中の温度をあげて、オオスズメバチを熱でころしてしまうのです。
ところが、ハチミツをあつめる目的でヨーロッパから輸入されたセイヨウミツバチは、オオスズメバチとたたかうための、特別なわざをもっていません。そのため、オオスズメバチがやってくると、巣は全滅してしまいます。
 強力なあごをもつオオスズメバチ。
強力なあごをもつオオスズメバチ。

14
アメンボはなぜ水にういていられるの?
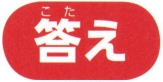 軽い体と、水をはじくあしをもっているから
軽い体と、水をはじくあしをもっているから
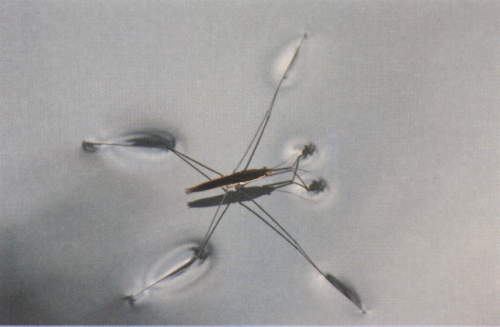
 池などで見かけるアメンボは、水の上にじっとしていてもしずみません。これには大きく3つの理由があります。
池などで見かけるアメンボは、水の上にじっとしていてもしずみません。これには大きく3つの理由があります。
1つ目の理由は、アメンボの体がとても軽いこと。胴もあしも細く、ボリュームのない体つきです。
2つ目は、水をはじく細長いあしをもっていることです。水とふれるあし先には、水をはじく細かい毛があります。毛には、体からでるあぶらをつけていて、水をはじきます。
そして3つめの理由が、水のもつ性質です。水は、水同士でまとまろうとする性質が強いのです。そのため水面は、水がおたがいをひっぱりあっていて、まるでまくをはったような状態になっています。
アメンボのあしがふれた水の部分をみてみると、そこだけ、へこんでいるようにみえますね。アメンボは、上手にあしをうごかして、水面のまくをやぶらずにういているのです。
 アメンボのあし。
アメンボのあし。
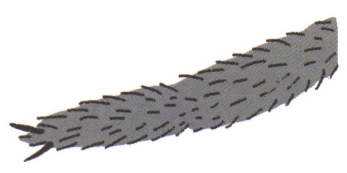
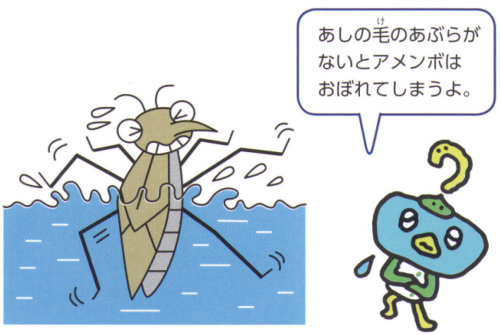
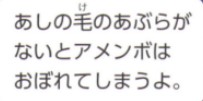
 3つめの理由――水のもつ性質「表面張力」
3つめの理由――水のもつ性質「表面張力」
水などで、その表面を小さくしようと分子同士がひきあう力を表面張力といいます。
ハスの葉にのった水滴がまるくなるのも、この力によるものです。
水の表面張力を弱くするには、水に洗剤をいれます。洗剤の分子が水とつながり、水面の水の分子のむすびつきを弱くしてしまうのです。

 水の分子がつながっているので、ものが水中にはいるのをふせいでいる。
水の分子がつながっているので、ものが水中にはいるのをふせいでいる。
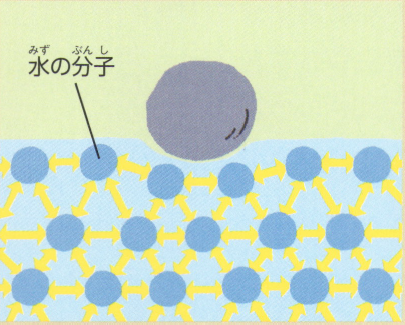
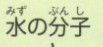
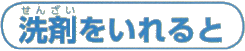
 水面の水のつながりがやぶられ、簡単にものが水中にしずむ。
水面の水のつながりがやぶられ、簡単にものが水中にしずむ。
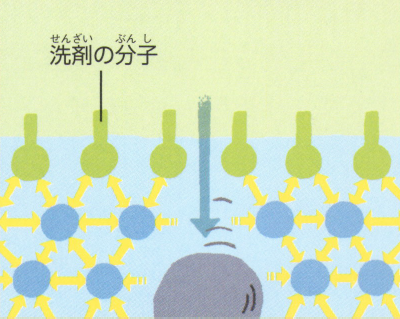
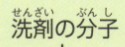
15
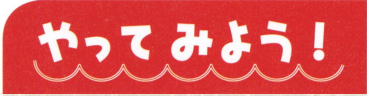 モールでアメンボをつくろう!
モールでアメンボをつくろう!

モール2本、防水スプレー
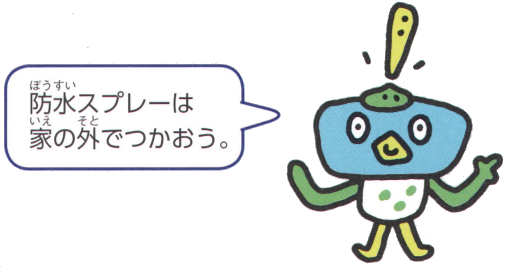
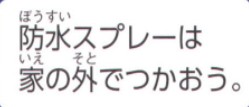

①モール2本をあわせて真ん中から両はしによじり胴体の部分をつくる。
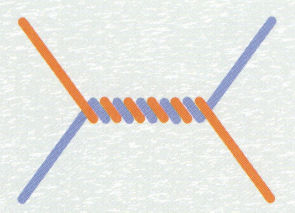
②それぞれあしを2本ずつ同じ方向へむけてまげ、ひろげる。
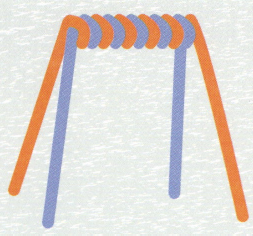
③4本のあしが地面と平らになるように形をととのえ、あしに防水スプレーをふきかける。
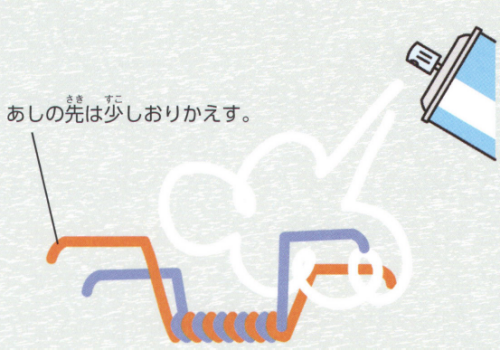
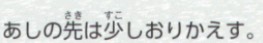

水をいれた洗面器に、モールアメンボをうかべましょう。あしを水面と並行にして、そっとおくのがポイントです。成功したら、いろいろなアメンボをつくってみましょう。
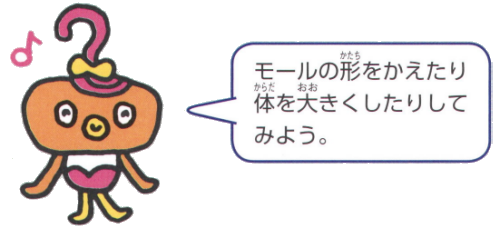
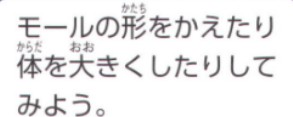
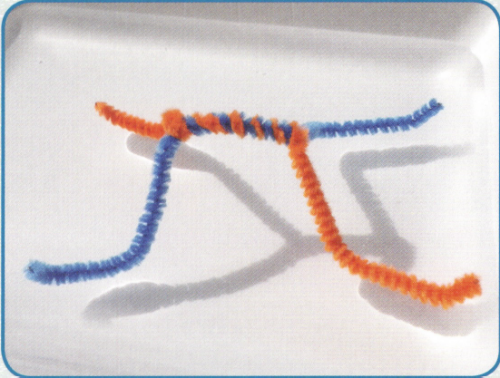

 アメンボのあしを長くしてやってみよう。
アメンボのあしを長くしてやってみよう。
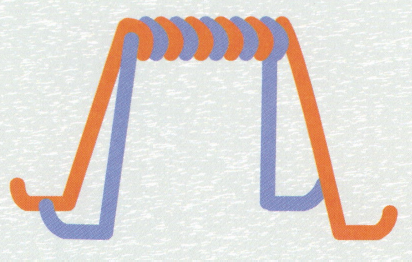
 胴体にクリップをつけて重くしてみよう。
胴体にクリップをつけて重くしてみよう。
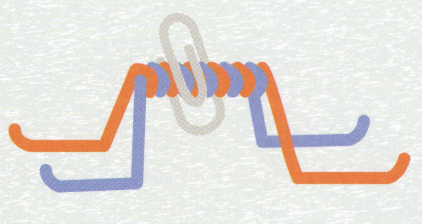
 洗面器の水に洗剤をいれるとどうなるかな?
洗面器の水に洗剤をいれるとどうなるかな?
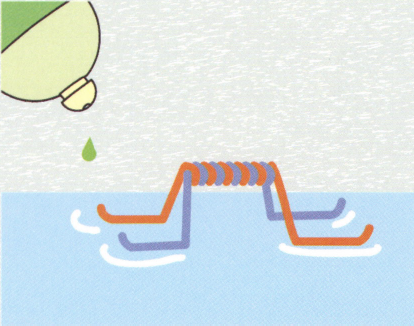
16
アリの行列はどこへいくの?
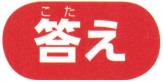 地下につくった巣の入り口へ食べ物をはこびます
地下につくった巣の入り口へ食べ物をはこびます
 アリは、巣を地面の下につくり、集団でくらす昆虫です。
アリは、巣を地面の下につくり、集団でくらす昆虫です。
一家は女王アリを中心につくられ、さまざまな役割をもつアリがいます。わたしたちがよく目にするのは、食べ物をあつめるために巣のまわりでうごきまわるハタラキアリたちです。
ハタラキアリは、自分だけではもちきれない食べ物をみつけると、ひとまず巣にかえり、なかまのアリにしらせます。そして、そのしらせをきいたたくさんのハタラキアリたちが、その食べ物へむかい、巣へともちかえります。このときに行列ができるのです。
 そのほか、みんなで新しい巣へひっこすときも、行列をつくります。
そのほか、みんなで新しい巣へひっこすときも、行列をつくります。
 大きなえものはなかまと一緒にはこぶ。
大きなえものはなかまと一緒にはこぶ。

 巣の中には、食べ物をためておく部屋もある。
巣の中には、食べ物をためておく部屋もある。
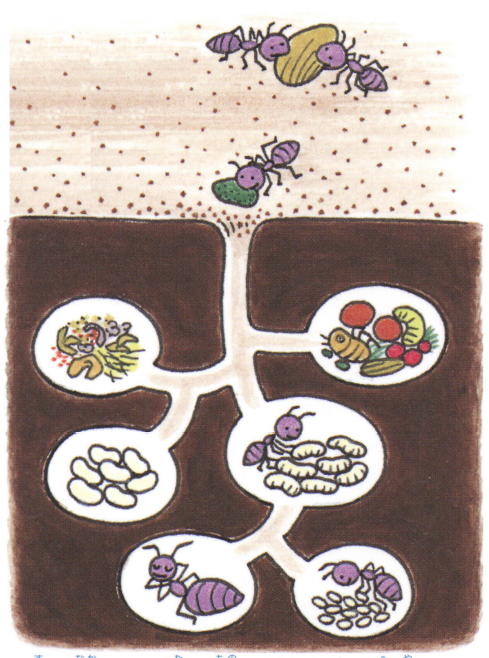
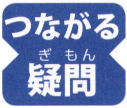 どうして食べ物と巣の場所がわかるの?
どうして食べ物と巣の場所がわかるの?
 道に道しるべをつけています
道に道しるべをつけています
 食べ物をみつけたハタラキアリは、巣にかえるときおしりから一家共通のにおいのする液をだし、道につけていきます。雨がふったあとでも、アリはこのにおいをかんじることができます。
食べ物をみつけたハタラキアリは、巣にかえるときおしりから一家共通のにおいのする液をだし、道につけていきます。雨がふったあとでも、アリはこのにおいをかんじることができます。
 においでなかまに道をおしえるので、この液は「道しるべフェロモン」とよばれる。
においでなかまに道をおしえるので、この液は「道しるべフェロモン」とよばれる。

 アリの行列をつくろう
アリの行列をつくろう
アメなどをアリの巣の近くにおいて、行列ができるかみてみましょう。アリの行列ができたら、行列の途中にじゃまになるものをおいてみましょう。アリたちはどんな行動をとるでしょうか? 行列は同じ道につながるでしょうか?
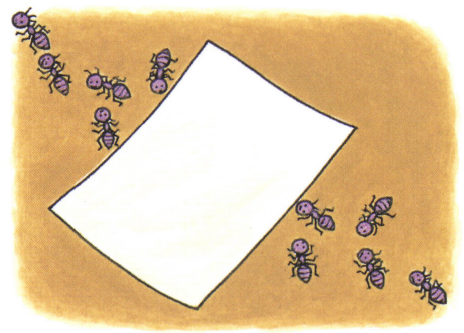
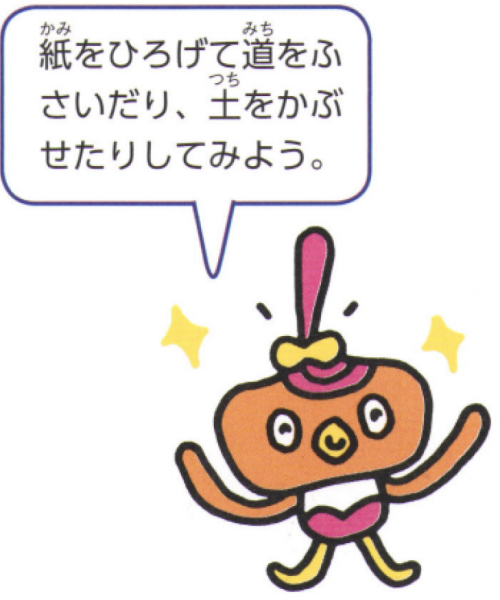
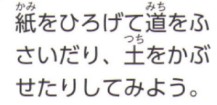
17
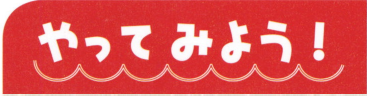 アリを観察できる巣箱をつくろう
アリを観察できる巣箱をつくろう

炭酸飲料系のペットボトル、空きカン、ハサミ、テープ、ガーゼ、輪ゴム、カッターナイフ

巣箱につかうのは、表面にでこぼこのないペットボトルがむいています。透明で、中のようすをよくみることができ、ハサミでもきりやすいからです。
容器の準備ができたら、10ぴきほどのハタラキアリをつかまえてきて中にいれます。かならず1か所から同じ巣のなかまをあつめること。土はその場所からアリと一緒にもってくるか、ペット飼育用の砂をべつに用意します。
①ペットボトルをハサミできる。きりにくいときは、最初にカッターナイフで切れ目をいれよう。
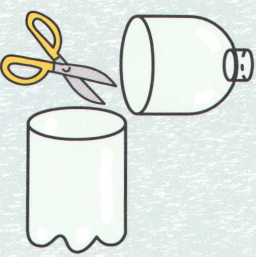
②きった下の容器の中央に空きカンをおいて、そのまわりに土をいれる。

③上の容器を下にかぶせる。すきまがあるときはまわりをテープでとめる。
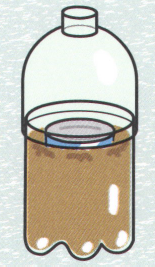
④口の部分からアリをいれ、小さくきったガーゼをかぶせて輪ゴムでとめる。数日しずかにしておく。ボトルはあまりうごかさないようにしよう。ボトルをもつときは底部のかたい部分をもとう。
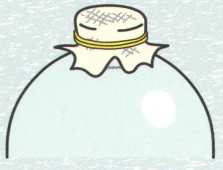
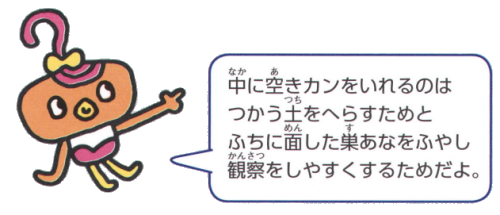
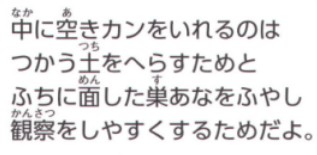
 アリの巣を観察しよう
アリの巣を観察しよう
巣箱にアリをいれたら、巣を暗くてしずかな場所へおき、あまりうごかさないようにしましょう。しばらくすると、アリは巣をほりはじめます。どんなふうに巣がひろがっていくでしょうか。毎日みて、記録していくといいですね。
えさは、お菓子のかけらなどをあげます。

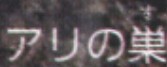


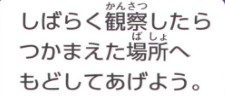
 女王アリのいない巣
女王アリのいない巣
この巣箱は短い期間の観察用です。ハタラキアリは巣をつくりますが、この巣には女王アリがいないので、子そだてのようすなどはみられません。
 野生では女王アリがつぎつぎとたまごをうみ、巣がひろがっていく。
野生では女王アリがつぎつぎとたまごをうみ、巣がひろがっていく。

18
オンブバッタはどうしておんぶしているの?
 オスがメスにおぶさって、たまごをうむときをまっています
オスがメスにおぶさって、たまごをうむときをまっています

 オンブバッタは、下にいる大きなほうがメスで、おぶさっているのがオスです。
オンブバッタは、下にいる大きなほうがメスで、おぶさっているのがオスです。
オンブバッタのオスは、メスをみつけると、交尾をするため、せなかにとびのります。ほかのバッタのなかまは、交尾がおわると2ひきははなれますが、オンブバッタのオスは、ずっとおぶさったままです。オスは、メスが産卵するまでくっついています。
おぶさったオスは、ほかのオスがメスに近づかないようにみはっているのです。最後に交尾したオスの子どもがうまれることが多いからです。

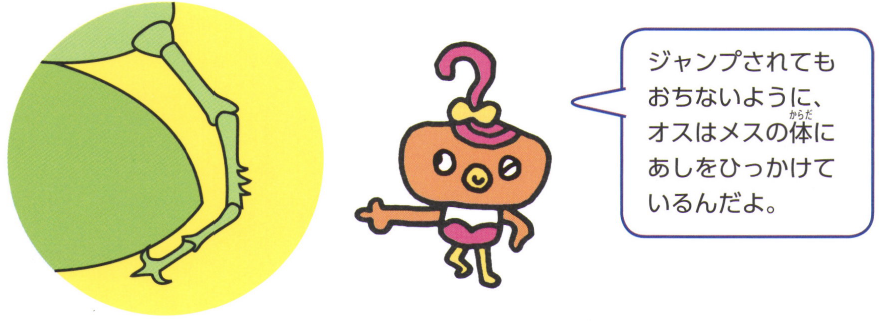
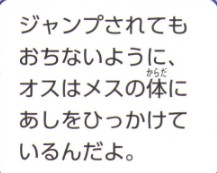
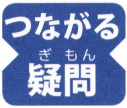 どうしてメスのほうが大きいの?
どうしてメスのほうが大きいの?
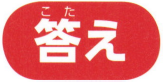 メスが大きいほうがたくさんの子孫をのこせるから
メスが大きいほうがたくさんの子孫をのこせるから
 ライオンなどの動物は、ライバルとの競争にかった、大きくて強いオスが、その子孫をのこしていきます。
ライオンなどの動物は、ライバルとの競争にかった、大きくて強いオスが、その子孫をのこしていきます。
一方バッタなどの昆虫は、たくさんのたまごをうんで、その中の一部の子どもがそだっていきます。その場合、なるべくたくさんのたまごをうめるほうが有利です。そのため、昆虫などはメスの体が大きいものが多いようです。
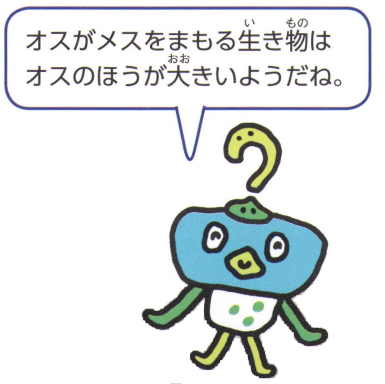
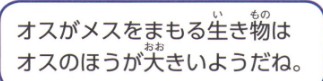
 カマキリのオス(下)とメス(上)。
カマキリのオス(下)とメス(上)。
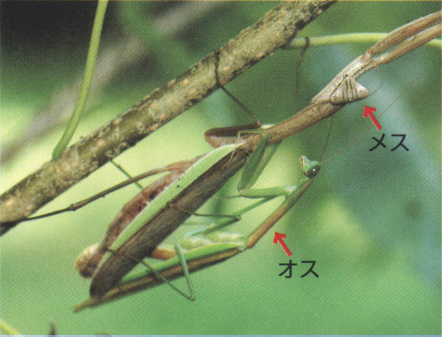


 クモのオスとメス。
クモのオスとメス。
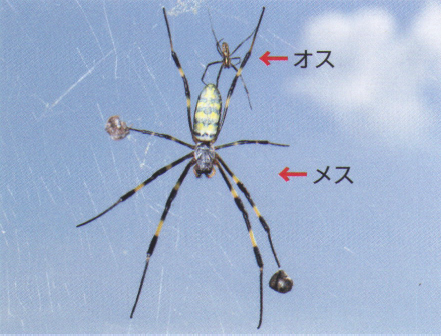


 イナゴのオス(上)とメス(下)。
イナゴのオス(上)とメス(下)。
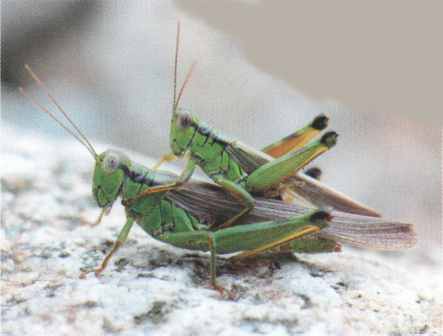
19
カにさされると、かゆくなるのはどうして?
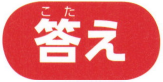 カのだすだ液が、かゆみのもとになっています
カのだすだ液が、かゆみのもとになっています
 カは、人から血をすうとき、まず自分のだ液を皮膚に注射します。
カは、人から血をすうとき、まず自分のだ液を皮膚に注射します。
このだ液には、さされたことを人に気づかれにくくするための麻酔の成分や、すっている血がかたまらないようにする成分がはいっています。
カのだ液が人の体の中にはいると、人の体は、はいってきた不審物から身をまもろうとします。これがアレルギー反応です。つまりかゆくなるのは、体がアレルギー反応をおこしているのです。
 カが一回ですうことができる血の量は、自分の体重と同じくらい。とまってからすいおわるまでかかる時間は、じゃまがなければおよそ2分30秒。
カが一回ですうことができる血の量は、自分の体重と同じくらい。とまってからすいおわるまでかかる時間は、じゃまがなければおよそ2分30秒。

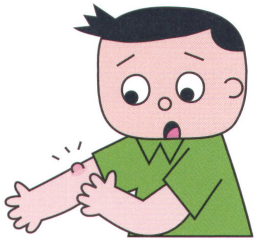
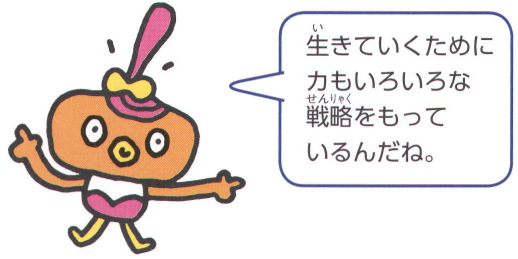
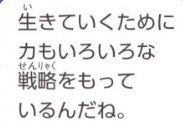
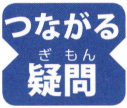 どうしてカは血をすうの?
どうしてカは血をすうの?
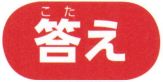 たまごをうむための栄養として、すいます
たまごをうむための栄養として、すいます
 ふだんカがすっているのは、血ではなく、植物のしるや、花のみつなどです。
ふだんカがすっているのは、血ではなく、植物のしるや、花のみつなどです。
血をすいにくるのは、これからたまごをうむメスのカだけです。オスのカはまったく血をすいません。メスはたまごをうむため、たくさんの栄養がいるのです。
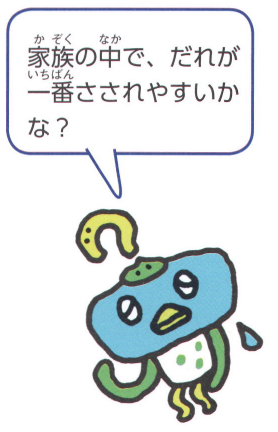
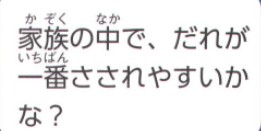
20
カメムシはどうしてくさいの?
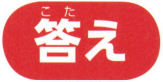 敵から身をまもるため
敵から身をまもるため
 カメムシは、敵におそわれそうになるなど、危険をかんじると、後ろあしのつけ根にある臭腺から、いやなにおいをだします。においによって、敵から身をまもっているのです。このにおいは、手などにつくと、いくらあらっても1日くらいはおちないほど強いものです。
カメムシは、敵におそわれそうになるなど、危険をかんじると、後ろあしのつけ根にある臭腺から、いやなにおいをだします。においによって、敵から身をまもっているのです。このにおいは、手などにつくと、いくらあらっても1日くらいはおちないほど強いものです。
また、むれでいるとき、その中の1ぴきがにおいをだすと、危険をしらせるために、ほかのカメムシたちもつぎつぎとにおいをだします。
 なかまのカメムシをよぶときにも、においがつかわれます。このときのにおいは、敵をおいはらうときより弱いものです。
なかまのカメムシをよぶときにも、においがつかわれます。このときのにおいは、敵をおいはらうときより弱いものです。
 においをだすのは一部のカメムシのなかまです。においをださないものも、たくさんいます。
においをだすのは一部のカメムシのなかまです。においをださないものも、たくさんいます。
 チャバネアオカメムシ
チャバネアオカメムシ

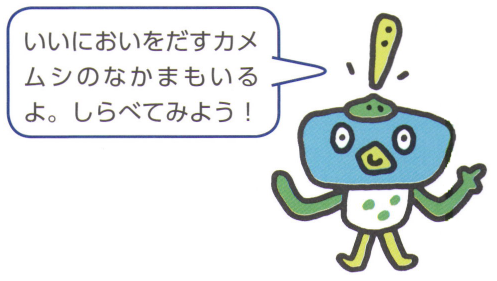
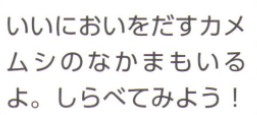
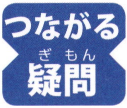 においで身をまもる生き物はほかにもいる?
においで身をまもる生き物はほかにもいる?
 いろいろななかまがいます
いろいろななかまがいます
 いやなにおいは、いやなこととして敵の頭にのこります。つまり、敵におそわれたときに役にたつだけでなく、その後においても、ねらわれにくくなります。においをうまく利用した、生き物たちのかしこい戦略です。
いやなにおいは、いやなこととして敵の頭にのこります。つまり、敵におそわれたときに役にたつだけでなく、その後においても、ねらわれにくくなります。においをうまく利用した、生き物たちのかしこい戦略です。


 敵にねらわれると、体をまるめて舌をだし、死んだふりをしてうごかなくなる。このとき、くさった肉のようなにおいをだすので、敵はえものへの興味をなくし、さっていく。
敵にねらわれると、体をまるめて舌をだし、死んだふりをしてうごかなくなる。このとき、くさった肉のようなにおいをだすので、敵はえものへの興味をなくし、さっていく。


 「ヘッピリムシ」の別名をもつ。危険をかんじると、おしりの先から100℃以上にもなるきり状のくさいガスを、大きな音とともにいきおいよくふきつける。ねらいはかなり正確で、連続発射もできる。
「ヘッピリムシ」の別名をもつ。危険をかんじると、おしりの先から100℃以上にもなるきり状のくさいガスを、大きな音とともにいきおいよくふきつける。ねらいはかなり正確で、連続発射もできる。


 アゲハチョウの幼虫は、敵におそわれると、頭とむねの間から臭角というふたまたの角をだす。この角は赤や黄色のはでな色でいやなにおいがするため、敵はおどろくのと同時に、たべる気をなくしてしまう。
アゲハチョウの幼虫は、敵におそわれると、頭とむねの間から臭角というふたまたの角をだす。この角は赤や黄色のはでな色でいやなにおいがするため、敵はおどろくのと同時に、たべる気をなくしてしまう。


 肛門から出ている2本の管から、おならではなく、黄色いあぶら状の液を3~4mもとばす。液はとても強力なにおいで、ついたものにしみつき、石けんなどであらっても1か月くらいはとれない。
肛門から出ている2本の管から、おならではなく、黄色いあぶら状の液を3~4mもとばす。液はとても強力なにおいで、ついたものにしみつき、石けんなどであらっても1か月くらいはとれない。
21
クモは自分の巣にくっつかないの?
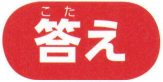 ねばらないたて糸をつたってあるいています
ねばらないたて糸をつたってあるいています
 クモの巣の糸を指でそっとさわると、ねばらない糸があることに気がつくとおもいます。ねばるのはぐるぐるとはられた横糸だけで、たて糸はねばらないのです。
クモの巣の糸を指でそっとさわると、ねばらない糸があることに気がつくとおもいます。ねばるのはぐるぐるとはられた横糸だけで、たて糸はねばらないのです。
クモはたて糸をつたって巣の上をあるきます。もし横糸にあしがふれたとしても、クモのあしにはべとつきをかわしやすいあぶらがついていて、からみにくくなっています。

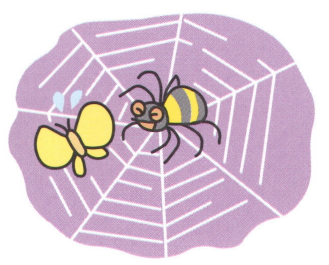
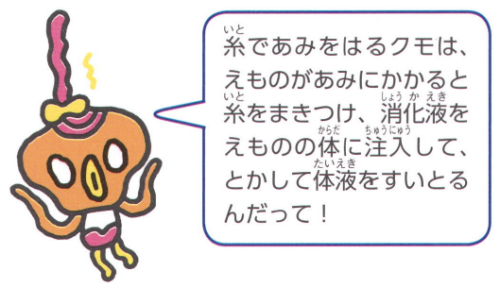
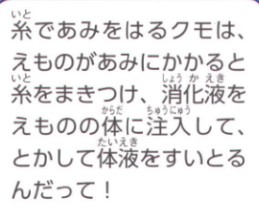
 横糸にはべとべとする液体がついている。たて糸は太く、よくのびる。
横糸にはべとべとする液体がついている。たて糸は太く、よくのびる。
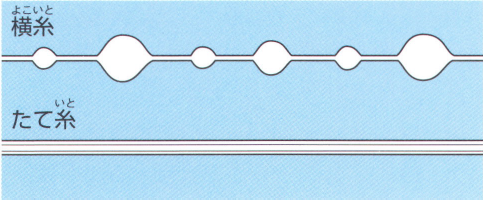


 クモの巣のつくりかた
クモの巣のつくりかた
体の小さなクモですが、どんなふうにして大きなあみをはっていくのでしょう。あみのできていくようすをみてみましょう。機会があれば、実際にクモの作業がみられるといいですね。
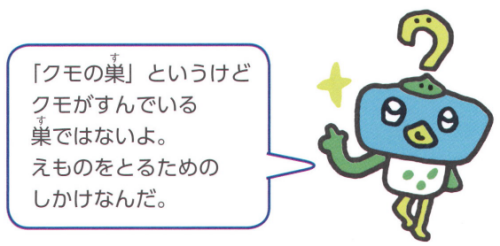
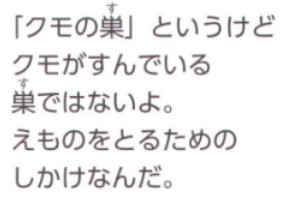
①ねらった場所にむけ、糸を風にながす。
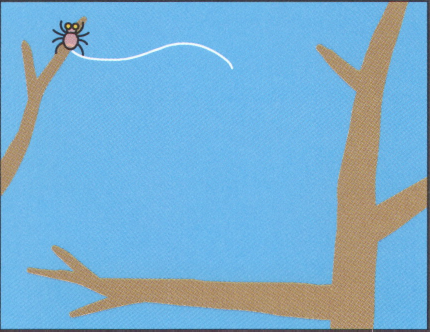
②ひっかかった糸をもとに橋糸をわたす。
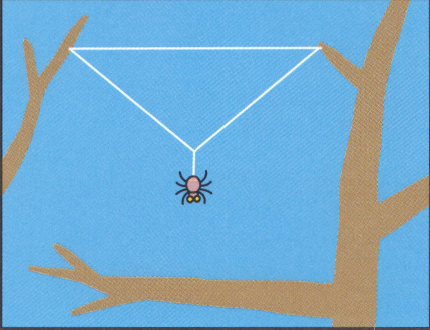
③わく糸とたて糸をはっていく。
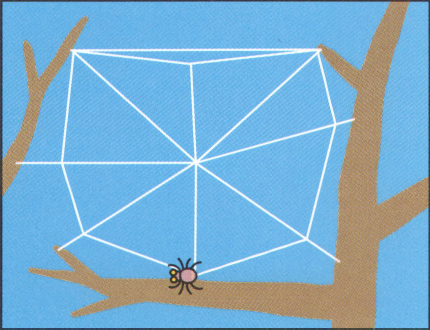
④中心からねばらない糸をはり、あし場にする。
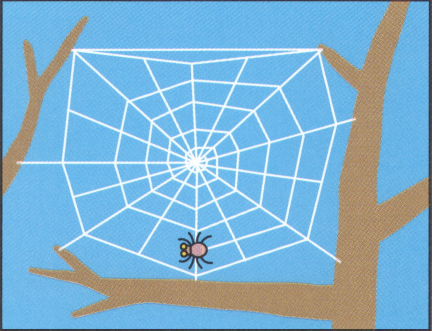
⑤外からあし場の糸をはずしつつ横糸をはる。
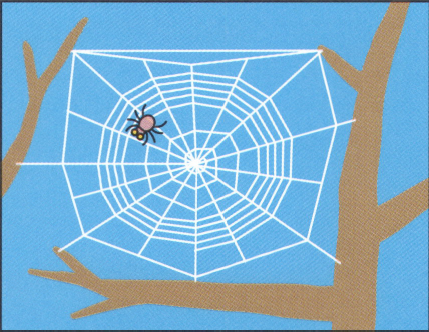
⑥あみのできあがり。
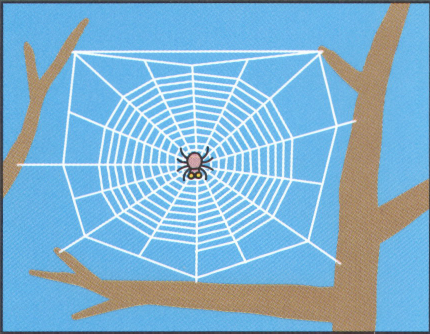
22
ゴキブリはどうして家の中にいるの?
 くらしやすいから
くらしやすいから
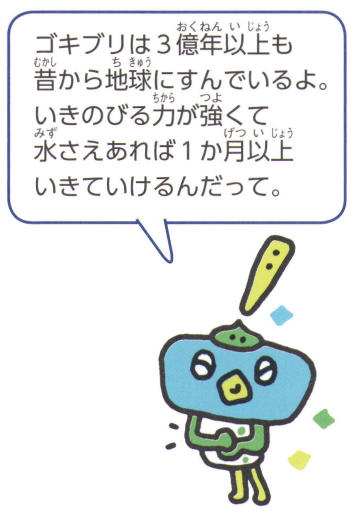
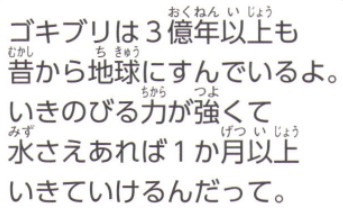
 日本には、およそ60種類のゴキブリがいます。しかしほとんどのゴキブリは、森など野外でくらしています。人の家にはいってくるのはそのうちの数種類です。
日本には、およそ60種類のゴキブリがいます。しかしほとんどのゴキブリは、森など野外でくらしています。人の家にはいってくるのはそのうちの数種類です。
ゴキブリは、人の家からでるにおいにひかれてやってきます。家の中は野外よりあたたかく、湿り気もあり、水や食べ物がたくさんあります。さらに、鳥などの敵にもおそわれないので、ゴキブリにとってくらしやすい場所なのです。
すみやすい家にはゴキブリは巣をつくって家族をふやします。そうすると家の中でよくみかけるようになります。
ゴキブリは、昼間は冷蔵庫のうらなど、あたたかく、暗い場所にいます。そういうところが大すきなのです。暗くなると水や食べ物をさがして、台所などにでてきます。
 林にすむヒメクロゴキブリ。
林にすむヒメクロゴキブリ。

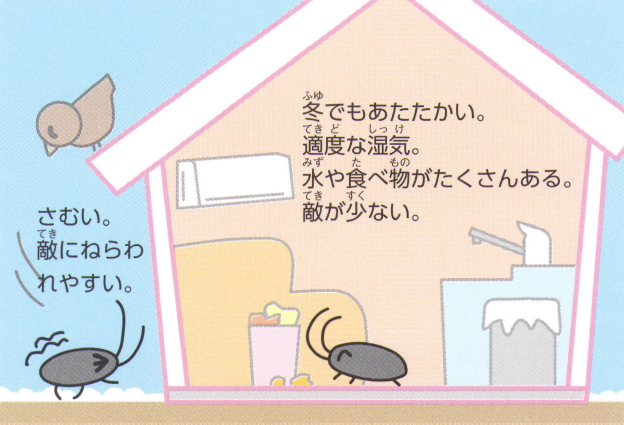
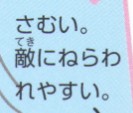
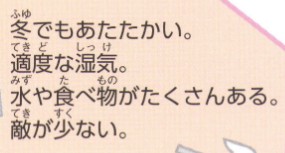
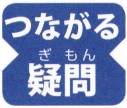 ゴキブリの苦手なものは何?
ゴキブリの苦手なものは何?
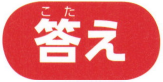 家の中の一番の敵は人間です
家の中の一番の敵は人間です
 ゴキブリが家の中でであう一番の敵は、やはり人間でしょう。わたしたちは、不潔なゴキブリをきらい、さまざまな方法で退治しようとします。そのほかでは、飼いネコにつかまったり、ヤモリやアシダカグモにたべられたりします。
ゴキブリが家の中でであう一番の敵は、やはり人間でしょう。わたしたちは、不潔なゴキブリをきらい、さまざまな方法で退治しようとします。そのほかでは、飼いネコにつかまったり、ヤモリやアシダカグモにたべられたりします。
また、レモンやトウガラシ、ミントなどのハーブのにおいをきらうようです。
 ネコ
ネコ

 レモン
レモン

 トウガラシ
トウガラシ
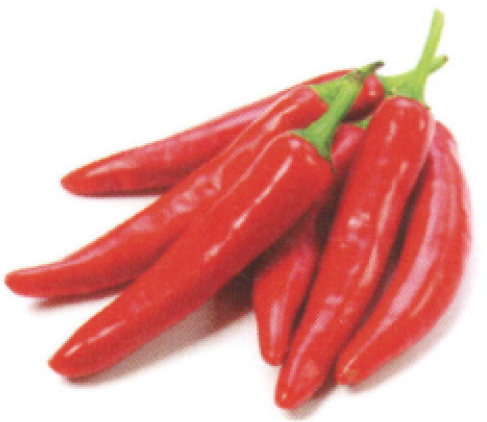
 ミント
ミント

 アシダカグモ
アシダカグモ

23
ダンゴムシはどうしてまるくなるの?
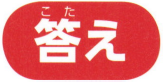 おなかと頭をまもるため
おなかと頭をまもるため
 ダンゴムシを指でさわると、体をまるめ、ボールのようなきれいな球形になります。なぜそんなかっこうになるのでしょう?
ダンゴムシを指でさわると、体をまるめ、ボールのようなきれいな球形になります。なぜそんなかっこうになるのでしょう?
ダンゴムシは「ムシ」と名前につきますが、じつはかたいからをもつ、エビやカニに近い甲殻類です。ダンゴムシも、せなか側はかたいからです。ところが、おなか側はとてもやわらかく、敵にねらわれやすいところです。
ダンゴムシは天敵のアリやトカゲ、カエルなどにねらわれます。ダンゴムシはきけんをかんじたときに体をまるくすることで、弱点であるおなかと、大事な頭を、かたいからですっぽりかくすことができるのです。
 ダンゴムシとよくにていて、体がひらべったく色がうすいのは、ワラジムシです。ワラジムシはさわってもまるくならないので、ダンゴムシとすぐにみわけがつきます。
ダンゴムシとよくにていて、体がひらべったく色がうすいのは、ワラジムシです。ワラジムシはさわってもまるくならないので、ダンゴムシとすぐにみわけがつきます。
 ダンゴムシの体
ダンゴムシの体
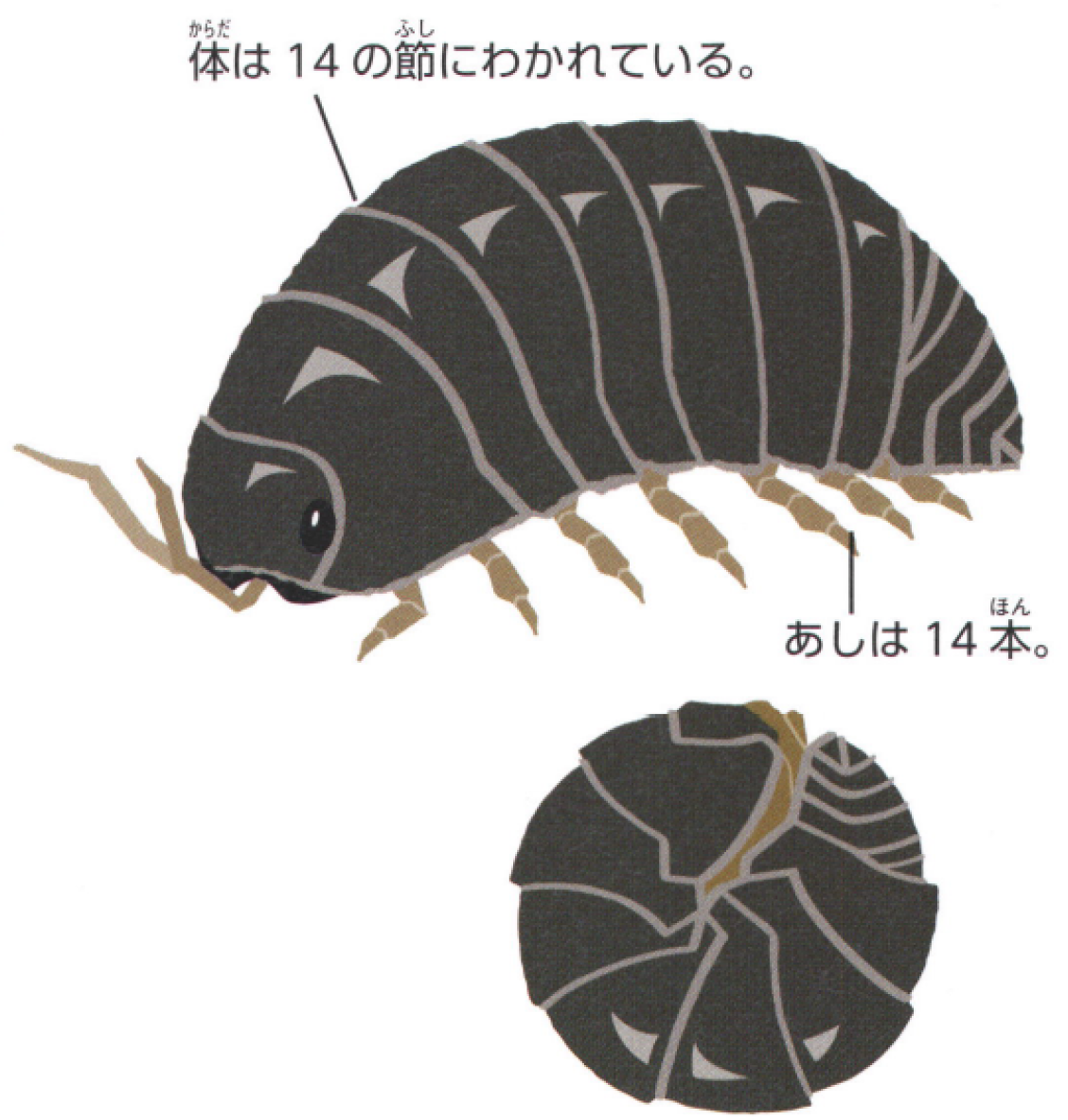

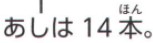
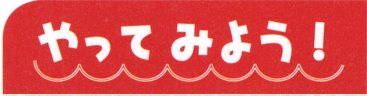 ダンゴムシ迷路をつくろう!
ダンゴムシ迷路をつくろう!
ダンゴムシは何かにぶつかると、右、左、右、左と交互にまがってすすみます。たしかめてみましょう。
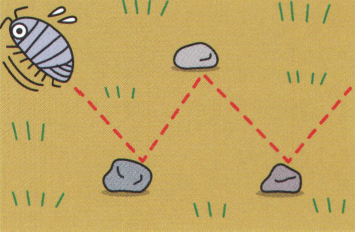

工作用紙(厚紙)、カッターナイフ

図のように、工作用紙にカッターで切れ目をいれてたたせる。
 方眼のある工作用紙をつかうと便利。
方眼のある工作用紙をつかうと便利。
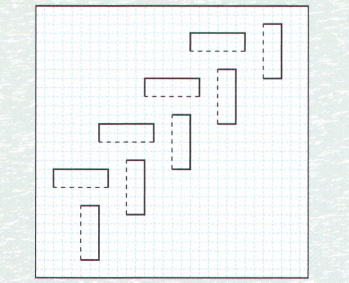
 切れ目をおりまげて2~3cmの高さのかべをつくる。
切れ目をおりまげて2~3cmの高さのかべをつくる。
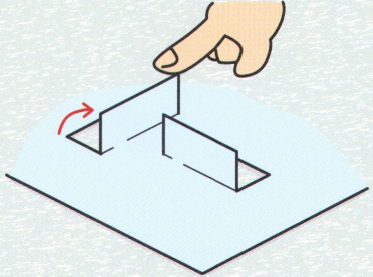
 きったすき間が気になるときは下にもう1枚かさねる。
きったすき間が気になるときは下にもう1枚かさねる。
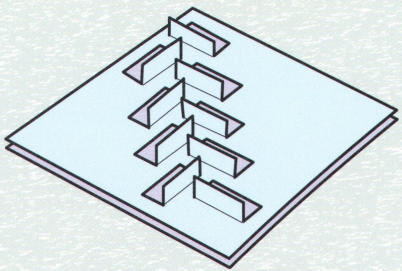

ダンゴムシをおいてすすませてみよう!
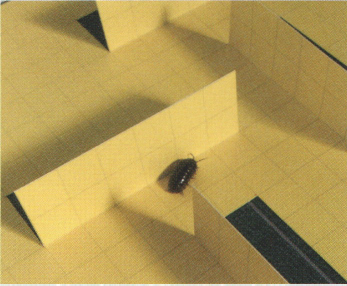
24
セミはなぜとぶときにおしっこをするの?
 すった木のしるが、とびたつときにおしだされるのです
すった木のしるが、とびたつときにおしだされるのです
 セミの口は、はりのようになっていて、これを木にさして木のしるをすいます。木のしるは多くが水分なので、ほとんどがおしっことしてすぐに外にだされます。セミは空をとぶため、体が軽いほうがいいのです。
セミの口は、はりのようになっていて、これを木にさして木のしるをすいます。木のしるは多くが水分なので、ほとんどがおしっことしてすぐに外にだされます。セミは空をとぶため、体が軽いほうがいいのです。
だれかがちかづいてきたりすると、木にとまっているセミはおどろいてとびたちます。そのときに、おしっこが体からおしだされるのです。とびたつときだけおしっこをしているわけではありません。
 おしっこといってもほとんど水のようなもの。かけられても大丈夫。
おしっこといってもほとんど水のようなもの。かけられても大丈夫。

25
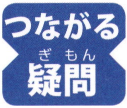 どうしてセミはすぐ死ぬの?
どうしてセミはすぐ死ぬの?
 すぐ死ぬわけではなく、何年も土の中ですごしています
すぐ死ぬわけではなく、何年も土の中ですごしています
 わたしたちが目にするのは、成虫のセミなので、すぐ死んでしまうようにおもいますね。アブラゼミの場合、幼虫時代の5~6年を地中ですごしています。その間に4回脱皮をして、大きくなっていきます。
わたしたちが目にするのは、成虫のセミなので、すぐ死んでしまうようにおもいますね。アブラゼミの場合、幼虫時代の5~6年を地中ですごしています。その間に4回脱皮をして、大きくなっていきます。
そして6~7年目の夏に、地上にでて羽化をします。成虫は、長くても1か月ほどで死んでしまいます。わたしたちが目にするのは、この成虫の時期だけなのです。
成虫は、子孫をのこすためのすがたです。セミは、地上では敵も多く、強い体ももっていません。だから最後の夏の間だけ、いっせいに地上で活動をするのです。

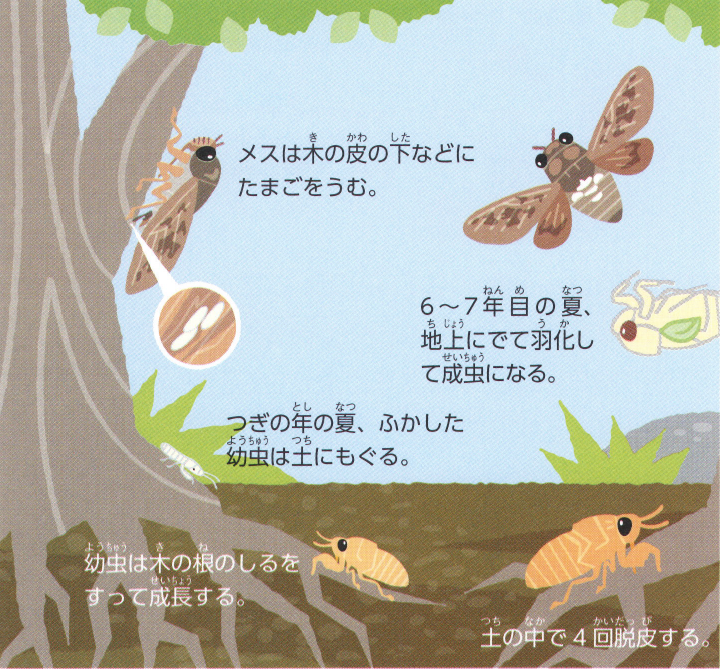
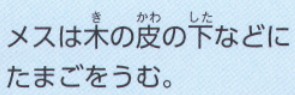
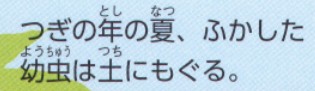
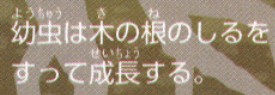

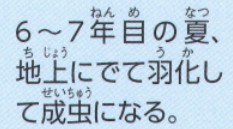
 17年ごとにあらわれるセミ
17年ごとにあらわれるセミ
北アメリカには、一定の長い年数ごとにすがたをあらわすセミがいます。ジュウシチネンゼミは、その名のとおり、17年間を土の中ですごし、きっちり17年目に地上で成虫となります。木々をうめつくすほどの、ものすごい数のジュウシチネンゼミが、あるときいっせいに発生して、ニュースになる年があります。

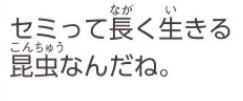
26
チョウの口はどうしてまるまっているの?
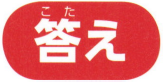 つかわないときは、まるめて大事にしまっています
つかわないときは、まるめて大事にしまっています
 チョウの食べ物は、主に花のみつです。チョウの口は、2本のひもがあわさった、長いストローのようになっています。これを花のおくのほうにある、めしべのつけねまでさしこんで、花のみつをすうのです。
チョウの食べ物は、主に花のみつです。チョウの口は、2本のひもがあわさった、長いストローのようになっています。これを花のおくのほうにある、めしべのつけねまでさしこんで、花のみつをすうのです。
チョウによって、口の長さはさまざまです。口が短いと、みつがおくのほうにある花からはすうことができません。それでチョウの種類によって、すきな花がちがうのです。
長い口は、花のみつをすうときには便利な形ですが、いつものばしたままだと、じゃまになります。それに、もし口がおれたりすると、みつがすえなくなってしまいます。だから、いためたりしないように、ふだんは大切に小さくまるめてしまっているのです。
 樹液にあつまるチョウ。
樹液にあつまるチョウ。

 樹液や、くさった果実がすきなチョウもいる。どのチョウも、口からしるをすっている。
樹液や、くさった果実がすきなチョウもいる。どのチョウも、口からしるをすっている。

 ほかの昆虫の口をみてみよう
ほかの昆虫の口をみてみよう
ほかの昆虫の口はどんなものがあるのでしょう。
カブトムシの口は、樹液をなめるのに便利なブラシのようです。カマキリはつかまえたえものをくいちぎるあごをもっています。カミキリムシは幼虫のときから強いあごで木をたべます。ゾウムシは長い口で植物の実の中をたべたり、あけた穴にたまごをうみます。
 ゾウムシ
ゾウムシ
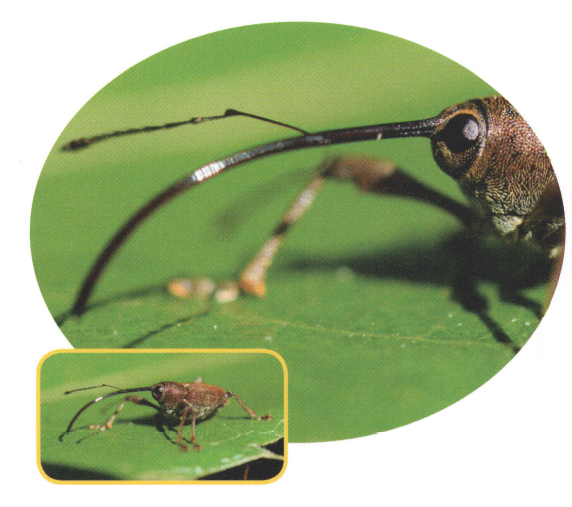
 カブトムシ
カブトムシ

 カマキリ
カマキリ

 カミキリムシ
カミキリムシ

27
ナミテントウにはどうしていろいろな模様があるの?
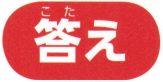 子どもに両親の模様がくみあわさってあらわれるから
子どもに両親の模様がくみあわさってあらわれるから
 わたしたちがよくみかけるテントウムシには、ナミテントウとナナホシテントウがいます。ナナホシテントウは、せなかの模様がきまっています。その名のとおり、赤地に7つの黒いはん点です。ところが、ナミテントウは模様がきまっていません。さまざまな模様のものがいますが、これがみんなナミテントウなのです。これは両親や、そのまた両親からうけついでいる模様が、くみあわさって子どもにあらわれるからなのです。そのしくみは複雑で、まだよくわかっていません。
わたしたちがよくみかけるテントウムシには、ナミテントウとナナホシテントウがいます。ナナホシテントウは、せなかの模様がきまっています。その名のとおり、赤地に7つの黒いはん点です。ところが、ナミテントウは模様がきまっていません。さまざまな模様のものがいますが、これがみんなナミテントウなのです。これは両親や、そのまた両親からうけついでいる模様が、くみあわさって子どもにあらわれるからなのです。そのしくみは複雑で、まだよくわかっていません。
自分のすむ地域ではどんな模様のナミテントウが多くみられるか、しらべてみるとおもしろいですよ。
 ナミテントウのいろいろな模様
ナミテントウのいろいろな模様
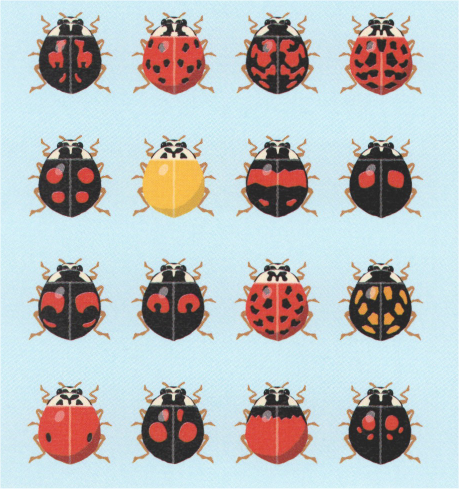
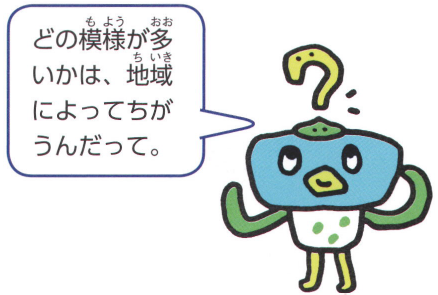
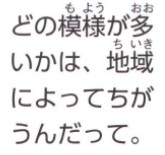
 そのほかのテントウムシの模様
そのほかのテントウムシの模様
ナミテントウとはちがい、ほかのテントウムシたちはきまった模様をもっています。
 ナナホシテントウ
ナナホシテントウ

 カメノコテントウ
カメノコテントウ

 ニジュウヤホシテントウ
ニジュウヤホシテントウ

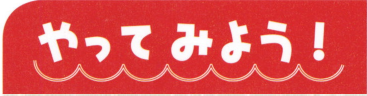 天をめざすテントウムシ
天をめざすテントウムシ
テントウムシの名前は「お天道さま」つまり、太陽からついたもの。その行動が太陽をめざすようにみえるためです。
テントウムシを手にとってみましょう。体をちぢこめますが、すぐにちょこちょことうごきはじめます。
このとき、必ず上にむかってのぼっていきます。とちゅうで手をかえして上下をひっくりかえすと、ターンしてまた上へのぼっていきます。
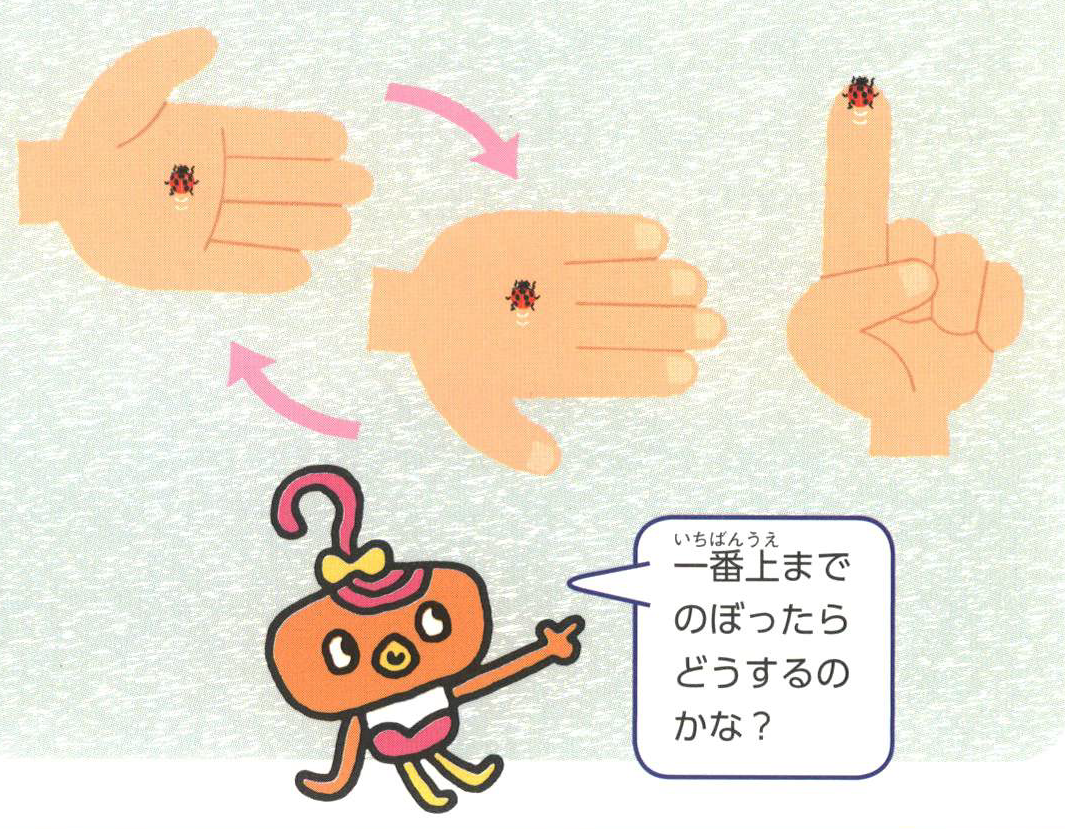
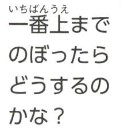
28
トンボの目はなぜ大きいの?
 たくさんの小さな目があつまってできているから
たくさんの小さな目があつまってできているから
 トンボは、複眼とよばれる大きな目をもっています。複眼は、六角形の小さな個眼が2万個以上あつまってできています。
トンボは、複眼とよばれる大きな目をもっています。複眼は、六角形の小さな個眼が2万個以上あつまってできています。
複眼は、えもののうごきを正確にとらえられます。また、とても広いはんいを一度にみることができます。トンボは頭がよくうごくので、すこし首をかたむけるだけで、自分のまわりをすべてみることができるのです。
 トンボは空をとびながら、小さな虫などをつかまえてたべます。すぐれたとぶ力をもち、とくべつにすぐれたみる力によって、トンボは一流の空中ハンターでいられるのです。
トンボは空をとびながら、小さな虫などをつかまえてたべます。すぐれたとぶ力をもち、とくべつにすぐれたみる力によって、トンボは一流の空中ハンターでいられるのです。
 複眼だけではなく、単眼もある。単眼はまわりの明るさをとらえる。
複眼だけではなく、単眼もある。単眼はまわりの明るさをとらえる。

 六角形の個眼がぎっしりならんでいる。
六角形の個眼がぎっしりならんでいる。
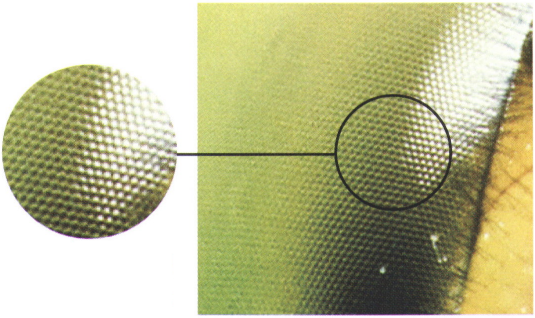
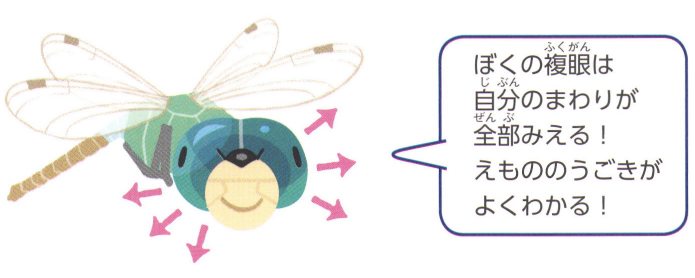
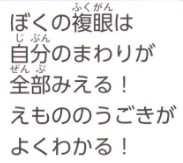
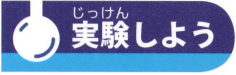 トンボの目をまわしてつかまえられるかな?
トンボの目をまわしてつかまえられるかな?
「トンボの目の前で指をくるくるまわすと、トンボが目をまわす」と、よくいわれます。でも、本当かな?
トンボは、すばやくちかづくものからはさっとにげてしまいます。
指をゆっくりまわしながらじわじわとちかづくと、えものや、敵だとはかんじにくいようです。すぐそばまでちかづければ、つかまえることができます。
しかし、目をまわしているわけではないようです。
 指をまわさずに、ゆらゆらゆらしてもよい。
指をまわさずに、ゆらゆらゆらしてもよい。
 トンボが首をかしげるしぐさをすることもある。これが目をまわしているようにみえる。
トンボが首をかしげるしぐさをすることもある。これが目をまわしているようにみえる。
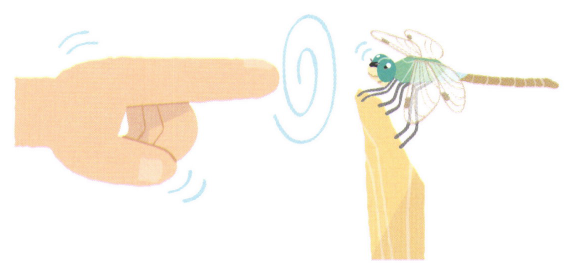

◎ゆっくりゆっくり体もゆらしながら、ちかづいてみよう。
◎数センチそばまでちかづいたら、指ではねをぱっとはさんでつかまえよう。
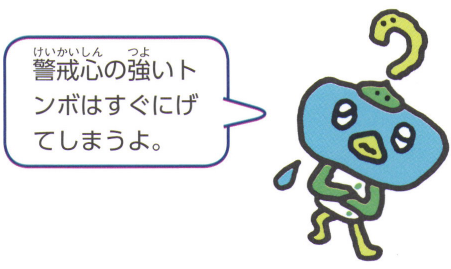
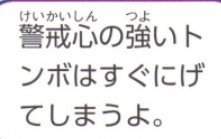
29
トンボの幼虫はなぜ水中でくらすの?
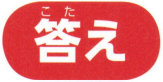 水中にはたまごをたべる敵が少なかったから
水中にはたまごをたべる敵が少なかったから
 おそらく、トンボのなかまが大繁栄した大昔、たまごをうむ場所、幼虫がそだつ場所をめぐって競争がおこり、幼虫が水中でそだつものがうまく生きのこってきたのでしょう。
おそらく、トンボのなかまが大繁栄した大昔、たまごをうむ場所、幼虫がそだつ場所をめぐって競争がおこり、幼虫が水中でそだつものがうまく生きのこってきたのでしょう。
 昆虫には、幼虫と成虫でくらす場所をかえるものが多くいます。カゲロウやカも、幼虫時代を水中でくらします。セミやカブトムシの幼虫は地中で大きくなります。
昆虫には、幼虫と成虫でくらす場所をかえるものが多くいます。カゲロウやカも、幼虫時代を水中でくらします。セミやカブトムシの幼虫は地中で大きくなります。
そして、成長するとちがう環境で活動するために、変態をします。水中でえら呼吸をし、小魚をたべていたヤゴは、羽化をしてトンボとなり、空をとび、空気をすって、虫をたべるようになります。
このように、すむ場所や食べ物をかえることで、ある年に成虫のすむ環境がわるくなっても、幼虫は無事でいられます。ひとつの生き物として長く生きのびるために昆虫がとってきた方法です。
 ヤゴはのびちぢみする強いアゴで小魚をつかまえる。
ヤゴはのびちぢみする強いアゴで小魚をつかまえる。


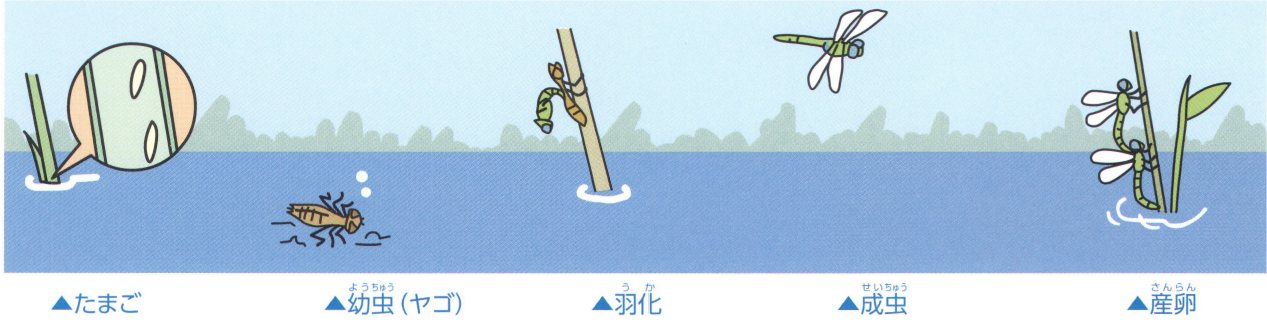





 水にすむ昆虫いろいろ
水にすむ昆虫いろいろ
水の中でくらす昆虫を水生昆虫といいます。ヤゴのほかにも、いろいろな水生昆虫のすがたがみられます。
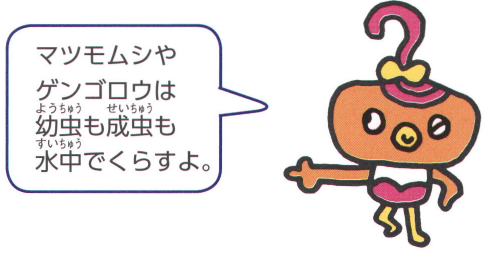
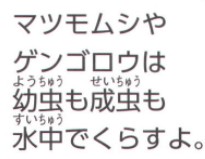
 マツモムシ
マツモムシ

 ゲンゴロウ
ゲンゴロウ

 カワゲラ(幼虫)
カワゲラ(幼虫)

 カゲロウ(幼虫)
カゲロウ(幼虫)

30
ホタルはどうしてひかるの?
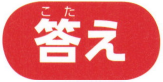 なかまと光で合図をしあっています
なかまと光で合図をしあっています
 ホタルの光は、なかまとの会話です。ホタルは夜に活動する昆虫で、光によって連絡をします。みんなに自分の場所をおしえたり、オスがメスにプロポーズしたり、敵をおいはらったりと、いろいろなことを光でつたえあいます。ホタルの光はうっすらとしたものです。明かりのある場所ではホタルは会話ができず、くらしていけません。
ホタルの光は、なかまとの会話です。ホタルは夜に活動する昆虫で、光によって連絡をします。みんなに自分の場所をおしえたり、オスがメスにプロポーズしたり、敵をおいはらったりと、いろいろなことを光でつたえあいます。ホタルの光はうっすらとしたものです。明かりのある場所ではホタルは会話ができず、くらしていけません。
 よくしられているのはゲンジボタルとヘイケボタルの2種類で、ゲンジボタルは、たまごや幼虫、さなぎのときもひかります。
よくしられているのはゲンジボタルとヘイケボタルの2種類で、ゲンジボタルは、たまごや幼虫、さなぎのときもひかります。
 ゲンジボタルのオス。
ゲンジボタルのオス。

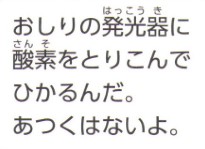
 日がおちてから、2時間後くらいでホタルのひかる活動が一番さかんになる。1ぴきのオスがプロポーズのためにとびながらひかる時間は、20分ほど。
日がおちてから、2時間後くらいでホタルのひかる活動が一番さかんになる。1ぴきのオスがプロポーズのためにとびながらひかる時間は、20分ほど。
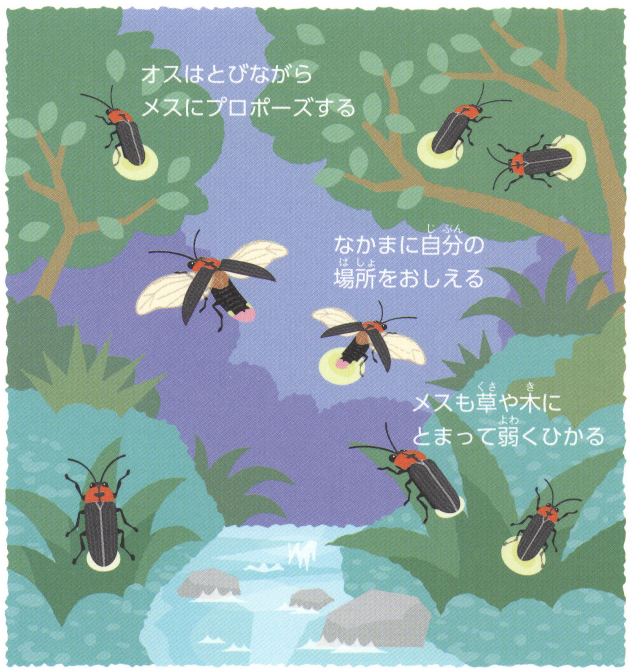
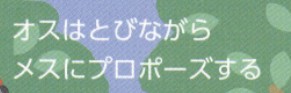
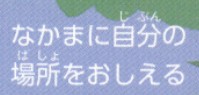
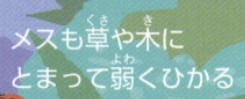
31
秋になるとなく虫が多いのはなぜ?
 子孫をのこすため、パートナーをさがしています
子孫をのこすため、パートナーをさがしています
 秋になく虫は、コオロギやキリギリスのなかまです。ないているのは、みんなオスです。
秋になく虫は、コオロギやキリギリスのなかまです。ないているのは、みんなオスです。
虫がなくのは、パートナーになるメスをよびよせるためです。子孫をのこすためには、冬がくる前に産卵をおわらせなければならないため、秋になるといっせいになきはじめるのです。
ほかにも、自分のなわばりをアピールしたり、オス同士がおどかすためになくこともあります。
 はねをこすりあわせてなく、エンマコオロギのオス。
はねをこすりあわせてなく、エンマコオロギのオス。


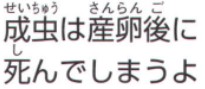
 鳴き方のひみつ
鳴き方のひみつ
秋になく虫は、声をだしているわけではありません。オスの左右の前のはねにはギザギザがついていて、2まいをすばやくこすりあわせて音をだします。
コオロギやキリギリスのなかまは、前あしに鼓膜があり、ここで音をきいています。
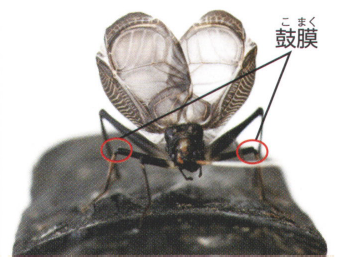

32
昆虫には骨がないの?
 かたい皮膚が骨のかわりになります
かたい皮膚が骨のかわりになります
 昆虫やカニなどは、外骨格という、じょうぶな体の表面をもっています。これは体をささえたり、うごかしたりするはたらきもしています。外骨格が骨のかわりをしているのです。
昆虫やカニなどは、外骨格という、じょうぶな体の表面をもっています。これは体をささえたり、うごかしたりするはたらきもしています。外骨格が骨のかわりをしているのです。
人や獣、魚などは、内骨格といって、背骨を中心とした骨で、体を内側からささえています。
 外骨格は、体をまもりとじこめた容器のようなもので、内骨格の体のように、だんだん大きくなることはできません。そのため昆虫などは、成長して体がきつくなると、新しい骨格をつくり、脱皮をして体を大きくします。
外骨格は、体をまもりとじこめた容器のようなもので、内骨格の体のように、だんだん大きくなることはできません。そのため昆虫などは、成長して体がきつくなると、新しい骨格をつくり、脱皮をして体を大きくします。
 人はうまれてからおとなになるまで、骨のしくみなどはほとんどかわらない。
人はうまれてからおとなになるまで、骨のしくみなどはほとんどかわらない。
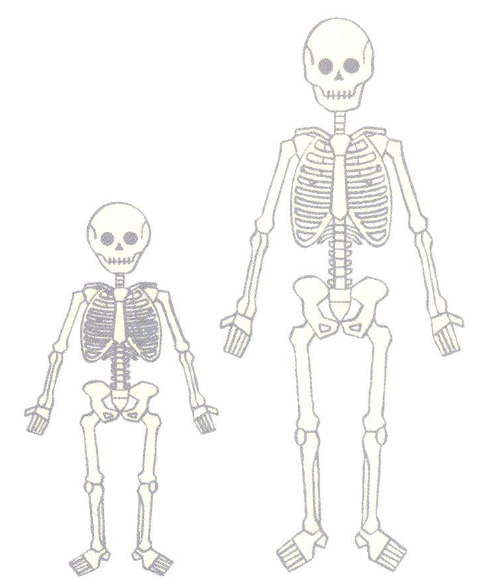
 昆虫は成長するにつれてすがたをかえるものが多い。
昆虫は成長するにつれてすがたをかえるものが多い。
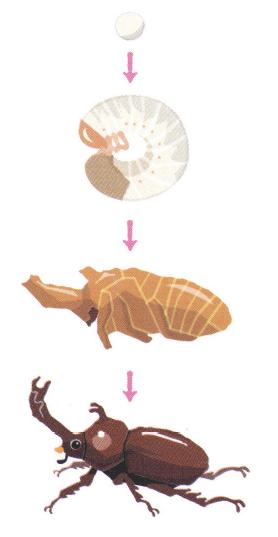
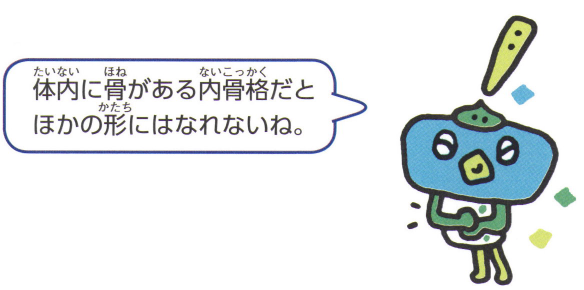
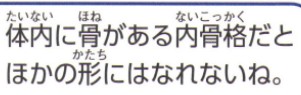
33
一番長生きする生き物は何?
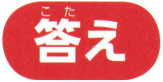 1ぴきだけの記録としては、アイスランド貝です
1ぴきだけの記録としては、アイスランド貝です
 2007年に、イギリスのバンゴー大学の研究者がつたえた調査によると、アイスランドおきの海底からとれたアイスランド貝は、405~410才の年齢だとわかりました。その後さらに調査がおこなわれ、正確には507才だということです。しかし、その後すぐにその貝は死んでしまいました。
2007年に、イギリスのバンゴー大学の研究者がつたえた調査によると、アイスランドおきの海底からとれたアイスランド貝は、405~410才の年齢だとわかりました。その後さらに調査がおこなわれ、正確には507才だということです。しかし、その後すぐにその貝は死んでしまいました。
 アイスランド貝の貝がら。
アイスランド貝の貝がら。

 長生きする生き物
長生きする生き物
どんな生き物が長生きなのでしょうか。ほかにも、生き方によっては、数千年、数万年以上もいきつづける植物のなかまもいます。


 長いものでは150~200年もいきるとかんがえられている。メスは90才になっても、まだ子どもがうめる。
長いものでは150~200年もいきるとかんがえられている。メスは90才になっても、まだ子どもがうめる。


 多くのゾウガメが100才以上いきる。正確な記録はないが、250才になるものもいる。
多くのゾウガメが100才以上いきる。正確な記録はないが、250才になるものもいる。


 成長のスピードがおそく、たまごをうめるようになるまで20年かかる。100年以上いきるようだ。
成長のスピードがおそく、たまごをうめるようになるまで20年かかる。100年以上いきるようだ。


 平均寿命は20才とされて、魚では長生きするなかま。中には70才をこえるものもいる。
平均寿命は20才とされて、魚では長生きするなかま。中には70才をこえるものもいる。
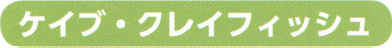

 成長のスピードがおそく、たまごがうめるようになるまで100年かかる。寿命は175才くらい。
成長のスピードがおそく、たまごがうめるようになるまで100年かかる。寿命は175才くらい。

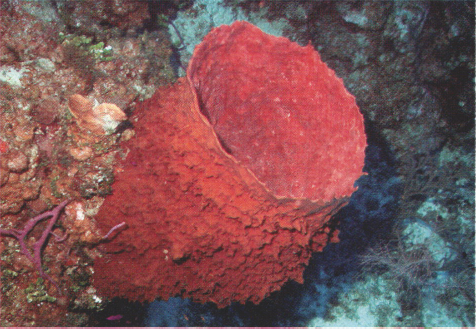
 海綿動物の南極の海にすむ種は、低温のためそだつのがゆっくりで、1550年いきているものが発見された。
海綿動物の南極の海にすむ種は、低温のためそだつのがゆっくりで、1550年いきているものが発見された。
 不老不死のクラゲ
不老不死のクラゲ
ベニクラゲはある程度そだつと、さなぎのような状態になったあと、また赤ちゃんにもどる。これをずっとくりかえすので「不老不死のクラゲ」とよばれる。

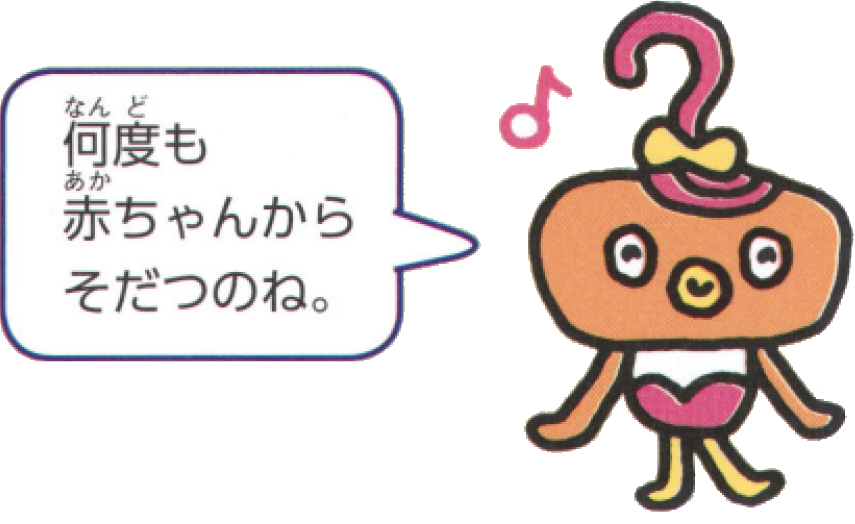
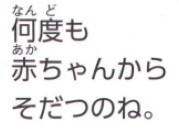
34
キリンとゾウのうんち、大きさがちがうのはなぜ?
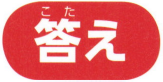 キリンは、食べ物をよく消化するから
キリンは、食べ物をよく消化するから
 キリンもゾウも草をたべる大型の草食動物です。それなのに、うんちをみてみると、キリンはコロコロした小さいうんちで、ゾウはどっしりとした大きいうんちです。何がちがうのでしょうか。
キリンもゾウも草をたべる大型の草食動物です。それなのに、うんちをみてみると、キリンはコロコロした小さいうんちで、ゾウはどっしりとした大きいうんちです。何がちがうのでしょうか。
 キリンは4つの胃で草を消化し、栄養をしっかりととりこみます。だから、のこりかすであるうんちはぐっと小さくなります。
キリンは4つの胃で草を消化し、栄養をしっかりととりこみます。だから、のこりかすであるうんちはぐっと小さくなります。
一方、ゾウの胃は1つしかないので、あまり上手に栄養がとれません。たくさんたべて、半分くらいは消化しないままだします。だから、うんちが大きくなります。
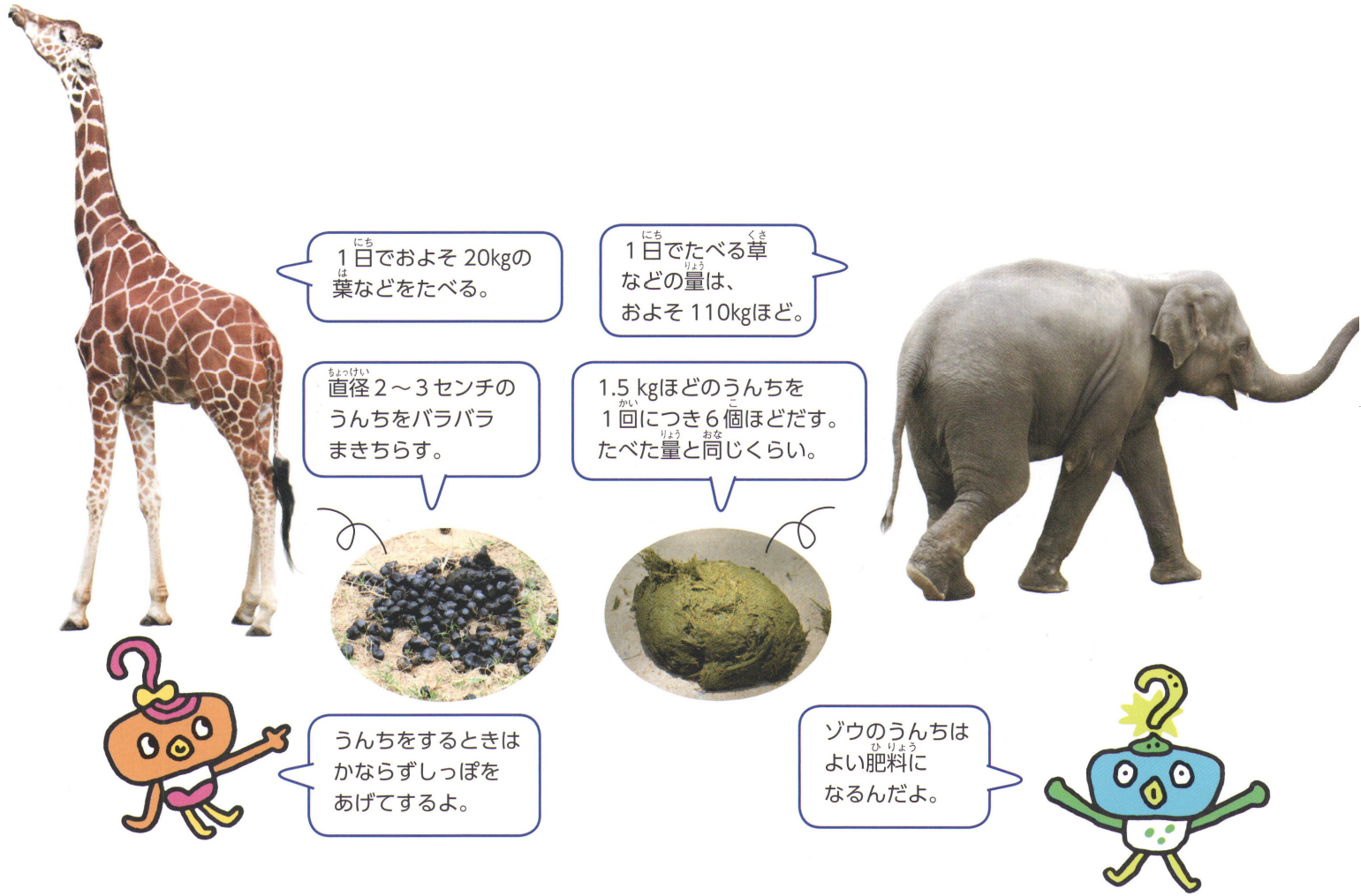
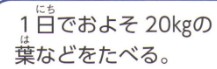
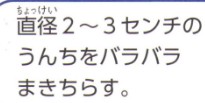
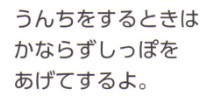
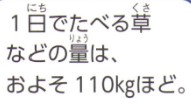
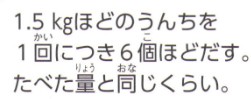
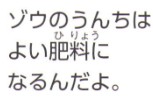
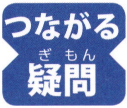 絶滅する生き物がふえているの?
絶滅する生き物がふえているの?
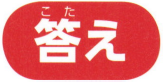 生き物の絶滅するペースがはやくなっています
生き物の絶滅するペースがはやくなっています
 大昔にさかえた恐竜のように、地球ではたくさんの生き物が絶滅してきました。これは自然のおきてで、しかたのないことです。
大昔にさかえた恐竜のように、地球ではたくさんの生き物が絶滅してきました。これは自然のおきてで、しかたのないことです。
しかし今、生き物が自然に絶滅するよりも1000~1万倍もはやいペースで、1年に4万種以上の生き物が絶滅しているといわれます。
 レッドデータブック
レッドデータブック
絶滅のおそれのある野生生物の状況をしらべて、まとめたものを「レッドデータブック」といいます。自然保護などの参考にされています。
 絶滅のおそれのある日本の生き物
絶滅のおそれのある日本の生き物
 コウノトリ
コウノトリ

 アカウミガメ
アカウミガメ
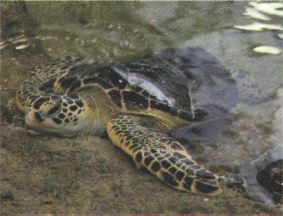
 オガサワラオオコウモリ
オガサワラオオコウモリ

36
一番強い生き物は何?
 1対1の強さならアフリカゾウです
1対1の強さならアフリカゾウです
 百獣の王といわれるライオンも、アフリカゾウにはかないません。ライオン数頭のむれでも、元気なゾウをおそうことはまずありません。
百獣の王といわれるライオンも、アフリカゾウにはかないません。ライオン数頭のむれでも、元気なゾウをおそうことはまずありません。
アフリカゾウは、陸上でもっとも大きく、重い動物です。大きなものでは全長7.5
、体の高さが3.5
、体重は7
にもなります。これはトラックのような重さです。
皮膚はあつくてじょうぶで、大きなキバももっています。サイやカバがぶつかってきても、かんたんにころがしてしまいます。鼻や足の力も強く、相手をはじきとばしたり、ふみつけたりしてしまいます
。
 アフリカゾウがあいてをおどそうとするときは、耳をひろげて鼻をもちあげる。
アフリカゾウがあいてをおどそうとするときは、耳をひろげて鼻をもちあげる。

 おそろしい集団行動
おそろしい集団行動

地面一帯がうめつくされるほどの数のアリが、途中にいるものを狩りながらすすみます。気があらく、大きくするどいあごで、動物や人にもかみつきます。

 環境にたえる体
環境にたえる体

クマムシは、きびしい環境におかれたとき、まるくちぢまってうごかなくなり、復活できるときをまちます。熱にも寒さにもとても強い生き物です。

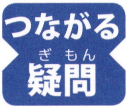 海で一番強い生き物は?
海で一番強い生き物は?
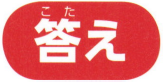 マッコウクジラとシャチです
マッコウクジラとシャチです
 おそらく1対1のたたかいでは、体が大きく力もあるマッコウクジラが、一番強いでしょう。尾びれによる打撃が強力です。
おそらく1対1のたたかいでは、体が大きく力もあるマッコウクジラが、一番強いでしょう。尾びれによる打撃が強力です。
集団なら、協力して狩りをするシャチが一番になります。ザトウクジラをおそったりもします。
 ただ、野生の動物は、力だめしのためにたたかうことなどしません。むしろ、むだなたたかいはさけます。けがは、野生ではそのまま命にかかわるからです。
ただ、野生の動物は、力だめしのためにたたかうことなどしません。むしろ、むだなたたかいはさけます。けがは、野生ではそのまま命にかかわるからです。
 マッコウクジラ
マッコウクジラ

 シャチ
シャチ

37
動物は虫歯にならないの?
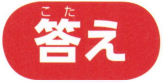 野生の動物は、ふつうはなりません
野生の動物は、ふつうはなりません
 野生の動物がたべるのは、生のものです。そのほとんどはかたいもので、よくかまなければたべられません。よくかむことが、歯のそうじにもなっているのです。
野生の動物がたべるのは、生のものです。そのほとんどはかたいもので、よくかまなければたべられません。よくかむことが、歯のそうじにもなっているのです。
それに、野生の食べ物には砂糖がはいっていません。人が虫歯になるのは、口の中にいる虫歯菌が食べ物にふくまれる糖分から酸をつくり、それが歯をとかすからです。
 人間にかわれているペットには、虫歯になるものもいます。やわらかいものや、砂糖のはいったものをたべているからです。動物園の動物も、野生の食べ物よりもやわらかいものをたべているので、歯につまりやすく、虫歯になることがあります。
人間にかわれているペットには、虫歯になるものもいます。やわらかいものや、砂糖のはいったものをたべているからです。動物園の動物も、野生の食べ物よりもやわらかいものをたべているので、歯につまりやすく、虫歯になることがあります。
 よくかむと、だ液がでる。だ液には虫歯をふせぐ力がある。
よくかむと、だ液がでる。だ液には虫歯をふせぐ力がある。

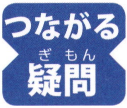 動物園の動物が虫歯になったらどうするの?
動物園の動物が虫歯になったらどうするの?
 ひどい虫歯はぬいてしまいます
ひどい虫歯はぬいてしまいます
 ひどくなる前にみつかった虫歯は、薬などでなおしますが、ひどいときはぬいてしまいます。動物は治療のとき、おとなしくしてくれないので、麻酔をかけてねむらせなければなりません。麻酔は体にふたんをかけるため、くりかえし治療することができないのです。
ひどくなる前にみつかった虫歯は、薬などでなおしますが、ひどいときはぬいてしまいます。動物は治療のとき、おとなしくしてくれないので、麻酔をかけてねむらせなければなりません。麻酔は体にふたんをかけるため、くりかえし治療することができないのです。
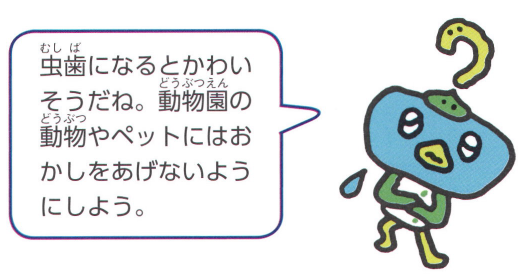
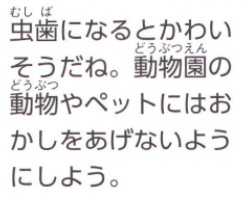
 歯のぐあいのわるくなったワラビーに、麻酔をかけて治療する。
歯のぐあいのわるくなったワラビーに、麻酔をかけて治療する。
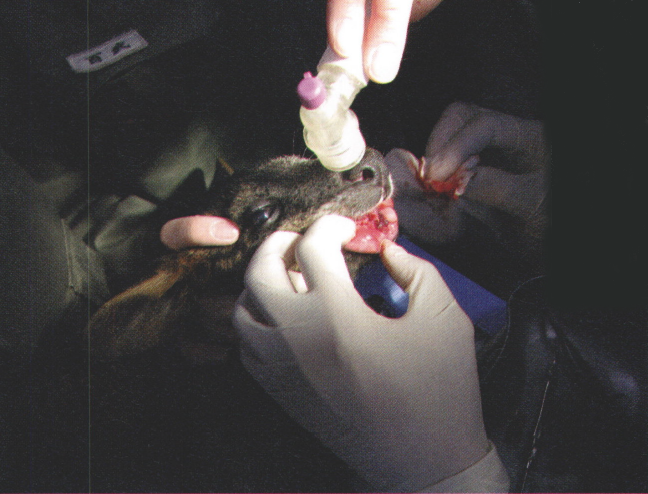
 ぬいたワラビーの前歯。
ぬいたワラビーの前歯。

 麻酔でねむっている間にレントゲン撮影をして、ほかにわるいところがないかしらべる。
麻酔でねむっている間にレントゲン撮影をして、ほかにわるいところがないかしらべる。

38
カバの口はどうして大きいの?
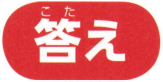 大きな口をみせて、相手をおどかすため
大きな口をみせて、相手をおどかすため
 カバは水の中にくらす草食動物です。昼間は水の中にいて、夜になると陸にあがって地面の草をたべます。大きな口やりっぱなきばは、食事にはつかいません。
カバは水の中にくらす草食動物です。昼間は水の中にいて、夜になると陸にあがって地面の草をたべます。大きな口やりっぱなきばは、食事にはつかいません。
 カバが口を大きくあけてあくびのようなしぐさをするのは、カバ同士のけんかのためです。より大きな口をあけたほうがかちます。なんと、150度もの角度でひらくといいます。
カバが口を大きくあけてあくびのようなしぐさをするのは、カバ同士のけんかのためです。より大きな口をあけたほうがかちます。なんと、150度もの角度でひらくといいます。
 また、カバのすむ川にはワニもいて、子どものカバをおそうこともあるので、カバは口を大きくあけてきばをみせつけ、ワニをおどすのです。それでも相手がなわばりからでないときは、きばをつかってたたかいます。カバはおとなしくみえますが、アフリカでは、ワニ以上に危険な動物としておそれられています。
また、カバのすむ川にはワニもいて、子どものカバをおそうこともあるので、カバは口を大きくあけてきばをみせつけ、ワニをおどすのです。それでも相手がなわばりからでないときは、きばをつかってたたかいます。カバはおとなしくみえますが、アフリカでは、ワニ以上に危険な動物としておそれられています。
 カバとワニが同じ川でくらす。
カバとワニが同じ川でくらす。


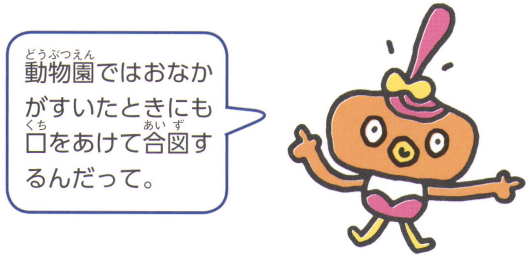
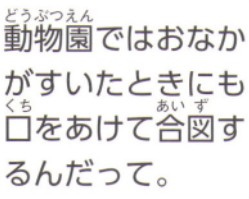
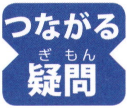 カバは赤い汗をかくって本当?
カバは赤い汗をかくって本当?
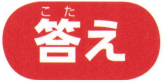 汗ではなく皮膚をまもる粘液です
汗ではなく皮膚をまもる粘液です
 カバの皮膚には、わたしたちのように汗や皮脂をだすしくみはありませんが、赤い汗のようなものをだします。
カバの皮膚には、わたしたちのように汗や皮脂をだすしくみはありませんが、赤い汗のようなものをだします。
この汗のようなものは、乾燥や強い日差し、細菌の感染などから皮膚をまもる効果があります。日焼け止めのようなものです。
色が赤いのは、血ではなく赤い色素で、紫外線をとおしません。でたばかりのあせは透明にちかく、しばらくすると赤くなってきます。これは細菌をころす効果もあります。
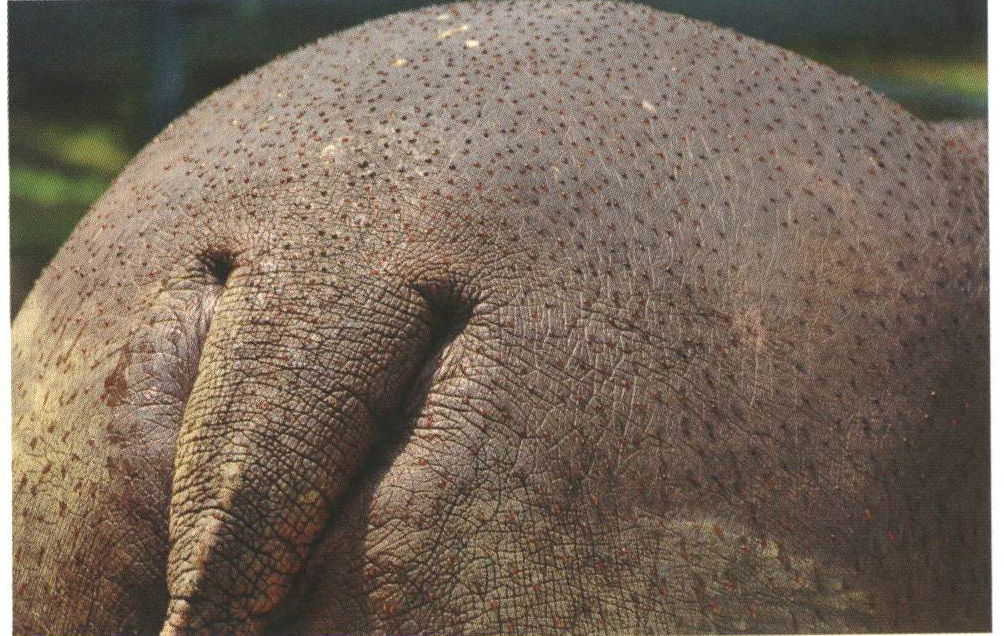
39
カンガルーはどうしておなかのふくろで子そだてするの?
 とても小さい赤ちゃんを、安全にそだてるため
とても小さい赤ちゃんを、安全にそだてるため
 カンガルーの赤ちゃんは、まだとても小さい早産の状態でうまれます。そのため、お母さんのふくろの中で、大きくなるまで安全にそだてられるのです。
カンガルーの赤ちゃんは、まだとても小さい早産の状態でうまれます。そのため、お母さんのふくろの中で、大きくなるまで安全にそだてられるのです。
ふくろの中にはおっぱいがあるので、赤ちゃんはいつでもお乳をのめます。
 このふくろは、もともとは体のしわでした。カンガルーははげしくとびまわる動物です。しわがあると赤ちゃんがつかまりやすいことで、だんだんとしわが深くなって、ふくろになったのです。
このふくろは、もともとは体のしわでした。カンガルーははげしくとびまわる動物です。しわがあると赤ちゃんがつかまりやすいことで、だんだんとしわが深くなって、ふくろになったのです。

 カンガルーの赤ちゃん(実際の大きさ)
カンガルーの赤ちゃん(実際の大きさ)

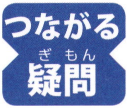 ふくろの中はうんちでよごれないの?
ふくろの中はうんちでよごれないの?
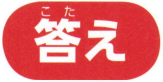 お母さんがきれいにそうじします
お母さんがきれいにそうじします
 赤ちゃんのころは、ふくろからでてこないので、中は赤ちゃんのしたうんちやおしっこでよごれますが、いつもお母さんがなめてきれいにしています。
赤ちゃんのころは、ふくろからでてこないので、中は赤ちゃんのしたうんちやおしっこでよごれますが、いつもお母さんがなめてきれいにしています。

 子そだてするふくろをもつ動物
子そだてするふくろをもつ動物
有袋類というふくろをもつなかまです。カンガルーのほかは、ふくろが後ろ(下)むきについています。アメリカ大陸にいるオポッサム以外は、みんなオーストラリアにすんでいます。


 土にトンネルをほって巣をつくる。
土にトンネルをほって巣をつくる。


 ユーカリの木で葉をたべてすごす。
ユーカリの木で葉をたべてすごす。


 大きくなった子どもをおんぶする。
大きくなった子どもをおんぶする。
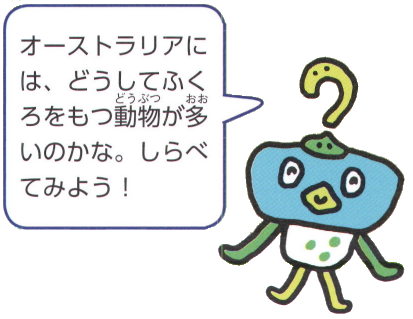
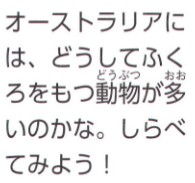
40
クジラの赤ちゃんは海の中でどうやってお乳をのむの?
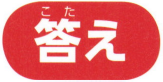 母クジラの下でおよぎながら息をとめてのんでいます
母クジラの下でおよぎながら息をとめてのんでいます
 ザトウクジラの赤ちゃんは、うまれたとき、すでに全長が3~5
、体重も1.5
あります。そして、うまれて30分ほどでおよげるようになります。
ザトウクジラの赤ちゃんは、うまれたとき、すでに全長が3~5
、体重も1.5
あります。そして、うまれて30分ほどでおよげるようになります。
クジラはほ乳類なので、赤ちゃんは母乳でそだちます。赤ちゃんはお母さんのおなかの下にもぐりこみ、おっぱいのあたりを口でつつきます。すると、口の中にお乳が噴射され、赤ちゃんは海水が少しまざったお乳をのみます。赤ちゃんは、まだ息が長くつづかないため、途中で何度も海面にあがって息つぎをしながら、くりかえしてのみます。
 クジラのお乳は、ウシのお乳の10倍も脂肪分がこく、どろっとした、栄養たっぷりのものです。これを赤ちゃんは毎日500ものみ、1日で体重が約60
もふえ、どんどん大きくなっていきます。
クジラのお乳は、ウシのお乳の10倍も脂肪分がこく、どろっとした、栄養たっぷりのものです。これを赤ちゃんは毎日500ものみ、1日で体重が約60
もふえ、どんどん大きくなっていきます。
 ザトウクジラの親子。母クジラは、赤ちゃんのために海面近くをゆっくりおよぐ。
ザトウクジラの親子。母クジラは、赤ちゃんのために海面近くをゆっくりおよぐ。

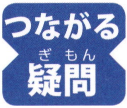 クジラはどうしてしおをふくの?
クジラはどうしてしおをふくの?
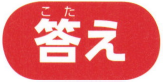 海面で息をするから
海面で息をするから
 クジラのしおふきは、海水をはきだしているわけではありません。寒い季節に、海面ではきだした息が白くみえたり、まわりの海水が息のいきおいでとばされて、きり吹きのようにまいあがったものです。
クジラのしおふきは、海水をはきだしているわけではありません。寒い季節に、海面ではきだした息が白くみえたり、まわりの海水が息のいきおいでとばされて、きり吹きのようにまいあがったものです。
 魚はエラをつかって水中で呼吸することができますが、クジラはほ乳類なので、わたしたちと同じように肺で空気をすって呼吸します。
魚はエラをつかって水中で呼吸することができますが、クジラはほ乳類なので、わたしたちと同じように肺で空気をすって呼吸します。
クジラの鼻の穴は頭の上にあいていて、海にいても呼吸がしやすくなっています。ときどき水面から顔をだして息をすったりはいたりする必要があるのです。
ザトウクジラの場合、ふつう10~20分おきに呼吸をしに海面にでてきます。
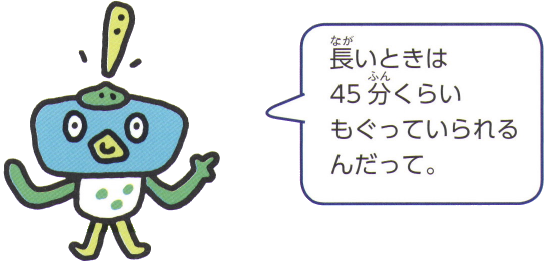
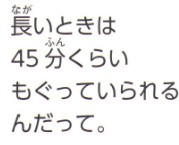
 ザトウクジラのしおふき。
ザトウクジラのしおふき。

 クジラは歌をうたう!?
クジラは歌をうたう!?
クジラは、なかまへの連絡や、一緒に魚をとるときに、声をだして会話をしています。
ザトウクジラのオスは、メスヘプロポーズの歌をうたうことでしられています。
41
ゴリラがむねをポコポコたたくのはなぜ?
 敵をおどしたり、なかまとの合図につかったりしています
敵をおどしたり、なかまとの合図につかったりしています
 野生のゴリラは、山の中にむれをつくってくらしています。みなれないものが、自分たちにちかづいてくると、ゴリラはむねをはげしくたたいて大きな音をだします。「ちかづくな!」と、相手をおどし、たたかいをさけようとします。
野生のゴリラは、山の中にむれをつくってくらしています。みなれないものが、自分たちにちかづいてくると、ゴリラはむねをはげしくたたいて大きな音をだします。「ちかづくな!」と、相手をおどし、たたかいをさけようとします。
また、むれのリーダーは、遠くへむかってむねをたたくことがあります。これは、ほかのむれに自分たちの居場所をおしえています。ほかのむれとであって、けんかにならないようにするためです。
ほかには、なかまとじゃれあったり、自分に注目してほしいときなどにも、むねをたたきます。人も、うれしいときや、注目してほしいときには手をたたきますね。
ゴリラはこわそうな外見ですが、なかまや、平和をあいする動物なのです。
 みなれないものへのおどし。
みなれないものへのおどし。
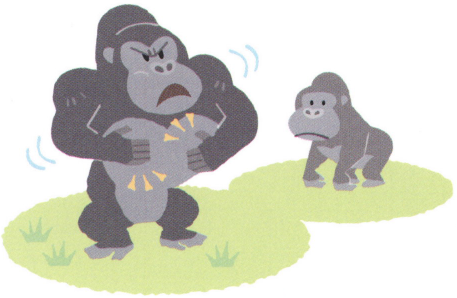
 なかまとの気持ちのふれあい。
なかまとの気持ちのふれあい。

 ほかのむれととつぜんはちあわせしないための合図。
ほかのむれととつぜんはちあわせしないための合図。

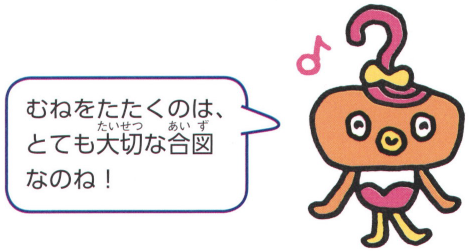
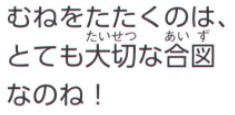
 音をつかう生き物たち
音をつかう生き物たち
ゴリラのほかにも、声ではなく、音を連絡につかう生き物がいます。

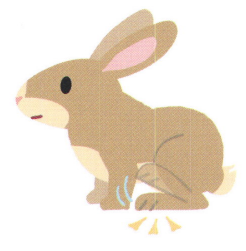
 あしをトントンと地面にうちつけ、なかまに危険をしらせる。(スタンピング)
あしをトントンと地面にうちつけ、なかまに危険をしらせる。(スタンピング)


 ジャンプをして海面に体をうちつけ、自分の場所をつたえる。(ブリーチング)
ジャンプをして海面に体をうちつけ、自分の場所をつたえる。(ブリーチング)

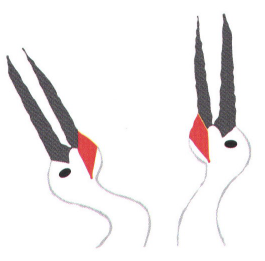
 くちばしをカタカタならし、メスにプロポーズする。(クラッタリング)
くちばしをカタカタならし、メスにプロポーズする。(クラッタリング)

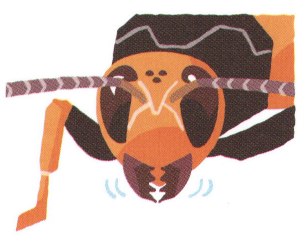
 巣にちかづくものに、あごをカチカチならしておどかす。
巣にちかづくものに、あごをカチカチならしておどかす。
42
シマウマの模様は何のためにあるの?
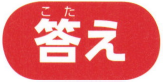 病気や、敵から身をまもるためだとかんがえられています
病気や、敵から身をまもるためだとかんがえられています
 シマウマの模様が何のためにあるのか、じつはまだはっきりわかっていません。
シマウマの模様が何のためにあるのか、じつはまだはっきりわかっていません。
新しい説のひとつが「病気をひきおこすハエから、身をまもるため」です。
シマウマのすむ地域には、ウシやウマをさして重い病気にするサシバエがいます。このサシバエは、白黒のしま模様をきらう性質があり、シマウマはそこにすむほかの動物よりおそわれにくいといわれています。でもなぜ、シマウマだけがしま模様なのかは、わかっていません。
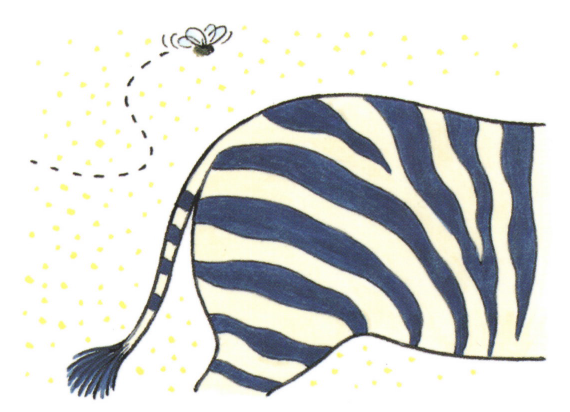
 これまでの説としては「模様によって、自分たちをねらう敵の目を混乱させる」というものがあります。
これまでの説としては「模様によって、自分たちをねらう敵の目を混乱させる」というものがあります。
シマウマはむれでくらしています。しま模様の集団は、一色の体の集団より、形の輪郭がわかりにくくなります。ライオンなどにねらわれにくいとかんがえられています。
 シマウマのむれ。
シマウマのむれ。

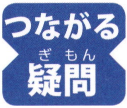 トラのしま模様も同じ?
トラのしま模様も同じ?
 森でめだたないためです
森でめだたないためです
 トラはほかの動物などをつかまえてたべるハンターです。はでにみえる黒と黄色のしま模様は、木々のしげる森にとけこんでめだたなくなり、えものに気づかれずにちかよることができるため、狩りをするにはぴったりなのです。
トラはほかの動物などをつかまえてたべるハンターです。はでにみえる黒と黄色のしま模様は、木々のしげる森にとけこんでめだたなくなり、えものに気づかれずにちかよることができるため、狩りをするにはぴったりなのです。
 トラは、えもののちかくにしのびよってつかまえたり、まちぶせしたりする狩りが得意です。
トラは、えもののちかくにしのびよってつかまえたり、まちぶせしたりする狩りが得意です。

 シマウマはたてじま? 横じま?
シマウマはたてじま? 横じま?
動物のしま模様は、地面に対しての方向ではなく、背骨との方向でみます。シマウマの模様は、背骨に対して横になるので、横じまです。シマリスは、背骨に対してたてになるので、たてじまです。


43
パンダは竹しかたべないの?
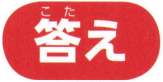 ほかの食べ物もたべることができます
ほかの食べ物もたべることができます
 パンダはクマのなかまです。実は、肉などもたべることができる雑食動物のなかまなのです。だから、竹以外のものもたべることができます。
パンダはクマのなかまです。実は、肉などもたべることができる雑食動物のなかまなのです。だから、竹以外のものもたべることができます。
野生のパンダの食べ物は、99%が竹ですが、死んだ動物の肉や昆虫、卵をたべることもあります。肉は大好物のようですが、野生ではほとんど手にはいりません。そこで竹やササをたくさんたべていきるのです。
動物園のパンダは、くだものや野菜もたべています。
 動物園で竹をたべるパンダ。
動物園で竹をたべるパンダ。

 どうして竹をたべるようになったのでしょう? 大昔にクマのようなちかいなかまと競争になり、弱かったパンダの先祖は、食べ物であらそうことをさけて、深い山のおくににげたのです。そこで1年中とれる食べ物が、竹やタケノコだったため、それをたべるようになりました。その結果、いきのこったのが今のパンダです。
どうして竹をたべるようになったのでしょう? 大昔にクマのようなちかいなかまと競争になり、弱かったパンダの先祖は、食べ物であらそうことをさけて、深い山のおくににげたのです。そこで1年中とれる食べ物が、竹やタケノコだったため、それをたべるようになりました。その結果、いきのこったのが今のパンダです。
野生のパンダは、季節によって竹のちがう部分をたべます。春と夏にはタケノコ、秋には竹の葉を、冬には竹の枝を主にたべます。パンダのくらす山には、たくさんの種類の竹がはえています。

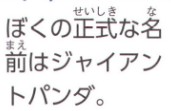
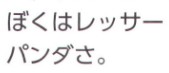
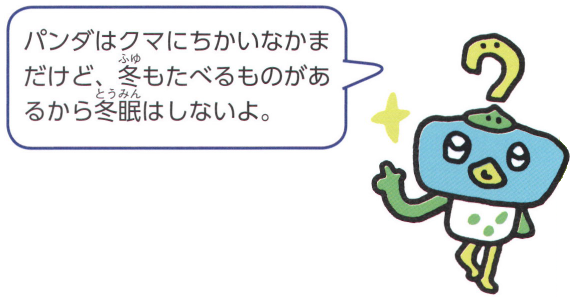
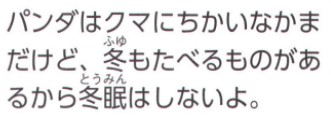
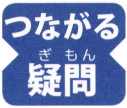 パンダのうんちは何色なの?
パンダのうんちは何色なの?
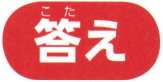 竹をたべたあとは緑色になります
竹をたべたあとは緑色になります
 もともとが雑食動物のパンダのおなかは、竹をしっかり消化できません。たべた量の80%くらいが、消化されずにそのままうんちになってでてきます。
もともとが雑食動物のパンダのおなかは、竹をしっかり消化できません。たべた量の80%くらいが、消化されずにそのままうんちになってでてきます。
そのため、竹をたべたパンダのうんちは、竹をぎゅっとつぶしてまるめたようなものです。緑色で、竹のようないいにおいがします。
 パンダのうんち
パンダのうんち

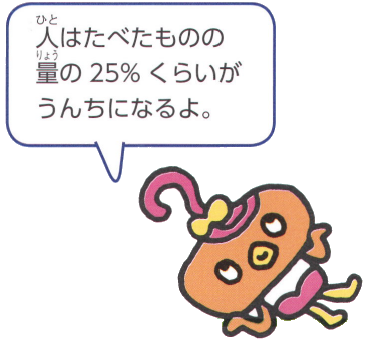
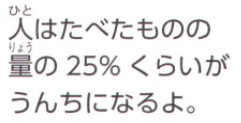
 ふつうのうんちとはべつに、パンダはときどき、腸の粘膜のかたまりをうんちとしてだします。このうんちをするとき、パンダは元気がなくなります。とてもいたいようです。
ふつうのうんちとはべつに、パンダはときどき、腸の粘膜のかたまりをうんちとしてだします。このうんちをするとき、パンダは元気がなくなります。とてもいたいようです。
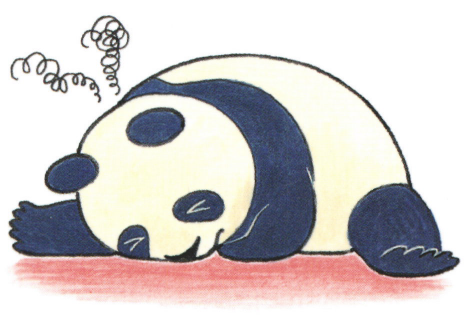
44
イヌはどうしてあちこちにおしっこするの?
 自分のなわばりをしめしています
自分のなわばりをしめしています
 イヌは散歩のとき、電柱など、あちこちにおしっこをします。少しずつ何回もするので、おしっこにいきたくてしているわけではなさそうですね。
イヌは散歩のとき、電柱など、あちこちにおしっこをします。少しずつ何回もするので、おしっこにいきたくてしているわけではなさそうですね。
このおしっこは、「マーキング」といって、大きく2つの意味があります。
 1つ目は、自分のにおいをつけて、なわばりをあらわします。なわばりといっても、ほかのイヌがはいるのをゆるさないわけではなく「オレはここにいるぞ」という、自分のアピールです。
1つ目は、自分のにおいをつけて、なわばりをあらわします。なわばりといっても、ほかのイヌがはいるのをゆるさないわけではなく「オレはここにいるぞ」という、自分のアピールです。
そのため1か所ではなく、たくさんの場所におしっこをして、自分の活動する範囲を、ほかのイヌにつたえています。
 さらに、においによって、イヌはおたがいの情報をやりとりしています。「いま、ここをとおったよ」という、おき手紙のようなものです。たくさんのイヌのおしっこがかかっていても、それらがどのイヌのものか、わかるようです。
さらに、においによって、イヌはおたがいの情報をやりとりしています。「いま、ここをとおったよ」という、おき手紙のようなものです。たくさんのイヌのおしっこがかかっていても、それらがどのイヌのものか、わかるようです。
また、メスは子どもがうめる時期になると、おしっこでそれをしらせます。
 自分のにおいに気づいてもらいやすいように、高い場所におしっこをかける。
自分のにおいに気づいてもらいやすいように、高い場所におしっこをかける。
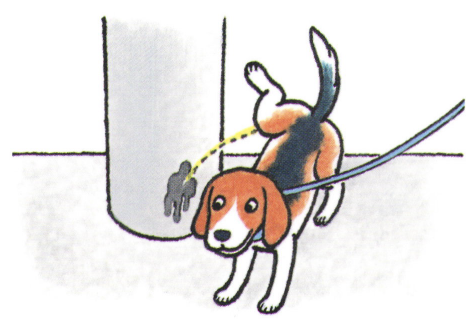
 おしっこのにおいで、体調や気持ちなどもわかるといわれている。
おしっこのにおいで、体調や気持ちなどもわかるといわれている。
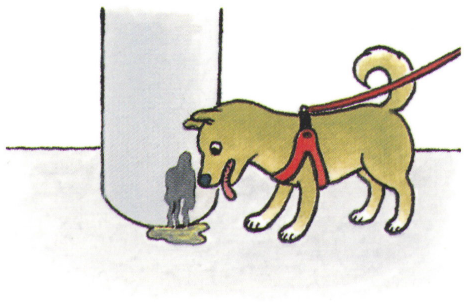
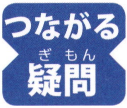 イヌの鼻がぬれているのはなぜ?
イヌの鼻がぬれているのはなぜ?
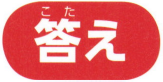 においの粒子をとらえられるようにするため
においの粒子をとらえられるようにするため
 鼻がぬれていることで、しっかりとにおいをとらえられます。
鼻がぬれていることで、しっかりとにおいをとらえられます。
さらに、イヌは鼻の中にあるにおいをかんじとる細胞の数がとても多く、においをかぎわける力は、人の100万倍以上、脂のにおいだと1億倍といわれます。
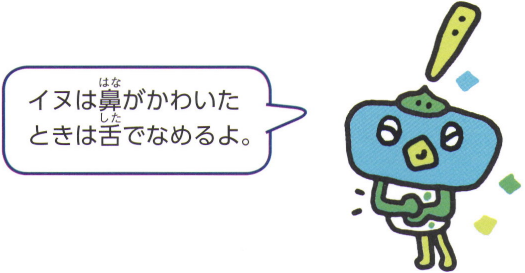
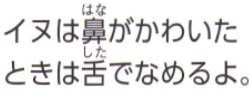
 鼻の表面の細かいみぞに、水分がたくわえられている。
鼻の表面の細かいみぞに、水分がたくわえられている。

45
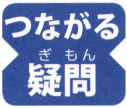 イヌはなぜ舌をだしてハアハアするの?
イヌはなぜ舌をだしてハアハアするの?
 あついときに体温をさげるため
あついときに体温をさげるため
 人はあついとき、汗をかきます。汗が蒸発するとき、体のねつをうばうので、体温がさがるというしくみです。
人はあついとき、汗をかきます。汗が蒸発するとき、体のねつをうばうので、体温がさがるというしくみです。
イヌは汗をかきません。あついときは、舌をだしてハアハアとしています。舌をだして体温をさげているのです。
 イヌは全身を毛におおわれているので、体温調節が苦手。
イヌは全身を毛におおわれているので、体温調節が苦手。

46
ネコのひげは何の役にたつの?
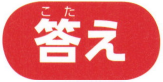 すき間をはかったり、バランスをとるのにつかっています
すき間をはかったり、バランスをとるのにつかっています
 ネコのひげは「触毛」ともよばれます。昆虫の触角と同じように、身のまわりの情報をとらえる、大切な役割をもっています。
ネコのひげは「触毛」ともよばれます。昆虫の触角と同じように、身のまわりの情報をとらえる、大切な役割をもっています。
 ネコのひげの根元には、敏感なセンサーがあります。わずかな空気の振動でもかんじとることができます。また音で風むきなどがわかります。
ネコのひげの根元には、敏感なセンサーがあります。わずかな空気の振動でもかんじとることができます。また音で風むきなどがわかります。
ネコは体がやわらかく、せまいすき間もとおりぬけますが、自分がとおれる大きさか、最初にひげではかっています。
また、体のバランスをとるためにも、ひげはつかわれています。
 目の上にあるひげは、何かがふれた瞬間に、まぶたがとじるようにできています。目をきずつけないための、まぶたのスイッチなのです。
目の上にあるひげは、何かがふれた瞬間に、まぶたがとじるようにできています。目をきずつけないための、まぶたのスイッチなのです。
 ネコのひげはこんなところにはえている
ネコのひげはこんなところにはえている
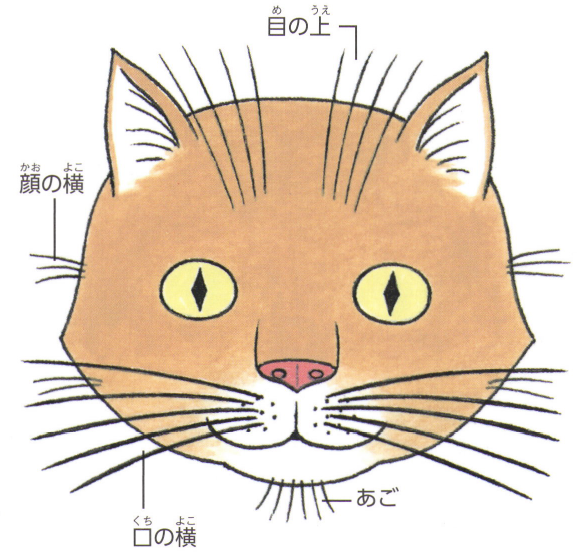





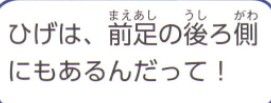
 ネコの能力をみてみよう
ネコの能力をみてみよう

ネコのジャンプ力は、自分の体長の5倍もあります。ですから、高いへいにも助走なしでとびあがることができます。人でいえば、身長150cmの人が2階の屋根にとびのるようなものです。
ネコは、体が軽くしなやかで、後ろ足の筋肉が発達しているので、高くジャンプできるのです。
 ジャンプするネコ。
ジャンプするネコ。
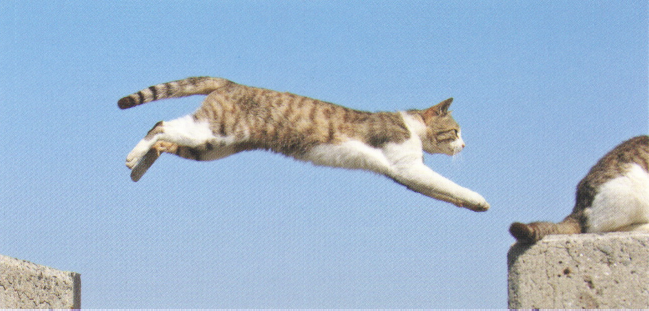

ネコの視力は、人でいうと0.2くらいしかありません。しかしうごくものをとらえる力にすぐれていて、広い範囲がみえます。
耳はとてもよく、とくに高音に対しては、人の4倍以上も敏感です。音の方向や距離を正確にとらえられます。
 ネコは左右の耳をべつべつの方向にうごかすことができる。
ネコは左右の耳をべつべつの方向にうごかすことができる。

47
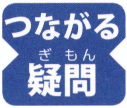 ネコのなぜ?
ネコのなぜ?
夜、目がひかるのはなぜ?
ネコは、月明かりなどの、わずかな光でもみえる目をもっています。目にはいってきた光を、目のおくで反射させ、明るくしてみているのです。ネコの目がひかってみえるのは、この反射させた光です。
暗いとき、ネコのひとみは多くの光をあつめるためにまるく、大きくなります。
 明るいときの目。
明るいときの目。

 暗いときの目。
暗いときの目。

爪をとぐのはなぜ?
爪のするどさをたもつためです。とぐのは前足だけで、ガリガリと柱などをひっかいて、爪の古くなった部分をはぎおとしています。後ろ足のつめは、口でかんではがします。
 ネコの前足。爪はだしいれができる。
ネコの前足。爪はだしいれができる。

虫やネズミをおいかけるのはなぜ?
それがネコのもつ本能だからです。ネコは、野生のヤマネコを、人がペットとしてかいならした生き物です。野生のヤマネコは、自分で狩りをして食べ物をとります。ネコにもそのときの性質がのこっているので、小さなうごくものをみると、とびかかってしまうのです。
とらえたえものは、たべたり、そのまましばらくいじったり、飼い主にもっていったりします
。
 うごく小さなものならなんでもとびかかっていく。
うごく小さなものならなんでもとびかかっていく。

よくねているのはなぜ?
じっとしているほうが、むだな体力をつかわず、狩りにそなえられます。これも野生のころの性質によるものです。
ネコは1日のうち、14~15時間をねてすごします。とはいえ、ぐっすりねむっているわけではなく、まわりの音などに注意しながら、うとうとしています。
 家の中だけでかわれているネコは、ねむっている時間が長くなる。
家の中だけでかわれているネコは、ねむっている時間が長くなる。

毛づくろいをするのはなぜ?
ネコはおきている時間の30%くらいを毛づくろいにあてています。体のよごれをきれいにするほかに、自分のにおいをけしたり、体温を調整するためにやっています。また、体をなめることで、リラックスできるようです。
 なでられたネコが毛づくろいするのは、毛についた人のにおいをけすため。
なでられたネコが毛づくろいするのは、毛についた人のにおいをけすため。

48
ヤギはどうして紙をたべるの?
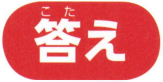 紙を木からできたエサだとおもうから
紙を木からできたエサだとおもうから
 ヤギはウシにちかいなかまです。消化しにくい植物を、なんども胃から口にもどしてかみかえしてたべることで、栄養にします。とくにヤギは、植物ならなんでもたべます。
ヤギはウシにちかいなかまです。消化しにくい植物を、なんども胃から口にもどしてかみかえしてたべることで、栄養にします。とくにヤギは、植物ならなんでもたべます。
紙は木からつくられたものです。ヤギは紙を木からできたえさだとおもい、たべてしまうのです。
でも、いまつくられている紙には、紙を白くする薬品などがふくまれています。ヤギの体にわるいので、あげないようにしましょう。
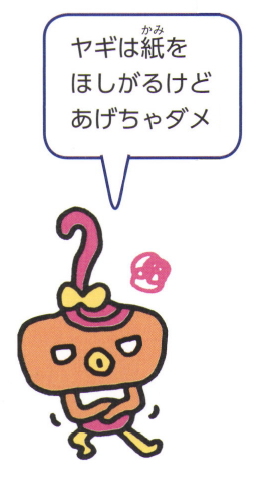
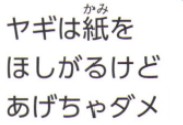
 動物園のふれあいコーナーでもおなじみのヤギ。
動物園のふれあいコーナーでもおなじみのヤギ。

49
ホッキョクグマはどうして氷の世界でも平気なの?
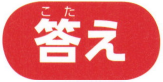 特殊な毛と、ぶあつい脂肪をもっているから
特殊な毛と、ぶあつい脂肪をもっているから
 ホッキョクグマがくらす北極地方は、冬の気温が平均で-25℃にもなる寒い地域です。ホッキョクグマがそんな寒さにたえられるのは、その毛に大きなひみつがあります。
ホッキョクグマがくらす北極地方は、冬の気温が平均で-25℃にもなる寒い地域です。ホッキョクグマがそんな寒さにたえられるのは、その毛に大きなひみつがあります。
白くみえるホッキョクグマの毛は、じつは透明です。たくさんあつまって、白くみえているのです。毛は、長い毛と短い毛の、二重構造です。長い毛は下にはえているフワフワの短い毛をまもります。短い毛は体のあたたかい空気をたもちます。
毛の1本1本は、ストローのように穴があいていて、中には空気がはいっています。ダウンジャケットのように、空気は寒さをふせぐのにとても効果があります。
皮膚の下にあるぶあつい脂肪は、体温をのがさず、また、栄養にもなります。
 ホッキョクグマの毛
ホッキョクグマの毛
ストローのように中に穴がある。穴には空気がはいっている。
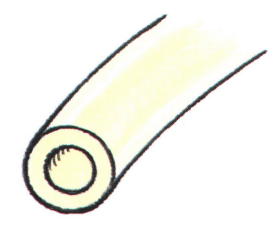
 体をあたためるしくみ
体をあたためるしくみ
毛が透明なので、太陽光線がさえぎられずに体にとどく。また、皮膚が黒いので、熱をむだなく吸収し、綿毛の間とぶあつい脂肪にためていられる。
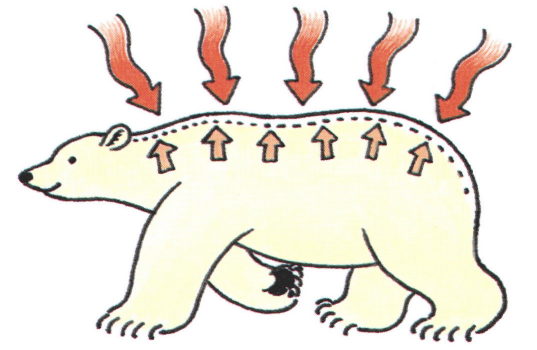
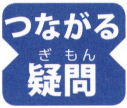 氷の海でもおよげるの?
氷の海でもおよげるの?
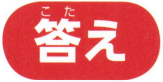 およいだり、もぐったりするのが得意です
およいだり、もぐったりするのが得意です
 ホッキョクグマは、泳ぎがとても上手です。時速およそ10kmのスピードでおよぐことができます。ときには数百kmの距離を、何時間もかけておよぐこともあります。
ホッキョクグマは、泳ぎがとても上手です。時速およそ10kmのスピードでおよぐことができます。ときには数百kmの距離を、何時間もかけておよぐこともあります。
体つきをみても、小さい顔に細長い首と、水の抵抗をうけにくい形です。あつい脂肪と、空気入りの毛があるので、つめたい水の中でも、平気です。
 ホッキョクグマは、主に陸の上でくらしていますが、海にうかぶ氷の上でやすんでいるアザラシなどのえものをみつけると、およいでちかづき、とらえます。
ホッキョクグマは、主に陸の上でくらしていますが、海にうかぶ氷の上でやすんでいるアザラシなどのえものをみつけると、およいでちかづき、とらえます。
 もぐるのもとくい。
もぐるのもとくい。

 陸にあがる瞬間に水をふるいおとすので、毛はこおりつかない。
陸にあがる瞬間に水をふるいおとすので、毛はこおりつかない。

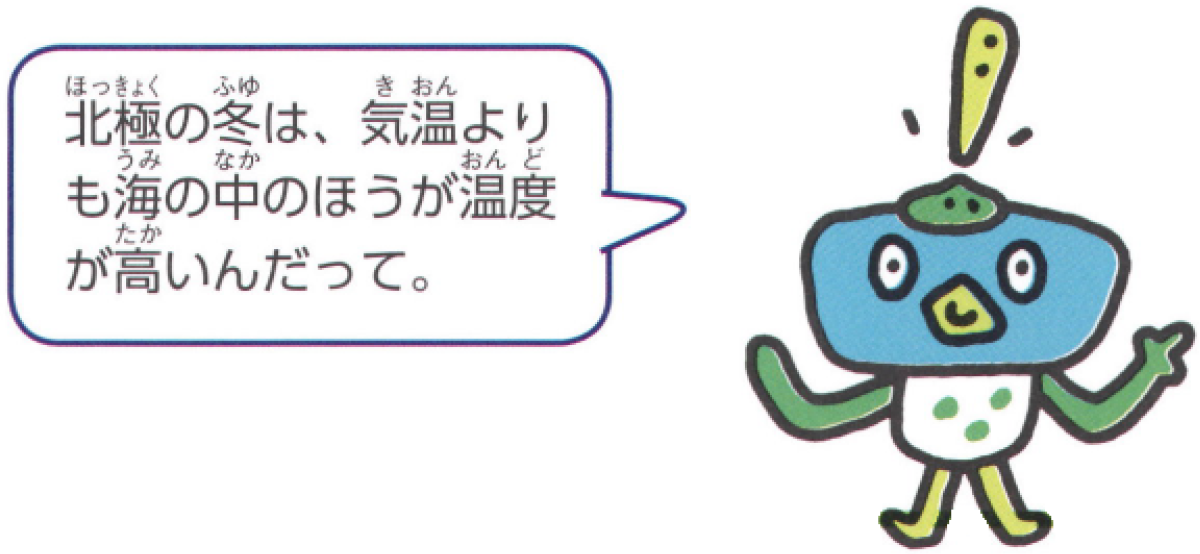
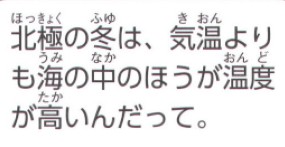
50
キツツキはどうして木をつつくの?
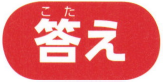 木の中の虫をつかまえたりするため
木の中の虫をつかまえたりするため
 キツツキが木をつつくのには、いくつかの理由があります。
キツツキが木をつつくのには、いくつかの理由があります。
まず、木の中にいる虫をつかまえるためです。木のまわりをつつきながら、音で中にいる虫をさがします。みつけると、あけた穴から長い舌をさしこみ、先にひっかけ、ひっぱりだしてたべます。
 またキツツキは木に穴をあけて巣をつくります。キツツキの巣のあとを、ほかの鳥や小動物が巣にすることも多いようです。
またキツツキは木に穴をあけて巣をつくります。キツツキの巣のあとを、ほかの鳥や小動物が巣にすることも多いようです。
 オスがなわばりをしめすためや、メスへのプロポーズをするときにも、キツツキは木をつついて音をだします。
オスがなわばりをしめすためや、メスへのプロポーズをするときにも、キツツキは木をつついて音をだします。
くちばしはどんどんのびるので、木をつついてもへりすぎることはありません。
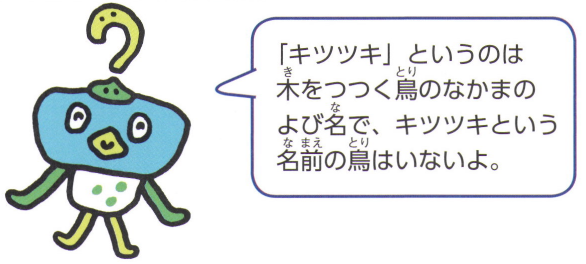
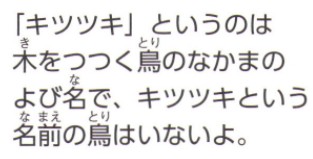
 コゲラ
コゲラ

 アカゲラ
アカゲラ

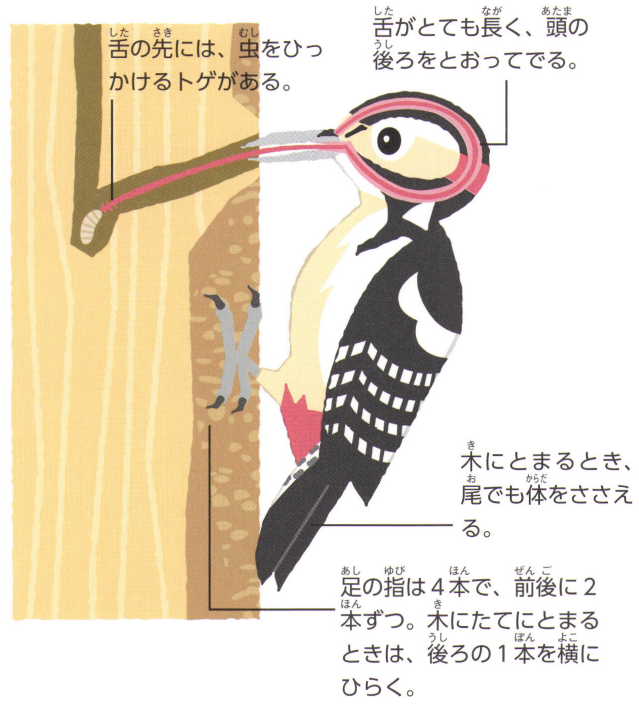
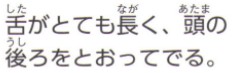
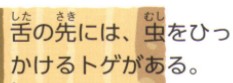
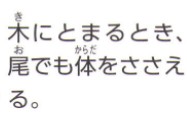
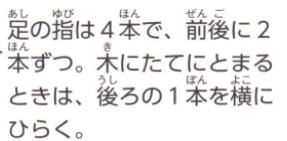
 鳥のくちばしをくらべてみよう
鳥のくちばしをくらべてみよう
鳥のくちばしは、種類によっていろいろな形をしています。食べ物の種類がちがうからです。
ほかにはどんなくちばしをもっている鳥がいるでしょう?


 かたい木の実のからをわることができる。
かたい木の実のからをわることができる。


 細長い形で、魚をはさんだり、さしたりする。
細長い形で、魚をはさんだり、さしたりする。


 とった小さなエビをのこして、水だけを外にこぼす。
とった小さなエビをのこして、水だけを外にこぼす。
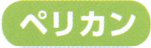

 水中の魚を水ごとすくう、バケツのような形。
水中の魚を水ごとすくう、バケツのような形。
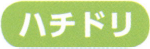

 細いくちばしで花のみつをなめる。
細いくちばしで花のみつをなめる。
51
小鳥はどうしてよくなくの?
 なかまと情報を交換したり、プロポーズしたりするため
なかまと情報を交換したり、プロポーズしたりするため
 鳥の鳴き声は、大きくわけて2種類あります。「じなき」と「さえずり」です。
鳥の鳴き声は、大きくわけて2種類あります。「じなき」と「さえずり」です。
じなきは、ふだんの会話です。なかまに居場所をおしえたり、危険をしらせたりする鳴き声です。スズメがふだん、チュンチュンとないているのは、じなきです。
さえずりは、オスがだす特別な鳴き声です。メスをさそったり、自分のなわばりにはいってきたほかのオスに対し、警告したりします。「ホーホケキョ」というよくしられた鳴き声は、ウグイスのさえずりです。
 スズメ
スズメ
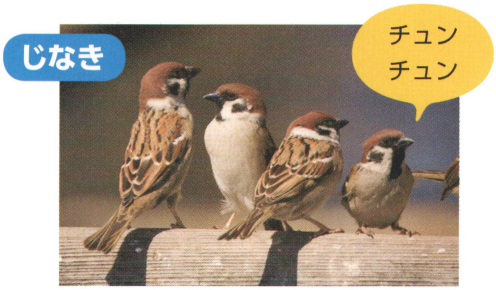


 ウグイス
ウグイス

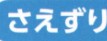

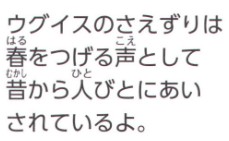
52
鳥はどうしてとべるの?
 軽い体に、大きなつばさと強い筋肉をもっているから
軽い体に、大きなつばさと強い筋肉をもっているから
 鳥が空をとぶためには、まず、何よりも、軽いことが大切です。鳥は、骨でさえ、とても軽くできています。
鳥が空をとぶためには、まず、何よりも、軽いことが大切です。鳥は、骨でさえ、とても軽くできています。
 つばさを大きくすれば、重くてもとべるのでしょうか? 大きなつばさをうごかすには、それだけ強い骨や、強い筋肉がなければなりません。そうすると、体が重くなってしまいます。
つばさを大きくすれば、重くてもとべるのでしょうか? 大きなつばさをうごかすには、それだけ強い骨や、強い筋肉がなければなりません。そうすると、体が重くなってしまいます。
また、体が重いと、とぶためのエネルギーも、たくさん必要になります。たくさん食べないとならないわけですが、食べるとその分、また重くなりますね。
このように、体が重いほど、とぶことがむずかしいのです。
 鳥はこうしてとんでいる
鳥はこうしてとんでいる
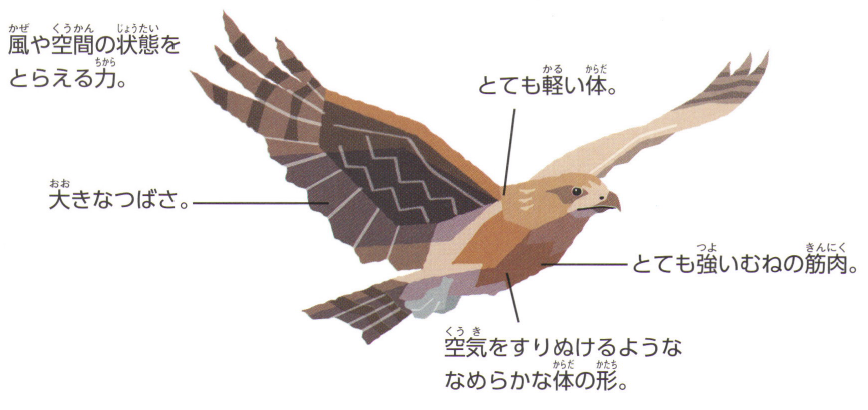
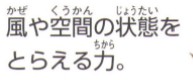
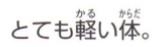
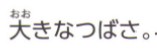
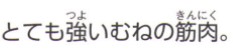
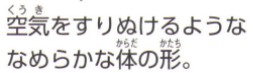
 鳥と飛行機のとびかたのちがい
鳥と飛行機のとびかたのちがい
 鳥はつばさをはばたかせることで、うかぶ力と、前にすすむ力をうみだしている。
鳥はつばさをはばたかせることで、うかぶ力と、前にすすむ力をうみだしている。
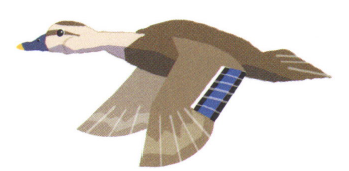
 飛行機はエンジンなどでつくった前にすすむ力をつかい、つばさに風をあて、うかぶ力をうみだしている。
飛行機はエンジンなどでつくった前にすすむ力をつかい、つばさに風をあて、うかぶ力をうみだしている。

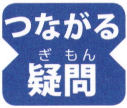 鳥のなかまはみんなとべるの?
鳥のなかまはみんなとべるの?
 とべない鳥もいます
とべない鳥もいます
 空をとぶ鳥たちとはちがう、ほかの生き方をみつけた鳥もいます。
空をとぶ鳥たちとはちがう、ほかの生き方をみつけた鳥もいます。
それぞれがくらしている場所や食べ物によって、つごうのいい体の形に変化したのです。
また、改良されて、とばなくなった鳥もいます。


 体が重く、とべないが、長くて強い足で速くはしれる。
体が重く、とべないが、長くて強い足で速くはしれる。
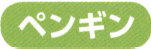

 つばさがひれにかわり、水中をとぶようにおよぐ。
つばさがひれにかわり、水中をとぶようにおよぐ。


 人にかわれたことで、とぶことが必要なくなった。
人にかわれたことで、とぶことが必要なくなった。
53
鳥はどんなところに巣をつくるの?
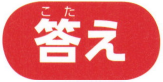 鳥の種類によってさまざまです
鳥の種類によってさまざまです
 鳥の巣は、ほとんどがすみかではなく、鳥がたまごをうみ、子どもをそだてるためにつくるものです。
鳥の巣は、ほとんどがすみかではなく、鳥がたまごをうみ、子どもをそだてるためにつくるものです。
鳥の巣というと、木の上に枝をあつめてつくられたものをイメージしがちですが、場所だけでなく、形や素材など、じつにいろいろな鳥の巣があります。
最近は、巣材にビニールひもなどの人工物がつかわれることもあります。


 かれた木などに穴をあけ、巣をつくる。巣は1回きりで、毎年新しくつくりなおす。
かれた木などに穴をあけ、巣をつくる。巣は1回きりで、毎年新しくつくりなおす。


 都会では電柱の上などにも巣がつくられる。巣材にははりがねハンガーもつかわれる。
都会では電柱の上などにも巣がつくられる。巣材にははりがねハンガーもつかわれる。


 木の枝の上に、体のわりに小さなおわん状の巣をつくる。巣材は細長い草など。
木の枝の上に、体のわりに小さなおわん状の巣をつくる。巣材は細長い草など。


 水辺の植物やくいの上に葉やくきをのせてつくった巣は、ういているようにみえる。
水辺の植物やくいの上に葉やくきをのせてつくった巣は、ういているようにみえる。


 河原のヨシ原に、ヨシの葉やくきなどをくみあわせたおわん形の巣をつくる。
河原のヨシ原に、ヨシの葉やくきなどをくみあわせたおわん形の巣をつくる。


 人の家のかべなどに、どろとかれ草をつばでまぜあわせて巣をつくる。
人の家のかべなどに、どろとかれ草をつばでまぜあわせて巣をつくる。


 小石の多い河原などにくぼみをつけて巣にする。たまごは石ににて、めだたない。
小石の多い河原などにくぼみをつけて巣にする。たまごは石ににて、めだたない。


 地面の草の根元などにあさい穴をほり、わらなどで簡単な巣をつくる。
地面の草の根元などにあさい穴をほり、わらなどで簡単な巣をつくる。
 カッコウは巣をつくらない?
カッコウは巣をつくらない?
カッコウは、ほかの鳥の巣に気づかれないようにたまごをうんで、その鳥に自分の子どもをそだてさせます。カッコウのひなは、本当のひなより早く大きくそだちます。
54
渡り鳥はどうしてわたってくるの?
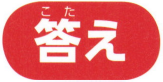 季節にあわせて、くらしやすい場所へうつります
季節にあわせて、くらしやすい場所へうつります
 渡り鳥は、夏に子そだてする土地と、冬をこす土地との間を、季節にあわせて移動します。この移動のことを「渡り」といいます。
渡り鳥は、夏に子そだてする土地と、冬をこす土地との間を、季節にあわせて移動します。この移動のことを「渡り」といいます。
渡りには、大きな危険をともないます。それなのに渡り鳥は、なぜ1か所の土地でくらさないのでしょうか?
 なぜ渡りをするようになったかは、よくわかっていませんが、たりなくなった食べ物をもとめて、大昔から毎年移動をくりかえすうちに、いまのような渡りの形になったのかもしれません。
なぜ渡りをするようになったかは、よくわかっていませんが、たりなくなった食べ物をもとめて、大昔から毎年移動をくりかえすうちに、いまのような渡りの形になったのかもしれません。
 日本に夏の間いる鳥を「夏鳥」、日本で冬をこす鳥を「冬鳥」、春と秋の時期だけみられる鳥を「旅鳥」とよんでいます。
日本に夏の間いる鳥を「夏鳥」、日本で冬をこす鳥を「冬鳥」、春と秋の時期だけみられる鳥を「旅鳥」とよんでいます。
夏鳥ではツバメが、冬鳥ではハクチョウやツルが、旅鳥ではシギ、チドリなどがしられています。
 ツバメの渡りルート
ツバメの渡りルート
 東南アジア、台湾などから、3000~5000
の距離をとんでくる。
東南アジア、台湾などから、3000~5000
の距離をとんでくる。
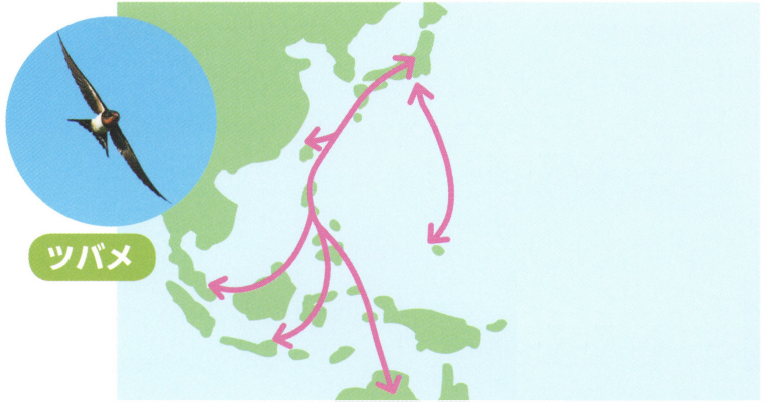
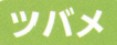

 オオハクチョウの渡りルート
オオハクチョウの渡りルート
 およそ3000
はなれたシベリアから、日本の北海道・本州へやってくる。
およそ3000
はなれたシベリアから、日本の北海道・本州へやってくる。


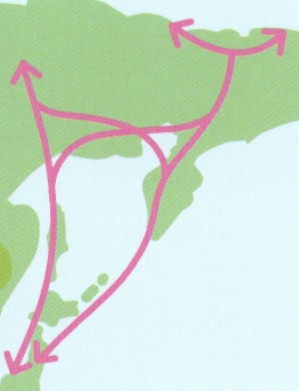
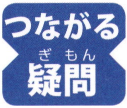 一番長い渡りをする鳥は?
一番長い渡りをする鳥は?
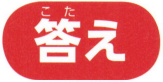 キョクアジサシです
キョクアジサシです
 キョクアジサシは、1年で世界を1周します。大陸ぞいをS字状にとぶきょりは、8万
にもなります。夏に北極で子そだてをしたあと、南極まで移動して冬をこします。夏にはまた北極へもどってきます。
キョクアジサシは、1年で世界を1周します。大陸ぞいをS字状にとぶきょりは、8万
にもなります。夏に北極で子そだてをしたあと、南極まで移動して冬をこします。夏にはまた北極へもどってきます。
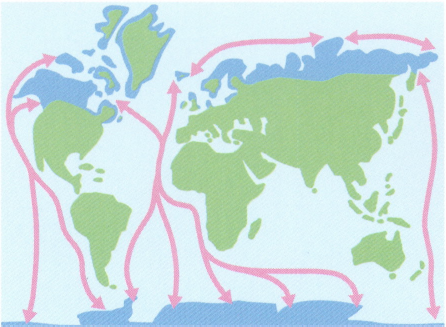

 渡りをするチョウもいる
渡りをするチョウもいる
アサギマダラは、春~夏は日本の山でくらし、秋になると南下します。海をわたり、遠く台湾で冬をこすものもいます。

55
カメレオンはなぜ体の色がかわるの?
 敵から身をまもり、えものをとりやすくなるから
敵から身をまもり、えものをとりやすくなるから
 体の色がまわりの色ににると、すがたがわかりにくくなります。カメレオンをねらう、ヘビや鳥などの敵の目からのがれることができます。
体の色がまわりの色ににると、すがたがわかりにくくなります。カメレオンをねらう、ヘビや鳥などの敵の目からのがれることができます。
また、カメレオンは、長い舌をのばして虫をとらえてたべますが、このときも、えものに気づかれずに、ねらいうつことができます。
 あざやかな色のカメレオン。
あざやかな色のカメレオン。


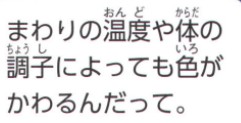
 体の色をかえる生き物
体の色をかえる生き物
このほか、ライチョウなど季節で色がかわるものもいます。生き物の体の色や模様が、まわりの色とそっくりなことを保護色といいます。

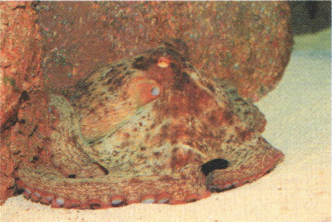
 色つきの細胞がうごいて色がかわる。体の形もかえられる変身の名人。
色つきの細胞がうごいて色がかわる。体の形もかえられる変身の名人。

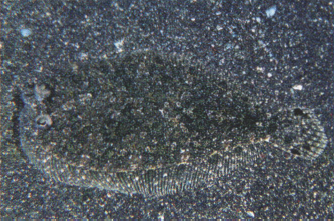
 明るさだけの変化だが、海底の砂や石の模様そっくりになる。
明るさだけの変化だが、海底の砂や石の模様そっくりになる。


 カメレオンと同じように虹色素胞をもっているが、色の変化はゆっくり。
カメレオンと同じように虹色素胞をもっているが、色の変化はゆっくり。
56
イルカは頭がいいの?
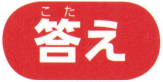 頭のいい生き物です
頭のいい生き物です
 バンドウイルカについて、これまでしられていることから、頭がいいといわれる理由をかんがえてみましょう。
バンドウイルカについて、これまでしられていることから、頭がいいといわれる理由をかんがえてみましょう。
①体重にしめる脳の重さが人間にちかい
つまり脳が大きく発達しているということです。
②人や図形を区別できる
水族館では新人飼育員にいたずらなどをします。
③なかまとはなす
声をだして何かをつたえあっています。
④楽しい、悲しいといった感情がある
あそぶことが大すきで、さそってきます。
⑤効率のよいやり方をかんがえられる
たとえば、何かをはこぶとき、ひとつひとつをはこぶのではなく、1か所にまとめてはこんだりします。
⑥サメから人をたすけたという報告が多い
弱いものをたすけようとします。
 人とはちがう生き物なので、単純にはいえませんが、頭がいいことはたしかでしょう。
人とはちがう生き物なので、単純にはいえませんが、頭がいいことはたしかでしょう。
 好奇心が強く、人なつっこいイルカ。
好奇心が強く、人なつっこいイルカ。

 なかまと協力して魚をとったりします。
なかまと協力して魚をとったりします。

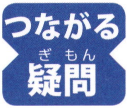 人にはない、すぐれた力をもってるの?
人にはない、すぐれた力をもってるの?
 音をつかってものをみることができます
音をつかってものをみることができます
 イルカは、真っ暗な海の中でも魚をとったりできます。目ではなく、音でまわりのようすをみているのです。
イルカは、真っ暗な海の中でも魚をとったりできます。目ではなく、音でまわりのようすをみているのです。
イルカは、高い音をだして、それが何かにあたってはねかえってくる音をきき、その物体をみわけることができます。その物体の位置はもちろん、形や大きさ、かたさや、やわらかさまでわかります。これは「エコーロケーション」という能力です。
 100
先にある野球のボールほどの大きさのものもわかる。
100
先にある野球のボールほどの大きさのものもわかる。
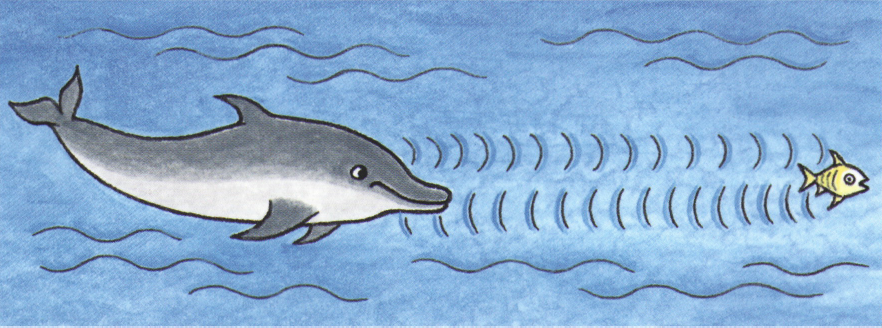
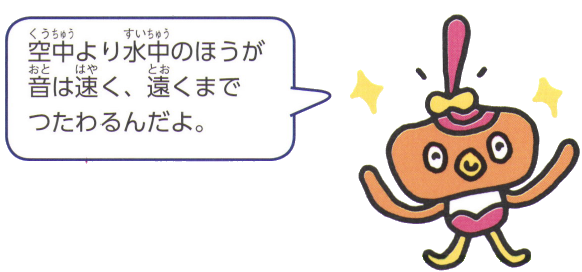
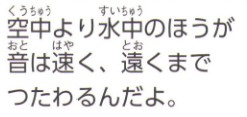
57
イカやタコはどうしてすみをはくの?
 敵から身をまもるため
敵から身をまもるため
 イカ、タコとも、身をかくすのが得意ですが、敵にみつかるときもあります。
イカ、タコとも、身をかくすのが得意ですが、敵にみつかるときもあります。
そんなとき、どちらも敵からにげるためにすみをはきます。でも、イカとタコのすみはきには、少しちがいがあります。
 イカのすみはきは「分身のじゅつ」です。イカのすみは、どろっとしていて、かたまりになります。敵にはこれがイカの体にみえ、そっちに気をとられます。このすきに、イカはにげてしまいます。
イカのすみはきは「分身のじゅつ」です。イカのすみは、どろっとしていて、かたまりになります。敵にはこれがイカの体にみえ、そっちに気をとられます。このすきに、イカはにげてしまいます。
 タコがつかうのは「えんまくのじゅつ」です。タコのはいたすみは、もわっと水中にひろがります。このすみは、目かくしになるほか、敵の鼻がきかなくなる成分がはいっていて、敵はタコをおうことがむずかしくなります。
タコがつかうのは「えんまくのじゅつ」です。タコのはいたすみは、もわっと水中にひろがります。このすみは、目かくしになるほか、敵の鼻がきかなくなる成分がはいっていて、敵はタコをおうことがむずかしくなります。
 イカのすみはき。
イカのすみはき。
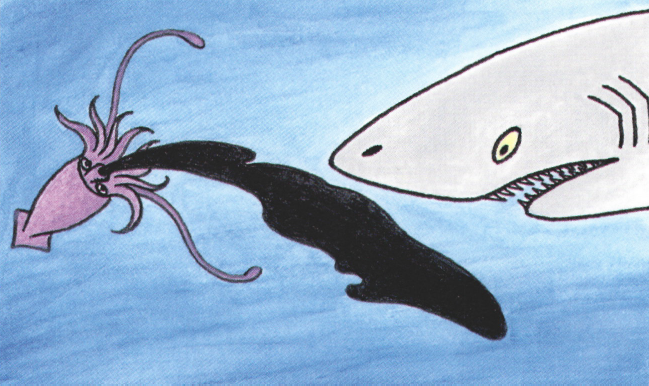
 タコのすみはき。
タコのすみはき。

 ほかにどんな身のまもり方をするなかまがいる?
ほかにどんな身のまもり方をするなかまがいる?
海の生き物たちは、じつにさまざまな方法で、敵から身をまもっています。イカやタコのように、じゅつにたとえてみてみましょう。

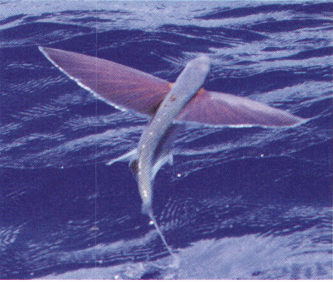
 「空とびのじゅつ」。海面からとびだし、海の上をとんでにげる。およそ400もの距離をとぶこともある。
「空とびのじゅつ」。海面からとびだし、海の上をとんでにげる。およそ400もの距離をとぶこともある。
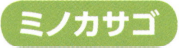

 「毒針のじゅつ」。大きなひれに、毒針をもつ。おそわれないように、わざとはでなすがたをしている。
「毒針のじゅつ」。大きなひれに、毒針をもつ。おそわれないように、わざとはでなすがたをしている。


 「毒液のじゅつ」。敵におそわれると、体の表面から、ひどいにおいのする毒液をだす。
「毒液のじゅつ」。敵におそわれると、体の表面から、ひどいにおいのする毒液をだす。

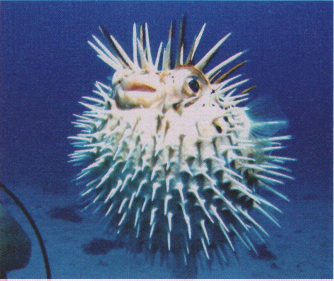
 「とげとげのじゅつ」。びっくりすると、水をすいこんでふくらみ、とげだらけの体になる。
「とげとげのじゅつ」。びっくりすると、水をすいこんでふくらみ、とげだらけの体になる。
58
ヤドカリがひっこすって本当?
 体の成長にあわせ、大きな貝がらにうつります
体の成長にあわせ、大きな貝がらにうつります
 ヤドカリは、カニやエビなどと同じ甲殻類ですが、ほかのなかまとは少しちがった特徴をもっています。おなかの部分が、やわらかいのです。おなかをまもるため、ヤドカリは海底などにおちている貝がらにおなかをさしこんて、せおいながらくらします。
ヤドカリは、カニやエビなどと同じ甲殻類ですが、ほかのなかまとは少しちがった特徴をもっています。おなかの部分が、やわらかいのです。おなかをまもるため、ヤドカリは海底などにおちている貝がらにおなかをさしこんて、せおいながらくらします。
 ヤドカリは脱皮をして大きくなっていきますが、貝がらは大きくなりません。そのため、それまでの貝がらがせまくかんじると、大きな貝がらをさがしてひっこしをするのです。ほかのヤドカリから、貝がらをうばいとることもあります。
ヤドカリは脱皮をして大きくなっていきますが、貝がらは大きくなりません。そのため、それまでの貝がらがせまくかんじると、大きな貝がらをさがしてひっこしをするのです。ほかのヤドカリから、貝がらをうばいとることもあります。
 新しい貝がらをとりあうヤドカリ。
新しい貝がらをとりあうヤドカリ。

 ヤドカリの体
ヤドカリの体
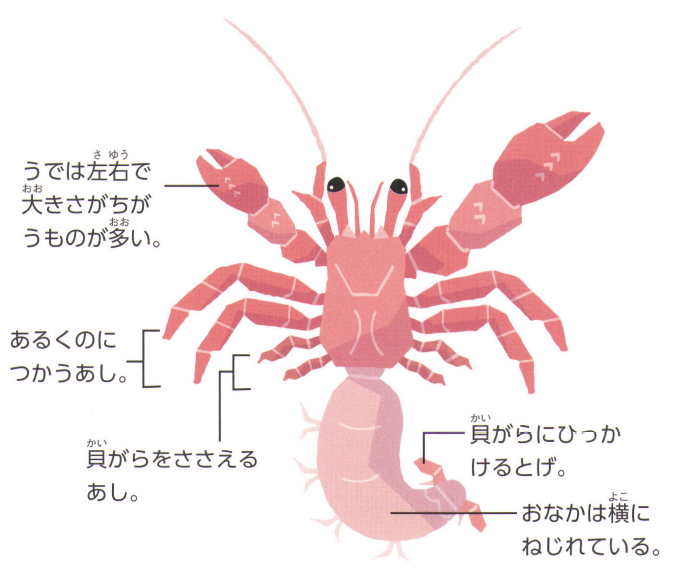
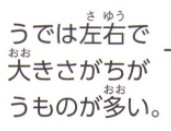
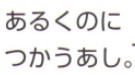
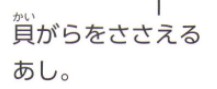
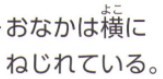
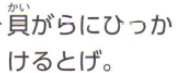
 カタツムリもひっこすの?
カタツムリもひっこすの?
ひっこしません。
カタツムリのからは、体の一部です。体と一緒に、からもだんだん大きくなっていきます。

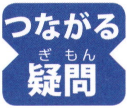 なぜイソギンチャクをせおうヤドカリがいるの?
なぜイソギンチャクをせおうヤドカリがいるの?
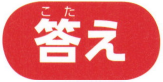 一緒にいると、おたがいにつごうがいいのです
一緒にいると、おたがいにつごうがいいのです
 これは、おたがいにたすけあう関係です。
これは、おたがいにたすけあう関係です。
イソギンチャクにしてみれば、ヤドカリにのって移動ができ、えものをとるチャンスがひろがります。
ヤドカリは、イソギンチャクをつかって身をまもります。イソギンチャクは毒のとげをもっているので、ヤドカリの敵の魚などから、ねらわれにくくなります。
 イソギンチャクをせおったソメンヤドカリ。ひっこすときは、新しい貝がらにイソギンチャクをつけかえる。
イソギンチャクをせおったソメンヤドカリ。ひっこすときは、新しい貝がらにイソギンチャクをつけかえる。

59
サケがうまれた川にもどるのはなぜ?
 自分がうまれた川でたまごをうむため
自分がうまれた川でたまごをうむため
 サケは川でうまれます。赤ちゃんから子どもになると川をくだり、海にでて、数年の間、海を大きく移動しながらそだちます。そしておとなになると、産卵のため、川をさかのぼり、ふるさとへかえってくるのです。本能的に自分がうまれたふるさとが、安心してたまごをうめる場所としっているのです。
サケは川でうまれます。赤ちゃんから子どもになると川をくだり、海にでて、数年の間、海を大きく移動しながらそだちます。そしておとなになると、産卵のため、川をさかのぼり、ふるさとへかえってくるのです。本能的に自分がうまれたふるさとが、安心してたまごをうめる場所としっているのです。
 それにしても、何年間も遠く広い海でくらしているのに、どうやって自分のうまれた川がわかるのでしょう。まいごにはならないのでしょうか
それにしても、何年間も遠く広い海でくらしているのに、どうやって自分のうまれた川がわかるのでしょう。まいごにはならないのでしょうか
サケはうまれた川のにおいをおぼえていて、それをみつけてかえってくるとかんがえられています。川のにおいにたどりつくまで、太陽の位置や、地球の磁力などもあわせて手がかりにするようです。
 日本うまれのサケがたどるルート
日本うまれのサケがたどるルート
 川から海へ、海から川へ。サケは一生の間、旅をする魚。
川から海へ、海から川へ。サケは一生の間、旅をする魚。
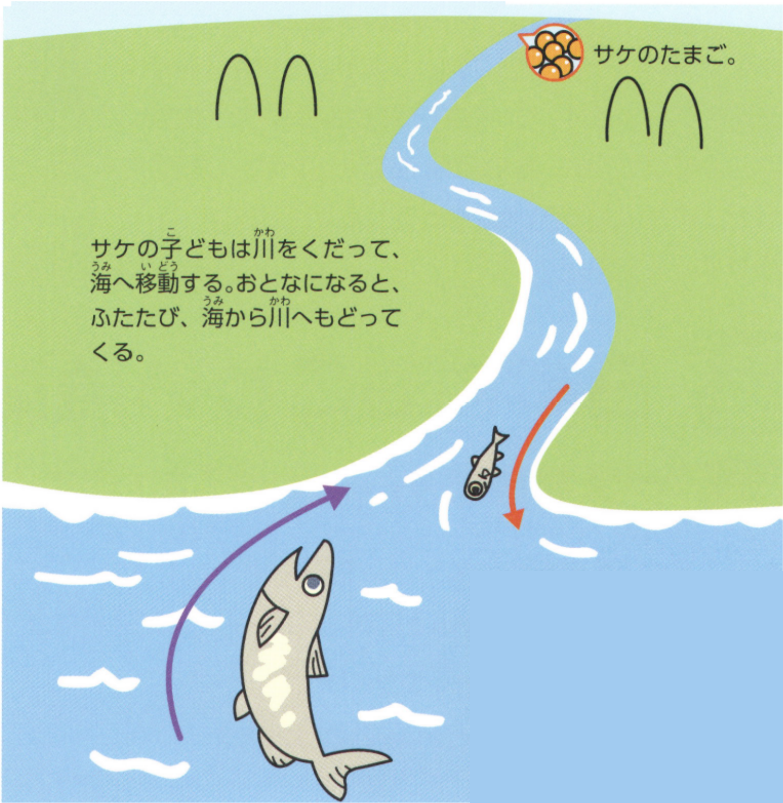
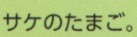
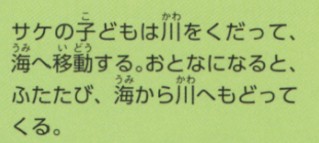
 オホーツク海から、アラスカの海まで移動し、もどってくる。
オホーツク海から、アラスカの海まで移動し、もどってくる。
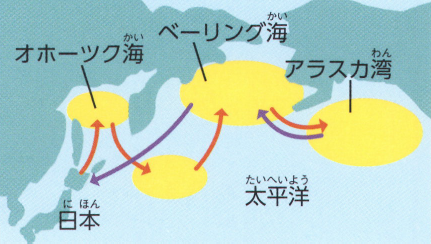

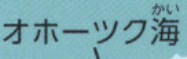

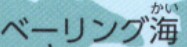
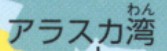
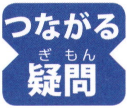 鼻のまがったサケはちがう種類?
鼻のまがったサケはちがう種類?
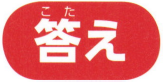 川へもどってきたオスのサケのすがたです
川へもどってきたオスのサケのすがたです
 交尾のために川へもどったオスのサケは体の色や形がかわり、メスに注目されます。鼻の先がワシのくちばしのようにまがるので「鼻曲がりサケ」とよばれます。
交尾のために川へもどったオスのサケは体の色や形がかわり、メスに注目されます。鼻の先がワシのくちばしのようにまがるので「鼻曲がりサケ」とよばれます。
メスも、体の色だけですが、かわります。

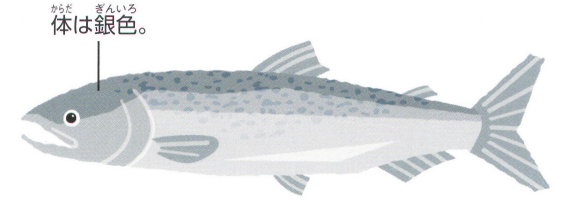


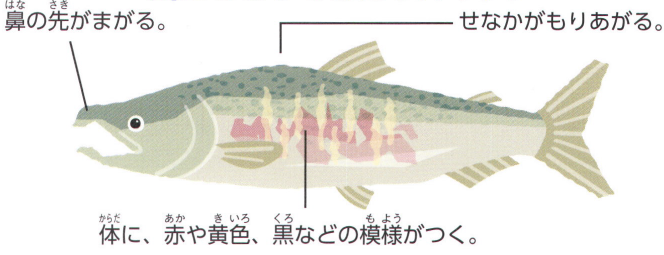

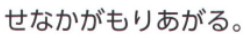
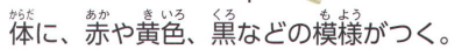
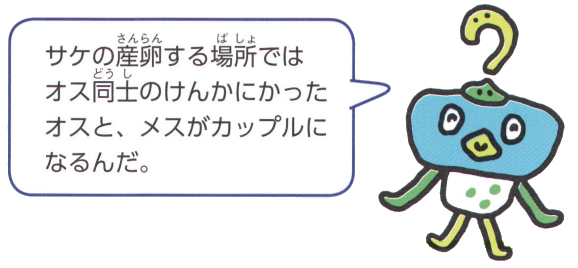
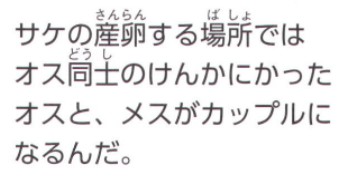
60
ピラニアはこわい魚って本当?
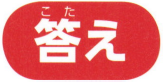 おくびょうだけど、するどい歯をもつ危険な魚です
おくびょうだけど、するどい歯をもつ危険な魚です
 南米のアマゾン川にすむピラニアは、こわい魚として有名です。カミソリのようによくきれる歯で、えものの肉をそぎおとしてたべます。性格はおくびょうで、ふつうは大きな生き物にはちかづきません。しかし、血のにおいに敏感で、いったん興奮すると、むれでおそいかかってくるのでたいへん危険です。
南米のアマゾン川にすむピラニアは、こわい魚として有名です。カミソリのようによくきれる歯で、えものの肉をそぎおとしてたべます。性格はおくびょうで、ふつうは大きな生き物にはちかづきません。しかし、血のにおいに敏感で、いったん興奮すると、むれでおそいかかってくるのでたいへん危険です。
 ピラニア。
ピラニア。

 するどい歯がならんでいる。
するどい歯がならんでいる。

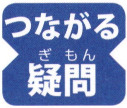 日本にもこわい魚はいるの?
日本にもこわい魚はいるの?
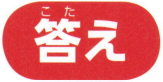 サメをはじめ、たくさんいます
サメをはじめ、たくさんいます
 かまれると危険な魚では、カッターのようにするどい歯のウツボ、タチウオ、フグ。ペンチのようにかむ力が強いイシダイなどです。ほかにも、とげや毒をもつ、危険な魚がいます。
かまれると危険な魚では、カッターのようにするどい歯のウツボ、タチウオ、フグ。ペンチのようにかむ力が強いイシダイなどです。ほかにも、とげや毒をもつ、危険な魚がいます。
するどい歯をもつ魚たち



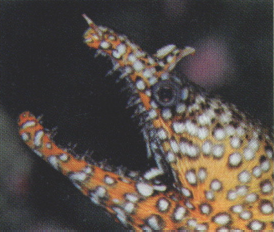


 ダイバーがおそれる魚
ダイバーがおそれる魚


 光にむかってすごいスピードでとっしんしてくるため、体につきささることがある。
光にむかってすごいスピードでとっしんしてくるため、体につきささることがある。


 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。
 魚はみんな歯をもっているのかな?
魚はみんな歯をもっているのかな?
魚の歯は、その魚が主に何をどうやってたべるかによってちがいます。歯をつかわずにたべる魚は、歯が少なかったり小さかったりします。
お店で魚をかったときや、身近にいる魚の口を、実際にみてみましょう。


 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。あごに歯はないが、のどのおくに歯のようなでっぱりをもつ。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。あごに歯はないが、のどのおくに歯のようなでっぱりをもつ。


 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。おびきよせた魚をとらえるため、たくさんの大きな歯がある。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。おびきよせた魚をとらえるため、たくさんの大きな歯がある。
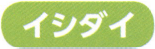

 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。
61
魚もねむるの?
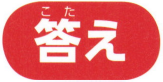 いろいろなねむり方をします
いろいろなねむり方をします
 金魚が、夜などしずかなときに、水そうのすみでじっとしていることがありますが、これは、ねむっている状態です。
金魚が、夜などしずかなときに、水そうのすみでじっとしていることがありますが、これは、ねむっている状態です。
ほとんどの魚にはまぶたがありません。目をとじないので、ねむっているのかわかりにくいですが、魚もやはりねむります。
魚の種類によって、ねむり方はいろいろあります。中にはとてもかわった方法をとる魚もいます。

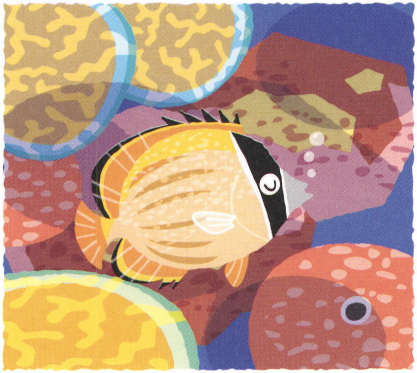
 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。きれいな体の色を地味な色にかえて、岩やサンゴのかげにかくれてねむる。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。きれいな体の色を地味な色にかえて、岩やサンゴのかげにかくれてねむる。

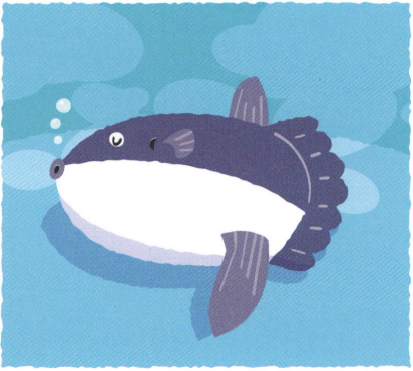
 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。平べったい体を横にしてねむる。海面で日光浴をしながら昼寝をすることもある。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。平べったい体を横にしてねむる。海面で日光浴をしながら昼寝をすることもある。
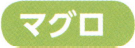

 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。およぎながら息をするため、ゆっくりおよいだまま、短いねむりをくりかえす。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。およぎながら息をするため、ゆっくりおよいだまま、短いねむりをくりかえす。


 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。ねている間にながされないように、口で海草につかまったままねむる。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。ねている間にながされないように、口で海草につかまったままねむる。
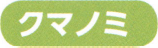

 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。大きな魚からねらわれないように、イソギンチャクの触手の中でねむる。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。大きな魚からねらわれないように、イソギンチャクの触手の中でねむる。
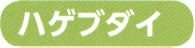

 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。ウツボなどから身をまもるため、粘膜でつくった透明なふくろの中でねむる。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。ウツボなどから身をまもるため、粘膜でつくった透明なふくろの中でねむる。
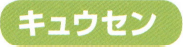
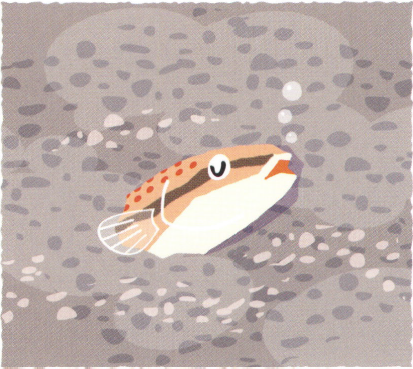
 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。夜になると、体を横むきにして、砂の中にはいってねむる。朝は早おき。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。夜になると、体を横むきにして、砂の中にはいってねむる。朝は早おき。
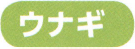
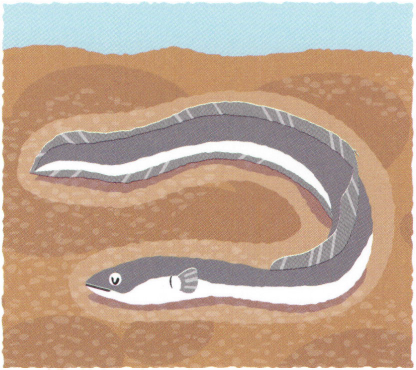
 なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。昼間に、どろにもぐってねむっている。暗くなるとおきて活動する。
なわばり意識が強く、人をおそうこともある。強力なあごで、ウエットスーツもくいちぎる。人のおく歯のような歯をもち、貝がらなどをかみくだく。昼間に、どろにもぐってねむっている。暗くなるとおきて活動する。
62
魚にも耳や鼻があるの?
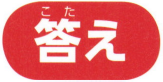 人とは形がちがいますが、あります
人とは形がちがいますが、あります
 魚には人のように、耳の穴はありません。しかし頭の中には、内耳という音をきく器官をもっています。
魚には人のように、耳の穴はありません。しかし頭の中には、内耳という音をきく器官をもっています。
さらに魚の体の横には、水の振動をかんじとる側線という器官があります。
音というのは、空気や水がふるえておきる波のこと。つまり振動です。魚は音を、きくというより、体でかんじとっているのです。
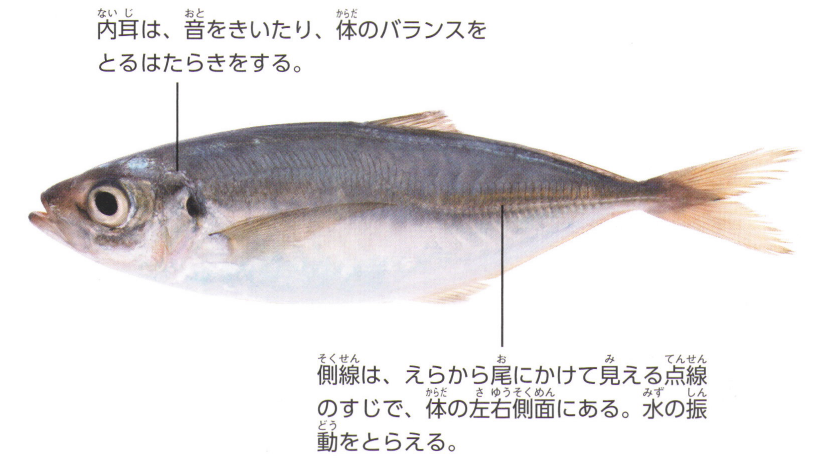
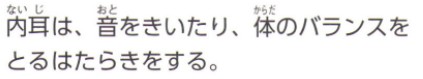
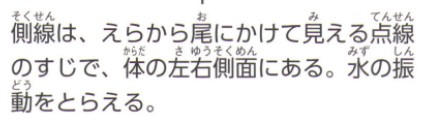
 魚にも鼻の穴があります。しかし魚は鼻で息はしません。鼻はにおいをとらえるためにあります。
魚にも鼻の穴があります。しかし魚は鼻で息はしません。鼻はにおいをとらえるためにあります。
魚の顔をよくみると、左右に2つずつ穴があります。前の穴を前鼻孔、後ろの穴を後鼻孔といって、前から後ろへ、トンネルのようにつながっています。このトンネルに水をくぐらせて、においをとらえるのです。
 金魚の鼻。穴がそれぞれ2つならんでいる。
金魚の鼻。穴がそれぞれ2つならんでいる。


 トラウツボは、つきでた前鼻孔と、角のような後鼻孔をもっている。
トラウツボは、つきでた前鼻孔と、角のような後鼻孔をもっている。



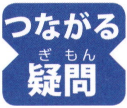 耳や鼻が一番すぐれた魚は何?
耳や鼻が一番すぐれた魚は何?
 サメです
サメです
 耳と鼻のどちらもすぐれているのは、おそらくサメでしょう。
耳と鼻のどちらもすぐれているのは、おそらくサメでしょう。
サメはふつう、えものをまず音でとらえます。数
はなれた場所にいるえものがだす音をきくことができます。数百
の距離までちかづくと、においをたどって、えものにせまっていきます。


 血のにおいにはとくに敏感で、100万倍にうすめた1てきの血のにおいがわかります。
血のにおいにはとくに敏感で、100万倍にうすめた1てきの血のにおいがわかります。
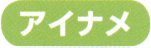

 体の左右に、それぞれ5本の側線をもっていて、物音に敏感な魚です。
体の左右に、それぞれ5本の側線をもっていて、物音に敏感な魚です。
63
田んぼにはなぜ水をはるの?
 雑草や寒さからイネをまもり、そだちやすくするため
雑草や寒さからイネをまもり、そだちやすくするため
 イネには、畑でそだつ陸稲という種類もありますが、日本で多いのは、水稲という水田でそだつものです。
イネには、畑でそだつ陸稲という種類もありますが、日本で多いのは、水稲という水田でそだつものです。
どうして水田が多いのかといえば、それが水のゆたかな日本にあった農業だからです。
 水田には、水の特性をいかした、いろいろな知恵がかくされています。
水田には、水の特性をいかした、いろいろな知恵がかくされています。
イネは寒さに弱い植物ですが、水田の水は、夜の寒さからイネをまもってくれます。昼間あたたまった水は、夜になってもあたたかいのです。また、水田は、畑よりも根をはる雑草が少ないので、イネはすくすくとそだちます。
 田んぼの水は、夏の暑さもやわらげてくれる。
田んぼの水は、夏の暑さもやわらげてくれる。

 水をはると、イネにいいことがいっぱい
水をはると、イネにいいことがいっぱい
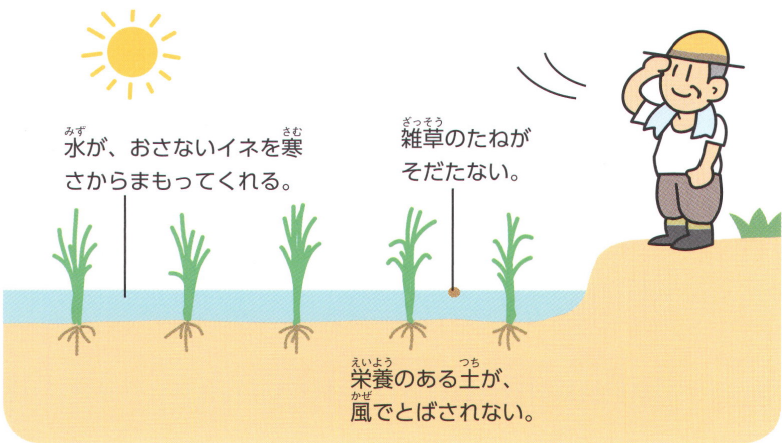
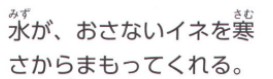
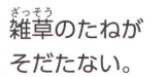
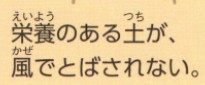

①広い田んぼの水まきをしなくてすむ。
②雑草とりの作業がへる。
③山からの水のおかげで、肥料が少なくてすむ。
④土が悪くならず、毎年お米がつくれる。
64
キノコは植物なの?
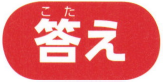 植物ではなく菌類です
植物ではなく菌類です
 キノコは以前、胞子でふえる植物のシダやコケにちかいなかまとされていました。しかし、今は「菌類」という新しい分類にあらためられています。
キノコは以前、胞子でふえる植物のシダやコケにちかいなかまとされていました。しかし、今は「菌類」という新しい分類にあらためられています。
植物と菌類の大きなちがいは、自分自身で養分をつくれるかどうかです。植物は光があれば、自分で養分をつくれます。菌類は自分では養分をつくらず、ほかから養分をとっていきています。
 キノコは木の根や、くさった木などにはえて、その養分をすう。
キノコは木の根や、くさった木などにはえて、その養分をすう。

 カビもキノコのなかま
カビもキノコのなかま
カビも菌類のなかまです。キノコと同じように菌糸をのばし、胞子でふえていきます。キノコはかさをつくって胞子をばらまきますが、カビは菌糸の先に胞子ができます。
 パンにはえた青カビ。
パンにはえた青カビ。
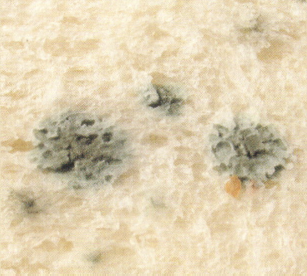
 みかんにはえた青カビ。
みかんにはえた青カビ。

 米こうじ。
米こうじ。

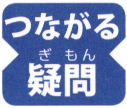 雷がおちたところにキノコがよくはえるって本当?
雷がおちたところにキノコがよくはえるって本当?
 電気でキノコがよくそだつことが、確認されています
電気でキノコがよくそだつことが、確認されています
 雷はキノコをふやします。これは、キノコの産地で昔からいいつたえられていたことでしたが、実験により本当だとわかっています。
雷はキノコをふやします。これは、キノコの産地で昔からいいつたえられていたことでしたが、実験により本当だとわかっています。
実験によると、高圧電流を一瞬だけながしてそだてたキノコは、ふつうにそだてたものより、かなりたくさんふえるのです。
電気によって死んでしまうキノコもあり、どうしてふえるのかは、まだよくわかっていません。
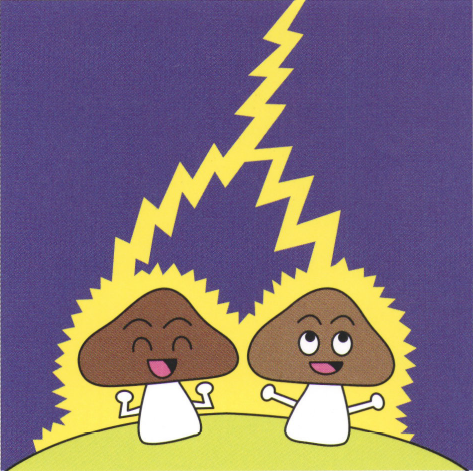
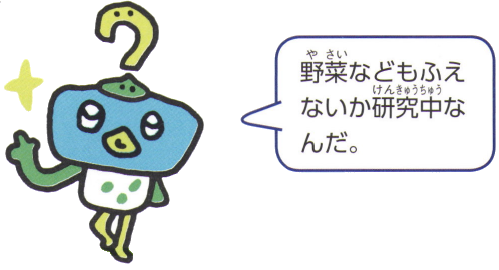
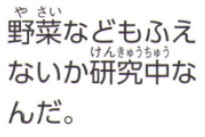
65
帰化植物って何?
 ほかの国からきた植物が、その国で野生化したもの
ほかの国からきた植物が、その国で野生化したもの
 風がはこんだたねから自然にふえたりしたものは、帰化植物とはいいません。輸入品のコンテナにまぎれこむなどして、意識せずにはこばれた場合もふくめて、人の手によって国内にもちこまれ、野外にひろがった植物が帰化植物です。
風がはこんだたねから自然にふえたりしたものは、帰化植物とはいいません。輸入品のコンテナにまぎれこむなどして、意識せずにはこばれた場合もふくめて、人の手によって国内にもちこまれ、野外にひろがった植物が帰化植物です。
多くの帰化植物は、そだつ力の強い種類です。人びとにこのまれるようになった植物もあれば、もともとあった植物に害をあたえるものもあります。
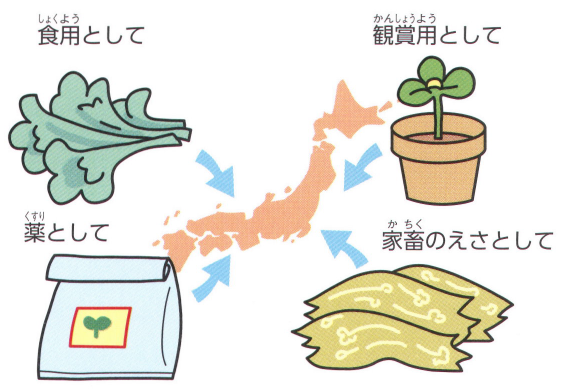
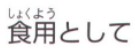

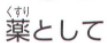
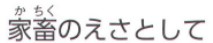
身近な帰化植物


 明治時代のはじめにつたわる。秋に花粉症をひきおこす原因のひとつになっている。
明治時代のはじめにつたわる。秋に花粉症をひきおこす原因のひとつになっている。


 南アメリカ原産の花。江戸時代には、たねの中の白いこながおしろいのかわりにつかわれた。
南アメリカ原産の花。江戸時代には、たねの中の白いこながおしろいのかわりにつかわれた。
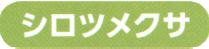

 西洋では、にもつのクッション材につかわれていたことからこの名前がついた。家畜のえさ用に輸入され、野生化した。
西洋では、にもつのクッション材につかわれていたことからこの名前がついた。家畜のえさ用に輸入され、野生化した。
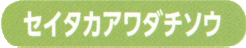

 明治時代のおわりに、園芸用にもちこまれた。そだつ力が強く、まわりの草をからしてしまう。
明治時代のおわりに、園芸用にもちこまれた。そだつ力が強く、まわりの草をからしてしまう。


 幕末に、観葉植物としてもちこまれた。強い花で、ほとんど1年をとおして道ばたにみられる。
幕末に、観葉植物としてもちこまれた。強い花で、ほとんど1年をとおして道ばたにみられる。
 ニホンタンポポをさがしてみよう
ニホンタンポポをさがしてみよう
野外でみかけるタンポポは、大きく2つにわけられます。ニホンタンポポと、セイヨウタンポポです。
セイヨウタンポポは帰化植物です。ニホンタンポポよりそだつ力が強く、どんどん数をふやし、いまではセイヨウタンポポのほうが多くみられるようになりました。
春の道ばたや野原で、タンポポをみかけたら、ニホンタンポポをさがしてみましょう。


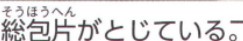


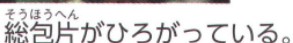
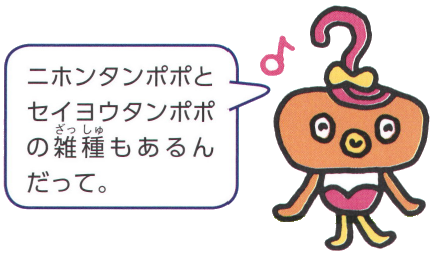
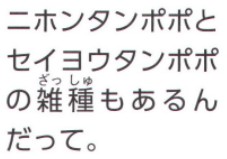
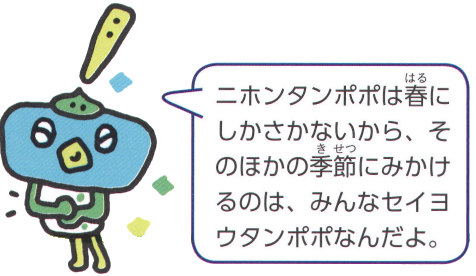
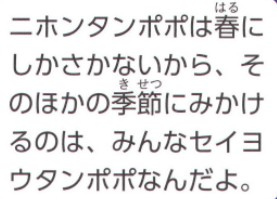
66
木の実に赤い実が多いのはなぜ?
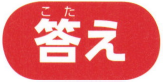 目立って、鳥にたべてもらうため
目立って、鳥にたべてもらうため
 実の中にはたねがはいっています。だれも実をとらないと、やがてすぐ下の地面におち、そこからたねが芽をだすでしょう。
実の中にはたねがはいっています。だれも実をとらないと、やがてすぐ下の地面におち、そこからたねが芽をだすでしょう。
では、鳥が実をたべた場合はどうなるでしょう? 鳥のおなかにはいったたねは、やがてふんといっしょに地面におとされます。中には、鳥にはこばれ、遠くの地面におちるたねもあることでしょう。鳥のふんには、木の実の中にあったたねが消化されないままのこっています。
つまり、木は自分の子孫を鳥にはこんでもらい、あちこちにふやそうとしているのです。そのため鳥に気づいてたべてもらえるように、緑の中で目立つ赤い色をしてるのです。
 いろいろな赤い実
いろいろな赤い実
 ヤマボウシ
ヤマボウシ

 ナンテン
ナンテン

 ナナカマド
ナナカマド

 サンシュユ
サンシュユ

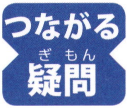 毒をもつ実があるのはどうして?
毒をもつ実があるのはどうして?
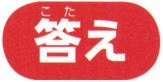 まだたねの準備ができていないからです
まだたねの準備ができていないからです
 梅のおさない実は青梅とよばれ、毒があります。毒があったら鳥はたべられませんね。
梅のおさない実は青梅とよばれ、毒があります。毒があったら鳥はたべられませんね。
これは、たねがそだっていくための準備が、まだおわっていないからです。今たべられてはこまるので、毒をもっているわけです。
おさないうちは実の色も緑色です。これが黄色になり、赤くなると、毒はきえてしまいます。

 鳥の目はどんなふうにみえる?
鳥の目はどんなふうにみえる?
鳥は人がみえている色にくわえ、人にはみえない紫外線をみることができます。どのように世界がうつっているのかわかりませんが、人より多くの情報を、目でキャッチしているとおもわれます。
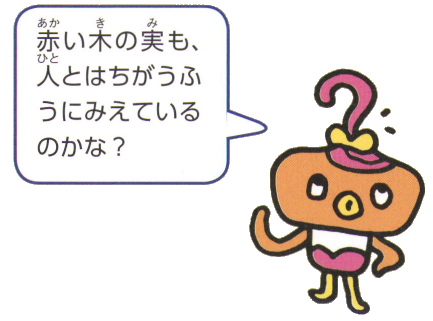
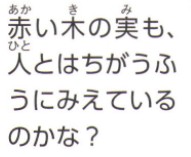
67
くっつき虫とよばれる実はなぜくっつくの?
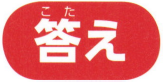 動物にくっついて遠くにはこんでもらうため
動物にくっついて遠くにはこんでもらうため
 草むらの中にはいると、ズボンにたくさんのくっつき虫がつくことがあります。くっつき虫は、どうしてこんなことをするのでしょう?
草むらの中にはいると、ズボンにたくさんのくっつき虫がつくことがあります。くっつき虫は、どうしてこんなことをするのでしょう?
植物は、うごくことができません。そのため自分の子孫をひろげていくために、たねを鳥などにはこんでもらったり、タンポポのように風でとばしたりします。
くっつき虫は、自分にさわった動物にくっついて、よそへはこんでもらいます。そのたねは服や毛につきやすくできています。
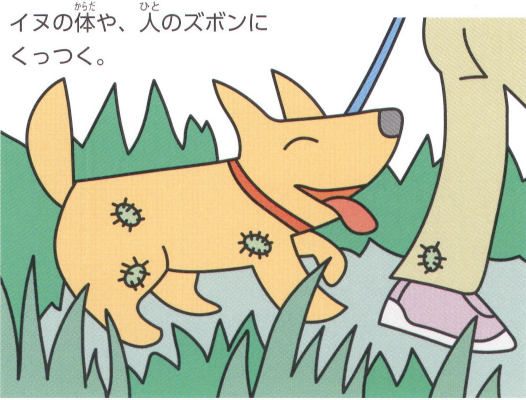
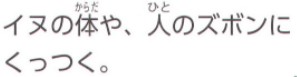

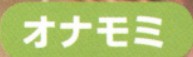
 たまごににた形のたねのまわりにたくさんのとげがある。とげの先には小さなフックがついている。
たまごににた形のたねのまわりにたくさんのとげがある。とげの先には小さなフックがついている。

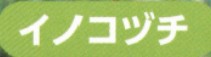
 細長いくきに、小さなバッタがたくさんとまっているようなたねをもつ。実にはとげがある。
細長いくきに、小さなバッタがたくさんとまっているようなたねをもつ。実にはとげがある。


 球状にひらいたたねの先には数本のとげがあり、このとげには小さなさかさとげがある。
球状にひらいたたねの先には数本のとげがあり、このとげには小さなさかさとげがある。
 とってもこわいくっつき虫
とってもこわいくっつき虫
南アフリカのくっつき虫「ライオンゴロシ」は、直径6~7センチのボール状で、たくさんのフックがあります。ライオンが体についたものを口でとろうとして、舌にささると、いたさのあまり何もたべられなくなって死んでしまうといいます。
 ライオンゴロシの実
ライオンゴロシの実


68
葉はどうして緑色なの?
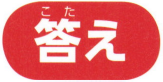 植物の栄養をつくる「葉緑素」の色です
植物の栄養をつくる「葉緑素」の色です
 植物の葉の細胞には、葉緑体というつぶがたくさんはいっています。葉緑体の中には葉緑素という緑色の色素があり、これが葉の色のもとです。
植物の葉の細胞には、葉緑体というつぶがたくさんはいっています。葉緑体の中には葉緑素という緑色の色素があり、これが葉の色のもとです。
葉緑素は、光をうけると、水と二酸化炭素から養分をつくり、さらに酸素をだすはたらきをします。これを光合成といいます。植物は、光合成をおこなうことにより、自分の体の中で栄養をうみだしているのです。
 植物の葉が、日の光をうけとめるような形でひろがっているのは、できるだけたくさんの日光をあびて、栄養をつくろうとしているわけです。
植物の葉が、日の光をうけとめるような形でひろがっているのは、できるだけたくさんの日光をあびて、栄養をつくろうとしているわけです。
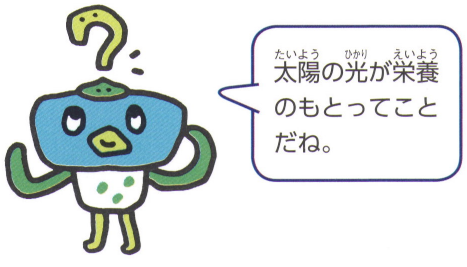
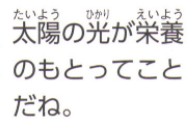
 植物の細胞
植物の細胞
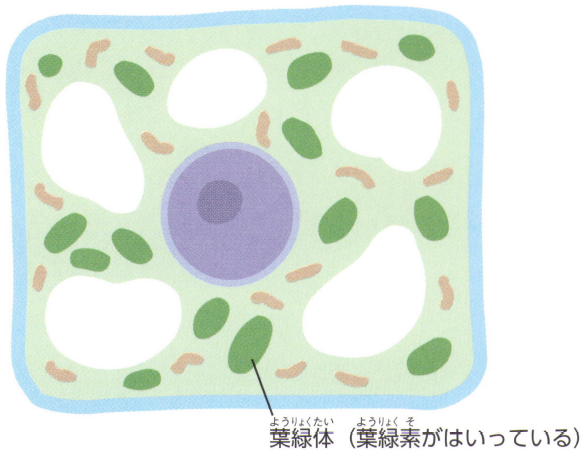
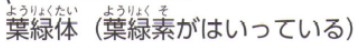
 光合成のしくみ
光合成のしくみ
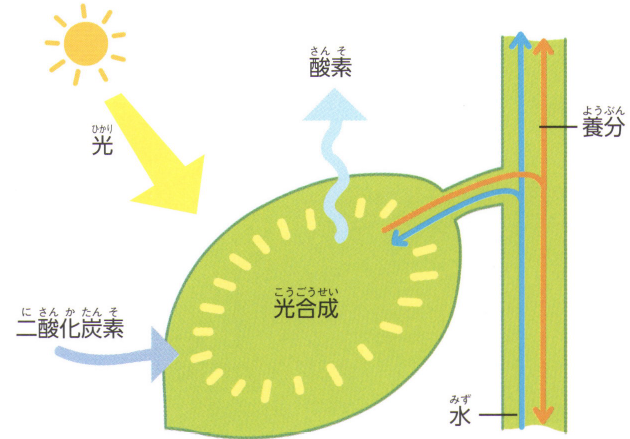

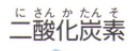




 植物は「生産者」
植物は「生産者」
地球の生き物を大きくわけると、植物は自分で栄養をつくりだせる「生産者」、動物・菌類は植物などをたべる「消費者」となります。
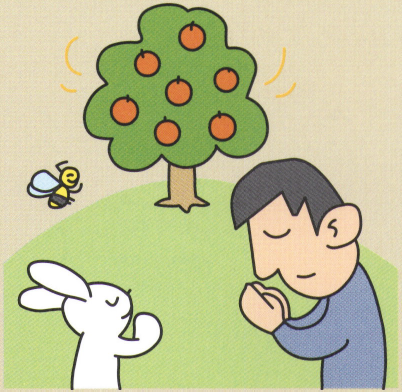
69
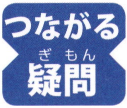 冬に葉をおとした木は、光合成をしていないの?
冬に葉をおとした木は、光合成をしていないの?
 していません
していません
 葉をおとす木を「落葉樹」といいます。冬は太陽の光が弱く、昼も短いので、落葉樹は、効率のわるい光合成をするよりも、葉をおとしてさむさから身をまもり、冬眠のようにして冬をのりきっているのです。
葉をおとす木を「落葉樹」といいます。冬は太陽の光が弱く、昼も短いので、落葉樹は、効率のわるい光合成をするよりも、葉をおとしてさむさから身をまもり、冬眠のようにして冬をのりきっているのです。
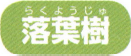

 幕末に、観葉植物としてもちこまれた。強い花で、ほとんど1年をとおして道ばたにみられる。冬には葉をおとし、春に新しい葉をだす。夏の光合成はたいへん活発。
幕末に、観葉植物としてもちこまれた。強い花で、ほとんど1年をとおして道ばたにみられる。冬には葉をおとし、春に新しい葉をだす。夏の光合成はたいへん活発。
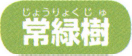
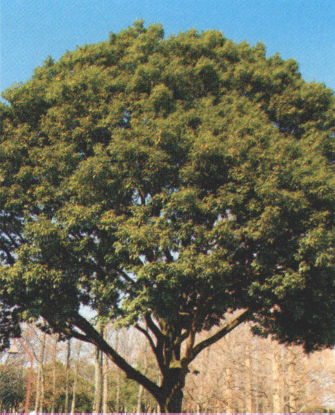
 冬も葉をおとさずひろげている。冬も光合成をおこなうが、量は少ない。
冬も葉をおとさずひろげている。冬も光合成をおこなうが、量は少ない。
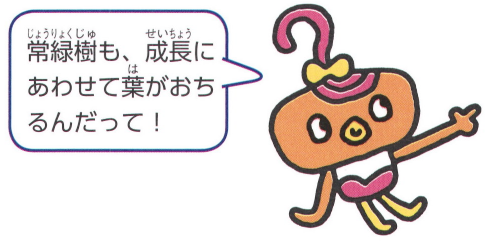
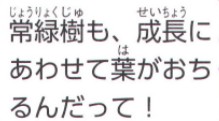
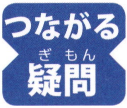 秋に葉はなぜ紅葉するの?
秋に葉はなぜ紅葉するの?
 役目をおえた葉の色です
役目をおえた葉の色です
 落葉樹は、さむくなると、葉の内部からつかえるものだけを幹にとりこんで、葉が木とつながるでいり口にふたをしてしまいます。
落葉樹は、さむくなると、葉の内部からつかえるものだけを幹にとりこんで、葉が木とつながるでいり口にふたをしてしまいます。
栄養がとりこめなくなった葉は、緑色の色素がきえ、もともともっていた「カロテノイド」という黄色い色素があらわれます。イチョウなど、黄色く紅葉する葉があるのはそのためです。
この葉に日光があたると、「アントシアニン」という赤い色素がつくられることがあります。サクラやカエデなどが赤く紅葉するのはそのためなのです。
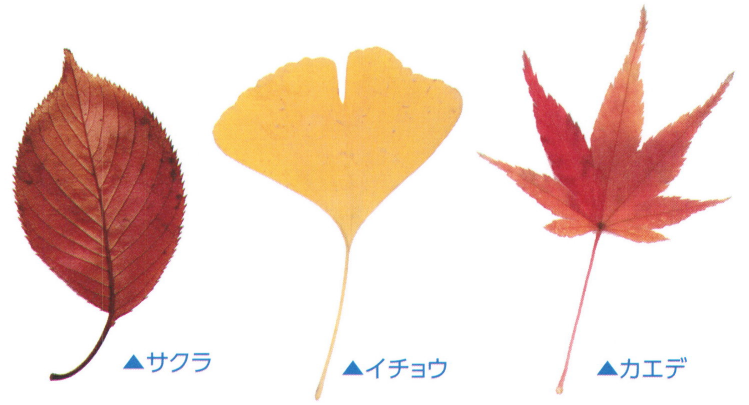

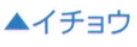

 光合成をする生き物
光合成をする生き物
コノハミドリガイというウミウシのなかまは、海そうから葉緑体をすいとって、体にとりいれます。それをつかって光合成をおこない、養分をつくっていきていきます。
ただ、光合成による養分は補助的なエネルギー源です。
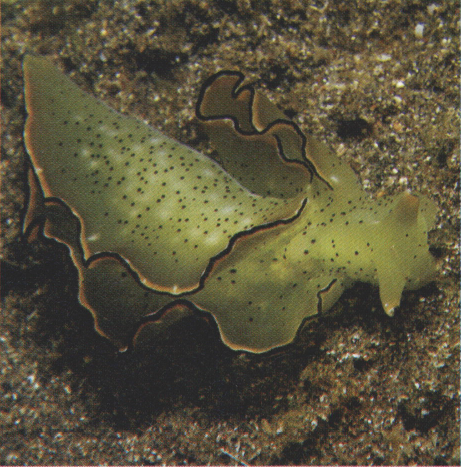
70
バラのとげは何のためにあるの?
 ひっかけて、体をささえるためなどです
ひっかけて、体をささえるためなどです
 バラの原種には、つるによってのびるものがたくさんあります。つる植物は、つるをのばして上や横にひろがります。高くひろくのびれば、日光をたくさんあびることができます。このとき、手がかりになるとげがあるほうが、つるはのびていきやすいですし、ほかの木やくき同士でからむことで、強くたっていられるようになります。
バラの原種には、つるによってのびるものがたくさんあります。つる植物は、つるをのばして上や横にひろがります。高くひろくのびれば、日光をたくさんあびることができます。このとき、手がかりになるとげがあるほうが、つるはのびていきやすいですし、ほかの木やくき同士でからむことで、強くたっていられるようになります。
 そのほかにも、動物にたべられるのをふせぐ役目もあるようです。バラを平気でたべる動物もいますが、とげをいやがるものも少なくありません。
そのほかにも、動物にたべられるのをふせぐ役目もあるようです。バラを平気でたべる動物もいますが、とげをいやがるものも少なくありません。
また、バラがまだわかいとき、くきをかたいとげでガードすることでも役にたっているとかんがえられます。
 小さな虫はよびよせて、動物はとおざけるバラ。
小さな虫はよびよせて、動物はとおざけるバラ。
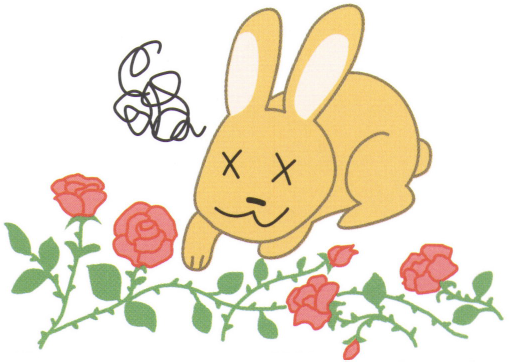
 何もないくきより、とげのあるくきのほうが、からみやすい。
何もないくきより、とげのあるくきのほうが、からみやすい。
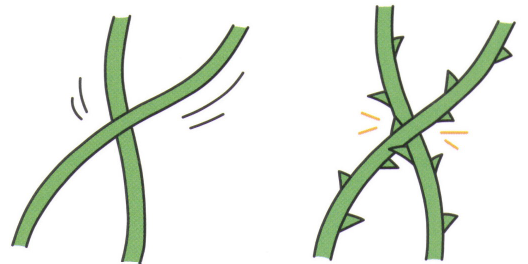
 とげのある植物
とげのある植物
バラのとげは、くきの表面の一部がかたくとがったものですが、ほかの多くの植物のとげは、枝や、葉が変化してできたものです。
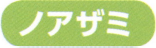

 ギザギザした葉のへりにとげをもつ。
ギザギザした葉のへりにとげをもつ。
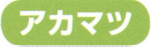

 はり状の葉が、2本ずつはえている。
はり状の葉が、2本ずつはえている。


 実をつつむ殻斗がとげにおおわれている。
実をつつむ殻斗がとげにおおわれている。


 葉のつけねに一対のとげをつける。
葉のつけねに一対のとげをつける。
 日本はバラの原産地
日本はバラの原産地
バラは、バラをあいする人たちの手によって、昔から改良されてきた花です。今のバラのもとをたどると8種類の原種のバラにたどりつきます。そのうちの2種は日本原産のバラです。
 ノイバラは8つの原種のうちのひとつ。
ノイバラは8つの原種のうちのひとつ。

1
サボテンにはどうしてとげがあるの?
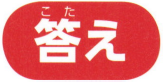 きびしい環境の砂漠で身をまもるため
きびしい環境の砂漠で身をまもるため
 サボテンのくきの中には、たくさんの水分がたくわえられています。水がほとんどない砂漠なので、当然サボテンをたべようとする動物がいます。とげは、そんな敵から身をまもるのに役だっています。
サボテンのくきの中には、たくさんの水分がたくわえられています。水がほとんどない砂漠なので、当然サボテンをたべようとする動物がいます。とげは、そんな敵から身をまもるのに役だっています。
 あつく乾燥した環境で、サボテンがいきていけるひみつは、徹底した水の節約です。サボテンは光合成を、昼と夜の作業にわけておこないます。あつい昼間に、体の表面にある気孔(空気がではいりする穴)から水分が蒸発するのをふせぐためです。
あつく乾燥した環境で、サボテンがいきていけるひみつは、徹底した水の節約です。サボテンは光合成を、昼と夜の作業にわけておこないます。あつい昼間に、体の表面にある気孔(空気がではいりする穴)から水分が蒸発するのをふせぐためです。
 サボテンは、くきがふとくなった形をしている。光合成はくきでおこなわれる。
サボテンは、くきがふとくなった形をしている。光合成はくきでおこなわれる。

 気孔をとじて、水分の蒸発をふせぐ。体にためたリンゴ酸をつかって光合成をおこなう。
気孔をとじて、水分の蒸発をふせぐ。体にためたリンゴ酸をつかって光合成をおこなう。


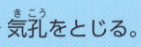
 気孔をあけて、外気から二酸化炭素をとりこみ、リンゴ酸という物質にかえ、体にためておく。
気孔をあけて、外気から二酸化炭素をとりこみ、リンゴ酸という物質にかえ、体にためておく。


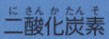
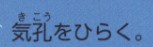

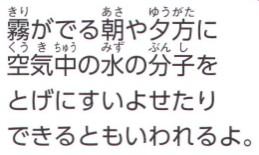
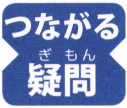 サボテンをこまらせるものはないの?
サボテンをこまらせるものはないの?
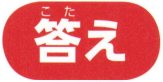 サボテンを利用する動物たちがいます
サボテンを利用する動物たちがいます
 とげを苦にせずにたべるトカゲやリクガメなどの動物がいます。
とげを苦にせずにたべるトカゲやリクガメなどの動物がいます。
またサボテンのくきに穴をあけ、巣をつくったり、果肉をたべたりするキツツキのなかまなどもいます。とげでまもられた安全な巣にするわけです。
 サボテンに巣をつくるキツツキ。
サボテンに巣をつくるキツツキ。

 サボテンをたべるリクイグアナ。
サボテンをたべるリクイグアナ。

72
マツヨイグサはどうして夜にさくの?
 夜行性のガに花粉をつけてもらうため
夜行性のガに花粉をつけてもらうため
 花は、おしべの花粉がめしべにつくことで実ができます。これを受粉といいます。多くの花が、花粉をつける役をチョウやハチなどの虫にまかせています。
花は、おしべの花粉がめしべにつくことで実ができます。これを受粉といいます。多くの花が、花粉をつける役をチョウやハチなどの虫にまかせています。
ほとんどの花は、太陽のでている明るいときに花をひらきます。たくさんの虫が活動するので、受粉させてもらいやすいからです。
しかしマツヨイグサのように、夜にひらく花もあります。夜に活動するスズメガなどが、花のみつをすいにやってきます。昼は虫も、さく花も多いですが、虫がこない花もあります。そこで数は少なくても、夜に活動する虫を相手にする花もあるのです。花と虫は、おたがい大切な関係です。
 夜、マツヨイグサのみつをすいにきたスズメガ。
夜、マツヨイグサのみつをすいにきたスズメガ。


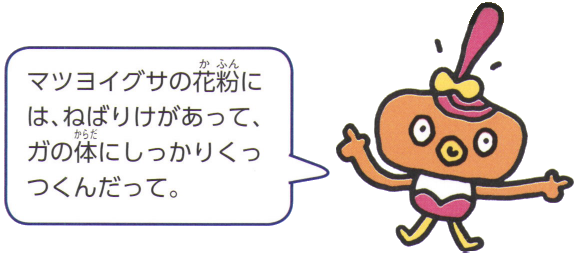
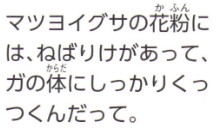
 夜にさく花のなかま
夜にさく花のなかま
ふだんであるかない、暗い時間帯なのであまりみかけませんが、夜にさく花はほかにもあります。暗い中でもめだつように、花も大きく、白や黄色の明るい色が多くなっています。

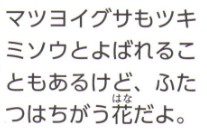
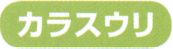

 花びらが白いレースのようにふわりとひろがっている。もともと日本にあった夜さく花。
花びらが白いレースのようにふわりとひろがっている。もともと日本にあった夜さく花。


 夕ぐれどきからさきはじめ、日のでるころには花をとじる。野生ではほとんどみられない。
夕ぐれどきからさきはじめ、日のでるころには花をとじる。野生ではほとんどみられない。


 1年に1~2回、一晩だけしか花をさかせない。中南米原産の熱帯雨林の花。
1年に1~2回、一晩だけしか花をさかせない。中南米原産の熱帯雨林の花。
73
レンコンにはどうして穴があいているの?
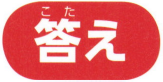 空気をはこぶパイプの役割をしています
空気をはこぶパイプの役割をしています
 わたしたちがたべているレンコンは、ハスという植物のくきの部分です。土の中にある地下茎に栄養がたまって、大きくなったものです。
わたしたちがたべているレンコンは、ハスという植物のくきの部分です。土の中にある地下茎に栄養がたまって、大きくなったものです。
レンコンがそだつのは、水底のどろの中です。ふつう植物は、葉のほか、くきや根からも空気をだしいれして呼吸をしています。しかし、レンコンはどろの中にあるため、空気がとりこめません。そこで、水上にある葉からとりいれた空気を、細いくだをとおしてレンコンまでおくっています。
レンコンにあいたいくつもの穴は、空気をはこぶパイプであり、十分な空気をためておくタンクなのです。根にもここから空気をおくっています。
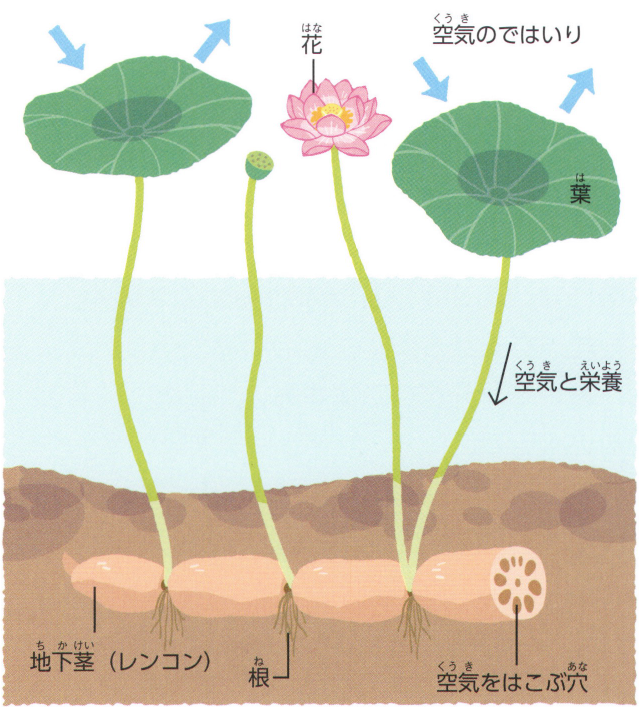



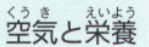
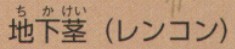

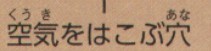
 水の中でそだつ植物
水の中でそだつ植物
水中でそだつ植物を水生植物といいます。水中は空気をとりにくくなりますが、水や、温度変化の面では陸上より有利です。
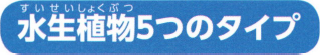
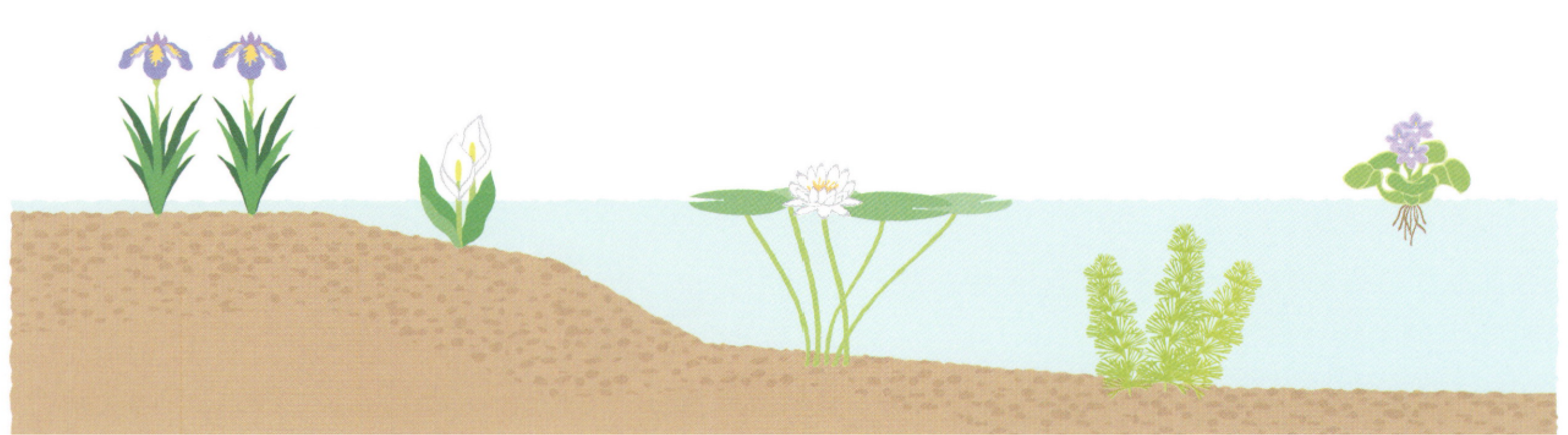
湿地タイプ
 ショウブなど。
ショウブなど。
池や川辺など、しめった場所でそだつ。

水の多い場所タイプ
 ミズバショウなど。
ミズバショウなど。
一部が水中につかった状態。

葉が水面タイプ
 スイレンなど。
スイレンなど。
水底に根をはり、葉と花を水面にだす。

水中タイプ
 カボンバなど。
カボンバなど。
水底に根をはり、水中でそだつ。
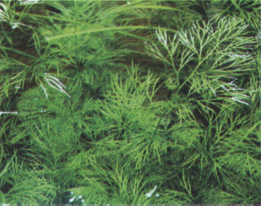
水にうくタイプ
 ホテイアオイなど。
ホテイアオイなど。
根を水中にひろげ、水面にうかぶ。

74
カミキリムシは、髪の毛をきれるの?
 髪の毛もきれる強いあごをもっています
髪の毛もきれる強いあごをもっています
 カミキリムシの名前は、「噛み切り」や「紙切り」ではなく、「髪切り」からついたものです。
カミキリムシの名前は、「噛み切り」や「紙切り」ではなく、「髪切り」からついたものです。
カミキリムシは、ノコギリのようなギザギザしたあごをもっています。はさむ力は、クワガタより強く、指をはさまれると血がでることもあります。
 これほど強いあごは、木をかむために必要なものです。カミキリムシの幼虫は、木の中で、木をたべてそだちます。木の中で羽化した成虫も、あごで木をほってすすみ、外にでてくるのです。
これほど強いあごは、木をかむために必要なものです。カミキリムシの幼虫は、木の中で、木をたべてそだちます。木の中で羽化した成虫も、あごで木をほってすすみ、外にでてくるのです。
 カミキリムシのなかまは、名前がついているものだけで、日本におよそ800種類がいます。
カミキリムシのなかまは、名前がついているものだけで、日本におよそ800種類がいます。
 カミキリムシのあご。
カミキリムシのあご。

 ゴマダラカミキリ
ゴマダラカミキリ

 ラミーカミキリ
ラミーカミキリ
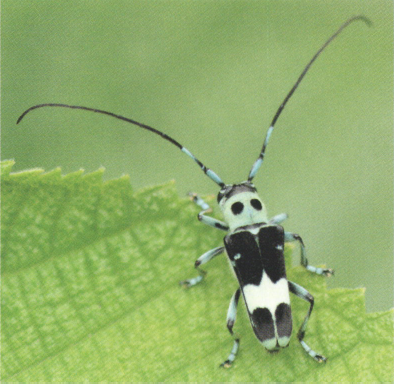
チョウとガのちがいはどこ?
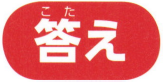 触角の形でみわけられます
触角の形でみわけられます
 日本ではチョウとガをわけていますが、フランスやドイツでは同じなかまとしてかんがえています。それほど近いなかまです。
日本ではチョウとガをわけていますが、フランスやドイツでは同じなかまとしてかんがえています。それほど近いなかまです。
 チョウとガをみわける一般的な方法は、触角の形や、目の大きさです。
チョウとガをみわける一般的な方法は、触角の形や、目の大きさです。
チョウの触角は先のほうが太くなっていますが、ガの触角は先がだんだん細くなっています。ガのオスには、くしのような形をした触角をもつものもいます。これは、メスのだすにおいをとらえるためです。
チョウは昼に活動するので、目が大きいのですが、ガは夜に活動するものが多く、目がつかえないぶん、すぐれた触角をもっているのです。

 アゲハチョウ
アゲハチョウ

 ツマグロヒョウモン
ツマグロヒョウモン


 アゲハモドキ
アゲハモドキ

 クスサン
クスサン

75
鳥は夜に目がみえないの?
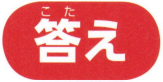 多くの鳥はみえています
多くの鳥はみえています
 暗くなるとよくみえないことを「鳥目」といいます。人と身近な鳥であるニワトリは目がわるく、暗いときはなおさらみえません。このニワトリのようすをみた人が、鳥は夜に目がみえないとおもったのでしょう。
暗くなるとよくみえないことを「鳥目」といいます。人と身近な鳥であるニワトリは目がわるく、暗いときはなおさらみえません。このニワトリのようすをみた人が、鳥は夜に目がみえないとおもったのでしょう。
しかし、鳥の多くは鳥目ではなく、夜でもちゃんとみえています。
 フクロウやヨタカなどの夜に活動する鳥は、暗くてもよくみえる特別な目をもっています。目の中に明るさをかんじる細胞がたくさんあり、目のつくりもたくさんの光があつめられるようになっているのです。
フクロウやヨタカなどの夜に活動する鳥は、暗くてもよくみえる特別な目をもっています。目の中に明るさをかんじる細胞がたくさんあり、目のつくりもたくさんの光があつめられるようになっているのです。
 鳥の中でもワシタカのなかまは、とくに視力がすぐれています。ワシタカのなかまのハヤブサは、10
先のえものをみわけることができるといわれています。
鳥の中でもワシタカのなかまは、とくに視力がすぐれています。ワシタカのなかまのハヤブサは、10
先のえものをみわけることができるといわれています。
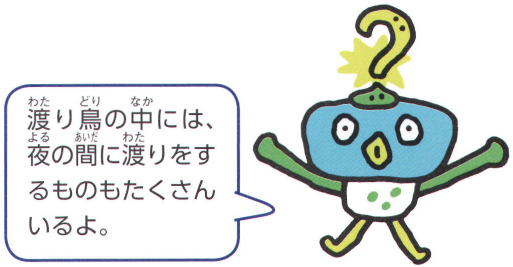
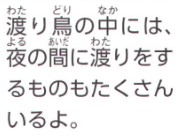
 夜に狩りをするフクロウ。
夜に狩りをするフクロウ。
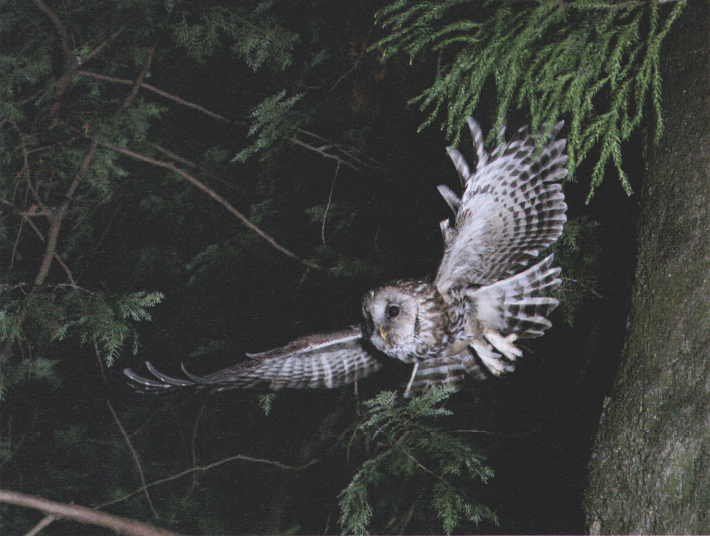
オウムはなぜことばをまねるの?
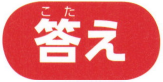 もともと、なかまと声のやりとりをする鳥だから
もともと、なかまと声のやりとりをする鳥だから
 オウムやインコ、キュウカンチョウは、かい主のことばをまねするものがたくさんいます。これは、かい主をなかまだとおもうからです。
オウムやインコ、キュウカンチョウは、かい主のことばをまねするものがたくさんいます。これは、かい主をなかまだとおもうからです。
これらの鳥は、なかまと声をだしあうことで関係をふかめる鳥のなかまです。相手の声をきき、同じようにくりかえす力がすぐれています。
また、声をだす部分の筋肉が発達しているため、いろいろな音をだすことができるのです。中には、人の声だけでなく、玄関のチャイムや音楽などを上手にまねすることもあります。
 1羽だけでかっていると、なかまはかい主だけなので、人のことばをくりかえして、なかよくなろうとします。そのため、2羽以上でかうと、人のことばをおぼえにくいようです。
1羽だけでかっていると、なかまはかい主だけなので、人のことばをくりかえして、なかよくなろうとします。そのため、2羽以上でかうと、人のことばをおぼえにくいようです。
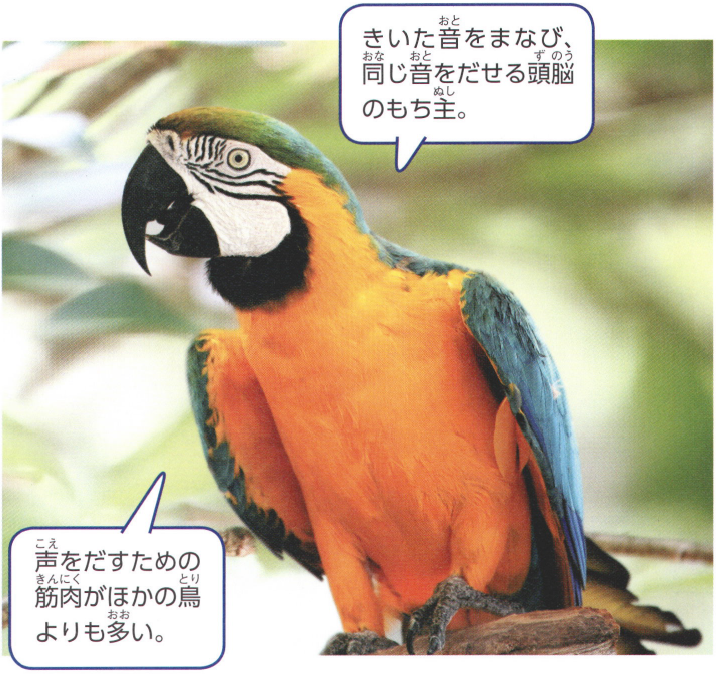
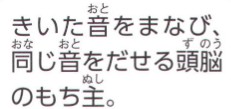
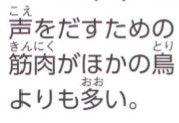
76
フラミンゴはなぜかた足でたつの?
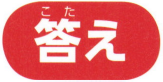 足がひえないようにしています
足がひえないようにしています
 フラミンゴの足は長く、皮膚には毛がはえていません。しかも血管が細いので、血の流れがわるくなりやすいのです。つまり、足がひえやすいわけです。
フラミンゴの足は長く、皮膚には毛がはえていません。しかも血管が細いので、血の流れがわるくなりやすいのです。つまり、足がひえやすいわけです。
十分にあたたかい場所では、フラミンゴは両足でたちますが、足がつめたい場所では、かた足をあげてたちます。またときどきたつ足をかえて、かわるがわるあたためています。ねむるときも、上手にかた足でたっています。
やすんでいるときは、かた足だちで十分で、かた方ずつやすませています。
シギやツルなど、同じようにかた足だちをするものがいます。みんな足の長い鳥のなかまです。

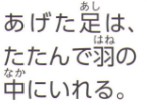
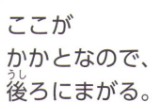


 ねているフラミンゴ。
ねているフラミンゴ。

ニワトリはどうして朝になくの?
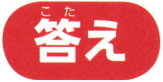 活動をはじめる前になわばりをつたえています
活動をはじめる前になわばりをつたえています
 「一番鶏」ということばもあるように、ニワトリは朝早くからなきはじめます。ひとことでいえば、これはなわばりの宣言です。
「一番鶏」ということばもあるように、ニワトリは朝早くからなきはじめます。ひとことでいえば、これはなわばりの宣言です。
なくのはオスだけです。その集団内の、一番強いニワトリからなきはじめ、順番に、2番手、3番手とないていきます。1日がはじまる前に、なわばりをまわりのニワトリにつたえることで、むだなけんかをさけるのに役だっているようです。
 また、たとえ外が暗いままでも、朝がくるとなきだすのは、ニワトリがしっかりした体内時計をもっているからです。
また、たとえ外が暗いままでも、朝がくるとなきだすのは、ニワトリがしっかりした体内時計をもっているからです。
 強いおんどりから順番にないていく。
強いおんどりから順番にないていく。
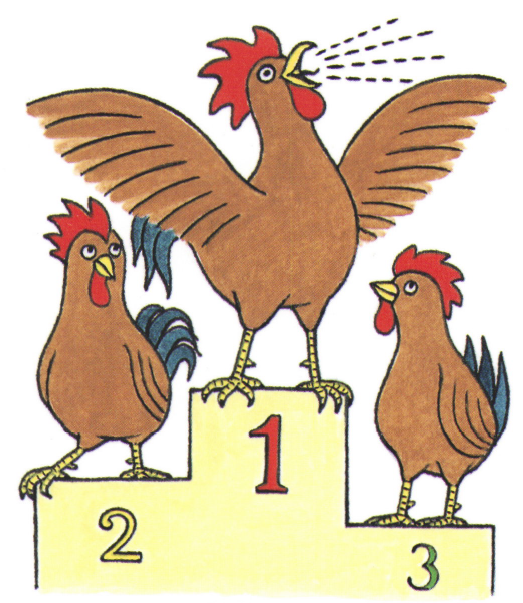
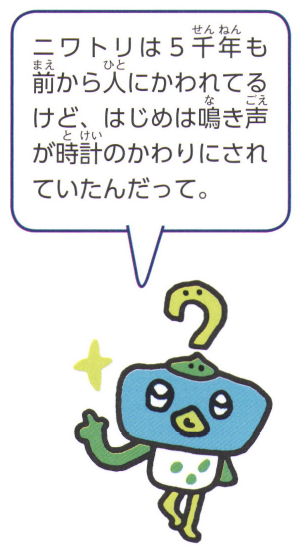
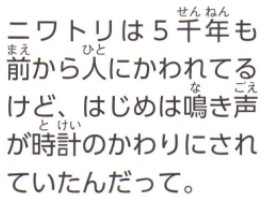
77
ウシはなぜ口をもぐもぐさせているの?
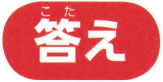 たべた草をなんどもかみなおしているため
たべた草をなんどもかみなおしているため
 ウシは、一度胃にいれた草を何度も口にもどしてかみなおしています。そのため、1日で10時間くらいは口をもぐもぐさせています。
ウシは、一度胃にいれた草を何度も口にもどしてかみなおしています。そのため、1日で10時間くらいは口をもぐもぐさせています。
 ウシは4つにわかれた胃をもっていて、それぞれに役目があります。
ウシは4つにわかれた胃をもっていて、それぞれに役目があります。
1つ目の胃は、タンクです。タンクの中には微生物がいて、草の細胞を分解してくれます。
2つ目の胃はポンプです。1つ目の胃の草をさらに細かくするため、口へもどす役目です。
3つ目の胃はフィルターで、小さくなったものだけをとおします。4つ目の胃が、わたしたちと同じような胃になります。
 ウシの胃
ウシの胃
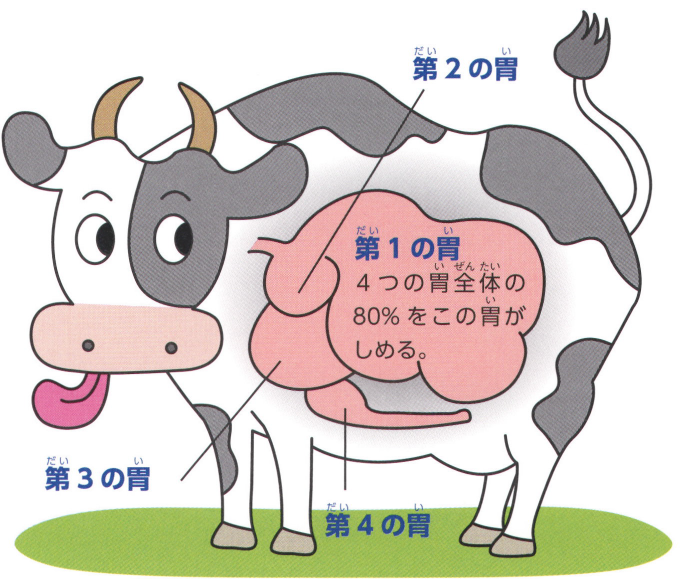
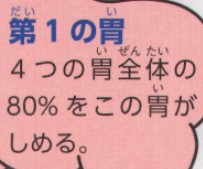



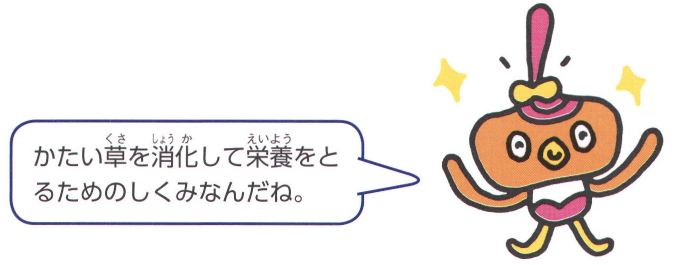
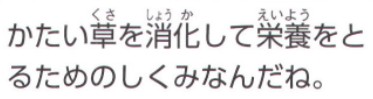
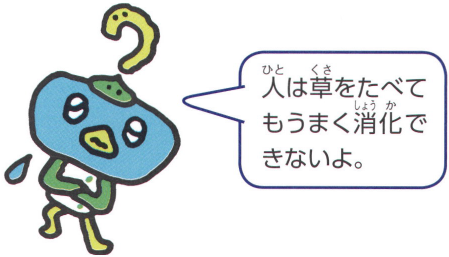
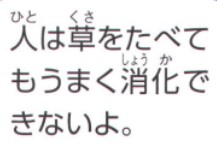
ゾウがよく水あびするのはなぜ?
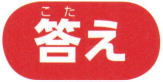 あつさをしのぎ、体をきれいにするため
あつさをしのぎ、体をきれいにするため
 ゾウが水あびをするのは、まず第一にあつさをやわらげるためです。
ゾウが水あびをするのは、まず第一にあつさをやわらげるためです。
野生のゾウは、アフリカやインド、東南アジアなどのあつい地域にすんでいますし、動物園のゾウも、蒸しあつい日本の夏は苦手です。
それから、皮膚がかわくのをふせぎ、体をきれいにするためでもあります。
水あびのあと、どろやすなを体につけますが、これはダニなどの体につく虫をとったりふせいだりするためです。
 ホースのような鼻で水をくみ、体にかける。
ホースのような鼻で水をくみ、体にかける。

 人にかわれているアジアゾウ。川で体をあらってもらう。
人にかわれているアジアゾウ。川で体をあらってもらう。
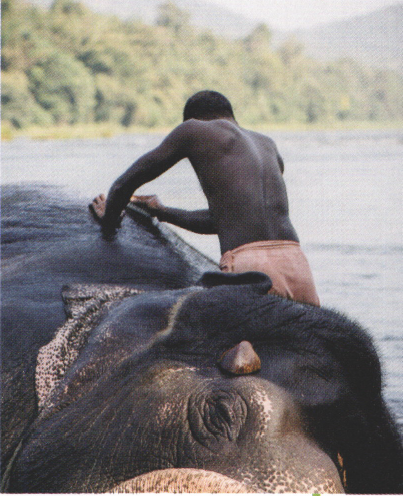
78
ラクダのこぶには何がはいっているの?
 栄養と脂肪のかたまりです
栄養と脂肪のかたまりです
 ラクダは、あつさのきびしい、乾燥した砂漠にくらす動物です。だから、体もその場所にてきした体のつくりをしています。
ラクダは、あつさのきびしい、乾燥した砂漠にくらす動物です。だから、体もその場所にてきした体のつくりをしています。
こぶもそのひとつで、せなかに非常食のような、脂肪のかたまりをもっているのです。十分な脂肪がたくわえられていれば、ラクダは1か月くらいは、のみくいなしでいきられます。
また、脂肪には熱をさえぎる効果があります。せなかにこぶがあることで、強い日ざしから身をまもることにも役だっています。
赤ちゃんラクダにはこぶはなく、成長するにつれて、こぶができていきます。
 砂漠にてきしたラクダの体
砂漠にてきしたラクダの体
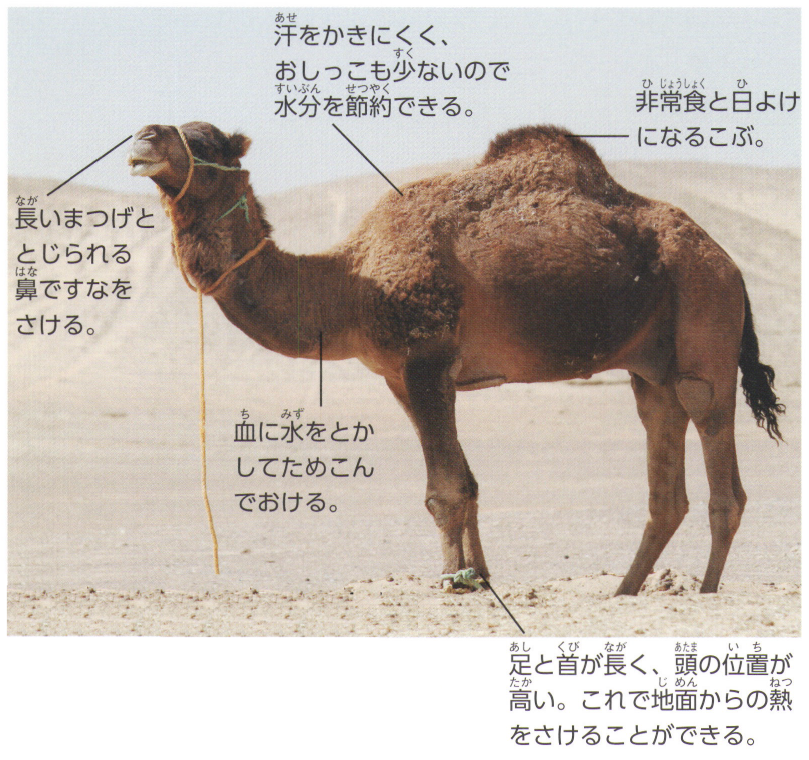
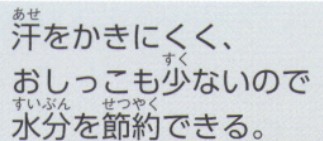
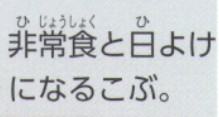
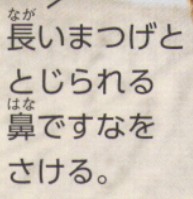
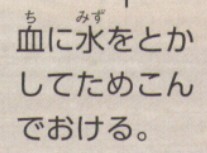
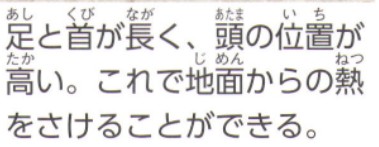
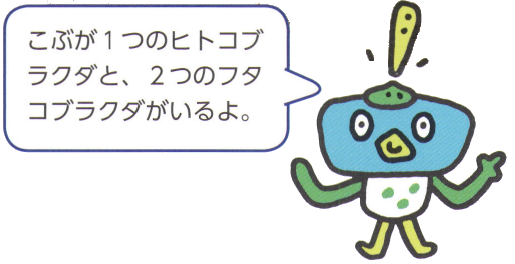
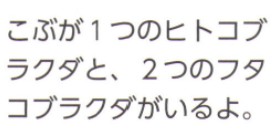
タヌキは本当にたぬきねいりするの?
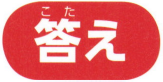 ねたふりはしません
ねたふりはしません
 タヌキは、敵におそわれるなど、びっくりすると、うごけなくなる場合があります。すぐに回復し、とつぜんにげだしたりしますが、それをみた人が、タヌキにだまされたとおもってできたことばが「たぬきねいり」です。
タヌキは、敵におそわれるなど、びっくりすると、うごけなくなる場合があります。すぐに回復し、とつぜんにげだしたりしますが、それをみた人が、タヌキにだまされたとおもってできたことばが「たぬきねいり」です。
 このように、敵におそわれるとうごかなくなることを「擬死」といいます。えものが急にうごかなくなると、敵は攻撃をやめ、気をゆるめることがあります。つまり、むだな体力をつかわず、体をきずつけられずに、すきをついてにげられる可能性が高くなるのです。
このように、敵におそわれるとうごかなくなることを「擬死」といいます。えものが急にうごかなくなると、敵は攻撃をやめ、気をゆるめることがあります。つまり、むだな体力をつかわず、体をきずつけられずに、すきをついてにげられる可能性が高くなるのです。
 昆虫にも、コガネムシやカメムシなど、擬死するものがたくさんいます。
昆虫にも、コガネムシやカメムシなど、擬死するものがたくさんいます。
 日本の本州や四国・九州でみられるホンドタヌキ。毛が長く、目のまわりや足が黒い。
日本の本州や四国・九州でみられるホンドタヌキ。毛が長く、目のまわりや足が黒い。

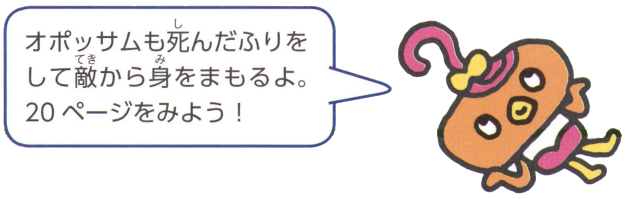
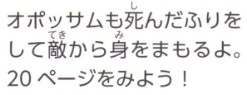
79
ヘビはどこからがしっぽなの?
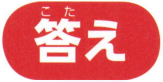 おしりの穴から後ろがしっぽになります
おしりの穴から後ろがしっぽになります
 ヘビの体は、まるで全身がしっぽのようですが、ちゃんと区別されています。
ヘビの体は、まるで全身がしっぽのようですが、ちゃんと区別されています。
ヘビをうらがえしてみると、おなか側にもうろこがならんでいます。おなかの部分は腹板という、はばの広いうろこです。それが「総排泄孔」というおしりの穴までつづいています。この穴から先が、ヘビのしっぽになります。穴の部分と、しっぽの部分は、うろこの形がまたちがっています。
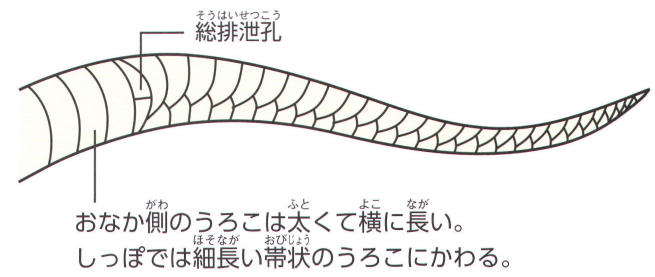
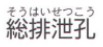
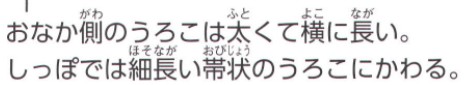
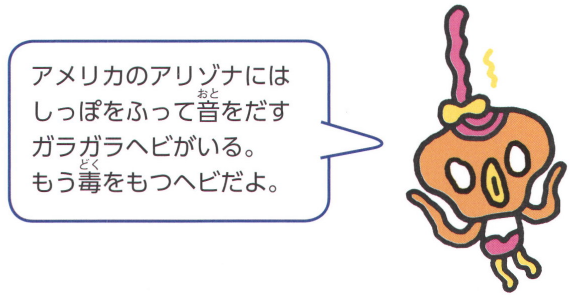
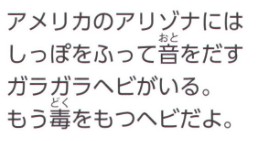
 ニシキヘビには足のあとがある?
ニシキヘビには足のあとがある?
ニシキヘビのおしりの穴の横には、昔のヘビにあった足のあとがのこっています。今はなくなった後ろ足の指の1本で、けづめとよばれる部分です。
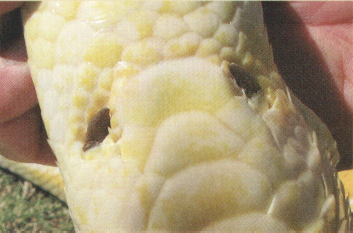
ヤモリはどうしてかべにはりついてあるけるの?
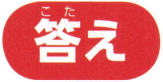 足のうらの細かい毛で、くっつく力をうみだしています
足のうらの細かい毛で、くっつく力をうみだしています
 ヤモリの足のうらには、カエルのような吸盤や、ナメクジのような粘液がついているわけではなく、ものすごく細かい毛がはえています。1センチ四方の面積にして、10億本以上ともいわれています。
ヤモリの足のうらには、カエルのような吸盤や、ナメクジのような粘液がついているわけではなく、ものすごく細かい毛がはえています。1センチ四方の面積にして、10億本以上ともいわれています。
ガラスはつるつるしているようですが、ミクロの世界まで拡大してみると、表面にでこぼこがあります。ヤモリが、ガラスやかべの表面にあるでこぼこに毛をぴっちりとくっつけると、毛とかべの面との間に、ひきあう力がうまれます。この力はごく弱いものですが、20億本分の力があつまって、ヤモリは、自分の体重の50倍もの重さをささえられるのです。
 毛のあたる角度をかえるだけで、すっとはがれるから、すばやくうごける。
毛のあたる角度をかえるだけで、すっとはがれるから、すばやくうごける。

 ヤモリの足の拡大写真。
ヤモリの足の拡大写真。

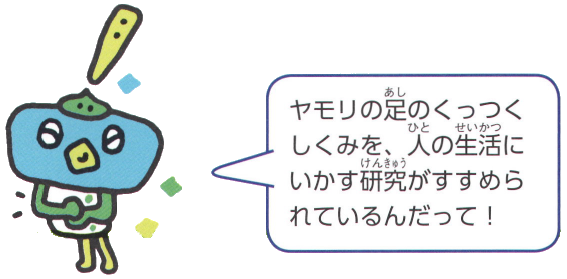
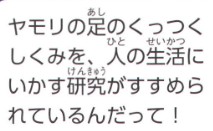
80
パイナップルにたねはあるの?
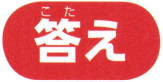 お店でうられているパイナップルは「たねなし」です
お店でうられているパイナップルは「たねなし」です
 パイナップルは、ちょっとふしぎなくだものです。わたしたちがたべているのは、果実ではなくて、花をささえている花托という部分です。パイナップルの果実は、外側のうろこのようなかたい部分なのです。
パイナップルは、ちょっとふしぎなくだものです。わたしたちがたべているのは、果実ではなくて、花をささえている花托という部分です。パイナップルの果実は、外側のうろこのようなかたい部分なのです。
そのうろこ状の果実のひとつひとつに、花がさきます。1つのパイナップルの実に、およそ150こあります。ふつうの植物ならば、150この果実それぞれにたねがあるはずですが、パイナップルにはみあたりません。パイナップルは、おいしくなるように品種改良されてきたため、たねがなくなってしまったのです。
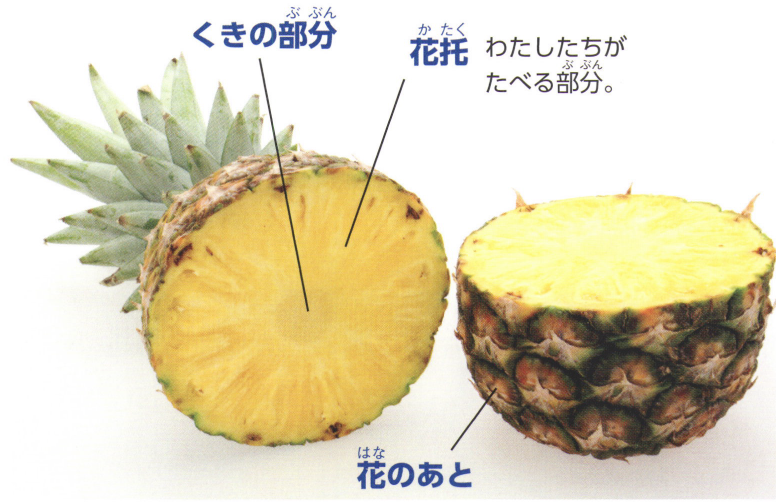

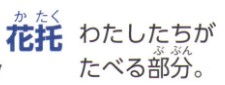
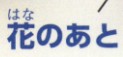
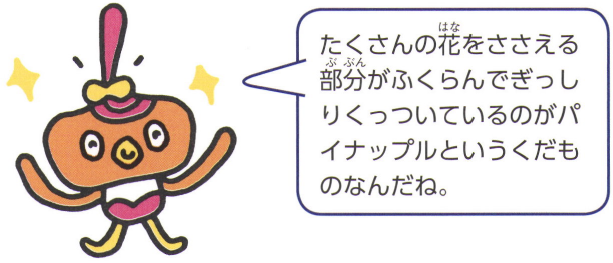
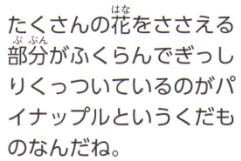
 パイナップル畑。木ではなく草にできる果実。
パイナップル畑。木ではなく草にできる果実。

落花生は土の中に実がなるの?
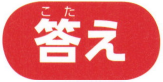 落花生の実(たね)は地中にできます
落花生の実(たね)は地中にできます
 落花生は、花をさかせたあと、豆のもとになる部分が下へのびていき、地面につきささります。その先が地面の中でだんだんふくらんでいき、その中に2つほどの豆ができます。これが落花生のたね(ピーナッツ)です。
落花生は、花をさかせたあと、豆のもとになる部分が下へのびていき、地面につきささります。その先が地面の中でだんだんふくらんでいき、その中に2つほどの豆ができます。これが落花生のたね(ピーナッツ)です。
 わたしたちがたべているピーナッツは、主にたねの子葉の部分です。子葉はたねが芽をだしたとき、最初にでる葉のことです。落花生のたねをまくと、子葉が地上で2つにひらきます。子葉は、胚が落花生本体へとそだっていく栄養になります。
わたしたちがたべているピーナッツは、主にたねの子葉の部分です。子葉はたねが芽をだしたとき、最初にでる葉のことです。落花生のたねをまくと、子葉が地上で2つにひらきます。子葉は、胚が落花生本体へとそだっていく栄養になります。
 土の中でふくらんださやの中に豆ができる。
土の中でふくらんださやの中に豆ができる。

 落花生の花。
落花生の花。

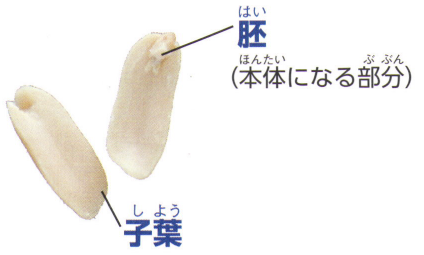
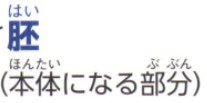

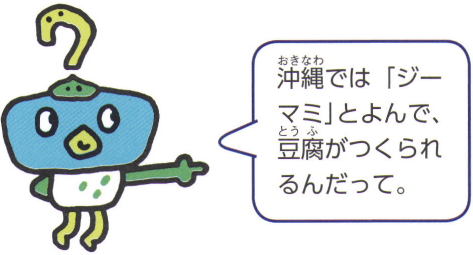
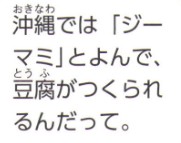
81
食虫植物は虫をどうやってつかまえるの?
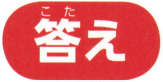 種類によって、いろいろな方法があります
種類によって、いろいろな方法があります
 多くの植物は、光合成をして養分をつくったり、土の中から養分をとりこんでそだちます。食虫植物は、光合成もしますが、虫をたべて養分をとります。
多くの植物は、光合成をして養分をつくったり、土の中から養分をとりこんでそだちます。食虫植物は、光合成もしますが、虫をたべて養分をとります。
 食虫植物がはえている土地は、養分が少ない場所です。そのため食虫植物たちは、やってくる虫をつかまえ、たりない養分をおぎなうようになりました。つかまえる方法は、種類によってさまざまです。
食虫植物がはえている土地は、養分が少ない場所です。そのため食虫植物たちは、やってくる虫をつかまえ、たりない養分をおぎなうようになりました。つかまえる方法は、種類によってさまざまです。
「くっつける」


 葉はびっしりと毛がはえていて、べとべとする液をだしている。虫がくっつくと、葉がまがってつつみこまれる。
葉はびっしりと毛がはえていて、べとべとする液をだしている。虫がくっつくと、葉がまがってつつみこまれる。

 モウセンゴケにつかまる虫。
モウセンゴケにつかまる虫。
「はさむ」


 虫が葉にとまると、ふちにとげをもつ葉がしまり、すばやく虫をはさみこむ。
虫が葉にとまると、ふちにとげをもつ葉がしまり、すばやく虫をはさみこむ。
「おとす」

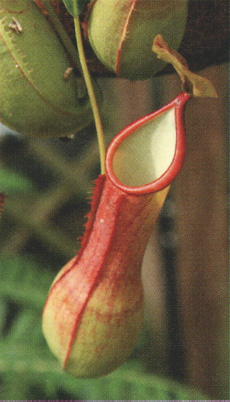
 つぼのような形で、内側はすべりやすく、虫はすべって下の消化液におちる。
つぼのような形で、内側はすべりやすく、虫はすべって下の消化液におちる。
「すいこむ」


 くきや葉に捕虫嚢というふくろがある。ふくろの入口にあるひげにミジンコなどがさわるとふくらみ、水ごとすいこむ。
くきや葉に捕虫嚢というふくろがある。ふくろの入口にあるひげにミジンコなどがさわるとふくらみ、水ごとすいこむ。
植物にもオスとメスがあるの?
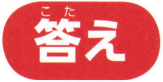 あります。大きく3つのグループにわけられます
あります。大きく3つのグループにわけられます
 ふつうは、1本の植物にさく花の中に、おしべとめしべがあるものですが、花がオスとメスにわかれているもの、木自体がオスとメスにわかれているものがあります。
ふつうは、1本の植物にさく花の中に、おしべとめしべがあるものですが、花がオスとメスにわかれているもの、木自体がオスとメスにわかれているものがあります。
これらの花や木は、自分とはちがう相手と受粉しようとします。そうすることで強い子孫ができるのです。
 両性花
両性花

 1つの花におしべとめしべがある。多くの花がこのタイプにはいる。
1つの花におしべとめしべがある。多くの花がこのタイプにはいる。
 雌雄異花
雌雄異花

 1つの株に、おしべだけの雄花と、めしべだけの雌花をさかせる。カボチャ、クリなど。
1つの株に、おしべだけの雄花と、めしべだけの雌花をさかせる。カボチャ、クリなど。
 キュウリの雌花(左)と雄花(右)。キュウリは雌雄異花。
キュウリの雌花(左)と雄花(右)。キュウリは雌雄異花。

 雌雄異株
雌雄異株
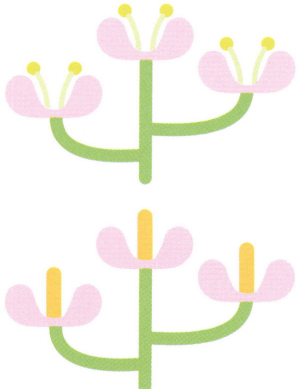
 多くの動物のように、雄花と雌花で別々の株にわかれている。イチョウ、キンモクセイなど。
多くの動物のように、雄花と雌花で別々の株にわかれている。イチョウ、キンモクセイなど。
81
82
第2章 体のなぜ?

83
はしると胸がどきどきするのはなぜ?
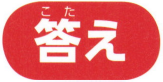 心臓の弁がはげしく開閉するから
心臓の弁がはげしく開閉するから
 わたしたちの胸の真ん中あたりにある心臓は、全身に血をおくりだすポンプのような役割をもつ内臓です。1分間に、おとなはおよそ70回、子どもはおよそ100回もちぢんで、しぼりだすようにして血をおくります。
わたしたちの胸の真ん中あたりにある心臓は、全身に血をおくりだすポンプのような役割をもつ内臓です。1分間に、おとなはおよそ70回、子どもはおよそ100回もちぢんで、しぼりだすようにして血をおくります。
心臓に血がでいりするときには心臓の中にある弁が、ひらいたりとじたりします。「どきどき」するのは、そのときの振動です。
 ふだんから弁は開閉しつづけていますが、「どきどき」をかんじることはありませんね。はしったりはげしい運動をしたりすると「どきどき」をかんじるのは、心臓が体全体により多くの血をおくって、栄養や酸素をおぎなおうとするためです。
ふだんから弁は開閉しつづけていますが、「どきどき」をかんじることはありませんね。はしったりはげしい運動をしたりすると「どきどき」をかんじるのは、心臓が体全体により多くの血をおくって、栄養や酸素をおぎなおうとするためです。
そのとき、血のでいり口の弁は、ふだんより速いテンポで、はげしく開閉されます。その「どきどき」という振動が、自分でわかるほど強くつたわってくるのです。
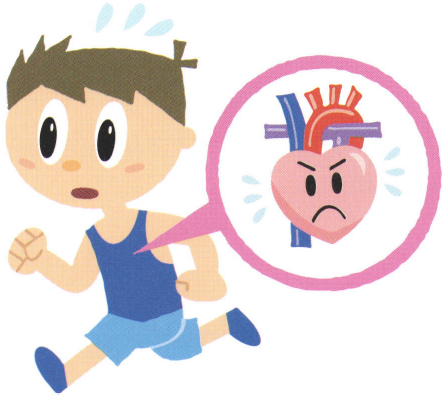
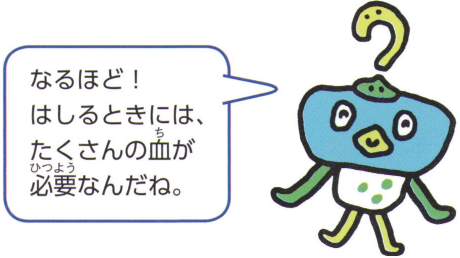
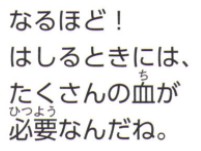
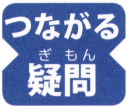 心臓の弁はなんのためについているの?
心臓の弁はなんのためについているの?
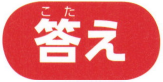 体におくりだした血が逆流しないようにするため
体におくりだした血が逆流しないようにするため
 心臓の中は、右心房、右心室、左心房、左心室という、4つの部屋にわかれています。弁は、この4つの部屋のでいり口についています。
心臓の中は、右心房、右心室、左心房、左心室という、4つの部屋にわかれています。弁は、この4つの部屋のでいり口についています。
血は、体全体をめぐった後、まず右心房にはいり、右心室をとおって肺におくられ、二酸化炭素と酸素を交換すると、今度は左心房にもどってきます。その後、左心室にはこばれ、そこからまた全身へとおくられます。
こうして、心臓は全身に血をめぐらせていますが、血が心臓の中を移動するとき、ぎゃくにながれないよう、4つの部屋のでいり口には弁がついていて、とじたりひらいたりしているのです。
 心臓には4か所に弁があり、つねに、ひらいたりとじたりして、血をおくりだしている。
心臓には4か所に弁があり、つねに、ひらいたりとじたりして、血をおくりだしている。
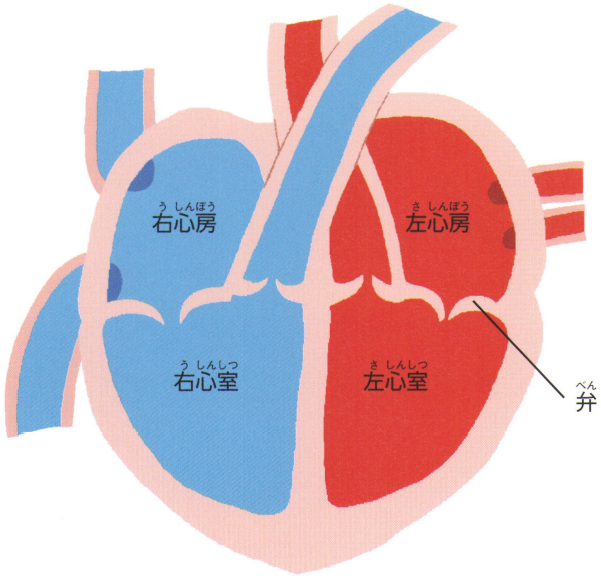
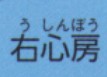
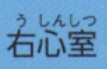
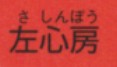
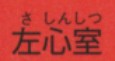

85
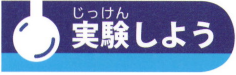 心拍数をはかってみよう
心拍数をはかってみよう
心臓はいつもうごいていますが、体の状態によって、血をおくりだすテンポを調節しています。1分間に何回心臓がうごくかは、心拍数(脈)をはかることによってしることができます。いろいろな状態で、心拍数をはかってみましょう。


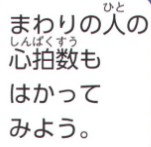
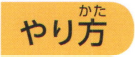
①手首の血管に指をあて、血がおくりだされて「どくどく」と脈うつのをかんじます。
②時計の秒針が12からひとまわりして12にもどってくるまでの1分間に、何回脈うつかをかぞえます。
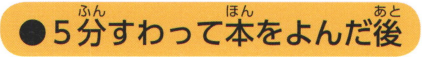
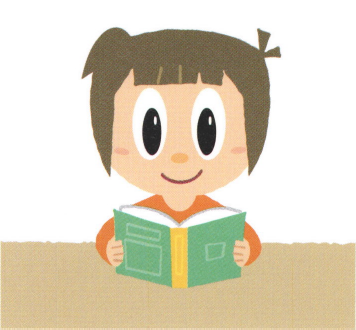
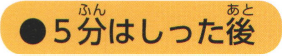
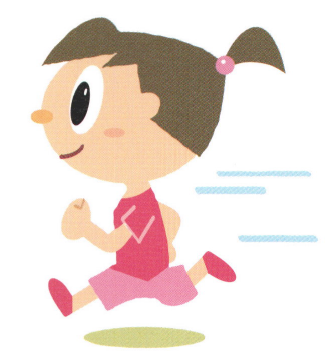
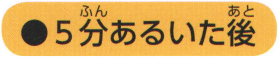
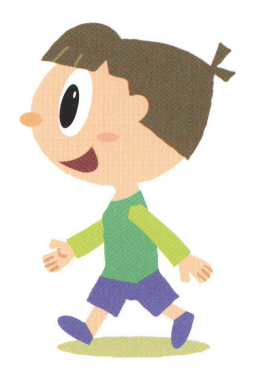
86
人の目とほかの生き物の目、どっちがすごいの?
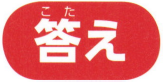 色をみわけたり、奥行きがわかるのが人の目のすごいところ!
色をみわけたり、奥行きがわかるのが人の目のすごいところ!
 人の目もほかの生き物の目も、それぞれのくらしにあった機能をもっているので、いちがいにどちらのほうがすごいとはいえません。
人の目もほかの生き物の目も、それぞれのくらしにあった機能をもっているので、いちがいにどちらのほうがすごいとはいえません。
たとえば、ワシやタカは視力がとてもすぐれていて、1
先にいるネズミなどの獲物をみつけることができます。こんなことは、人にはできませんね。
しかし、人の目は、たくさんの色をみわけることができたり、立体感(奥行き)がわかるという、すごい能力をもっています。
 人の目は、どうやって色をみわけているのでしょうか。
人の目は、どうやって色をみわけているのでしょうか。
太陽の光や電球の光は透明ですが、本当はたくさんの色があつまっています。光がものにあたると、光の中の色によって、すいこまれるものと、はねかえるものにわかれます。
人の目にはいるのは、はねかえった光だけです。その光の色が、ものの色としてとらえられるのです。
 また、立体感がわかると、自分とほかのものとの距離をかんじることができます。
また、立体感がわかると、自分とほかのものとの距離をかんじることができます。
目でものをみるとき、右目と左目は左右に少しはなれてついているので、少しちがう画像がうつります。左右の目にうつった像の情報は、視神経をとおって脳におくられ、脳でふたつの画像をかさねあわせることで、ものとの距離をはかっているのです。
 光のスペクトル
光のスペクトル
 透明にみえる光も、この図のようにたくさんの色の光があつまっている。
透明にみえる光も、この図のようにたくさんの色の光があつまっている。
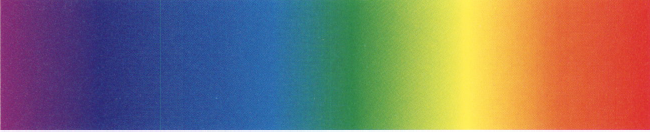
 色をみわけるしくみ
色をみわけるしくみ
 バナナが黄色にみえるのは、バナナにあたった光のうち、主に黄色い光がはねかえって、目にはいってくるから。
バナナが黄色にみえるのは、バナナにあたった光のうち、主に黄色い光がはねかえって、目にはいってくるから。

87
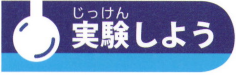 かた方の目でキャップをはめられるかな?
かた方の目でキャップをはめられるかな?
①両目でみながら、ペンにキャップをはめてみよう。かんたんにできるね。
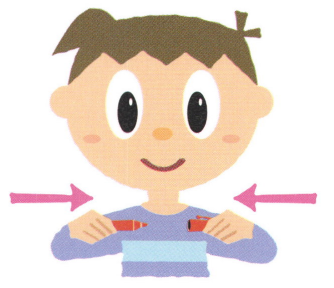
②今度はかた方の目をつぶって、やってみよう。
あれっ!? 少しずれてしまうよ。
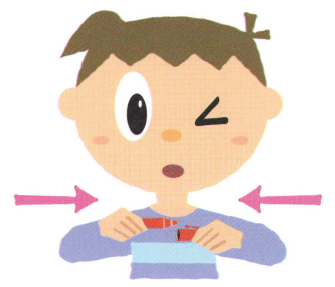
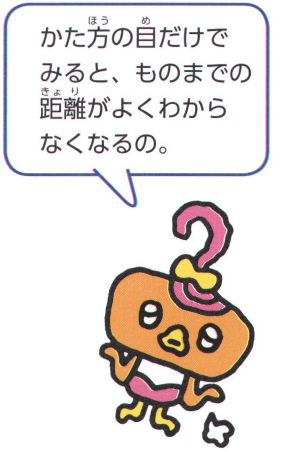
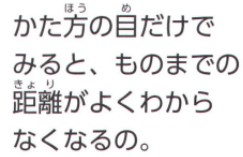
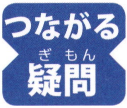 ほかの生き物は、どんなふうにみえているの?
ほかの生き物は、どんなふうにみえているの?
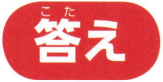 目の位置や機能によって、みえ方がちがう!
目の位置や機能によって、みえ方がちがう!
 生き物の目は、それぞれのくらしに便利なようにできています。
生き物の目は、それぞれのくらしに便利なようにできています。
たとえば、人の目は、太陽の光の中の紫外線をみわけられませんが、ほとんどの昆虫はみわけることができます。そのため、チョウやハチなどの昆虫の目には、花の中心が黒くみえています。食料となる蜜がある場所を、かんたんに見つけることができます。
 目でみえる範囲(視野)も、人とほかの生き物ではちがいます。たとえば、シマウマの視野は、約350°といわれています。目が顔の真横についているので、周囲のほとんどをみわたすことができるのです。ライオンなどの肉食動物がどの方向からきても、すぐにみつけてにげだすことができます。
目でみえる範囲(視野)も、人とほかの生き物ではちがいます。たとえば、シマウマの視野は、約350°といわれています。目が顔の真横についているので、周囲のほとんどをみわたすことができるのです。ライオンなどの肉食動物がどの方向からきても、すぐにみつけてにげだすことができます。
 昆虫がみている花は?
昆虫がみている花は?
 紫外線撮影したタンポポ。チョウなどには、花の中心が黒くはっきりとみえる。
紫外線撮影したタンポポ。チョウなどには、花の中心が黒くはっきりとみえる。

 人がみている花は?
人がみている花は?
 可視光線で撮影した花。人の目は、いろいろな色をみわけることができる。
可視光線で撮影した花。人の目は、いろいろな色をみわけることができる。

 人の視野は?
人の視野は?
 視野は約200°。両目が前についているため、両目でみられる範囲が広く、ものとの距離が正確にわかる。
視野は約200°。両目が前についているため、両目でみられる範囲が広く、ものとの距離が正確にわかる。

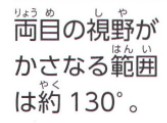
 シマウマの視野は?
シマウマの視野は?
 視野は約350°。両目が顔の真横にはなれてついているため、視野は広いが、真正面はみえにくいといわれている。
視野は約350°。両目が顔の真横にはなれてついているため、視野は広いが、真正面はみえにくいといわれている。

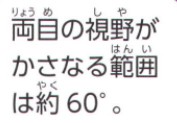
88
目の錯覚って何?
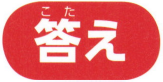 ものが実際とはちがってみえること
ものが実際とはちがってみえること
 目の錯覚とは、ものの大きさや形、色などのようすが、実際とはちがってみえてしまうことです。
目の錯覚とは、ものの大きさや形、色などのようすが、実際とはちがってみえてしまうことです。
下の図1をみてみましょう。2つの青い円をくらべると、小さい円にかこまれたほうが大きく見えますね。でも、実際はまったく同じ大きさです。これが目の錯覚です。
 図1 「エビングハウス錯視」
図1 「エビングハウス錯視」
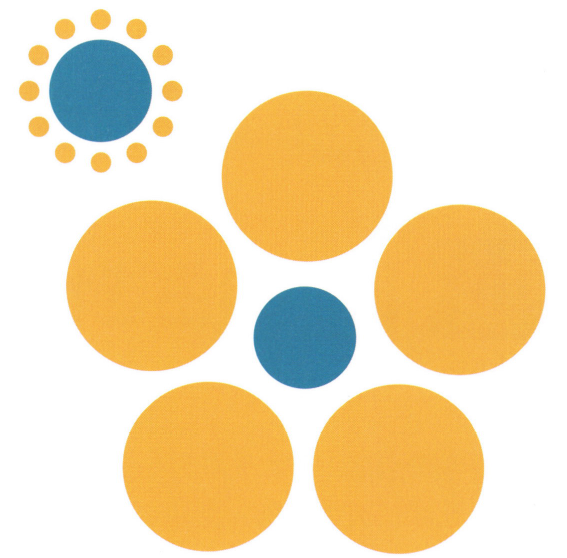
 目の錯覚は、目のしくみでおこることもありますが、多くは脳でおこります。
目の錯覚は、目のしくみでおこることもありますが、多くは脳でおこります。
人はものをみるとき、目だけでみているのではなく、脳もつかっています。目からはいった情報を脳がうけとり、調整をくわえて、みたものが何なのかを判断しています。その調整にずれがあると、目の錯覚がおこるのです。
図1は、青い円の大きさを、まわりの円とくらべて判断するため、小さい円にかこまれたほうが大きくみえたのです。
もうひとつ、図2をみてみましょう。矢じるしのような形が上下にならんでいます。横のぼうは、どちらが長くみえますか? 下のほうが長くみえますが、実際は同じ長さです。両はしの短いぼうの角度によって、脳がだまされてしまうのです。
 図2 「ミュラー・リヤー錯視」
図2 「ミュラー・リヤー錯視」
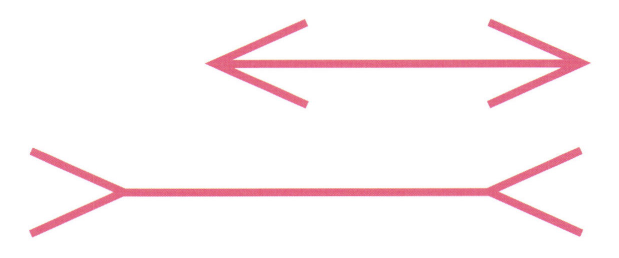
 いろいろな錯視をみてみよう
いろいろな錯視をみてみよう
大きさや形、色がちがってみえたり、まっすぐなものがまがってみえたり、ないものがみえたり、いろいろな目の錯覚を体験してみましょう。
 長いのはどっち?
長いのはどっち?
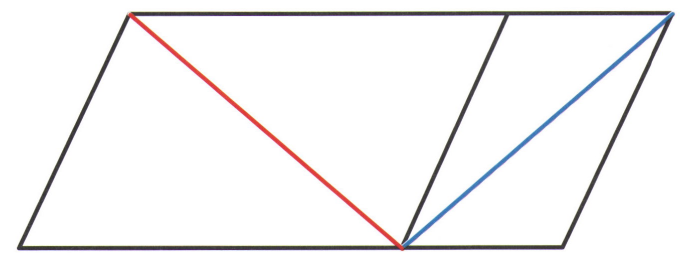
 「ザンダー錯視」
「ザンダー錯視」
青と赤の線は同じ長さなのに、赤いほうが長くみえる。線のはいっている平行四辺形の大きさがちがうために、長さがちがってみえる。
 同じ形?
同じ形?
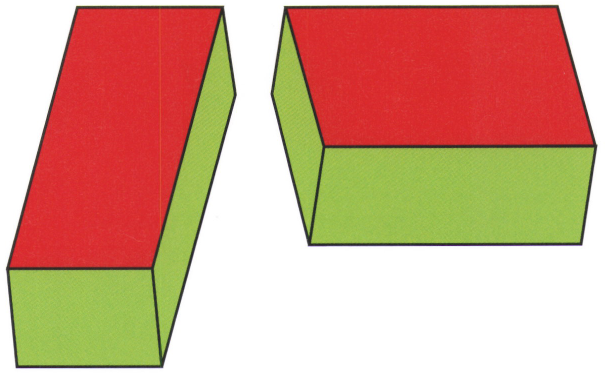
 「シェパード錯視」
「シェパード錯視」
2つの箱の赤いふたは、形も大きさも同じなのに、左のほうが細長くみえる。奥行きの長さが、実際よりも長くかんじられるから。
89
 白い三角形がみえる?
白い三角形がみえる?
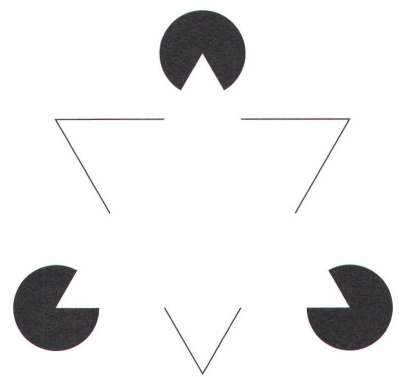
 「カニッツァの三角形」
「カニッツァの三角形」
円や線がとぎれているところに、まわりよりも白い三角形がのっているようにみえる。
 ゆらすとうごいてみえる?
ゆらすとうごいてみえる?
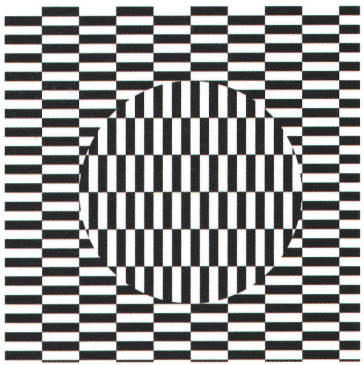
 「オオウチ錯視」
「オオウチ錯視」
本をゆらすと、真ん中の円がゆらゆらとうごいてみえる。
 色は同じ?
色は同じ?
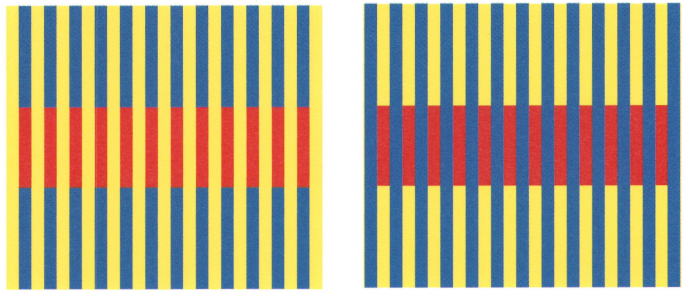
 「ムンカー錯視」
「ムンカー錯視」
左右の図の赤いおびは同じ色なのに、はさまれる線の色にちかづいてみえる。
 線はまっすぐ?
線はまっすぐ?
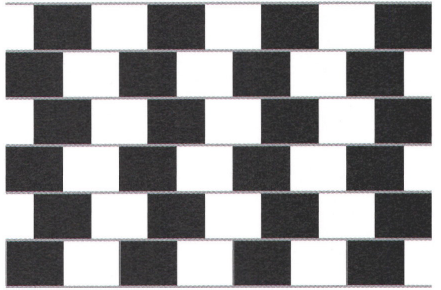
 「カフェウォール錯視」
「カフェウォール錯視」
白黒のタイルをずらしてならべると、線がかたむいてみえる。
 サイコロのたねあかし
サイコロのたねあかし
サイコロは、中心がくぼんだ形をしています。箱のような形にみえるのは、「サイコロなら、中心がでっぱっているはずだ」と脳がまちがえてしまうからです。
91
鼻がつまると、なぜ味がわからなくなるの?
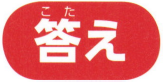 舌だけではなく、鼻もつかってあじわっているから
舌だけではなく、鼻もつかってあじわっているから
 かぜや花粉症などで鼻がつまっているときは、大好物をたべても、あまりおいしくかんじませんね。
かぜや花粉症などで鼻がつまっているときは、大好物をたべても、あまりおいしくかんじませんね。
人は、基本的な味を舌でかんじます。あま味、酸味、苦味、塩味、うま味が、舌でかんじる5つの味の基本です。
しかし、おいしい、まずいとかんじるのは、舌だけではありません。人が食事をするときには、五感をつかってあじわっているのです。
 五感というのは、視覚(みる)、聴覚(きく)、嗅覚(かぐ)、味覚(あじわう)、触覚(さわる)の5つの感覚のことです。
五感というのは、視覚(みる)、聴覚(きく)、嗅覚(かぐ)、味覚(あじわう)、触覚(さわる)の5つの感覚のことです。
おいしさは、形や色、もりつけなどの「見た目」を視覚で、サクサクやポリポリといったかむときの「音」を聴覚で、「におい」を嗅覚で、「味」を味覚で、「舌ざわり」や「歯ごたえ」を触覚でかんじて、総合的に判断しています。
 鼻がつまると五感のうちの嗅覚がにぶるため、においをかんじにくくなるので、おいしいかどうかがよくわからなくなるというわけです。
鼻がつまると五感のうちの嗅覚がにぶるため、においをかんじにくくなるので、おいしいかどうかがよくわからなくなるというわけです。
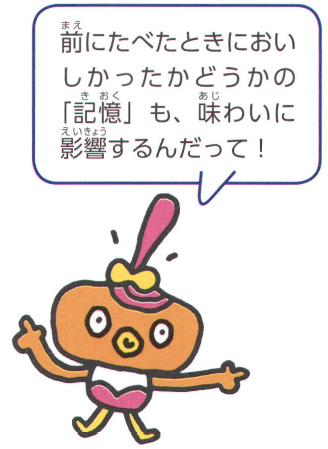
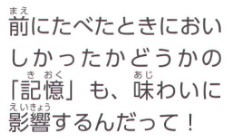
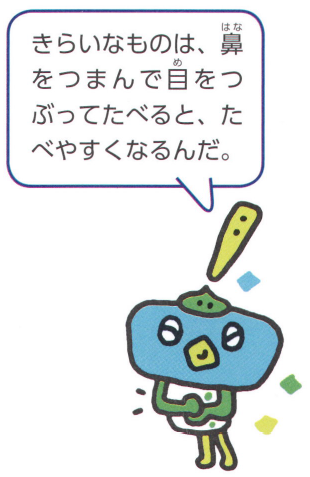
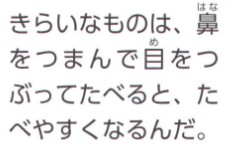
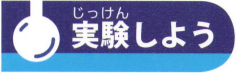 鼻をつまんで味をあてよう
鼻をつまんで味をあてよう
鼻をつまんだり、目かくしをしたりして情報をへらすと、味のかんじ方がどうかわるか、実験してみよう。
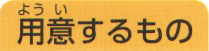
いろいろな味のジュース(グレープ、オレンジ、アップルなど)
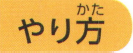
①目かくしをし、鼻をつまんで、順番にジュースをのみます。
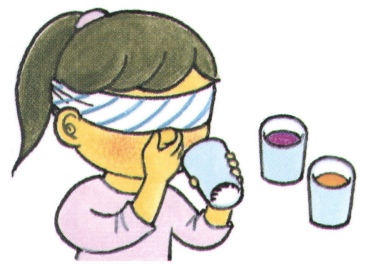
②それぞれ、何の味のジュースかあててみましょう。
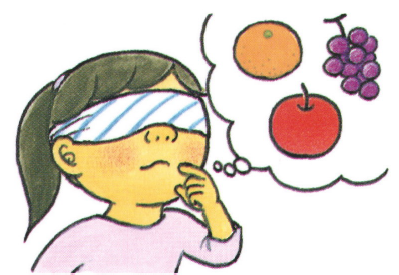
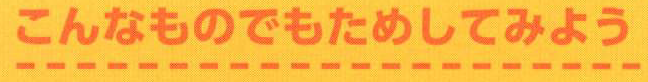
・カレーとシチュー
・みそしるとコーンポタージュ、コンソメスープ
・いろいろな味のキャンディー

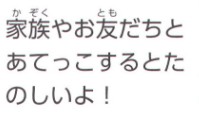
92
皮膚の色はどうしてちがうの?
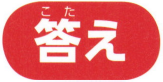 メラニン色素の量がちがうから
メラニン色素の量がちがうから
 メラニン色素が少ないのが白色人種、多いと黒色人種、その中間が黄色人種です。
メラニン色素が少ないのが白色人種、多いと黒色人種、その中間が黄色人種です。
皮膚の色のちがいは、メラニン色素の量によってきまります。メラニン色素の量は、親からの遺伝によってきまりますが、うまれてきてからの環境によっても、ふえたりへったりします。
メラニン色素は、太陽の光にふくまれる紫外線から体をまもるはたらきをしています。
 アフリカなど、陽ざしが強く、暑い地域では、体に害のある紫外線から皮膚をまもるためには、メラニン色素が多いほうが都合がよく、皮膚の黒い黒色人種がうまれました。
アフリカなど、陽ざしが強く、暑い地域では、体に害のある紫外線から皮膚をまもるためには、メラニン色素が多いほうが都合がよく、皮膚の黒い黒色人種がうまれました。
また、スウェーデンやフィンランドといった北欧の寒い国では、陽ざしが弱いので、このような地域では、メラニン色素の量は少なくてもよく、白色人種が多いといわれています。その中間の気候のアジアでは、黄色人種が多いのです。
 メラニン色素のちがいが皮膚の色のちがいになる。
メラニン色素のちがいが皮膚の色のちがいになる。

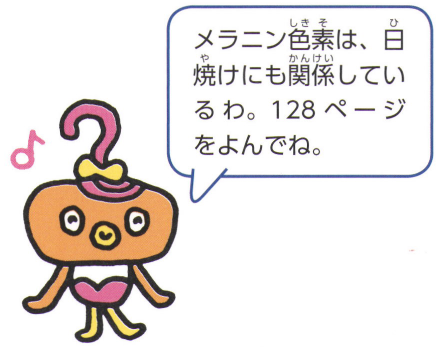
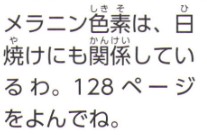
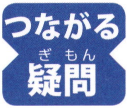 髪や目の色はどうしてちがうの?
髪や目の色はどうしてちがうの?
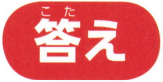 皮膚と同じくメラニン色素の量が、人それぞれちがうから
皮膚と同じくメラニン色素の量が、人それぞれちがうから
 毛の皮膚の外にでている部分を毛幹といいます。毛幹は、毛小皮(キューティクル)、毛皮質、毛髄質の3つの層でできています。
毛の皮膚の外にでている部分を毛幹といいます。毛幹は、毛小皮(キューティクル)、毛皮質、毛髄質の3つの層でできています。
毛の色は、毛皮質にふくまれるメラニン色素と、毛髄質にはいった空気の量できまります。空気がたくさんはいっていると、光にすけて、金色など、明るい色にみえます。
 日本人は黒っぽい目の人が多いのですが、世界には、明るい茶色や灰色、青緑や青い目の人もたくさんいます。
日本人は黒っぽい目の人が多いのですが、世界には、明るい茶色や灰色、青緑や青い目の人もたくさんいます。
目の色をきめるのも、黒目の瞳孔をかこむ虹彩という部分にあるメラニン色素です。
 髪や目の色もやはり、陽ざしが弱い北欧では、メラニン色素の少ない金髪や青い目の人が多く、アフリカなど陽ざしが強い地域では黒い髪や黒っぽい目が多いのです。メラニン色素が紫外線から、大切な頭や目をまもるよう、環境にあわせた進化をしているのです。
髪や目の色もやはり、陽ざしが弱い北欧では、メラニン色素の少ない金髪や青い目の人が多く、アフリカなど陽ざしが強い地域では黒い髪や黒っぽい目が多いのです。メラニン色素が紫外線から、大切な頭や目をまもるよう、環境にあわせた進化をしているのです。
93
悲しいと涙がでるのはなぜ?
 脳からでてくる副交感神経によって涙腺が刺激されるから
脳からでてくる副交感神経によって涙腺が刺激されるから
 涙は上まぶたの裏側にある「涙腺」というところでつくられています。悲しい気持ちになると、脳からでてくる副交感神経によって涙腺が刺激されて、涙がながれるのです。
涙は上まぶたの裏側にある「涙腺」というところでつくられています。悲しい気持ちになると、脳からでてくる副交感神経によって涙腺が刺激されて、涙がながれるのです。
このときにでる涙は水分が多く、塩素やナトリウム、たんぱく質、ブドウ糖、カルシウム、カリウムなどのほかの成分は少ないといわれています。
 しかし、涙のもともとの役目は、目をまもることです。目にはいったごみやほこりをあらいながしたり、目の表面を殺菌消毒して、目に酸素やたんぱく質などの栄養をはこぶため、涙はつねに少しずつ分泌されて、目をぬらしているのです。
しかし、涙のもともとの役目は、目をまもることです。目にはいったごみやほこりをあらいながしたり、目の表面を殺菌消毒して、目に酸素やたんぱく質などの栄養をはこぶため、涙はつねに少しずつ分泌されて、目をぬらしているのです。
このような涙は、悲しくてないたときにでる涙よりも水分が少なく、ほかの成分が多くなっています。また、おこったときやくやしいときにでる涙も、水分は少なく、ほかの成分が多いといわれています。
 ふだん、少しずつでている涙は、目をまもる役目をおえた後、下の図のように、鼻にながれて、今度は鼻の粘膜をうるおします。
ふだん、少しずつでている涙は、目をまもる役目をおえた後、下の図のように、鼻にながれて、今度は鼻の粘膜をうるおします。
 涙は、目の表面をあらいながした後、涙のうにためられ、鼻にながれて、今度は鼻の粘膜をしめらせる。
涙は、目の表面をあらいながした後、涙のうにためられ、鼻にながれて、今度は鼻の粘膜をしめらせる。
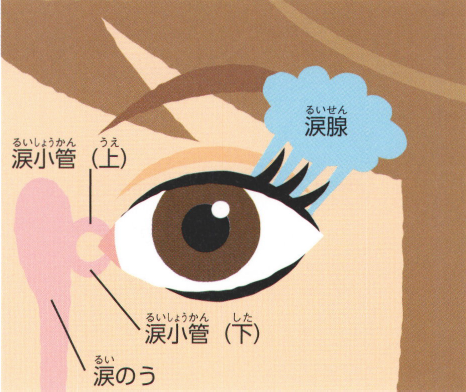
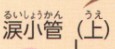
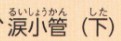


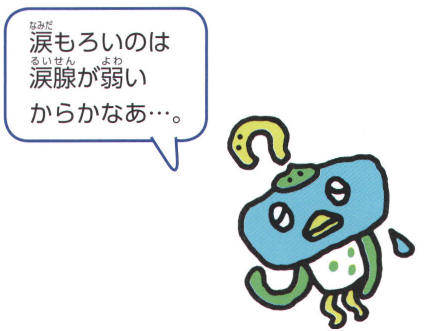
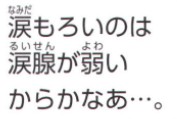
 涙がでるのはどんなとき?
涙がでるのはどんなとき?
涙がながれるのは、悲しいときだけではありませんね。どんなときに涙はでるのかな?
 タマネギをきったとき
タマネギをきったとき
タマネギからでる硫化アリルという成分に、目が刺激されて、涙がでる。

 いたいとかんじたとき
いたいとかんじたとき
いたみをかんじて脳が刺激され、涙がでる。

 目にごみがはいったとき
目にごみがはいったとき
大きなごみがはいると、それをおしだそうとして大量の涙がだされる。

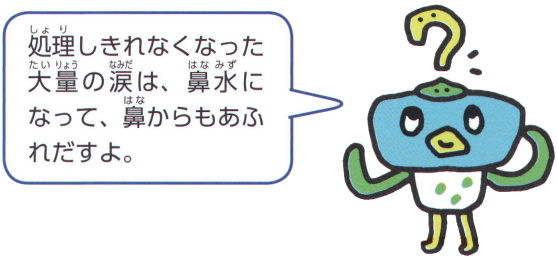
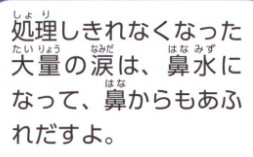
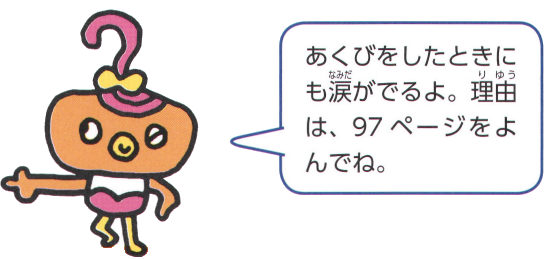
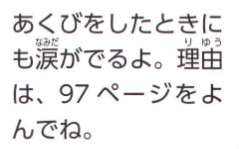
94
赤ちゃんはどうしてよくなくの?
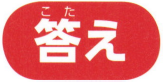 なくことで、気持ちをつたえようとしているのです
なくことで、気持ちをつたえようとしているのです
 うまれて間もない赤ちゃんは、自分ひとりではまだ何もできず、お母さんやお父さん、きょうだいなど、まわりの人に世話をしてもらっています。まだことばをはなすこともできません。ですから、まわりの人に気持ちをつたえるために、ないて、注意をひきます。
うまれて間もない赤ちゃんは、自分ひとりではまだ何もできず、お母さんやお父さん、きょうだいなど、まわりの人に世話をしてもらっています。まだことばをはなすこともできません。ですから、まわりの人に気持ちをつたえるために、ないて、注意をひきます。
 「おむつがぬれていて気持ちわるいよ」とか、「おなかがすいたから、おっぱいをちょうだい」とか、「ねむたいから、だっこして」などという気持ちを、なくことでつたえようとしているのです。
「おむつがぬれていて気持ちわるいよ」とか、「おなかがすいたから、おっぱいをちょうだい」とか、「ねむたいから、だっこして」などという気持ちを、なくことでつたえようとしているのです。
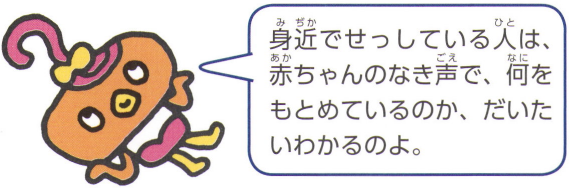
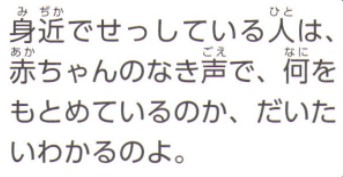
 動物の赤ちゃん、鳴き声あつめ
動物の赤ちゃん、鳴き声あつめ
動物の赤ちゃんは、どんな鳴き声でお母さんをよぶのかな?
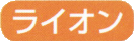 ニャア
ニャア
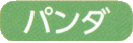 アアン
アアン
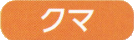 ミャーミャー
ミャーミャー
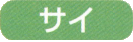 ミューミュー
ミューミュー
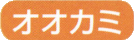 クゥーン
クゥーン
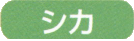 ピァー
ピァー
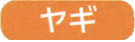 メェー
メェー
 ピーィピーィ
ピーィピーィ
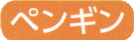 ピーピー
ピーピー
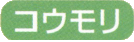 ピヨピヨ
ピヨピヨ
 ライオンの赤ちゃんは、ネコのように「ニャア」となく。
ライオンの赤ちゃんは、ネコのように「ニャア」となく。
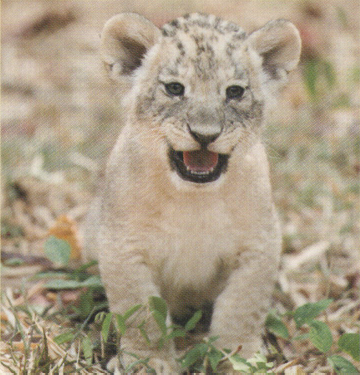
 赤ちゃんとふれあってみよう
赤ちゃんとふれあってみよう
身近に0歳の赤ちゃんがいたら、おうちの人におねがいして、赤ちゃんとふれあわせてもらいましょう。
 赤ちゃんの手のひらに指をいれてみよう
赤ちゃんの手のひらに指をいれてみよう
小さい赤ちゃんは手をグーの形に軽くむすんでいることが多い。その中に人さし指をいれてみよう。刺激に反射して、赤ちゃんは強い力で、ぎゅっと指をにぎってくる。
 赤ちゃんのほほをさわってみよう
赤ちゃんのほほをさわってみよう
赤ちゃんの口もとを人さし指で軽くつんつんとさわると、赤ちゃんはそのほうに顔をむけてパクッと指にすいつきます。お母さんのおっぱいをさがしているのかな? 指を強い力でチューチューすったりもします。
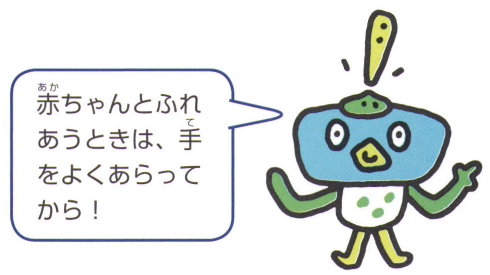
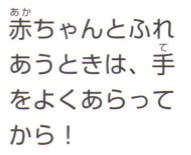
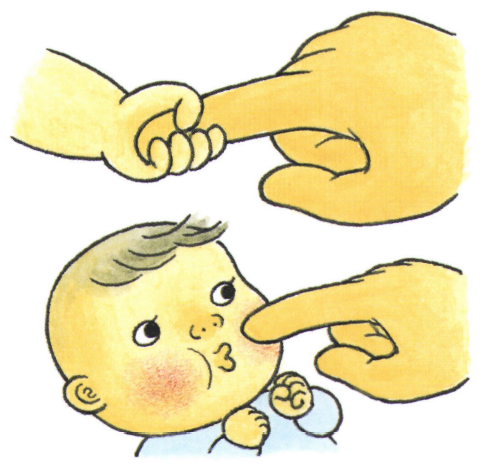
95
赤ちゃんはどうしてうまれてすぐにたてないの?
 骨格や筋肉が発達していないから
骨格や筋肉が発達していないから
 赤ちゃんは、お母さんのおなかの中にいるときには、羊水という液体の中にぷかぷかとういています。その中では、はいはいのような動きをしたり、2本足であるくような動作もしているのです。
赤ちゃんは、お母さんのおなかの中にいるときには、羊水という液体の中にぷかぷかとういています。その中では、はいはいのような動きをしたり、2本足であるくような動作もしているのです。
 それなのに、お母さんの体の外にでてしまうとたつことはもちろん、よつんばいではいはいすることさえ、できませんね。
それなのに、お母さんの体の外にでてしまうとたつことはもちろん、よつんばいではいはいすることさえ、できませんね。
それは、骨格や筋肉がまだ十分発達しないままうまれてくるので、地球の重力に体がたえられないからです。
 赤ちゃんは、骨格や筋肉、脳などが、時間をかけて少しずつ発達し、うまれてからおよそ1年で、たつことができるようになります。
赤ちゃんは、骨格や筋肉、脳などが、時間をかけて少しずつ発達し、うまれてからおよそ1年で、たつことができるようになります。
 うまれてから8か月くらいで、はいはいをはじめる。
うまれてから8か月くらいで、はいはいをはじめる。
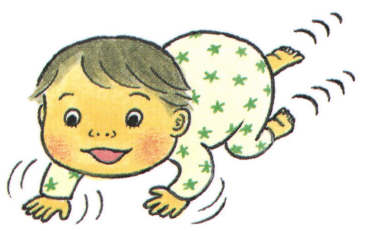
 うまれて1年くらいで、たったり、数歩あるけるようになる。
うまれて1年くらいで、たったり、数歩あるけるようになる。
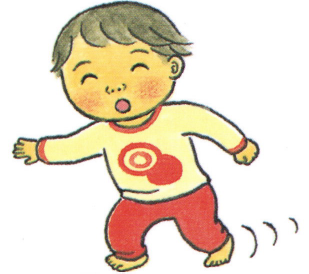

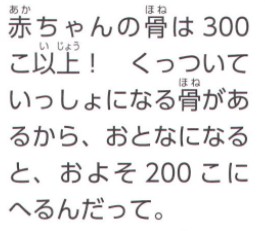
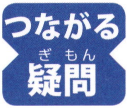 動物の赤ちゃんも、うまれてすぐにはたてないの?
動物の赤ちゃんも、うまれてすぐにはたてないの?
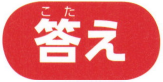 うまれたその日にたてる動物もいます
うまれたその日にたてる動物もいます
 動物の赤ちゃんの中には、うまれてすぐにたつものもいます。ウマやシカ、キリンなどです。
動物の赤ちゃんの中には、うまれてすぐにたつものもいます。ウマやシカ、キリンなどです。
これらの動物に共通していることは、巣をつくらない動物だということ。お母さんは、巣にかくれて赤ちゃんをうんだり、そだてたりすることができません。敵である肉食の動物にねらわれたら、赤ちゃんは自分の足でにげなければなりません。
そのため、うまれてすぐにたてるよう、お母さんのおなかの中で体が十分発達してからでてきます。
 たとえばキリンの赤ちゃんは、うまれて20~30分でたちあがれるようになり、よろよろとしながらも、あるきはじめます。2日もすると、もうはしることもできるようになっているのです。
たとえばキリンの赤ちゃんは、うまれて20~30分でたちあがれるようになり、よろよろとしながらも、あるきはじめます。2日もすると、もうはしることもできるようになっているのです。
 人の赤ちゃんは、お母さんのおなかの中からおよそ10か月でうまれるが、キリンの赤ちゃんは15か月おなかの中にいて、十分に体が発達してからでてくる。
人の赤ちゃんは、お母さんのおなかの中からおよそ10か月でうまれるが、キリンの赤ちゃんは15か月おなかの中にいて、十分に体が発達してからでてくる。
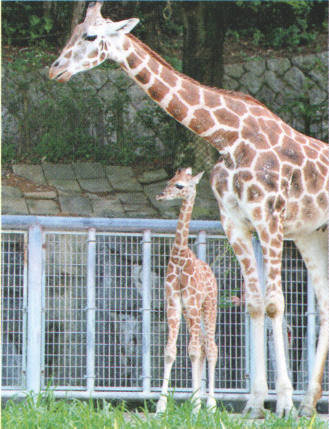
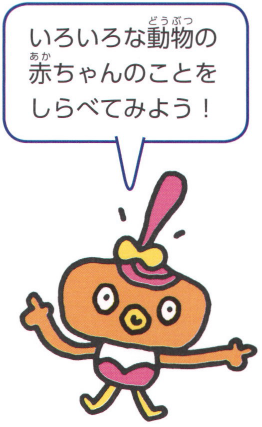
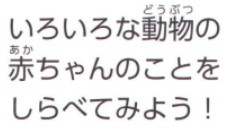
96
人はどうして2本足であるけるの?
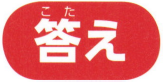 重い体重をささえられるよう、背骨と足の骨が進化したから
重い体重をささえられるよう、背骨と足の骨が進化したから
 動物園などで、たってあるく動物が話題になることがありますが、2本足で背中の筋肉をのばして長時間あるく「直立二足歩行」ができるのは、人だけです。
動物園などで、たってあるく動物が話題になることがありますが、2本足で背中の筋肉をのばして長時間あるく「直立二足歩行」ができるのは、人だけです。
 人は、進化していく中で、2本足であるくのにてきした体を手にいれることができました。
人は、進化していく中で、2本足であるくのにてきした体を手にいれることができました。
たとえば、たっているときに上半身をしっかりとささえる、ゆるいS字形の背骨があります。これは、脳が大きくなって重くなった頭をささえます。
もうひとつは、足のうらの骨がアーチ形になっているため、上からの力に強く、地面からうけるしょうげきもやわらげます。
 わたしたちの祖先が2本足であるくようになったのは、今から400万年くらい前だといわれています。両手が自由になったことで、人は道具をつくったりつかったりするようになり、脳も発達して、ほかの動物にはない、文明や文化をつくりだすことができたのです。
わたしたちの祖先が2本足であるくようになったのは、今から400万年くらい前だといわれています。両手が自由になったことで、人は道具をつくったりつかったりするようになり、脳も発達して、ほかの動物にはない、文明や文化をつくりだすことができたのです。
 人の背骨はゆるいS字形にまがっていて、重い頭をしっかりとささえることができる。
人の背骨はゆるいS字形にまがっていて、重い頭をしっかりとささえることができる。
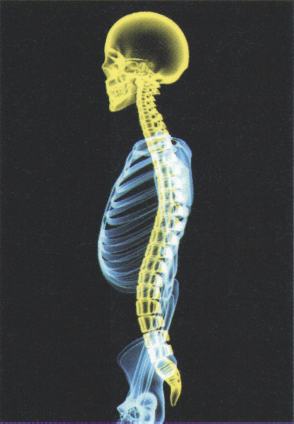
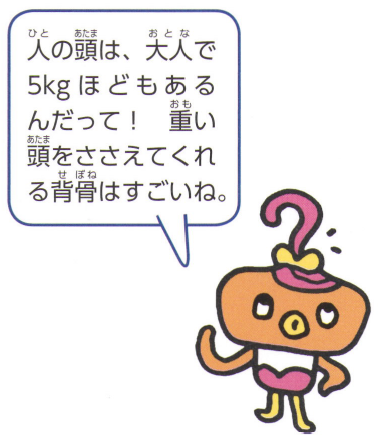
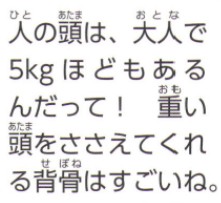
 くるぶしから下のかた足は全部で26この骨でできていて、横からみるとアーチ形になっている。かかとの骨は大きく、全体重がかかってもたえられる。
くるぶしから下のかた足は全部で26この骨でできていて、横からみるとアーチ形になっている。かかとの骨は大きく、全体重がかかってもたえられる。

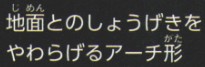
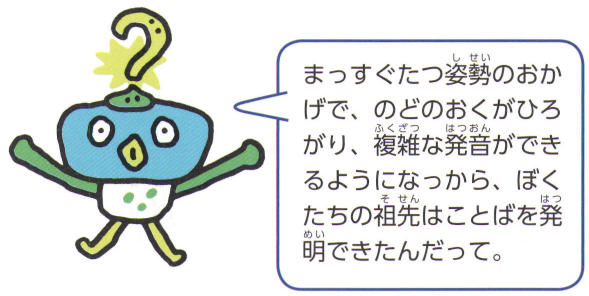
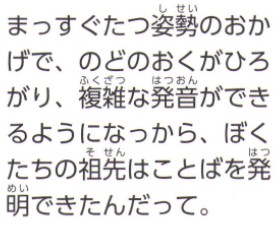
 足のうらをみてみよう
足のうらをみてみよう
はだしになってゆかに足のうらをつけると、つま先とかかとの間に、すき間ができますね。この、ゆかにつかずにういている部分を「土ふまず」といいます。
土ふまずがあるのは、人の足の特長です。人によくにた動物のゴリラやチンパンジーには、この土ふまずはありません。
2本足であるくのにてきしたアーチ形の骨にそって筋肉がついているからこそ、人の足には土ふまずができるのです。

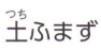
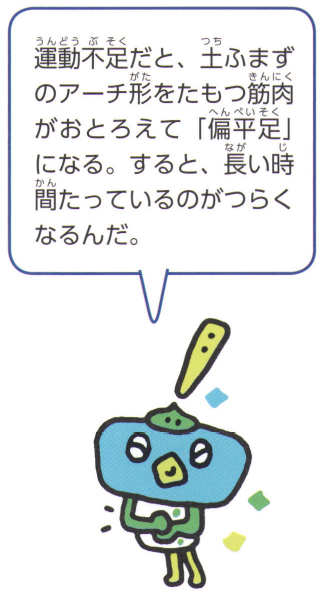
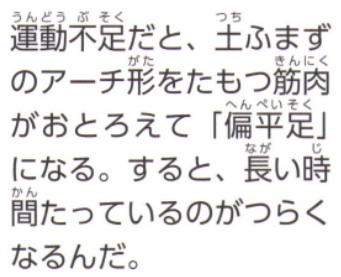
97
あくびがうつるって本当?
 あくびがうつることはありません
あくびがうつることはありません
 だれかがあくびをすると、まわりの人もあくびをすることがありますね。よく、「あくびがうつった」といいますが、あくびは病気ではないので、ほかの人にはうつりません。
だれかがあくびをすると、まわりの人もあくびをすることがありますね。よく、「あくびがうつった」といいますが、あくびは病気ではないので、ほかの人にはうつりません。
昼食の後や、夜ねる時間など、だれかがねむたくなってあくびをするときには、ほかの人もちょうど同じようにねむたくなり、同じようにあくびがでるので、まるであくびがうつったようにかんじられるのでしょう。
ただし、「あくびはうつるのだ」という学者もいます。ほかの人の動作や「ねむたい」という気持ちに自分も共感して、同じ動作をしたくなるのだ、というのです。
 人は空気から酸素をとりいれ、さまざまな活動をしていますが、ねむいときは息をするのがゆっくりになり、体の中の酸素が不足しやすくなります。
人は空気から酸素をとりいれ、さまざまな活動をしていますが、ねむいときは息をするのがゆっくりになり、体の中の酸素が不足しやすくなります。
酸素がたりなくなると、体にさまざまな命令をだす脳は、活動がにぶくなります。
そこで脳は、「大きく息をして、酸素をとりいれなさい」と体に命令するのです。脳の命令をうけて、体はより多くの酸素をとりいれようと、口を大きくあけ、あくびをするというわけです。
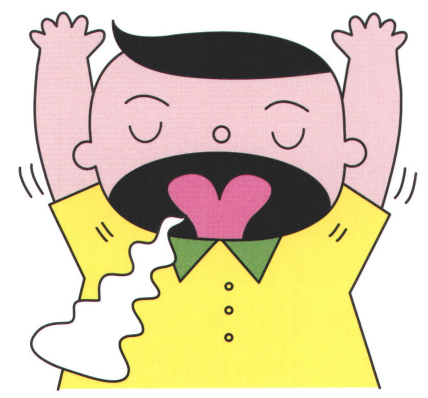
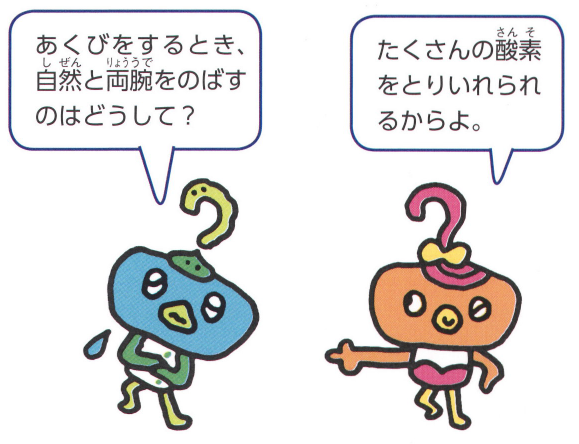
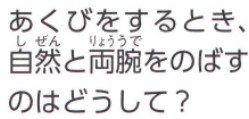
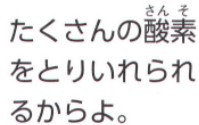
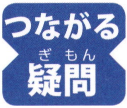 あくびをすると、涙がでるのはなぜ?
あくびをすると、涙がでるのはなぜ?
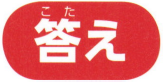 顔の筋肉がうごいて、涙をおしだすから
顔の筋肉がうごいて、涙をおしだすから
 涙は、目の上にある「涙腺」というところからでています。悲しかったりいたかったりしてなくとき以外にも、涙は、涙腺から少しずつでているのです。
涙は、目の上にある「涙腺」というところからでています。悲しかったりいたかったりしてなくとき以外にも、涙は、涙腺から少しずつでているのです。
涙は、目に酸素や栄養をはこんだり、目の表面のよごれをあらいながしたりしています。役目をおえたあとの涙は、目頭のおくにある、「涙のう」というふくろにためられます。そして、ある程度たまると、鼻の中にすてられます。
あくびをすると、顔の筋肉が大きくうごいて、この涙のうをおすので、涙が目にぎゃくもどりして、こぼれでてしまうのです。
98
からい物をたべると汗がでるのはなぜ?
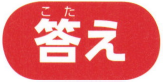 胃や腸での消化が活発になるため
胃や腸での消化が活発になるため
 からい料理には、トウガラシなどの、からさをかんじさせる香辛料がはいっています。香辛料には、胃や腸に強い刺激をあたえて、消化を活発にさせるはたらきをもつものがあります。
からい料理には、トウガラシなどの、からさをかんじさせる香辛料がはいっています。香辛料には、胃や腸に強い刺激をあたえて、消化を活発にさせるはたらきをもつものがあります。
消化が活発になると、たくさんのエネルギーがつかわれて、体の中があつくなります。すると、脳から「汗をだして熱をにがしなさい」という命令がでるのです。
 からい物をたべたときだけでなく、運動をしたときなど、汗がでるきっかけはさまざまですが、汗の役割は、あつくなった体をひやして、体温をちょうどよくたもつことです。
からい物をたべたときだけでなく、運動をしたときなど、汗がでるきっかけはさまざまですが、汗の役割は、あつくなった体をひやして、体温をちょうどよくたもつことです。
汗はほとんどが水分で、体の表面から蒸発するときに体の熱をうばい、体温をさげてくれるのです。
 消化が活発になってあつくなった体を汗でひやすよう、脳が命令する。
消化が活発になってあつくなった体を汗でひやすよう、脳が命令する。

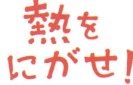


 汗がでるのはどんなとき?
汗がでるのはどんなとき?
汗の役割は、あつくなった体をひやして、体温を調節すること。さまざまな場面での汗を観察してみましょう。
 運動をしたとき
運動をしたとき

 熱がでたとき
熱がでたとき

 気温が高いとき
気温が高いとき

 緊張したとき
緊張したとき

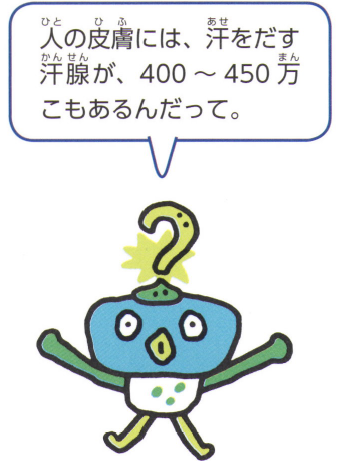
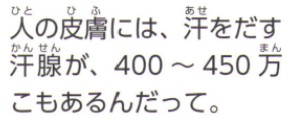
99
子どもが親ににるのはなぜ?
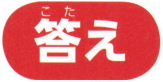 両親から「遺伝子」をうけつぐから
両親から「遺伝子」をうけつぐから
 親の特徴が子どもにうけつがれることを「遺伝」といいます。遺伝のために必要な設計図を「遺伝子」といって、お母さんのおなかの中の赤ちゃんの目、耳、内臓、骨などすべてが、この設計図によってつくられていきます。
親の特徴が子どもにうけつがれることを「遺伝」といいます。遺伝のために必要な設計図を「遺伝子」といって、お母さんのおなかの中の赤ちゃんの目、耳、内臓、骨などすべてが、この設計図によってつくられていきます。
 生き物の体をつくっている細胞の中には、両親からもらった「染色体」があります。染色体を拡大してみると、ねじれたはしごのようなものがあるのがわかります。これは、遺伝子がくさりのようにびっしりとつながったもので、「DNA」とよばれています。
生き物の体をつくっている細胞の中には、両親からもらった「染色体」があります。染色体を拡大してみると、ねじれたはしごのようなものがあるのがわかります。これは、遺伝子がくさりのようにびっしりとつながったもので、「DNA」とよばれています。
 DNAには、生き物の種類や性別、見た目の特徴や性質などをきめる大事な情報がかきこまれています。
DNAには、生き物の種類や性別、見た目の特徴や性質などをきめる大事な情報がかきこまれています。
DNAのところどころには、「背を高く」とか「耳を大きく」といったその人をつくる情報が暗号のようにかきこまれています。
 遺伝子がはしごのように長くつながっている。
遺伝子がはしごのように長くつながっている。

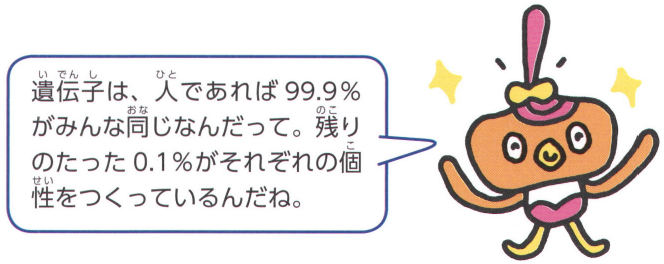
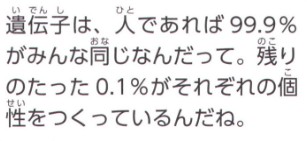
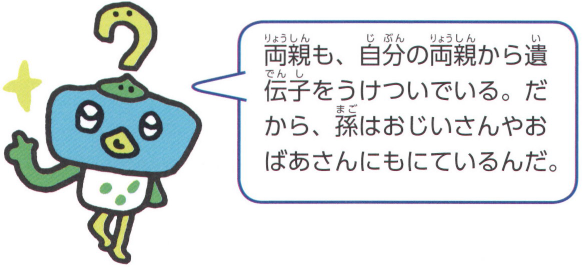
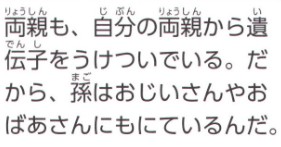
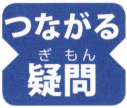 うまれてくる子が男か女かは、どうやってきまるの?
うまれてくる子が男か女かは、どうやってきまるの?
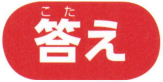 たった1組の染色体のくみあわせのちがいできまります
たった1組の染色体のくみあわせのちがいできまります
 人の細胞の中には、2つ1組になった染色体が23種類あります。その23番目の染色体が、男女の性をきめています。
人の細胞の中には、2つ1組になった染色体が23種類あります。その23番目の染色体が、男女の性をきめています。
23番目の染色体には、X染色体とY染色体の2種類があります。男性の細胞にはX染色体とY染色体が1つずつありますが、女性はX染色体が2つです。
子どもは、この染色体を、両親から1つずつもらいます。そのくみあわせによって男か女かにわかれるのです。
 染色体のくみあわせの23番目で男か女かがきまる。
染色体のくみあわせの23番目で男か女かがきまる。
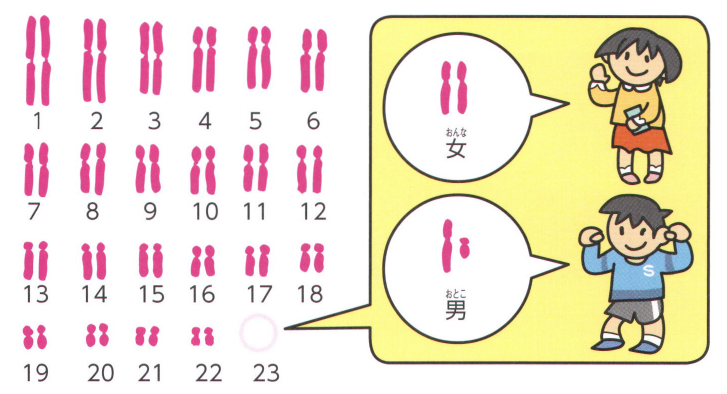


100
人にはどうしてしっぽがないの?
 生活に必要なくなったから
生活に必要なくなったから
 おしりのわれめの少し上のほうをさぐってみましょう。とがった小さな骨がみつかりましたか。これは、尾骨といって、人の骨にのこるしっぽのなごりだといわれています。人が、今のように進化する前、わたしたちの祖先には、しっぽがはえていたのです。
おしりのわれめの少し上のほうをさぐってみましょう。とがった小さな骨がみつかりましたか。これは、尾骨といって、人の骨にのこるしっぽのなごりだといわれています。人が、今のように進化する前、わたしたちの祖先には、しっぽがはえていたのです。
 じつは、わたしたちにも、お母さんのおなかにやどって1か月半くらいまでの間はしっぽがはえていました。おなかの中で成長する途中で、うまれてからの生活に必要のないしっぽは、なくなってしまうのです。
じつは、わたしたちにも、お母さんのおなかにやどって1か月半くらいまでの間はしっぽがはえていました。おなかの中で成長する途中で、うまれてからの生活に必要のないしっぽは、なくなってしまうのです。
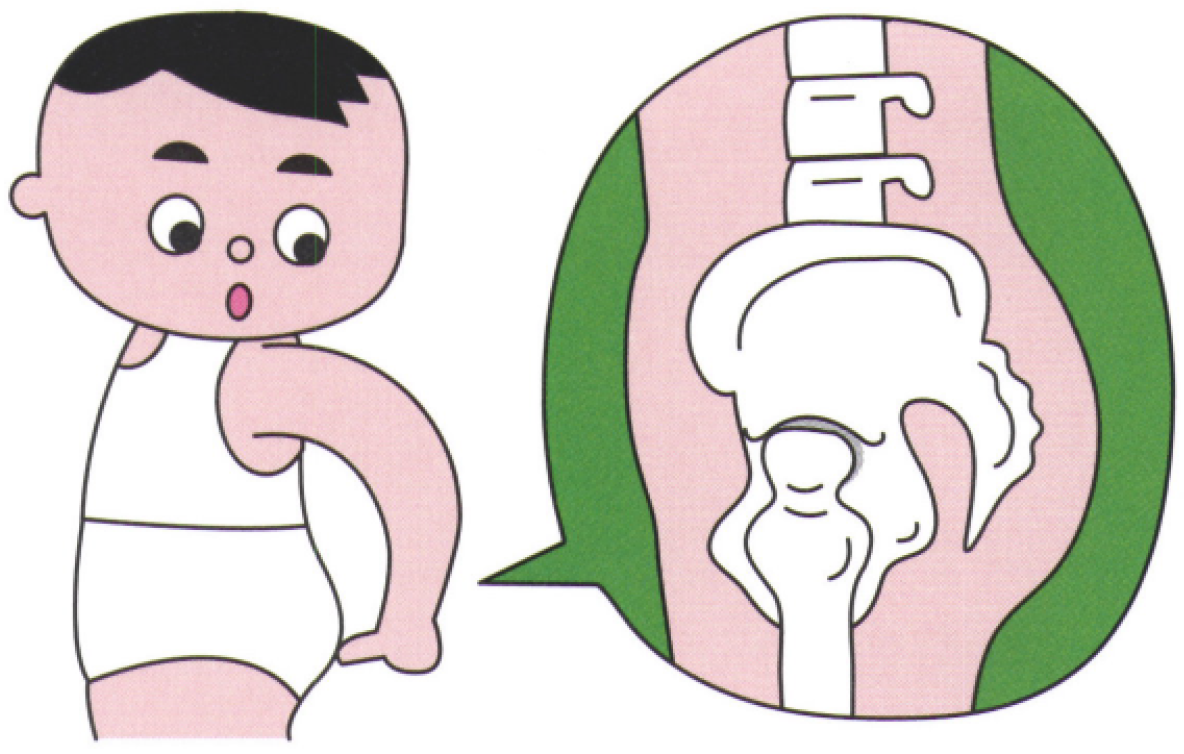
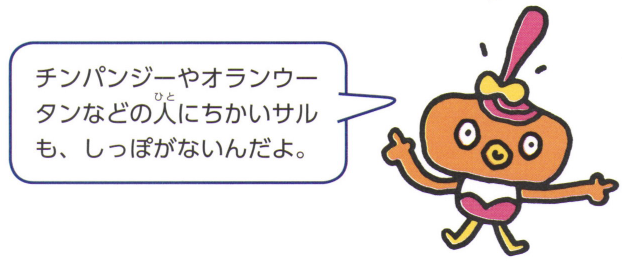
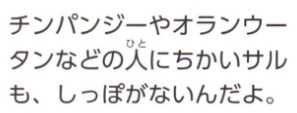
 動物のしっぽにはどんな役割があるの?
動物のしっぽにはどんな役割があるの?
動物のしっぽは、さまざまな役割をもっています。
つかむ、バランスをとる
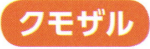
木のえだにまきつけてぶらさがる。枝の上をあるくときは、しっぽを左右にふってバランスをとる。
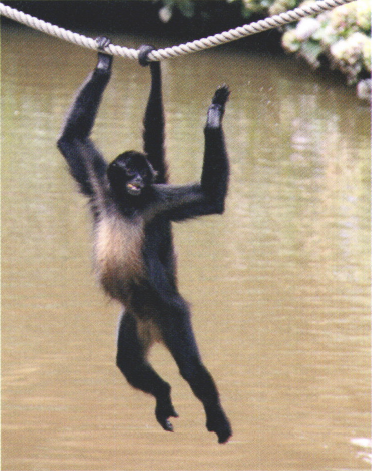
危険をしらせる

しっぽをたてて、なかまに危険をしらせる。

バランスをとる
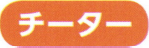
はしるとき、まがる方向とぎゃくにしっぽをたおすことで、バランスをとる。

あたためる
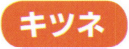
寒いとき、顔にまきつける。

101
どうして、人にはへそがあるの?
 お母さんのおなかにいたときのなごりです
お母さんのおなかにいたときのなごりです
 へそは、「へそのお」という管がとれたあとです。へそのおは、お母さんの子宮の胎盤と赤ちゃんをつないでいます。
へそは、「へそのお」という管がとれたあとです。へそのおは、お母さんの子宮の胎盤と赤ちゃんをつないでいます。
お母さんのおなかの中にいるとき、赤ちゃんは、へそのおをとおして、酸素や栄養をもらっているのです。
 お母さんのおなかの中からでてくると、もう必要なくなるため、へそのおはきりはなされますが、きりはなしたあとであるへそは、おとなになってもずっとのこっています。
お母さんのおなかの中からでてくると、もう必要なくなるため、へそのおはきりはなされますが、きりはなしたあとであるへそは、おとなになってもずっとのこっています。
 動物の中でも、お母さんのおなかの中でそだつほ乳類にはへそがあり、たまごからうまれる鳥やは虫類などにはありません。
動物の中でも、お母さんのおなかの中でそだつほ乳類にはへそがあり、たまごからうまれる鳥やは虫類などにはありません。
 おなかの赤ちゃんには、へそのおをとおして、酸素や栄養がおくられている。
おなかの赤ちゃんには、へそのおをとおして、酸素や栄養がおくられている。
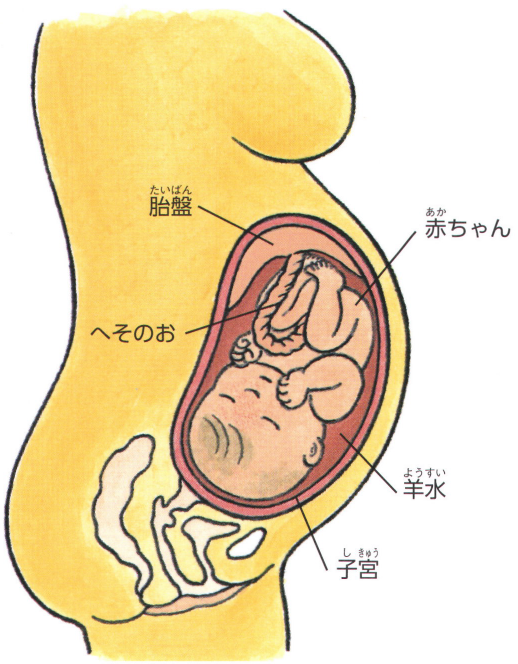

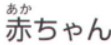
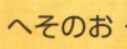


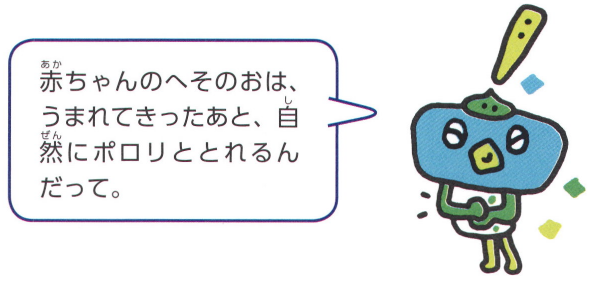
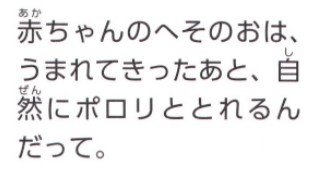
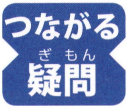 おなかの中で、赤ちゃんはどんなふうにすごすの?
おなかの中で、赤ちゃんはどんなふうにすごすの?
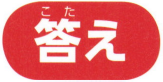 およそ10か月かけて成長していきます
およそ10か月かけて成長していきます
 へそのおからおくられてくる酸素や栄養によって、赤ちゃんは、体の中の組織がつくられ、成長していきます。
へそのおからおくられてくる酸素や栄養によって、赤ちゃんは、体の中の組織がつくられ、成長していきます。
人の赤ちゃんは、うまれてくるまでに、およそ10か月、お母さんのおなかの中ですごします。
6か月ごろから、明るさの変化をかんじたり、お母さんの声などに反応するようになります。
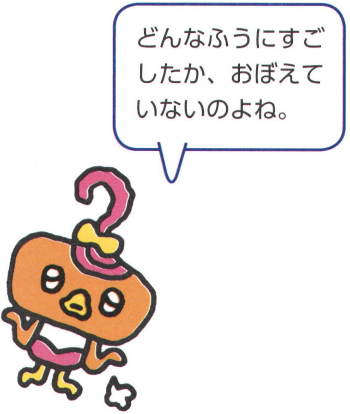
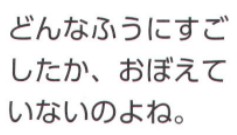
| 1か月
| 赤ちゃんは数mmしかない。
体重は1gほど。
まだ人の形になっていない。
|
|---|
| 5~7か月
| 大きさ30cmくらいに成長。
体重は、およそ600g。
爪、髪の毛、まつ毛、うぶ毛などがはえはじめる。
内臓や聴覚が発達する。
足でけったり、くるりとまわったり、うごきが活発になる。
|
|---|
| 10か月
| 身長はおよそ50cm、体重3000g前後。
へそのおの長さは、なんと、およそ50cmに。
頭を下にし、あまりうごかなくなる。
うまれる準備ができている。
|
|---|
102
どうしてかぜをひくの?
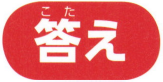 体にはいったウイルスがどんどんふえて、体を攻撃するから
体にはいったウイルスがどんどんふえて、体を攻撃するから
 息をするとき、空気と一緒に体にウイルスがはいってくることがあります。わたしたちの体には抵抗力があり、調子よくうごいているときは、少しくらいウイルスがはいってきても、退治することができます。
息をするとき、空気と一緒に体にウイルスがはいってくることがあります。わたしたちの体には抵抗力があり、調子よくうごいているときは、少しくらいウイルスがはいってきても、退治することができます。
ところが、体がつかれているとき、抵抗力が弱まっているときには、はいってきたウイルスはどんどんふえて、体を攻撃してきます。この状態を、わたしたちは「かぜをひいた」といっています。
 かぜをひくと、せきやくしゃみ、鼻水がでたり、熱がでたりしますね。これは、はいってきたウイルスをおいだしたり、退治しようとして、一生懸命、体がたたかっている証拠なのです。
かぜをひくと、せきやくしゃみ、鼻水がでたり、熱がでたりしますね。これは、はいってきたウイルスをおいだしたり、退治しようとして、一生懸命、体がたたかっている証拠なのです。
 せきやくしゃみは、鼻やのどの中のウイルスに刺激されて、おいだそうとする反応。
せきやくしゃみは、鼻やのどの中のウイルスに刺激されて、おいだそうとする反応。
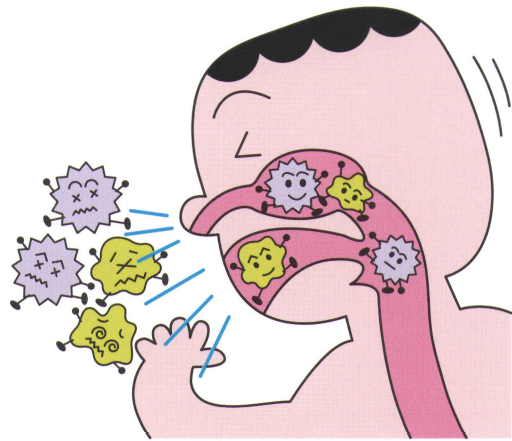
 かぜのいろいろな症状
かぜのいろいろな症状

体にウイルスがはいると、反応して体温があがる。白血球がウイルスとたたかっている。

鼻にくっついたウイルスを、あらいながしておいだそうとする。

鼻やのどにくっついたウイルスをふきとばして、体の外においだそうとする。

ウイルスがのどや気管支にはいって炎症をおこし、粘液がたくさんでる。
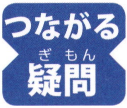 動物はかぜをひかないの?
動物はかぜをひかないの?
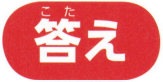 動物もかぜをひくことがあります
動物もかぜをひくことがあります
 動物もかぜをひくことがあります。とくに、チンパンジーやオランウータン、ゴリラなど、人とよくにた動物のかぜは、鼻水がでたり、呼吸があらくなったりするなど、かぜの症状も人とよくにています。
動物もかぜをひくことがあります。とくに、チンパンジーやオランウータン、ゴリラなど、人とよくにた動物のかぜは、鼻水がでたり、呼吸があらくなったりするなど、かぜの症状も人とよくにています。
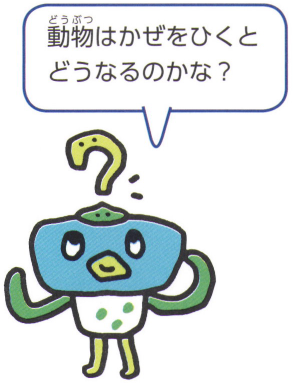
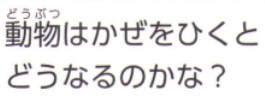
 チンパンジー
チンパンジー
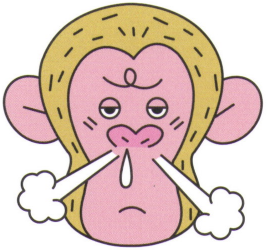
 人と同じように、鼻水がでたり、息があらくなったりする。
人と同じように、鼻水がでたり、息があらくなったりする。
 鳥
鳥
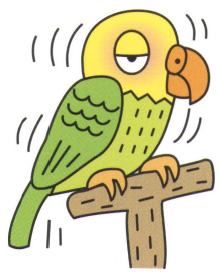
 バランスがとれなくなってふらつく。えさをたべなくなる。
バランスがとれなくなってふらつく。えさをたべなくなる。
 イヌ
イヌ
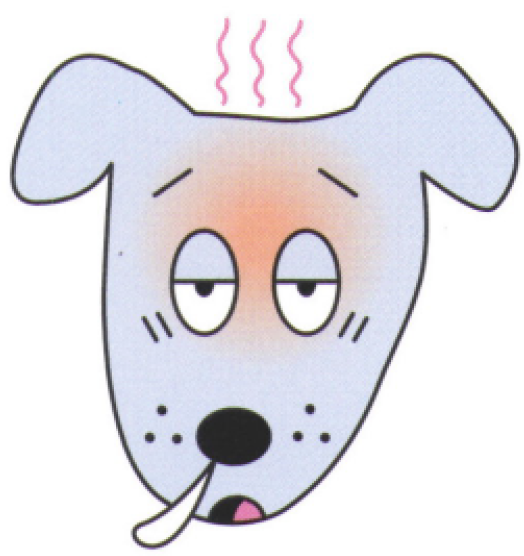
 えさをたべない。熱がでる、鼻水がでる。
えさをたべない。熱がでる、鼻水がでる。
 ネコ
ネコ
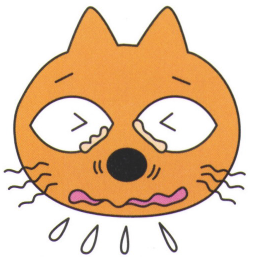
 目やにや涙がたまる、くしゃみをする。
目やにや涙がたまる、くしゃみをする。
103
予防接種って、なぜするの?
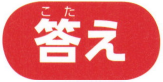 病気のもとになるウイルスや細菌をみわけて退治するため
病気のもとになるウイルスや細菌をみわけて退治するため
 わたしたちの血の中の白血球という細胞は、体の中にはいってきたウイルスや細菌、体に害のある物質をのみこみ、たべてくれるはたらきがあります。また、それらに対抗する物質である「抗体」をつくります。
わたしたちの血の中の白血球という細胞は、体の中にはいってきたウイルスや細菌、体に害のある物質をのみこみ、たべてくれるはたらきがあります。また、それらに対抗する物質である「抗体」をつくります。
抗体は、ウイルスや細菌など、一度たたかった相手をおぼえていて、同じ敵があらわれると、簡単に退治してくれます。これが「免疫」というしくみです。
 予防接種のワクチンは、病気のもとになるウイルスや細菌といった病原菌の力を弱めたものでできています。注射すると、症状はださずに、その病気に対する抗体をつくります。
予防接種のワクチンは、病気のもとになるウイルスや細菌といった病原菌の力を弱めたものでできています。注射すると、症状はださずに、その病気に対する抗体をつくります。
予防接種は、あらかじめインフルエンザやはしかなど、かかってしまうと症状が重くなる病気に対する免疫をつけて、病気を予防したり、かかっても症状が重くならないようにするのが目的です。
 血管の中をながれる白血球と赤血球。
血管の中をながれる白血球と赤血球。
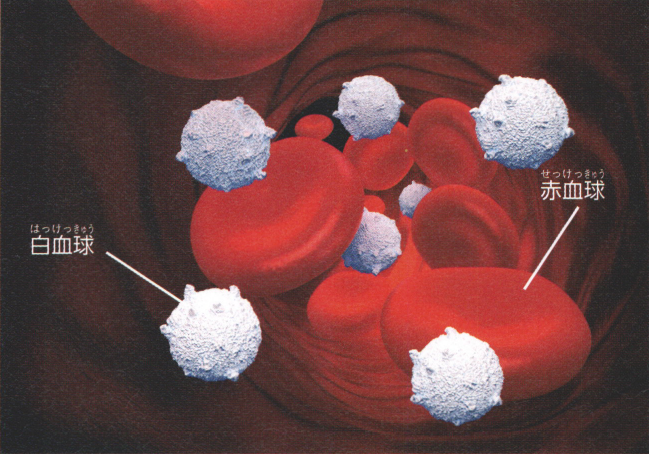


 白血球は細菌をとりかこむように形をかえ、中にとりこんでたべてしまう。
白血球は細菌をとりかこむように形をかえ、中にとりこんでたべてしまう。
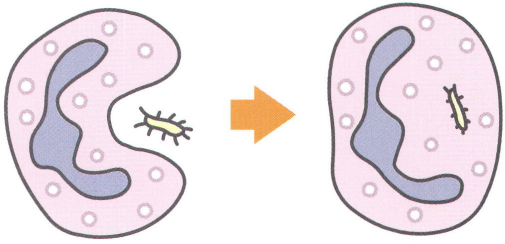
104
血液型が4種類あるのはなぜ?
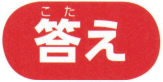 血液の中にあるたんぱく質の種類でわけられます
血液の中にあるたんぱく質の種類でわけられます
 血液の中には、いろいろなたんぱく質があって、その種類によっていくつかの血液型にわけられます。代表的なものはABO式で、A型、B型、O型、AB型の4つです。
血液の中には、いろいろなたんぱく質があって、その種類によっていくつかの血液型にわけられます。代表的なものはABO式で、A型、B型、O型、AB型の4つです。
この4つの型は、下の表のようにAとBとOの3つの遺伝子のくみあわせできまります。
 血液型は両親からうけつぐ遺伝子によってきまります。A型(AO)とB型(BO)の親の場合、下の図のように、親からOとOの遺伝子をうけついで、O型の子どもがうまれる可能性があります。
血液型は両親からうけつぐ遺伝子によってきまります。A型(AO)とB型(BO)の親の場合、下の図のように、親からOとOの遺伝子をうけついで、O型の子どもがうまれる可能性があります。
 血液型と遺伝子のくみあわせ
血液型と遺伝子のくみあわせ
| 血液型
| 遺伝子
|
|---|
| A型
| AAまたはAO
|
| B型
| BBまたはBO
|
| AB型
| AB
|
| O型
| OO
|
 A型の父(または母)とB型の母(または父)から、うけつぐ遺伝子のくみあわせによって、うまれてくる子どもは、4種類すべての血液型になる可能性がある。
A型の父(または母)とB型の母(または父)から、うけつぐ遺伝子のくみあわせによって、うまれてくる子どもは、4種類すべての血液型になる可能性がある。
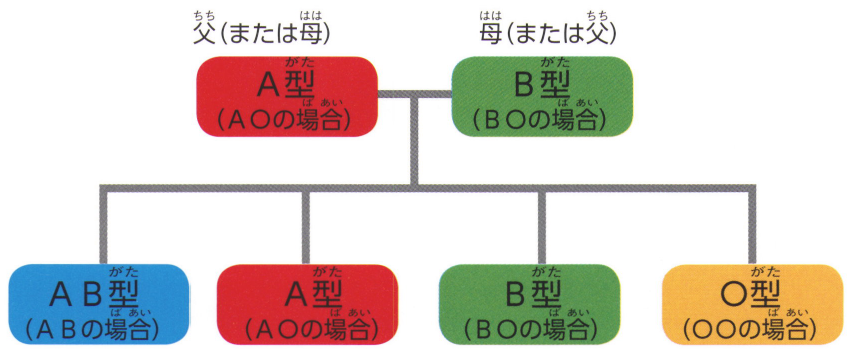
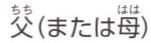
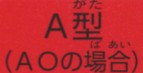
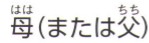
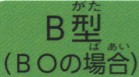
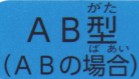
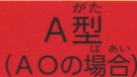
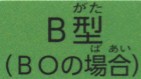
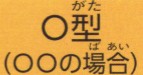
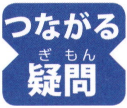 どうして血液型をしらべるの?
どうして血液型をしらべるの?
 血液型のあわない血液は輸血できないから
血液型のあわない血液は輸血できないから
 けがや手術などで大量の血液をうしなうと、命の危険があります。そのとき、ほかの人の血液を体にいれておぎなうことを「輸血」といいます。
けがや手術などで大量の血液をうしなうと、命の危険があります。そのとき、ほかの人の血液を体にいれておぎなうことを「輸血」といいます。
輸血するときに、ことなる血液型の血液を輸血すると血がかたまってしまうため、同じ型の血液をえらばなくてはなりません。
ですから、あらかじめ自分の血液型をしっておくことが必要です。また、輸血が必要な人に血をわけてあげる献血のときにも、それぞれの血液型ごとに血をとることになります。
 日本人のABO式血液型の割合
日本人のABO式血液型の割合
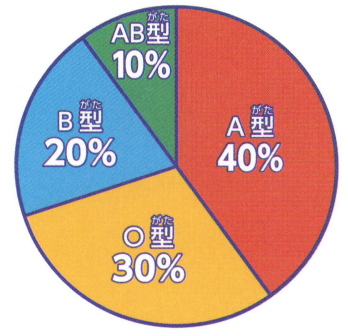




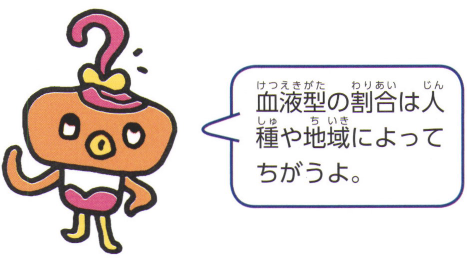
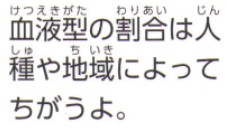
105
血がでても自然にとまるのはなぜ?
 血小板がはたらいて、傷口をふさいでくれるから
血小板がはたらいて、傷口をふさいでくれるから
 血の中にふくまれる血小板はとても小さく、1滴の血の中におよそ25万こもあるといわれています。けがなどで血がでると、血小板は血しょうや赤血球と力をあわせて血をかため、傷口をふさいでくれます。こうして血は、体の外にながれでなくなるのです。
血の中にふくまれる血小板はとても小さく、1滴の血の中におよそ25万こもあるといわれています。けがなどで血がでると、血小板は血しょうや赤血球と力をあわせて血をかため、傷口をふさいでくれます。こうして血は、体の外にながれでなくなるのです。
 血がかわくと、かさぶたになります。かさぶたというのは、傷口をとじる茶色の皮のことです。傷がなおっていくと、かさぶたは自然にはがれおちます。
血がかわくと、かさぶたになります。かさぶたというのは、傷口をとじる茶色の皮のことです。傷がなおっていくと、かさぶたは自然にはがれおちます。
 また、血小板より大きな白血球は、血管の中を、形をかえながら移動します。体に傷ができると、傷口のちかくにたくさんあつまって、病気の原因になるウイルスや細菌をのみこみ、感染をふせぐはたらきをします。白血球がのみこんだウイルスや細菌は、肝臓などにはこばれてこわされます。
また、血小板より大きな白血球は、血管の中を、形をかえながら移動します。体に傷ができると、傷口のちかくにたくさんあつまって、病気の原因になるウイルスや細菌をのみこみ、感染をふせぐはたらきをします。白血球がのみこんだウイルスや細菌は、肝臓などにはこばれてこわされます。
白血球には色がなく、その数は、血1滴の中に、5000~1万こふくまれるといわれています。
106
どうして頭には髪の毛がはえているの?
 外からくる刺激から頭をまもるため
外からくる刺激から頭をまもるため
 頭は、体にさまざまな命令をだす脳がはいっている、大切なところです。
頭は、体にさまざまな命令をだす脳がはいっている、大切なところです。
頭をぶつけたときには、髪の毛がクッションの役割をして、ショックをやわらげてくれます。また、あついときにはあつさから、さむいときにはさむさから頭をまもってくれているのです。
また、頭が汗をかいても、髪の毛が水分を吸収しすばやく蒸発させることで、目に汗がはいるのをふせいでいます。
ほかにも、体の中の毒素を髪の毛の中にとじこめて、体の外にだす役割もあります。
 髪の毛の断面。根元の毛球で毛がつくられ、のびていく。
髪の毛の断面。根元の毛球で毛がつくられ、のびていく。
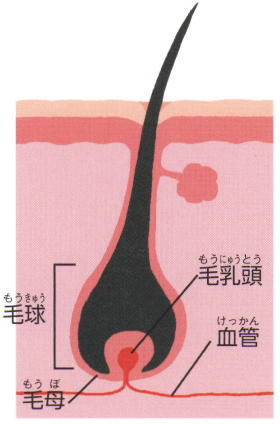




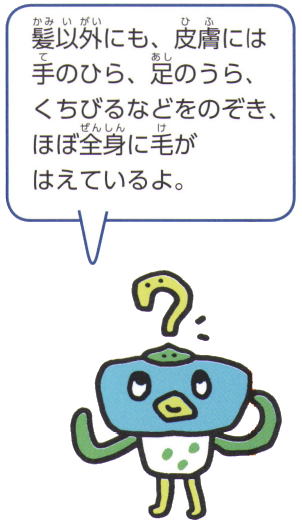
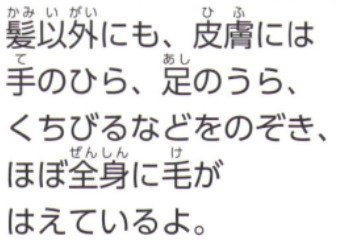
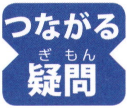 どうして髪の毛はのびるの?
どうして髪の毛はのびるの?
 根元の毛球で新しい髪の毛がつくられ、おしだされるから
根元の毛球で新しい髪の毛がつくられ、おしだされるから
 髪の毛は皮膚の角質が変形してできたものです。毛が皮膚にうまった部分を毛根といい、その根元のふくらんだ部分を毛球といいます。毛球で新しい髪の毛がつくられ、順番に上におしだされるので、髪の毛はどんどんのびていくのです。
髪の毛は皮膚の角質が変形してできたものです。毛が皮膚にうまった部分を毛根といい、その根元のふくらんだ部分を毛球といいます。毛球で新しい髪の毛がつくられ、順番に上におしだされるので、髪の毛はどんどんのびていくのです。
 髪の毛は、1日に0.2~0.5
くらいのびます。はえかわるスピードは、気温が高くなる夏は速く、さむい冬はおそくなるといわれています。
髪の毛は、1日に0.2~0.5
くらいのびます。はえかわるスピードは、気温が高くなる夏は速く、さむい冬はおそくなるといわれています。
 1本の毛がぬけているときにはほかの毛が成長しているというように、周期がずれているため、一度にぬけおちることはありません。日本人の髪の毛の本数は平均10万本で、1日に50~100本ほどが順番にぬけ、はえていきます。
1本の毛がぬけているときにはほかの毛が成長しているというように、周期がずれているため、一度にぬけおちることはありません。日本人の髪の毛の本数は平均10万本で、1日に50~100本ほどが順番にぬけ、はえていきます。
 髪の毛の断面と、成長期から脱毛期まで
髪の毛の断面と、成長期から脱毛期まで
成長期
毛母細胞がつぎつぎに分裂して、成長をつづける。(2~6年)
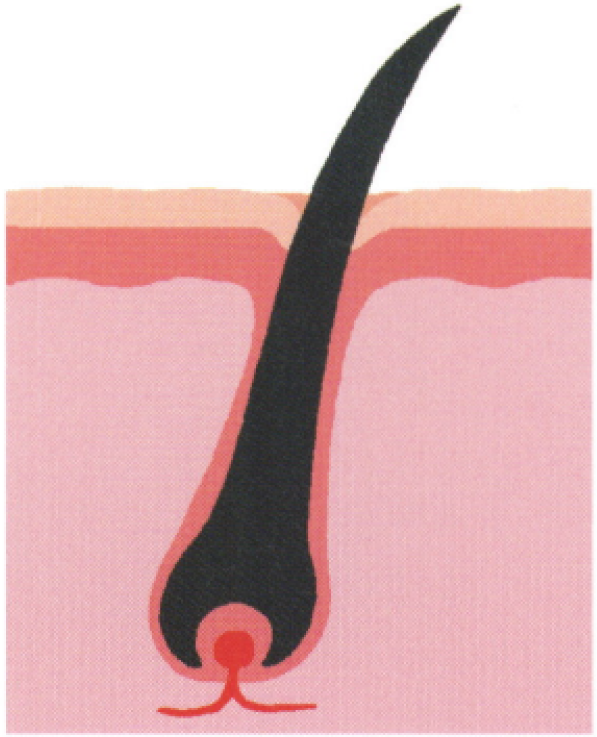
退行期
毛母細胞の分裂がとまり、成長がとまる。(2~3週間)
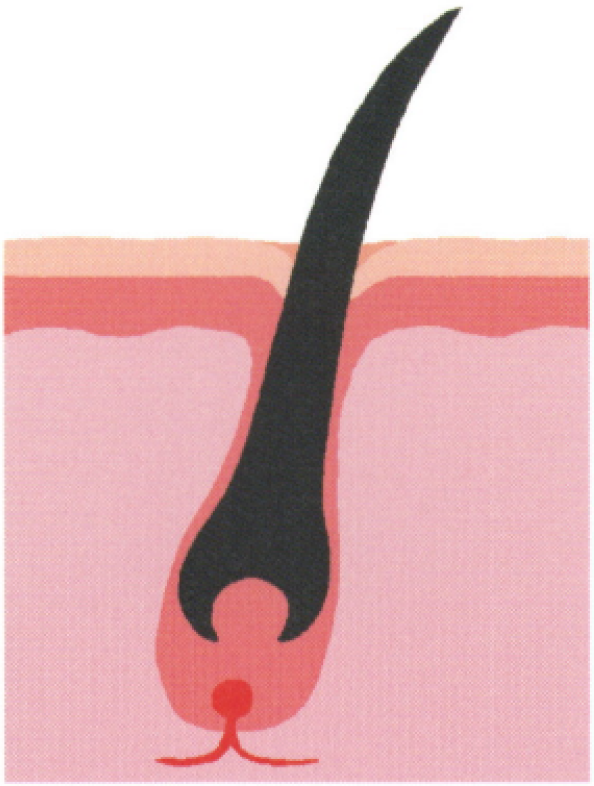
休止期
毛母とはなれて毛乳頭があがる。(3~4か月)
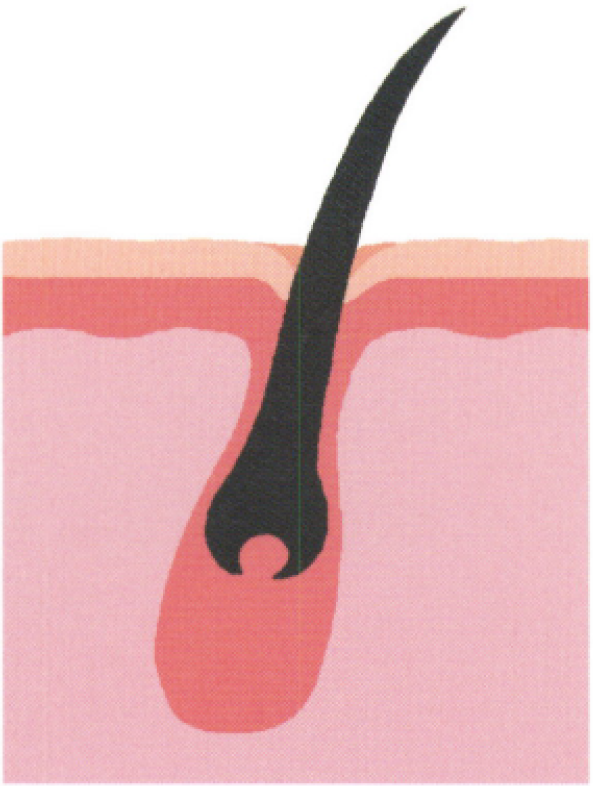
脱毛期
髪の毛がぬける。4~6か月後には、新しい髪の毛が皮膚の表面にでてくる。
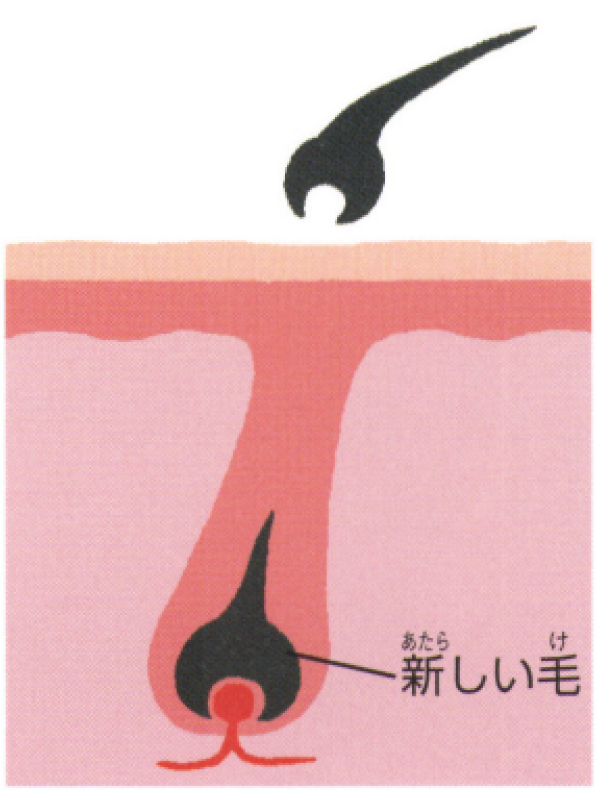
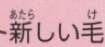
107
しゃっくりがでるのはなぜ?
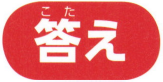 横隔膜がけいれんして、空気がいつもより速くはいってくるから
横隔膜がけいれんして、空気がいつもより速くはいってくるから
 わたしたちが息をするとき、大事な役割をになっているのが、肺の下にある横隔膜です。横隔膜というのは、胸とおなかをしきる筋肉です。
わたしたちが息をするとき、大事な役割をになっているのが、肺の下にある横隔膜です。横隔膜というのは、胸とおなかをしきる筋肉です。
深呼吸すると、胸が大きくふくらみますね。このとき、体の中でふくらんでいるのが肺です。肺に息をいれるときには、横隔膜はちぢみ、ひきさげられるようにうごいて、肺がふくらむのをたすけます。息をはきだすときには横隔膜はゆるんで上にあがり、肺はしぼみます。
息をすったりはいたりするたびに、横隔膜はさがったりあがったりして、肺をふくらませたりしぼませたりしているのです。
 ふだんは規則正しくうごいている横隔膜ですが、何かのきっかけでけいれんをおこすことがあります。けいれんした瞬間に息をすってしまうと、空気がいつもより速いスピードではいってくるため、のどの声帯がとじて、空気の流れをとめようとします。このときにたてる「ヒック」という音が、しゃっくりなのです。
ふだんは規則正しくうごいている横隔膜ですが、何かのきっかけでけいれんをおこすことがあります。けいれんした瞬間に息をすってしまうと、空気がいつもより速いスピードではいってくるため、のどの声帯がとじて、空気の流れをとめようとします。このときにたてる「ヒック」という音が、しゃっくりなのです。
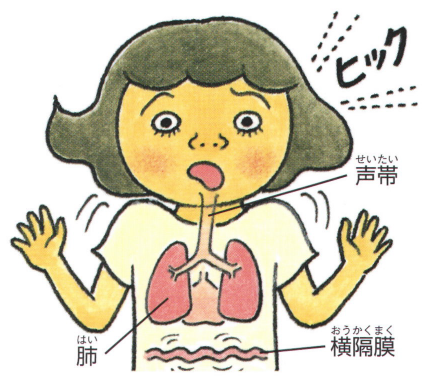


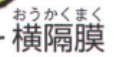
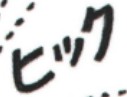
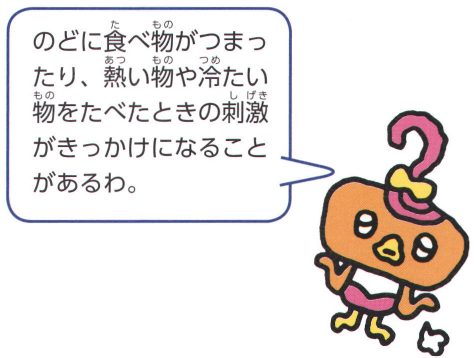
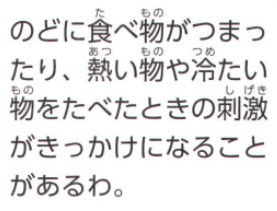
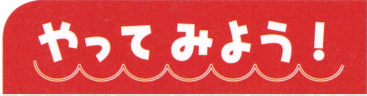 しゃっくりは、どうしたらとめられる?
しゃっくりは、どうしたらとめられる?
しゃっくりには、いろいろなとめ方があるといわれています。しゃっくりがでたら、ためしてみましょう。

 息が一瞬とまり、水をのむことに気持ちが集中するので、横隔膜のけいれんがおさまるといわれている。
息が一瞬とまり、水をのむことに気持ちが集中するので、横隔膜のけいれんがおさまるといわれている。
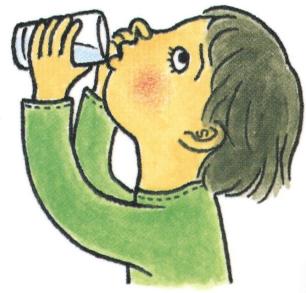
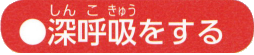
 空気のはいってくるスピードをおそくすることで、横隔膜のけいれんがおちつくといわれている。
空気のはいってくるスピードをおそくすることで、横隔膜のけいれんがおちつくといわれている。


 おどろくと一瞬呼吸がとまるので、その拍子に横隔膜のけいれんがとまることもある。
おどろくと一瞬呼吸がとまるので、その拍子に横隔膜のけいれんがとまることもある。



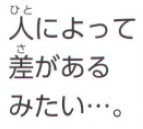
108
虫歯はどうしてできるの?
 食べ物のかすに虫歯菌がつき、歯をとかすから
食べ物のかすに虫歯菌がつき、歯をとかすから
 虫歯菌が歯をとかすと、虫歯ができます。虫歯菌は、食べ物ののこりかすなどがあると、その中にふくまれる糖分をえさにして、のこりかすを酸にかえます。歯の外側のエナメル質はカルシウムなどでできていて、とてもかたいのですが、酸でとけてしまう性質があります。
虫歯菌が歯をとかすと、虫歯ができます。虫歯菌は、食べ物ののこりかすなどがあると、その中にふくまれる糖分をえさにして、のこりかすを酸にかえます。歯の外側のエナメル質はカルシウムなどでできていて、とてもかたいのですが、酸でとけてしまう性質があります。
 エナメル質の内側は、象牙質という少しやわらかい部分です。虫歯がすすむと、歯の外側のエナメル質がとけて象牙質がむきだしになったり、さらにとけて歯の形がなくなっていったりします。
エナメル質の内側は、象牙質という少しやわらかい部分です。虫歯がすすむと、歯の外側のエナメル質がとけて象牙質がむきだしになったり、さらにとけて歯の形がなくなっていったりします。
 砂糖のはいったあまい物をたべた後など、口の中をそのままにしておくと、たいへん虫歯ができやすくなります。おやつや食事の後は、歯をみがいたり口をゆすいだりして、食べ物のかすを口の中にのこさないようにしましょう。
砂糖のはいったあまい物をたべた後など、口の中をそのままにしておくと、たいへん虫歯ができやすくなります。おやつや食事の後は、歯をみがいたり口をゆすいだりして、食べ物のかすを口の中にのこさないようにしましょう。
 食べ物ののこりかすが歯にたまる。
食べ物ののこりかすが歯にたまる。
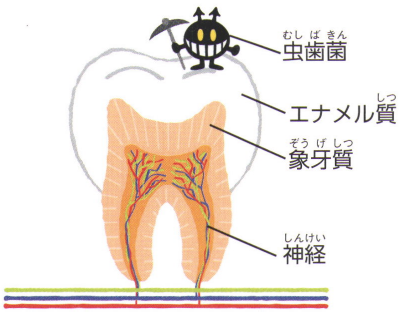

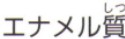


 虫歯菌が食べかすをえさにして酸をだし、エナメル質をとかしていく。
虫歯菌が食べかすをえさにして酸をだし、エナメル質をとかしていく。
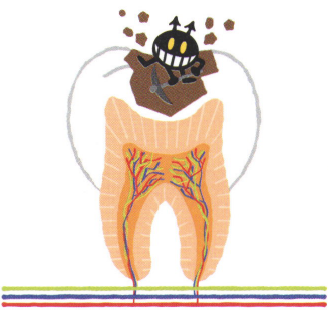
 象牙質まで歯をとかし、虫歯がすすむと、神経を刺激し、水がしみたり、いたみがでたりする。
象牙質まで歯をとかし、虫歯がすすむと、神経を刺激し、水がしみたり、いたみがでたりする。
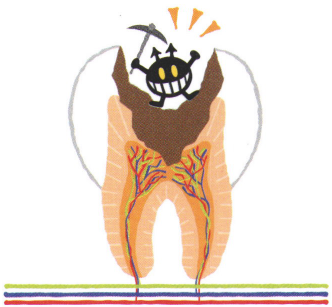
109
爪の根元にある白い部分は何?
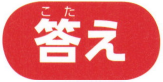 新しくできたばかりの爪です
新しくできたばかりの爪です
 爪のつけ根の白いところは、新しくできたばかりの爪です。半月のような形をしていることから、「爪半月」とよばれています。
爪のつけ根の白いところは、新しくできたばかりの爪です。半月のような形をしていることから、「爪半月」とよばれています。
皮膚におおわれてかくれている部分にも爪はあり、皮膚でおおいかくしている爪を「爪母」といいます。
新しい爪は爪母でつくられ、指先にむかって、古い爪をおしあげるようにして、毎日少しずつのびます。1か月におよそ3mmほどのびていきます。そして、3か月から半年ではえかわります。
 「爪半月」はできたばかりの新しい爪。
「爪半月」はできたばかりの新しい爪。
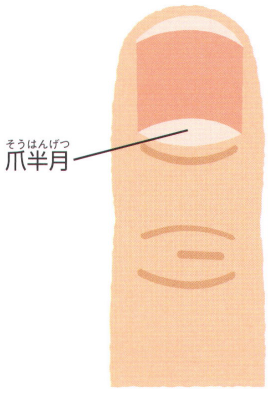

 新しい爪がつくられるところを「爪母」とよぶ。爪は、指先にむかってのびる。
新しい爪がつくられるところを「爪母」とよぶ。爪は、指先にむかってのびる。
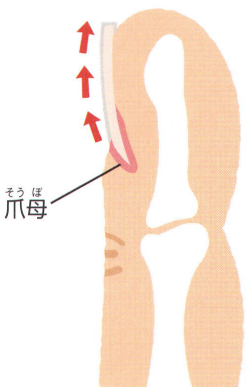

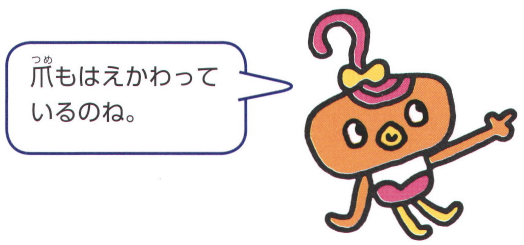
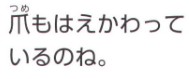
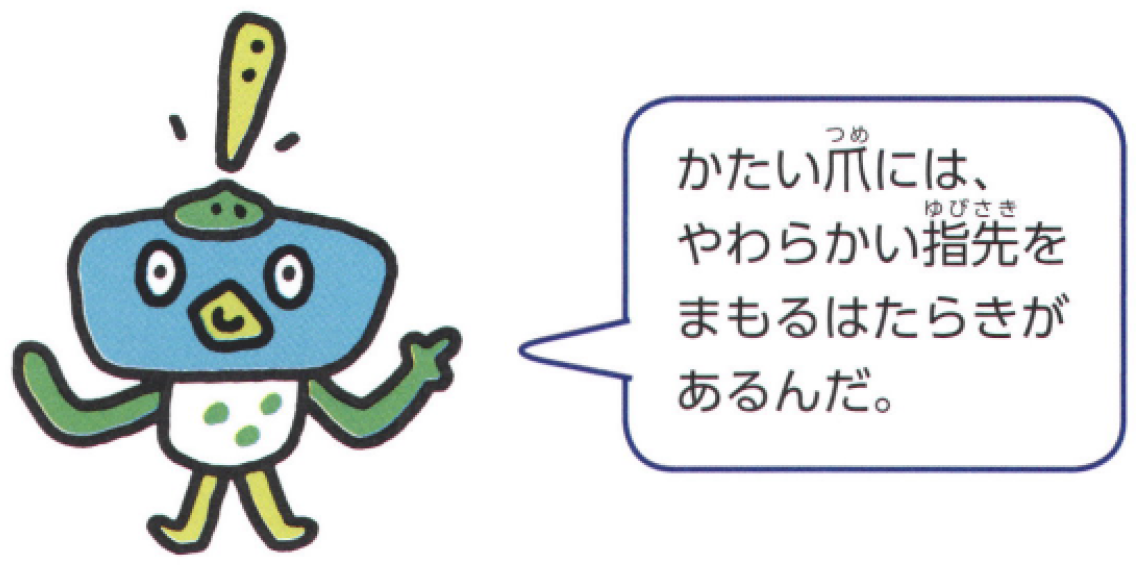
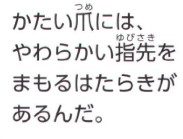
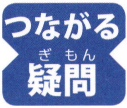 爪をきってもいたくないのはなぜ?
爪をきってもいたくないのはなぜ?
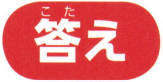 爪には、神経も血管もとおっていないから
爪には、神経も血管もとおっていないから
 爪は毛と同じように、皮膚の表面の角質層が変化してできたもので、もともとは皮膚の一部です。
爪は毛と同じように、皮膚の表面の角質層が変化してできたもので、もともとは皮膚の一部です。
 皮膚の角質層には、血管や神経はとおっていません。同じように、爪の中にも血管や神経はとおっていません。
皮膚の角質層には、血管や神経はとおっていません。同じように、爪の中にも血管や神経はとおっていません。
だから、爪をきっても、血はでず、いたくもないのです。
 ウマのひづめは爪が発達したもの
ウマのひづめは爪が発達したもの
ウマのひづめは、爪が発達したものです。
足先をかたいひづめにまもられているウマは、ちょうど人がはしっているときと同じように、ふだんからかかとをうかせた状態でたっています。
敵である肉食動物から身をまもるため、すばやくはしりだせるよう、進化したのでしょう。
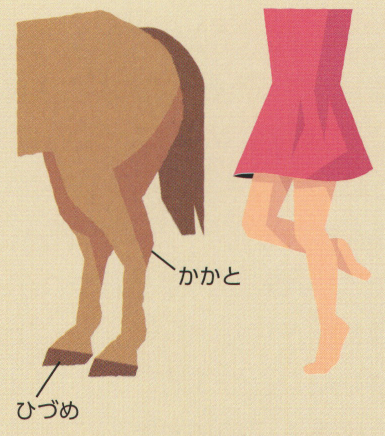


110
すっぱい物をみるとつばがでるのはなぜ?
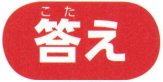 以前の経験から、脳が自然に反応するから
以前の経験から、脳が自然に反応するから
 つばは、左右の耳下腺、顎下腺、舌下腺という6か所の大きな唾液腺のほか、舌やほほの内側にたくさんある、小さな唾液腺からだされます。
つばは、左右の耳下腺、顎下腺、舌下腺という6か所の大きな唾液腺のほか、舌やほほの内側にたくさんある、小さな唾液腺からだされます。
 レモンやうめぼしなどのすっぱい物をみたり、頭におもいうかべただけでも、口の中につばがわいてきますね。
レモンやうめぼしなどのすっぱい物をみたり、頭におもいうかべただけでも、口の中につばがわいてきますね。
これは、わたしたちがすっぱい物を何度もたべる経験をしたことで、すっぱい物に対して、「すっぱいぞ。つばをたくさんだしてうすめろ」と、素早く脳が命令するためです。
 このように、あることをくり返し経験しているうちに、脳が自然に反応するようになることを、「条件反射」といいます。
このように、あることをくり返し経験しているうちに、脳が自然に反応するようになることを、「条件反射」といいます。
 すっぱいものをみると、脳が「つばをだしなさい」と命令する。
すっぱいものをみると、脳が「つばをだしなさい」と命令する。
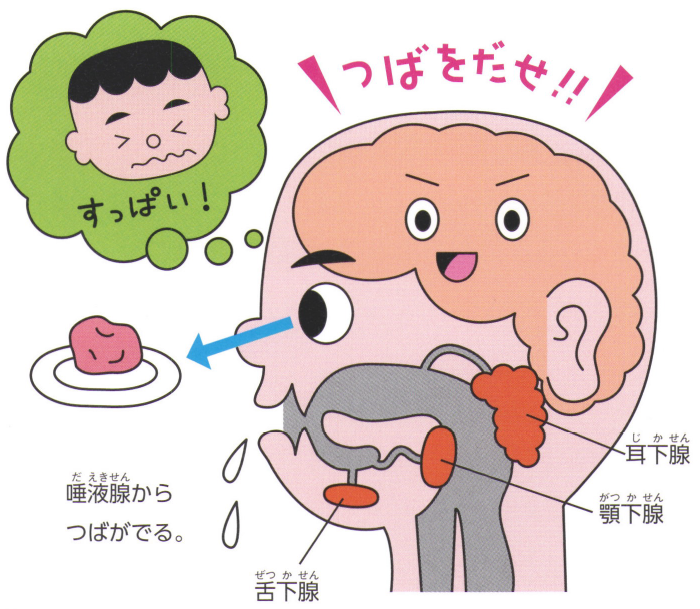
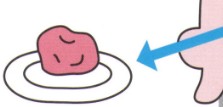
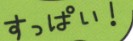
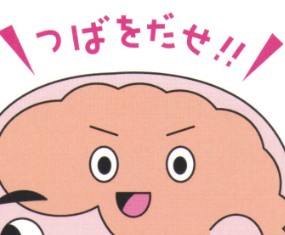



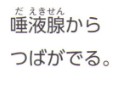

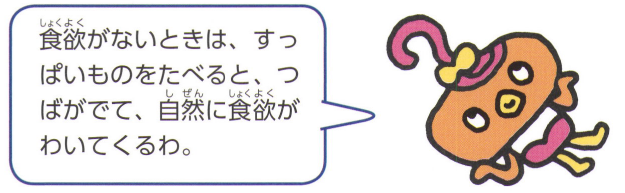
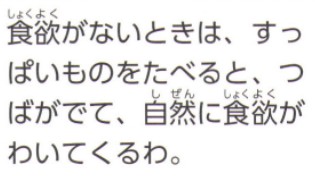
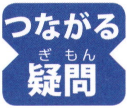 つばはどんなはたらきをしているの?
つばはどんなはたらきをしているの?
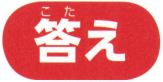 食べ物の消化をたすけ、口の中を清潔にします
食べ物の消化をたすけ、口の中を清潔にします
 つばは、食べ物の消化をたすけるはたらきをしています。もしも、つばがでなくなったら、口の中にいれた食べ物をやわらかくすることができず、うまくのみこめなくなってしまうでしょう。
つばは、食べ物の消化をたすけるはたらきをしています。もしも、つばがでなくなったら、口の中にいれた食べ物をやわらかくすることができず、うまくのみこめなくなってしまうでしょう。
ほかにも、食べ物の味をひきだしておいしくしたり、食品添加物などの中にふくまれる発がん物質の毒消しをする役割があります。
 また、つばには、虫歯菌やウイルスなどを退治し、口の中を清潔にたもつはたらきもあります。食べ物をよくかんでつばをたくさんだすことは、虫歯やかぜなどの予防にもなるわけです。
また、つばには、虫歯菌やウイルスなどを退治し、口の中を清潔にたもつはたらきもあります。食べ物をよくかんでつばをたくさんだすことは、虫歯やかぜなどの予防にもなるわけです。
 このほか、口の中が乾燥しないように、しめらせるはたらきもあります。口がかわくと、わたしたちはうまくはなすことができなくなってしまいます。
このほか、口の中が乾燥しないように、しめらせるはたらきもあります。口がかわくと、わたしたちはうまくはなすことができなくなってしまいます。
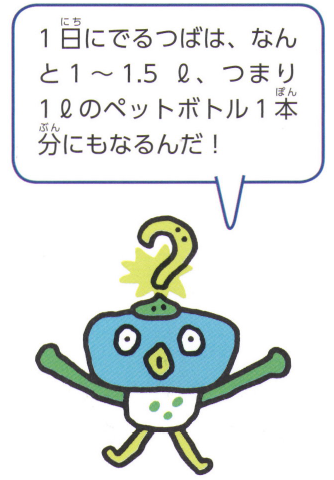
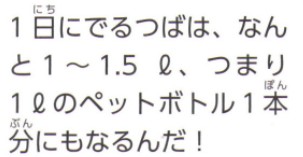
111
ぐるぐるまわると目がまわるのはなぜ?
 半規管からおくられつづける信号に、脳が混乱するため
半規管からおくられつづける信号に、脳が混乱するため
 体がまわっているとき、耳のおくの半規管の中では、リンパ液がながれて、脳に信号をおくっています。人の脳は、この信号をもとにして、体のバランスをたもっています。
体がまわっているとき、耳のおくの半規管の中では、リンパ液がながれて、脳に信号をおくっています。人の脳は、この信号をもとにして、体のバランスをたもっています。
 回転した後、体がとまっても半規管の中のリンパ液は、すぐにはとまれずに、しばらくながれつづけます。
回転した後、体がとまっても半規管の中のリンパ液は、すぐにはとまれずに、しばらくながれつづけます。
回転がとまっているのに、半規管から「体がまわっています」という信号がおくられつづけるため、脳は混乱し、バランスがたもてなくなって、くらくらと目がまわるのです。
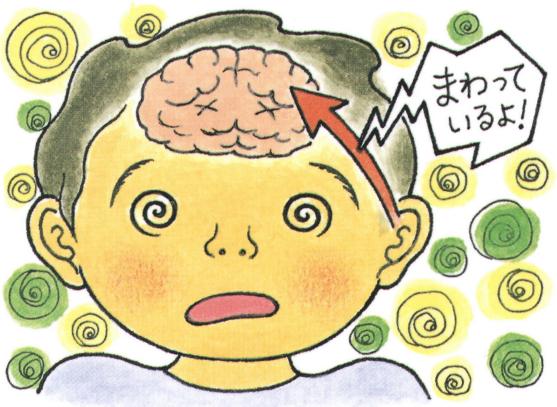

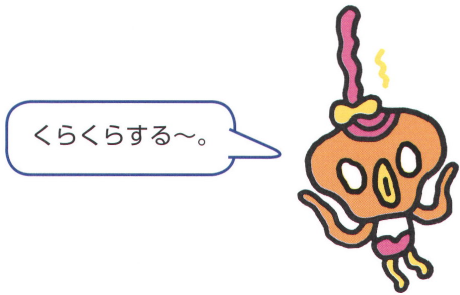
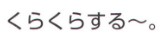
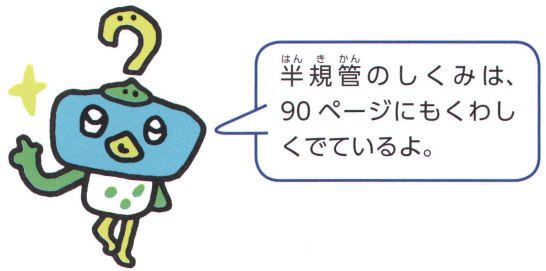
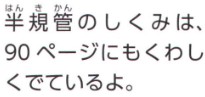
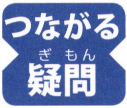 バレリーナはどうして目がまわらないの?
バレリーナはどうして目がまわらないの?
 なるべく目をうごかさないようにしているから
なるべく目をうごかさないようにしているから
 バレリーナやフィギュアスケートの選手は、くるくると回転しますが、目をまわしてふらふらになったりはしませんね。これにはひみつがあります。
バレリーナやフィギュアスケートの選手は、くるくると回転しますが、目をまわしてふらふらになったりはしませんね。これにはひみつがあります。
 回転によって頭が上下左右にうごき、半規管の中のリンパ液が混乱すると、すぐに目がまわってしまうので、できるだけリンパ液のゆれを小さくしているのです。
回転によって頭が上下左右にうごき、半規管の中のリンパ液が混乱すると、すぐに目がまわってしまうので、できるだけリンパ液のゆれを小さくしているのです。
そのため、回転するときには一点をみつめて目をうごかさず、頭の位置を一定にたもたせています。
テレビでスローモーションの映像をみると、ぎりぎりまで一点をみつめるため、体がまわるのと同時ではなく、頭は少しおくれて素早くまわっているのが、よくわかります。
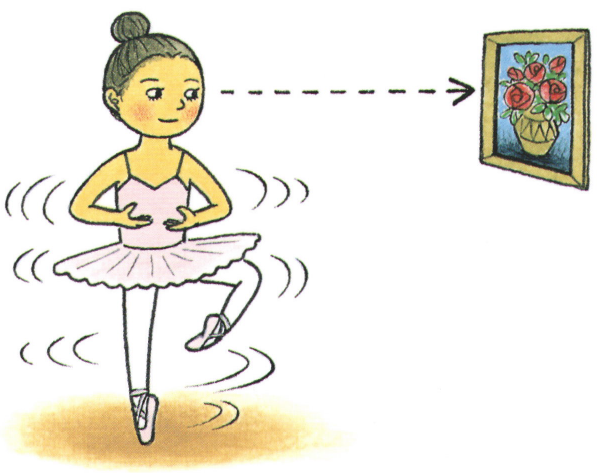
112
1日にどのくらい息をするの?
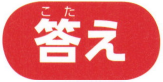 2万8800回くらい
2万8800回くらい
 小学生なら、ふつう、1日に2万8800回くらいも息をしているといわれています。
小学生なら、ふつう、1日に2万8800回くらいも息をしているといわれています。
息をすることによって鼻や口からすいこんだ空気は、気管支をとおって、胸の左右にある2つの肺におくられます。
 肺は、空気からとりいれた酸素を血管におくりこみ、全身の細胞にとどけます。そして、体の中をめぐってきた血の中から、体に必要のない二酸化炭素をうけとって、空気中にはきだす役割をしています。
肺は、空気からとりいれた酸素を血管におくりこみ、全身の細胞にとどけます。そして、体の中をめぐってきた血の中から、体に必要のない二酸化炭素をうけとって、空気中にはきだす役割をしています。
 肺には筋肉はなく、心臓のように自分でのびちぢみすることができません。そのため、横隔膜や肋間筋といった、まわりの筋肉がうごいて、肺をふくらませたり、ちぢめたりして、息をするのをてつだってくれているのです。
肺には筋肉はなく、心臓のように自分でのびちぢみすることができません。そのため、横隔膜や肋間筋といった、まわりの筋肉がうごいて、肺をふくらませたり、ちぢめたりして、息をするのをてつだってくれているのです。
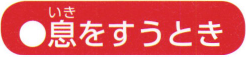
 肋間筋がちぢんだり、横隔膜がさがったりして、肺をふくらませて酸素をとりいれる。
肋間筋がちぢんだり、横隔膜がさがったりして、肺をふくらませて酸素をとりいれる。





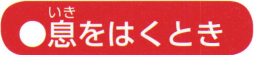
 肋間筋がゆるんだり、横隔膜があがったりして、肺をちぢめて二酸化炭素をおしだす。
肋間筋がゆるんだり、横隔膜があがったりして、肺をちぢめて二酸化炭素をおしだす。
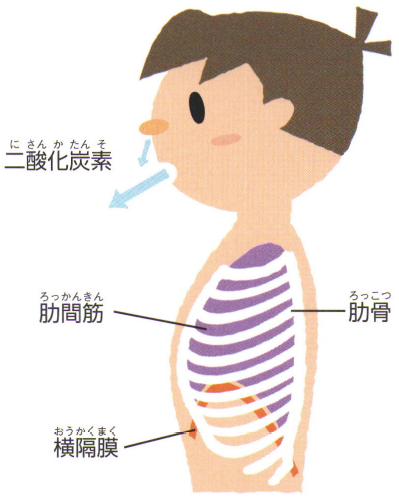
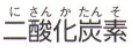



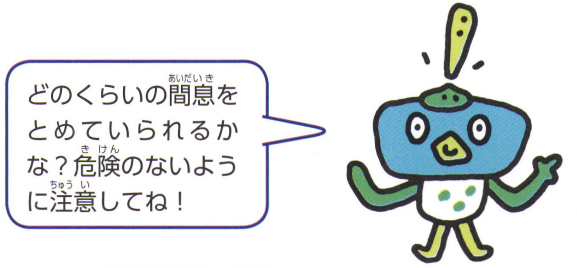
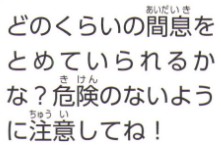
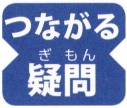 どうして息をしないといけないの?
どうして息をしないといけないの?
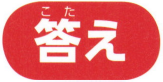 息をしないと死んでしまうから
息をしないと死んでしまうから
 人の体の中にはエネルギーをつくるしくみがありますが、その材料になる酸素は、自分ではつくることができません。
人の体の中にはエネルギーをつくるしくみがありますが、その材料になる酸素は、自分ではつくることができません。
そのため、つねに息をして、わたしたちは空気の中の酸素を体にとりいれ、体をうごかすエネルギーにしています。
 運動すると、ハアハアと息があらくなることがありますね。これは、体をうごかすとエネルギーをたくさんつかうので、呼吸の回数をふやして、たくさんの酸素を全身の細胞にとどけようとするからです。
運動すると、ハアハアと息があらくなることがありますね。これは、体をうごかすとエネルギーをたくさんつかうので、呼吸の回数をふやして、たくさんの酸素を全身の細胞にとどけようとするからです。
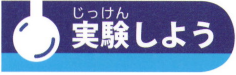 家族や友達と、くすぐり実験してみよう
家族や友達と、くすぐり実験してみよう
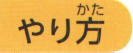
①まず、自分で自分をくすぐってみて、その感覚をおぼえておく。
②つぎに、おたがいにくすぐりあう。
 自分でくすぐるのと、人にくすぐってもらうのでは、どうちがったかな?
自分でくすぐるのと、人にくすぐってもらうのでは、どうちがったかな?
 こんなこともためしてみよう
こんなこともためしてみよう
◎「くすぐるよ~」といって手をちかづけてみよう。
◎相手に目をつむってもらい、「わきの下まであと5
、あと3
」といいながら手をちかづけてみよう。

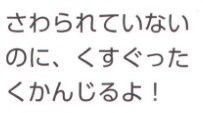
114
どうしておふろにはいるの?
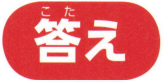 体についたよごれや、体からでるごみをあらいながし、清潔にするため
体についたよごれや、体からでるごみをあらいながし、清潔にするため
 体のあかや、頭のふけは、古くなった皮膚のかけらに、体からでる汗やあぶらがまじり、ちりなどの空気中のよごれがついてできたものです。
体のあかや、頭のふけは、古くなった皮膚のかけらに、体からでる汗やあぶらがまじり、ちりなどの空気中のよごれがついてできたものです。
わたしたちの体はつねにうまれかわっていて、いらないものをごみとしてすてることで清潔をたもっています。
 湯船にゆっくりとつかったり、頭や顔、体をあらうことは、皮膚のうまれかわりをたすけるために、とても大切です。
湯船にゆっくりとつかったり、頭や顔、体をあらうことは、皮膚のうまれかわりをたすけるために、とても大切です。
もし何日もおふろにはいらなければ、皮膚の表面がよごれでふさがり、新しい髪の毛がはえてきたり、新しい皮膚ができるのをじゃましてしまいます。細菌もそだちやすく、病気にもかかりやすくなるでしょう。
 皮膚の細胞は、つねに新しくうまれてくる。古い角質はおしだされて、あかやふけとなって、はがれおちる。
皮膚の細胞は、つねに新しくうまれてくる。古い角質はおしだされて、あかやふけとなって、はがれおちる。
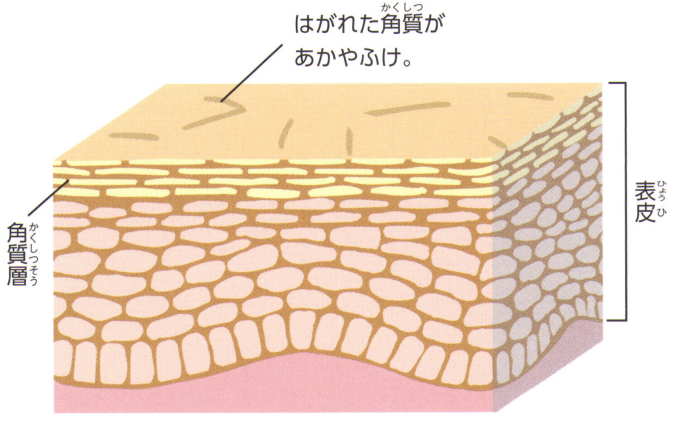
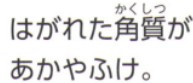


 体からでるごみをしらべよう
体からでるごみをしらべよう

あかやふけ以外にも、体からはいろいろなごみがでるよ。どんなものがあるかな?
| おしっこ
| 血液の中のいらないものをすてる。
おしっこの95%が水。
|
|---|
| うんち
| 食べ物ののこりかすや、水分、古くなった
腸のかべ、腸の中の細菌の死がいなど。
|
|---|
| 耳あか
| 耳にはいったほこりや、耳の中の
古くなった皮膚のかすがまざったもの。
|
|---|
| 鼻水
| 花粉やウイルスなどをおいだすのに
鼻からでる分泌液。
|
|---|
| 鼻くそ
| 鼻水とほこりがまざって、鼻の中で
かたまったもの。
|
|---|
| たん
| 息といっしょに体にはいってきた
ほこりやウイルス、細菌などをすてる。
|
|---|

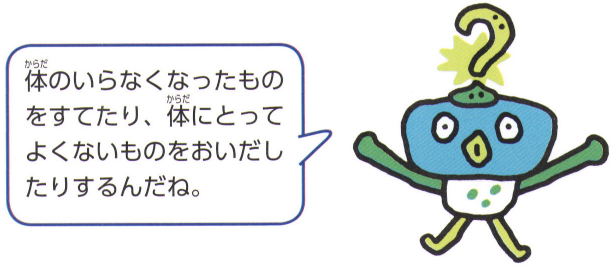
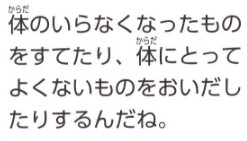
115
右利きと左利きは、いつきまるの?
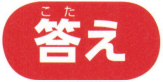 うまれる前にほぼきまっていますが、うまれてからの環境でもかわります
うまれる前にほぼきまっていますが、うまれてからの環境でもかわります
 お母さんのおなかの中の赤ちゃんのようすを超音波の画像でみると、指しゃぶりする手が、すでに右か左かきまっているといわれています。
お母さんのおなかの中の赤ちゃんのようすを超音波の画像でみると、指しゃぶりする手が、すでに右か左かきまっているといわれています。
うまれた後の環境によってもかわり、最終的に4~5さいくらいできまることが多いようです。
 右手をつかうときは、左脳で手の動きをコントロールし、左手をつかうときは右脳でコントロールします。
右手をつかうときは、左脳で手の動きをコントロールし、左手をつかうときは右脳でコントロールします。
右利きの人のほとんどは左脳で言葉をつかさどり、直感的な判断をするときは右脳をつかうというふうに、左右の脳をつかいわけています。
左利きの人の場合は、およそ2割ほどの人が、右脳に言葉をつかさどる機能がはいっているということです。
右利きと左利きでは、脳の使い方もちがうのですね。
 真上からみた大脳
真上からみた大脳
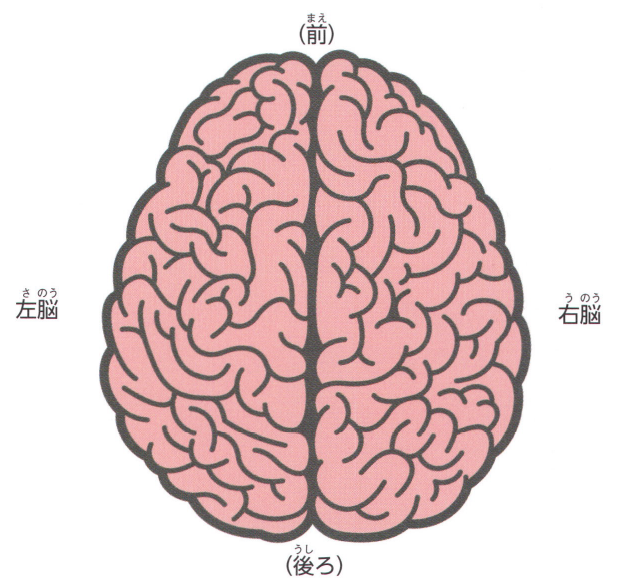




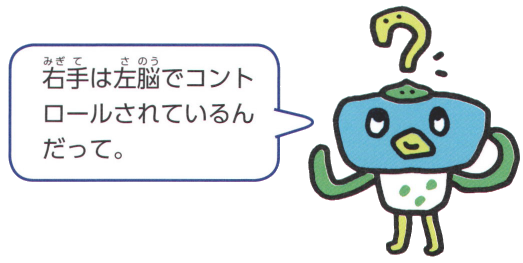
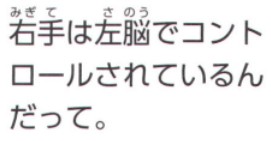
116
人は水がないといきられないの?
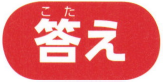 1日に3の水が必要です
1日に3の水が必要です
 おとなの体のおよそ60%、子どもはおよそ70%が水分でできています。水分をとらないでいると、体の中の水分バランスがくずれてしまうので、いきられないのです。
おとなの体のおよそ60%、子どもはおよそ70%が水分でできています。水分をとらないでいると、体の中の水分バランスがくずれてしまうので、いきられないのです。
 人は、おとなの場合で、毎日3ほどの水分を、食べ物や飲み物によって体にとりいれています。わたしたちがいきていくためには、1日に少なくとも、飲み水として、1.5の水を体にとりいれることが必要だといわれています。
人は、おとなの場合で、毎日3ほどの水分を、食べ物や飲み物によって体にとりいれています。わたしたちがいきていくためには、1日に少なくとも、飲み水として、1.5の水を体にとりいれることが必要だといわれています。
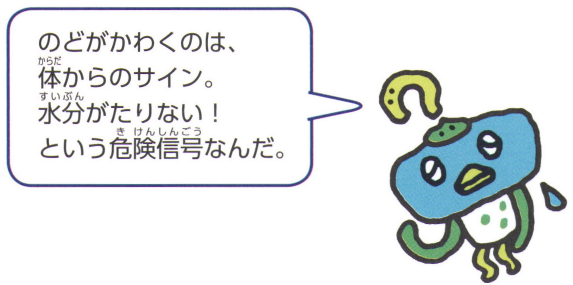
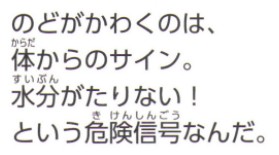
 体にふくまれる水分を計算しよう
体にふくまれる水分を計算しよう
(子どもの場合)
自分の体重
水分の量

体重30
の場合
体にふくまれる水分は、およそ
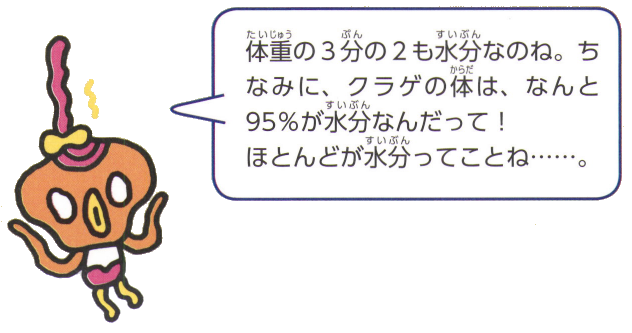
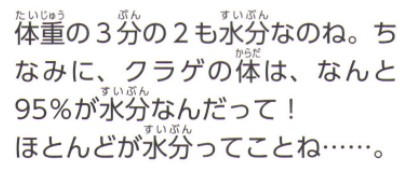
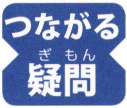 体液は、どんなはたらきをしているの?
体液は、どんなはたらきをしているの?
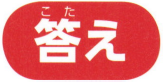 体をつくっている「細胞」の活動をたすけています
体をつくっている「細胞」の活動をたすけています
 体の中の水分を「体液」といいます。体液には、体に必要な栄養などがふくまれていて、つねに全身をめぐっています。血管の中の血も、体液の一種です。
体の中の水分を「体液」といいます。体液には、体に必要な栄養などがふくまれていて、つねに全身をめぐっています。血管の中の血も、体液の一種です。
わたしたちの体は、およそ60兆こもの細胞でできています。細胞と細胞の間には体液がながれていて、細胞は体液から必要な栄養などをとり、いらなくなったものをすてています。
細胞がいきていけるのは、このようにしてその活動をたすけてくれる体液のおかげなのです。
117
どうして、たべないといきられないの?
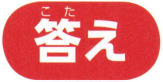 人は、たべたものから栄養をとって活動しているから
人は、たべたものから栄養をとって活動しているから
 わたしたちの体は、食べ物から必要な栄養をとりいれてつくられています。また、とった栄養をエネルギーにかえて、活動しています。
わたしたちの体は、食べ物から必要な栄養をとりいれてつくられています。また、とった栄養をエネルギーにかえて、活動しています。
じっとしているときやねているときでも、心臓や肺などの内臓は、たえ間なくうごいて、エネルギーをつかっています。
ですから、たべなければいきていくことはできません。
 わたしたちがいきていくために必要な栄養素は、45~50種類もあるといわれています。
わたしたちがいきていくために必要な栄養素は、45~50種類もあるといわれています。
中でもとくに重要なものを、大きく5種類にわけて、5大栄養素とよんでいます。
体をつくるには「たんぱく質」、体をうごかすには「糖質(炭水化物)」や「脂質」がつかわれています。
 5大栄養素
5大栄養素
| 栄養素
| 主なはたらき
| 多くふくまれている食品
|
|---|
| 糖質(炭水化物)
| 体温や力のもとになる。
| ご飯、パン、めん類、イモ、砂糖など。
|
|---|
| 脂質
| 体をうごかすための
エネルギーになる。
| バターやマーガリン、油、マヨネーズ、
肉のあぶら身など。
|
|---|
| たんぱく質
| 血や筋肉など、体をつくる
もとになる。
| 肉、魚、卵、大豆製品
(納豆、とうふなど)
|
|---|
| ビタミン
| 体の調子をととのえ、
健康でいられるよう、たすける。
| 野菜、果物、レバーなど。
|
|---|
| ミネラル
| 歯や骨などをつくる。
成長をたすける。
体の調子をととのえる。
| 海藻類、牛乳、乳製品(ヨーグルト、
チーズなど)、小魚、貝など。
|
|---|
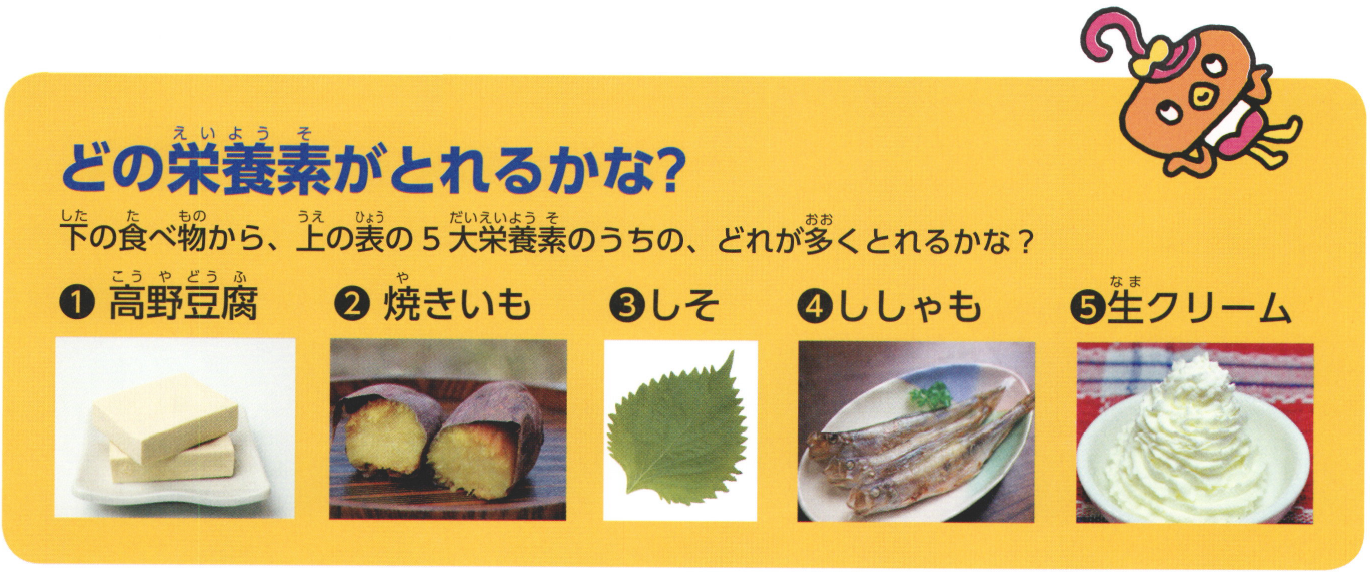

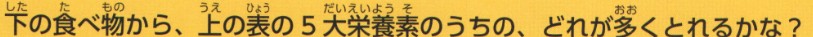
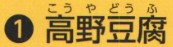
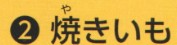
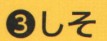
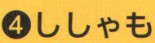
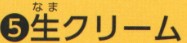

❶たんぱく質
❷糖質
❸ビタミン
❹ミネラル
❺脂質
118
どうしておならがでるの?
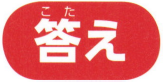 食べ物といっしょにのみこんだ空気と腸で発生するガスを、体からだすため
食べ物といっしょにのみこんだ空気と腸で発生するガスを、体からだすため
 おならの正体は、食べ物といっしょにのみこんだ空気と、食べ物が腸にはこばれて細かく消化されるときに発生するガスです。
おならの正体は、食べ物といっしょにのみこんだ空気と、食べ物が腸にはこばれて細かく消化されるときに発生するガスです。
食べ物と一緒にのみこんだ空気は、げっぷとなって口からでることもありますが、そのまま体の中を移動する場合もあります。口からでなかった空気は、ほとんどが腸におくられます。
腸におくられた空気と、腸内で発生したガスがまざって、おしりの穴からでてくるのがおならなのです。おならがくさいのは、たんぱく質が分解されるときにでるインドールというにおい成分が発生するからです。
 おならをがまんしすぎると、空気やガスでおなかがふくらんでいたくなることがあります。また、腸のかべから吸収されて、血管の中にはいり、全身にまわって、体にわるい影響をあたえるのです。
おならをがまんしすぎると、空気やガスでおなかがふくらんでいたくなることがあります。また、腸のかべから吸収されて、血管の中にはいり、全身にまわって、体にわるい影響をあたえるのです。
なるべくおならがでないようにするには、食事のときに余分な空気をのみこまないようにすればいいのです。口に食べ物をいれたまましゃべったり、口の中へごはんをかきこんだりせず、ゆっくりよくかんでたべましょう。
 口からはゲップ、おしりからはおならとしてだされる。
口からはゲップ、おしりからはおならとしてだされる。
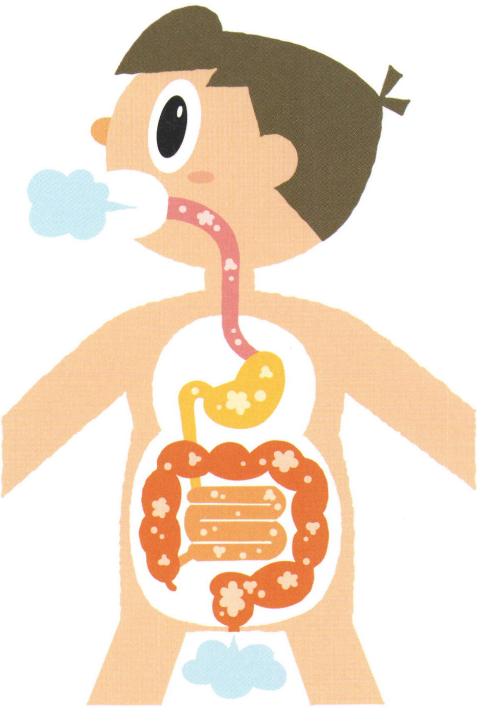
 たべるものでおならがかわる!?
たべるものでおならがかわる!?
おならのにおいは、たべるものでかわってきます。
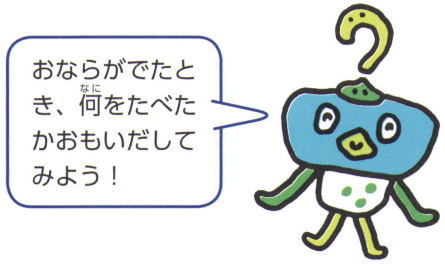
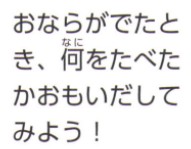
 肉などのたんぱく質食品をたべすぎたとき
肉などのたんぱく質食品をたべすぎたとき
 くさいにおいのおならがでる。
くさいにおいのおならがでる。
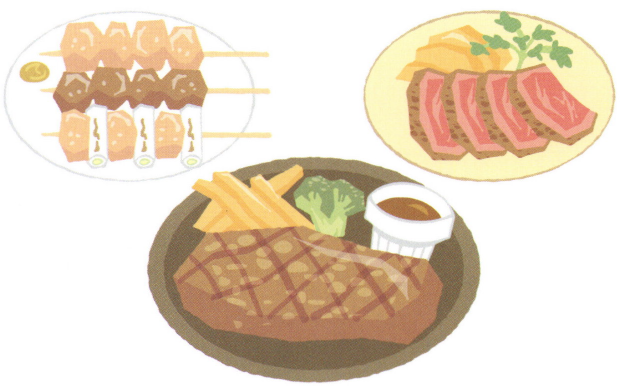
 さつまいもやごぼうなど、繊維の多いものをたべたとき
さつまいもやごぼうなど、繊維の多いものをたべたとき
 おならの回数はふえるが、あまりくさくない。
おならの回数はふえるが、あまりくさくない。

119
指紋はみんなちがうの?
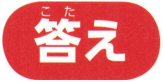 まったく同じ指紋はないといわれています
まったく同じ指紋はないといわれています
 手の指先にある指紋のもようは、大きくわけると、うずまき形、ながれ形(ひづめ形)、弓形の3種類です。
手の指先にある指紋のもようは、大きくわけると、うずまき形、ながれ形(ひづめ形)、弓形の3種類です。
しかし、よくにているようにみえても、ひとりひとりみんなちがっていて、全く同じもようの人はいないとかんがえられているため、犯罪の捜査などにも利用されています。
日本人のおよそ50%はうずまき形、40%ほどがながれ形、残りの10%ぐらいが弓形の模様だといわれています。
 指紋は、皮膚の表面にある汗の出口がもりあがってできたもので、ものをにぎったりおさえたりするときのすべり止めのはたらきをしています。
指紋は、皮膚の表面にある汗の出口がもりあがってできたもので、ものをにぎったりおさえたりするときのすべり止めのはたらきをしています。
ほかにも、指先の感覚をするどくするはたらきをもっているとかんがえられています。
 指紋があるのは、人だけではありません。チンパンジーやオランウータンなどサルのなかまや、ネズミ、コアラなどにも指紋はあります。
指紋があるのは、人だけではありません。チンパンジーやオランウータンなどサルのなかまや、ネズミ、コアラなどにも指紋はあります。
 うずまき形
うずまき形
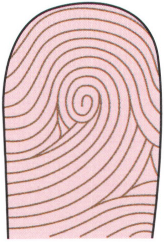
 ながれ形(ひづめ形)
ながれ形(ひづめ形)
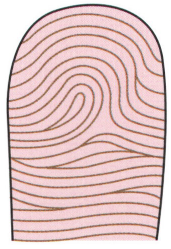
 弓形
弓形
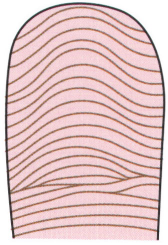
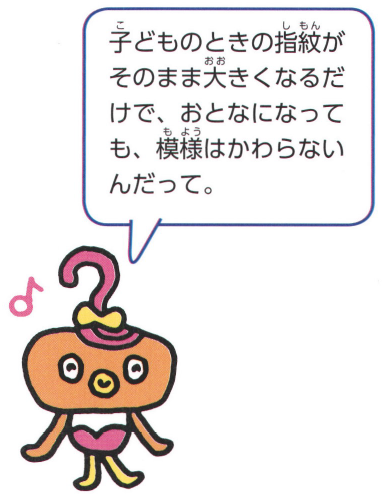
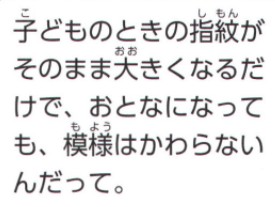
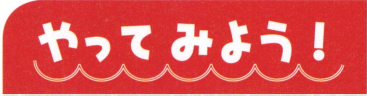 自分の指紋をみてみよう
自分の指紋をみてみよう
家にあるものをつかって指紋をみてみよう!

朱肉(またはスタンプインク)、白い紙
虫めがね

①指に朱肉をつけて、白い紙におしつける。
②虫めがねで、それぞれの指の指紋の種類や形のちがいを観察する。
③手だけでなく、足の指でもやってみよう。

 親指の指紋。いろいろな指でやってみよう。
親指の指紋。いろいろな指でやってみよう。


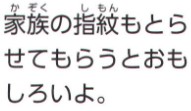
120
どうして野菜をたべないといけないの?
 体に必要な栄養をとりいれるため
体に必要な栄養をとりいれるため
 わたしたちがいきていくには、いろいろな種類の栄養が必要です。
わたしたちがいきていくには、いろいろな種類の栄養が必要です。
とくに体が成長する時期には、すきなものだけでなく、さまざまな食品をバランスよくたべることが大切です。
 野菜には、体の調子をととのえてくれる「ビタミン」という栄養がたくさんふくまれています。
野菜には、体の調子をととのえてくれる「ビタミン」という栄養がたくさんふくまれています。
また、栄養以外にも、体に必要な水分や、腸の中をそうじして、いらなくなったものをうんちとしてだすのをてつだう「食物繊維」が豊富です。
 野菜には緑黄色野菜と淡色野菜があります。野菜によってふくまれているビタミンの種類や量がちがうので、いろいろな種類の野菜を毎日とることが、体のためには重要です。
野菜には緑黄色野菜と淡色野菜があります。野菜によってふくまれているビタミンの種類や量がちがうので、いろいろな種類の野菜を毎日とることが、体のためには重要です。
 緑黄色野菜(こい色の野菜)
緑黄色野菜(こい色の野菜)
 ブロッコリー、ピーマン、カボチャ、ホウレンソウ、トマトなど。
ブロッコリー、ピーマン、カボチャ、ホウレンソウ、トマトなど。

 淡色野菜(うすい色の野菜)
淡色野菜(うすい色の野菜)
 キャベツ、ダイコン、タマネギ、カリフラワー、白ネギ、モヤシなど。
キャベツ、ダイコン、タマネギ、カリフラワー、白ネギ、モヤシなど。

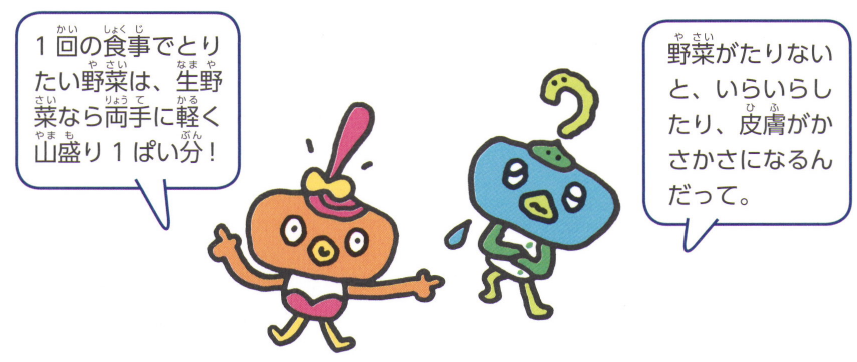
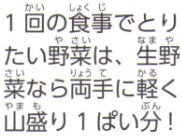
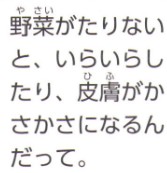
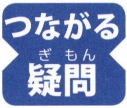 ビタミンって何?
ビタミンって何?
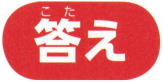 いきていくために大切な5大栄養素のひとつ
いきていくために大切な5大栄養素のひとつ
 野菜の中にも多くふくまれるビタミンは、わたしたちがいきていくために、とくに大切といわれている5大栄養素のひとつです。目や鼻やのどなどの粘膜にうるおいをあたえてくれたり、免疫力をたかめて、病気になりにくくするなど、さまざまなはたらきがあり、わたしたちの健康にはかかせないものです。
野菜の中にも多くふくまれるビタミンは、わたしたちがいきていくために、とくに大切といわれている5大栄養素のひとつです。目や鼻やのどなどの粘膜にうるおいをあたえてくれたり、免疫力をたかめて、病気になりにくくするなど、さまざまなはたらきがあり、わたしたちの健康にはかかせないものです。
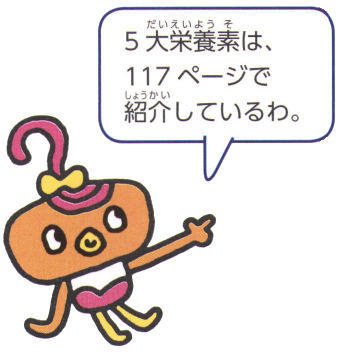
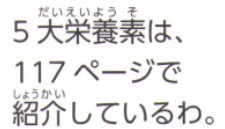
 ビタミンの種類
ビタミンの種類
| 種類
| 主なはたらき
| 多くふくまれている食品
|
|---|
| ビタミンA
| ひふや粘膜を強くする
| トマト、にんじん、
カボチャなど
|
|---|
| ビタミンB1
| 炭水化物をエネルギーにかえる
| さやえんどう、ブロッコリー、
アスパラなど
|
|---|
| ビタミンB2
| ひふや髪の毛を健康にする
| レバー、うなぎ、たまごなど
|
|---|
| ビタミンC
| 血管や骨を丈夫にする
| レモン、いちご、キャベツなど
|
|---|
| ビタミンD
| 骨や歯をつくる
| さけ、きくらげ、しらすなど
|
|---|
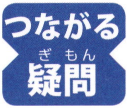 動物はどうやってねむるの?
動物はどうやってねむるの?
 人とはちがうねむり方をします
人とはちがうねむり方をします
 わたしたち人は、夜ぐっすりとねむることができますが、野生の生き物たちはそうはいきません。ねむっている間も敵におそわれる危険があるからです。また、一部の肉食動物をのぞいては、十分な栄養をとるために、食事に長い時間をついやすため、ゆっくりとねむっているひまはありません。
わたしたち人は、夜ぐっすりとねむることができますが、野生の生き物たちはそうはいきません。ねむっている間も敵におそわれる危険があるからです。また、一部の肉食動物をのぞいては、十分な栄養をとるために、食事に長い時間をついやすため、ゆっくりとねむっているひまはありません。
 そこで、生き物たちはいろいろなねむり方をします。たとえば、キリンやフラミンゴは、脳の右側と左側をかた方ずつねむらせます。かた方がねむっている間も、もうかた方の脳がおきていて、まわりの危険に気をくばるのです。
そこで、生き物たちはいろいろなねむり方をします。たとえば、キリンやフラミンゴは、脳の右側と左側をかた方ずつねむらせます。かた方がねむっている間も、もうかた方の脳がおきていて、まわりの危険に気をくばるのです。
また、ネズミなどは、すぐに危険がわかるように一度に長い時間ねむらずに、数秒というごく短いねむりをくりかえします。
 シマウマは、たったままでねむる。
シマウマは、たったままでねむる。

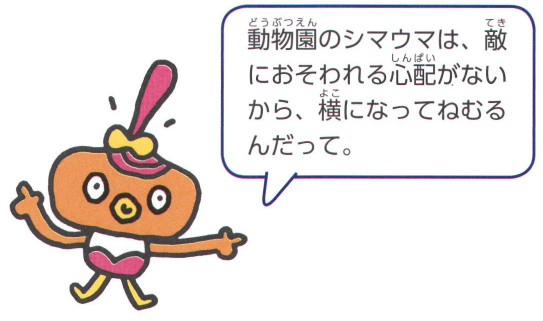
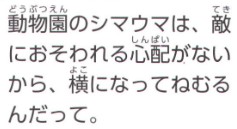
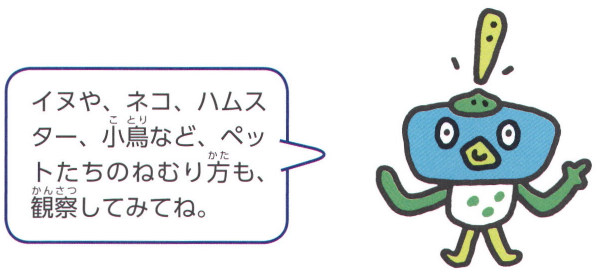
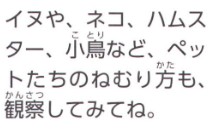
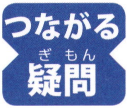 動物も、ゆめをみるのかな?
動物も、ゆめをみるのかな?
 大脳が発達している動物は、ゆめをみます
大脳が発達している動物は、ゆめをみます
 イヌやネコなど、大脳が発達している動物は、ゆめをみていることがわかっています。
イヌやネコなど、大脳が発達している動物は、ゆめをみていることがわかっています。
イヌやネコなどが、ねながら鳴き声をだしたり、前足をはげしくうごかしたりしているときは、きっと、ゆめをみて、それに反応しているのでしょう。
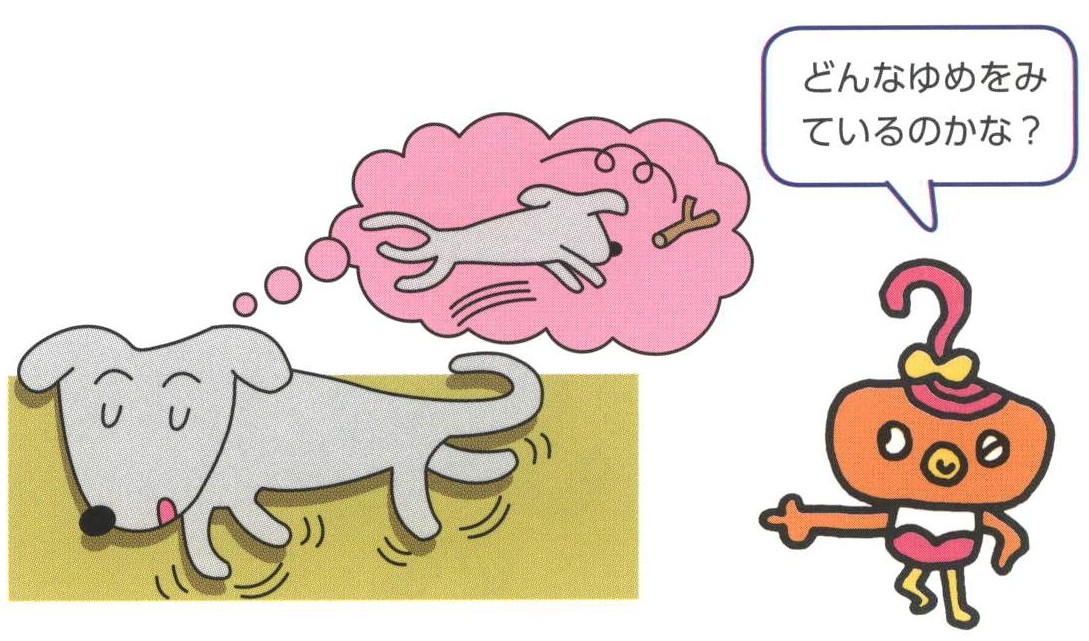
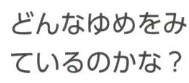
123
おなかの中には細菌がいるの?
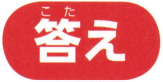 腸の中には1000種以上の細菌がいます
腸の中には1000種以上の細菌がいます
 わたしたちのおなかの中には、胃で消化された食べ物をさらにこまかく消化し、栄養分として吸収する小腸と、小腸からおくられてきたどろどろの残りかすから水分を吸収してうんちをつくる大腸があります。
わたしたちのおなかの中には、胃で消化された食べ物をさらにこまかく消化し、栄養分として吸収する小腸と、小腸からおくられてきたどろどろの残りかすから水分を吸収してうんちをつくる大腸があります。
 大腸の主なはたらきは、食べ物の残りかすから水分を吸収することですが、それだけではありません。大腸には小腸の中よりもたくさんの細菌がすみついていて、それらの細菌の助けをかりて、栄養分の吸収もおこなっています。
大腸の主なはたらきは、食べ物の残りかすから水分を吸収することですが、それだけではありません。大腸には小腸の中よりもたくさんの細菌がすみついていて、それらの細菌の助けをかりて、栄養分の吸収もおこなっています。
 ヨーグルトにふくまれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸の調子をととのえてくれるといわれています。
ヨーグルトにふくまれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸の調子をととのえてくれるといわれています。
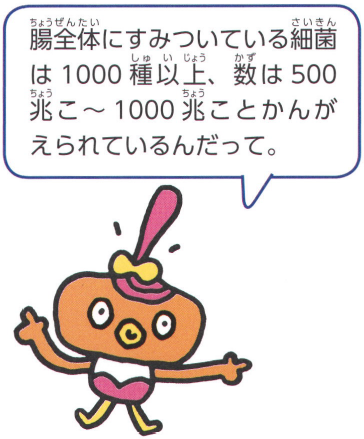
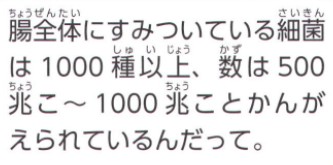
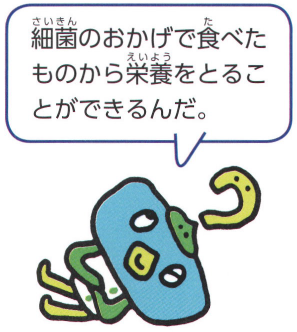
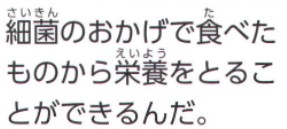
 乳酸菌は納豆やつけもの、みそ汁にもふくまれている。
乳酸菌は納豆やつけもの、みそ汁にもふくまれている。

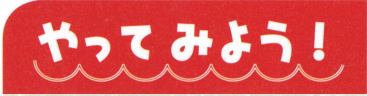 ヨーグルトをつくってたべよう
ヨーグルトをつくってたべよう
スーパーなどにうっているプレーンヨーグルト(菌がいきているタイプ)で、ヨーグルトをつくって、たべてみましょう。

ヨーグルト大さじ3、牛乳1、輪ゴム
ガラスびんなどの容器、キッチンペーパー

①せいけつなガラスびんにヨーグルトをいれ、牛乳をそそいで、よくまぜる。
②ほこりがはいらないようキッチンペーパーをかぶせて、輪ゴムでとめる。
③家の中の、風通しがよく直射日光のあたらない場所に、1日(24時間)くらいおいておく。
※ガラスびんでつくるときは、びんをきれいにしてから実験しましょう。

表面がヨーグルト状にかたまっていたら、できあがり。はちみつやジャムなどであま味をつけて、たべる。
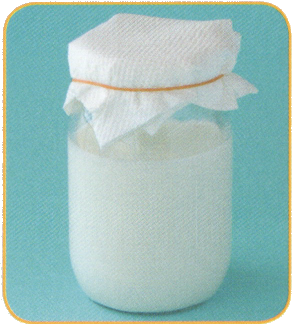

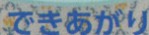

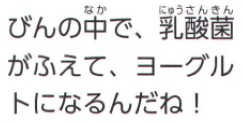
124
どうしておねしょをしちゃうの?
 おしっこをためておけなくなるから
おしっこをためておけなくなるから
 だれでもおねしょをしてしまった経験はありますね。なぜ気がつかないうちにおしっこがでてしまうのでしょうか。
だれでもおねしょをしてしまった経験はありますね。なぜ気がつかないうちにおしっこがでてしまうのでしょうか。
おしっこは、腎臓でつくられて膀胱にためられます。膀胱におしっこが半分くらいたまると、脳に信号がつたわり、「トイレにいきたい」という気持ちになります。
膀胱は、成長するにつれて大きくなりますが、子どものうちはまだ小さいため、たくさんのおしっこをためておくことができずにあふれてしまうのです。
 また、夜ねている間はホルモンがでて、おしっこがたくさんつくられないようにしてくれています。そのホルモンがきちんとはたらかないと、夜の間でもおしっこがたくさんつくられてしまいます。
また、夜ねている間はホルモンがでて、おしっこがたくさんつくられないようにしてくれています。そのホルモンがきちんとはたらかないと、夜の間でもおしっこがたくさんつくられてしまいます。
膀胱の大きさと、つくられるおしっこの量のバランスがくずれると、おねしょをしてしまうのです。おとなになって、膀胱が大きくなり、おしっこがつくられるリズムがととのえば、おねしょをすることはなくなります。
 おとなと子どもの膀胱。
おとなと子どもの膀胱。
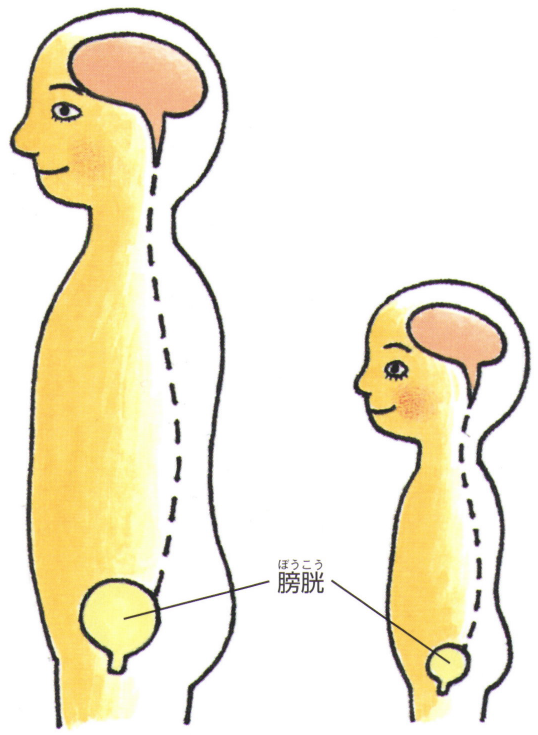

男女の声はどうしてちがうの?
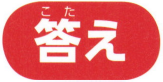 声をだす声帯の長さのちがいです
声をだす声帯の長さのちがいです
 声の高さは人によってちがいますが、ふつう、おとなの男の人は低く、それにくらべて女の人は高い声をしていますね。
声の高さは人によってちがいますが、ふつう、おとなの男の人は低く、それにくらべて女の人は高い声をしていますね。
声は、のどのおくにある声帯という部分をふるわせてだしています。声帯は2まいのまくのようなものでできていますが、ギターのげんのように、長ければ低い音が、短ければ高い音がでます。
男の人の声帯は女の人よりも長いので、低い声になるのです。
 子どものうちは、男の子も女の子も声帯は同じような長さですが、思春期になって、おとなの体になると、男の子の声帯は発育して長くなります。
子どものうちは、男の子も女の子も声帯は同じような長さですが、思春期になって、おとなの体になると、男の子の声帯は発育して長くなります。
一方、女の子の声帯も発育しますが、長さはあまりかわりません。
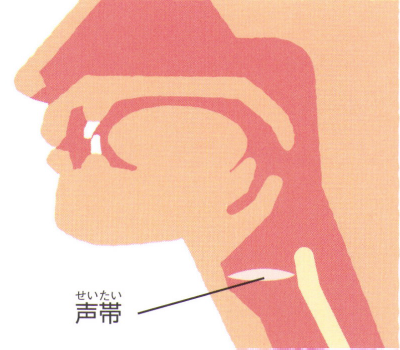

 息をすうときは声帯がひらく。
息をすうときは声帯がひらく。
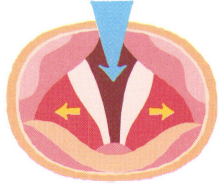
 声をだすときは声帯がとじる。
声をだすときは声帯がとじる。
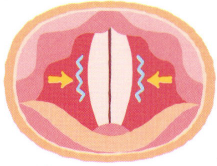
125
としをとるとはげたり、しらががはえたりするのはなぜ?
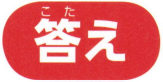 髪の毛や、色のもとになるメラニン色素をつくる細胞がはたらかなくなるから
髪の毛や、色のもとになるメラニン色素をつくる細胞がはたらかなくなるから
 髪の毛は、一日に何十本もぬけますが、皮膚の中にある毛球でたえずつくられています。毛球では、髪の毛の色のもとになるメラニン色素もつくられていて、新しくはえてくる毛を黒くしています。
髪の毛は、一日に何十本もぬけますが、皮膚の中にある毛球でたえずつくられています。毛球では、髪の毛の色のもとになるメラニン色素もつくられていて、新しくはえてくる毛を黒くしています。
としをとると、毛球でつくられる毛やメラニン色素がへったり、新しい毛がつくられなくなったりします。それで、はげたり、しらがになったりするのです。
 はげるかどうかや、しらがになるかどうかは、人によってちがいます。としをとればいつかはだれでも白髪になったり、はげたりします。
はげるかどうかや、しらがになるかどうかは、人によってちがいます。としをとればいつかはだれでも白髪になったり、はげたりします。
しらがをぬくとふえるといわれることがありますが、ぬいても数がふえたりへったりすることはありません。ただし、むりやりぬくと、毛根がきずついてしまうので、やめたほうがいいでしょう。
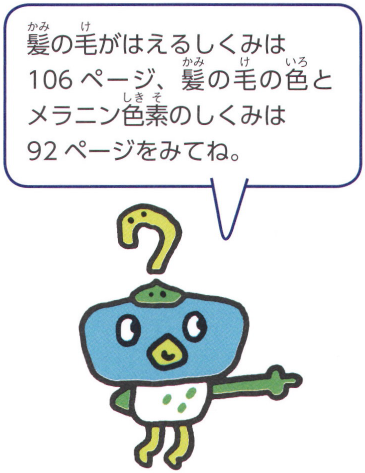
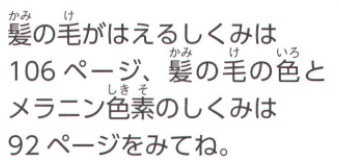
たんこぶはどうしてできるの?
 皮膚の下の血管がやぶれて血がでるから
皮膚の下の血管がやぶれて血がでるから
 頭やおでこを強くぶつけると、そこがふくらんでたんこぶができますね。たんこぶは、皮膚の下の血管がやぶれて、血がたまったものです。
頭やおでこを強くぶつけると、そこがふくらんでたんこぶができますね。たんこぶは、皮膚の下の血管がやぶれて、血がたまったものです。
頭の皮膚のすぐ下には、かたい骨があります。ぶつけると、外からの力とかたい骨にはさまれて、血管がやぶれ、血がでます。血は骨のほうにはひろがることができないので、皮膚をおしあげてふくらんでしまうのです。
おしりやおなかなどのやわらかい部分は、皮膚の下で血がでても内側にひろがることができるので、たんこぶはできません。
 たんこぶができても、やぶれた血管はしぜんにふさがり、たまった血も吸収されて、しばらくするときえてしまいます。もし、たんこぶができてしまったら、すぐにぬれたタオルなどでひやすと、はれやいたみをやわらげることができます。
たんこぶができても、やぶれた血管はしぜんにふさがり、たまった血も吸収されて、しばらくするときえてしまいます。もし、たんこぶができてしまったら、すぐにぬれたタオルなどでひやすと、はれやいたみをやわらげることができます。
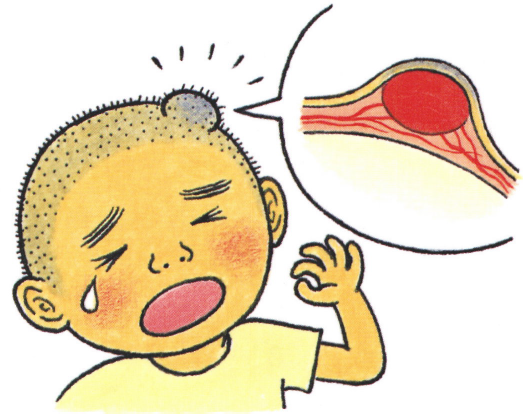

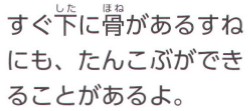
126
どうして鳥はだがたつの?
 筋肉がちぢんで毛穴がもりあがるから
筋肉がちぢんで毛穴がもりあがるから
 急にさむいところにでると、うでや足の皮膚にぶつぶつができますね。鳥の皮膚ににているので、「鳥はだ」とよばれています。
急にさむいところにでると、うでや足の皮膚にぶつぶつができますね。鳥の皮膚ににているので、「鳥はだ」とよばれています。
鳥はだをよくみると、ぶつぶつは、毛がまっすぐにたって、ねもとがもりあがっているのがわかります。
さむいと、毛のねっこにある「立毛筋」という小さな筋肉がちぢみます。すると、ふだんは横向きにねている毛がまっすぐになって、まわりの皮膚も一緒にもちあがるのです。
 鳥はだは何の役にたっているのでしょうか? 全身が毛でおおわれている動物の場合、毛をたてることで、毛と毛の間にたくさんの空気をためてさむさをふせぐことができます。でも、人の体の毛はうすいので、さむさをふせぐことはできません。
鳥はだは何の役にたっているのでしょうか? 全身が毛でおおわれている動物の場合、毛をたてることで、毛と毛の間にたくさんの空気をためてさむさをふせぐことができます。でも、人の体の毛はうすいので、さむさをふせぐことはできません。
 鳥はだは、さむいときだけでなく、こわいときやおどろいたとき、ぞっとしたときにもでることがありますね。立毛筋は、自分で意識してうごかすことはできず、緊張やストレスをかんじたときにはたらく交感神経がうごかしています。
鳥はだは、さむいときだけでなく、こわいときやおどろいたとき、ぞっとしたときにもでることがありますね。立毛筋は、自分で意識してうごかすことはできず、緊張やストレスをかんじたときにはたらく交感神経がうごかしています。
 ふだんの皮膚(左)と、鳥はだの皮膚(右)。
ふだんの皮膚(左)と、鳥はだの皮膚(右)。
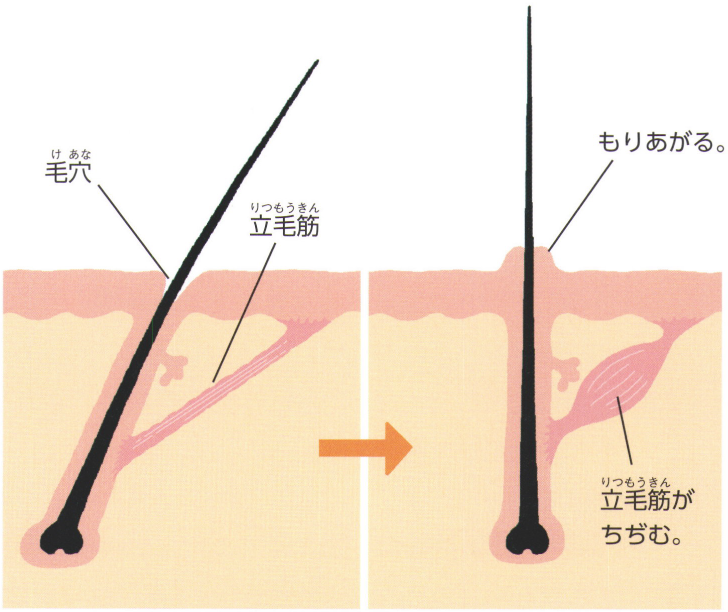



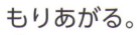
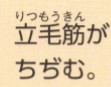
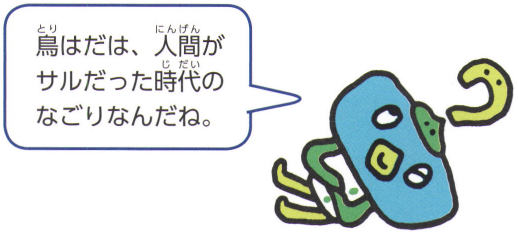
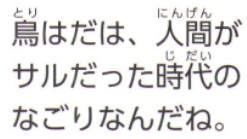
ほくろはどうしてできるの?
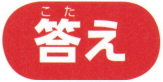 メラニン色素がかたまって黒くなります
メラニン色素がかたまって黒くなります
 ほくろは、皮膚の色をつくっているメラニンという色素が1か所にかたまったものです。
ほくろは、皮膚の色をつくっているメラニンという色素が1か所にかたまったものです。
メラニン色素は、太陽の光にふくまれる紫外線が体にわるい影響をおよぼすのをふせいでくれる役割があります。そのメラニン色素が何かの理由でかたまってしまうのです。
 ほくろの数は人によってちがいますが、うまれたばかりの赤ちゃんにはほとんどありません。成長するにつれて、ふえていきます。数のちがいは遺伝によるものだともいわれますが、はっきりとはわかっていません。
ほくろの数は人によってちがいますが、うまれたばかりの赤ちゃんにはほとんどありません。成長するにつれて、ふえていきます。数のちがいは遺伝によるものだともいわれますが、はっきりとはわかっていません。
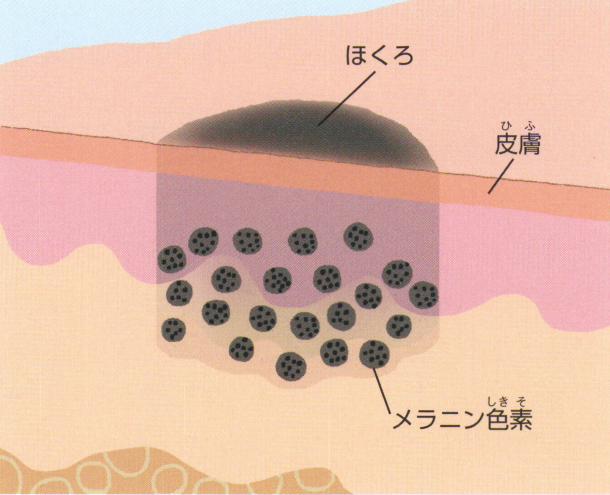
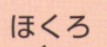

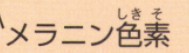
127
まばたきをするのはなぜ?
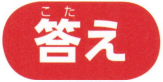 目についたごみをあらいながしたり、目に涙をいきわたらせるため
目についたごみをあらいながしたり、目に涙をいきわたらせるため
 まばたきには主に2つの役割があります。
まばたきには主に2つの役割があります。
1つ目は、目についたごみをあらいながすことです。空気中には、目にみえない細かいごみがたくさんただよっていて、いつも目にくっついています。まばたきをすることで、このようなごみをぬぐいさるのです。
2つ目の役割は、目がかわくのをふせぐことです。目の表面は、ごくうすい涙のまくによってまもられています。涙がかわいてしまうと、目がきずついたり、病気の原因になったりします。
 わたしたちは、1分間に平均20回もまばたきをしています。1日にすると、2万8800回にもなります。
わたしたちは、1分間に平均20回もまばたきをしています。1日にすると、2万8800回にもなります。
ふだんは意識することなくまばたきをしていますが、本やパソコンなど、何かに集中していると、まばたきの回数がへることがあります。すると、目の表面の涙がかわいて目がゴロゴロしたり、しょぼしょぼしたりするのです。
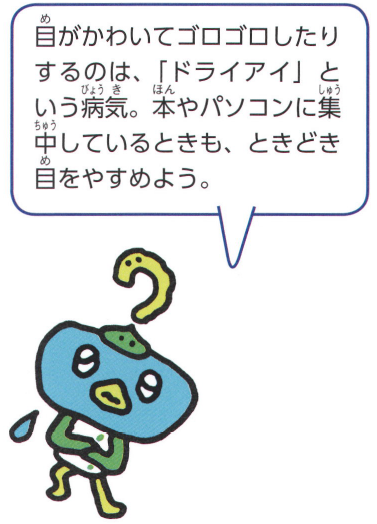
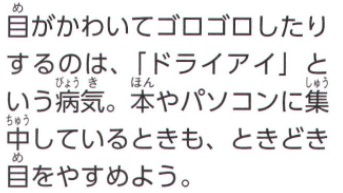
大声をだすと力がでるって本当?
 自分がおもった以上の力がでるときもあります
自分がおもった以上の力がでるときもあります
 「火事場の馬鹿力」ということばをきいたことがありますか。これは、火事のときに、ふだんは絶対にもてないような、重いたんすなどをもちだしてしまうほどの力がでることから、人はきけんがせまると、ふだんではおもいもよらない力をだすことがあるというたとえです。そんな力が本当にあるのでしょうか?
「火事場の馬鹿力」ということばをきいたことがありますか。これは、火事のときに、ふだんは絶対にもてないような、重いたんすなどをもちだしてしまうほどの力がでることから、人はきけんがせまると、ふだんではおもいもよらない力をだすことがあるというたとえです。そんな力が本当にあるのでしょうか?
 重量あげの選手が、バーベルをもちあげる瞬間に、大きな声をだすことがあります。大きな声をだすことで、自分がおもっている以上の力がでるといわれています。
重量あげの選手が、バーベルをもちあげる瞬間に、大きな声をだすことがあります。大きな声をだすことで、自分がおもっている以上の力がでるといわれています。
人は、本来もっている力の70%しかださないように、脳がブレーキをかけているとかんがえられています。100%の力をだしてしまうと、筋肉や骨をいためるおそれがあるからです。このブレーキをはずす方法が、大声をだすことだといわれています。
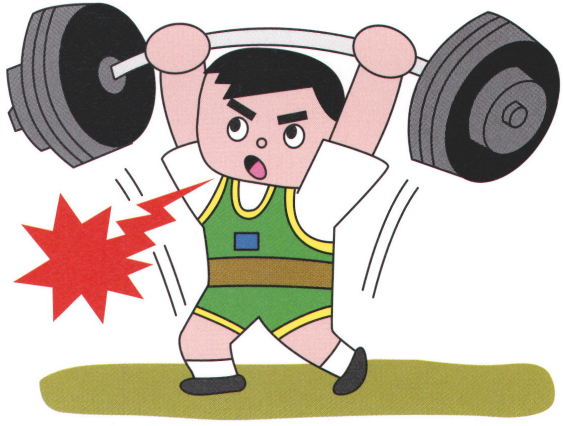
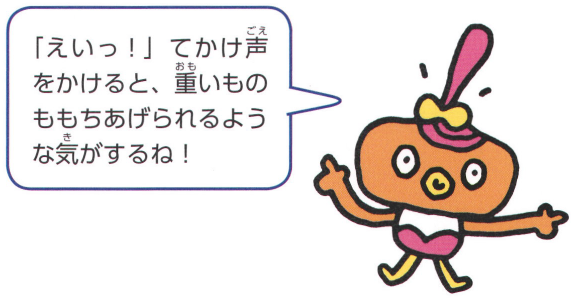
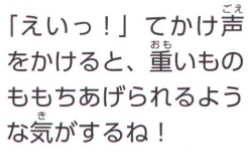
128
熱中症ってどんなもの?
 あつさで体調がわるくなること
あつさで体調がわるくなること
 人は、体で熱をつくりだしています。あついときは、汗をだすことで体温をさげて調節します。
人は、体で熱をつくりだしています。あついときは、汗をだすことで体温をさげて調節します。
しかし、この調節がうまくいかないと、体に熱がこもって体温があがりすぎてしまいます。また、汗をかきすぎると、体の中の水分や塩分がたりなくなってしまいます。すると、目まいや頭痛、けいれんなどのさまざまな症状がでます。ひどくなると、死んでしまうこともあります。
 あつい日に、外で運動などをするときは、熱中症にならないように、注意が必要です。こまめに水分や塩分をとって、むりをしないことが大切です。また、外だけでなく、室内でも熱中症になる危険があります。エアコンなどをつかって、部屋の温度があがりすぎないようにしましょう。
あつい日に、外で運動などをするときは、熱中症にならないように、注意が必要です。こまめに水分や塩分をとって、むりをしないことが大切です。また、外だけでなく、室内でも熱中症になる危険があります。エアコンなどをつかって、部屋の温度があがりすぎないようにしましょう。
 熱中症をふせぐ方法
熱中症をふせぐ方法


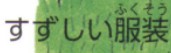
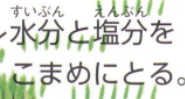
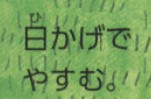
日やけをするとはだが黒くなるのはなぜ?
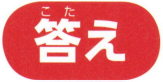 太陽の光にあたると、メラニン色素がふえるから
太陽の光にあたると、メラニン色素がふえるから
 太陽の光は、いろいろな色の光がまざって透明な光にみえています。その中にふくまれる、目にみえない「紫外線」という光は、あたりすぎると人の体にわるい影響があります。
太陽の光は、いろいろな色の光がまざって透明な光にみえています。その中にふくまれる、目にみえない「紫外線」という光は、あたりすぎると人の体にわるい影響があります。
しかし、わたしたちの体には、メラニンという黒い色素があって、紫外線をすいとってくれます。メラニン色素は、太陽の光にあたるとふえ、光がよわまるとへります。日やけをするとはだが黒くなるのは、メラニン色素がふえるからです。
 日やけをすると、黒くなるだけでなく、ひどいときには水ぶくれになったり、皮がむけたりしますね。
日やけをすると、黒くなるだけでなく、ひどいときには水ぶくれになったり、皮がむけたりしますね。
これはやけどと同じことなので、ぬらしたタオルなどでひやしてあげましょう。また、強い日ざしを長い時間あびるときは、日焼けどめクリームをぬったり、ぼうしをかぶったりして、日やけをしすぎないように注意しましょう。
 月ごとの紫外線量
月ごとの紫外線量
 紫外線は5月から9月にかけて強くなる。
紫外線は5月から9月にかけて強くなる。
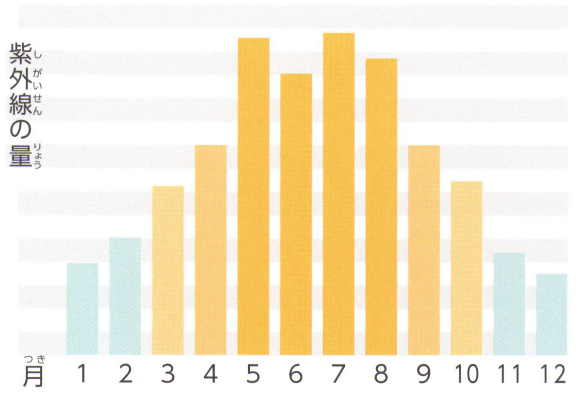



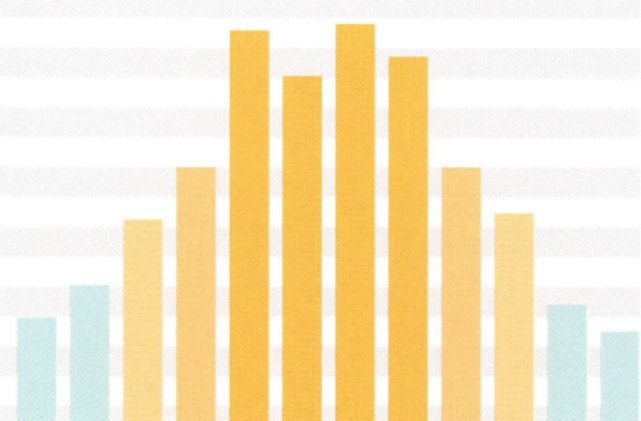
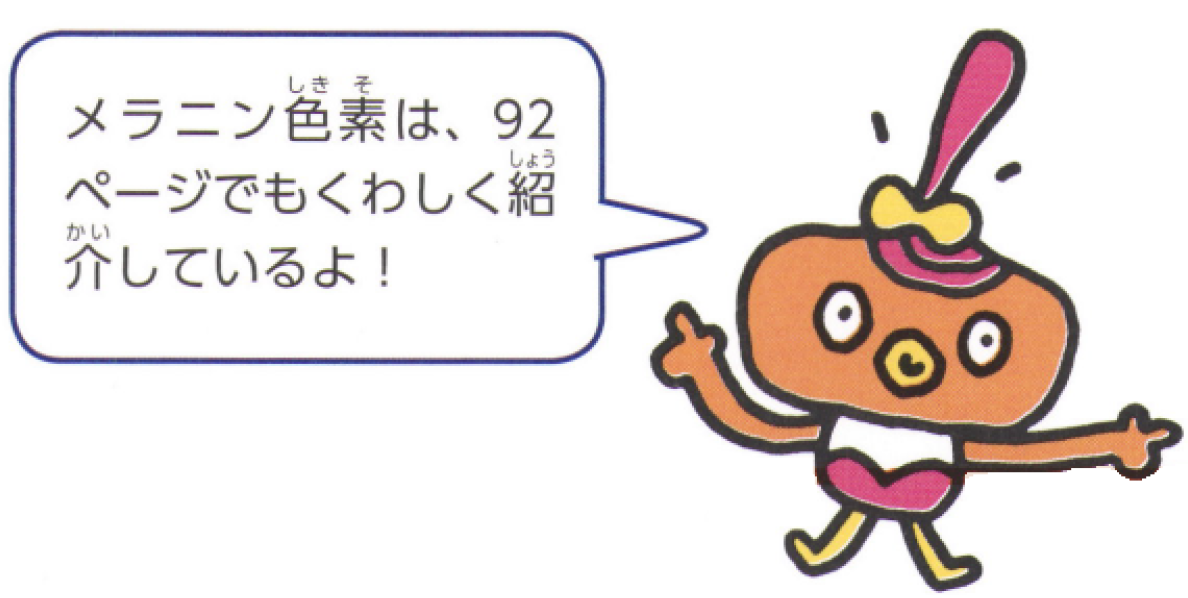
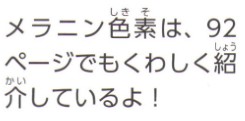
129
おなかがすくとグーグーなるのはなぜ?
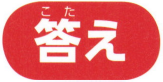 胃や腸の中で空気と食べ物がうごく音です
胃や腸の中で空気と食べ物がうごく音です
 おなかがすいたとき、グーッという音がすることがありますね。じつは、この音とおなかがすいていることとは、直接の関係はありません。
おなかがすいたとき、グーッという音がすることがありますね。じつは、この音とおなかがすいていることとは、直接の関係はありません。
この音は、おなかの中にある胃や小腸という、食べ物を消化する器官からでています。小腸はおとなで長さが約5~7
もあります。その中をとおって、胃からはいってきた食べ物が大腸へおくられますが、このときにグーッとなります。
また、食べ物をだいたいおくってしまい、かすだけがのこると、空気とまざりあいます。すると、小腸がうごいたときにグーッと音がでるのです。
音がなるのは、ちょうど前にたべた食べ物が消化されて、おなかがすく時間とかさなるので、おなかがすいた合図のようにかんじるのです。
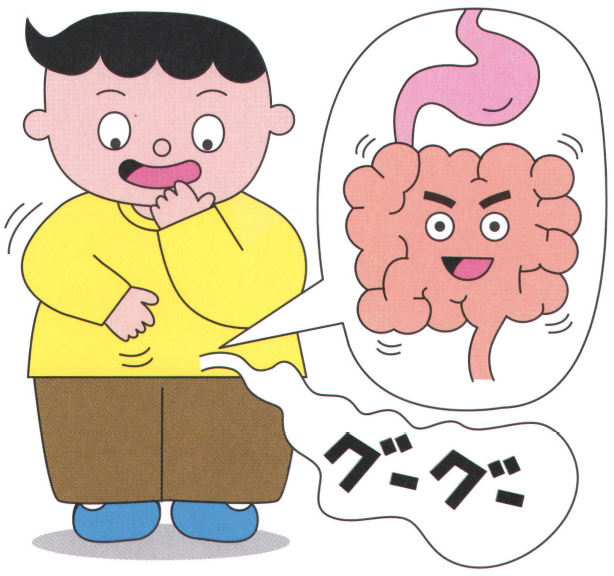

たべた後にはしるとおなかがいたくなるのはなぜ?
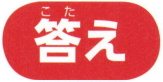 血がたりなくなって腸がけいれんするから
血がたりなくなって腸がけいれんするから
 たべた後にすぐにはしったりあるいたりすると、わきばらがキリキリといたくなることがありますね。
たべた後にすぐにはしったりあるいたりすると、わきばらがキリキリといたくなることがありますね。
食事をすると、消化をするために胃や腸がいっしょうけんめいはたらきます。このとき、たくさんの血液が必要になるので、胃や腸にあつまります。すると、体のほかの部分にいく血液がへってしまいます。たべた後に頭がぼーっとしてねむくなるのも、脳にいく血液がへるからです。
はしるためには、筋肉にも血液がたくさん必要になります。血液が筋肉のほうにいってしまうと、腸では血液がたりなくなって、けいれんがおこります。それでおなかがいたくなってしまうのです。
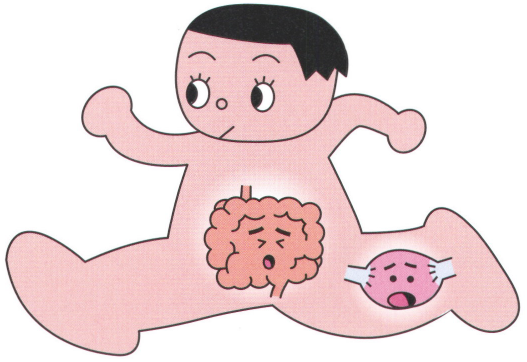
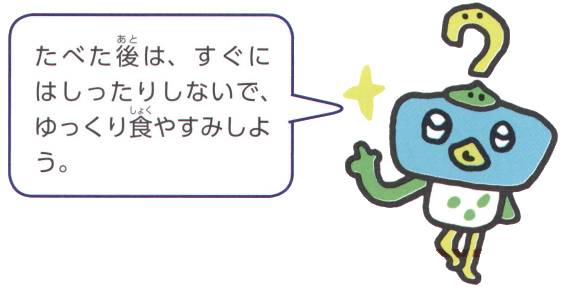
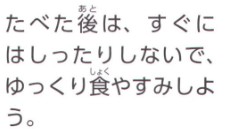
130
おふろで指がしわしわになるのはなぜ?
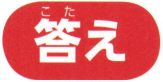 皮膚が水をすってふやけるから
皮膚が水をすってふやけるから
 皮膚の一番外側には、「角質層」という水をふくみやすい層があります。手の角質層は、体のほかの部分にくらべてとくにあつく、0.5~1
もあります。
皮膚の一番外側には、「角質層」という水をふくみやすい層があります。手の角質層は、体のほかの部分にくらべてとくにあつく、0.5~1
もあります。
水に長くつかっていると、角質層が水をすってふくらみ、面積がふえます。しかし、角質層の下の皮膚はそのままなので、ふやけた角質層がひだのようになって、しわになるのです。
よくみると、指先だけでなく、手のひらや足のうらもふやけているのがわかります。
 皮膚の断面。
皮膚の断面。
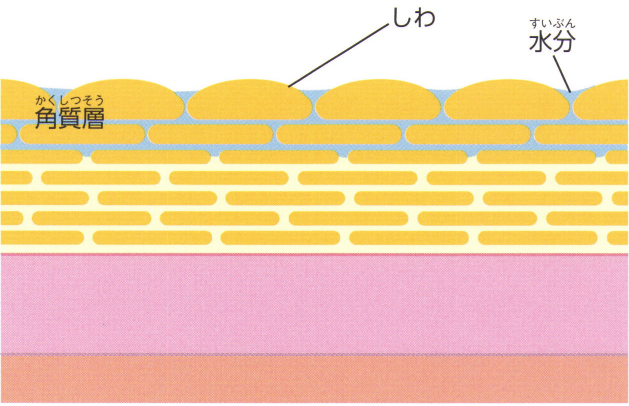



花粉症って何?
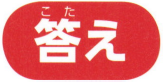 植物の花粉がひきおこす病気です
植物の花粉がひきおこす病気です
 人の体にはもともと、細菌やウイルスなどのわるいものがはいりこむと、みつけだしておいだすしくみがあります。しかし、体に害がないものにもまちがって反応してしまうことがあります。これを「アレルギー」といいます。
人の体にはもともと、細菌やウイルスなどのわるいものがはいりこむと、みつけだしておいだすしくみがあります。しかし、体に害がないものにもまちがって反応してしまうことがあります。これを「アレルギー」といいます。
花粉症は、植物の花粉にたいしてこの仕組みが強くはたらき、いろいろな症状をひきおこす病気です。空気中の花粉が鼻や目にはいると、くしゃみや鼻水がでたり、目がかゆくなって涙がでたりします。
 現在、日本人の4人に1人が花粉症にかかっているといわれます。
現在、日本人の4人に1人が花粉症にかかっているといわれます。
花粉症はスギ花粉によるものが多く、早いところでは2月からとびはじめ、2か月ほどつづきます。とくに、雨の後の晴れた日の昼間にとぶことが多いようです。
スギのほかにも、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサなど、日本には、アレルギーの原因になる植物が、およそ60種類もあるといわれています。
 花粉症の原因になる主な植物
花粉症の原因になる主な植物
 ハンノキ(春)
ハンノキ(春)

 スギ(春)
スギ(春)

 カモガヤ(夏)
カモガヤ(夏)

 ホソムギ(春~夏)
ホソムギ(春~夏)

 ブタクサ(夏~秋)
ブタクサ(夏~秋)

 ヨモギ(夏~秋)
ヨモギ(夏~秋)

131
正座をするとどうして足がしびれるの?
 体の重みで血のめぐりがわるくなるから
体の重みで血のめぐりがわるくなるから
 現代のくらしでは、いすにすわることがふえて、正座をすることは少なくなりました。でも、きちんとした場面で正座をすることがありますね。
現代のくらしでは、いすにすわることがふえて、正座をすることは少なくなりました。でも、きちんとした場面で正座をすることがありますね。
しばらく正座をしていると、足がしびれてきて、あるくどころか、たつこともできなくなってしまいます。
 足がしびれるのは、体重におされて足の血管に血がながれにくくなって、神経がまひしてしまうからです。足をうごかすと、また血がながれますが、今度は神経が敏感になりすぎてジンジンといういたみをかんじるようになります。
足がしびれるのは、体重におされて足の血管に血がながれにくくなって、神経がまひしてしまうからです。足をうごかすと、また血がながれますが、今度は神経が敏感になりすぎてジンジンといういたみをかんじるようになります。
 正座をしても足がしびれにくくなる方法として、同じところに体重がかからないように体の位置をずらしたり、親指同士をかさねて、ときどき上下をいれかえたりするのがよいといわれています。
正座をしても足がしびれにくくなる方法として、同じところに体重がかからないように体の位置をずらしたり、親指同士をかさねて、ときどき上下をいれかえたりするのがよいといわれています。
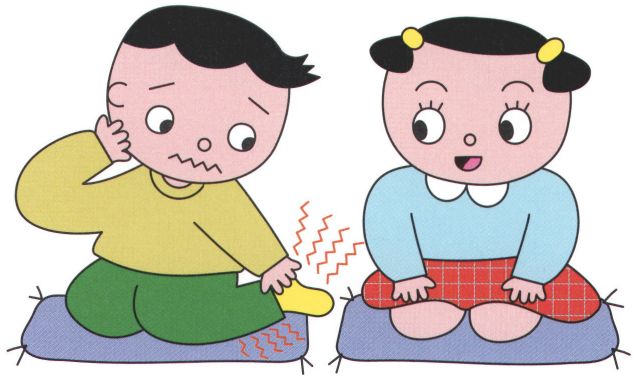
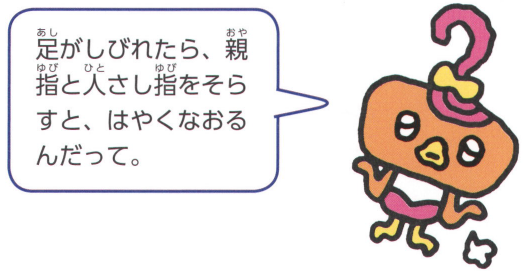
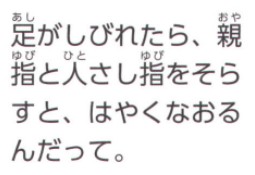
かき氷をたべると頭がキーンといたくなるのはなぜ?
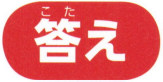 つめたさの情報がいたみとまちがわれるから
つめたさの情報がいたみとまちがわれるから
 かき氷をいそいでたべると、こめかみや頭のうしろにキーンといういたみをかんじることがありますね。この頭痛は、正式に「アイスクリーム頭痛」という名前があります。アイスクリーム頭痛がおこる原因は2つあるとかんがえられています。
かき氷をいそいでたべると、こめかみや頭のうしろにキーンといういたみをかんじることがありますね。この頭痛は、正式に「アイスクリーム頭痛」という名前があります。アイスクリーム頭痛がおこる原因は2つあるとかんがえられています。
1つは、口の中がひやされると、脳は体温がさがらないように、血をたくさんながそうとして、血管をひろげます。すると、頭の血管に炎症がおきていたみをかんじます。
もう1つは、つめたすぎて、のどの感覚を脳につたえる神経が、「つめたい」という情報をまちがって「いたい」と脳につたえてしまうためです。
アイスクリーム頭痛は長くはつづかないので、心配はありませんが、いそがずにゆっくりたべると、いたみをかんじにくいようです。
 アイスクリーム頭痛は、かき氷だけでなくアイスクリームやつめたい飲み物でもおこる。
アイスクリーム頭痛は、かき氷だけでなくアイスクリームやつめたい飲み物でもおこる。

第3章 身のまわりのなぜ?

134
セーターをぬぐとパチッとするのはなぜ?
 下着とセーターにたまった静電気が放電されるから
下着とセーターにたまった静電気が放電されるから
 ものには、ふつう、プラスとマイナスの電気が同じ量だけふくまれています。しかし、ものをこすりあわせると、一方がもっているマイナスの電気がもう一方にうつり、マイナスの電気を多くもったものとプラスの電気を多くもったものができるのです。これが「静電気」です。こするくみあわせによって、プラスとマイナスのどちらの電気を多くもつかがきまります。
ものには、ふつう、プラスとマイナスの電気が同じ量だけふくまれています。しかし、ものをこすりあわせると、一方がもっているマイナスの電気がもう一方にうつり、マイナスの電気を多くもったものとプラスの電気を多くもったものができるのです。これが「静電気」です。こするくみあわせによって、プラスとマイナスのどちらの電気を多くもつかがきまります。
 セーターをきていると、セーターと体(または中にきている衣服)がこすれあい、一方はマイナスの電気、もう一方はプラスの電気が多い状態になります。
セーターをきていると、セーターと体(または中にきている衣服)がこすれあい、一方はマイナスの電気、もう一方はプラスの電気が多い状態になります。
セーターをぬぐと、プラスとマイナスの電気がひきはがされてしまいます。すると、プラスとマイナスの量をひとしくするためマイナスの電気が移動し、そのとき「パチッ」と電気をかんじるのです。
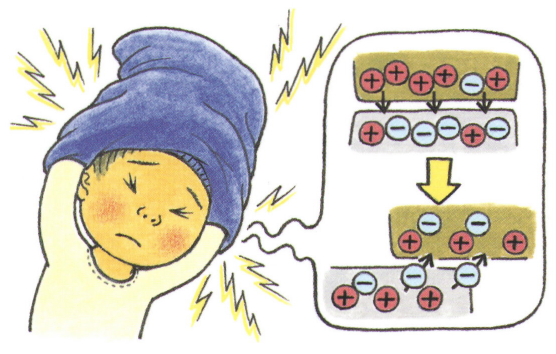
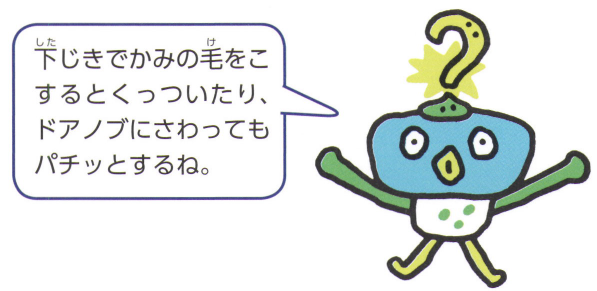
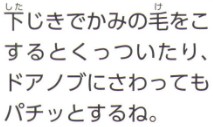
 ゴム風船でゆらゆらふわふわあそび
ゴム風船でゆらゆらふわふわあそび
静電気を利用して、ティッシュペーパーの人形をおどらせてあそぼう。

細長いゴム風船、ティッシュペーパー、マフラーやかわいた布、セロハンテープ

ティッシュペーパーをちぎって、すきな形をつくり、下のはしをつくえにセロハンテープでとめる。

ふくらませたゴム風船をマフラーなどでよくこすり、ティッシュペーパーにちかづける。
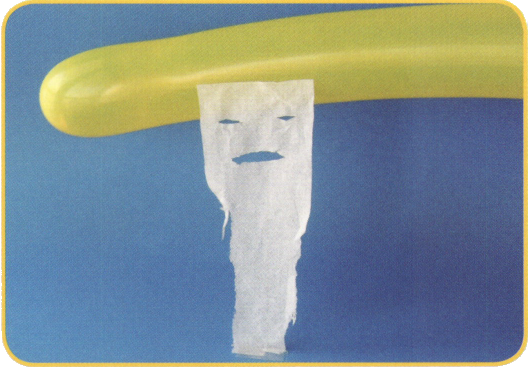
 ゴム風船をこすると静電気がおこる
ゴム風船をこすると静電気がおこる
ゴム風船をこすると、ゴム風船にはマイナスの電気がたまった状態になります。この風船をティッシュペーパーにちかづけると、ティッシュペーパーのプラスの電気が風船にひきつけられて、くっつきます。
135
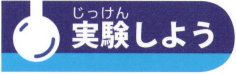 電気コップで静電気をかんじよう
電気コップで静電気をかんじよう
静電気をためる電気コップをつくって、静電気をしらべてみよう!
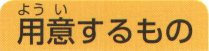
使い捨てのプラスチックのコップ3こ、アルミホイル、はさみ、油性ペン、セロハンテープ、細長いゴム風船、マフラーやかわいた布

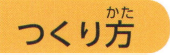
①プラスチックのコップ1つをきりひらく。側面にそって、たてにはさみできりひらき、ふちと底をきりとる。
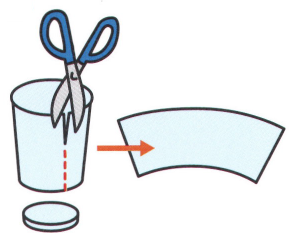
②きりひらいたコップをアルミホイルの上におき、油性ペンでなぞってはさみできる。同じようにして2枚つくる。

③2つのコップに②のアルミホイルをまいて、セロハンテープでとめる。
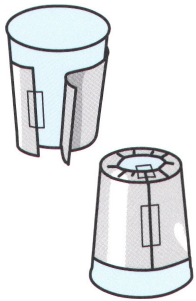
④アルミホイルを15
15
の大きさにきり、1
幅におって、アンテナをつくる。
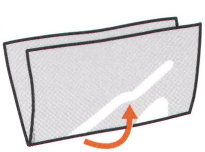
⑤コップを2こかさねる。アンテナを図のようにまげて、かさねたコップとコップの間にはさむ。
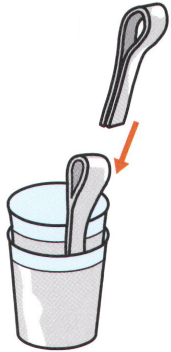
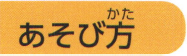
①ゴム風船をマフラーなどでよくこすって静電気をおこし、風船をアンテナにちかづける。これを何度もくりかえして、アンテナに電気をためる。
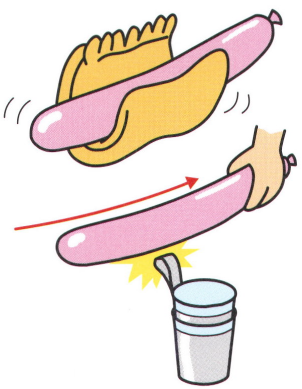
②部屋をくらくする。はさみをひらき、かた方の刃をアンテナに、もう片方をコップの側面にちかづけると、一瞬だけ電気がはしるのがみえる。

③もう一度電気をコップにためる。手にコップをもち、すばやく指でアンテナをさわると、バチッと電気がかんじられる。数人で手をつないでもできる。

 電気コップのひみつ
電気コップのひみつ
金属や水は電気をながしやすい性質があります。金属のアルミホイルに静電気がたまり、金属のはさみの刃や、水分を多くもつ人の体にふれると、急激に放電するため、バチッとかんじるのです。
136
乾電池には電気がはいっているの?
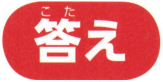 電気がはいっているのではなく、乾電池の中で電気をつくっています
電気がはいっているのではなく、乾電池の中で電気をつくっています
 乾電池は、2種類の金属を液体の中にいれると、電子の移動がおきて、電気がおこる性質を利用して、電気をつくっています。
乾電池は、2種類の金属を液体の中にいれると、電子の移動がおきて、電気がおこる性質を利用して、電気をつくっています。
乾電池には、プラス極とマイナス極があります。この2つをつなぐと、マイナス極の亜鉛という金属が化学反応をおこして、電子が電解液にとけだします。とけだした電子はマイナス極から導線をつたってながれて電気としてはたらき、プラス極にもどります。これがつづく間、電気がながれつづけるのです。
 乾電池には、マンガン電池とアルカリ電池があります。アルカリ電池はマンガン電池よりもパワーがあり、長持ちします。
乾電池には、マンガン電池とアルカリ電池があります。アルカリ電池はマンガン電池よりもパワーがあり、長持ちします。
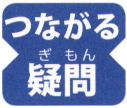 電池にはどのくらいの種類があるの?
電池にはどのくらいの種類があるの?
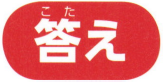 つかい道によっていくつかの種類の電池があります
つかい道によっていくつかの種類の電池があります
 電池は大きくわけて、1回でつかいきりの「一次電池」と充電してくりかえしつかえる「二次電池」の2種類があります。
電池は大きくわけて、1回でつかいきりの「一次電池」と充電してくりかえしつかえる「二次電池」の2種類があります。
一次電池には、一般的につかわれるマンガン電池やアルカリ電池などの乾電池、ボタン電池という平たい形をした電池があります。二次電池には、充電式の乾電池、携帯電話やゲーム機、自動車のバッテリーなどがあります。つかわれている金属によって「アルカリ電池」「鉛蓄電池」「リチウムイオン電池」「ニカド電池」とよばれます。
 乾電池は、大きい順に「単1」「単2」「単3」「単4」「単5」にわかれています。「単」は「単位電池」という意味で、いくつかをまとめた電池ではなく、1つの電池だということをあらわしています。
乾電池は、大きい順に「単1」「単2」「単3」「単4」「単5」にわかれています。「単」は「単位電池」という意味で、いくつかをまとめた電池ではなく、1つの電池だということをあらわしています。
 ボタン電池
ボタン電池

 いろいろな乾電池
いろいろな乾電池
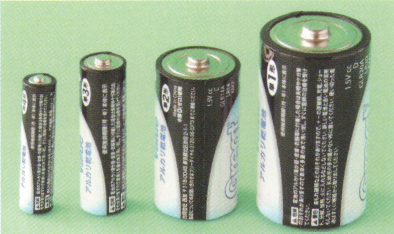
 デジタルカメラなどの器機につかわれるリチウムイオン電池。
デジタルカメラなどの器機につかわれるリチウムイオン電池。

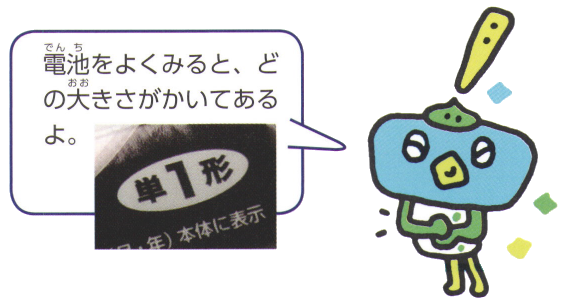
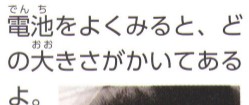

137
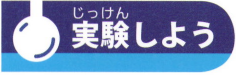 木炭で電池をつくろう
木炭で電池をつくろう
乾電池のしくみをつかって、自分でも電池をつくることができるよ。バーベキューなどでつかう木炭で、電池をつくってみよう!
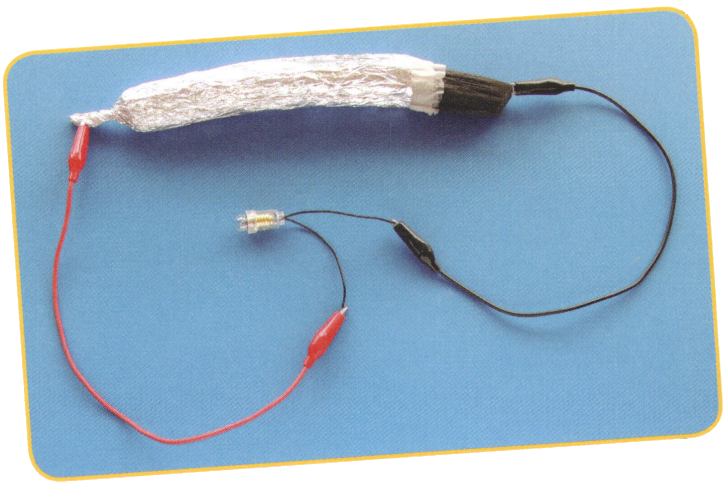
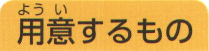
木炭(備長炭)(20
くらいの長さ)、LED豆電球、ソケット*、導線*、ミノムシクリップつきコード*、ペーパータオル、アルミホイル、水、塩
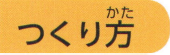
①こいめの食塩水をつくる。(底に塩がのこるくらいが目安)
②ペーパータオルで備長炭を図のようにまく。備長炭がかた方のはしからはみだすようにする。
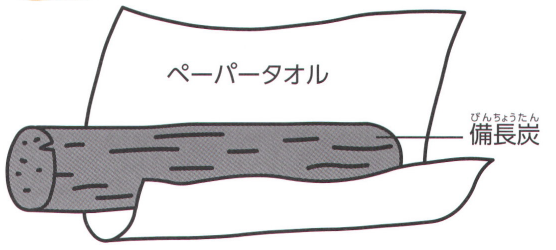
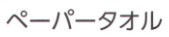

③ペーパータオルに食塩水をかけて、かるくしぼる。
④その上から図のようにアルミホイルをまき、アルミホイルのはしをねじる。そのとき、アルミホイルが備長炭にふれないようにすること。アルミホイルの上からぎゅっとにぎって密着させると、接触がよくなる。
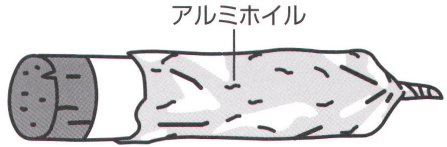

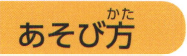
①豆電球をソケットにいれて、図のように導線をつなぐ。
②ミノムシクリップつきコードで木炭電池の両はしをはさみ、豆電球につなぐと、明りがつく。
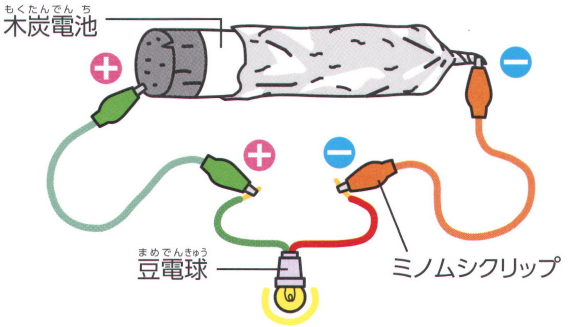





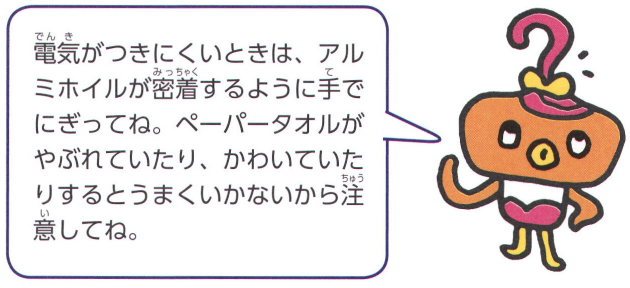
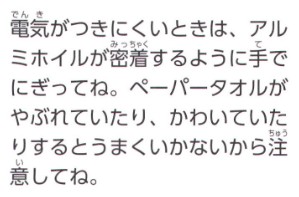
138
電気はどうやってできるの?
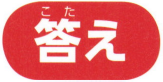 コイルの間で磁石をまわすと電気がうまれます
コイルの間で磁石をまわすと電気がうまれます
 電気は、コイル(電線をぐるぐるまいたもの)の間で磁石をまわすことでできます。たとえば、自転車のライトはコンセントも電池もありませんが、明りがつきます。自転車のタイヤがまわる力をつかってモーターをまわし、電気をつくることで、ライトの明かりがつくのです。
電気は、コイル(電線をぐるぐるまいたもの)の間で磁石をまわすことでできます。たとえば、自転車のライトはコンセントも電池もありませんが、明りがつきます。自転車のタイヤがまわる力をつかってモーターをまわし、電気をつくることで、ライトの明かりがつくのです。
 自転車のライトやおもちゃのモーターと、わたしたちがふだんつかっている電気をつくる発電所は、基本的に同じしくみで電気をつくっています。発電所では、巨大な発電機をまわすために、水の力や燃料をもやした熱の力をつかいます。
自転車のライトやおもちゃのモーターと、わたしたちがふだんつかっている電気をつくる発電所は、基本的に同じしくみで電気をつくっています。発電所では、巨大な発電機をまわすために、水の力や燃料をもやした熱の力をつかいます。
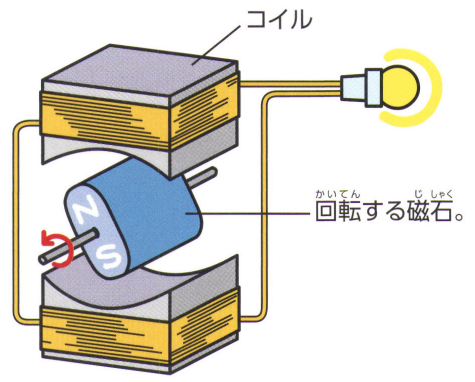

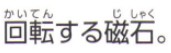
 自転車のライト。
自転車のライト。

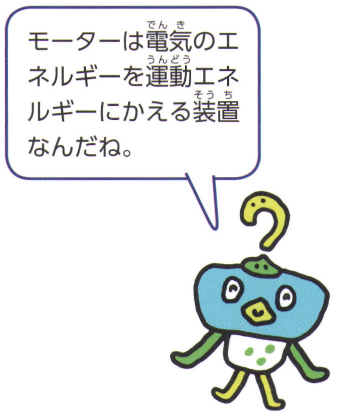
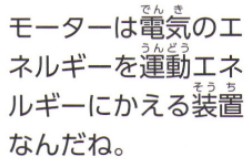
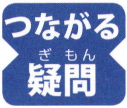 再生可能エネルギーって何?
再生可能エネルギーって何?
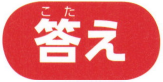 くりかえしずっとつかうことができる新しい発電方法です
くりかえしずっとつかうことができる新しい発電方法です
 わたしたちがふだんつかう電気は、発電所でつくられます。主に、水をつかった水力発電、石油や石炭をもやす火力発電、ウランをつかう原子力発電がありますが、つかわれている資源の多くは地球上にかぎられた量しかないので、いつかはなくなってしまいます。
わたしたちがふだんつかう電気は、発電所でつくられます。主に、水をつかった水力発電、石油や石炭をもやす火力発電、ウランをつかう原子力発電がありますが、つかわれている資源の多くは地球上にかぎられた量しかないので、いつかはなくなってしまいます。
 これに対して、再生可能エネルギーは、ずっとつかうことができる、新しい発電方法です。
これに対して、再生可能エネルギーは、ずっとつかうことができる、新しい発電方法です。
風をつかう風力発電、太陽の光をつかう太陽光発電、ゴミをもやした熱をつかう廃棄物発電、木くずや家畜のおしっこやうんちをつかうバイオマス発電、波の力をつかった波力発電など、さまざまな方法がためされ利用されています。
 太陽光発電のソーラーパネル
太陽光発電のソーラーパネル
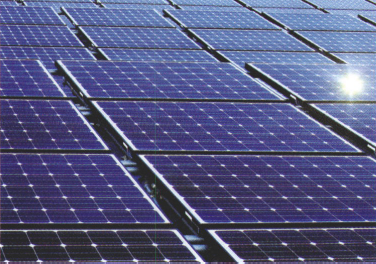
 風力発電の風車
風力発電の風車
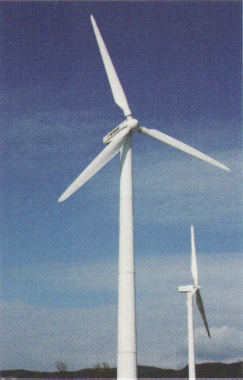
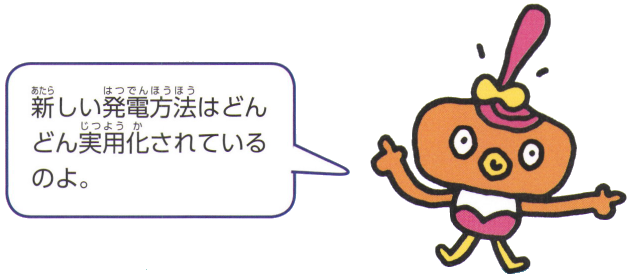
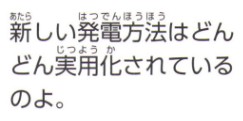
 身のまわりのLEDをみつけよう
身のまわりのLEDをみつけよう
長持ちして、環境にやさしいLEDは、いろいろなところでつかわれているよ。
どんなところでつかわれているのか、さがしてみましょう。
 信号機
信号機
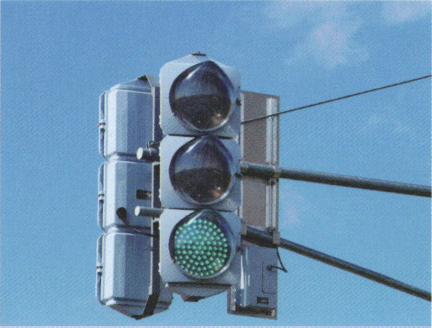
LEDの光はまっすぐにすすむので、遠くからでもみやすくなります。
 電光掲示板
電光掲示板

電車や高速道路、野球場やサッカースタジアムなどの掲示板もLED電球です。
 イルミネーション
イルミネーション

LEDは熱や紫外線をあまりださないので、木をいためにくいのです。
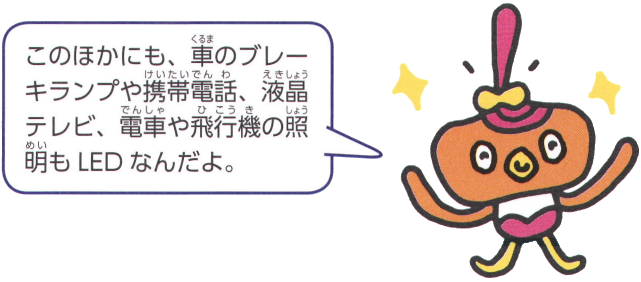
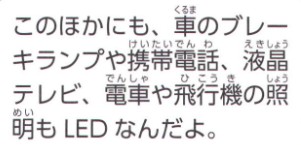
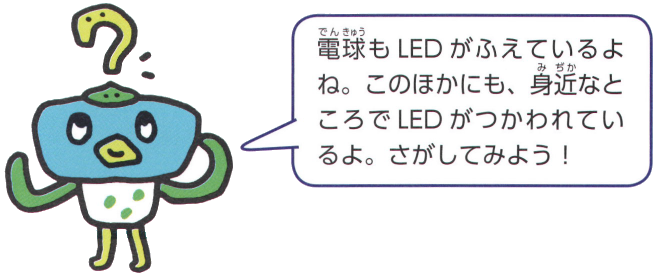
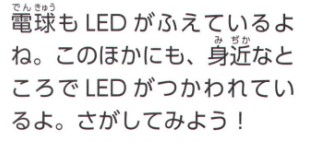
140.
電子レンジでものがあたたまるのはなぜ?
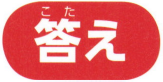 食べ物などにふくまれる水分が電波によってあたためられるから
食べ物などにふくまれる水分が電波によってあたためられるから
 食べ物を電子レンジにかけると、マイクロ波という電波が食べ物の水分をふるわせます。すると、食べ物にふくまれる水の分子がかきまわされ、ぶつかりあい、こすれあって摩擦がおこります。その摩擦の熱によって、食べ物があたたまるのです。
食べ物を電子レンジにかけると、マイクロ波という電波が食べ物の水分をふるわせます。すると、食べ物にふくまれる水の分子がかきまわされ、ぶつかりあい、こすれあって摩擦がおこります。その摩擦の熱によって、食べ物があたたまるのです。
 電子レンジは、水の分子をふるわせてあたためるので、水分がはいっていないものはあたたまりません。
電子レンジは、水の分子をふるわせてあたためるので、水分がはいっていないものはあたたまりません。
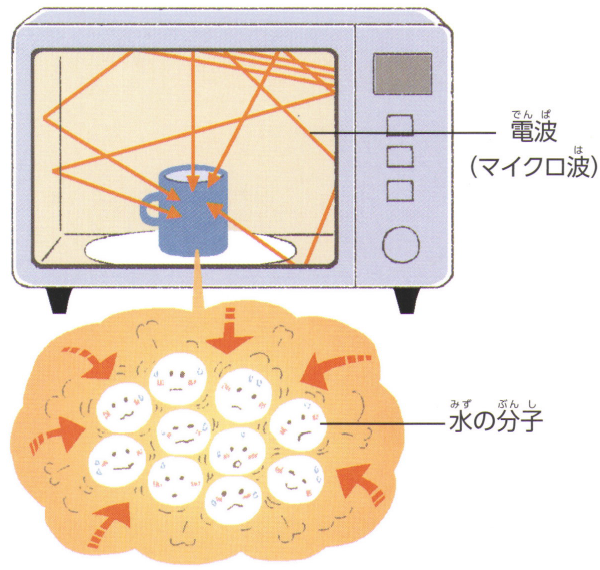
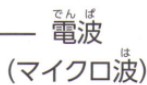
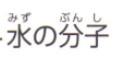
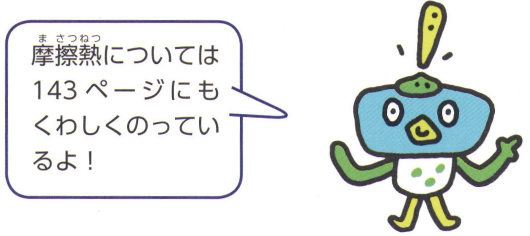
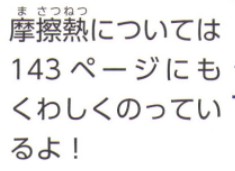
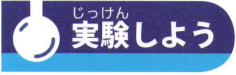 いろいろなものを電子レンジであたためよう
いろいろなものを電子レンジであたためよう
電子レンジでは、水分がないものはあたたまらないのは本当? 実験でたしかめよう!
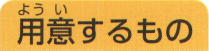
陶器のカップ、水、氷1~2こ
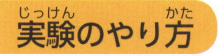
①陶器のカップの片方に水をいれ、電子レンジで2分あたためる。2分後、カップをそっとさわってみる。カップの温度はどうなったかな?
②氷を冷蔵庫からとりだして、すぐにカップにいれ、レンジで1分あたためる。1分後、氷のようすをみてみる。氷はとけているかな?
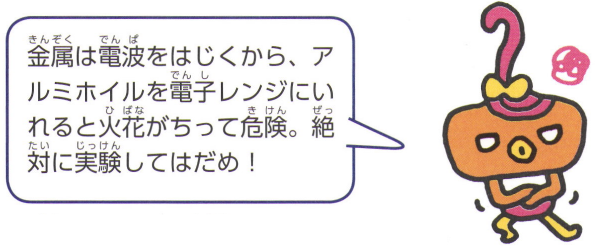
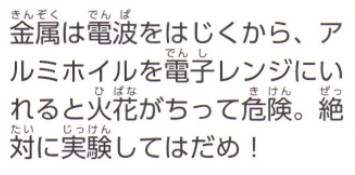
※器をつかうときは、表示をかならずたしかめましょう。
 あたたまらないものには理由がある!
あたたまらないものには理由がある!
ガラスや陶器は、水分がないのであたたまりません。中にはいっている水分があたたまると、器があつくなるのです。そのため、中に水分がはいっていない器は、電子レンジであたためてもあつくなりません。氷は水分でできていますが、カチコチにかたまって水の分子はうごくことができません。そのため、電子レンジにかけてもとけないのです。ただし、氷がとけている部分が少しでもあると、氷は電子レンジでとけてしまいます。
142
鉄でつくられた大きな船がしずまないのはなぜ?
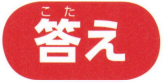 船をおしあげ、うかせようとする力がはたらくから
船をおしあげ、うかせようとする力がはたらくから
 ものを水にいれると、ものがおしのけた水の重さの分だけ、うかせようとする力がはたらきます。これを「浮力」といいます。
ものを水にいれると、ものがおしのけた水の重さの分だけ、うかせようとする力がはたらきます。これを「浮力」といいます。
 鉄のかたまりを水にいれるとしずんでしまいますが、同じ重さの鉄を中に空間があるおわんのような形にすると、おしのける水の量がふえるので、水にうかびます。空間の大きさ(体積)が大きいほど、浮力は大きくなります。船の中は、人や荷物をのせる空間がたくさんあります。そのため、浮力が大きくなって、重い鉄でできた船でもしずまないのです。
鉄のかたまりを水にいれるとしずんでしまいますが、同じ重さの鉄を中に空間があるおわんのような形にすると、おしのける水の量がふえるので、水にうかびます。空間の大きさ(体積)が大きいほど、浮力は大きくなります。船の中は、人や荷物をのせる空間がたくさんあります。そのため、浮力が大きくなって、重い鉄でできた船でもしずまないのです。
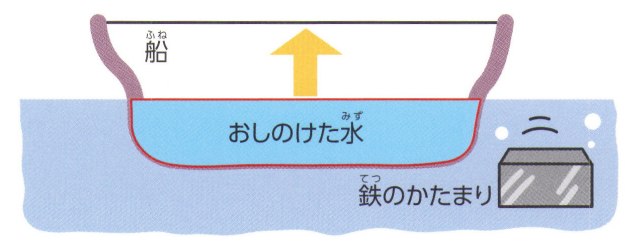

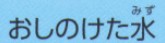
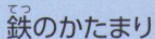
 船の中には空間がたくさんある。
船の中には空間がたくさんある。
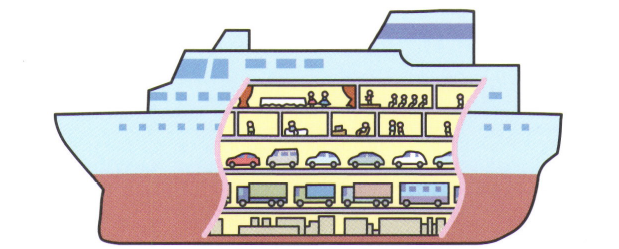
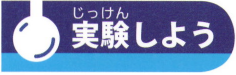 塩水と真水でうかび方はかわるかな?
塩水と真水でうかび方はかわるかな?
プールよりも海のほうが体がうくのはなぜ? 実験をして、その理由をさぐってみましょう。
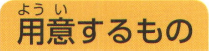
水1
、塩10
、深めの容器(バケツ、洗面器、ボウルなど)、うきしずみをしらべたいもの
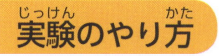
①まず容器に真水をいれ、しらべるものをいれて、うきしずみのようすを記録する。
②つぎに容器に塩水をいれ、同じものをいれてようすをしらべる。
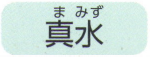
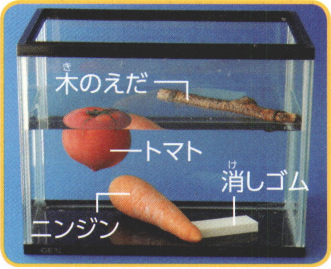
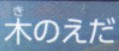

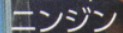
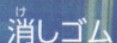
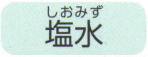
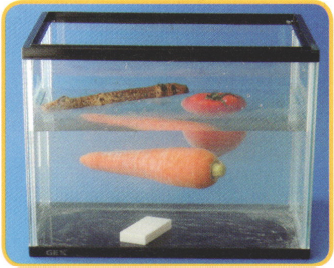
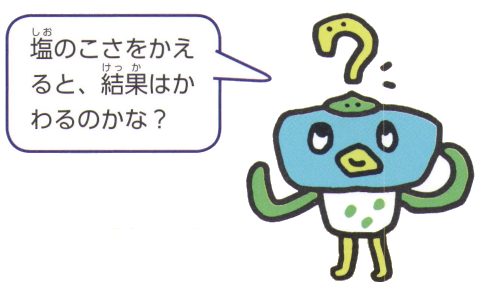
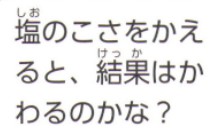
 塩水と真水では浮力がちがう!
塩水と真水では浮力がちがう!
真水ではしずんだけれど、塩水ではういたものがありましたか? 同じ量の塩水と真水の重さをくらべると、塩がとけているぶん、塩水のほうが重くなります。そのため、塩水のほうが、ものがおしのける水も重くなり、浮力が大きくなるのです。これが、プールよりも海のほうが体がうく理由です。
143
すべり台をすべるとなぜおしりがあつくなるの?
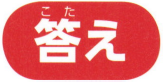 すべり台とおしりがこすれて、熱がうまれるから
すべり台とおしりがこすれて、熱がうまれるから
 ものと、ものとがこすれあうと、「摩擦」という力がはたらき、熱がうまれます。さむいときに手をこすりあわせるとあたたかくなりますね。これも、摩擦で熱がうまれるからです。
ものと、ものとがこすれあうと、「摩擦」という力がはたらき、熱がうまれます。さむいときに手をこすりあわせるとあたたかくなりますね。これも、摩擦で熱がうまれるからです。
すべり台でも同じことがおこります。すべり台とズボンのおしりがこすれあい、摩擦で熱がうまれるので、おしりがあつくかんじるのです。
 大昔の人は、木と木をこすりあわせて火をおこしていましたが、これも摩擦でおこる熱を利用していたのです。
大昔の人は、木と木をこすりあわせて火をおこしていましたが、これも摩擦でおこる熱を利用していたのです。
 こすれあうズボンのおしり(上)とすべり台(下)。
こすれあうズボンのおしり(上)とすべり台(下)。
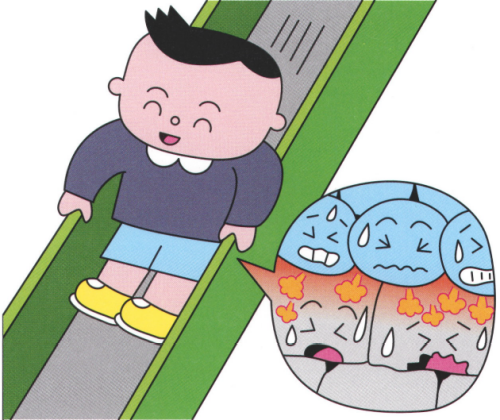
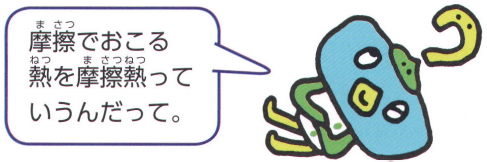
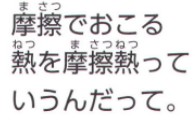
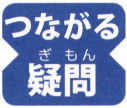 摩擦の力がなくなると、どうなるの?
摩擦の力がなくなると、どうなるの?
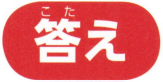 あるいたりはしったりすることができなくなります
あるいたりはしったりすることができなくなります
 わたしたちは、道路はふつうにあるくことができますが、氷の上はつるつるすべってしまい、うまくあるくことができませんね。道路のようなざらざらしたものとの間では摩擦の力が大きくなりますが、つるつるした氷の表面は摩擦がおきにくいため、すべってしまうのです。
わたしたちは、道路はふつうにあるくことができますが、氷の上はつるつるすべってしまい、うまくあるくことができませんね。道路のようなざらざらしたものとの間では摩擦の力が大きくなりますが、つるつるした氷の表面は摩擦がおきにくいため、すべってしまうのです。
もしも、摩擦の力がなくなったら、道路は、氷の上をあるくのと同じ状態になります。もちろん、はしることもできません。
 ものをうごかすときや、楽器の弦をこすって音をだすときなど、あらゆるところに摩擦の力がはたらいています。
ものをうごかすときや、楽器の弦をこすって音をだすときなど、あらゆるところに摩擦の力がはたらいています。
 氷の上をすべるスケート。
氷の上をすべるスケート。

 くつの底。
くつの底。
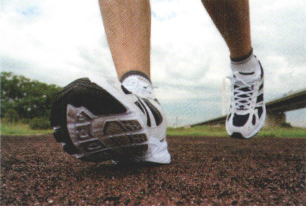
 弦をこすって音をだす弦楽器。
弦をこすって音をだす弦楽器。

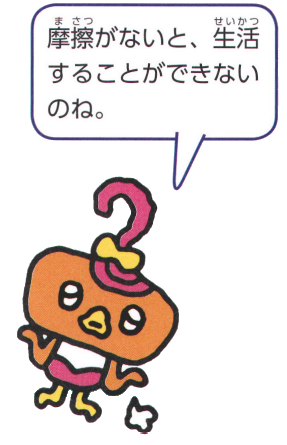
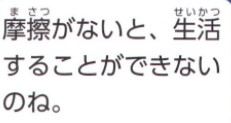
144
紙はどうやってリサイクルされるの?
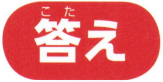 あつめた紙をどろどろにとかし、もう一度紙をつくります
あつめた紙をどろどろにとかし、もう一度紙をつくります
 廃品回収などであつめられた紙は、新聞・雑誌・段ボールなどの種類ごとに分別され、製紙工場へはこばれます。
廃品回収などであつめられた紙は、新聞・雑誌・段ボールなどの種類ごとに分別され、製紙工場へはこばれます。
分別した紙は「パルパー」という大きなミキサーで水と一緒にどろどろにとかされます。このとき、ホチキスの針や紙以外のものがとりのぞかれます。その後、薬品をつかってインクやよごれをとりのぞいてあらい、「古紙パルプ」という紙のもとになります。パルプとは紙の原料のことです。
古紙パルプに新しいパルプなどをくわえてふたたび紙をつくります。
 こうしてうまれかわった再生紙は、紙の質によって、段ボールやトイレットペーパー、商品の梱包材、新聞、雑誌などになります。また、細かい綿のようにして、住宅の断熱・防音材にすることもあります。
こうしてうまれかわった再生紙は、紙の質によって、段ボールやトイレットペーパー、商品の梱包材、新聞、雑誌などになります。また、細かい綿のようにして、住宅の断熱・防音材にすることもあります。
 再生紙でつくられる製品
再生紙でつくられる製品



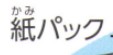

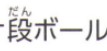

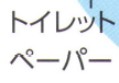
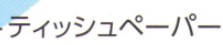
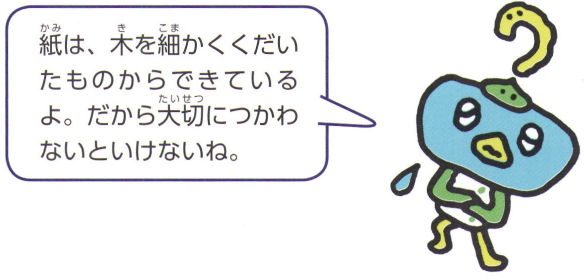
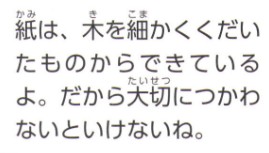
 リサイクルのマークをさがそう
リサイクルのマークをさがそう
リサイクルがしやすいように、紙製品にはリサイクルのマークがついているよ。さがしてみよう!
 グリーンマーク
グリーンマーク

再生紙をつかっている商品をしめすマーク。
 エコマーク
エコマーク
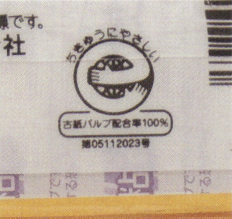
環境をまもるのに役だつとみとめられる商品につけられるマーク。
 紙パック識別マーク
紙パック識別マーク
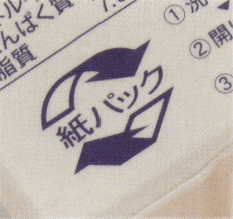
リサイクルできる紙パックであることをしめすマーク。
 紙識別マーク
紙識別マーク

リサイクルできる紙でつくられている容器・梱包材であることをしめすマーク。
 段ボール製容器包装マーク
段ボール製容器包装マーク
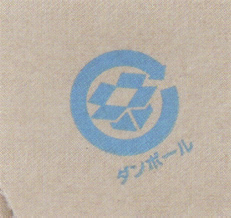
リサイクルできる段ボールをつかっていることをしめすマーク。
145
 紙パックで手づくりコースターをつくろう
紙パックで手づくりコースターをつくろう

・ジュースや牛乳などの紙パック(1
)2本分
・洗面器(大きくてふかいもの。バケツなどでもよい)1つ
・洗濯のり(またはでんぷんのり)60
・ミキサー(またはフードプロセッサー、ジューサー)
・ハンカチなどの布1枚
・新聞紙
・水
・タオル1枚
・下じき1枚
・大きめのざる
 色紙をまぜてつくったおしゃれなコースター。
色紙をまぜてつくったおしゃれなコースター。


①紙パックを2~3日水につけておく。
②やわらかくなったら表面のフィルムをはがし、小さくちぎる。
 表面のフィルムをはがす。
表面のフィルムをはがす。
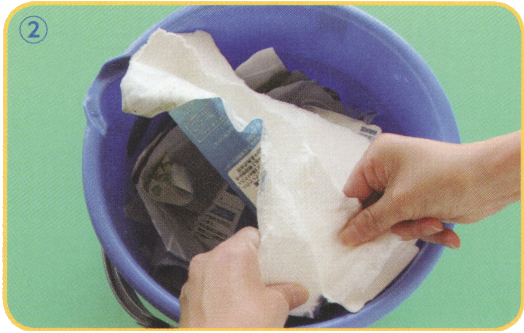
③水1
と一緒に②をミキサーにかける。ミキサーなどがないときは、作業がたいへんですが、どろどろになるまで手でこまかくちぎってもできる。
※ミキサーにはいらないときは、数回にわける。
④洗面器などに③をうつし、洗濯のりをくわえてよくまぜる。これが紙のもとになる。
⑤ざるを④の容器にしずめて、紙のもとをすくう。(ざるをたてながらしずめると、すくいやすい。)
 ざるで紙のもとをすくいあげる。
ざるで紙のもとをすくいあげる。

⑥5
ほどのあつさになったら、ざるをひきあげる。ひきあげた紙のもとを下じきの上にはりつける。(ざるの上に下じきをあてて、くるっとひっくりかえすとやりやすい。)
 下じきに紙のもとをはりつける。
下じきに紙のもとをはりつける。

⑦下じきの上で紙の形をととのえる。
⑧新聞紙の上に、タオル、布の順番でかさね、その上にそっと紙のもとをおく。紙のもとは布の片側半分におくようにし、その上にタオルと布をおりかえして、上から平らなおもしをして水をきる。
⑨布から紙をそっとはがし、紙をかわかす。(窓ガラスにはりつけるとかわきやすい。)
⑩かわいた紙を、すきな大きさにきる。
※⑤で紙をすくうときに、押し花や色紙をいれると、もようがはいったコースターになる。

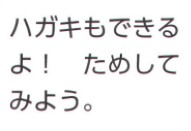
146
ジェットコースターはなぜさかさまでもおちないの?
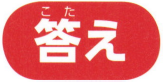 中心の外側にむかおうとする「遠心力」がはたらくから
中心の外側にむかおうとする「遠心力」がはたらくから
 ジェットコースターは、高い場所から、スピードをつけてのぼったりおりたり、円をえがくように回転したりします。円をえがいているとき、ものすごいスピードでまわっていると、円の中心からはなれて、外側にむかおうとする力がはたらきます。これを「遠心力」といいます。ジェットコースターにも、この遠心力がはたらくため、さかさまになってもおちてこないのです。
ジェットコースターは、高い場所から、スピードをつけてのぼったりおりたり、円をえがくように回転したりします。円をえがいているとき、ものすごいスピードでまわっていると、円の中心からはなれて、外側にむかおうとする力がはたらきます。これを「遠心力」といいます。ジェットコースターにも、この遠心力がはたらくため、さかさまになってもおちてこないのです。
 身近なところにも、遠心力ははたらいています。洗濯機の脱水機能は、洗濯槽を高速でまわすことで遠心力をおこし、水をとばして脱水します。また、ハンマー投げも、ハンマーをぐるぐるまわし、遠心力をつかう競技です。
身近なところにも、遠心力ははたらいています。洗濯機の脱水機能は、洗濯槽を高速でまわすことで遠心力をおこし、水をとばして脱水します。また、ハンマー投げも、ハンマーをぐるぐるまわし、遠心力をつかう競技です。
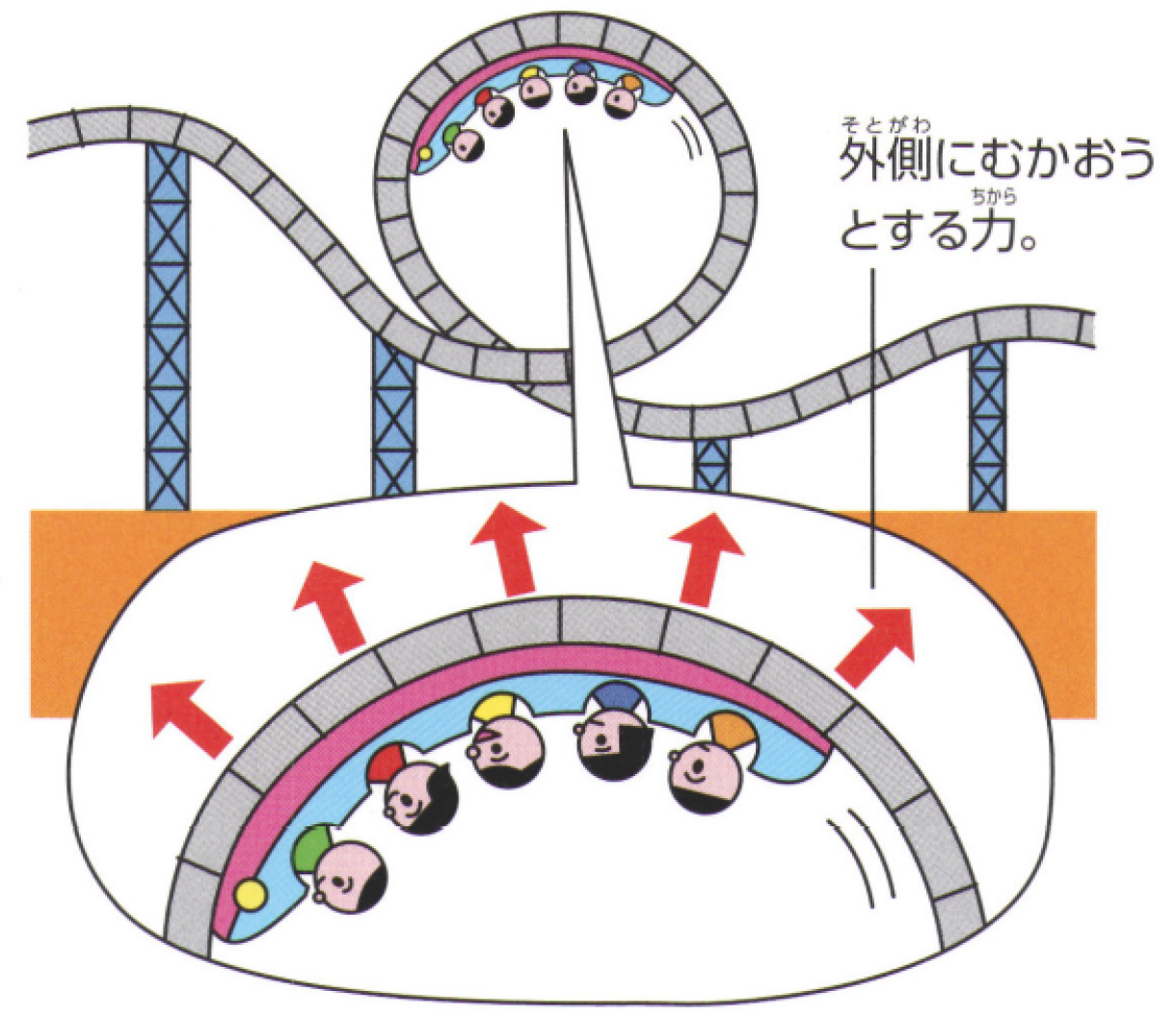
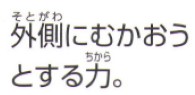
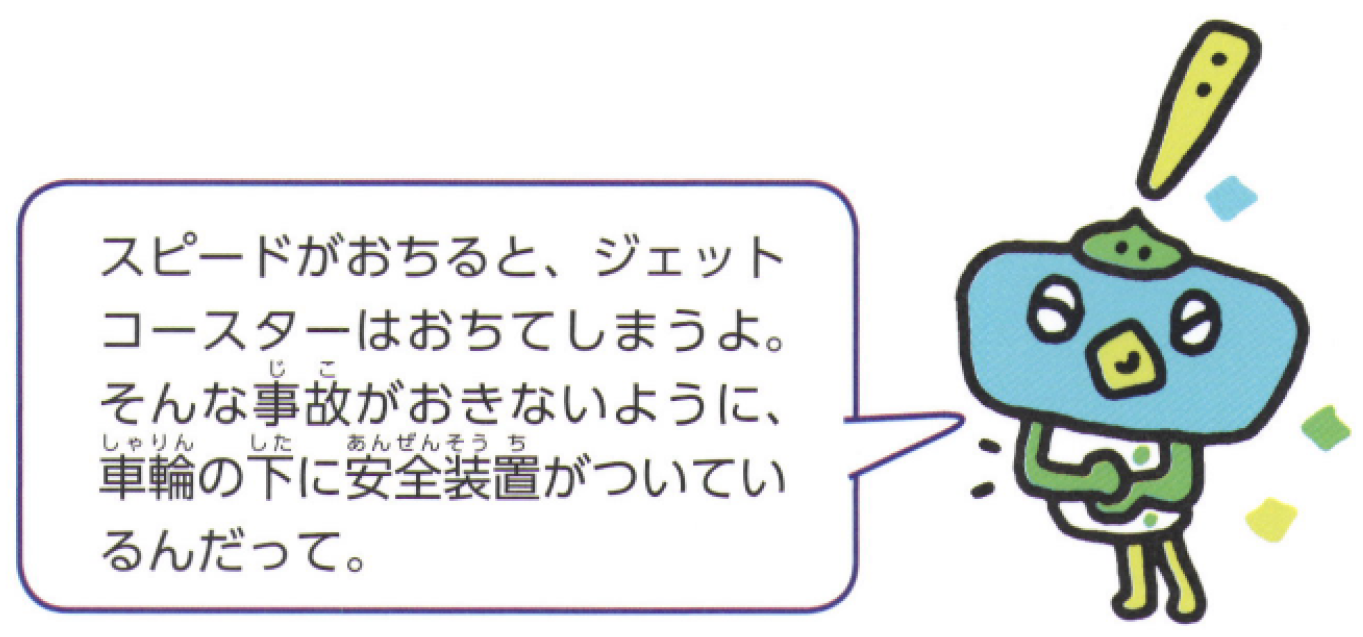
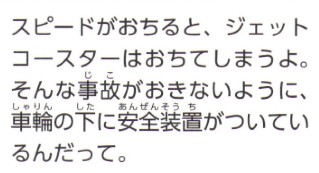
 遠心力をかんじてみよう
遠心力をかんじてみよう
バケツをつかって、自分でできる遠心力の実験をしてみよう!
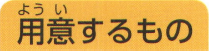
バケツ、水
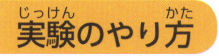
水をいれたバケツを、ふりこのようにふって、いきおいをつけてから一気にまわす。

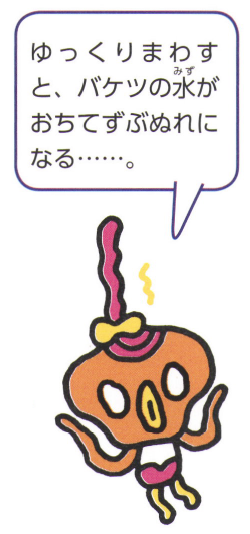
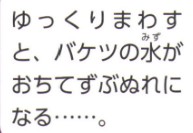
 バケツの水がこぼれない理由
バケツの水がこぼれない理由
バケツをいきおいよくまわすと、遠心力がはたらきます。バケツと中の水が、まわした円の中心から外側へむかおうとするため、水はおちてこないのです。
海やプールなど、水にぬれてもいい場所でやってみましょう。バケツをゆっくりまわすと遠心力のちがいがよくわかります。
147
自転車はどうしてたおれないの?
 車輪のかたむきを一定にたもとうとする力がはたらくから
車輪のかたむきを一定にたもとうとする力がはたらくから
 回転している自転車の車輪には、回転する面を一定のむきにたもとうとする力がはたらきます。
回転している自転車の車輪には、回転する面を一定のむきにたもとうとする力がはたらきます。
ほかから力をくわえられなければ、ものはとまっている状態やうごいている状態がずっとかわらずにつづくのです。これを「慣性の法則」といいます。
 自転車がたおれない理由は、これだけではありません。人は自転車にのっているとき、自然にバランスをとっています。自転車がかたむいた方向にハンドルをきり、体を反対側にかたむけることでたおれないようにしているのです。
自転車がたおれない理由は、これだけではありません。人は自転車にのっているとき、自然にバランスをとっています。自転車がかたむいた方向にハンドルをきり、体を反対側にかたむけることでたおれないようにしているのです。
また、ハンドルの軸になっているパイプは、少し前にかたむいています。ハンドルが正面をむいたときに、重心がひくくなり、安定してはしれるのです。

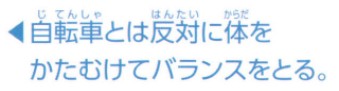
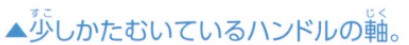
 身近な「慣性の法則」をさがそう
身近な「慣性の法則」をさがそう
「慣性の法則」は、わたしたちのまわりにたくさんあります。よく観察して、みつけてみましょう。
 まわるコマ
まわるコマ

すばやく回転しているこまは、かたむいても同じ状態でまわりつづけます。
 のりものの急ブレーキ
のりものの急ブレーキ

急ブレーキがかかると、体が前のめりになります。のりものがとまろうとしても、体はそのままの速さでうごこうとするからです。
 だるまおとし
だるまおとし
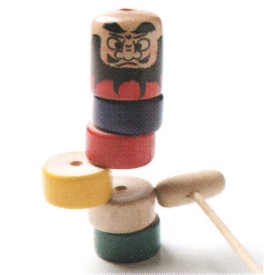
途中のこまをうつと、うたなかったこまはとまっていようとするため、うったこまだけとびだします。
 エレベーターの中
エレベーターの中

体はとまっていようとするのに対し、エレベーターはうごくので、上にいくときは床におしつけられるように、下におりるときは体がういたような感覚になります。
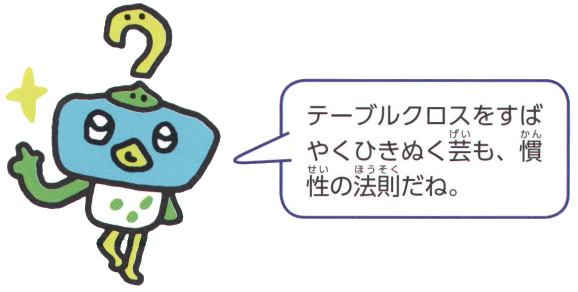
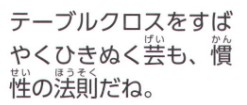
148
ブーメランはなぜもどってくるの?
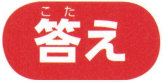 ブーメランをおしあげる力とすすむ方向をかえる力がはたらくから
ブーメランをおしあげる力とすすむ方向をかえる力がはたらくから
 とんでいるときのブーメランには、2種類の力がくわえられています。1つ目はブーメランがおちないように上へとおしあげる力。2つ目はブーメランをかたむける力です。この2つの力で、ブーメランは空中でかたむきながら回転し、カーブをえがいてなげた場所にもどってきます。
とんでいるときのブーメランには、2種類の力がくわえられています。1つ目はブーメランがおちないように上へとおしあげる力。2つ目はブーメランをかたむける力です。この2つの力で、ブーメランは空中でかたむきながら回転し、カーブをえがいてなげた場所にもどってきます。
 なぜ、かたむきながら回転すると、カーブをえがくのでしょうか。たとえば、自転車にのっているときに体を左右どちらかにかたむけると、自転車も自然に同じ方向にまがりますね。回転している車輪がかたむくと、その方向にまがるのです。ブーメランにも同じことがおこっているのです。
なぜ、かたむきながら回転すると、カーブをえがくのでしょうか。たとえば、自転車にのっているときに体を左右どちらかにかたむけると、自転車も自然に同じ方向にまがりますね。回転している車輪がかたむくと、その方向にまがるのです。ブーメランにも同じことがおこっているのです。
 ブーメランのはじまりはとても古く、最も古いものは、オーストラリアでみつかった1万5000年前のものだといわれています。狩りや儀式などにつかわれていました。
ブーメランのはじまりはとても古く、最も古いものは、オーストラリアでみつかった1万5000年前のものだといわれています。狩りや儀式などにつかわれていました。
 ブーメランのうごき。
ブーメランのうごき。
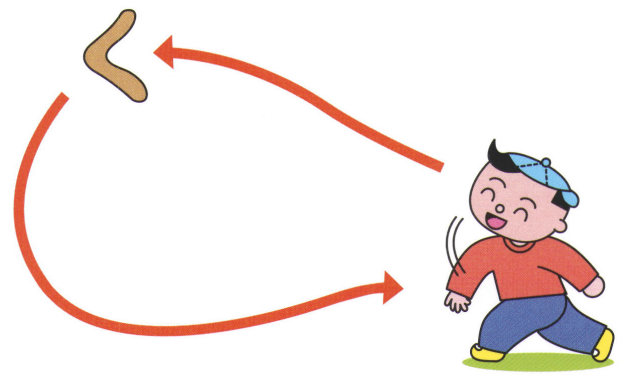
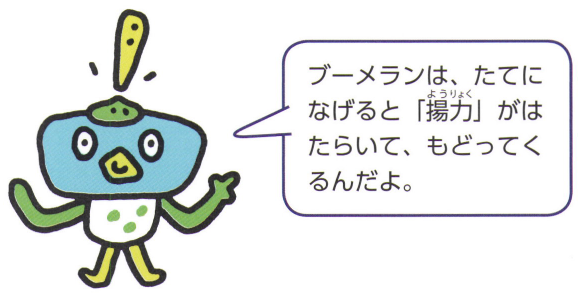
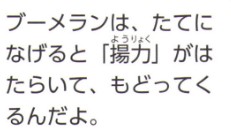
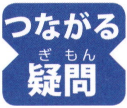 ブーメランにはたらく力はどこからうまれるの?
ブーメランにはたらく力はどこからうまれるの?
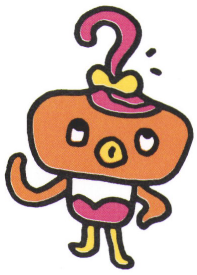
 ブーメランの羽根の形からうまれます
ブーメランの羽根の形からうまれます
 ブーメランの断面をみると、上が少しふくらんだ形をしています。羽根にそって空気がながれると、羽根の上側では空気におされる力が弱くなり、ブーメランをおしあげようとする力がはたらきます。この力が「揚力」です。「揚力」は、飛行機やパラグライダーのつばさにもはたらいています。揚力があるおかげで、飛行機やパラグライダーは空をとんでいるのです。
ブーメランの断面をみると、上が少しふくらんだ形をしています。羽根にそって空気がながれると、羽根の上側では空気におされる力が弱くなり、ブーメランをおしあげようとする力がはたらきます。この力が「揚力」です。「揚力」は、飛行機やパラグライダーのつばさにもはたらいています。揚力があるおかげで、飛行機やパラグライダーは空をとんでいるのです。
 ブーメランの断面と揚力
ブーメランの断面と揚力

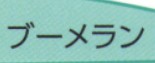


 羽根の上側では、空気におされる力が弱くなり、空気の流れのおそい下側からおしあげられる。
羽根の上側では、空気におされる力が弱くなり、空気の流れのおそい下側からおしあげられる。
149
 空とぶペーパーブーメランをつくろう
空とぶペーパーブーメランをつくろう
厚紙でかんたんにつくれるブーメラン。なげると回転しながらもどってきます。

厚紙(板目表紙ぐらいの厚さ)(13.52.5
を3枚)
はさみ、ホチキス、分度器
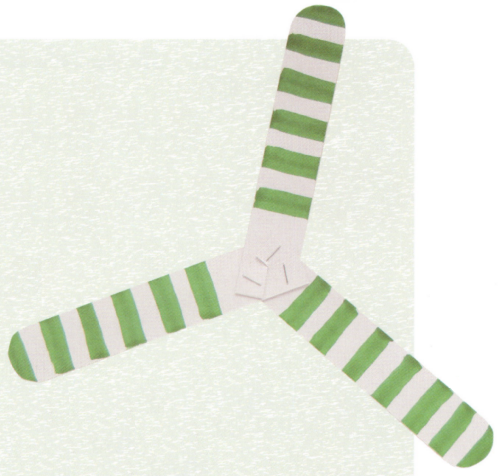

①厚紙の片側に、図のようにまん中に1
のきりこみをいれる。3枚とも同じようにする。
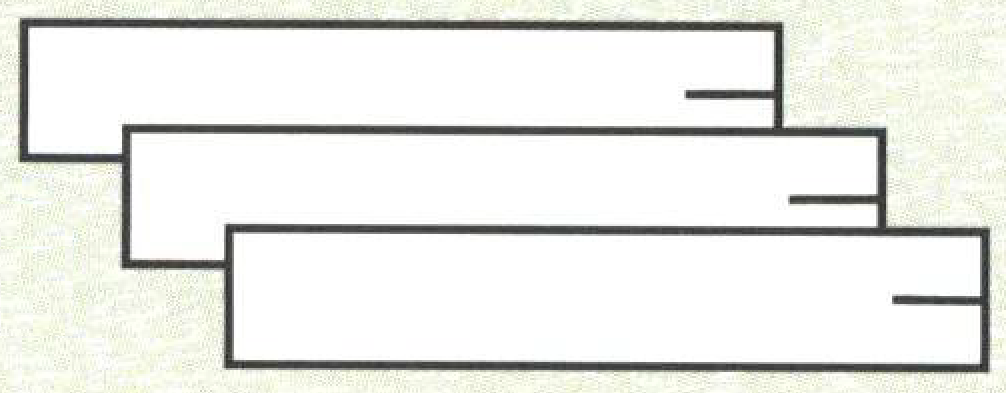
②2枚のきりこみをくみあわせてV字のような形にする。そこに残りの1枚もくみあわせ、3枚が同じ角度(120度ずつ)になるようにする。
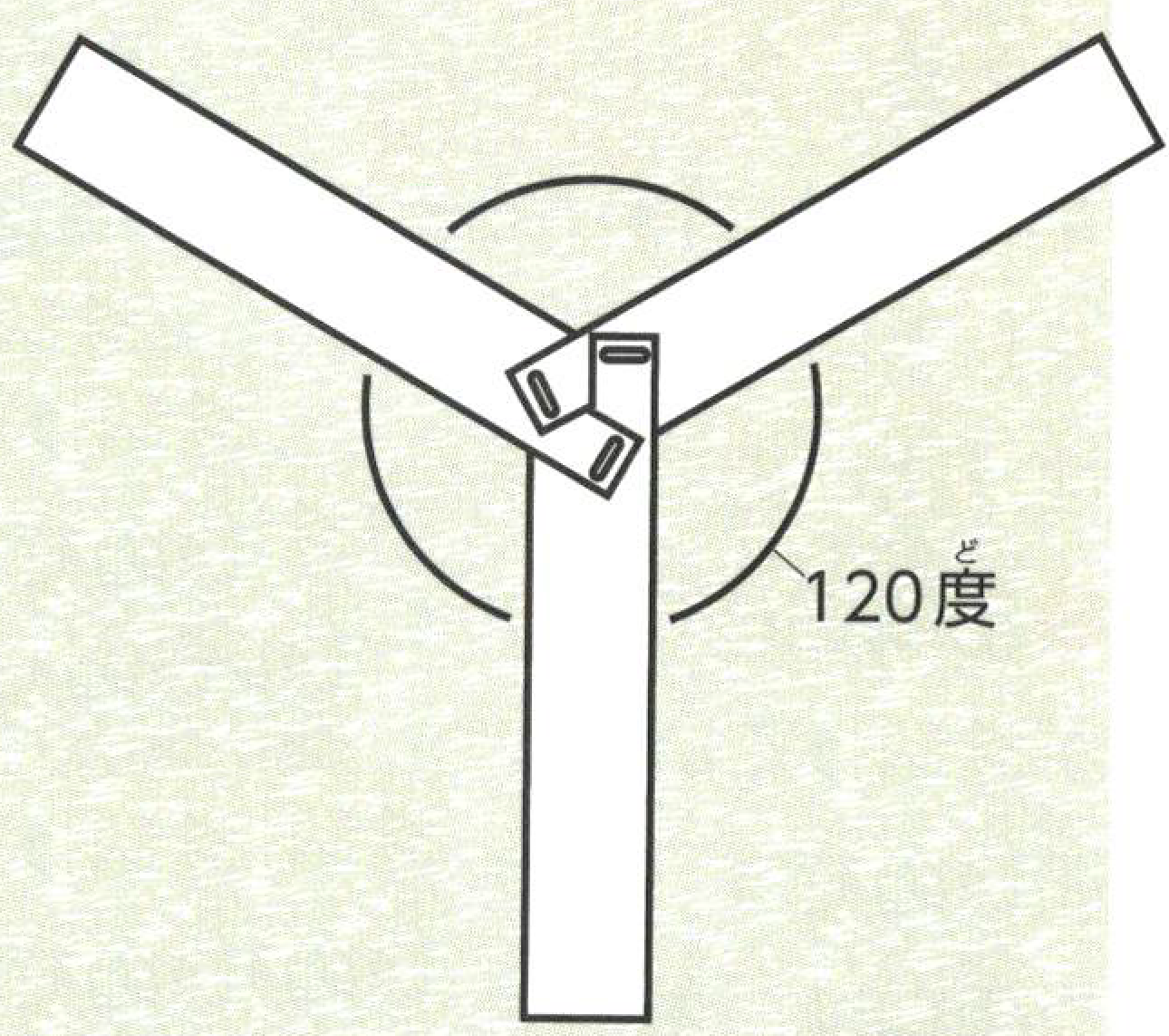
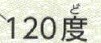
③くみあわせた部分をホチキスでとめる。
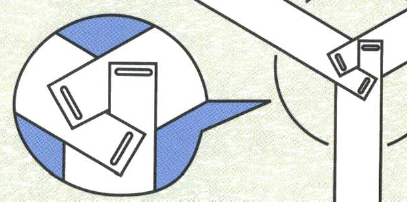

④羽根の先を少しだけねじる。3枚とも同じようにする。
 羽根のねじり方(右ききの場合)
羽根のねじり方(右ききの場合)
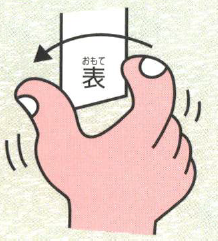

※羽根の先をまるくしておくと、とばしたときに安全です。
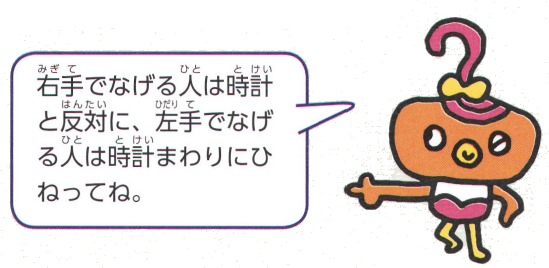
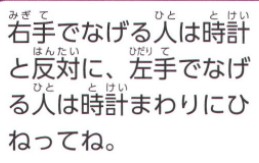

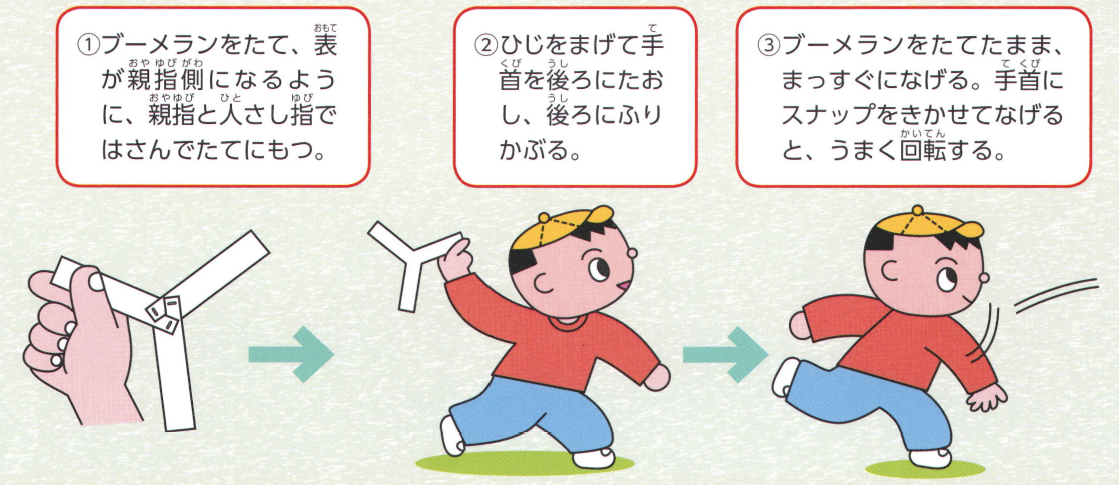
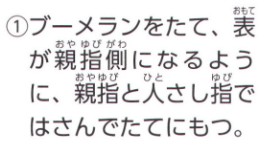
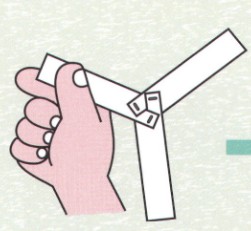
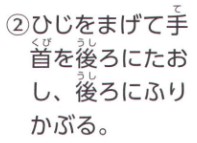
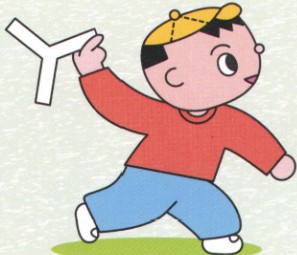
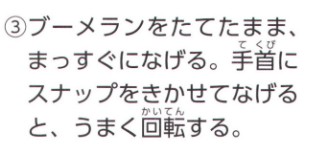

150
ボールはなぜはずむの?
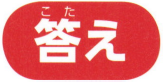 つぶれたゴムと空気が元にもどろうとするから
つぶれたゴムと空気が元にもどろうとするから
 ボールを手でおすとへこみますが、すぐにもとの形にもどります。これは、ボールと、ボールの中にはいっている空気がもとにもどろうとするためです。
ボールを手でおすとへこみますが、すぐにもとの形にもどります。これは、ボールと、ボールの中にはいっている空気がもとにもどろうとするためです。
ボールが地面についた瞬間も同じように、もとの形にもどろうとする力がはたらいています。そのため、ボールは地面をはねかえし、はずむのです。この、形がもとにもどろうとする性質を「弾性」といいます。ボールをつくっているゴムは弾性が強いので、よくはずむのです。
 紙風船はボールと同じようにまるく、中に空気がはいっていますが、はずみません。紙は弾性が弱いのです。また、弾性がほとんどない、ガラスや陶器は、おとすとわれてしまいます。
紙風船はボールと同じようにまるく、中に空気がはいっていますが、はずみません。紙は弾性が弱いのです。また、弾性がほとんどない、ガラスや陶器は、おとすとわれてしまいます。
 はずむボール。
はずむボール。
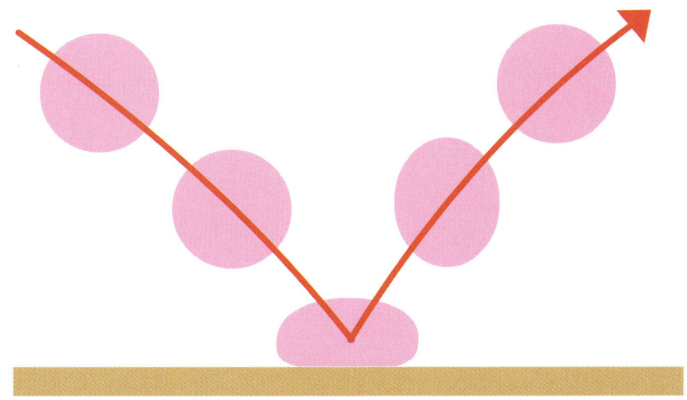
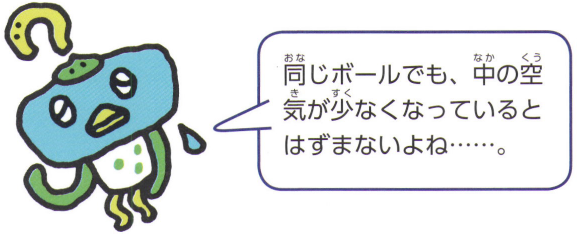
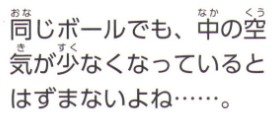
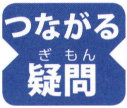 スーパーボールは空気がはいっていないのに、なぜよくはずむの?
スーパーボールは空気がはいっていないのに、なぜよくはずむの?
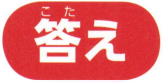 弾性がとても強いゴムをつかっているから
弾性がとても強いゴムをつかっているから
 スーパーボールは、ふつうのボールよりもずっと弾性が強い種類のゴムでつくられています。そのため、中に空気がはいっていなくても、よくはずむのです。
スーパーボールは、ふつうのボールよりもずっと弾性が強い種類のゴムでつくられています。そのため、中に空気がはいっていなくても、よくはずむのです。
スーパーボールは、アメリカでうまれたおもちゃで、もともとは天然のゴムでつくられていましたが、現在は「ポリブタジエン」という石油が原料の合成ゴムでつくられています。
サッカーボールやテニスボールなど、ボールによってつかわれている材料はちがいます。
 屋台のカラフルなスーパーボール。
屋台のカラフルなスーパーボール。
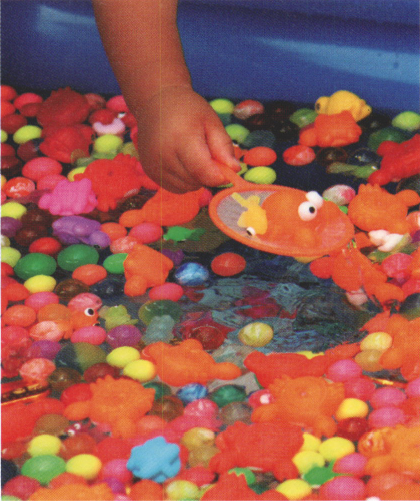
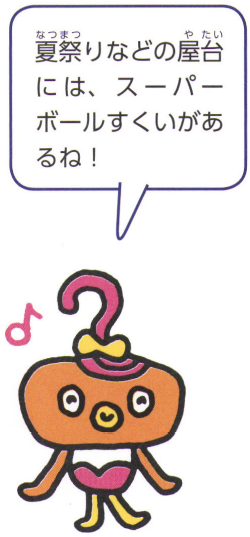
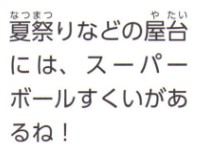
151
おふろのお湯はなぜ上からあつくなるの?
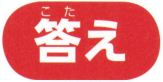 水はあたたまると上にいく性質があるから
水はあたたまると上にいく性質があるから
 水などの液体は、同じ量でも、つめたい場合とあたたかい場合で、重さがちがいます。
水などの液体は、同じ量でも、つめたい場合とあたたかい場合で、重さがちがいます。
水はあたためられると膨張して体積が大きくなります。また反対に、つめたくなるとちぢんで体積が小さくなります。同じ体積だと、あたたかいお湯は軽くなって上へ、つめたい水は重いので下にしずむため、おふろのお湯は上のほうがあたたかいのです。
 あたたまった部分が上にいき、つめたくなると下へいくうごきをくりかえして、だんだん全体があたたかくなっていきます。このしくみを「対流」といいます。対流は、空気をあたためる場合も同じしくみです。
あたたまった部分が上にいき、つめたくなると下へいくうごきをくりかえして、だんだん全体があたたかくなっていきます。このしくみを「対流」といいます。対流は、空気をあたためる場合も同じしくみです。
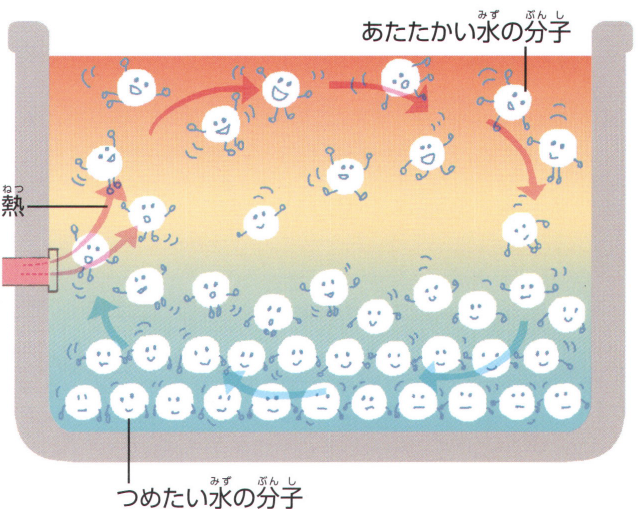

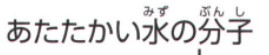
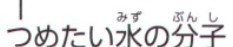
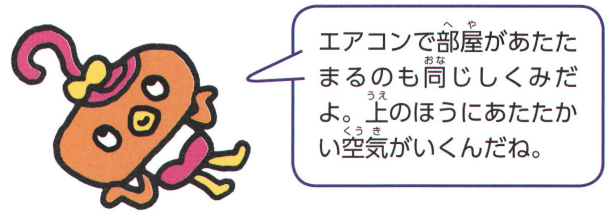
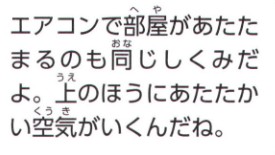
 身近にある対流をみつけよう
身近にある対流をみつけよう
対流でものがあたたまるしくみは、どんなところにあるかな? みつけてみよう。
 なベ
なベ
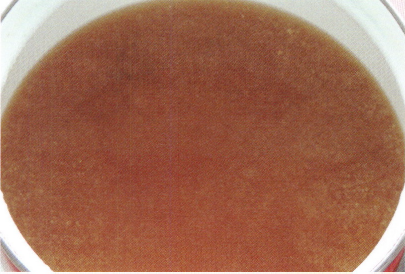
スープや味噌汁などがはいったなべを観察してみよう。なべに水をいれて底に味噌をおき、火にかけると、味噌のうごきで対流がよくわかるよ。
 おちゃのポット
おちゃのポット

紅茶やお茶の葉をいれたポットを観察してみよう。ガラスのポットに茶葉をいれて熱湯をそそぐと、うごきがよくわかるよ。
 エアコン
エアコン
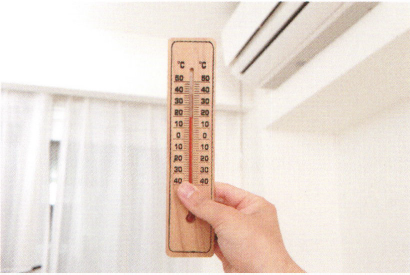
部屋をあたためたり、ひやしたりしたとき、床と天井ちかくで温度をはかってみると、温度の差ができていて対流のうごきがわかるよ。
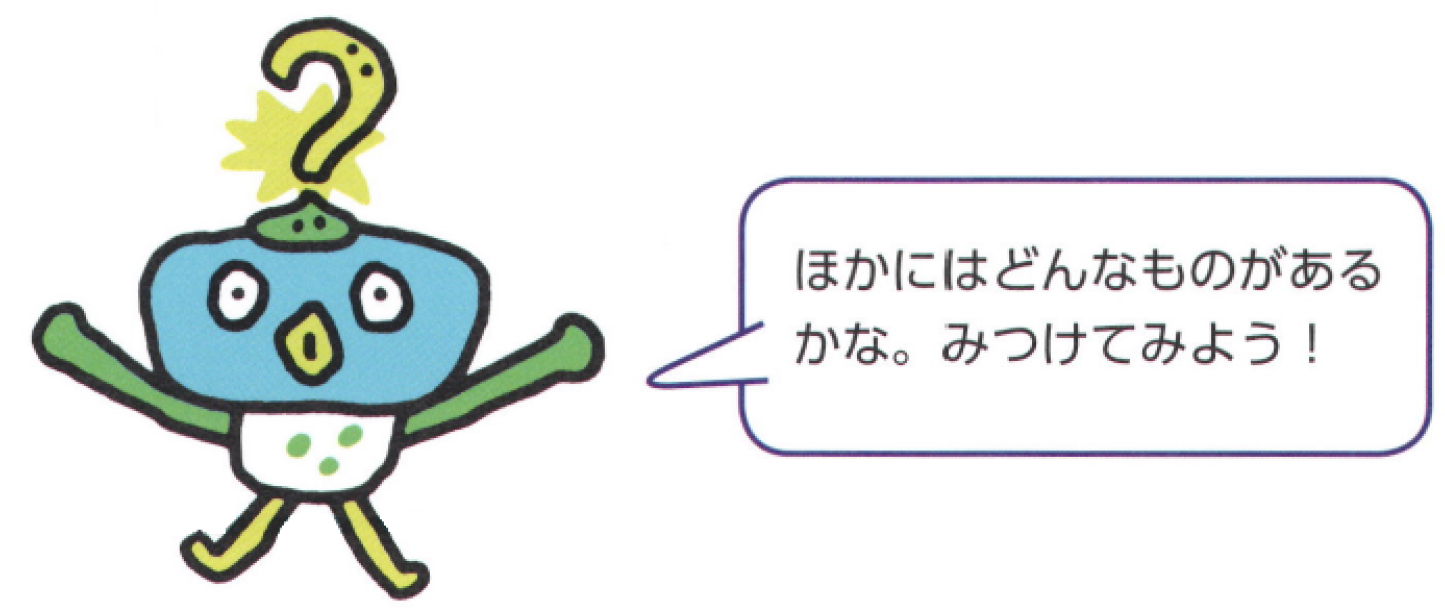
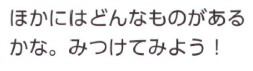
 水のいろいろなすがたをみつけよう
水のいろいろなすがたをみつけよう
水はいろいろなすがたに変化します。どんなものがあるか、さがしてみましょう。
 つらら
つらら

屋根などから水がおちるときに棒状にこおったもの。
 しもばしら
しもばしら

土の中の水分が地面にしみでて、柱のようにこおったもの。
 湯気
湯気

お湯やあたたかいものからでる湯気は液体。
 雪の結晶
雪の結晶

雪も小さな氷のつぶ。雪がふっているところに黒っぽい布をおくと、雪の結晶がみられる。
 樹氷
樹氷

木のえだについた水のつぶがこおり、木全体をおおって、かたまったもの。

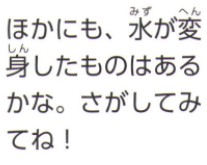
153
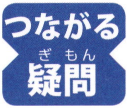 氷はどうして水にうくの?
氷はどうして水にうくの?
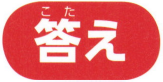 氷のほうが水よりも軽いから
氷のほうが水よりも軽いから
 製氷皿に水をいれてこおらせると、いれた水の量よりもふくらんでいます。水がかたまって氷になったときに、分子と分子の間にすき間ができるため、体積がふえるのです。つまり、同じ体積の氷と水をくらべると、水よりも氷のほうが軽くなるということです。そのため、氷は水にうかびます。
製氷皿に水をいれてこおらせると、いれた水の量よりもふくらんでいます。水がかたまって氷になったときに、分子と分子の間にすき間ができるため、体積がふえるのです。つまり、同じ体積の氷と水をくらべると、水よりも氷のほうが軽くなるということです。そのため、氷は水にうかびます。
 池の水も水面からこおっていきます。もしも、氷が水よりも重かったら、氷が水の底にたまり、生き物がすむことはできません。氷が水にうかぶおかげで、寒い冬でも、水の中の生き物はいきていられるのです。
池の水も水面からこおっていきます。もしも、氷が水よりも重かったら、氷が水の底にたまり、生き物がすむことはできません。氷が水にうかぶおかげで、寒い冬でも、水の中の生き物はいきていられるのです。
 海にうかぶ氷山も、氷のひとつ。
海にうかぶ氷山も、氷のひとつ。
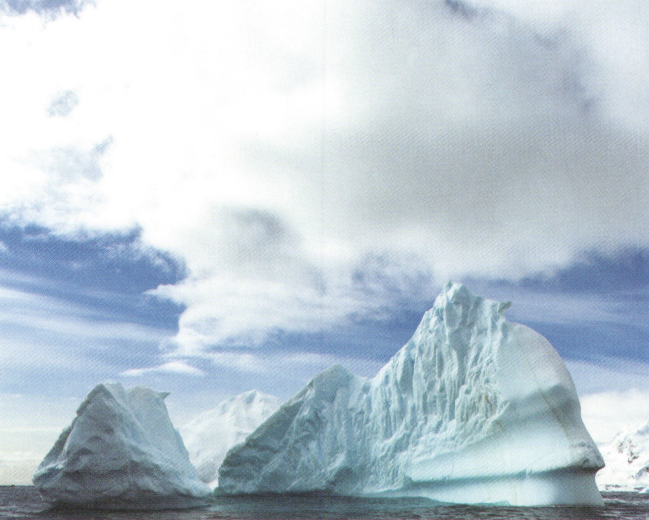
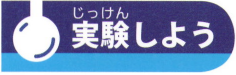 ミニ氷山をつくって氷の重さをかんじよう
ミニ氷山をつくって氷の重さをかんじよう
どんな氷でも本当に水にうくのかな? 大きさのちがう氷を水にうかべてたしかめてみよう。
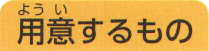
ポリぶくろ2枚、水、深めのバケツか洗面器
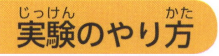
①かた方のポリぶくろには水をたっぷり、もうかた方には少しだけ水をいれて、口をしっかりしばる。
②水をいれたポリぶくろを冷凍庫にいれて、こおらせる。氷ができる時間は大きさによってちがうが、だいたい1日が目安。
③深めの大きな容器に水をいれ、②でつくった氷をポリぶくろからとりだしてうかべ、うかび方をかんさつする。
大きめの容器がない場合は、おふろに水をはってもいい。
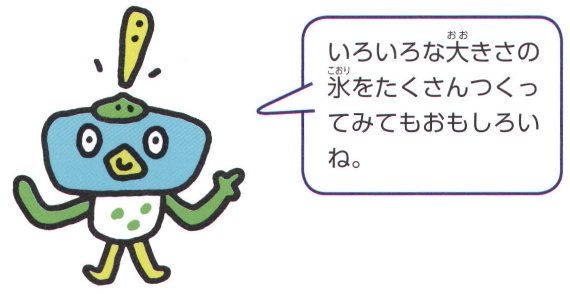
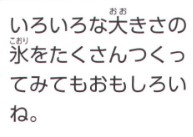
 ミニ氷山ができた!
ミニ氷山ができた!
実験でつくったミニ氷山は、水にうかびましたか? 大きさがちがっても、氷は水にうかびます。上の写真のような海にうかぶ大きな氷山も、このミニ氷山と同じです。氷は水よりも軽いことがよくわかりますね。
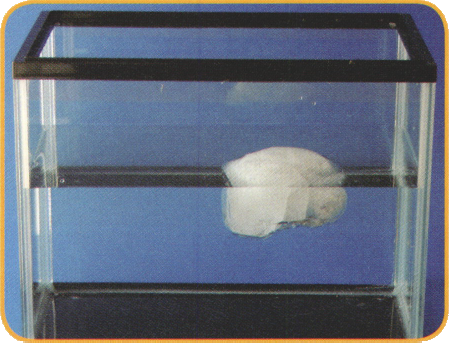
154
磁石がくっつくのはなぜ?
 磁石のN極とS極がひきあうから
磁石のN極とS極がひきあうから
 磁石にはN極とS極があります。N極とS極はひきあい、同じ極同士は反発する性質があるのです。このときにはたらく力を「磁力」といい、N極とS極のちかくはより強い磁力がはたらいています。下の写真のように、砂鉄をつかうと、磁力のようすがよくわかります。
磁石にはN極とS極があります。N極とS極はひきあい、同じ極同士は反発する性質があるのです。このときにはたらく力を「磁力」といい、N極とS極のちかくはより強い磁力がはたらいています。下の写真のように、砂鉄をつかうと、磁力のようすがよくわかります。
 磁力は、鉄を強くひきつける性質があります。磁石も主に鉄からできています。鉄は小さな磁石のつぶがあつまったものなので、鉄が多くふくまれる金属は磁石にくっつくのです。
磁力は、鉄を強くひきつける性質があります。磁石も主に鉄からできています。鉄は小さな磁石のつぶがあつまったものなので、鉄が多くふくまれる金属は磁石にくっつくのです。
 砂鉄をまいた上に磁石をおくと、磁力がよくわかる。
砂鉄をまいた上に磁石をおくと、磁力がよくわかる。
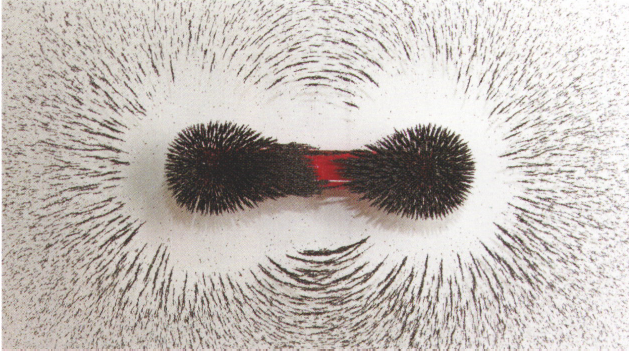
 N極とS極はひきあうけれど、同じ極は反発する。
N極とS極はひきあうけれど、同じ極は反発する。
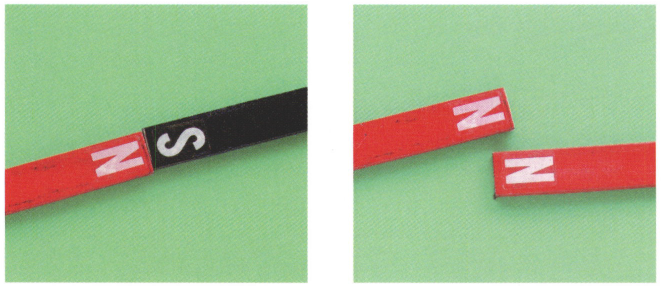
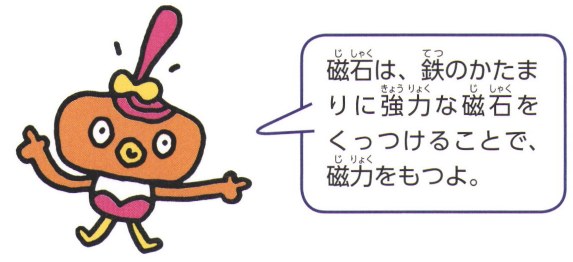
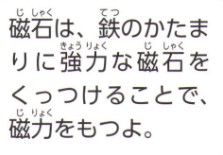
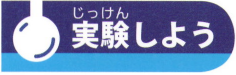 即席磁石をつくろう
即席磁石をつくろう
家にある道具をつかって、即席磁石をつくってみよう!
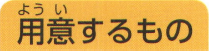
磁石、ステンレスのフォーク(またはスプーン)1本、金属のクリップ
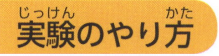
①磁石でフォークを同じ方向に10~15回ほどよくこする。
②こすったフォークをクリップにちかづけてみる。

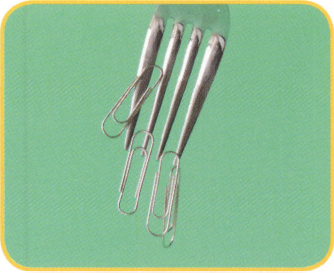
 磁石になった理由
磁石になった理由
フォークを磁石でこすると、フォークの中の磁石のつぶのむきがそろえられ、磁力がうまれます。そのため、フォークにクリップがくっついたのです。
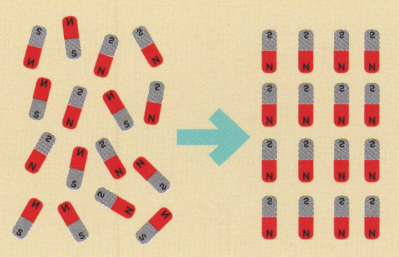
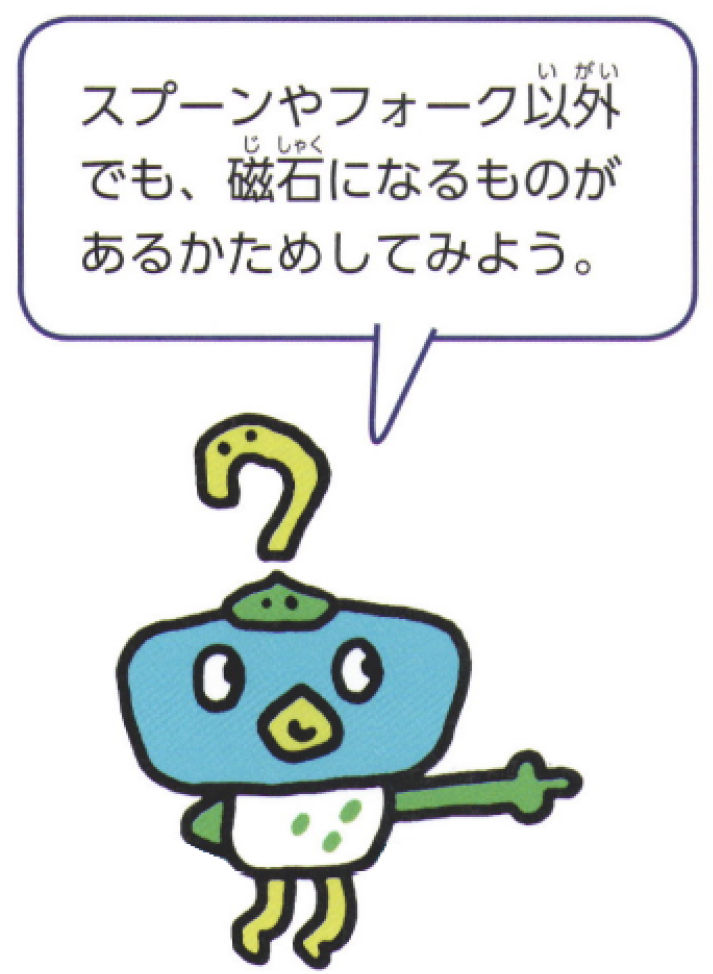
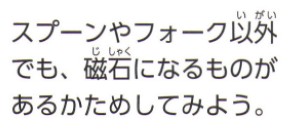
155
アニメーションがうごいてみえるのはなぜ?
 少しずつうごかした絵を高速でみせているから
少しずつうごかした絵を高速でみせているから
 テレビや映画などのアニメーションは、1秒間のうごきを約24枚の絵にわけてかいています。かいた絵を順番通りに高速で連続してみせると、まるでうごいているようにみえるのです。
テレビや映画などのアニメーションは、1秒間のうごきを約24枚の絵にわけてかいています。かいた絵を順番通りに高速で連続してみせると、まるでうごいているようにみえるのです。
15分間のアニメでは、2万枚以上もの絵が必要になります。うごきを自然にみせるためには、よりたくさんの絵が必要になってくるのです。下絵を順番どおりにかさねてかき、うごきを確認しながら絵を完成させていきます。
 昔は、すべての工程を手作業でおこなっていましたが、現在は、ほとんどの工程でコンピュータがつかわれています。
昔は、すべての工程を手作業でおこなっていましたが、現在は、ほとんどの工程でコンピュータがつかわれています。
 1つのうごきを細かくわけてかいている。
1つのうごきを細かくわけてかいている。
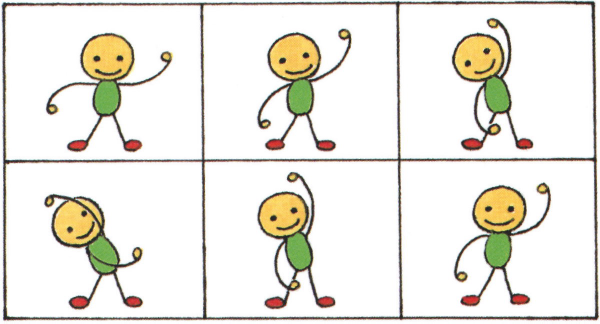
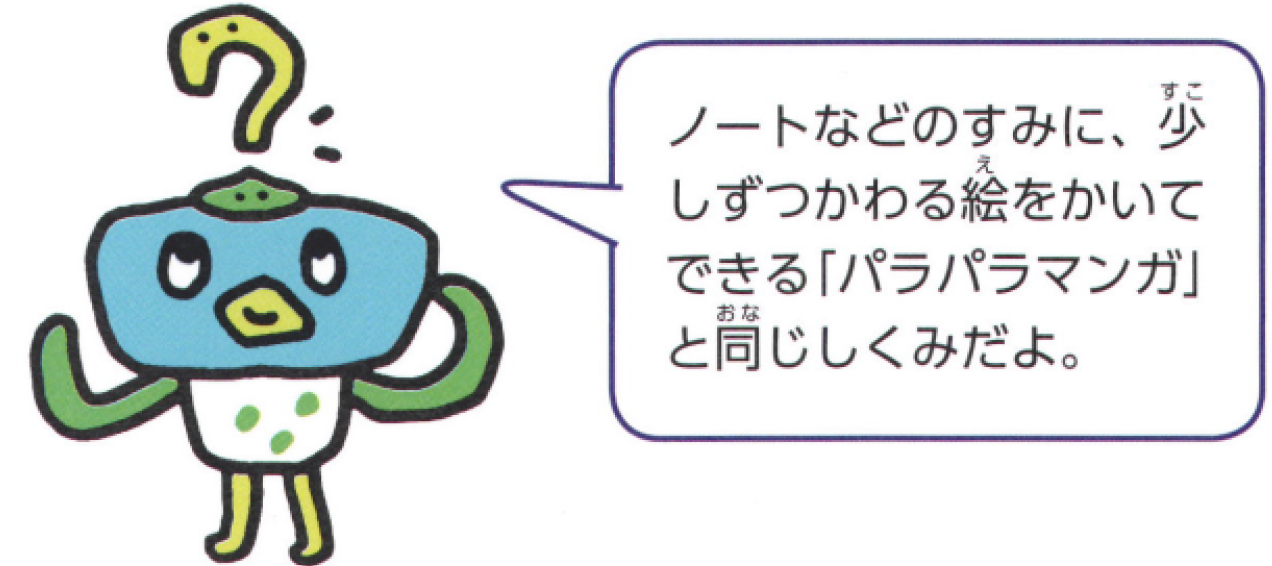
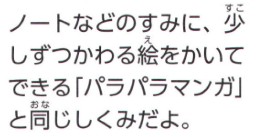
 手づくりアニメーションソーマトロープをつくろう!
手づくりアニメーションソーマトロープをつくろう!

厚紙7
四方くらい、輪ゴム2本、サインペン、はさみ、きり

①厚紙をまるくきる。くみあわさると1つの絵になるように、表と裏に絵をかく。裏の絵は、表とはさかさまにかく。
②両はしにきりであなをあけ、輪ゴムをとおし、ぬけないように輪ゴムをむすぶ。
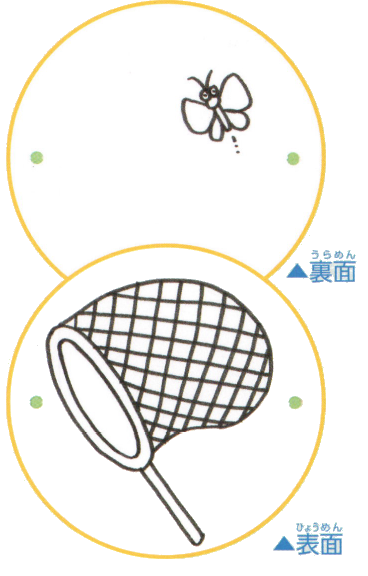



①両はしの輪ゴムをもって、前後に回転させ、ゴムにねじりをくわえる。
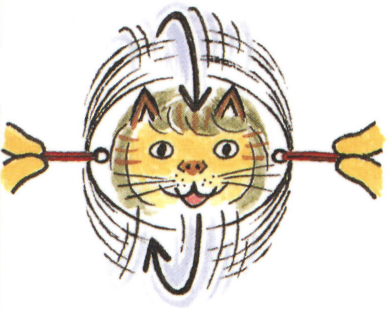
②輪ゴムを左右にひっぱり、円ばんを回転させると、表裏の絵がかさなってみえる。
※両はしの輪ゴムをもって、指でゴムをねじってまわしたほうが速くまわせます。
156
ガラスはどうしてすきとおっているの?
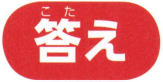 光がそのままとおりぬけてしまうから
光がそのままとおりぬけてしまうから
 わたしたちは、ものにあたって反射した光が目にはいることで、ものをみています。しかし、ガラスは、光が反射せずにそのままとおりぬけてしまうため、すきとおってみえるのです。
わたしたちは、ものにあたって反射した光が目にはいることで、ものをみています。しかし、ガラスは、光が反射せずにそのままとおりぬけてしまうため、すきとおってみえるのです。
 光がとおりぬけてしまう理由は、2つあります。1つは、ガラスの中の分子がとても小さいこと、もう1つはガラスが「非晶体」であることです。
光がとおりぬけてしまう理由は、2つあります。1つは、ガラスの中の分子がとても小さいこと、もう1つはガラスが「非晶体」であることです。
すきとおっていないものは、「結晶体」とよばれ、分子が規則正しくつながっていて、光を反射するさかい目があります。しかし、ガラスの分子はつながり方が不規則なので、そのすき間を光がとおりぬけてしまうのです。
 ガラスは光がそのままとおりぬけてしまうので、すきとおってみえる。
ガラスは光がそのままとおりぬけてしまうので、すきとおってみえる。
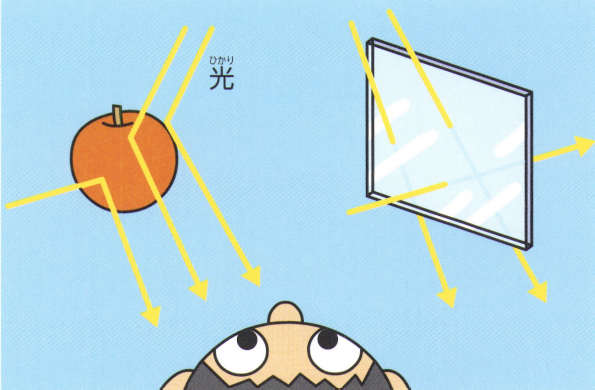

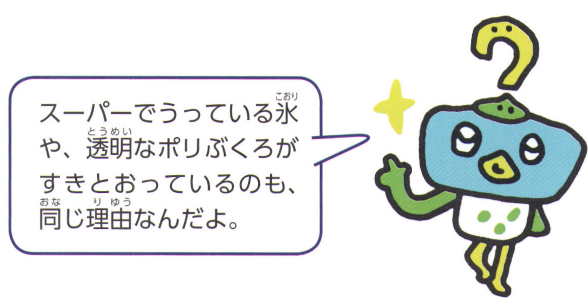
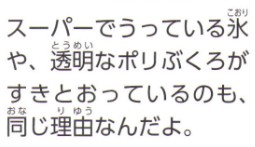
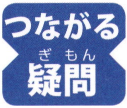 ガラスは何でできているの?
ガラスは何でできているの?
 天然の鉱物からできています
天然の鉱物からできています
 ガラスの多くは、主に、ケイ砂(ケイ石)・ソーダ灰・石灰石といった鉱物をまぜて1500℃以上の高温でねっし、真っ赤などろどろの状態にして形をつくります。
ガラスの多くは、主に、ケイ砂(ケイ石)・ソーダ灰・石灰石といった鉱物をまぜて1500℃以上の高温でねっし、真っ赤などろどろの状態にして形をつくります。
ケイ砂、石灰石は自然にとれる鉱物です。ソーダ灰はもともとは鉱物からつくられていましたが、現在は炭酸ナトリウムという薬品からつくられます。
 ガラスは、紀元前1500年ごろにはすでにあったといいます。息をふきこんでガラス製品をつくる「ふきガラス」は紀元1世紀ごろからあり、現在でもふきガラスの製品があります。
ガラスは、紀元前1500年ごろにはすでにあったといいます。息をふきこんでガラス製品をつくる「ふきガラス」は紀元1世紀ごろからあり、現在でもふきガラスの製品があります。
 ふきガラス。ガラスがついているパイプに息をふきこんでふくらませる。
ふきガラス。ガラスがついているパイプに息をふきこんでふくらませる。
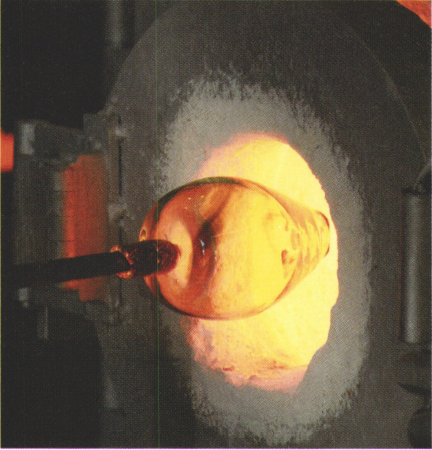

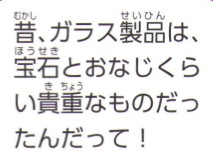
157
望遠鏡でとおくのものが大きくみえるのはなぜ?
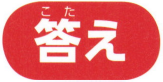 レンズをくみあわせて、大きくみえるしくみをつくっています
レンズをくみあわせて、大きくみえるしくみをつくっています
 虫めがねのレンズをみてみると、真ん中がふくらんだ形をしています。これを「凸レンズ」といいます。この凸レンズが、望遠鏡の中にはいっています。
虫めがねのレンズをみてみると、真ん中がふくらんだ形をしています。これを「凸レンズ」といいます。この凸レンズが、望遠鏡の中にはいっています。
望遠鏡の凸レンズには、ものを大きくみせる「接眼レンズ」と、光を1か所にあつめる「対物レンズ」があります。対物レンズでうつしたものを、接眼レンズで大きくみせているので、望遠鏡でとおくのものが大きくみえるのです。
実際の望遠鏡は、たくさんのレンズをつかったり、さまざまな工夫がされて、より大きくみやすくなっています。
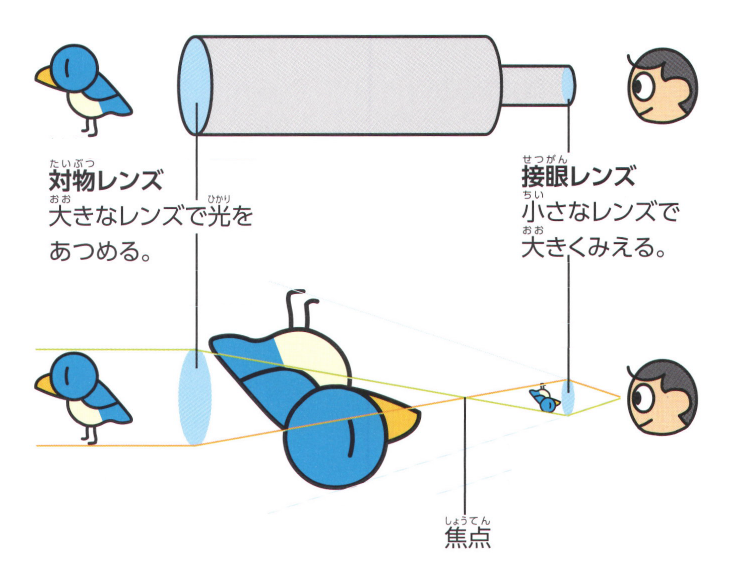
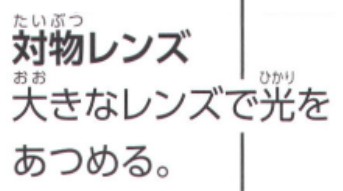

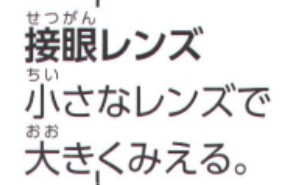
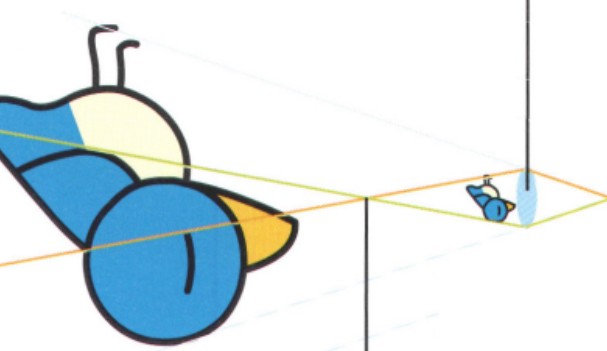

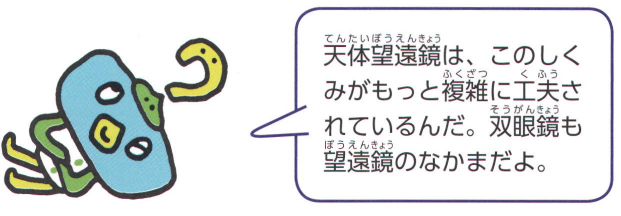
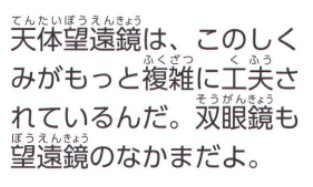
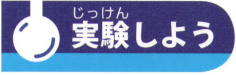 虫めがねでレンズのはたらきをみてみよう
虫めがねでレンズのはたらきをみてみよう
虫めがねで、レンズのおもしろいはたらきがわかるよ。
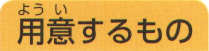
虫めがね
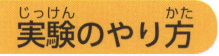
①虫めがねに目をちかづけ、とおくのものをみる。
②つぎに、少しずつ目から虫めがねをはなしてみる。途中で、さかさまにみえるところがある。
 目にちかづけたとき。
目にちかづけたとき。

 目からはなしたとき。
目からはなしたとき。

 どうしてさかさまになるの?
どうしてさかさまになるの?
凸レンズは光をまげて焦点にあつめるため、焦点をすぎると上下さかさまにみえてしまいます。そのため望遠鏡は、さかさまにみえないようにレンズをふやして、像が正しくみえるようにしています。
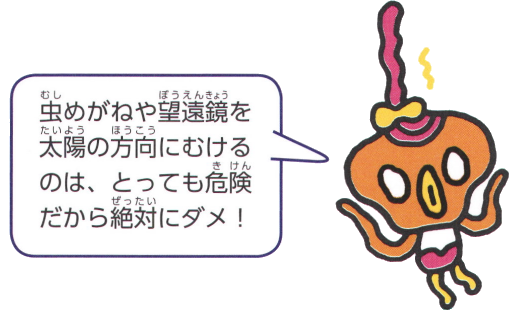
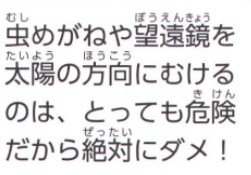
158
録音した声がちがってきこえるのはなぜ?
 自分がきいている声と録音した声はつたわり方がちがうから
自分がきいている声と録音した声はつたわり方がちがうから
 いつもきいている自分の声は、体の中の骨をとおして耳につたわる音と、口や鼻からでて空気をとおして耳につたわる音がまざっています。
いつもきいている自分の声は、体の中の骨をとおして耳につたわる音と、口や鼻からでて空気をとおして耳につたわる音がまざっています。
しかし、録音した声は、空気をとおしてつたわる音だけがマイクにひろわれているので、ちがう声のようにきこえるのです。ですから、ほかの人がきいているあなたの声は、録音したものと同じ声なのです。
 録音するときのマイクの位置によっても、声がかわります。口の近くで録音すると、口からでた声ばかりで鼻がつまったようにきこえますが、少しはなして録音すると、口と鼻からでたふだんどおりの声が録音できるのです。
録音するときのマイクの位置によっても、声がかわります。口の近くで録音すると、口からでた声ばかりで鼻がつまったようにきこえますが、少しはなして録音すると、口と鼻からでたふだんどおりの声が録音できるのです。
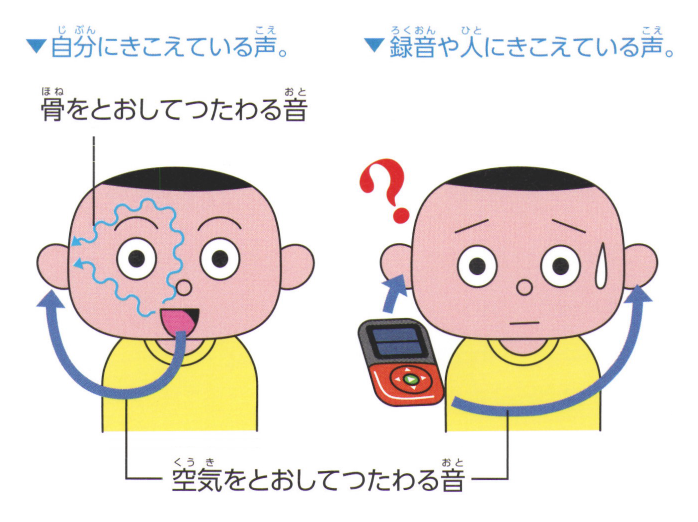
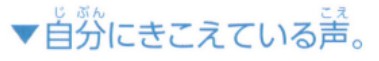
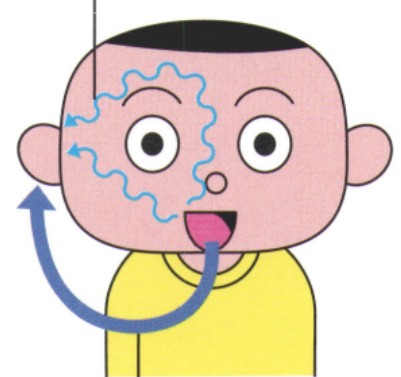
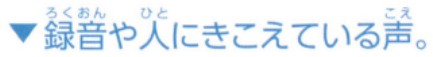
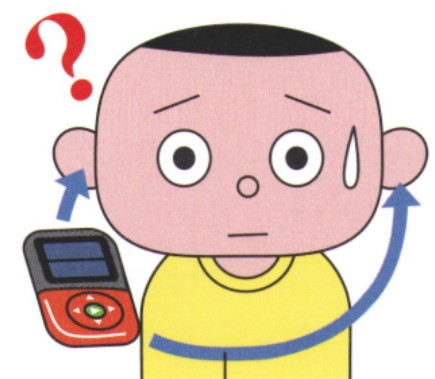
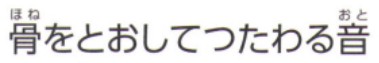
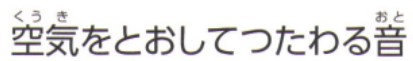
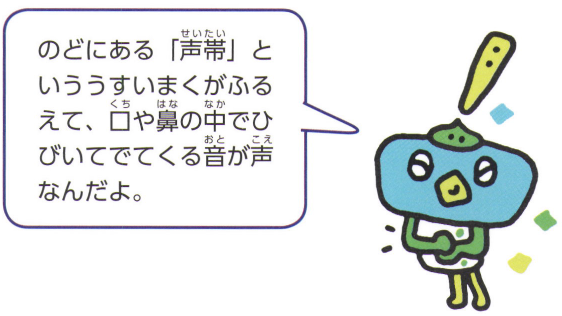
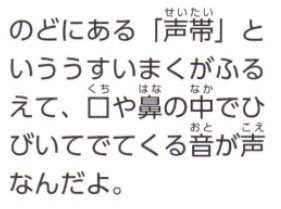
159
新幹線の先頭車両は、どうして細長いの?
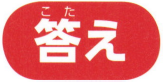 トンネルからでたときの大きな音や車両のゆれをふせぐため
トンネルからでたときの大きな音や車両のゆれをふせぐため
 新幹線は、時速200
以上の高速ではしるため、はしっているときに、とても強い空気の抵抗をうけます。
新幹線は、時速200
以上の高速ではしるため、はしっているときに、とても強い空気の抵抗をうけます。
新幹線の先頭車両がまるい場合、トンネルにはいると、前の空気がどんどんおしちぢめられて、出口で一気にとびだします。このとき、破裂したような大きな音とゆれがおこり、騒音問題がおきてしまいます。この空気の抵抗と破裂音、ゆれを少しでもへらすために、新幹線の先頭車両は、細長い形をしているのです。
 新しい新幹線には、空気が車体の横をうまくとおりぬけられるような、さまざまな工夫がされています。
新しい新幹線には、空気が車体の横をうまくとおりぬけられるような、さまざまな工夫がされています。
 先がまるい場合。
先がまるい場合。
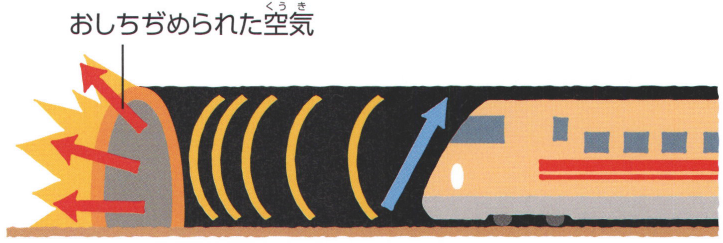
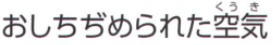
 先が細長い場合。
先が細長い場合。

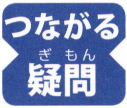 新幹線の先端はどうなっているの?
新幹線の先端はどうなっているの?
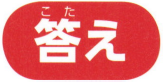 ほかの車両と連結するため、連結器がはいっています。
ほかの車両と連結するため、連結器がはいっています。
 新幹線は、ルートによって、2つの路線の新幹線がつながってはしる場合があります。また、途中で故障したり、万が一事故があったときなどのために、新幹線の先端にはかならず、ほかの車両と連結するための「連結器」がはいっています。
新幹線は、ルートによって、2つの路線の新幹線がつながってはしる場合があります。また、途中で故障したり、万が一事故があったときなどのために、新幹線の先端にはかならず、ほかの車両と連結するための「連結器」がはいっています。
2つの車両が連結したり、はなれたりするのがみられる駅もありますよ。
 連結する東北新幹線のE5系とE6系。
連結する東北新幹線のE5系とE6系。

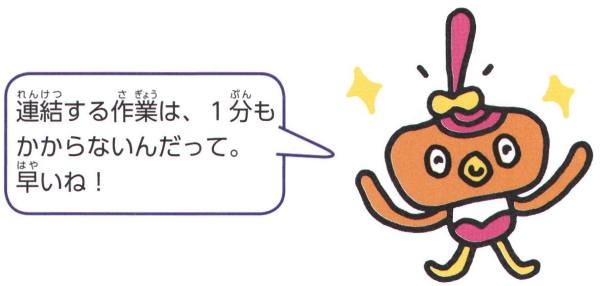
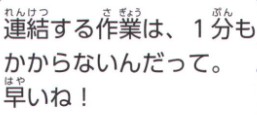
160
ダイヤモンドはどうやってみがくの?
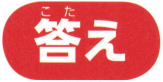 ダイヤモンドを粉にしたものでみがきます
ダイヤモンドを粉にしたものでみがきます
 ダイヤモンドは、天然の鉱物の中で一番かたいといわれています。そのため、ダイヤモンドを粉にしたもので原石をみがいて、かがやく宝石にするのです。
ダイヤモンドは、天然の鉱物の中で一番かたいといわれています。そのため、ダイヤモンドを粉にしたもので原石をみがいて、かがやく宝石にするのです。
 宝石や鉱物のかたさの単位を「硬度」といいます。ドイツの鉱物学者モースは、10種類の鉱物をかたさの基準にして、硬度を10段階にわけました。これは「モース硬度」とよばれています。硬度の数字が大きくなるにつれて、かたくなります。
宝石や鉱物のかたさの単位を「硬度」といいます。ドイツの鉱物学者モースは、10種類の鉱物をかたさの基準にして、硬度を10段階にわけました。これは「モース硬度」とよばれています。硬度の数字が大きくなるにつれて、かたくなります。
鉱物のかたさをしらべるときには、基準となる鉱物としらべる鉱物をこすりあわせます。しらべる鉱物のほうにきずがついたら、基準となる鉱物よりもやわらかいということがわかります。
 モース硬度表
モース硬度表
| 硬度1 滑石
| 爪で簡単に傷がつく。
|
|---|
| 硬度2 石膏
| 爪で傷がつく。
|
|---|
| 硬度3 方解石
| 10円銅貨で傷がつく。
|
|---|
| 硬度4 蛍石
| ナイフで簡単に傷がつく。
|
|---|
| 硬度5 燐灰石
| ナイフで傷がつく。
|
|---|
| 硬度6 正長石
| かろうじてガラスを傷つけられる
|
|---|
| 硬度7 石英
| ガラスを簡単に傷つけられる
|
|---|
| 硬度8 黄玉
| ガラスをとても簡単に傷つけられる
|
|---|
| 硬度9 鋼玉
| ガラスをきることができる。
|
|---|
| 硬度10 ダイヤモンド
| ガラスをきることができる。
|
|---|
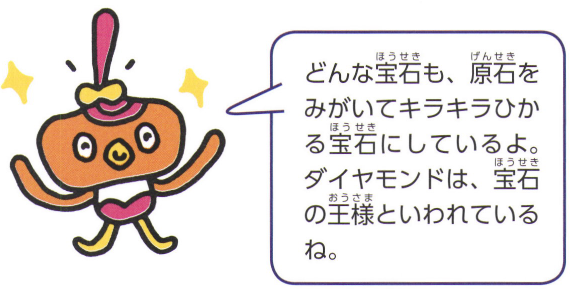
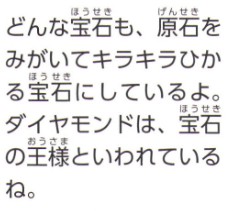
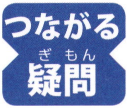 ダイヤモンドは何からできているの?
ダイヤモンドは何からできているの?
 炭素という物質からできています
炭素という物質からできています
 石をよくみると、小さなつぶからできていることがわかります。この小さなつぶを鉱物といいます。鉱物もまた、マグネシウムや銅などの物質からできていますが、この物質のくみあわせによって、まったくちがう宝石になるのです。
石をよくみると、小さなつぶからできていることがわかります。この小さなつぶを鉱物といいます。鉱物もまた、マグネシウムや銅などの物質からできていますが、この物質のくみあわせによって、まったくちがう宝石になるのです。
 ダイヤモンドは炭素からできていますが、同じ炭素でも、できたときの条件や炭素のむすびつき方で、まったくちがうものになります。黒鉛は色が黒く、モース硬度は0.5~1とやわらかい鉱物ですが、ダイヤモンドは透明でとてもかたい鉱物です。
ダイヤモンドは炭素からできていますが、同じ炭素でも、できたときの条件や炭素のむすびつき方で、まったくちがうものになります。黒鉛は色が黒く、モース硬度は0.5~1とやわらかい鉱物ですが、ダイヤモンドは透明でとてもかたい鉱物です。
 同じ炭素からできたものでも、みた目はまったくちがう。石炭は燃料、黒鉛は鉛筆などの芯になる鉱物。
同じ炭素からできたものでも、みた目はまったくちがう。石炭は燃料、黒鉛は鉛筆などの芯になる鉱物。
石炭

黒鉛(グラファイト)

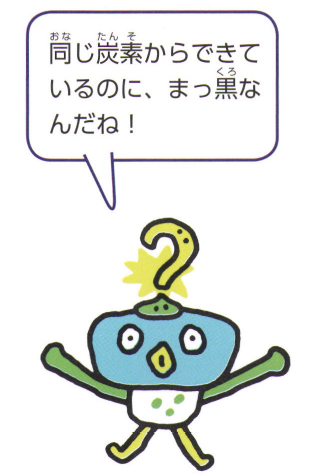
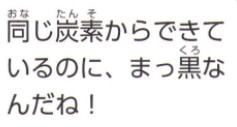
161
タイヤにみぞがあるのはなぜ?
 雨の日に車がすべらないようにするため
雨の日に車がすべらないようにするため
 雨の日、道路は雨でぬれていたり、水たまりができたりしています。タイヤと道路の間に水がはいりこむと、車は水の上をすべってしまいます。タイヤにみぞがあると、そこに水がたまり、タイヤがちゃんと道路にふれることができます。水をかきだして、車がすべらずに安全にはしれるようにするのが、タイヤのみぞの役割です。
雨の日、道路は雨でぬれていたり、水たまりができたりしています。タイヤと道路の間に水がはいりこむと、車は水の上をすべってしまいます。タイヤにみぞがあると、そこに水がたまり、タイヤがちゃんと道路にふれることができます。水をかきだして、車がすべらずに安全にはしれるようにするのが、タイヤのみぞの役割です。
 このすべらない工夫は、くつの底にもつかわれています。くつの底をみてみると、でこぼこしたみぞがあります。とくに雨の日にはく長ぐつには、しっかりみぞがついています。このみぞのおかげで、雨の日でもすべらずにあるくことができるのです。
このすべらない工夫は、くつの底にもつかわれています。くつの底をみてみると、でこぼこしたみぞがあります。とくに雨の日にはく長ぐつには、しっかりみぞがついています。このみぞのおかげで、雨の日でもすべらずにあるくことができるのです。
 水がみぞの間にはいることで、タイヤと道路がふれる。
水がみぞの間にはいることで、タイヤと道路がふれる。
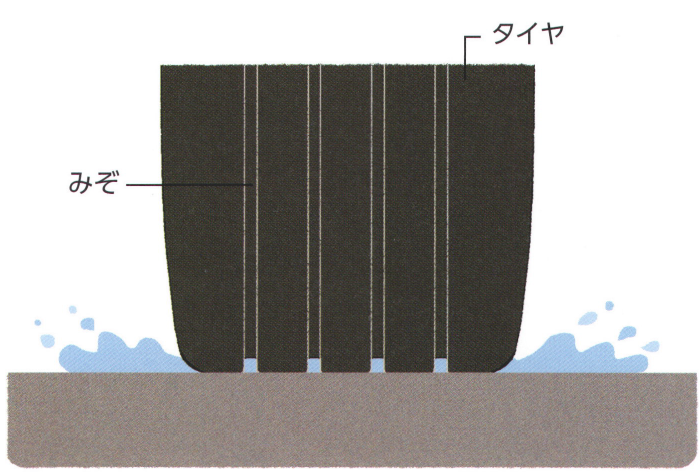


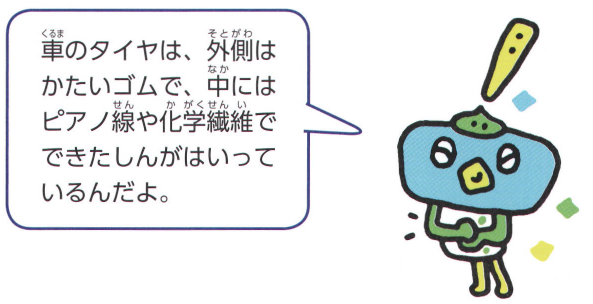
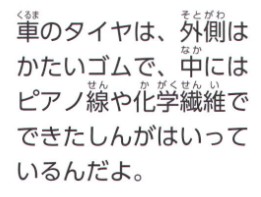
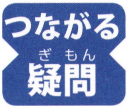 レース用のタイヤには、みぞがないって本当?
レース用のタイヤには、みぞがないって本当?
 晴れた日は、みぞがないタイヤをつかいます
晴れた日は、みぞがないタイヤをつかいます
 F1などのカーレースをみたことがありますか? レースでつかわれるレーシングカーのタイヤには、みぞがついていないものがあります。みぞがないほうが速くはしれるのです。「スリックタイヤ」というもので、晴れの日につかわれます。みぞがないかわりに、すべりにくいように表面がべたべたしています。それは、はしるとタイヤの表面が摩擦熱でとけるタイヤだからです。雨の日のレースでは、みぞがついたタイヤをつかいます。
F1などのカーレースをみたことがありますか? レースでつかわれるレーシングカーのタイヤには、みぞがついていないものがあります。みぞがないほうが速くはしれるのです。「スリックタイヤ」というもので、晴れの日につかわれます。みぞがないかわりに、すべりにくいように表面がべたべたしています。それは、はしるとタイヤの表面が摩擦熱でとけるタイヤだからです。雨の日のレースでは、みぞがついたタイヤをつかいます。
 上が晴れた日につかわれるスリックタイヤ。
上が晴れた日につかわれるスリックタイヤ。
下が雨の日につかわれる、みぞがあるタイヤ。

162
花火はどうしていろいろな色があるの?
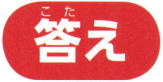 花火の中に、もえるといろいろな色をだす金属がはいっているから
花火の中に、もえるといろいろな色をだす金属がはいっているから
 夏の夜空にうちあげられる花火は、色あざやかでとてもきれいですね。赤、青、黄色、緑、むらさきなど、花火にはたくさんの色があります。このようないろいろな花火の色は、花火につかわれる金属によるものです。
夏の夜空にうちあげられる花火は、色あざやかでとてもきれいですね。赤、青、黄色、緑、むらさきなど、花火にはたくさんの色があります。このようないろいろな花火の色は、花火につかわれる金属によるものです。
 金属の化合物をもやすと、その金属の種類によって、それぞれちがった色の炎をだします。これを「炎色反応」といいます。花火はこの金属の炎色反応を利用してつくられます。
金属の化合物をもやすと、その金属の種類によって、それぞれちがった色の炎をだします。これを「炎色反応」といいます。花火はこの金属の炎色反応を利用してつくられます。
 打ち上げ花火の中には、「星」とよばれる小さな火薬の玉がたくさんつまっています。星には、花火の色を変化させるための金属の粉がまぜられていて、花火が破裂すると、星に火がついて金属が色のついた炎をだすのです。
打ち上げ花火の中には、「星」とよばれる小さな火薬の玉がたくさんつまっています。星には、花火の色を変化させるための金属の粉がまぜられていて、花火が破裂すると、星に火がついて金属が色のついた炎をだすのです。
 色とりどりのうちあげ花火。
色とりどりのうちあげ花火。

 金属の炎の色。左から、リチウム ナトリウム カリウム ルビジウム セシウム カルシウム ストロンチウム バリウム 銅
金属の炎の色。左から、リチウム ナトリウム カリウム ルビジウム セシウム カルシウム ストロンチウム バリウム 銅
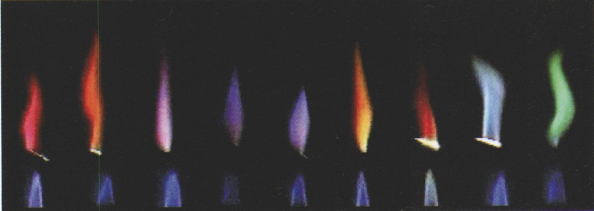
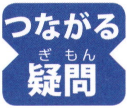 花火の色がかわるのはなぜ?
花火の色がかわるのはなぜ?
 何種類かの金属の粉を重ねてぬってあるから
何種類かの金属の粉を重ねてぬってあるから
 花火の中には、上空にうちあがってから色が変化するものがあります。これは、星に何種類かの金属の粉が重ねてぬってあるからです。
花火の中には、上空にうちあがってから色が変化するものがあります。これは、星に何種類かの金属の粉が重ねてぬってあるからです。
星は外側からもえていくため、外側に赤に変化する金属を、内側に黄に変化する金属をぬった花火は、赤から黄に色がかわるのです。
炎色反応は身近なところでもみることができます。なべのみそ汁がふきこぼれると、ガスコンロの青色の炎は黄色く変化します。これは、みそにふくまれるナトリウム(塩)がもえて、黄色い炎をだすからです。
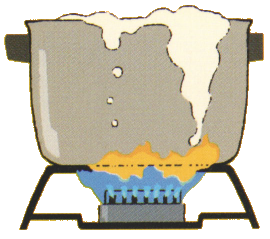
163
クレーンはどうやってビルの上にあげるの?
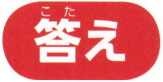 自分の力で少しずつのぼります
自分の力で少しずつのぼります
 高いビルをたてるためには、必要な材料を地上からあげるタワークレーンが活躍します。このクレーンは、自らの力で上にのぼっていくことから、「クライミングクレーン」とよばれています。クライミングクレーンは、細かい部材によってできています。つかうときは、工事現場で、その部材をくみたてます。
高いビルをたてるためには、必要な材料を地上からあげるタワークレーンが活躍します。このクレーンは、自らの力で上にのぼっていくことから、「クライミングクレーン」とよばれています。クライミングクレーンは、細かい部材によってできています。つかうときは、工事現場で、その部材をくみたてます。
 クライミングクレーンは、「フロアクライミング方法」というやり方でビルの上にあげていきます。台座ごと、自らたてた建物をよじのぼる方法です。超高層ビルはこの方法をつかいます。
クライミングクレーンは、「フロアクライミング方法」というやり方でビルの上にあげていきます。台座ごと、自らたてた建物をよじのぼる方法です。超高層ビルはこの方法をつかいます。
 ほかにも、台座の位置はかえずに、支柱を自分でつぎたしていき、高くしていく「マストクライミング」という方法もあります。ともにクレーン専門の職人が操作します。
ほかにも、台座の位置はかえずに、支柱を自分でつぎたしていき、高くしていく「マストクライミング」という方法もあります。ともにクレーン専門の職人が操作します。
 フロアクライミング方法
フロアクライミング方法
①まず、クレーンをくみたて、数階分をつくる。
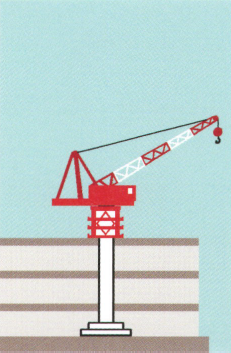
②一番上の階にクレーンの本体を固定して、下のマストをひきあげる。
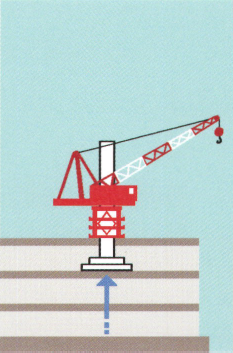
③マストの土台を固定して本体をもちあげる。これをくりかえす。
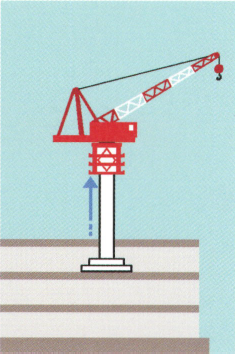
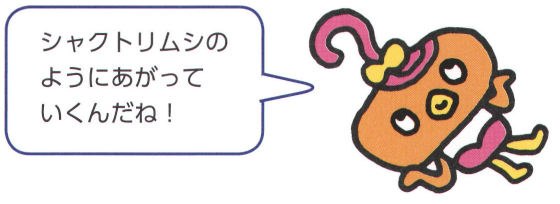
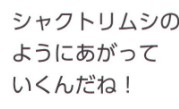
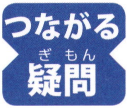 クレーンはどうやっておろすの?
クレーンはどうやっておろすの?
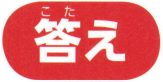 少しずつクレーンを小さくしておろしていきます
少しずつクレーンを小さくしておろしていきます
 建物がある程度完成すると、クレーンの役目もおしまいです。どのようにして大きなクレーンを地上におろすのでしょうか。
建物がある程度完成すると、クレーンの役目もおしまいです。どのようにして大きなクレーンを地上におろすのでしょうか。
まず、クレーンをつかって、ひと回り小さなクレーンの部材をつりあげてくみたてます。そして、そのひと回り小さなクレーンで、最初の大きなクレーンを解体しておろします。同じように、クレーンを少しずつ小さくしていき、最後には、人の手で解体し、建設用のエレベーターではこびだします。
①
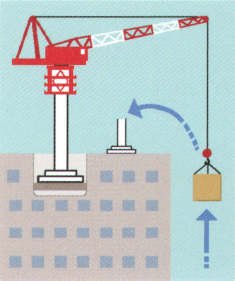
②
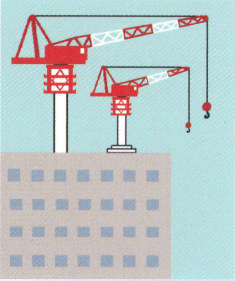
③
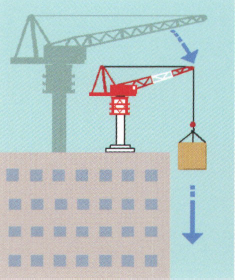
④
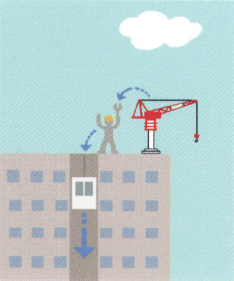
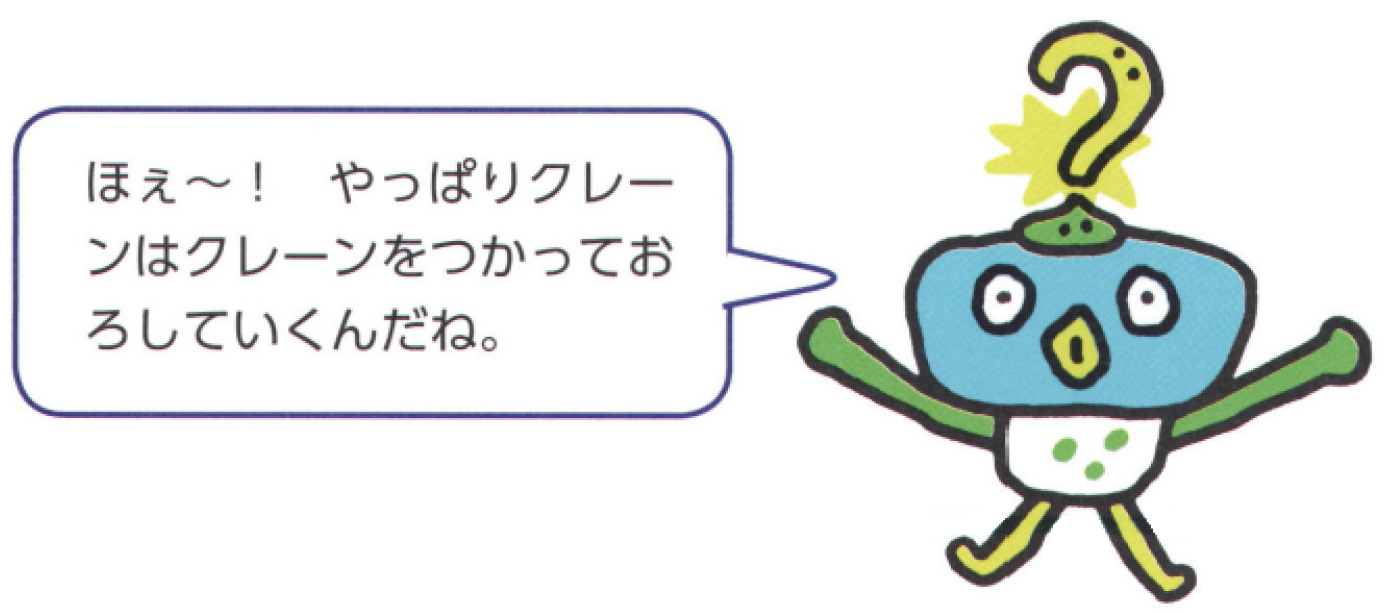
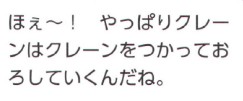
165
鉄はどうしてさびるの?
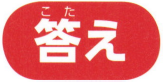 空気中の酸素とむすびつくから
空気中の酸素とむすびつくから
 はさみやくぎ、包丁などがさびてつかえなくなってしまったことはありませんか? 庭においていた自転車のネジや、校庭の鉄棒が赤茶色になっているのもさびが原因です。
はさみやくぎ、包丁などがさびてつかえなくなってしまったことはありませんか? 庭においていた自転車のネジや、校庭の鉄棒が赤茶色になっているのもさびが原因です。
 さびの正体は「酸化鉄」という成分で、空気中の酸素と鉄がむすびついてできたものです。さびた鉄は弱くなって、ぼろぼろとくずれてしまいます。この反応は、水があるとすすみやすいため、湿気の多い場所や雨にぬれる場所では、さびつきやすくなります。
さびの正体は「酸化鉄」という成分で、空気中の酸素と鉄がむすびついてできたものです。さびた鉄は弱くなって、ぼろぼろとくずれてしまいます。この反応は、水があるとすすみやすいため、湿気の多い場所や雨にぬれる場所では、さびつきやすくなります。
 なぜ鉄は酸素とむすびついてしまうのでしょうか。鉄は、もともと酸素とむすびついた酸化鉄の状態でほりおこされます。そして人の手で、高温でねっして中の酸素をとりのぞくことで鉄になります。
なぜ鉄は酸素とむすびついてしまうのでしょうか。鉄は、もともと酸素とむすびついた酸化鉄の状態でほりおこされます。そして人の手で、高温でねっして中の酸素をとりのぞくことで鉄になります。
むりやり酸素をうばわれた鉄は、つねに酸素とむすびついてもとのすがたにもどろうとします。だから鉄はさびるのです。
 鉄を多くふくむ鉱石、赤鉄鉱。
鉄を多くふくむ鉱石、赤鉄鉱。

 鉄でできたボルトやナット。
鉄でできたボルトやナット。


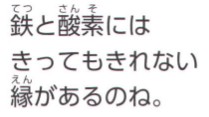
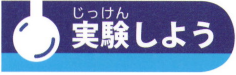 くぎのさび方をしらべよう
くぎのさび方をしらべよう
いろいろな液体に鉄くぎをひたして、さび方のちがいを観察してみよう。
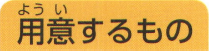
鉄くぎ5本、水、塩水、砂糖水、酢、サンドペーパー
ティッシュペーパー、プラスチックの小さな容器5つ
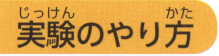
①くぎをさびやすくさせるため、サンドペーパーでみがく。
②塩、砂糖それぞれ小さじ半分を100
の水にとかして、塩水と砂糖水をつくる。
③4つの容器にティッシュペーパーをしき、1つはそのまま、ほかの4つには、それぞれ水、塩水、砂糖水、酢でひたす。
④くぎを1本ずつそれぞれの容器にいれる。ふたはせず、毎日くぎのさび具合を観察しよう。
166
消しゴムでえんぴつの文字がきえるのはなぜ?
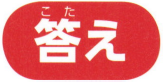 消しゴムがえんぴつのしんのこなを紙からはがしとります
消しゴムがえんぴつのしんのこなを紙からはがしとります
 えんぴつでかいた文字を拡大してみると、紙の繊維のすき間に細かい黒いこながくっついているのがわかります。わたしたちが紙にかいた文字は、えんぴつのしんがけずれて紙の繊維のでこぼこにのこったものなのです。
えんぴつでかいた文字を拡大してみると、紙の繊維のすき間に細かい黒いこながくっついているのがわかります。わたしたちが紙にかいた文字は、えんぴつのしんがけずれて紙の繊維のでこぼこにのこったものなのです。
 現在多くつかわれているプラスチック製の消しゴムは、ゴムではなく、樹脂と細かい研磨剤、そして樹脂をやわらかくする油(かそ材)からできています。
現在多くつかわれているプラスチック製の消しゴムは、ゴムではなく、樹脂と細かい研磨剤、そして樹脂をやわらかくする油(かそ材)からできています。
消しゴムで文字をこすると、研磨剤が黒いこなをかきだします。つぎに、そのこなが油にすいつけられ、紙からはがれます。このとき消しゴムの表面もけずられ、黒いこなはその消したかすと一緒にまるめこまれるのです。こうして文字がきえるのです。
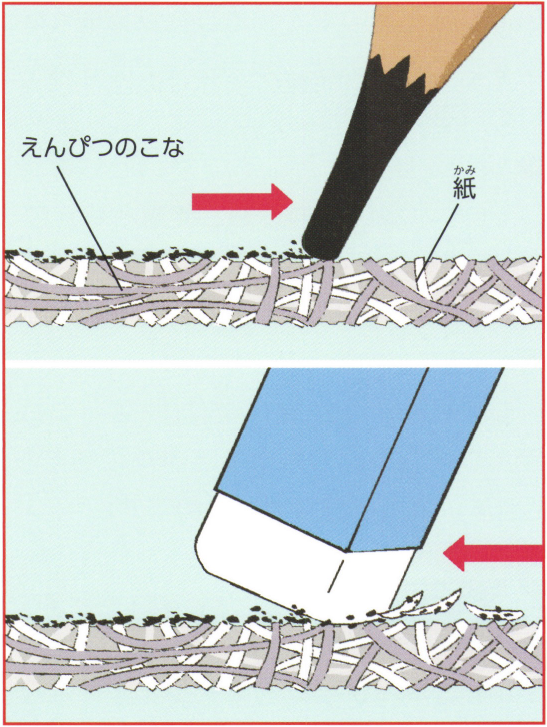

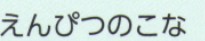

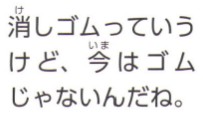
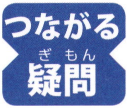 ボールペンは消しゴムできえないの?
ボールペンは消しゴムできえないの?
 インクが紙にしみこむから
インクが紙にしみこむから
 えんぴつのしんは、黒鉛とねんどでできています。黒鉛というのは、黒くてやわらかいのが特徴です。
えんぴつのしんは、黒鉛とねんどでできています。黒鉛というのは、黒くてやわらかいのが特徴です。
えんぴつで文字をかいたとき、黒鉛は紙の繊維のでこぼこにのっているだけなので、消しゴムでけすことができます。しかし、ボールペンや色えんぴつは消しゴムではけせませんね。それは、ボールペンが黒鉛でなくインクでできているからです。インクは紙の繊維のなかにしみこんでしまいます。
また、色えんぴつのしんにはろうがはいっているため、消しゴムにくっつきにくく、えんぴつのようにけすことができないのです。
 筆記用具の材料
筆記用具の材料
| えんぴつ
| 黒鉛、ねんど
|
|---|
| ボールペン
| インク(樹脂、溶剤、着色料)
|
|---|
| 色えんぴつ
| 顔料、のり、ろう、タルク
|
|---|
| 油性ペン
| インク(樹脂、溶剤、染料)
|
|---|
167
方位磁石はどうして北をさすの?
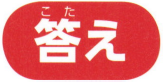 地球が巨大な磁石だから
地球が巨大な磁石だから
 地球のどこにいても磁石のN極はいつも北の方向をさします。これは地球が大きな磁石だからです。
地球のどこにいても磁石のN極はいつも北の方向をさします。これは地球が大きな磁石だからです。
地球は北極の方向がS極、南極の方向がN極になっていて、地球のまわりには「磁場」という磁力のはたらくところがあります。そのために方位磁石は、N極が北極の方向、北をさします。
 なぜ地球では磁力がうまれるのでしょうか。地球の中心には「核」とよばれる部分があります。
なぜ地球では磁力がうまれるのでしょうか。地球の中心には「核」とよばれる部分があります。
そこにはどろどろにとけた鉄やニッケルなどの金属がうずをまいてまわっています。その流れが発電機のようなはたらきをして、電気と磁気がうまれるとかんがえられています。
 地球は大きな磁石。
地球は大きな磁石。
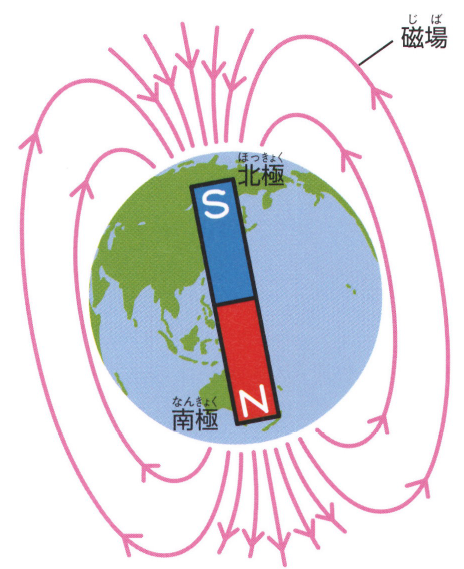





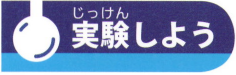 普通の磁石も北をさすのかな?
普通の磁石も北をさすのかな?
方位磁石も、鉄をひきつける磁石も、同じ磁石です。U字型磁石や棒状磁石も北をさすでしょうか。実験でたしかめてみましょう。
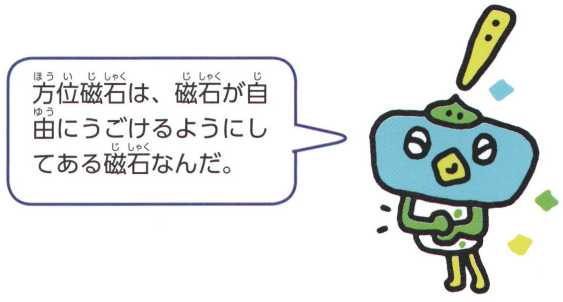
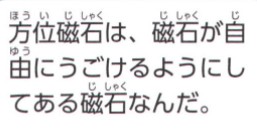
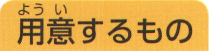
U字型磁石、棒状磁石、方位磁石、たこ糸
発泡スチロールの食品トレー、洗面器、水
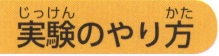
U字型磁石と棒磁石が自由にうごけるようにして、N極がさす方向を方位磁石のむきとくらべます。
 U字型磁石
U字型磁石
タコ糸でつるして、自由にうごけるように手にもつ。
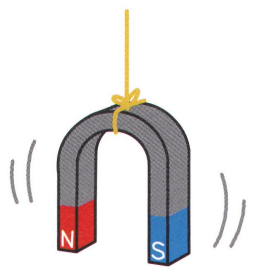


 棒磁石
棒磁石
発泡スチロールのトレーにのせて、水をいれた洗面器にうかべる。
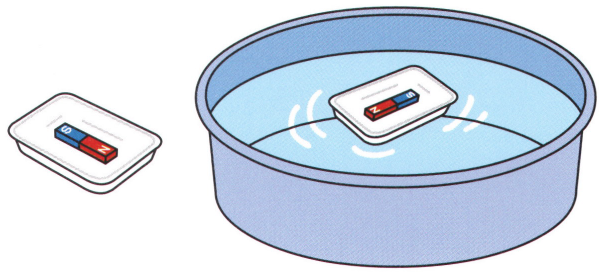
168
どうしてふとんをほすの?
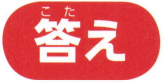 しめったふとんをかわかしてふかふかにするため
しめったふとんをかわかしてふかふかにするため
 ふかふかのふとんでねるのはとても気持ちがいいですね。ふとんがふかふかしているのは、中にはいっている綿の間に空気がたくさんふくまれているからです。
ふかふかのふとんでねるのはとても気持ちがいいですね。ふとんがふかふかしているのは、中にはいっている綿の間に空気がたくさんふくまれているからです。
 わたしたちはねている間に、およそコップ1ぱい分の汗をかくといわれています。汗がふとんにしみこむと、しめって重くなり、中の空気も少なくなります。
わたしたちはねている間に、およそコップ1ぱい分の汗をかくといわれています。汗がふとんにしみこむと、しめって重くなり、中の空気も少なくなります。
天気のいい日、ふとんを太陽にあてると、熱であたたまり、中の水分がでていきます。かわいたふとんは、ふたたびふかふかになり、夜にはまた気持ちよくねることができるのです。
 また、ふとんをかわかすことで、湿気をこのむカビやダニがふえるのをふせぎます。太陽の光には紫外線がふくまれているため、消毒の効果もあります。
また、ふとんをかわかすことで、湿気をこのむカビやダニがふえるのをふせぎます。太陽の光には紫外線がふくまれているため、消毒の効果もあります。
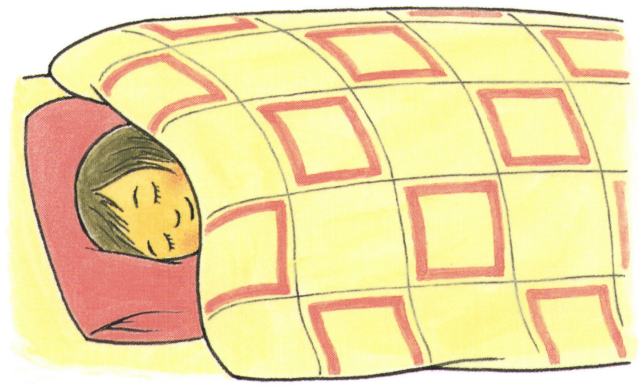
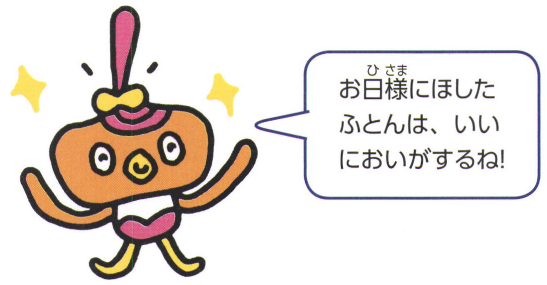
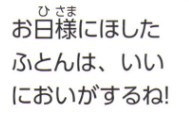
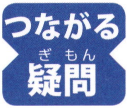 布団の水分はどこへいくの?
布団の水分はどこへいくの?
 蒸発して空気中にでていきます
蒸発して空気中にでていきます
 ものは、温度が高くなるにつれて、固体から液体、気体へと変化します。液体の表面から自然に気体になることを「蒸発」といいます。
ものは、温度が高くなるにつれて、固体から液体、気体へと変化します。液体の表面から自然に気体になることを「蒸発」といいます。
沸騰しているやかんを火にかけつづけると、水がなくなって、やかんがからっぽになってしまいますね。これは、水が蒸発して空気中にでていくからです。雨でぬれた道路や洗濯ものがかわくのも、蒸発によるものです。
蒸発は、温度が高いほどおこりやすくなります。布団の中の汗も、太陽の熱であたためられ、風にあたることで、自然にでていくのです。
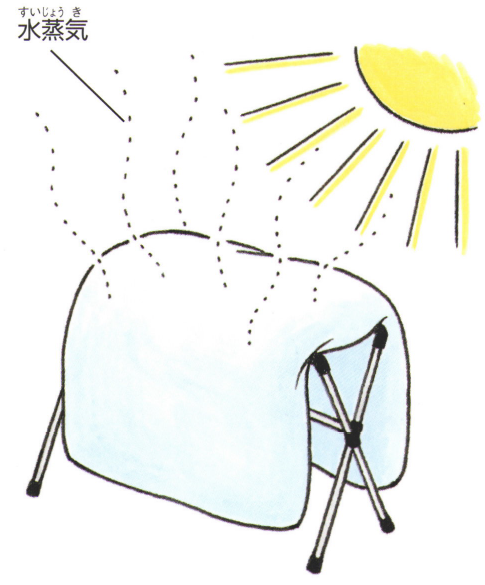

169
布や道路がぬれると色がかわるのはなぜ?
 反射する光の量が少なくなるから
反射する光の量が少なくなるから
 ぬれた洋服や雨にぬれた道路は、いつもよりこい色に見えますね。これは、布や道路がぬれると、表面に反射する光の量が少なくなるからです。
ぬれた洋服や雨にぬれた道路は、いつもよりこい色に見えますね。これは、布や道路がぬれると、表面に反射する光の量が少なくなるからです。
ふだん、わたしたちがものの明るさをかんじるのは、ものにあたってはねかえった光が目にとどくからです。はねかえる光の量が多ければ明るく、少なければ暗くみえるのです。
 かわいた道路の表面は、よくみるとでこぼこしています。そこに光があたると、あちこちに光がぶつかり、はねかえる光の量はふえます。
かわいた道路の表面は、よくみるとでこぼこしています。そこに光があたると、あちこちに光がぶつかり、はねかえる光の量はふえます。
道路が水にぬれると、でこぼこが水によって平らになります。すると、光は一方向にはねかえるだけで光の量が少なくなります。だから、水にぬれたものは暗く、こくみえるのです。
 布の場合は、ぬれると光がとおりぬけてしまうので反射する光が少なくなって、暗くこくみえるのです。
布の場合は、ぬれると光がとおりぬけてしまうので反射する光が少なくなって、暗くこくみえるのです。
 かわいたところでは、光がいろいろな方向にはねかえる。
かわいたところでは、光がいろいろな方向にはねかえる。
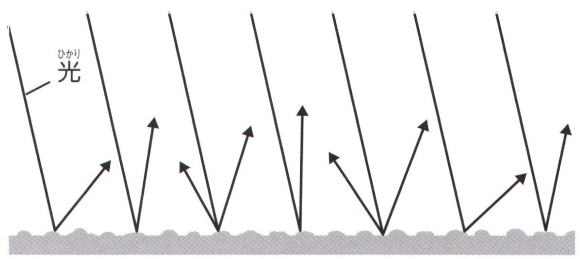

 水にぬれて鏡のようになると、光はひとつの方向へしかはねかえらない。
水にぬれて鏡のようになると、光はひとつの方向へしかはねかえらない。
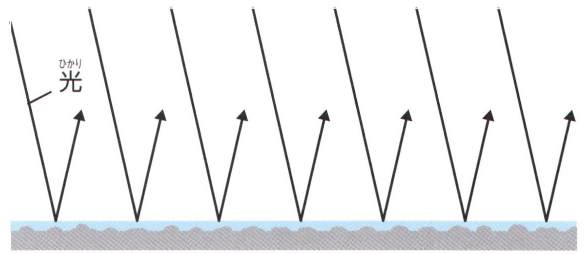

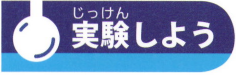 ティッシュペーパーでしらべよう
ティッシュペーパーでしらべよう
ものがぬれたときの色の変化を、ティッシュペーパーをつかってたしかめよう。
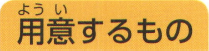
ティッシュペーパー、水
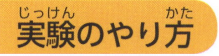
①ティッシュペーパーをつくえの上において、まんなかに水をたらす。水でぬれた部分の色はどうかわるかな?
②つぎにそのティッシュペーパーを明りにかざしてみる。今度はぬれた部分はどうみえるかな?
 実験の結果
実験の結果
①では、水でぬらした部分の色がこくなりますが、②ではぎゃくに、ぬれた部分が明るくみえます。なぜでしょうか? それは、水が繊維にしみこんだため、光が表面ではねかえらずに、とおりぬけてしまうからです。
 つくえの上においたとき。
つくえの上においたとき。
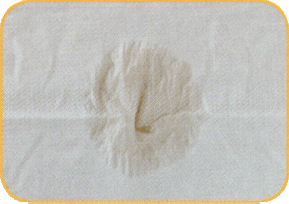
 明かりにかざしたとき。
明かりにかざしたとき。

170
お湯がわくとなぜシューシュー音がでるの?
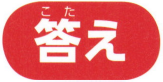 すき間から蒸気がでようとするから
すき間から蒸気がでようとするから
 やかんでお湯をわかすと、やかんの口から湯気がでて、シューシューという音がしますね。
やかんでお湯をわかすと、やかんの口から湯気がでて、シューシューという音がしますね。
そのとき、やかんの口をよくみると、出口のすぐちかくでは湯気がみえません。やかんからでたばかりでは、まだ目にみえない水蒸気だからです。
水蒸気は、水が沸騰して、空気のような気体になったものです。水蒸気は空気中でひやされると、また液体にもどり、目にみえる小さな水のつぶになります。これが湯気です。
 やかんの中で水がねっせられ、100℃になると水蒸気になりはじめます。水蒸気は軽いので、上へ上へとあがります。そして、やかんの中にとじこめられた水蒸気はふたをおしあげ、すき間から外へにげようとします。そのとき、シューシューという音をたてるのです。
やかんの中で水がねっせられ、100℃になると水蒸気になりはじめます。水蒸気は軽いので、上へ上へとあがります。そして、やかんの中にとじこめられた水蒸気はふたをおしあげ、すき間から外へにげようとします。そのとき、シューシューという音をたてるのです。
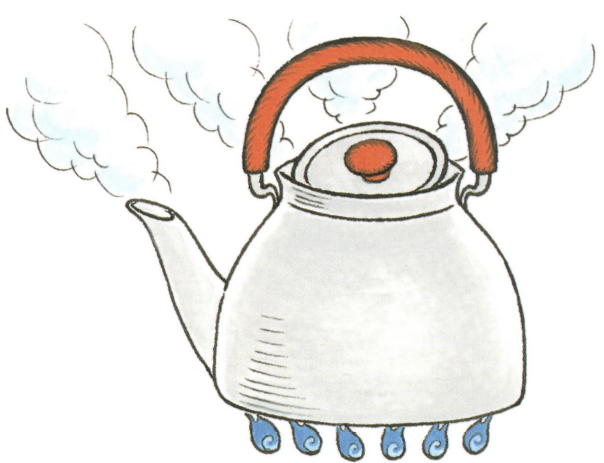

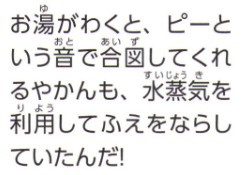
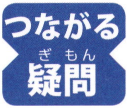 お湯をわかすとなべの底からでてくるあわは何?
お湯をわかすとなべの底からでてくるあわは何?
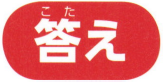 気体になった水です
気体になった水です
 なべややかんでお湯をわかすと、底からぷくぷくとあわがでてきますね。いったいどこからわいてくるのでしょうか。
なべややかんでお湯をわかすと、底からぷくぷくとあわがでてきますね。いったいどこからわいてくるのでしょうか。
どこからか空気がでているようにみえますが、このあわの正体は空気ではなく水蒸気です。つまり、水そのものが気体にかわったすがたなのです。
 水はなべの底にちかい部分から温度が高くなり、100℃になると水蒸気になってどんどんうきあがってきます。
水はなべの底にちかい部分から温度が高くなり、100℃になると水蒸気になってどんどんうきあがってきます。
このように、ねっせられた水が気体になることを「沸騰」といいます。沸騰がつづくと、やがてなべの水はすべて水蒸気になり、からっぽになります。

171
冷たいコップに水滴がつくのはなぜ?
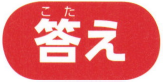 空気中の水蒸気がひやされて水にかわるから
空気中の水蒸気がひやされて水にかわるから
 冷たいジュースをいれたコップの表面に水滴ができるのをみたことがありますか? この水滴はどこからやってきたのでしょうか。
冷たいジュースをいれたコップの表面に水滴ができるのをみたことがありますか? この水滴はどこからやってきたのでしょうか。
 空気の中には水が気体になった水蒸気がふくまれています。空気中に存在できる水蒸気の量は、温度によってきまり、温度が低いほど少なく、高いほど多くなります。
空気の中には水が気体になった水蒸気がふくまれています。空気中に存在できる水蒸気の量は、温度によってきまり、温度が低いほど少なく、高いほど多くなります。
冷たい飲み物がはいったコップのまわりの空気は、飲み物にひやされ、温度が低くなります。すると、今までコップのまわりにあった水蒸気が水蒸気でいられなくなり、液体の状態、つまり水にもどります。それが水滴となってコップの表面につくのです。
 冬の暖房がきいた部屋の窓にも同じ現象がおこります。窓やドアのちかくの空気がひやされて、水蒸気でいられなくなり、窓のサッシやガラスに水滴がつくのです。この現象を「結露」といいます。
冬の暖房がきいた部屋の窓にも同じ現象がおこります。窓やドアのちかくの空気がひやされて、水蒸気でいられなくなり、窓のサッシやガラスに水滴がつくのです。この現象を「結露」といいます。
 コップについた水滴。
コップについた水滴。

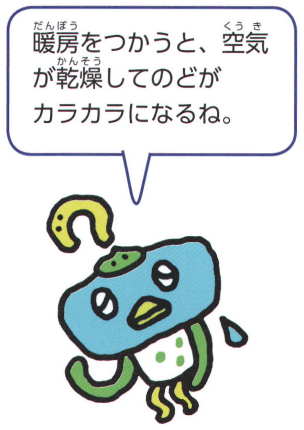
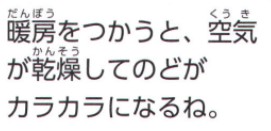
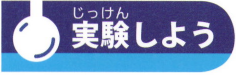 空気中の水蒸気をつかまえよう
空気中の水蒸気をつかまえよう
目にはみえませんが、晴れの日にも空気中にたくさんの水蒸気が存在しています。水の温度をかえて水滴のつき方をしらべてみましょう。
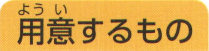
お湯、水(室温にしたもの)、氷、ラップ
耐熱性のコップ3つ、温度計、湿度計
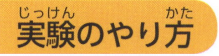
①3つのコップにお湯、水、氷水をそれぞれ同じくらいいれ、ラップでふたをする。
②コップのまわりや内側の水滴のでき方を観察しよう。
観察例:
| 気温
| 湿度
| 水滴のでき方
|
|---|
| ○○℃
| ○○%
| 水
| 氷水
| お湯
|
| 水滴はつかない。
| コップの外に
水滴がついた。
| ラップの内側に
水滴がついた。
|
 温度と水滴の関係
温度と水滴の関係
3つのコップの水滴のつき方と温度の関係がわかったかな。お湯をいれたコップは、ラップの内側に水滴がつきます。これは、コップの中の水蒸気が外側からひやされて水滴になったものです。
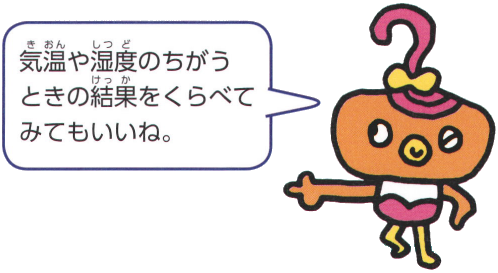
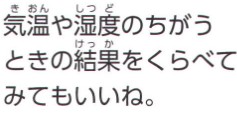
172
雪はどうしてふるの?
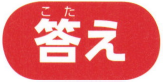 空でこおった水蒸気がおちてくるから
空でこおった水蒸気がおちてくるから
 雪がふっているとき、空をみあげると雲がありますね。雲は、空気中の水蒸気が空の高いところでひやされ、小さな水のつぶになってあつまったものです。
雪がふっているとき、空をみあげると雲がありますね。雲は、空気中の水蒸気が空の高いところでひやされ、小さな水のつぶになってあつまったものです。
冬、気温がさがると、水のつぶはこおって、氷になります。氷のつぶがくっつきあい、重くなるとやがて地上へとおちてきます。それが雪です。
 雪をよくみると、ひとつひとつは、小さな花のような形をしているのがわかります。これを「雪の結晶」といいます。
雪をよくみると、ひとつひとつは、小さな花のような形をしているのがわかります。これを「雪の結晶」といいます。
雪の結晶の形は、たいていきれいな六角形をしています。五角形や八角形はありません。これは、最初に水蒸気が氷のつぶになるときに六角形になるからです。この六角形のつぶの角に水蒸気がつぎつぎとくっついて、結晶が成長するのです。
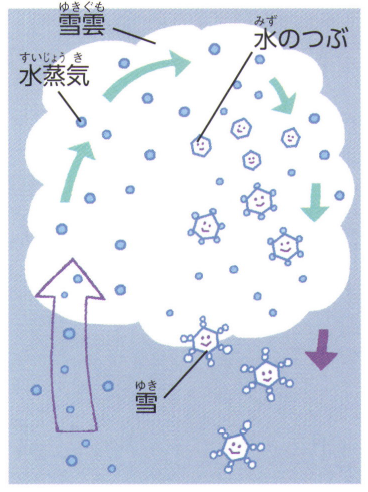

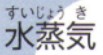
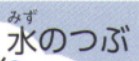

 雪の結晶。
雪の結晶。
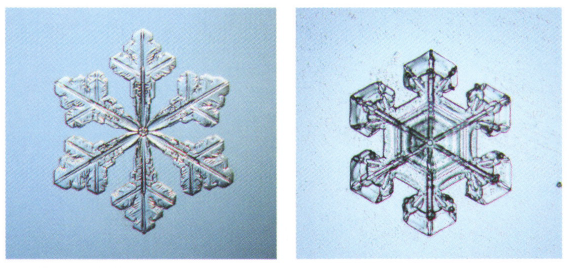
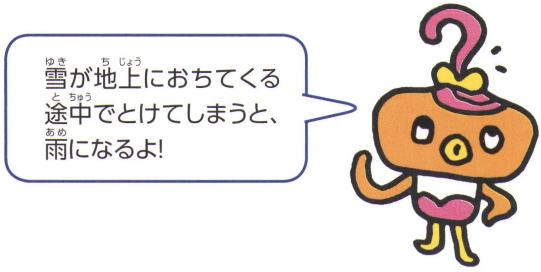
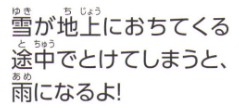
173
飛行機雲はどうしてできるの?
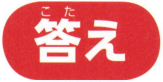 飛行機のエンジンからでた水蒸気がこおるから
飛行機のエンジンからでた水蒸気がこおるから
 飛行機雲には2種類のでき方があります。
飛行機雲には2種類のでき方があります。
まず1つ目は、エンジンからでる排気ガスが雲になるものです。飛行機がとぶのは、地面から1万
以上の高さです。そのあたりは、温度がとても低く、-40℃以下になります。
飛行機がこのような気温が低いところをとぶと、エンジンからでる排気ガスにふくまれる水蒸気が、すべて氷のつぶにかわってしまいます。そのようすが地上からは、白い雲のようにみえるのです。
 2つ目のでき方は、飛行機の主翼の後ろに空気のうずができて、部分的に気圧と気温がさがり、空気中の水蒸気がこおってできるというものです。空気中にふくまれる水蒸気が多いときほど、飛行機雲ができやすくなります。
2つ目のでき方は、飛行機の主翼の後ろに空気のうずができて、部分的に気圧と気温がさがり、空気中の水蒸気がこおってできるというものです。空気中にふくまれる水蒸気が多いときほど、飛行機雲ができやすくなります。
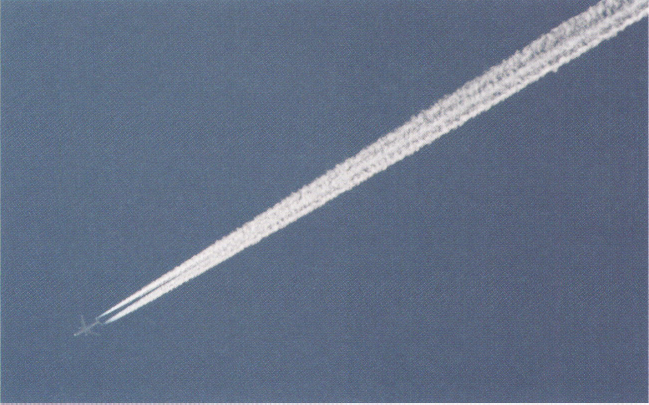
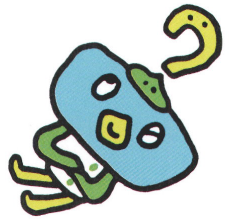
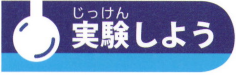 ペットボトルで雲をつくろう
ペットボトルで雲をつくろう
上空で雲ができる現象をペットボトルの中で実験してみよう。

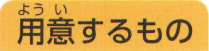
炭酸飲料のペットボトル(500
)
ポンプつきのキャップ(炭酸がぬけにくくなるペットボトル用のキャップ。ホームセンターなどでかえる)
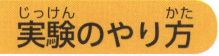
①ペットボトルの内側を水でぬらす。
②ポンプつきのキャップをしっかりとはめる。
③ポンプをおして、ペットボトルに空気をいれる。
④もうそれ以上はいらないくらいにぱんぱんになったら、ポンプのキャップを一気にあける。すると、ペットボトルの中に雲ができる。
※炭酸以外のペットボトルは破裂の危険があります。使用しないこと!
 雲ができるわけ
雲ができるわけ
ポンプつきのキャップで、ペットボトルの中に空気をおしこむと空気がちぢみます。空気はおしちぢめられると温度があがるため、ペットボトルの中の水が蒸発して空気の中にまざります。
そこでキャップをはずすと、中の空気が一気にふくらんで、今度は温度がさがり、水蒸気がふたたび水になって雲ができるのです。
174
空気にも重さはあるの?
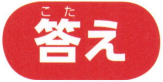 空気は目にみえなくても重さがあります
空気は目にみえなくても重さがあります
 自分のまわりにある空気の重さをかんじたことはありますか。空気は目でみたり、さわってかんじたりすることができません。でも、空気にもほかのものと同じようにきちんと重さがあります。
自分のまわりにある空気の重さをかんじたことはありますか。空気は目でみたり、さわってかんじたりすることができません。でも、空気にもほかのものと同じようにきちんと重さがあります。
強い風がふいているとき、風で体がおされることがありますね。これは、体に空気の重さがぶつかってくるからです。台風の風で木がたおれたり、屋根がとんだりしてしまうのも、空気の重さにたえられなくなるからです。
空気は1
で1円玉1こ(1
)と同じくらいの重さがあります。
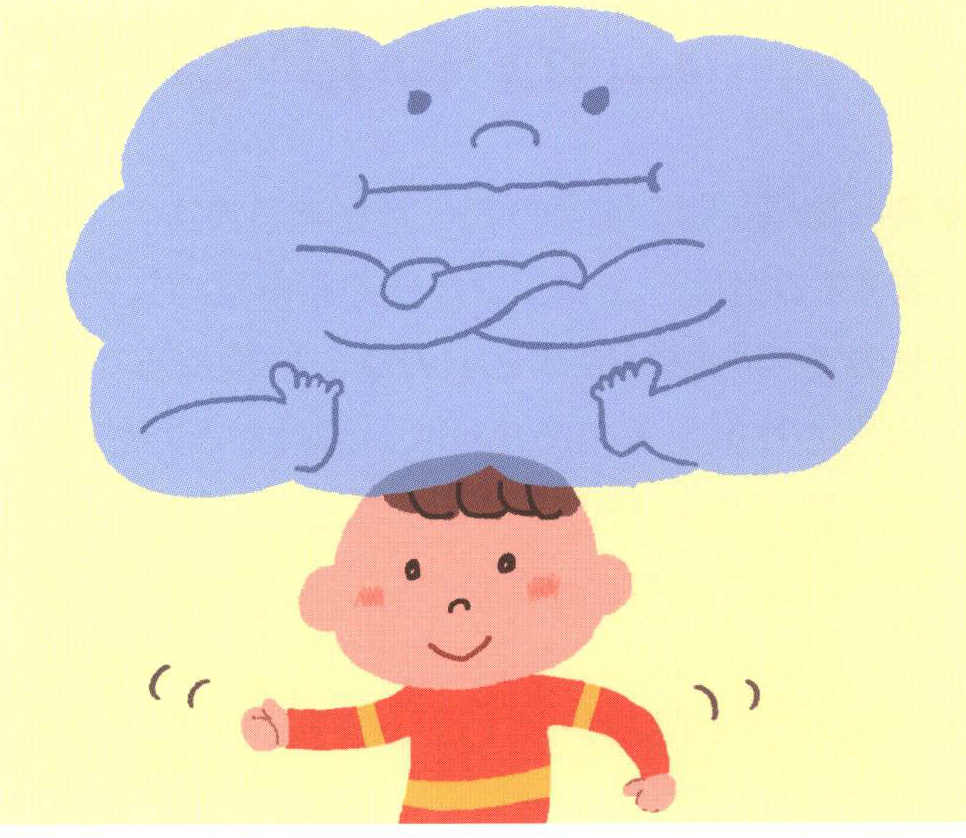
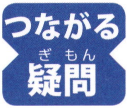 空気の重さをかんじないのはなぜ?
空気の重さをかんじないのはなぜ?
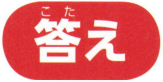 体の中から空気をおしかえす力があるからです
体の中から空気をおしかえす力があるからです
 わたしたちの頭の上には、およそ10
の高さまで空気がつみかさなっています。その空気は、手の平におとなひとりをのせているのと同じ力でわたしたちを上からおしています。
わたしたちの頭の上には、およそ10
の高さまで空気がつみかさなっています。その空気は、手の平におとなひとりをのせているのと同じ力でわたしたちを上からおしています。
それなのに、なぜ重さをかんじないのでしょうか? それは、わたしたちの体の中に、空気をおしかえす力があって、ちょうどつりあっているからです。
 空気のおす力は、高いところほど小さくなります。自分の上にある空気が少なくなるからです。
空気のおす力は、高いところほど小さくなります。自分の上にある空気が少なくなるからです。
高い山にふくろ入りのおかしやパンをもっていくと、ふくろがパンパンにふくらんでしまいます。外からの空気がおす力よりも、ふくろの中にとじこめられている空気が内側からおしかえす力のほうが強くなるためです。
高い山にのぼるときは、ふくろ入りのおやつをもっていって観察してみましょう。
 高いところほど空気におされる力が弱い。
高いところほど空気におされる力が弱い。
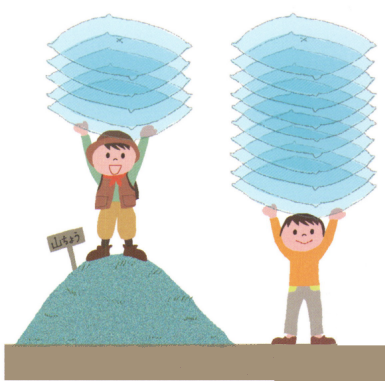
 パンパンになったおかしのふくろ。
パンパンになったおかしのふくろ。

175
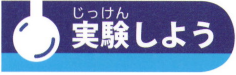 空気砲で空気のパワーをかんじよう
空気砲で空気のパワーをかんじよう
空気のたまがとびだす空気砲をつくって、空気の力を体験しよう。
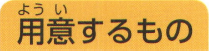
段ボール箱、布ガムテープ、カッターナイフ
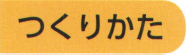
①段ボール箱のつなぎ目に、布ガムテープを3重にはって密閉する。
②箱の側面に直径10
くらいの丸い穴をあける。おわんや缶などの丸いものをあてて、ぐるりとしるしをつけてから、カッターナイフできりとる。
③ふたの部分がうごかないように、穴から手をいれて内側から数か所とめておく。
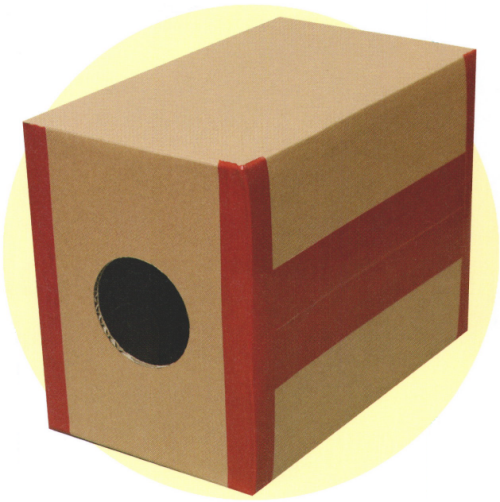
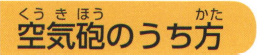
①空気をあてたいものに丸い穴をむけ、片手で箱をかかえる。
②もう片方の手で箱の反対側を強くたたく。箱を台の上において、両側からたたいてもいい。


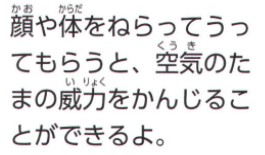
 空気砲のたまはこんな形をしている
空気砲のたまはこんな形をしている
箱をたたいた瞬間、中の空気がいきおいよく外へおしだされます。とびだした空気は、うずのわになってとんでいきます。
 うずをまくことで、たまは空気をかいてすすむ力が強くなり、いきおいよくとんでいく。
うずをまくことで、たまは空気をかいてすすむ力が強くなり、いきおいよくとんでいく。
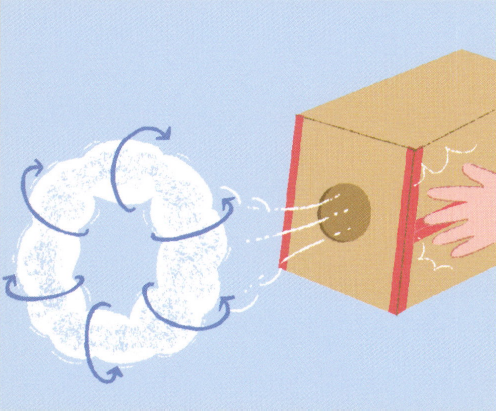
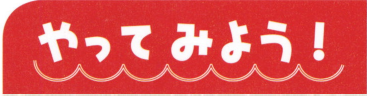 こんなあそびもやってみよう。
こんなあそびもやってみよう。
 紙をおってつくったまとをねらって、たおしてみよう。
紙をおってつくったまとをねらって、たおしてみよう。
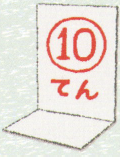
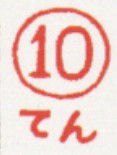
 はなれたところにたてたろうそくをねらって、火をけしてみよう。
はなれたところにたてたろうそくをねらって、火をけしてみよう。
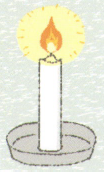
※火をつかうときはかならずおとなの人とやりましょう。
176
紅茶にレモンをいれると色がかわるのはなぜ?
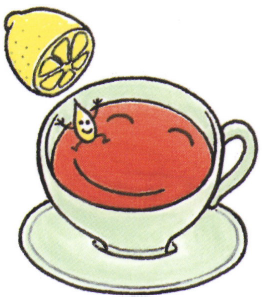
 茶の色の成分がレモンの酸できえるから
茶の色の成分がレモンの酸できえるから
 紅茶は、もともと、葉をつむときには緑色をしています。この緑色の葉をかわかして、手でよくもんで、あたたかい部屋にねかせて発酵させると、赤茶色の紅茶ができあがります。
紅茶は、もともと、葉をつむときには緑色をしています。この緑色の葉をかわかして、手でよくもんで、あたたかい部屋にねかせて発酵させると、赤茶色の紅茶ができあがります。
 紅茶にお湯をそそぐと、葉の赤茶色がお湯にうつります。この紅茶の色はいくつかの成分でできていますが、そのなかのひとつの成分「テアフラビン」がレモンにふくまれる「クエン酸」という酸性の成分によって変化し、無色になるのです。そのため、紅茶にレモンをいれると、色がうすくかわるのです。
紅茶にお湯をそそぐと、葉の赤茶色がお湯にうつります。この紅茶の色はいくつかの成分でできていますが、そのなかのひとつの成分「テアフラビン」がレモンにふくまれる「クエン酸」という酸性の成分によって変化し、無色になるのです。そのため、紅茶にレモンをいれると、色がうすくかわるのです。
紅茶にはちみつをいれると、今度は色がこくなります。これは、はちみつにふくまれるアルカリ性の成分に紅茶が反応するからです。
 レモンをいれる前の紅茶。
レモンをいれる前の紅茶。

 レモンをいれた後の紅茶。
レモンをいれた後の紅茶。

177
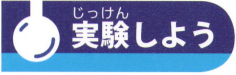 ナスの色素で水溶液をしらべよう
ナスの色素で水溶液をしらべよう
ナスの皮からとった色水にいろいろな水溶液をまぜてみましょう。どんな色にかわるかな?
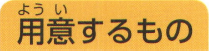
ナス1本、レモン汁、酢、台所用洗剤、重曹、ミョウバン、せっけん水、サンドペーパー
たまごの空きパック(透明なもの)
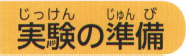
 ナスから色水をつくる
ナスから色水をつくる
ナスの皮をサンドペーパーでこすって、きずをつける。コップに水をいれナスをつけて、水に色をうつす。
 重曹とミョウバンの水溶液をつくる
重曹とミョウバンの水溶液をつくる
大さじ2のぬるま湯を2つ用意し、重曹とミョウバンをそれぞれ小さじ半分ずつとかし、さましておく。
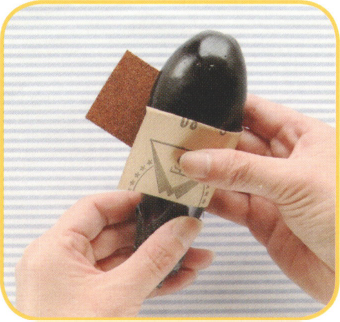

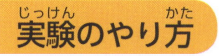
①たまごのパックのくぼみに、ナスの色水を半分くらいまでいれる。

②レモン汁、酢、台所用洗剤、重曹水、ミョウバン水、石けん水をそれぞれのくぼみに少しずつくわえる。

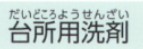

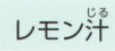
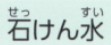
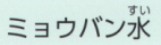

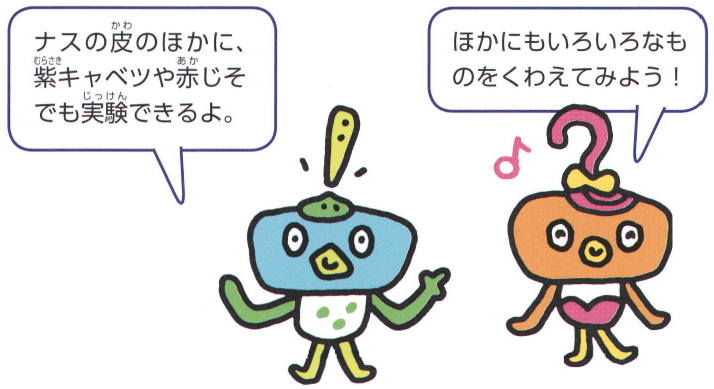
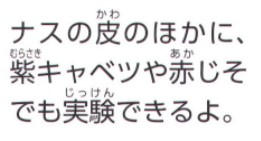
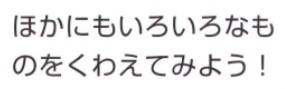
 ナスの色のひみつ
ナスの色のひみつ
ナスのむらさき色は、皮にふくまれるポリフェノールの一種の「ナスニン」という色素です。
ナスニンは、アントシアニンという色素のなかまで、酸性では赤に、中性ではむらさきに、アルカリ性では青になるという性質があります。
この実験では、このナスニンの性質をつかって、水溶液の酸性・中性・アルカリ性をしらべることができます。
赤やピンクに変化したレモン汁、酢、台所用洗剤は酸性、青く変化した重曹水、ミョウバン水はアルカリ性、ほとんどかわらなかった石けん水は、中性であることがわかります。
178
たまごをゆでるとかたまるのはなぜ?
 たまごにふくまれるたんぱく質は熱をくわえるとかたまるから
たまごにふくまれるたんぱく質は熱をくわえるとかたまるから
 生たまごをわると、黄色い黄身と、透明な白身がどろっとでてきますね。それでは、ゆでたまごをわるとどうでしょう? たまごはゆでるとかたくなりますね。
生たまごをわると、黄色い黄身と、透明な白身がどろっとでてきますね。それでは、ゆでたまごをわるとどうでしょう? たまごはゆでるとかたくなりますね。
たまごにはたんぱく質がたくさんふくまれています。たんぱく質は熱をくわえるとかたまる性質があるので、たまごをゆでるとかたまるのです。ちゃわんむしやプリンも、この性質を利用してかためます。
 たまごの黄身と白身は、それぞれかたまる温度がちがいます。黄身は70℃くらい、白身は80℃くらいで完全にかたまります。
たまごの黄身と白身は、それぞれかたまる温度がちがいます。黄身は70℃くらい、白身は80℃くらいで完全にかたまります。
100℃のお湯で長い時間ゆでると、白身も黄身もしっかりとかたまった、かたゆでたまごになります。ゆでる時間をみじかくすると、黄身がとろっとした半熟たまごになります。

 たんぱく質の性質をキッチンでみてみよう!
たんぱく質の性質をキッチンでみてみよう!
牛乳も、たんぱく質をたくさんふくむ食品です。牛乳でたんぱく質の性質を観察してみましょう。
 牛乳のまく
牛乳のまく
牛乳をあたためると、表面にうすいまくができますね。これは、牛乳にふくまれるたんぱく質が熱によってかたまったものです。牛乳は40℃以上になると、表面の空気にふれているところから水分が蒸発して、たんぱく質が脂肪と乳糖をつつみこみながらかたまります。
大豆からつくられる豆乳でも同じようにまくができます。これは「ゆば」という食材になります。
 牛乳とオレンジジュース
牛乳とオレンジジュース
牛乳に果汁100%のオレンジジュースをまぜると、とろとろとヨーグルトのようになります。牛乳にふくまれるたんぱく質がオレンジの酸によってかたまるからです。レモンなどの酸性のものでもできます。
 豆乳からつくるゆば。
豆乳からつくるゆば。

 牛乳にオレンジジュースをいれるとたんぱく質がかたまって分離する。
牛乳にオレンジジュースをいれるとたんぱく質がかたまって分離する。

179
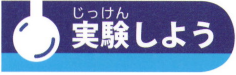 ゆでたまごと温泉たまごをつくろう
ゆでたまごと温泉たまごをつくろう
黄身と白身のかたまる温度のちがいを利用して、ゆでたまごと温泉たまごをつくってみましょう。

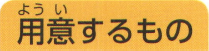
たまご1こ、水、小さななべ、キッチンタイマー
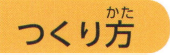
①なべに水をいれて火にかけ、沸騰したらたまごをしずかにいれる。
②10分たったらとりだして水でひやし、からをむく。
③包丁で半分にきって、中のようすを観察しよう。
 沸騰したお湯にたまごをいれてゆでる。
沸騰したお湯にたまごをいれてゆでる。
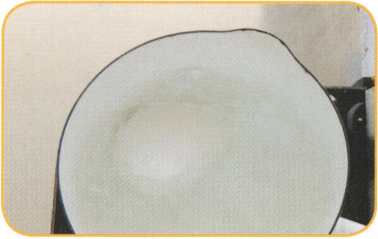
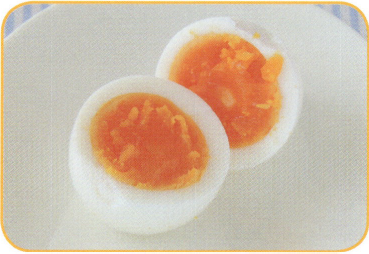
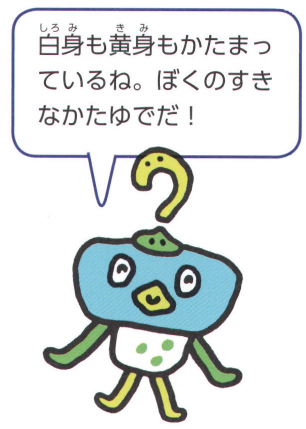
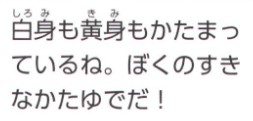

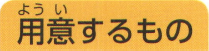
たまご1こ、熱湯、カップめんの容器
キッチンタイマー
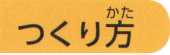
①カップめんの容器に沸騰したお湯をいれ、その中にたまごをしずかにいれる。
②ふたはせず、30分おいたらとりだす。
③からをわってお皿にだし、中のようすを観察しよう。
 カップめんの容器に沸騰したお湯とたまごをいれ、加熱せずにおいておく。
カップめんの容器に沸騰したお湯とたまごをいれ、加熱せずにおいておく。

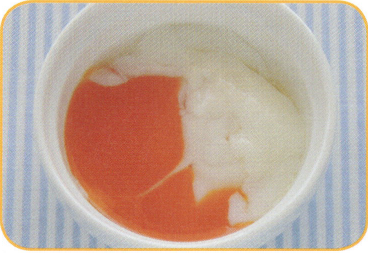

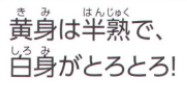
※火をつかう実験はやけどなどに注意しましょう。
 黄身と白身のかたまる温度がポイント
黄身と白身のかたまる温度がポイント
ゆでたまごは、沸騰したお湯にいれてゆでます。加熱されつづけるお湯は100℃の状態をたもちます。すると、まず外側の白身からかたまりはじめ、その後、だんだん内側の黄身がかたまります。黄身の中までしっかり熱がつたわる前にとりだすと、半熟たまごになります。
温泉たまごのつくり方では、はじめ沸騰した100℃のお湯にいれますが、その後少しずつ温度がさがっていきます。そのため、白身も黄身も完全にはかたまらず、どろっとした温泉たまごができあがるのです。
| 温度\時間
| 5分
| 10分
| 15分
| 20分
|
|---|
| 100℃
| 半熟
| かたゆで
|
|
|
|---|
| 90℃
| 半熟
|
| かたゆで
|
|
|---|
| 80℃
|
| 温泉
|
| かたゆで
|
|---|
| 70℃
|
|
| 温泉
|
|
|---|
| 65℃
|
|
|
| 温泉
|
|---|
180
タマネギをきると涙がでるのはなぜ?
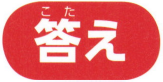 タマネギから涙をださせる成分がでてくるから
タマネギから涙をださせる成分がでてくるから
 タマネギをきっていると、涙や鼻水がでてくることがありますね。これは、タマネギから「硫化アリル」という成分がでてきて、目や鼻を刺激するからです。
タマネギをきっていると、涙や鼻水がでてくることがありますね。これは、タマネギから「硫化アリル」という成分がでてきて、目や鼻を刺激するからです。
 硫化アリルは、タマネギの細胞の中にあるアミノ酸と酵素が反応してできる物質で、タマネギのかわをむいたぐらいではでてきません。しかし、包丁などでタマネギをきると、細胞がこわれて硫化アリルができるのです。
硫化アリルは、タマネギの細胞の中にあるアミノ酸と酵素が反応してできる物質で、タマネギのかわをむいたぐらいではでてきません。しかし、包丁などでタマネギをきると、細胞がこわれて硫化アリルができるのです。
硫化アリルは空気中にひろがりやすく、タマネギをきっている人の目にはいりやすいのです。
 硫化アリルは、タマネギのほかに、ネギやニラ、ニンニクやワサビにもふくまれています。
硫化アリルは、タマネギのほかに、ネギやニラ、ニンニクやワサビにもふくまれています。
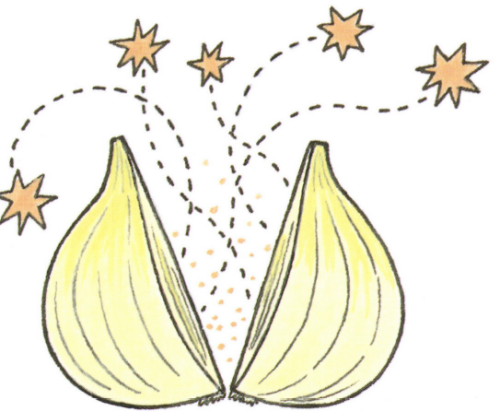
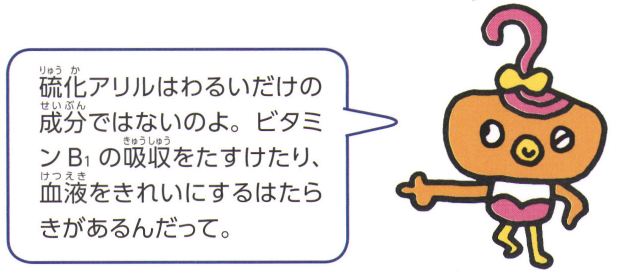
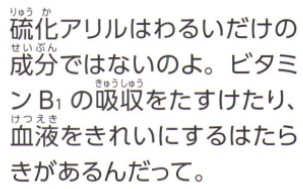
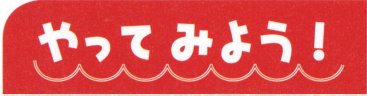 涙がでないくふうをしよう!
涙がでないくふうをしよう!
硫化アリルの性質をしって、涙がでるのをふせぐ工夫をためしてみよう。
 タマネギをひやす
タマネギをひやす
硫化アリルがでやすい温度は常温。きる前にタマネギを冷蔵庫でひやしておくと、硫化アリルがでにくい。
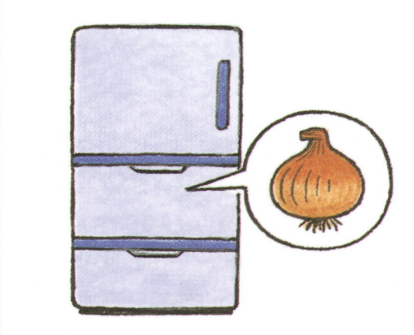
 よくきれる包丁をつかう
よくきれる包丁をつかう
きれにくい包丁できると、タマネギの細胞がこわれやすい。よくきれる包丁をつかうと、硫化アリルがでにくい。
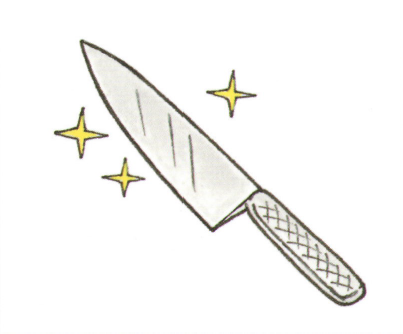
 目と鼻をふさいできる
目と鼻をふさいできる
空気中にひろがる硫化アリルが目や鼻からはいらないように、ゴーグルをつけて、鼻にティッシュペーパーをつめる。
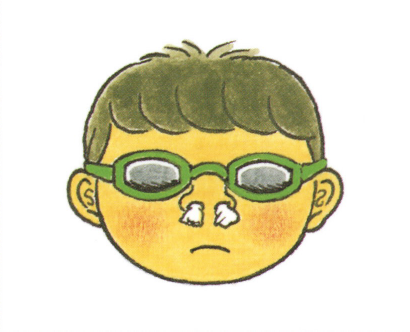
181
うどんの「こし」ってなに?
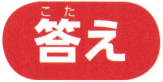 かんだときの歯ごたえのこと
かんだときの歯ごたえのこと
 うどんの「こし」とは、口にいれてかんだときの歯ごたえ、つまり、ねばりや弾力のことをいいます。歯ごたえがあるほど、「こしが強い」とされます。
うどんの「こし」とは、口にいれてかんだときの歯ごたえ、つまり、ねばりや弾力のことをいいます。歯ごたえがあるほど、「こしが強い」とされます。
 では、この「こし」は、どこからうまれるのでしょうか。これは、うどんの原料である小麦粉にふくまれる成分が関係しています。
では、この「こし」は、どこからうまれるのでしょうか。これは、うどんの原料である小麦粉にふくまれる成分が関係しています。
うどんにつかう小麦粉は、たんぱく質が8~9%、でんぷんが77%ふくまれています。このたんぱく質に水をくわえるとねばりと弾力がある「グルテン」がうまれます。
うどんにほどよいこしをもたせるため、うどん職人は、小麦粉にくわえる水や塩の量をかえて、グルテンのできる量を調節します。人の手や足でよくこねたりふんだりすると、グルテンの繊維のむきが複雑になって、強いこしがうまれます。
 こしの強いさぬきうどん。
こしの強いさぬきうどん。
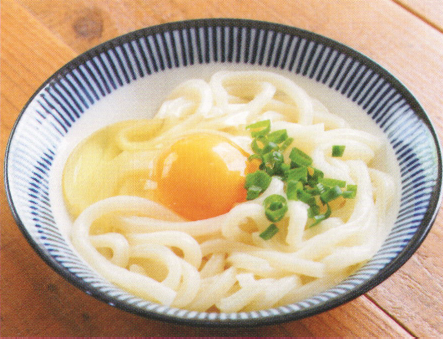
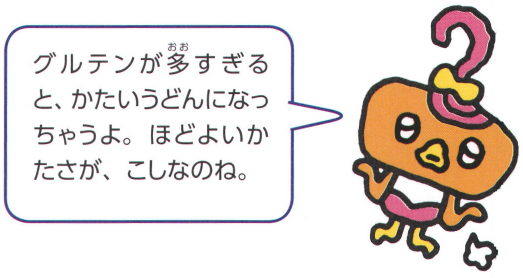
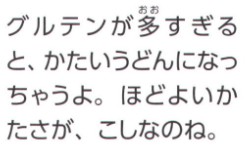
 うどん以外のめんにも、こしはあるのかな?
うどん以外のめんにも、こしはあるのかな?
めんには、うどんのほかにそばやそうめん、パスタなどがありますが、こしはあるでしょうか?
うどんのこしは材料の小麦粉にふくまれる成分にひみつがありました。ほかのめんの材料やつくり方をみてみましょう。
いろいろなめんをたべて、特徴をくらべてみましょう。
 そうめん
そうめん

うどんと同じ小麦粉、水、塩が材料。太さはおよそ1.3
と、うどんよりも細いため、こしはかんじにくいが、つるつるとしたのどごしのよさが特徴。
 パスタ
パスタ
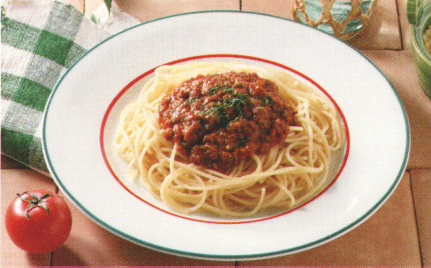
うどんとはちがう種類のデュラム小麦粉が材料。塩をいれたお湯でゆでて、こしをだす。ゆですぎないようにすると、歯ごたえがよくなる。
 そば
そば

そば粉と水でつくられる。ものによってはねばりをだすために、小麦粉などの「つなぎ」とよばれるものをつかう。このつなぎはグルテンの力を利用している。
 ラーメン
ラーメン

小麦粉に「かん水」といわれるアルカリ塩水溶液をくわえてつくる。このかん水は小麦粉にやわらかさや弾力をもたせ、独特のこしがうまれる。

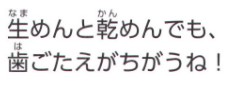
182
納豆はどうしてねばねばするの?
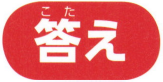 納豆菌がねばねばをつくりだすから
納豆菌がねばねばをつくりだすから
 納豆をまぜると糸をひいて、ねばねばしますね。納豆は、ゆでた大豆に納豆菌という細菌をくわえることでつくられます。細菌といってもおなかをこわしたり、病気をおこしたりするわるい菌ではなく、人の役にたつよい細菌です。この納豆菌は、ふだんはイネのわらの中にすんでいます。
納豆をまぜると糸をひいて、ねばねばしますね。納豆は、ゆでた大豆に納豆菌という細菌をくわえることでつくられます。細菌といってもおなかをこわしたり、病気をおこしたりするわるい菌ではなく、人の役にたつよい細菌です。この納豆菌は、ふだんはイネのわらの中にすんでいます。
 納豆菌を大豆にうつすと、納豆菌が大豆の成分をたべて新しい成分がうまれます。
納豆菌を大豆にうつすと、納豆菌が大豆の成分をたべて新しい成分がうまれます。
納豆のねばねばは、納豆菌がつくりだしたアミノ酸の一種、「グルタミン酸」という成分からできています。長く糸をひくのは、このグルタミン酸がつながってできた長い糸とフラクタンとよばれる糖の一種がからみあってできたものです。グルタミン酸は、昆布などにもふくまれています。
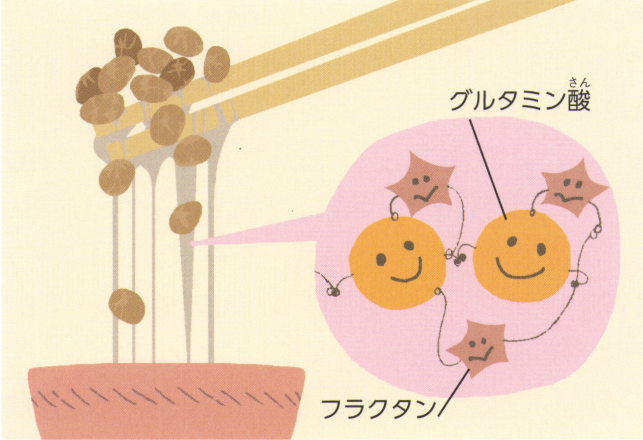
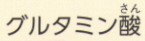
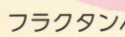
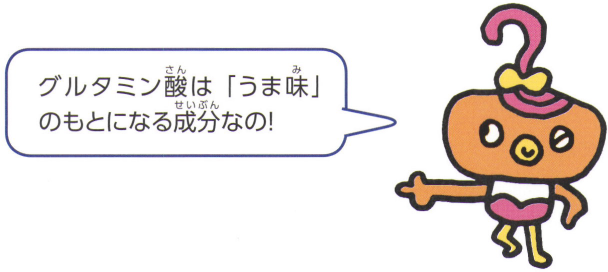
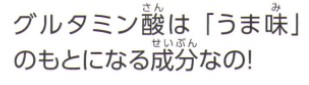
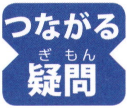 納豆はくさっているの?
納豆はくさっているの?
 くさっているのではなく、発酵しています
くさっているのではなく、発酵しています
 納豆菌が大豆の成分を変化させて、納豆ができあがります。このように菌のはたらきによって食べ物の成分がかわることを「発酵」といいます。
納豆菌が大豆の成分を変化させて、納豆ができあがります。このように菌のはたらきによって食べ物の成分がかわることを「発酵」といいます。
乳酸菌によって牛乳の成分が変化してできたものはヨーグルトですし、こうじ菌によって大豆の成分が変化したものにみそがあります。
 発酵とくさるのとはどうちがうのでしょうか。どちらの場合も、菌がはたらきます。
発酵とくさるのとはどうちがうのでしょうか。どちらの場合も、菌がはたらきます。
発酵するときにはたらく菌は、食べ物によってちがいますが、くさるときには「腐敗菌」がはたらきます。腐敗菌がこのむ条件がそろうと、腐敗菌はふえて、ものはくさっていきます。
発酵とくさることとのちがいは、菌のはたらきによってできたものが「体にいい影響があるか、わるい影響があるか」なのです。
 発酵
発酵
(体にいい影響のある菌)
・納豆菌
・乳酸菌
・ビフィズス菌
・酵母菌
・麹菌
など

 くさる
くさる
(体に悪い影響のある菌)
・病原菌
・腐敗菌
など

184
野菜に塩をかけると水がでてくるのはなぜ?
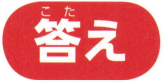 塩の力で野菜のもっていた水が外にでてしまうから
塩の力で野菜のもっていた水が外にでてしまうから
 野菜を塩でもむと、水がでてきてしんなりしますね。これは、塩の力で野菜がもっていた水分が外にでてしまうからです。
野菜を塩でもむと、水がでてきてしんなりしますね。これは、塩の力で野菜がもっていた水分が外にでてしまうからです。
野菜などの植物をはじめ、生き物の細胞は「半透膜」というまくでおおわれています。このまくをとおして、細胞に必要な物質をとりいれたり、すてたりしています。
半透膜には、まくの内側と外側で塩分のこさがちがうと、同じこさにしようとするはたらきがあります。
野菜を塩水につけると、まくの内側のほうが塩分がうすいので、同じこさになるように、水が外へと移動するのです。
 サラダをつくるときに、野菜を水につけておくとパリっと元気になるのも同じ理由です。水がぬけてしなっとした野菜の中に、また水がまくをとおってはいるからです。
サラダをつくるときに、野菜を水につけておくとパリっと元気になるのも同じ理由です。水がぬけてしなっとした野菜の中に、また水がまくをとおってはいるからです。
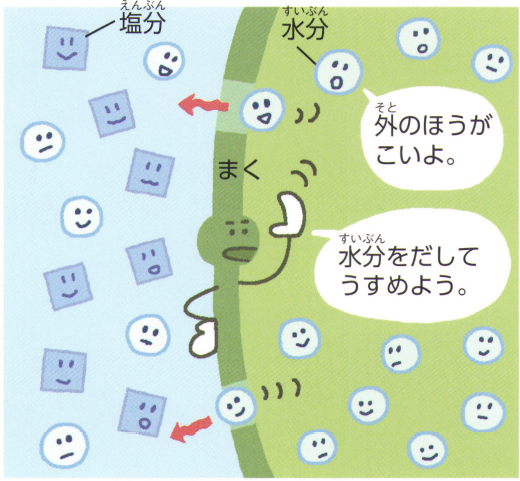



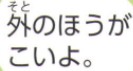
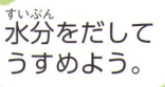
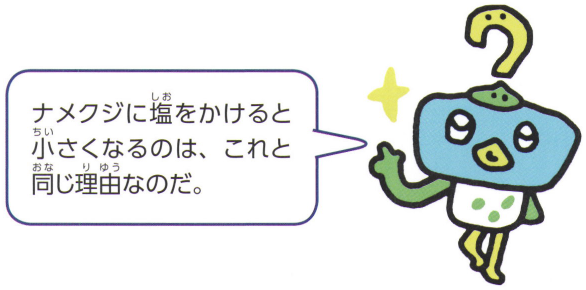
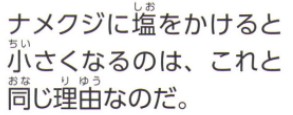
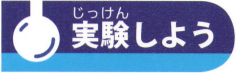 キュウリで実験!
キュウリで実験!
塩が野菜から水をひきだすようすを、キュウリをつかってたしかめよう。
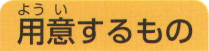
キュウリ1本、塩と砂糖、それぞれ小さじ1/2
ボウル(おわんなどでもいい)3つ、はかり、計量スプーン、コップ
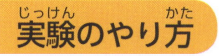
①キュウリをうすぎりにし、3つのボウルに同じ重さになるようにはかってわける。
②1つ目のボウルに塩、2つ目に砂糖をいれて、よくもむ。3つ目は何もいれない。
③20分ほどおいてから、手でキュウリをよくしぼって、でてきた水をコップにうつし、量をくらべる。



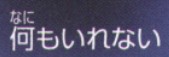
 塩が水をひきだす力
塩が水をひきだす力
何もいれなかったキュウリからは水はあまりでませんが、塩と砂糖でもんだキュウリからは水がでてきます。塩と砂糖をくらべると、塩のほうがでる水が多く、水をだすはたらきが強いことがわかります。
185
きったリンゴを塩水につけるのはどうして?
 リンゴが茶色くなるのをふせぐため
リンゴが茶色くなるのをふせぐため
 リンゴの皮をむいてきり、しばらくおいておくと、白くてきれいだった切り口が茶色くなってしまった経験はありますか?
リンゴの皮をむいてきり、しばらくおいておくと、白くてきれいだった切り口が茶色くなってしまった経験はありますか?
リンゴをきったり、すったりすると、リンゴにふくまれる酵素のはたらきで、リンゴのポリフェノールが空気中の酸素とむすびつきます。すると、ポリフェノールが茶色く変化します。これを「酸化」といいます。鉄が酸素とむすびついてさびるのも、酸化のひとつです。
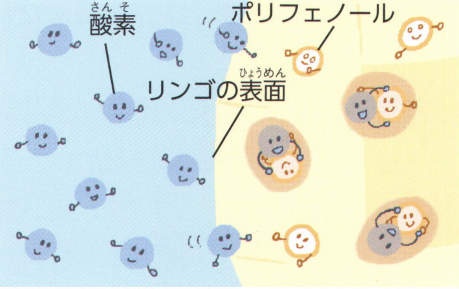

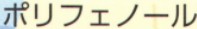
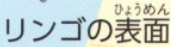
 酸化をふせぐためには塩が活躍します。塩は、酸素がポリフェノールとむすびつく前に、ポリフェノールをつつみこんでしまいます。すると、酵素はポリフェノールと酸素とをむすびつけることができなくなります。そのため、塩水につけることで、リンゴが酸化するのをふせぎ、茶色くならないのです。
酸化をふせぐためには塩が活躍します。塩は、酸素がポリフェノールとむすびつく前に、ポリフェノールをつつみこんでしまいます。すると、酵素はポリフェノールと酸素とをむすびつけることができなくなります。そのため、塩水につけることで、リンゴが酸化するのをふせぎ、茶色くならないのです。

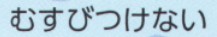

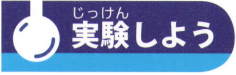 リンゴをいろいろな水につけてみよう!
リンゴをいろいろな水につけてみよう!
塩のほかに、リンゴの酸化をおさえるものはあるかな? いろいろなものでしらべてみよう!
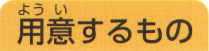
リンゴ1こ、塩、砂糖、レモン汁、酢
小さな容器5つ、小皿5つ
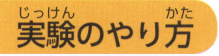
①砂糖と塩それぞれ小さじ1/2を、水100
にとかして砂糖水と塩水をつくる。レモン汁と酢も、それぞれ小さじ1/2を100
の水にまぜる。
②水、塩水、砂糖水、レモン汁、酢をそれぞれ容器にいれ、きったリンゴを1つずつひたして10分おく(リンゴはきったらすぐにいれる)。
③10分たったら、リンゴを小皿にとりだす。30分、60分、90分と時間をおいて、リンゴの色とようすの変化をしらべる。
 60分後の結果
60分後の結果
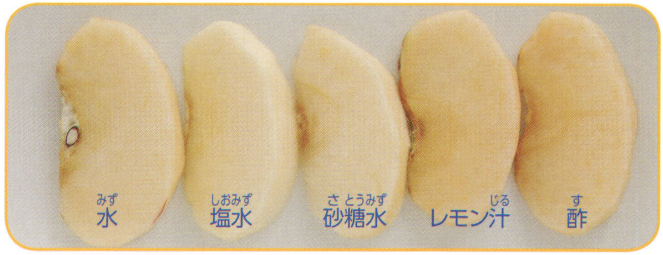



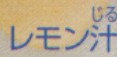

 一番色がかわらないのは?
一番色がかわらないのは?
水以外のものは、どれもリンゴの変色をふせぐ効果があります。とくに、レモン汁にふくまれているビタミンCは、酸化をおさえる力が強いのです。
砂糖の場合は、酵素のはたらきをじゃまするのではなく、リンゴの表面をコーティングして、空気にふれるのをふせぎます。
186
水と油はどうしてまざらずにわかれるの?
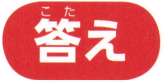 油は水にとけないから
油は水にとけないから
 水に塩や砂糖をいれてかきまぜると、とけてみえなくなってしまいます。でも、油はかきまぜても、しばらくすると2つにわかれてしまいます。
水に塩や砂糖をいれてかきまぜると、とけてみえなくなってしまいます。でも、油はかきまぜても、しばらくすると2つにわかれてしまいます。
水はいろいろなものをとかしますが、油は水にとけないため、まざらずにわかれてしまうのです。
 地球には「引力」という、ものを地球にひきつける力があり、重いものほど強くひっぱられます。油は水よりも軽いので、コップに油と水をいれると、油は上に水は下にわかれるのです。
地球には「引力」という、ものを地球にひきつける力があり、重いものほど強くひっぱられます。油は水よりも軽いので、コップに油と水をいれると、油は上に水は下にわかれるのです。
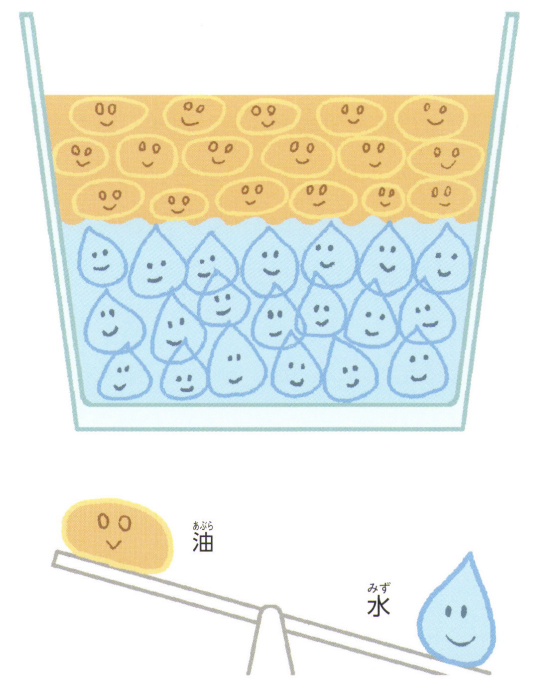


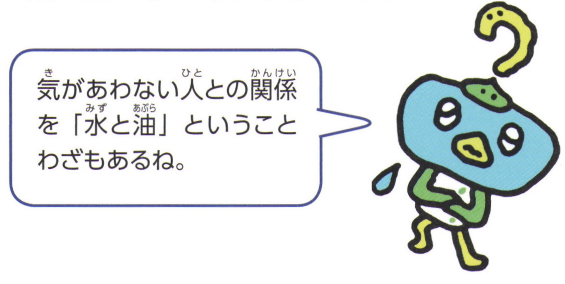
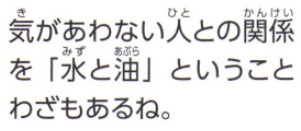
 水と油のペットボトルオブジェをつくろう!
水と油のペットボトルオブジェをつくろう!

水、サラダ油、食紅、ペットボトル、コップ

①コップに水100
と食紅を少しいれてとかす。
②ペットボトルに、サラダ油と色水を半分ずついれ、しっかりとふたをしめる。

ペットボトルをふったり、ひっくりかえしたりして、色水や油のうごきをみてたのしもう。

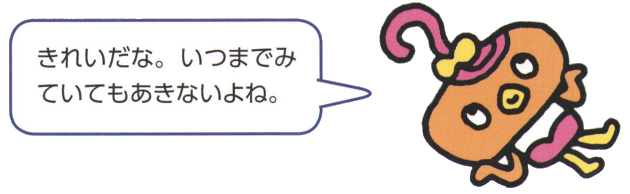
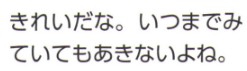
188
食べものは何でも冷凍できるの?
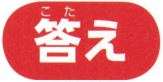 冷凍にむいているものとそうでないものがあります
冷凍にむいているものとそうでないものがあります
 たいたごはんを冷凍庫でこおらせておけば、長く保存ができます。それをとりだして解凍すれば、おいしいごはんをいつでもたべることができて便利ですね。
たいたごはんを冷凍庫でこおらせておけば、長く保存ができます。それをとりだして解凍すれば、おいしいごはんをいつでもたべることができて便利ですね。
おうちの冷凍庫をのぞいてみましょう。どんな食べ物がはいっていますか? 食べ物はどんなものでも冷凍できるのでしょうか?
食べ物には、冷凍して保存するのにむいているものと、そうでないものとがあります。それは、冷凍することで、生き物の体をつくっている一番小さな単位「細胞」に変化がおこることに関係しています。

冷凍に
むいているもの
| 冷凍に
むいていないもの
|
|---|
ごはん、パン、納豆
肉、魚介類、スープ
ソースなど
| 生野菜、きのこ、だいこん、スイカ
こんにゃく、たまご、牛乳、
マヨネーズ、ヨーグルトなど
|
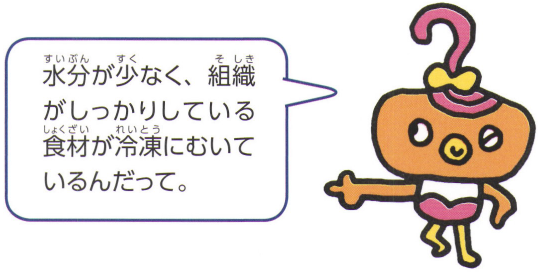
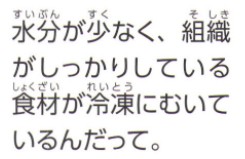
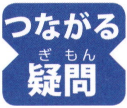 食べ物を冷凍すると何がおこるの?
食べ物を冷凍すると何がおこるの?
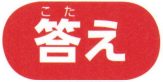 食べ物の細胞が変化します
食べ物の細胞が変化します
 わたしたちの体と同じように、食べ物も細胞からできています。冷凍庫で「冷凍」すると、細胞の中の水がこおることで、食べ物はこおります。
わたしたちの体と同じように、食べ物も細胞からできています。冷凍庫で「冷凍」すると、細胞の中の水がこおることで、食べ物はこおります。
電子レンジにかけたり、そのまま常温(部屋の温度)においたりして自然解凍すると、こおっていた細胞の中の水がとけて元にもどります。
しかし、解凍してももとのすがたにもどらない食べ物もあります。細胞がこわれてしまったり、解凍するときに細胞の中の水が蒸発してしまったり、水と油などのちがう成分がわかれてしまったりするのです。
 細胞がこわれる
細胞がこわれる
細胞の中の水分がこおってふくらみ、細胞がこわれる。葉野菜などの野菜でおこる。
 水分がぬける
水分がぬける
解凍するときに温度があがり、細胞の中から水分がぬける。きのこやこんにゃくなどでおこる。
 成分がわかれる
成分がわかれる
水分と油はこおる温度がちがうため、成分がわかれてしまう。牛乳やマヨネーズなどでおこる。
189
カビはどうしてはえるの?
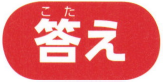 カビは生き物なので、くらしやすい場所をみつけてはえます
カビは生き物なので、くらしやすい場所をみつけてはえます
 ペットボトルののみのこしやパンをほうっておくと、青や黒い色のカビがつきますね。カビは菌類という生き物です。
ペットボトルののみのこしやパンをほうっておくと、青や黒い色のカビがつきますね。カビは菌類という生き物です。
カビは、「胞子」とよばれる植物のたねのようなものをとばして、ふえていきます。胞子は、とても小さく目にはみえませんが、空気中のどこにでもいて、いろいろなものにくっつきます。そして、カビがちょうどいい温度と水分がある場所につくと、そこから糸のような根っこをのばして成長します。これが、成長して大きくなると人間の目にもみえるカビになるのです。
 空気中の胞子がついて、カビのこのむ温度、湿度、栄養の条件がそろえばカビははえる。でも、この3つがすべてそろわないと胞子がついてもカビにはならない。
空気中の胞子がついて、カビのこのむ温度、湿度、栄養の条件がそろえばカビははえる。でも、この3つがすべてそろわないと胞子がついてもカビにはならない。
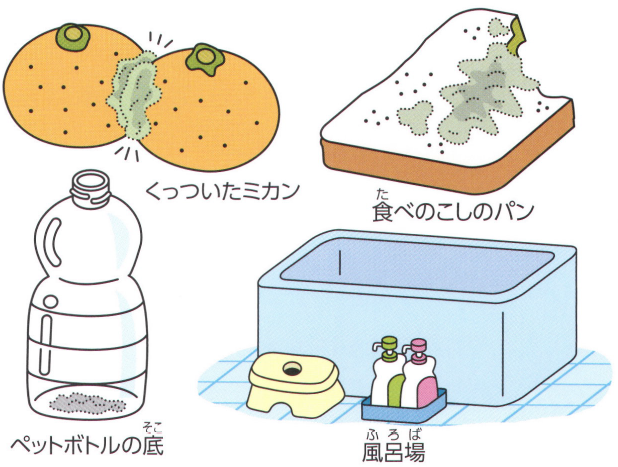
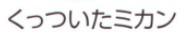
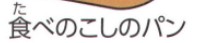
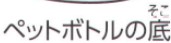

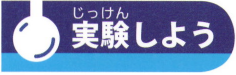 カビのはえやすい場所をしらべよう
カビのはえやすい場所をしらべよう
カビのえさになるかんてんを家のいろいろな場所において、カビをそだててみよう。
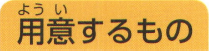
水200
、粉かんてん4
、砂糖小さじ1
紙コップ5~6こ、はさみ、ラップ
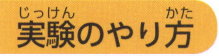
①紙コップをはさみできって、深さを半分にする。
②カンテンをつくる。なべに水をいれて火にかけ、粉かんてん、砂糖をとかし、あら熱をとる。
③紙コップに②をそれぞれわけていれる。ラップをかけて、冷蔵庫で30分ほどひやす。
④冷蔵庫からだしてラップをはずし、油性ペンでつくった日づけをかく。
⑤家のいろいろな場所において、毎日観察し、記録する。カビの色などのようすを絵にかいてみよう。
 こんなところにおいてみよう
こんなところにおいてみよう
玄関、靴箱の中、台所
冷蔵庫の中、風呂場
トイレ、窓のそば、
勉強机の上、ろうか
 1週間後のようす。
1週間後のようす。
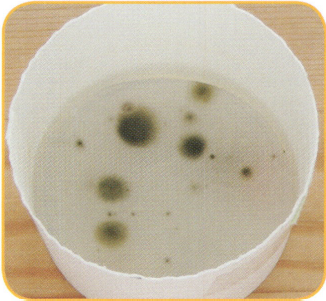
 カビは生き物
カビは生き物
空気中のカビの胞子がかんてんにつくと、かんてんをえさにしてふえていきます。カビがうまくはえるかどうかは、その場所の温度や湿度によってかわります。
カビは生き物なので、うまくいかないこともあるかもしれませんが、何度かちがう状態でもためして、挑戦してみてください。
190
ゼラチンとかんてんはどうちがうの?
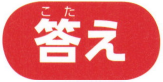 まったくべつの原料からつくられます
まったくべつの原料からつくられます
 つるんとしたフルーツゼリーや、あんみつなどにはいっているぷるぷるしたかんてんは食感がよくて、みんなだいすきですね。
つるんとしたフルーツゼリーや、あんみつなどにはいっているぷるぷるしたかんてんは食感がよくて、みんなだいすきですね。
ゼリーとかんてんは、よくにていますが、原料がまったくちがいます。
 ゼリーをかためるゼラチンは、豚や牛の骨や皮が原料で、動物性たんぱく質からできています。
ゼリーをかためるゼラチンは、豚や牛の骨や皮が原料で、動物性たんぱく質からできています。
一方かんてんは、「天草」や「オゴノリ」という海藻が原料で、植物性炭水化物からできています。
 ゼラチン
ゼラチン
豚や牛の骨や皮
(動物性たんぱく質)
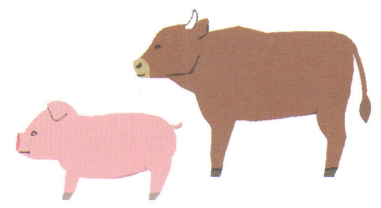
 かんてん
かんてん
天草やオゴノリ
(植物性炭水化物)
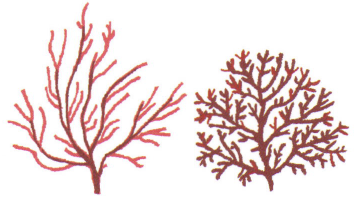
 ゼラチンと寒天のちがい
ゼラチンと寒天のちがい
|
| ゼラチン
| かんてん
|
|---|
| 原料
| 豚や牛の骨や皮
| 天草やオゴノリ(ともに海藻)
|
|---|
| 主な成分
| たんぱく質
| 炭水化物
|
|---|
| かたまる温度
| 10℃
| 30~40℃
|
|---|
| カロリー(100gあたり)
| 344kcal
| 0kcal
|
|---|
| 栄養
| コラーゲンが豊富
| 食物繊維が豊富
|
|---|
| 食感
| やわらかくてつるんとしている
| ぷりぷりとして、ややかため
|
|---|
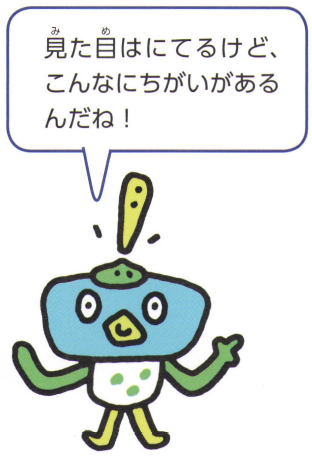
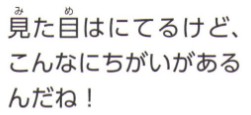
 ほかにもある、かためる食材
ほかにもある、かためる食材
ゼラチンやかんてんのほかにも食べ物をかためる材料がいろいろあるよ。
 ペクチン
ペクチン
 くだものや野菜にふくまれる成分。ジャムやゼリーにつかわれる。
くだものや野菜にふくまれる成分。ジャムやゼリーにつかわれる。

 たまご
たまご
 たまごにふくまれるたんぱく質で、プリンや茶碗蒸しなどをかためる。
たまごにふくまれるたんぱく質で、プリンや茶碗蒸しなどをかためる。

 くず
くず
 クズという植物の根からとれるでんぷんが原料。和菓子などにつかう。
クズという植物の根からとれるでんぷんが原料。和菓子などにつかう。
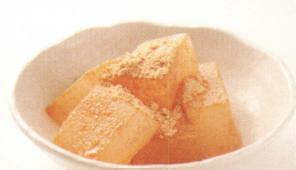
 アガー
アガー
 カラギーナンという海藻やローカストビーンガムというたねが原料。ゼリーの材料。
カラギーナンという海藻やローカストビーンガムというたねが原料。ゼリーの材料。

191
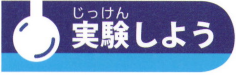 ゼラチンとかんてんの性質をくらべよう
ゼラチンとかんてんの性質をくらべよう
ゼリーとかんてんをつくって、ゼラチンとかんてんのちがいをもっとくらべよう!
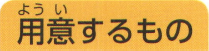
 ゼリー
ゼリー
粉ゼラチン:10
、水:大さじ4、ジュース:500
、砂糖
 かんてん
かんてん
粉かんてん:4
、ジュース:400
、砂糖
キウイフルーツ:1こ、小さいなべ、小皿、ゼリー型:6こ

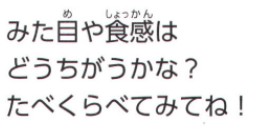
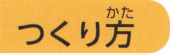
 ゼリー
ゼリー
①小皿に粉ゼラチンと水をいれてふやかす。
②なべに①のゼラチンとジュース、このみの量の砂糖をくわえて弱火にかけて、かきまぜながらとかす。
③沸騰する前に火をとめ、あら熱をとる。3つの型にながしいれて冷蔵庫でひやしてかためる。
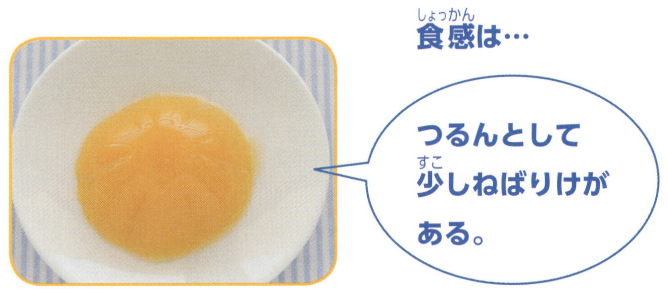

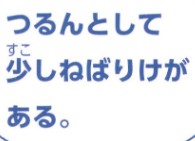
 かんてん
かんてん
①なべにジュースをいれて火にかける。沸騰したら粉かんてんをいれてとかす。さらに砂糖をくわえてとかし、火からおろしてあら熱をとる。
②3つの型にながしいれて、冷蔵庫でひやしてかためる。
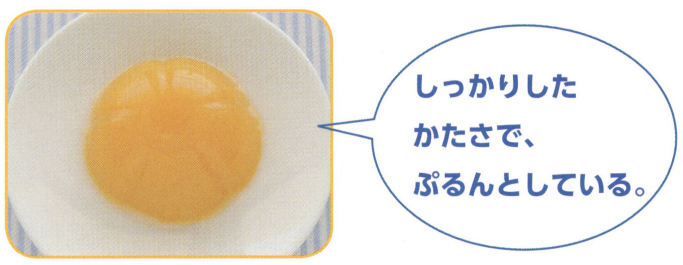
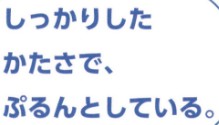
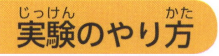
1.電子レンジで10秒あたためる
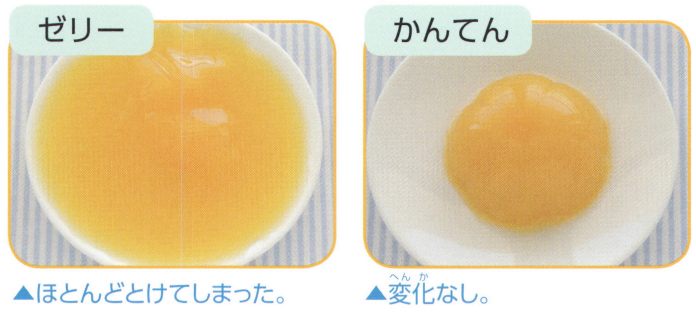
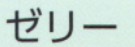

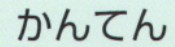

2.きったキウイフルーツをのせてしばらくおく
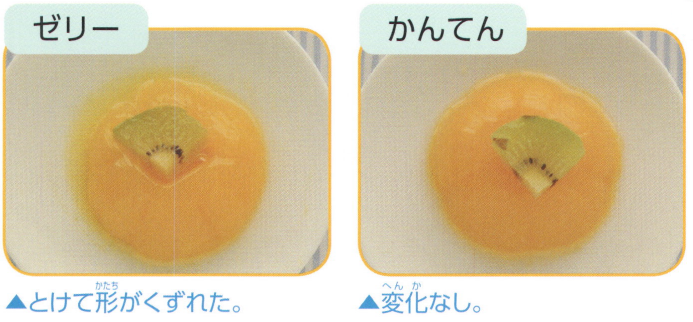
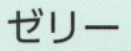

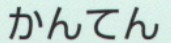


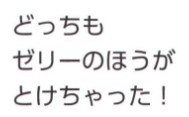
 どうしてとけたの?
どうしてとけたの?
どちらの実験でも、ゼラチンのゼリーだけがとけました。
ゼラチンとかんてんは、かたまる温度がちがいます。ゼラチンは約10℃でかたまるので、それ以上にあたためるととけてしまいます。お弁当にゼリーをいれたいときは、かんてんでつくるといいですね。
また、キウイフルーツにふくまれる酵素は、たんぱく質をこわす性質があります。ゼラチンのゼリーは、動物性たんぱく質が原料なので、とけてしまうのです。
192
ジャムはどうしてくさらないの?
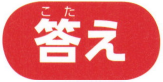 砂糖が水分をかかえこむから
砂糖が水分をかかえこむから
 生のくだものは部屋においておくとくさってしまいますが、ジャムにすると、くさらずに長く保存できますね。
生のくだものは部屋においておくとくさってしまいますが、ジャムにすると、くさらずに長く保存できますね。
ものがくさるおもな原因は、カビや細菌などの微生物がふえることです。微生物がいきるためには、水と酸素が必要です。また、微生物は低い温度ではふえにくく、加熱すると死んでしまいます。
 ジャムは、くだものにたくさんの砂糖をくわえて、につめてつくります。砂糖はくだものにふくまれる水分をつつみこみ、はなさなくなります。そうすることによって、くだものの中の水分は自由にうごけなくなって、くさる原因になる微生物と水分がむすびつくことが少なくなります。
ジャムは、くだものにたくさんの砂糖をくわえて、につめてつくります。砂糖はくだものにふくまれる水分をつつみこみ、はなさなくなります。そうすることによって、くだものの中の水分は自由にうごけなくなって、くさる原因になる微生物と水分がむすびつくことが少なくなります。
 また、びんにつめてから加熱殺菌することで、びんの中の微生物と酸素をできるだけへらし、長持ちさせるのです。
また、びんにつめてから加熱殺菌することで、びんの中の微生物と酸素をできるだけへらし、長持ちさせるのです。
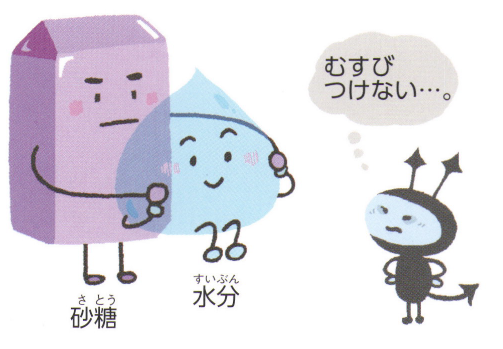


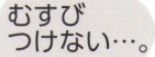
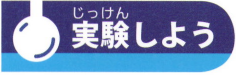 生のイチゴとジャムでしらべよう
生のイチゴとジャムでしらべよう
ジャムのくさりにくさを、生のイチゴとくらべよう。
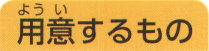
生のイチゴ1こ、イチゴジャム、小さじ1
小皿2枚
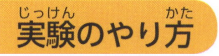
①生のイチゴとジャムをそれぞれ小皿にのせる。
②1日ごとにどんな変化があるか、1週間くらい観察する。
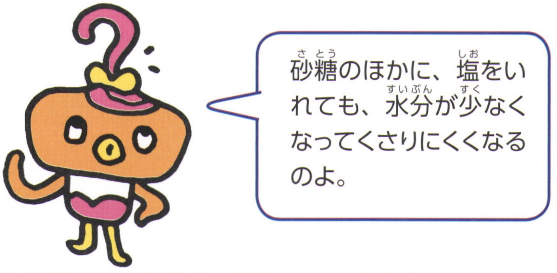
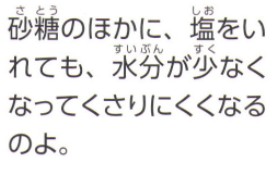
193
人前で緊張してあがっちゃうのはなぜ?
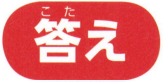 たたかうために必要なエネルギーがからだのなかでつくられるから
たたかうために必要なエネルギーがからだのなかでつくられるから
 みんなの前で発表したり、話をしたりすると、緊張してむねがどきどきしたり、手がふるえたりすることがありますね。これは、苦手なものとたたかうために必要なエネルギーを体がつくりだそうとするからです。
みんなの前で発表したり、話をしたりすると、緊張してむねがどきどきしたり、手がふるえたりすることがありますね。これは、苦手なものとたたかうために必要なエネルギーを体がつくりだそうとするからです。
エネルギーを筋肉にとどけるために、心臓が血液をたくさんおくろうとすると、むねがどきどきします。脳にストレスがかかって、体内でたくさんの酸素が必要になり、呼吸がはげしくなるのです。
 緊張しすぎてあがってしまうと、自分の力がおもうようにだせませんね。緊張をおさえるためには、どのようにしたらいいのでしょうか。まず、「緊張はだれでもすること」ということをおぼえておきましょう。だから、たとえ失敗しても気にすることはありません。
緊張しすぎてあがってしまうと、自分の力がおもうようにだせませんね。緊張をおさえるためには、どのようにしたらいいのでしょうか。まず、「緊張はだれでもすること」ということをおぼえておきましょう。だから、たとえ失敗しても気にすることはありません。
 スポーツ選手は緊張することによって、集中し、自分の力を最大限にだすことができるといいます。緊張とうまくつきあって、失敗をおそれずに何度も挑戦することが大事です。
スポーツ選手は緊張することによって、集中し、自分の力を最大限にだすことができるといいます。緊張とうまくつきあって、失敗をおそれずに何度も挑戦することが大事です。
 緊張が大きくなりすぎると、いつもどおりにはなしたり、体をうごかしたりできなくなってしまう。
緊張が大きくなりすぎると、いつもどおりにはなしたり、体をうごかしたりできなくなってしまう。

 緊張しない工夫をしよう!
緊張しない工夫をしよう!
緊張はだれでもするものだけど、緊張をかるくすることはできるよ。いざというときにはためしてみよう!
 深呼吸する
深呼吸する
心臓がドキドキして、体温があがっているときは、ゆっくり呼吸をしておちつこう。

 べつのことに集中する
べつのことに集中する
前の失敗をおもいだすのはだめ。体をうごかすなどべつのことに集中しよう。
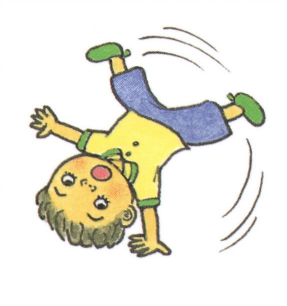
 練習する
練習する
前もって何度も練習すれば、自信がついて、緊張をおさえられる。

 ひらきなおる
ひらきなおる
「失敗してもいいや」とひらきなおれば、緊張もほぐれる。
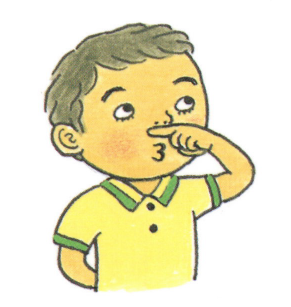
194
暗いところや高いところがこわいのはなぜ?
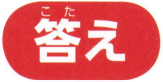 危険を察知する、動物ならあたりまえの気持ちです
危険を察知する、動物ならあたりまえの気持ちです
 暗いところがこわい、高いところが苦手という気持ちは、あってあたりまえの気持ちです。
暗いところがこわい、高いところが苦手という気持ちは、あってあたりまえの気持ちです。
このような「恐怖心」がなければ、高いところからおちたり、暗いところで動物におそわれたりして死んでしまう危険があるからです。こういう気持ちは動物ならあたりまえな感情なのです。
 暗いところや高いところがこわい理由として、まず、そのような場所に「なれていない」というのがあります。もしも、高層マンションの上にずっとすんでいたら、高いことになれて恐怖心もなくなるでしょう。
暗いところや高いところがこわい理由として、まず、そのような場所に「なれていない」というのがあります。もしも、高層マンションの上にずっとすんでいたら、高いことになれて恐怖心もなくなるでしょう。
 また、「高いところからおちたら、けがをするよ」とか「暗い部屋にはおばけがでるよ」とおしえられると、脳が高いところや暗いところをさけるようになります。
また、「高いところからおちたら、けがをするよ」とか「暗い部屋にはおばけがでるよ」とおしえられると、脳が高いところや暗いところをさけるようになります。
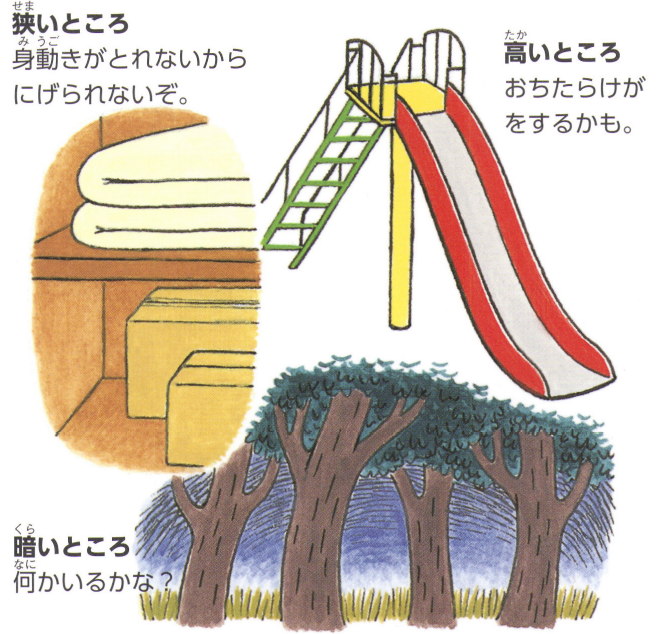
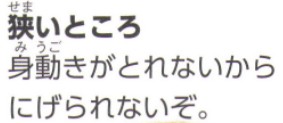
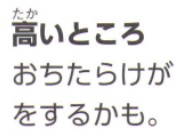
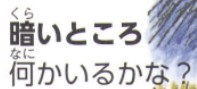
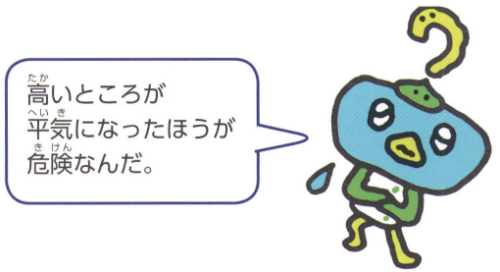
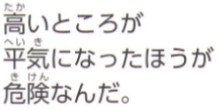
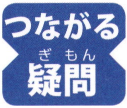 ストレスって何?
ストレスって何?
 外からかかる「力」のこと
外からかかる「力」のこと
 緊張したときに、「ストレスがある」なんてことをいう人がいますね。このストレスということばは、もともと科学の世界でつかわれることばでした。たとえば、まくらのはね返りをしらべるために、まくらをおしますね。このように外からかかる力のことをストレスといいます。
緊張したときに、「ストレスがある」なんてことをいう人がいますね。このストレスということばは、もともと科学の世界でつかわれることばでした。たとえば、まくらのはね返りをしらべるために、まくらをおしますね。このように外からかかる力のことをストレスといいます。
 これを、こころの問題にあてはめてみましょう。
これを、こころの問題にあてはめてみましょう。
「明日は成績表がくばられるな。いやだな」とおもうと、こころが苦しくなりませんか? 現代では、このような気持ちを「ストレス」というようになりました。

195
おばあちゃんにもおばあちゃんがいたの?
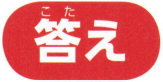 おばあちゃんのそのまたおばあちゃんにもおばあちゃんはいる
おばあちゃんのそのまたおばあちゃんにもおばあちゃんはいる
 あなたは、お父さんとお母さんがいなければ、うまれてきませんでした。人はみな、お父さんとお母さんがいないとうまれてきません。
あなたは、お父さんとお母さんがいなければ、うまれてきませんでした。人はみな、お父さんとお母さんがいないとうまれてきません。
ですから、あなたにおばあちゃんがいるように、おばあちゃんにもおばあちゃんはかならずいます。
 下の図のような家系図をみると、あなたのおばあちゃんにもおばあちゃんがいて、そのまたおばあちゃんがいるのがわかりますね。
下の図のような家系図をみると、あなたのおばあちゃんにもおばあちゃんがいて、そのまたおばあちゃんがいるのがわかりますね。
同じように、おじいちゃんにもまた、かならずおじいちゃんがいるのです。
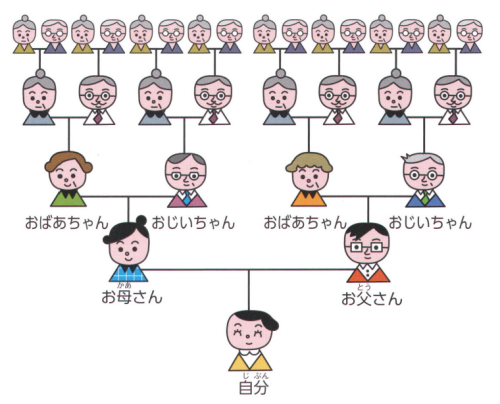

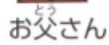
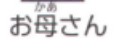
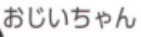
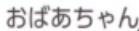
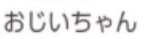
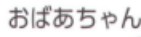
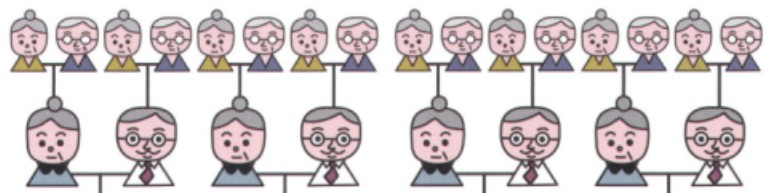
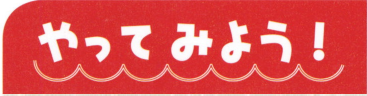 家族の年表をつくろう
家族の年表をつくろう
自分の家族の歴史をどのくらいしっているかな? お父さんやお母さん、おばあちゃんやおじいちゃんにインタビューして、家族の歴史年表をつくってみましょう。
年代とできごとをかいて、年表をつくります。社会でおこったこともくわえると、りっぱな年表ができますよ。
 年表の例
年表の例
| 年代
| できごと
|
|---|
| 昭和25年
| おじいちゃんがうまれる。
|
|---|
| 昭和45年
| おばあちゃんとおじいちゃんが結婚する。
|
|---|
| 昭和49年
| お父さんの山田太郎が北海道・旭川市でうまれる。
|
|---|
| 昭和50年
| お母さんの田中恭子が東京都渋谷区でうまれる。
|
|---|
| 平成9年
| お父さんが〇×会社にはいった。
|
|---|
| 平成16年
| お父さんとお母さんが結婚して、東京都渋谷区にひっこす。
|
|---|
| 平成18年
| ぼくが東京都・武蔵野市でうまれる。
|
|---|
| 平成24年
| ぼくが小学校に入学する。妹のミナがうまれる。
|
|---|
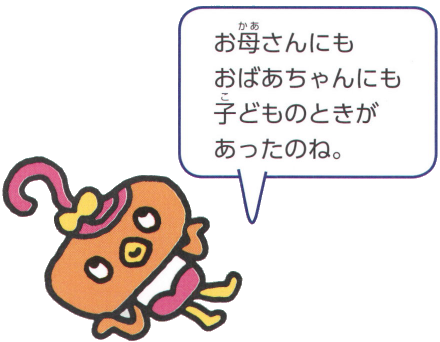
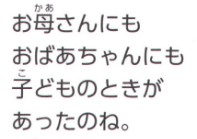
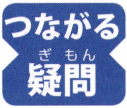 どうして寿命があるの?
どうして寿命があるの?
 長生きしても子孫をふやせないから
長生きしても子孫をふやせないから
 寿命は動物の進化の途中であらわれたもので、もともとは寿命などなかったという説があります。
寿命は動物の進化の途中であらわれたもので、もともとは寿命などなかったという説があります。
たとえば、植物には樹齢数千年の木もあって、これらは火災などがないかぎり寿命はないとされています。
 寿命が長い木は、毎年たねをつくりつづけますが、動物の場合は、子どもをうんだり、そだてたりする期間が長くて、それより長くいきることはむずかしいとされています。もし、長生きできたとしても、それによって子どもがふえるわけでもないからです。
寿命が長い木は、毎年たねをつくりつづけますが、動物の場合は、子どもをうんだり、そだてたりする期間が長くて、それより長くいきることはむずかしいとされています。もし、長生きできたとしても、それによって子どもがふえるわけでもないからです。
 木は毎年たくさんのたねをつくる。そのたねは、鳥や虫など、ほかの力をかりてひろがる。
木は毎年たくさんのたねをつくる。そのたねは、鳥や虫など、ほかの力をかりてひろがる。
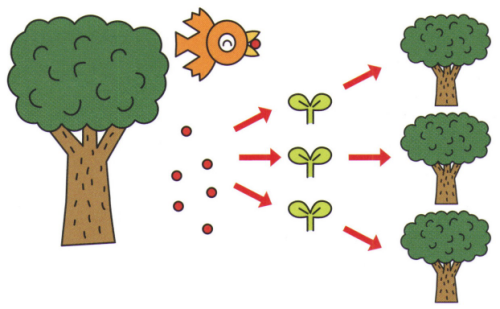
 人は子どもをうんでも、子そだてが必要だから、たとえ長生きしてもたくさんの子孫をのこせない。
人は子どもをうんでも、子そだてが必要だから、たとえ長生きしてもたくさんの子孫をのこせない。
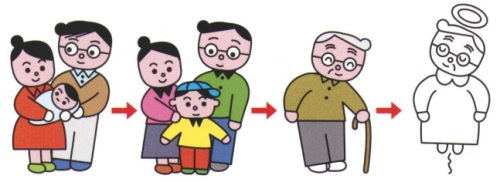
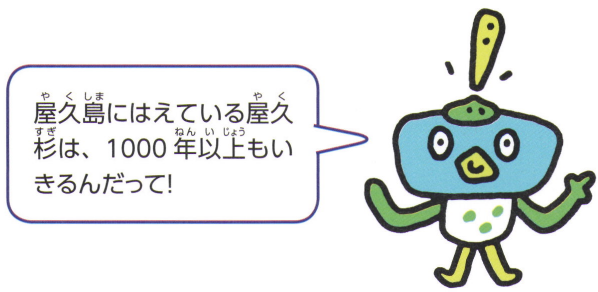
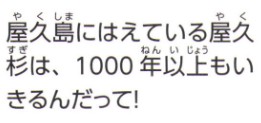
197
人は死んだらどうなるの?
 この世からはいなくなるけど、人の心の中でいきつづけます
この世からはいなくなるけど、人の心の中でいきつづけます
 人が死んだらどうなるのか? 人は死んだらどこにいくのか? それは、だれにもわかりません。
人が死んだらどうなるのか? 人は死んだらどこにいくのか? それは、だれにもわかりません。
天国にいくのかもしれませんし、うまれかわるのかもしれません。また、何もないのかもしれません。国や宗教によって、かんがえ方もさまざまです。
 しかし、死んでしまった人はどこにもいなくなるわけではありません。死んでしまったおばあちゃんをおもいだすと、あなたの心の中におばあちゃんのことがうかびますね。いきているときにおばあちゃんにしてもらったことや、ことばがおもいうかぶかもしれません。
しかし、死んでしまった人はどこにもいなくなるわけではありません。死んでしまったおばあちゃんをおもいだすと、あなたの心の中におばあちゃんのことがうかびますね。いきているときにおばあちゃんにしてもらったことや、ことばがおもいうかぶかもしれません。
このように、死んでしまった人はわたしたちの心の中でいきています。
 死んでしまった人は、現実にはこの世界にいなくなってしまっても、記憶の中でずっといきつづける。
死んでしまった人は、現実にはこの世界にいなくなってしまっても、記憶の中でずっといきつづける。
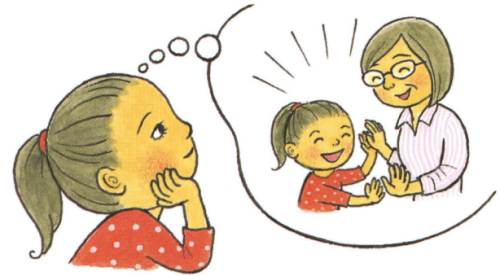
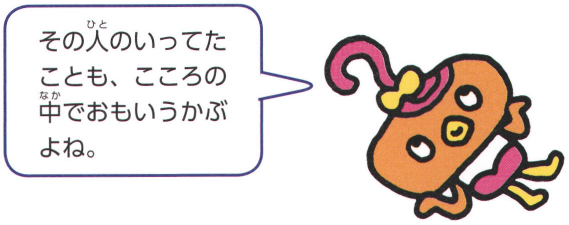
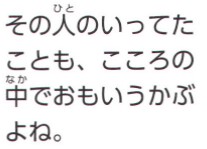
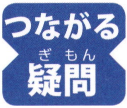 うまれかわりってあるの?
うまれかわりってあるの?
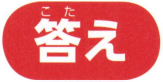 だれにもわかりません
だれにもわかりません
 人が死んだあと、うまれかわるかどうかはだれにもわかりません。もし、死んだ人がその答えをしったとしても、わたしたちにはつたえることができませんね。そして、今いきている人は、死んだことがないので、わからないのです。
人が死んだあと、うまれかわるかどうかはだれにもわかりません。もし、死んだ人がその答えをしったとしても、わたしたちにはつたえることができませんね。そして、今いきている人は、死んだことがないので、わからないのです。
 でも、こうかんがえるとうまれかわりはあるかもしれません。それは、人がうまれてくるためには、かならずお父さんやお母さんが必要です。その親にも親がいて、さらに昔にさかのぼると広い宇宙に地球ができたところまでいきつきます。
でも、こうかんがえるとうまれかわりはあるかもしれません。それは、人がうまれてくるためには、かならずお父さんやお母さんが必要です。その親にも親がいて、さらに昔にさかのぼると広い宇宙に地球ができたところまでいきつきます。
人は死ぬと動物や植物と同じように、土にかえります。その土から、植物や小さな生き物がそだつとかんがえると、人はうまれかわるといえるのかもしれません。
 みんなの命は、地球につづいてきたたくさんの命と、お母さんとお父さんによってうまれる。
みんなの命は、地球につづいてきたたくさんの命と、お母さんとお父さんによってうまれる。
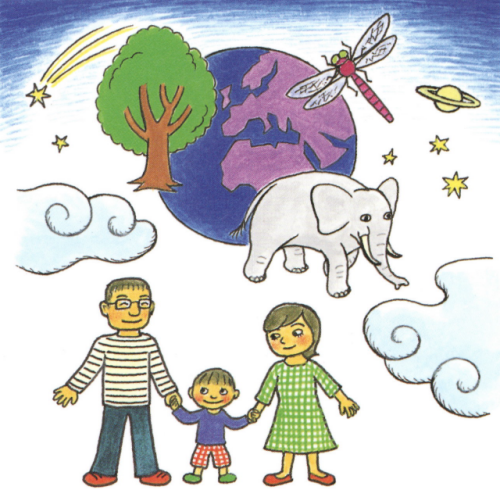
198
電車でジャンプしても同じ場所におちるのはなぜ?
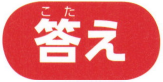 電車と人がいっしょにうごいているから
電車と人がいっしょにうごいているから
 電車がはしっているときにジャンプするとどうなるでしょう? ジャンプしたときと同じ場所におちますね。電車は前にすすんでいるのに、なぜ同じ場所におちるのでしょうか。
電車がはしっているときにジャンプするとどうなるでしょう? ジャンプしたときと同じ場所におちますね。電車は前にすすんでいるのに、なぜ同じ場所におちるのでしょうか。
それは、電車がはしっているとき、のっている人も同じ速さで前にすすんでいるからです。これは、電車と一緒にうごいているときに、電車が急にとまったりして外の力がくわわらないかぎり、人や物体がうごきつづけようとする運動のきまりがあるからです。これを「慣性」といいます。
 電車が急にとまったり、ブレーキがかかったりすると、体が前のめりになりますね。これは、今まで体も電車といっしょにうごいていたのに、電車が急にとまったために、体だけが前にうごきつづけるからです。
電車が急にとまったり、ブレーキがかかったりすると、体が前のめりになりますね。これは、今まで体も電車といっしょにうごいていたのに、電車が急にとまったために、体だけが前にうごきつづけるからです。
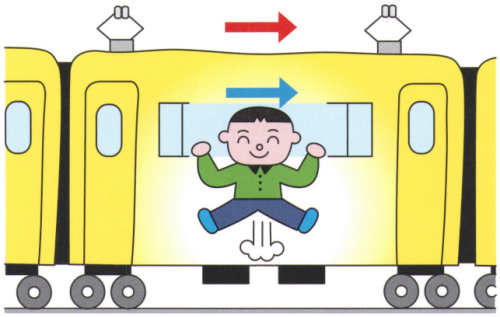
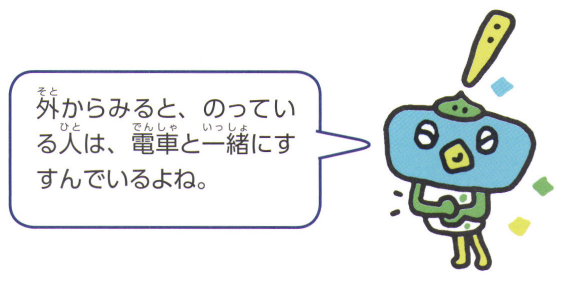
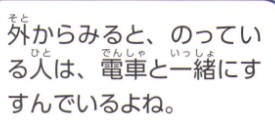
なぜリモコンでテレビがうごくの?
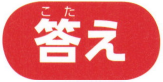 リモコンからでる赤外線がうごかします
リモコンからでる赤外線がうごかします
 電源をいれたり、チャンネルやボリュームをかえたり、録画したり、テレビのリモコンはいろいろな操作ができてとても便利ですね。でも、いったいリモコンは、どのようにテレビを操作しているのでしょうか。
電源をいれたり、チャンネルやボリュームをかえたり、録画したり、テレビのリモコンはいろいろな操作ができてとても便利ですね。でも、いったいリモコンは、どのようにテレビを操作しているのでしょうか。
 リモコンには「赤外線」とよばれる、人にはみえない光がつかわれています。日光をプリズムにあてたときに7色の光がでますが、赤外線は、赤の光の外側にある目にはみえない光です。「赤外線ヒーター」などにも、この光がつかわれています。
リモコンには「赤外線」とよばれる、人にはみえない光がつかわれています。日光をプリズムにあてたときに7色の光がでますが、赤外線は、赤の光の外側にある目にはみえない光です。「赤外線ヒーター」などにも、この光がつかわれています。
 リモコンのボタンをおすと赤外線がでて、それがテレビ本体にある赤外線をうける部分(センサー)にあたると、中の装置がうごくのです。
リモコンのボタンをおすと赤外線がでて、それがテレビ本体にある赤外線をうける部分(センサー)にあたると、中の装置がうごくのです。
 リモコンとテレビの間に人がいると、赤外線がさえぎられるため、操作ができない。
リモコンとテレビの間に人がいると、赤外線がさえぎられるため、操作ができない。
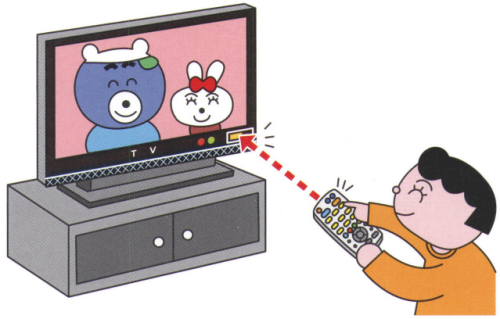
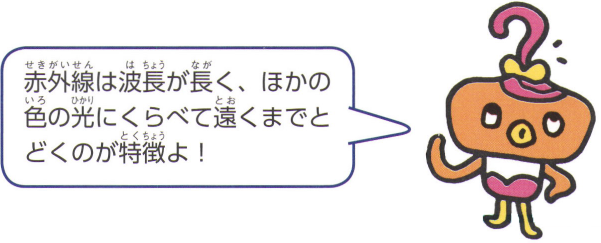
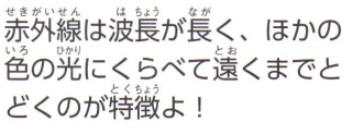
199
鳥はどうして電線にとまってもへいきなの?
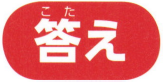 電気の通り道がないと感電しません
電気の通り道がないと感電しません
 「感電」とは、外からの電気が生き物の体の中をながれることをいいます。体にながれる電気が大きければ死んでしまうこともあります。
「感電」とは、外からの電気が生き物の体の中をながれることをいいます。体にながれる電気が大きければ死んでしまうこともあります。
 では、電線にとまっている鳥はなぜ感電しないのでしょうか。これは、鳥が2本ある電線のかた側一本にだけとまっているために、電気のぬけ道がありません。それで、電気がながれずに、鳥は感電しないのです。
では、電線にとまっている鳥はなぜ感電しないのでしょうか。これは、鳥が2本ある電線のかた側一本にだけとまっているために、電気のぬけ道がありません。それで、電気がながれずに、鳥は感電しないのです。
 でも、一本の電線をさわっただけで人は感電してしまいます。これは、人がふつう地面にたっているため、電線からながれた電気が地面ににげていけるからです。このように、鳥は電線にふれても電気がながれないので感電しませんが、人のように地面などの電気のにげ道がある場合は感電するのです。
でも、一本の電線をさわっただけで人は感電してしまいます。これは、人がふつう地面にたっているため、電線からながれた電気が地面ににげていけるからです。このように、鳥は電線にふれても電気がながれないので感電しませんが、人のように地面などの電気のにげ道がある場合は感電するのです。
 もし、鳥が2本の送電線をまたぐようにとまったら感電する。
もし、鳥が2本の送電線をまたぐようにとまったら感電する。
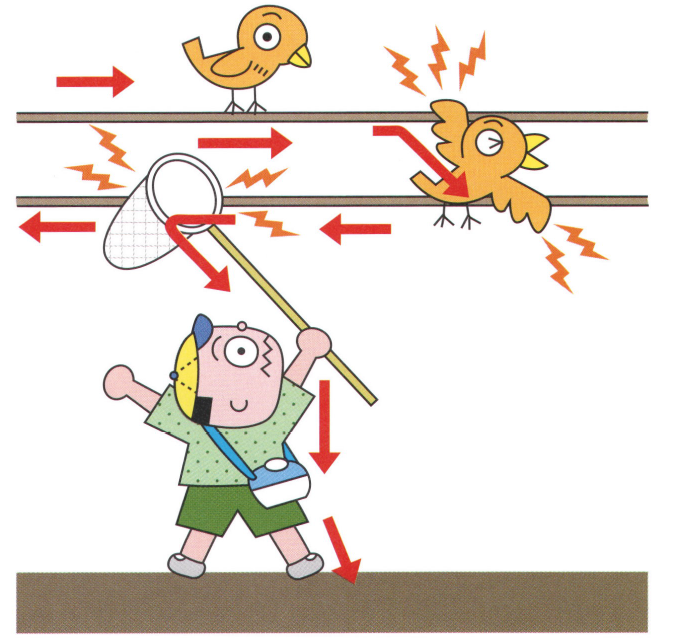
さむい日に息が白くなるのはなぜ?
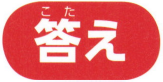 息の中にふくまれる水蒸気が水になるから
息の中にふくまれる水蒸気が水になるから
 ふだん、わたしたちがはく息は目にみえないのに、さむい日にはく息は、白くみえますね。これは、人のはく息と外の温度の差によっておこります。
ふだん、わたしたちがはく息は目にみえないのに、さむい日にはく息は、白くみえますね。これは、人のはく息と外の温度の差によっておこります。
人間の体温は、およそ36~37℃です。息は、体の中からでてくるため、体温と同じくらいにあたためられています。
そのあたたかい息が、外のつめたい空気にあたります。すると、息にふくまれている水蒸気は、外のつめたい空気にいっきにひやされ、小さな水滴になるのです。その水滴が、わたしたちには白くみえているのです。
これは、あたたかい飲み物から湯気がでたり、やかんからでた水蒸気が外の空気にひやされ湯気になるのとにています。
 白い息をはく冬のウマ。
白い息をはく冬のウマ。

200
おもちはどうしてかたくなるの?
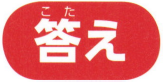 おもちにふくまれるでんぷんが変化するから
おもちにふくまれるでんぷんが変化するから
 つきたてのおもちはやわらかくてのびるのに、少し時間をおいたおもちは、みるみるかたくなりますね。これはなぜでしょう。
つきたてのおもちはやわらかくてのびるのに、少し時間をおいたおもちは、みるみるかたくなりますね。これはなぜでしょう。
これには、おもちにふくまれる「アミロペクチン」というでんぷんの変化が関係しています。
 たく前の生のお米はとてもかたいですね。これは、アミロペクチンの分子が規則正しくならんでいるからです。しかし、水や熱をくわえてたいたりむしたりしたお米は、アミロペクチンの分子にすき間ができて、やわらかくなります。
たく前の生のお米はとてもかたいですね。これは、アミロペクチンの分子が規則正しくならんでいるからです。しかし、水や熱をくわえてたいたりむしたりしたお米は、アミロペクチンの分子にすき間ができて、やわらかくなります。
しかし、このやわらかくなったお米にふくまれるアミロペクチンは、時間をおくと、ふたたびもとの生の米のときと同じように、規則正しくならびなおします。それでおもちはかたくなるのです。
 生の米はかたい。
生の米はかたい。

 つきたてのやわらかいもち。
つきたてのやわらかいもち。

 もちは時間をおくとかたくなる。
もちは時間をおくとかたくなる。

 やくとふたたびやわらかくなる。
やくとふたたびやわらかくなる。
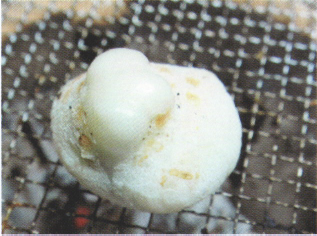
ポップコーンはなぜはじけるの?
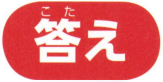 トウモロコシのたねにひみつがあります
トウモロコシのたねにひみつがあります
 ポップコーンは、トウモロコシのたねを熱してつくります。ポップコーン用につかわれるのは、ゆでてたべるトウモロコシの種類とはちがい、とてもたねがかたい種類のものです。
ポップコーンは、トウモロコシのたねを熱してつくります。ポップコーン用につかわれるのは、ゆでてたべるトウモロコシの種類とはちがい、とてもたねがかたい種類のものです。
 このトウモロコシのたねは、外側がかたいでんぷんでおおわれていて、中は水分をふくんだやわらかいでんぷんがはいっています。
このトウモロコシのたねは、外側がかたいでんぷんでおおわれていて、中は水分をふくんだやわらかいでんぷんがはいっています。
たねに熱をくわえると、内側の水分があたためられ、水蒸気になってふくらもうとします。出口がない水蒸気は必死に外にでようと、たねのかたいでんぷんをおします。そして、最後にははじけてしまいます。
 できあがったポップコーンが白いのは、はじけたときにたねがうらがえって、内側のでんぷんが外にでるためです。
できあがったポップコーンが白いのは、はじけたときにたねがうらがえって、内側のでんぷんが外にでるためです。
 ポップコーンにつかわれる「爆裂種(ポップ種)」という種類のトウモロコシ。
ポップコーンにつかわれる「爆裂種(ポップ種)」という種類のトウモロコシ。

 もとのたねの大きさの15~35倍くらいの大きさにふくらむ
もとのたねの大きさの15~35倍くらいの大きさにふくらむ
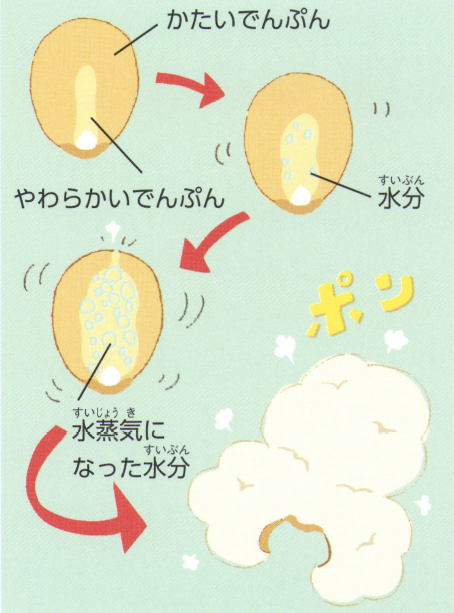
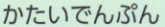
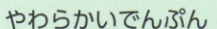

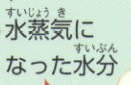

201
シュガーレスの砂糖はどうしてあまくかんじるの?
 砂糖のかわりにあまい味のする材料がはいっているから
砂糖のかわりにあまい味のする材料がはいっているから
 「シュガーレス」や「ノンシュガー」「砂糖不使用」という表示を、おかしや飲み物のパッケージで目にすることがあります。これは、どれも「砂糖をつかっていない」という意味です。
「シュガーレス」や「ノンシュガー」「砂糖不使用」という表示を、おかしや飲み物のパッケージで目にすることがあります。これは、どれも「砂糖をつかっていない」という意味です。
でも、シュガーレスのおかしや飲み物は、あまい味がします。これはなぜでしょうか。
それは、シュガーレスの食べ物には、砂糖のかわりに、あまさをかんじる「甘味料」という材料がはいっているからです。
 甘味料は、砂糖やでんぷん、植物のくきや葉などからつくられます。この甘味料の特徴は砂糖よりカロリーが少ないことです。また、カロリーはあまりかわらなくても、砂糖の160倍以上ものあまさがあるので、つかう量を少なくできる甘味料もあります。
甘味料は、砂糖やでんぷん、植物のくきや葉などからつくられます。この甘味料の特徴は砂糖よりカロリーが少ないことです。また、カロリーはあまりかわらなくても、砂糖の160倍以上ものあまさがあるので、つかう量を少なくできる甘味料もあります。
 炭酸飲料などにつかわれる「アスパルテーム」という甘味料は、砂糖のおよそ160倍以上もあまさがあり、つかう量をおさえられる。
炭酸飲料などにつかわれる「アスパルテーム」という甘味料は、砂糖のおよそ160倍以上もあまさがあり、つかう量をおさえられる。
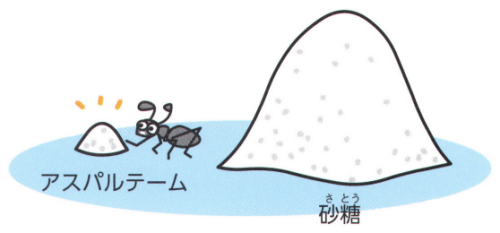
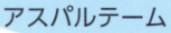

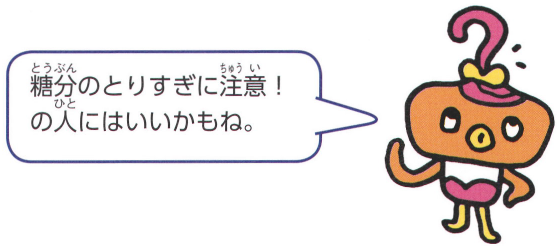
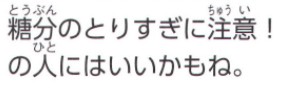
スイカに塩をかけるのはなぜ?
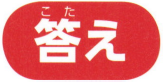 塩をくわえるとあま味がますから
塩をくわえるとあま味がますから
 スイカに塩をふってたべたことはありますか? また、甘味処では、おしるこに、しょっぱいお漬物がそえられてでてくることがあります。これは、あまいものにしょっぱい塩をくわえることで、スイカやあんこのあま味を強くかんじるという、味覚の効果があるからです。これを「味の対比効果」とよびます。
スイカに塩をふってたべたことはありますか? また、甘味処では、おしるこに、しょっぱいお漬物がそえられてでてくることがあります。これは、あまいものにしょっぱい塩をくわえることで、スイカやあんこのあま味を強くかんじるという、味覚の効果があるからです。これを「味の対比効果」とよびます。
たとえば、あめをなめたあとに、ミカンをたべると、とてもすっぱくかんじますね。また、ミカンをたべたあとにあめをなめると、いつもよりあまくかんじます。これらも、味の対比効果です。
ただし、スイカやあんこなど、あまいものにくわえる塩の量は少量がおすすめです。一定の量をこえると逆にしょっぱくなってしまいます。
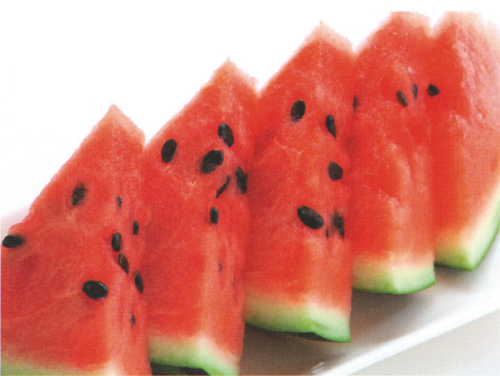
202
カニやエビをゆでると赤くなるのはなぜ?
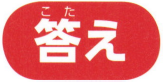 熱をくわえると赤い色の物質がでてくるから
熱をくわえると赤い色の物質がでてくるから
 カニやエビは、いきているときには茶色だったり黒かったり、青みがかった色をしているのに、ゆでると赤く色がかわります。
カニやエビは、いきているときには茶色だったり黒かったり、青みがかった色をしているのに、ゆでると赤く色がかわります。
これは、カニやエビに「アスタキサンチン」という赤い色をした成分がふくまれているからです。アスタキサンチンは、サケやカニ、イクラなどにもふくまれています。
 アスタキサンチンは、もとは藻類の一種にふくまれていますが、カニやエビなどの魚介類がそれをたべることによって、体内にたくわえられています。
アスタキサンチンは、もとは藻類の一種にふくまれていますが、カニやエビなどの魚介類がそれをたべることによって、体内にたくわえられています。
 カニやエビのアスタキサンチンは、ふだんはたんぱく質とむすびついているため青緑色をしていますが、熱や酸をくわえると、たんぱく質からはなれて、赤色になります。だから、カニやエビをゆでると赤くなるのです。
カニやエビのアスタキサンチンは、ふだんはたんぱく質とむすびついているため青緑色をしていますが、熱や酸をくわえると、たんぱく質からはなれて、赤色になります。だから、カニやエビをゆでると赤くなるのです。
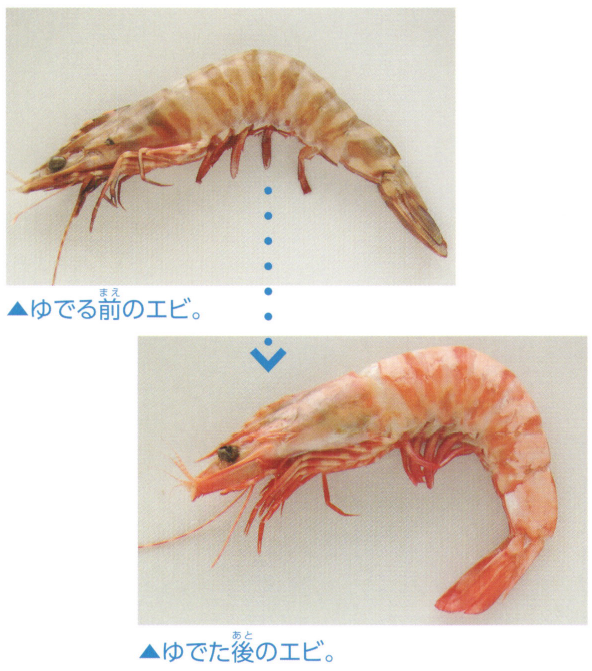


パンはどうしてふくらむの?
 イースト菌という微生物が呼吸をするから
イースト菌という微生物が呼吸をするから
 パンは、小麦粉に水や塩、バター、イーストなどの材料をまぜて生地をつくります。ねかせている間に、生地は発酵して大きくふくらみます。
パンは、小麦粉に水や塩、バター、イーストなどの材料をまぜて生地をつくります。ねかせている間に、生地は発酵して大きくふくらみます。
パン生地をふくらませるのは、イースト菌とよばれる酵母菌です。酵母菌が小麦粉の中の栄養素をたべて活発に活動し、たくさんのガス(二酸化炭素)やアルコールをつくります。これを「発酵」といいます。
パンにはグルテンというねばり気のある成分がふくまれているので、ガスが外ににげだせません。それで、パン生地がぐんぐんふくらむのです。
 生地をやくと、イースト菌は死んでしまいますが、はきだしたガスによってできたすき間は、そのままのこります。だから、やきあがったパンは、空気をふくんでふかふかしているのです。
生地をやくと、イースト菌は死んでしまいますが、はきだしたガスによってできたすき間は、そのままのこります。だから、やきあがったパンは、空気をふくんでふかふかしているのです。
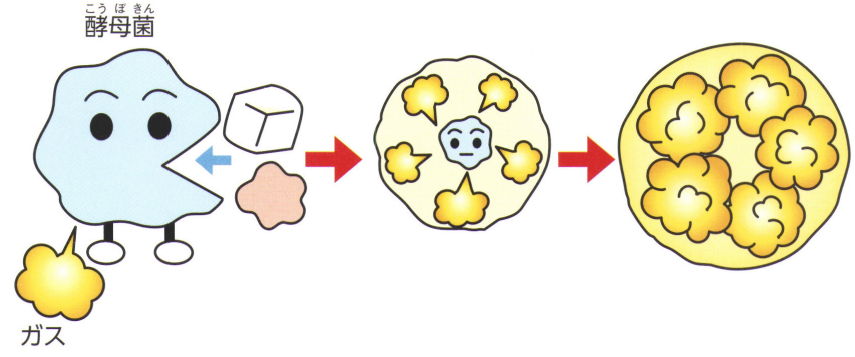


 発酵したパン生地。
発酵したパン生地。
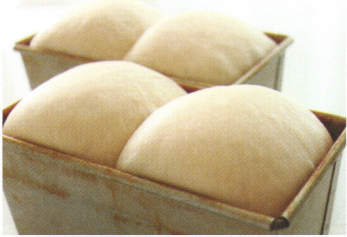
203
お医者さんはどうして白衣をきているの?
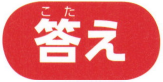 よごれていることがわかるから
よごれていることがわかるから
 お医者さんは、病気の人にせっする仕事ですから、いつも清潔に気をくばらなければなりません。一日に何人もの人をみるので、患者さんのせきやくしゃみがかかって、きているものがよごれることもあります。そんなときに、白衣をきていれば、よごれていることがすぐにわかって、きがえることができるのです。
お医者さんは、病気の人にせっする仕事ですから、いつも清潔に気をくばらなければなりません。一日に何人もの人をみるので、患者さんのせきやくしゃみがかかって、きているものがよごれることもあります。そんなときに、白衣をきていれば、よごれていることがすぐにわかって、きがえることができるのです。
最近は、小児科のお医者さんで色つきの白衣をきることもあります。小さな子どもが、白衣をみてこわがったり、緊張してしまうのをふせぐためです。
 また、手術のときには、お医者さんは白ではなく、青や緑の服をきます。これにも科学的な理由があります。
また、手術のときには、お医者さんは白ではなく、青や緑の服をきます。これにも科学的な理由があります。
手術中、お医者さんは患者さんの体の中や血などの赤い色をみることが多くなります。赤い色をみつづけると、白いものをみたときに、緑色のしみのようなものがみえてしまうのです。これを「残像」といいます。
緑の服をきていれば、緑色のしみをみなくてすむので、手術に集中することができるのです。

ウイルスって生き物なの?
 生き物とも生き物でないともいえる
生き物とも生き物でないともいえる
 いろいろな病気をひきおこすウイルスは、とても小さくて人の目ではみることができません。動物や植物の細胞にすまいをかりてふえていきます。
いろいろな病気をひきおこすウイルスは、とても小さくて人の目ではみることができません。動物や植物の細胞にすまいをかりてふえていきます。
ふつう、生き物は、細胞からなっているものをいいます。そういう意味では、ウイルスは細胞をもっていないので、生き物ではないといえます。
一方、食中毒をおこすサルモネラ菌や体にいいビフィズス菌などの細菌は、細胞をもっているので「生き物」です。
 でも、ウイルスは生き物の細胞をかりてではありますが、自分で子孫をふやすことができます。そういう意味で、ウイルスは、生き物であるものとそうでないものの中間であるとかんがえられます。インフルエンザはウイルスのひとつです。
でも、ウイルスは生き物の細胞をかりてではありますが、自分で子孫をふやすことができます。そういう意味で、ウイルスは、生き物であるものとそうでないものの中間であるとかんがえられます。インフルエンザはウイルスのひとつです。
 インフルエンザウイルス(A/H1N1)。
インフルエンザウイルス(A/H1N1)。
せきやくしゃみでとびちったインフルエンザウイルスは、のどやはなの粘膜の細胞にすみついて、体の中でふえる。
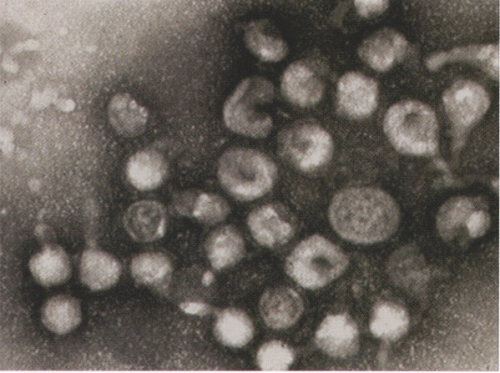
204
線路にしいてある石は何のためにあるの?
 はしっている電車のクッションの役目がある
はしっている電車のクッションの役目がある
 線路の下にはたくさんの石がしきつめられていますね。この石を「バラスト(砕石)」といいます。石があるおかげで、はしる電車が線路にかける力が分散され、クッションの役目をします。その結果、電車の中の振動も少なくなります。
線路の下にはたくさんの石がしきつめられていますね。この石を「バラスト(砕石)」といいます。石があるおかげで、はしる電車が線路にかける力が分散され、クッションの役目をします。その結果、電車の中の振動も少なくなります。
 バラストのはたらきを、踏切で観察することができます。踏切を電車がとおるとき、線路のレールがぐっとしずみこむのがわかるはずです。このように、電車の重みがレールをおす力をバラストが分散させて、レールがゆがむのをふせいでいるのです。
バラストのはたらきを、踏切で観察することができます。踏切を電車がとおるとき、線路のレールがぐっとしずみこむのがわかるはずです。このように、電車の重みがレールをおす力をバラストが分散させて、レールがゆがむのをふせいでいるのです。
 石がないと、電車の重さでまくら木が地面にしずんでしまう。バラストがあると、力が分散されて1か所にかかる力が小さくなる。
石がないと、電車の重さでまくら木が地面にしずんでしまう。バラストがあると、力が分散されて1か所にかかる力が小さくなる。
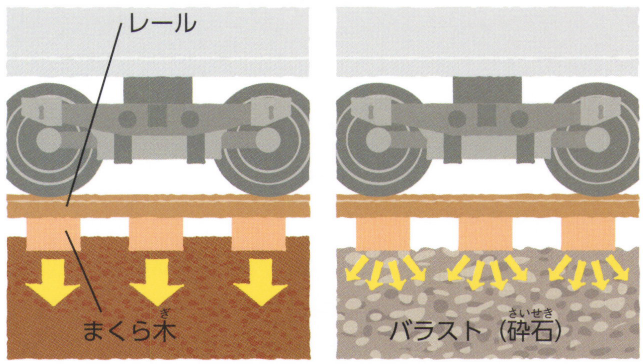

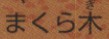
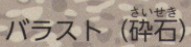
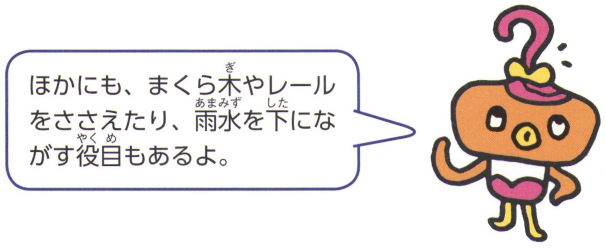
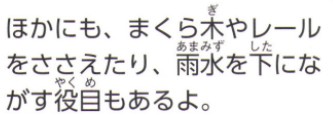
あつい日に水をまくのはなぜ?
 水を蒸発させてまわりをすずしくするため
水を蒸発させてまわりをすずしくするため
 あつい日の少し日がかげってきた時間に、玄関まわりや道路に水をまくようすをみたことはありませんか?
あつい日の少し日がかげってきた時間に、玄関まわりや道路に水をまくようすをみたことはありませんか?
これは、「打ち水」といって、古くから夕すずみの方法として、おこなわれてきました。
 気温があがるのは、太陽が空気を直接あたためるのではなく、地面をあたためることで、その熱が空気につたわるためです。
気温があがるのは、太陽が空気を直接あたためるのではなく、地面をあたためることで、その熱が空気につたわるためです。
真夏の道路や地面は、太陽にあたためられて、とてもたくさんの熱をもっています。そんなとき、水を地面にまくと、水は地面の熱で蒸発して気体になります。水は地面の熱をうばいながら蒸発するため、まわりの温度がさがり、すずしくかんじるのです。
打ち水は、地面をひやすことで、少しでもすずしくしようという昔からの知恵なのです。

205
こんにゃくは何でできているの?
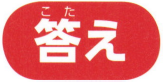 コンニャクという植物のくきからつくります
コンニャクという植物のくきからつくります
 おでんや煮物にはいっているこんにゃくは、ぷりぷりとした、どくとくの食感ですね。こんにゃくは、コンニャクという植物の「球茎」とよばれる、くきがふとった部分が原料です。「コンニャクイモ」や「こんにゃく玉」などともよばれます。
おでんや煮物にはいっているこんにゃくは、ぷりぷりとした、どくとくの食感ですね。こんにゃくは、コンニャクという植物の「球茎」とよばれる、くきがふとった部分が原料です。「コンニャクイモ」や「こんにゃく玉」などともよばれます。
 こんにゃくのつくり方は、まず球茎をほりだし、よくあらって、きってから日にあてます。かわいたら粉にしてふるい、重たい粉だけをよりわけます。それに熱湯をくわえてよくまぜ、おいておくとねばりがでてきます。そこに、こんにゃくをかためる作用がある石灰をまぜて、型にいれます。最後に、熱湯でゆでてかため、つめたい水の中であくをとったらできあがりです。
こんにゃくのつくり方は、まず球茎をほりだし、よくあらって、きってから日にあてます。かわいたら粉にしてふるい、重たい粉だけをよりわけます。それに熱湯をくわえてよくまぜ、おいておくとねばりがでてきます。そこに、こんにゃくをかためる作用がある石灰をまぜて、型にいれます。最後に、熱湯でゆでてかため、つめたい水の中であくをとったらできあがりです。
 コンニャクイモ
コンニャクイモ

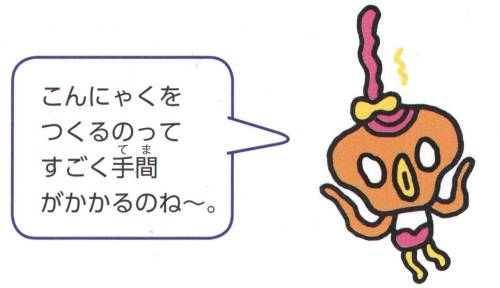
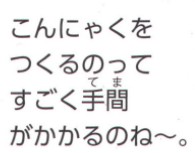
昔の人はどうやって大きな石をきったの?
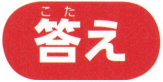 小さな穴をたくさんあけてわりました
小さな穴をたくさんあけてわりました
 お城の石垣やピラミッドにつかわれている石は、1つ数メートルの高さがあり、とても大きいですね。このような大きな石を昔の人たちはどのようにきっていたのでしょうか。
お城の石垣やピラミッドにつかわれている石は、1つ数メートルの高さがあり、とても大きいですね。このような大きな石を昔の人たちはどのようにきっていたのでしょうか。
 石のきり方には、時代や国によってさまざまな手法があったようですが、今でもつかわれているきり方をみてみましょう。
石のきり方には、時代や国によってさまざまな手法があったようですが、今でもつかわれているきり方をみてみましょう。
まず、「石目」とよばれる、石のわれやすい方向をみきわめます。のみとかなづちをつかって、石目にそって小さな穴(矢穴)をあけます。そこに、くさびをうちこんで石をわります。
石をまっすぐに、きれいにきるには、石目をみきわめる経験と技術が必要でした。現代では、ダイヤモンドの刃のついたカッターがつかわれています。
 矢穴ののこる石。(萩城/山口県)
矢穴ののこる石。(萩城/山口県)

 石のきり方
石のきり方
①石目にそって穴をあける。

②くさびをうちこむ。
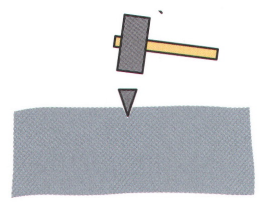
③石がわれる。
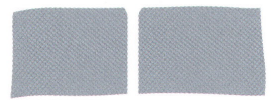
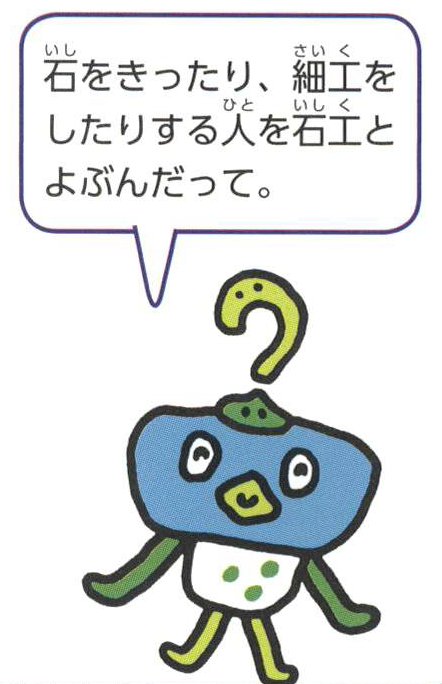
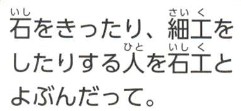
206
207
第4章 地球・宇宙のなぜ?
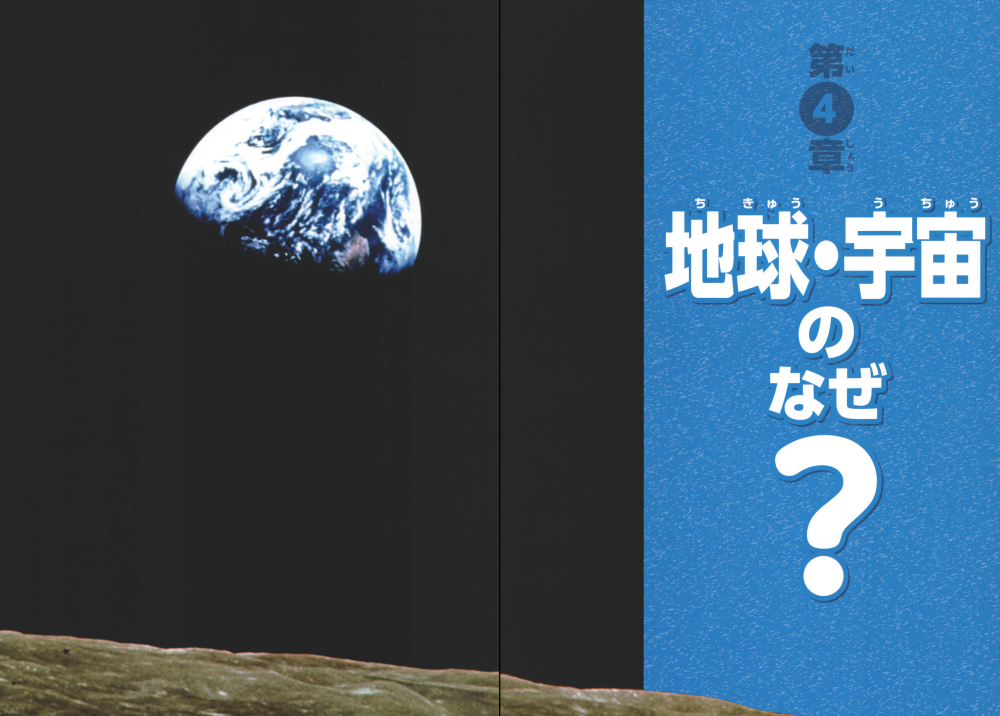
208
月の形はどうしてかわるの?
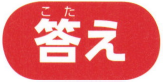 太陽光のあたる部分だけがみえるから
太陽光のあたる部分だけがみえるから
 満月、半月、三日月など、月は形をさまざまにかえます。月は、それ自体がひかっているのではなく、太陽の光をうけている部分がひかってみえています。
満月、半月、三日月など、月は形をさまざまにかえます。月は、それ自体がひかっているのではなく、太陽の光をうけている部分がひかってみえています。
そのため、太陽に対して月がどの方向にあるかによって、月の見た目の形がかわります。
 地球からみて月が太陽と同じ方向にあるのが新月です。このとき、地球からみえる月は、太陽の光があたるちょうど反対側なので、かげになりみえません。反対に、地球をはさむように反対側にくると、全体がみえる満月になります。
地球からみて月が太陽と同じ方向にあるのが新月です。このとき、地球からみえる月は、太陽の光があたるちょうど反対側なので、かげになりみえません。反対に、地球をはさむように反対側にくると、全体がみえる満月になります。
この月のみちかけの周期はおよそ29日と12時間で「朔望月」といいます。周期が1か月よりも少し短いため、ときどきひと月に2回満月になるときがあります。これをブルームーンといいます。
 月のみちかけの状態をあらわすのに「月齢」がつかわれます。新月を0として、翌日が「1」にその翌日が「2」と1日ずつふえ、月齢が7前後は上弦、15前後は満月、22前後は下弦、30にちかい数字であれば新月がちかづきます。
月のみちかけの状態をあらわすのに「月齢」がつかわれます。新月を0として、翌日が「1」にその翌日が「2」と1日ずつふえ、月齢が7前後は上弦、15前後は満月、22前後は下弦、30にちかい数字であれば新月がちかづきます。
 地球のまわりの月の運動と、月の見た目の変化。
地球のまわりの月の運動と、月の見た目の変化。
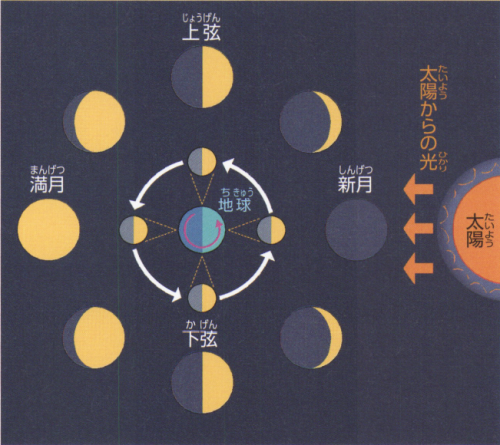


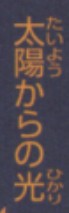




209
月食や日食がおこるのはなぜ?
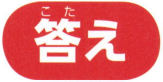 月のかげに太陽がかくれたり、地球の影に月がかくれたりするため
月のかげに太陽がかくれたり、地球の影に月がかくれたりするため
 月食がおこるしくみ
月食がおこるしくみ
 月食とは、太陽、地球、月の順に一直線上にならび、月が地球のかげにかくれてしまうことです。
月食とは、太陽、地球、月の順に一直線上にならび、月が地球のかげにかくれてしまうことです。
月食には月がすべて地球のかげにかくれてしまう皆既月食と、一部がかくれる部分月食があります。
皆既月食でも、月がまったくみえなくなるわけではなく、月が赤くみえる現象がしられています。太陽の光が大気を通過するときに、波長の長い赤色の光が地球をまわりこんで月をてらすため、赤くみえるのです。
 月食のしくみ。
月食のしくみ。
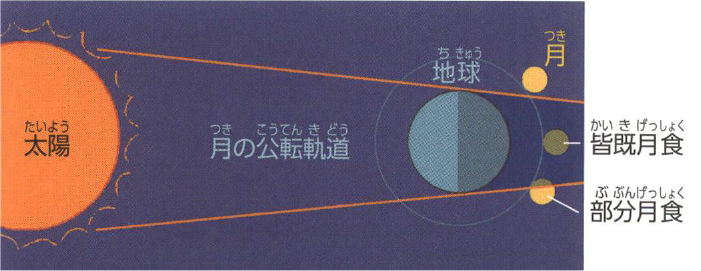



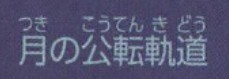
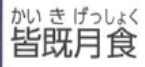
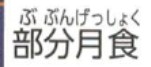
 皆既月食の月のようす。
皆既月食の月のようす。

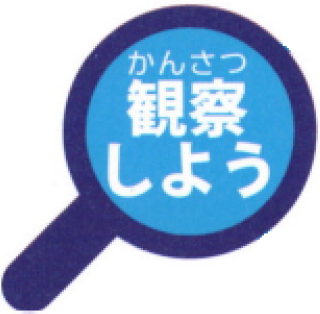 月食・日食はいつみられるの?
月食・日食はいつみられるの?
2016年以降におこる日食・月食です。
| 年・月・日
| 種類
| 場所
|
|---|
| 2017年8月8日
| 部分月食
| 日本でみえる
|
| 2018年1月31日
| 皆既月食
| 日本でみえる
|
| 2018年7月28日
| 皆既月食
| 日本でみえる
|
| 2019年1月21日
| 皆既月食
| 日本でみえない
|
| 2019年7月17日
| 部分月食
| 日本の一部でみえる
|
| 年・月・日
| 種類
| 場所
|
|---|
| 2016年9月1日
| 金環日食
| 南大西洋、アフリカ、インド洋など
|
| 2017年2月26日
| 金環日食
| 南太平洋、南米、アフリカなど
|
| 2017年8月22日
| 皆既日食
| 北太平洋、アメリカ、北大西洋など
|
| 2019年1月6日
| 部分日食
| 日本、アジア東部、北太平洋など
|
| 2019年7月3日
| 皆既日食
| 南太平洋、南米など
|
| 2019年12月26日
| 金環日食
| アラビア半島、インド、東南アジアなど
|
| 2020年6月21日
| 金環日食
| アフリカ、アジア、太平洋など
|
※日食は、金環日食、皆既日食、部分日食(日本でみられるもの)のみとりあげています。
210
太陽はどのくらいあついの?
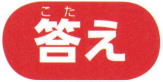 太陽の表面のフレアは、およそ1000万℃もの高温です
太陽の表面のフレアは、およそ1000万℃もの高温です
 太陽は地球のある太陽系の中心の星です。熱や光など、たくさんのめぐみをあたえてくれる太陽ですが、地球とはおよそ1億5000万kmもの距離があります。そんな遠くから地球へ太陽の熱がとどくのです。
太陽は地球のある太陽系の中心の星です。熱や光など、たくさんのめぐみをあたえてくれる太陽ですが、地球とはおよそ1億5000万kmもの距離があります。そんな遠くから地球へ太陽の熱がとどくのです。
 太陽はいくつかの層にわかれています。太陽の中心には核があり、温度は1600万℃もあります。
太陽はいくつかの層にわかれています。太陽の中心には核があり、温度は1600万℃もあります。
また、フレアとよばれる太陽の表面でおきる爆発の温度は1000万℃で、太陽の表面でもっとも高温です。鉄のとける温度がおよそ1500℃なので、くらべてみても太陽の温度がどれほど高いかがわかります。
 太陽の断面と温度。
太陽の断面と温度。
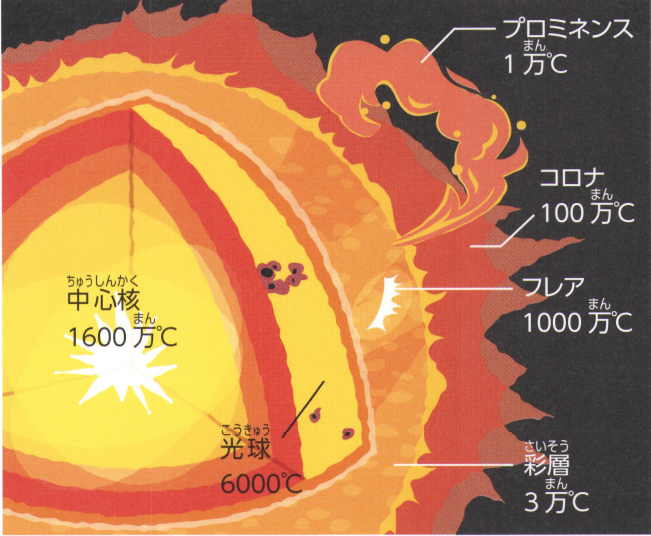
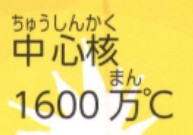
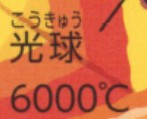
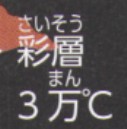
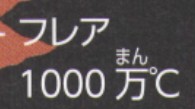
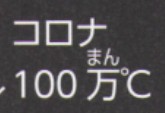
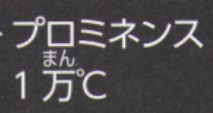
211
流れ星はどうしてできるの?
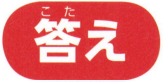 宇宙のちりなどが地球にぶつかるためです
宇宙のちりなどが地球にぶつかるためです
 流れ星は、夜空の星がうごいているのではありません。その正体は宇宙にただよっているちりや小石です。このちりや小石が地球にぶつかると、地球をおおう空気の層とこすれて高温になり、かがやきます。これが流れ星です。
流れ星は、夜空の星がうごいているのではありません。その正体は宇宙にただよっているちりや小石です。このちりや小石が地球にぶつかると、地球をおおう空気の層とこすれて高温になり、かがやきます。これが流れ星です。
 流れ星はそのほとんどが途中でもえつきて、地表におちてくることはありません。しかし、ごくまれに流れ星のもとになるものが大きいと、途中でもえつきずにおちてくることがあります。これがいん石です。
流れ星はそのほとんどが途中でもえつきて、地表におちてくることはありません。しかし、ごくまれに流れ星のもとになるものが大きいと、途中でもえつきずにおちてくることがあります。これがいん石です。
流れ星はつねにうまれていて、まわりが暗い場所で、すんだ夜空をじっくり観察すれば1時間に数こはみることができます。
 流れ星ができるようす。
流れ星ができるようす。

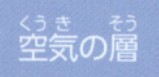
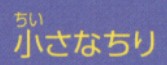
212
流星群って何?
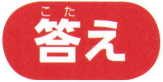 放射状にひろがる流れ星の集団です
放射状にひろがる流れ星の集団です
 たくさんの流れ星があらわれる流星群には、すい星が関係しています。
たくさんの流れ星があらわれる流星群には、すい星が関係しています。
すい星とは、太陽のまわりをまわる小さな天体のことです。本体の大きさは数百
から数十までさまざまで、その成分のほとんどが水でできている氷のかたまりです。のこりは二酸化炭素などで、この中にたくさんのちりがまざっています。
 すい星がとおったあとには、たくさんのちりがおびのようにちらばります。地球がすい星の軌道にちかづいたり横切ったりするとき、それらがまとめて地球の大気にふれることで、たくさんの流れ星の集団が放射状にながれるようすが観察できるのです。これが流星群です。
すい星がとおったあとには、たくさんのちりがおびのようにちらばります。地球がすい星の軌道にちかづいたり横切ったりするとき、それらがまとめて地球の大気にふれることで、たくさんの流れ星の集団が放射状にながれるようすが観察できるのです。これが流星群です。
 流星群のできるしくみ。
流星群のできるしくみ。
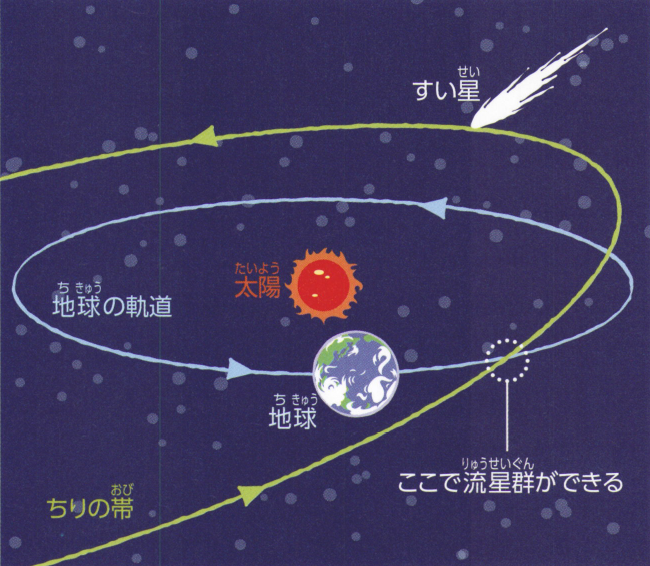
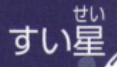


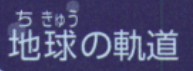
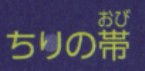
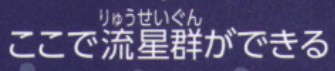

 流星群を観察しよう!
流星群を観察しよう!
 流星群。
流星群。

NASA
流星群は、地球がすい星の軌道に接近するのにあわせて周期的にみることができます。とくに、「しぶんぎ座流星群」「ペルセウス座流星群」「ふたご座流星群」は三大流星群といわれ、多くの流れ星を観察できます。
| 流星群名
| 流星出現期間
| 極大※
| 1時間あたりにみられる数
|
|---|
| しぶんぎ座流星群
| 1月1日~1月7日
| 1月4日頃
| 40
|
| こと座χ流星群
| 4月15日~4月25日
| 4月22日頃
| 10
|
| みずがめ座η流星群
| 4月25日~5月17日
| 5月6日頃
| 5
|
| みずがめ座δ南流星群
| 7月12日~8月19日
| 7月27日頃
| 5
|
| ペルセウス座流星群
| 7月17日~8月24日
| 8月13日頃
| 50
|
| オリオン座流星群
| 10月2日~10月30日
| 10月21日頃
| 40
|
| おうし座流星群(南群)
| 10月15日~11月30日
| 11月5日頃
| 5
|
| おうし座流星群(北群)
| 10月15日~11月30日
| 11月12日頃
| 5
|
| しし座流星群
| 11月10日~11月25日
| 11月18日頃
| 10
|
| ふたご座流星群
| 12月5日~12月20日
| 12月14日頃
| 80
|
「世界天文年の流星群」(国立天文台)http://www.nao.ac.jp/phenomena/20090000/index.html
※極大…もっとも流星が多くみられる期間のこと。
213
土星にはなぜわがあるの?
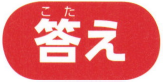 氷や岩のかけらの集まりがわになってみえます
氷や岩のかけらの集まりがわになってみえます
 土星は、太陽系の中で2番目に大きく、地球の9倍もあります。しかし、そのほとんどがガスでできていて、とても軽い惑星です。
土星は、太陽系の中で2番目に大きく、地球の9倍もあります。しかし、そのほとんどがガスでできていて、とても軽い惑星です。
本体のほかに、大きなわをもつかわった形をしています。そのわの正体は、氷や岩石などのつぶの集まりです。
わのはばは数十万
もあり、とても大きいのですが、あつさは100
ほどであることが観測されています。
 なぜわができたのか、はじまりについてはっきりした理由はわかっていませんが、たとえば氷をたくさんふくんだすい星などの天体が土星にちかづき、こわれたのこりがわになったとかんがえられています。
なぜわができたのか、はじまりについてはっきりした理由はわかっていませんが、たとえば氷をたくさんふくんだすい星などの天体が土星にちかづき、こわれたのこりがわになったとかんがえられています。
 土星。
土星。
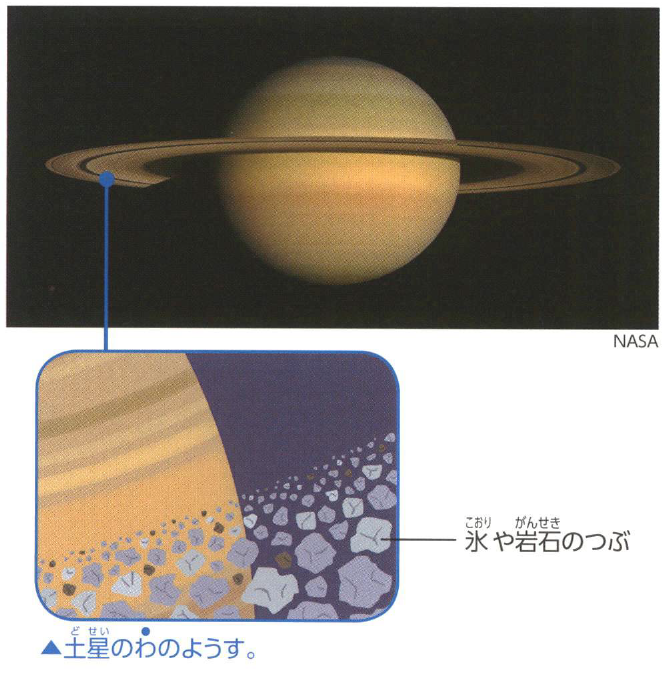
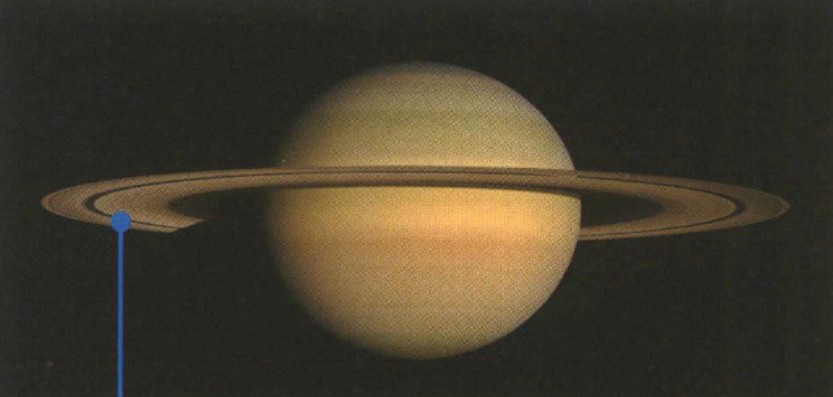


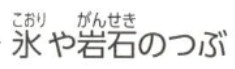
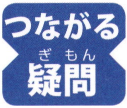 土星のほかにもわをもつ惑星はあるの?
土星のほかにもわをもつ惑星はあるの?
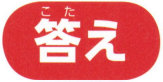 太陽系の中では天王星、海王星、木星にはわがあります
太陽系の中では天王星、海王星、木星にはわがあります
 特徴的なわをもつ土星ですが、太陽系の惑星の中には、土星以外にもわをもつものがあります。
特徴的なわをもつ土星ですが、太陽系の惑星の中には、土星以外にもわをもつものがあります。
 天王星と海王星には、土星と同じように氷のつぶがあつまってできたわがあります。しかし、土星ほどはっきりしたものでなく細いものです。
天王星と海王星には、土星と同じように氷のつぶがあつまってできたわがあります。しかし、土星ほどはっきりしたものでなく細いものです。
木星にも細いわがありますが、こちらは木星のまわりの衛星からとびだしたちりがあつまってできています。
 天王星と、ほそいわ。
天王星と、ほそいわ。
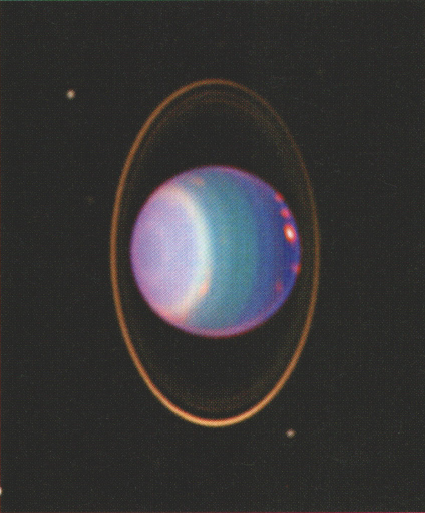
 海王星のほそいわ。
海王星のほそいわ。
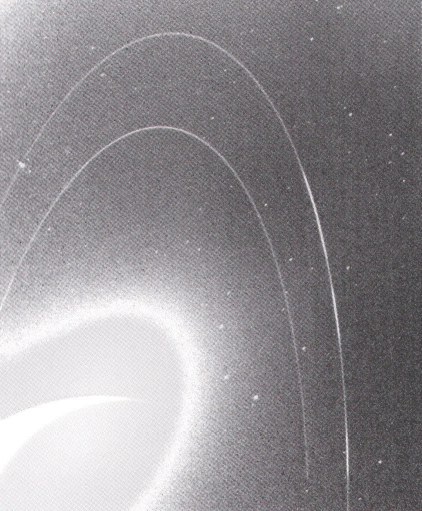
NASA
214
星はどうして夜だけひかるの?
 1日中ひかっていますが、明るい日中はみえません
1日中ひかっていますが、明るい日中はみえません
 星は夜にしかそのすがたをみることはできません。昼間の空には星はなく、太陽がしずむと星がのぼってくるようにみえますがそうではありません。
星は夜にしかそのすがたをみることはできません。昼間の空には星はなく、太陽がしずむと星がのぼってくるようにみえますがそうではありません。
 星は、昼間の空でも夜空と同じようにかがやいています。しかし、日中は太陽の光が空をおおって明るいため、太陽にくらべて明るさの弱い星はかすんでみえなくなってしまうのです。
星は、昼間の空でも夜空と同じようにかがやいています。しかし、日中は太陽の光が空をおおって明るいため、太陽にくらべて明るさの弱い星はかすんでみえなくなってしまうのです。
夜、満月のころも同じです。太陽ほどではありませんが、満月のころは月の光が強いため、星がみえにくくなります。
 夜の星のようす。
夜の星のようす。
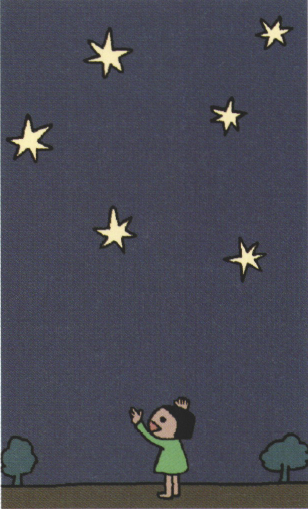
 日中の星のようす。
日中の星のようす。

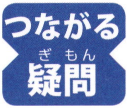 星はどうしてまたたくの?
星はどうしてまたたくの?
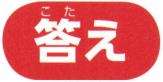 大気が不安定になると空気がゆれて光がまがってみえるから
大気が不安定になると空気がゆれて光がまがってみえるから
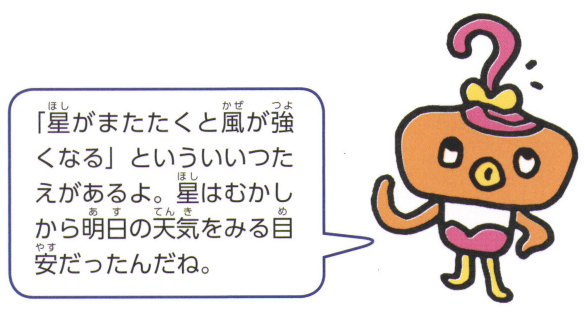
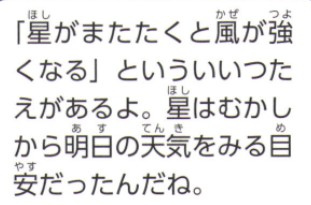
 星がチカチカとまたたくようにみえることがありますね。これは、星がひかったりきえたりしているわけではなく、地球をおおう大気が関係しています。
星がチカチカとまたたくようにみえることがありますね。これは、星がひかったりきえたりしているわけではなく、地球をおおう大気が関係しています。
 地球は、地表からおよそ数百の空気の層におおわれていて、星の光はその空気の層をとおってわたしたちにとどいています。
地球は、地表からおよそ数百の空気の層におおわれていて、星の光はその空気の層をとおってわたしたちにとどいています。
空気の層は透明で目にはみえませんが、ゆれうごく空気の中を光がとおると光はおれまがり、ゆれてみえます。このゆれが、まるで星がチカチカとまたたくようにみえる理由です。
 大気が安定していると、光はまっすぐわたしたちのもとにとどくので、星のまたたきは少なくなります。
大気が安定していると、光はまっすぐわたしたちのもとにとどくので、星のまたたきは少なくなります。
 大気が安定しているときは星のまたたきは少ない。
大気が安定しているときは星のまたたきは少ない。
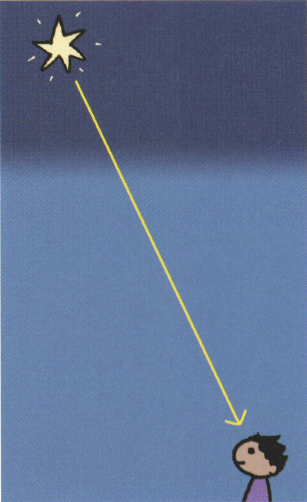
 大気が不安定なときは星がまたたいてみえる。
大気が不安定なときは星がまたたいてみえる。
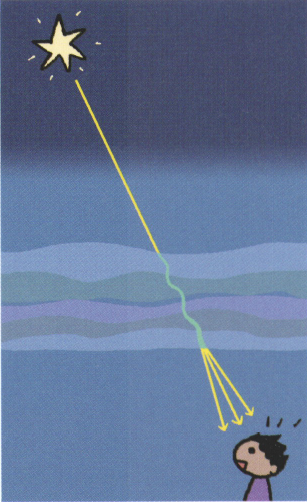
215
星の明るさがちがうのはなぜ?
 星自体の明るさや地球との距離がちがうため
星自体の明るさや地球との距離がちがうため
 星の明るさは、「等級」という単位であらわされます。地球からみたときの明るさを実視等級、同じ距離にあると仮定した場合の明るさを絶対等級といいます。わたしたちが肉眼でみることのできる星は、実視等級で1~6等星までです。
星の明るさは、「等級」という単位であらわされます。地球からみたときの明るさを実視等級、同じ距離にあると仮定した場合の明るさを絶対等級といいます。わたしたちが肉眼でみることのできる星は、実視等級で1~6等星までです。
1等星から6等星までの星の数はおよそ8600あり、さらに地平線の上にでている半分しかみえないので、実際にみえる数は4000ほどです。
 星の明るさがちがう理由の1つは地球との距離です。同じ星の場合でも、地球に近ければ明るく、遠ければ暗くみえます。
星の明るさがちがう理由の1つは地球との距離です。同じ星の場合でも、地球に近ければ明るく、遠ければ暗くみえます。
 もう1つの理由は、星自体の明るさです。星はガスからなりたっています。たくさんのガスからできるほど、大きくて明るい星になります。少ないガスからなりたっている星は、小さくて暗い星です。
もう1つの理由は、星自体の明るさです。星はガスからなりたっています。たくさんのガスからできるほど、大きくて明るい星になります。少ないガスからなりたっている星は、小さくて暗い星です。
 等級の明るさくらべ(実視等級)
等級の明るさくらべ(実視等級)
6等星を1としたとき、1等星は100倍の明るさ。
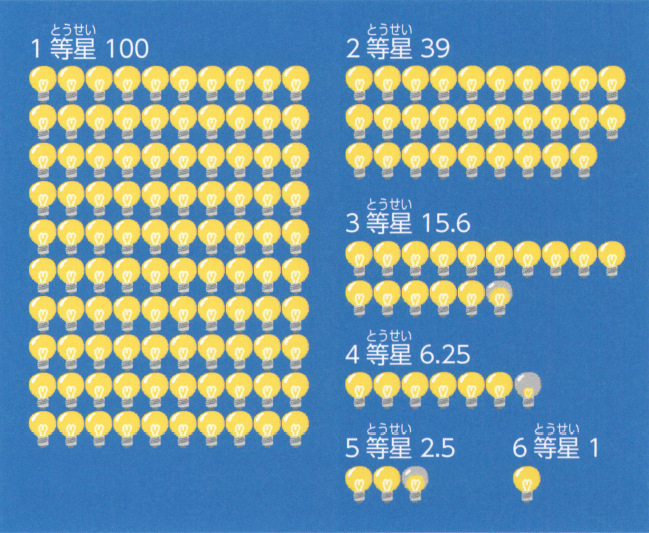
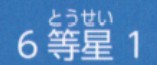
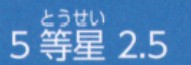
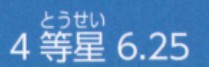
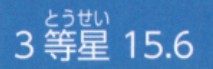
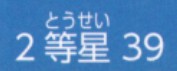
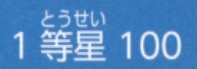
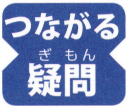 星の色はどうしてちがうの?
星の色はどうしてちがうの?
 星の表面温度によって、色がかわります
星の表面温度によって、色がかわります
 星をよくみると、青白くひかるものや赤みをおびてひかるものなどがあります。色がちがうのは、星の表面温度がちがうからです。
星をよくみると、青白くひかるものや赤みをおびてひかるものなどがあります。色がちがうのは、星の表面温度がちがうからです。
表面温度が低い3000℃ぐらいの星は赤っぼく、6000℃くらいだと黄色に、さらに温度が高くなると白っぽくみえます。1万℃をこえる高温の星になると、青白くかがやきます。
このように、星の色からその星の表面温度がどのくらいかがわかります。
夏の代表的な星座、さそり座のアンタレスは赤くひかり、冬の代表的な星座、おおいぬ座のシリウスは青くひかります。ともに1等星で明るく、観察しやすい星です。
 星の表面温度とその例。
星の表面温度とその例。
| 色
| 表面温度
| 例
|
|---|

| ~3500℃
| アンタレス(さそり座)
|
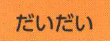
| 3500~6000℃
| ポルックス(ふたご座)
|

| 6000℃
| 太陽
|
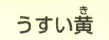
| 6000~7000℃
| プロキオン(こいぬ座)
|

| 7000~1万℃
| シリウス(おおいぬ座)
|

| 1万℃
| スピカ(おとめ座)
|
 さそり座のアンタレス。
さそり座のアンタレス。

 おおいぬ座のシリウス。
おおいぬ座のシリウス。

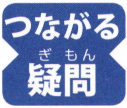 雷がひかるのはなぜ?
雷がひかるのはなぜ?
 雷が空気の中をながれると、空気が熱くなるから
雷が空気の中をながれると、空気が熱くなるから
 ものは高温になると光を発する性質がありますが、空気も同じです。雷の電気が空気の中をとおると、空気がこすれて摩擦がおき、高温になってひかるのです。細いすじのようにひかる稲妻は、電気のとおった道すじというわけです。
ものは高温になると光を発する性質がありますが、空気も同じです。雷の電気が空気の中をとおると、空気がこすれて摩擦がおき、高温になってひかるのです。細いすじのようにひかる稲妻は、電気のとおった道すじというわけです。
 ゴロゴロやバリバリといった雷の大きな音も、雷のふれた空気が高温になってふくらみ、ふるえるときの音です。
ゴロゴロやバリバリといった雷の大きな音も、雷のふれた空気が高温になってふくらみ、ふるえるときの音です。
雷の音が光よりおくれてきこえるのは、光よりも音の方が空気をつたわるのに時間がかかるためです。
光の速さは、秒速およそ30万ですので、1秒で地球を7まわり半するほどです。音がつたわる速さは1秒におよそ340なので、雷がひかってから3秒後に音がきこえた場合、1
ほどはなれていることになります。

 雷の電気がむりやり空気の中をとおると、そのまわりの空気がひかる。
雷の電気がむりやり空気の中をとおると、そのまわりの空気がひかる。
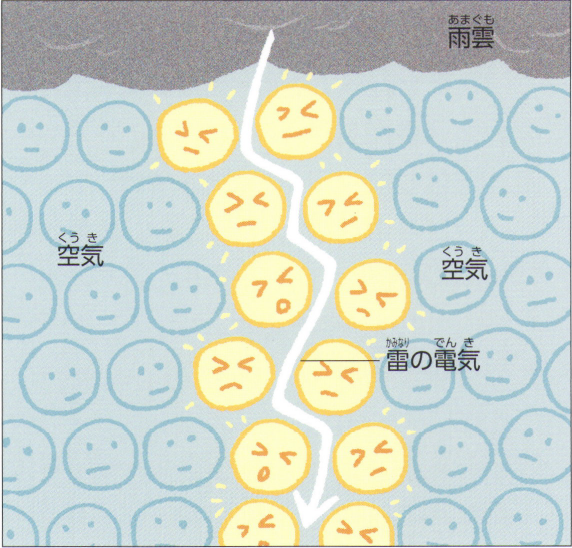



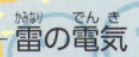
217
夕焼けが赤いのはなぜ?
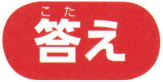 太陽の位置によって、赤い光が強くみえるから
太陽の位置によって、赤い光が強くみえるから
 空は、昼間は青く、夕方になるにつれて赤にかわっていきます。空の色の変化には、太陽の位置が関係しています。
空は、昼間は青く、夕方になるにつれて赤にかわっていきます。空の色の変化には、太陽の位置が関係しています。
太陽の光は白っぽくみえますが、実は虹にあらわれるのと同じ7色の光があつまって白くみえています。
この7色の光は、色によって性質がちがいます。青い光は、空気中の酸素や窒素にぶつかるとちらばってしまい、まっすぐにすすむことができません。それにくらべて、赤やオレンジ色の光はちらばりにくく、空気中をそのまますすめるため、遠くまでとどくのです。
 夕日は昼間にくらべて太陽の光が空気の層をとおって目にとどくまでの距離が長くなります。そのため、青い光がへり、赤い光が多く目にとどきます。だから、夕焼けは赤くみえるのです。
夕日は昼間にくらべて太陽の光が空気の層をとおって目にとどくまでの距離が長くなります。そのため、青い光がへり、赤い光が多く目にとどきます。だから、夕焼けは赤くみえるのです。
 昼間は太陽が高い位置にあり、光が空気の層をとおる距離が短い。
昼間は太陽が高い位置にあり、光が空気の層をとおる距離が短い。
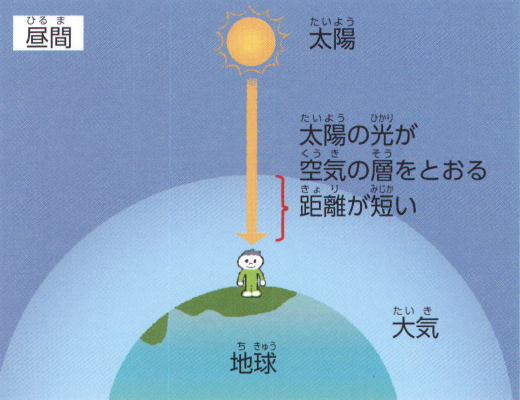
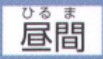



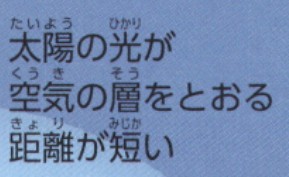
 夕方は、太陽がかたむくため、空気の層をとおる距離が長い。
夕方は、太陽がかたむくため、空気の層をとおる距離が長い。
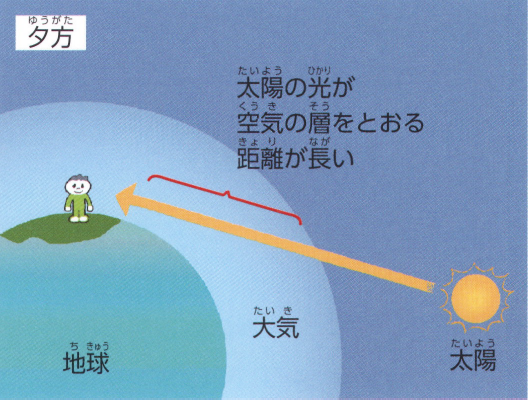
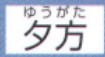



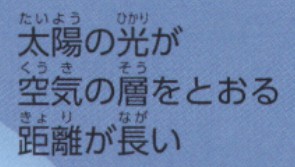
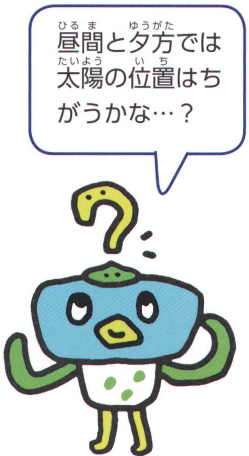
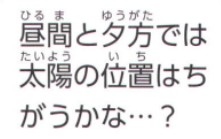
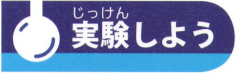 夕焼けをつくってみよう!
夕焼けをつくってみよう!
ペットボトルと懐中電灯をつかって、昼間の太陽と夕方の空を再現してみましょう。光のあて方でどんなちがいがあるかな?
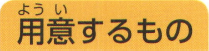
角型の2
ペットボトル、懐中電灯、牛乳、水
①ペットボトルに小さじ1の牛乳をいれ、水をいっぱいまでいれたら、ふたをしてよくふってまぜる。
②平らな場所に①を横にしておき、部屋を暗くする。
③懐中電灯でペットボトルを真上からてらしたときと、ペットボトルの底の方からてらしたときで、水の色をくらべる。
 上からてらすと、白っぽくみえる。(昼間の太陽)
上からてらすと、白っぽくみえる。(昼間の太陽)
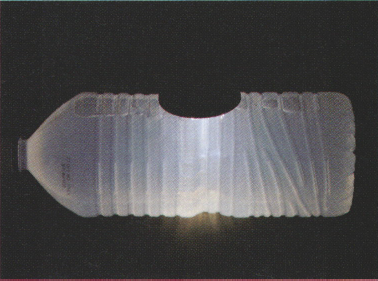
 底からてらすと、赤っぽくみえる。(夕方の太陽)
底からてらすと、赤っぽくみえる。(夕方の太陽)
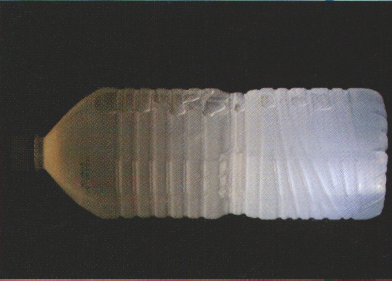
218
にじはどうしてできるの?
 空気中の水のつぶの中で太陽の光が反射して色がわかれてみえます
空気中の水のつぶの中で太陽の光が反射して色がわかれてみえます
 空ににじがみえるのは、主に雨上がりです。雨上がりは、すでに雨がやんでいても空気中に小さな水のつぶがたくさんただよっている状態です。にじは、その水のつぶの中に太陽の光がはいることであらわれます。
空ににじがみえるのは、主に雨上がりです。雨上がりは、すでに雨がやんでいても空気中に小さな水のつぶがたくさんただよっている状態です。にじは、その水のつぶの中に太陽の光がはいることであらわれます。
 太陽の光は、白くみえても実際にはいろいろな色の光がまざりあっています。水のつぶに太陽の光がはいり、中で反射すると、光の色がわかれてあらわれます。これがにじです。
太陽の光は、白くみえても実際にはいろいろな色の光がまざりあっています。水のつぶに太陽の光がはいり、中で反射すると、光の色がわかれてあらわれます。これがにじです。
 ごくまれに、2つのにじがかかることがあります。これは、水のつぶの中で光が2回反射することで、本来のにじとは色の順番が反対のにじができることがあります。このとき主となるにじを「主にじ」、主にじよりうすいにじを「副にじ」といいます。
ごくまれに、2つのにじがかかることがあります。これは、水のつぶの中で光が2回反射することで、本来のにじとは色の順番が反対のにじができることがあります。このとき主となるにじを「主にじ」、主にじよりうすいにじを「副にじ」といいます。
 にじのできるしくみ。
にじのできるしくみ。
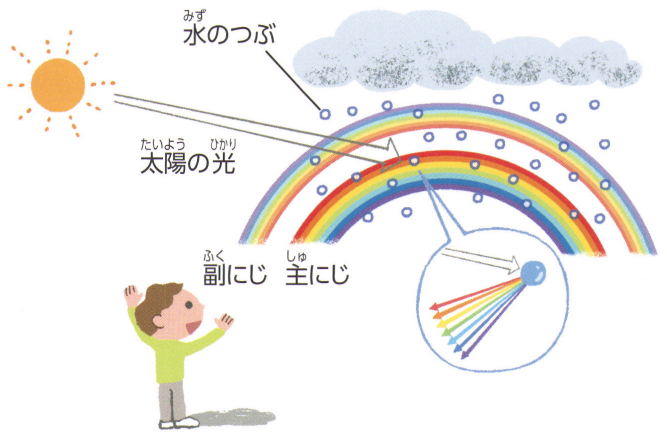
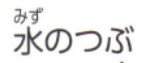
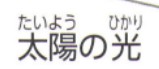
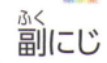


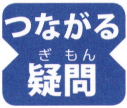 にじはどうして7色なの?
にじはどうして7色なの?
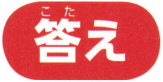 太陽の光のうち、人の目にみえる成分は、大きく7つの色にわけられるから
太陽の光のうち、人の目にみえる成分は、大きく7つの色にわけられるから
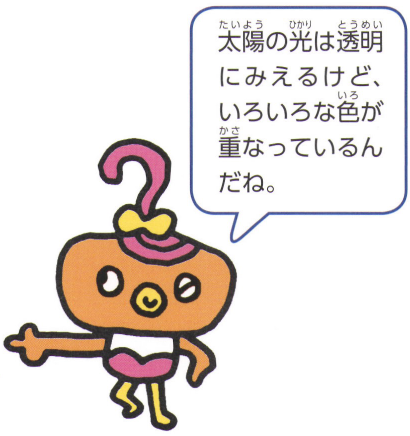
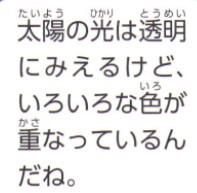
 にじは太陽の光の反射でできますが、太陽の光には、赤、だいだい、黄、緑、青、あい、むらさきの7つの色がまざりあっています。ガラスでできた三角柱の「プリズム」に太陽の光をとおすとそのようすがよくわかります。
にじは太陽の光の反射でできますが、太陽の光には、赤、だいだい、黄、緑、青、あい、むらさきの7つの色がまざりあっています。ガラスでできた三角柱の「プリズム」に太陽の光をとおすとそのようすがよくわかります。
プリズムに太陽の光をあてると、光はまがってでてきます。これを「屈折」といいます。
光は波長によって色がちがいます。プリズムの中で波長の長い赤やだいだいなどの光は小さくまがり、波長の短い青やむらさきの光は大きくまがります。角度のちがう光が順番にあらわれるので、光が赤、だいだい、黄、緑、青、あい、むらさきの7色がきれいにならぶのです。
 プリズムの中でおきる現象と同じことが、空気中をただよう水のつぶの中でもおきます。これが空に大きなにじをかけるのです。
プリズムの中でおきる現象と同じことが、空気中をただよう水のつぶの中でもおきます。これが空に大きなにじをかけるのです。
 プリズムに太陽の光をあてると、7つの色にわかれる。
プリズムに太陽の光をあてると、7つの色にわかれる。
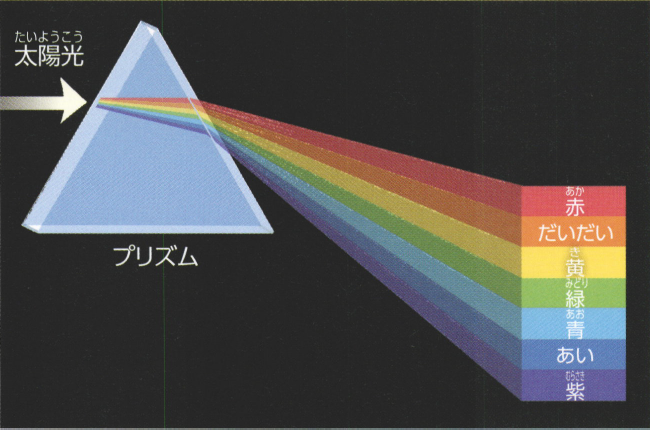
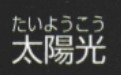
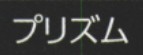

219
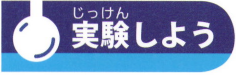 屋外でにじをつくってみよう
屋外でにじをつくってみよう
きりふきをつかえば、屋外で簡単ににじを観察することができます。
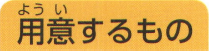
きりふき・水
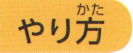
①きりふきに水をいれる。
②外がはれているときに、太陽をせにしてたち、きりふきで水をふくと、にじがあらわれる。

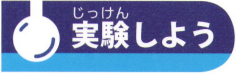 家の中でにじをつくってみよう
家の中でにじをつくってみよう
光がプリズムをとおったときと同じような現象で、懐中電灯と虫めがねをつかって、家の中で丸いにじをつくってみましょう。
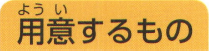
懐中電灯、虫めがね(大きいもの)、黒い画用紙、両面テープ、はさみ、白いかべ(または白い紙)
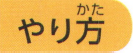
①懐中電灯の先端の直径をはかり、黒い画用紙でひとまわり小さな円をつくる。
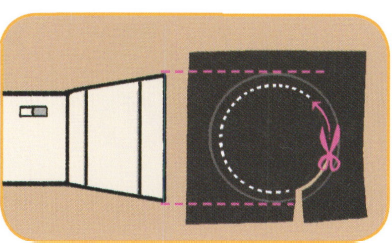
②虫めがねのレンズの中心に、①を両面テープでかるくとめる。
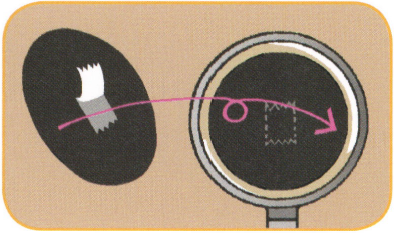
③部屋を暗くして、懐中電灯の光を白いかべにあてる。
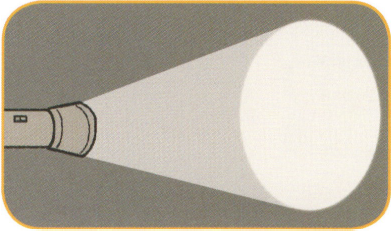
④②の虫めがねを懐中電灯の光の前にかざす。(虫めがねの中心と懐中電灯の光の中心があうようにする)
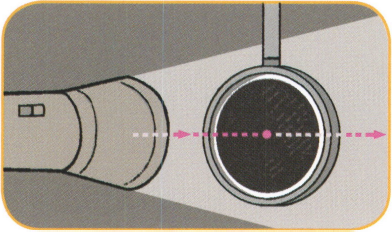
⑤光の円の中ににじの色があらわれるように虫めがねと懐中電灯の位置を調節する。
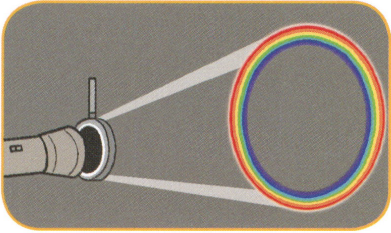
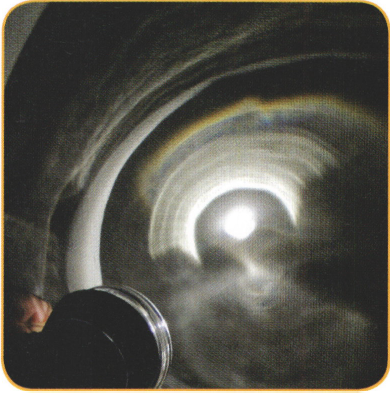
220
梅雨って何?
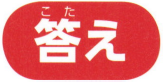 5月から7月にかけてくもりや雨のつづく気象現象のこと
5月から7月にかけてくもりや雨のつづく気象現象のこと
 梅雨とは、春から夏に季節がうつりかわる5月から7月の間、日本をはじめとする東アジア地域で雨が多くふる現象のことです。
梅雨とは、春から夏に季節がうつりかわる5月から7月の間、日本をはじめとする東アジア地域で雨が多くふる現象のことです。
梅雨の時期は、北からのしめったつめたい空気と、南からのしめったあたたかい空気が日本上空でぶつかります。その2つがぶつかりあったところを梅雨前線といいます。
 梅雨前線の上空では、温度差により水蒸気が発生し、上昇する気流によって上空へともちあげられます。その結果、水蒸気があつまって多くの雲ができ、たくさんの雨をふらせます。
梅雨前線の上空では、温度差により水蒸気が発生し、上昇する気流によって上空へともちあげられます。その結果、水蒸気があつまって多くの雲ができ、たくさんの雨をふらせます。
梅雨の期間はあたたかい空気とつめたい空気のおしあう力がどちらとも強いので梅雨前線の位置がなかなかうごきません。そのため、梅雨前線のかかった日本では梅雨の間雨がふりつづくのです。
 北からの空気と南からの空気がおしあって、日本の上空に前線ができる。
北からの空気と南からの空気がおしあって、日本の上空に前線ができる。
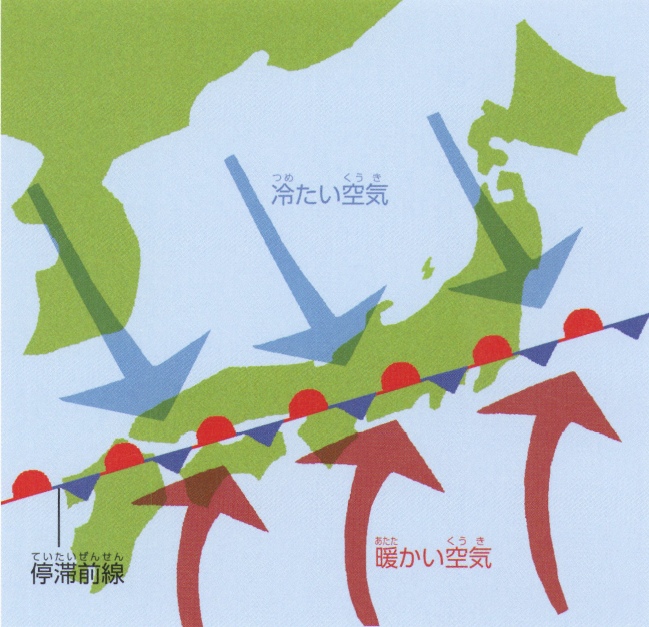
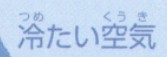
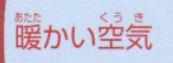
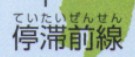
221
朝日や夕日はなぜ大きくみえるの?
 目の錯覚で大きさがちがってみえます
目の錯覚で大きさがちがってみえます
 1日の中で、朝日と夕日は日中の太陽にくらべて大きくみえます。
1日の中で、朝日と夕日は日中の太陽にくらべて大きくみえます。
しかし、実際には太陽の大きさがかわることはありません。太陽の位置によって人の脳は錯覚をおこして、大きさがかわったようにかんちがいをしてしまうとかんがえられています。
 わたしたちは、ものの大きさを、何かとくらべたり、距離をはかったり、さまざまな情報から判断しています。
わたしたちは、ものの大きさを、何かとくらべたり、距離をはかったり、さまざまな情報から判断しています。
 日中の太陽は、真上にでているため何かとくらべて正しい大きさをはかることができないため、遠くにあるようにかんじます。反対に、朝日や夕日は地平線の近くにあるため、建物や山など、大きさをくらべられるものがいくつもあり、ちかくにあるように感じます。ちかくにくらべるものがあるかないかによって、日中の太陽と、朝日や夕日の大きさがちがってみえるとかんがえられています。
日中の太陽は、真上にでているため何かとくらべて正しい大きさをはかることができないため、遠くにあるようにかんじます。反対に、朝日や夕日は地平線の近くにあるため、建物や山など、大きさをくらべられるものがいくつもあり、ちかくにあるように感じます。ちかくにくらべるものがあるかないかによって、日中の太陽と、朝日や夕日の大きさがちがってみえるとかんがえられています。
 地平線にしずむ夕日。太陽が地平線や水平線のちかくにあると、目の錯覚で大きくみえる。でも、実際の大きさはわからない。
地平線にしずむ夕日。太陽が地平線や水平線のちかくにあると、目の錯覚で大きくみえる。でも、実際の大きさはわからない。

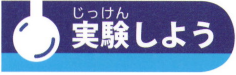 月の大きさをはかってみよう
月の大きさをはかってみよう
太陽を直接みることはできませんが、同じような現象は、月でもかんじることができます。5円玉をつかって実験してみましょう。
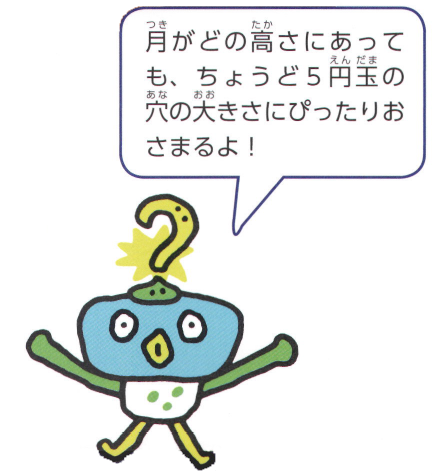
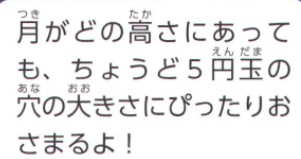
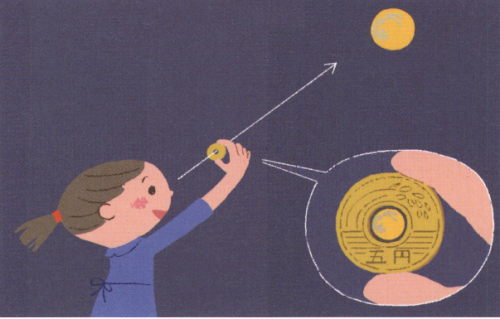
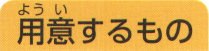
5円玉
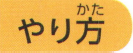
①満月の日に5円玉を手にもち、うでをいっぱいにのばしたら5円玉の穴から月をのぞく。
②地平線に近いとき、真上にあるときなど、時間をかえて①をおこなう。
222
雲は何でできているの?
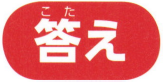 空気中の水や氷のつぶがたくさんあつまってできています
空気中の水や氷のつぶがたくさんあつまってできています
 空気中には、海や川、地面などから蒸発した水分が気体(水蒸気)になってたくさんふくまれています。
空気中には、海や川、地面などから蒸発した水分が気体(水蒸気)になってたくさんふくまれています。
水蒸気はあたためられるとふくらんで軽くなる性質をもっているので、太陽であたためられると空高くあがります。
しかし、地面からはなれて上へあがるにつれ、気温は低くなります。水蒸気はひやされて0.02(1の100分の2)ほどのとても小さな水や氷のつぶへと変化します。この小さな水や氷のつぶがたくさんあつまったものが雲です。
 雲のできるしくみ。
雲のできるしくみ。
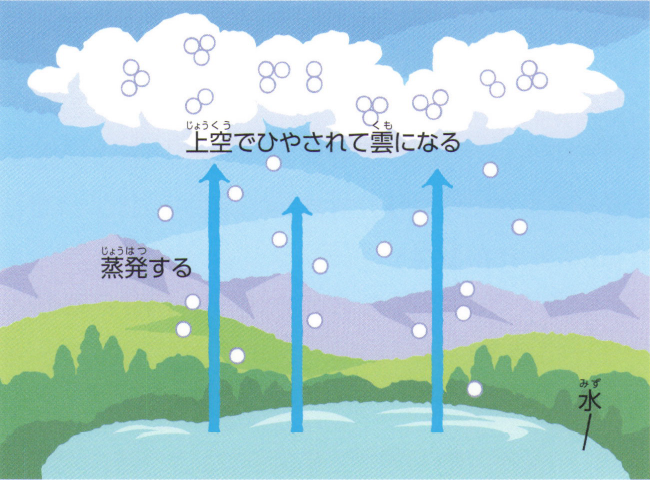

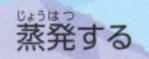
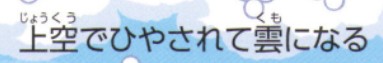
223
 10種雲形をさがそう
10種雲形をさがそう
雲は形によって10種類にわけられています。天気の変化をかんじることができるのでぜひおぼえましょう。
 積乱雲
積乱雲
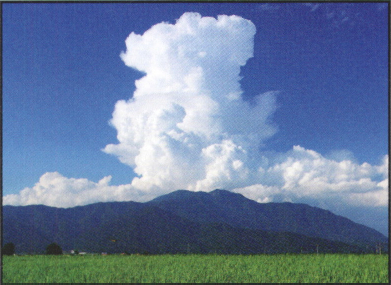
入道雲や雷雲ともよばれる。とても大きなかたまりになった雲で、雨やひょうをふらせる。
 巻雲
巻雲

すじ雲ともよばれる。筆で線をかいたような、すじのような雲。
 巻層雲
巻層雲

うす雲ともよばれる。空全体にかすみがかかったような雲。天気がくずれる前ぶれ。
 巻積雲
巻積雲
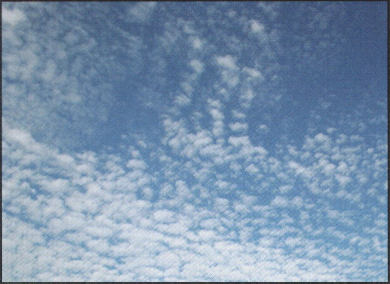
いわし雲やうろこ雲ともよばれる。魚のうろこににた細かな雲。
 高層雲
高層雲

おぼろ雲ともよばれる。空全体をおおう層になったぶあつい雲。雨や雪のふる前ぶれ。
 高積雲
高積雲

ひつじ雲ともよばれる。巻積雲よりも雲のかたまりが大きい。
 乱層雲
乱層雲

雨雲ともよばれる。こい灰色に空全体をおおう。低気圧や前線がちかづき、雨や雪がふりつづく。
 層積雲
層積雲

くもり雲、うね雲ともよばれる。畑のうねのようにならんでできる雲。
 積雲
積雲

わた雲ともよばれる。大きくかたまりになった雲。日中のはれているときにあらわれる。
 層雲
層雲

きり雲ともよばれる。地上に近く低い場所でできるうすい層の雲。弱い雨や雪がふる。
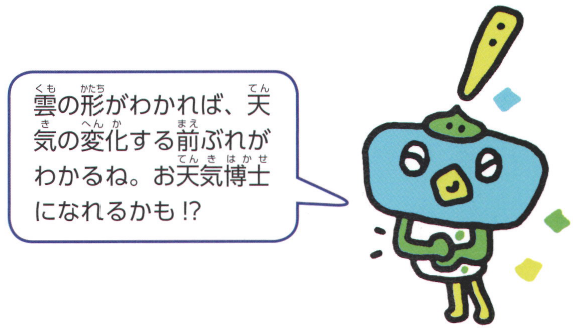
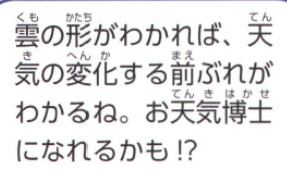
224
天気予報はどうやってするの?
 世界中のいろいろなデータをあつめて予報します
世界中のいろいろなデータをあつめて予報します
 天気予報は、日本だけでなく世界中で観測された気象のデータをもとにつくられています。宇宙にある気象衛星で雲のようすをみたり、日本各地にある気象観測所からおくられてくるデータをもちいたり、風のむきや風の速さをしらべるために特別な風船を空にとばしたりします。
天気予報は、日本だけでなく世界中で観測された気象のデータをもとにつくられています。宇宙にある気象衛星で雲のようすをみたり、日本各地にある気象観測所からおくられてくるデータをもちいたり、風のむきや風の速さをしらべるために特別な風船を空にとばしたりします。
それらの情報は気象庁のスーパーコンピュータにあつめられ、気象がどのように変化していくかが計算されます。そうしてできるのが数値予報という細かい図です。
この数値予報をもとに、気象予報官が天気の予報業務をおこない、気象予報士がテレビや新聞、ラジオなどで予報やその解説をします。
 天気予報が発表されるまでのながれ。
天気予報が発表されるまでのながれ。

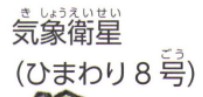
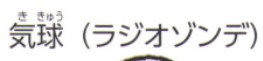

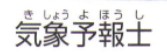
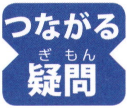 天気予報はどのくらいあたるの?
天気予報はどのくらいあたるの?
 およそ70~80%の確率であたるといわれています
およそ70~80%の確率であたるといわれています
 天気を完璧にあてるのはとてもむずかしいことです。
天気を完璧にあてるのはとてもむずかしいことです。
たとえば、はれときどきくもりの予報を発表したとき、結果がくもりときどきはれになるなど、少しのちがいで判断がむずかしい場合もあるからです。
 そこで気象庁では、1
以上の雨がふるかふらないかという予報にかんして採点をしています。その結果は、2014年17時発表の翌日の予報では全国の平均で84点でした。週間天気予報では3日先の予報が80点、7日先の予報は69点という結果でした。
そこで気象庁では、1
以上の雨がふるかふらないかという予報にかんして採点をしています。その結果は、2014年17時発表の翌日の予報では全国の平均で84点でした。週間天気予報では3日先の予報が80点、7日先の予報は69点という結果でした。
このように、平均するとおよそ70~80%はあたるとかんがえていいでしょう。
気象庁のホームページでは3時間ごとの予報も発表されていますので、より正確な予報をしることができます。
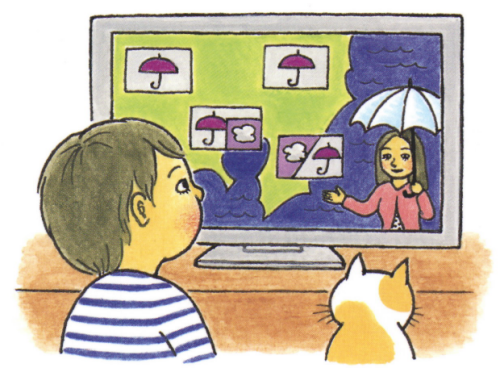
 等圧線
等圧線
同じ気圧の地点をむすんだ線。風は気圧の高いほうから低いほうへふき、線と線の間がせまいほど強くふく。
 気圧
気圧
周囲より気圧の高いところを高気圧、低いところを低気圧という。
| 高…高気圧
| 上空から地表へ下降気流がおこる。
雲ができにくくはれている。
|
|---|
| 低…低気圧
| 地表から上空へ上昇気流がおこる。
雲が発達しやすく天気がわるい。
|
|---|
226
夕立はどうしておこるの?
 強い日ざしによって急速に雨雲ができるため
強い日ざしによって急速に雨雲ができるため
 夕立は先ほどまではれていた空が急にくもって、どしゃぶりの雨がふる現象です。夏の暑い日の午後にふることが多く、名前の由来にもなっています。
夕立は先ほどまではれていた空が急にくもって、どしゃぶりの雨がふる現象です。夏の暑い日の午後にふることが多く、名前の由来にもなっています。
 夏は太陽からの光が強く、地面があたためられます。地面があたためられると水蒸気を多くふくんだ上昇気流がおこり、その結果たくさんの雨をふらせる積乱雲を発生させます。この積乱雲は夕立雲ともよばれ、10
四方くらいの地域にはげしいにわか雨をふらせます。
夏は太陽からの光が強く、地面があたためられます。地面があたためられると水蒸気を多くふくんだ上昇気流がおこり、その結果たくさんの雨をふらせる積乱雲を発生させます。この積乱雲は夕立雲ともよばれ、10
四方くらいの地域にはげしいにわか雨をふらせます。
 夕立がおこる前には、ひんやりとしたつめたい風が強くふいたり、空気がしめっぽくかんじられたりします。大きな積乱雲ができはじめたら、急に雨がふりはじめるので、注意しましょう。
夕立がおこる前には、ひんやりとしたつめたい風が強くふいたり、空気がしめっぽくかんじられたりします。大きな積乱雲ができはじめたら、急に雨がふりはじめるので、注意しましょう。
 夕立が発生するしくみ。
夕立が発生するしくみ。
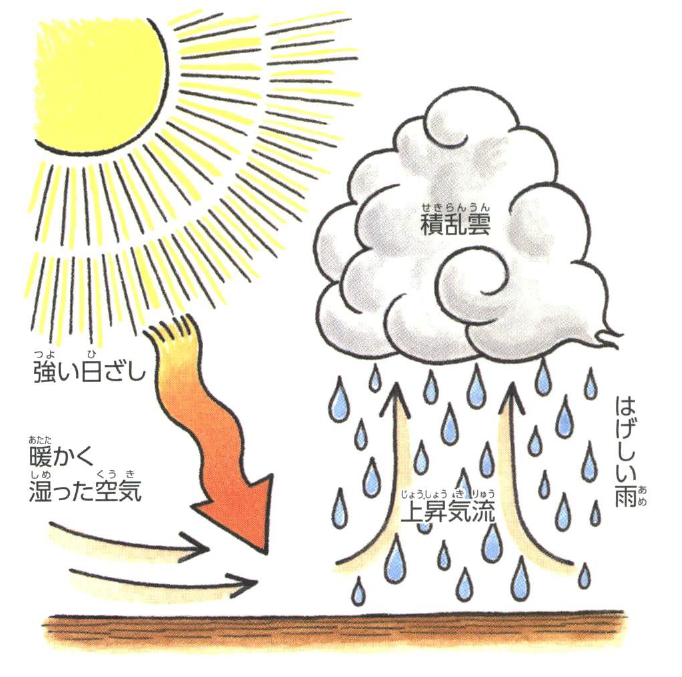
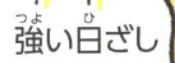
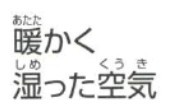
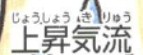
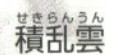

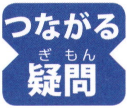 天気雨がふるのはなぜ?
天気雨がふるのはなぜ?
 風で雨がとばされたり、雨雲がきえたりするからです
風で雨がとばされたり、雨雲がきえたりするからです
 空に太陽がさんさんとてっているのに、雨がふってきてびっくりすることがありますね。このような現象に正式な名前はありませんが「天気雨」とよばれます。
空に太陽がさんさんとてっているのに、雨がふってきてびっくりすることがありますね。このような現象に正式な名前はありませんが「天気雨」とよばれます。
 天気雨がおきる原因は3つあるとかんがえられています。1つ目は、雲が雨をふらせたあとその雲がきえてしまう場合です。雨が地面におちるまでには時間がかかります。その間に雲が風にながされるなどして、きえてしまうのです。
天気雨がおきる原因は3つあるとかんがえられています。1つ目は、雲が雨をふらせたあとその雲がきえてしまう場合です。雨が地面におちるまでには時間がかかります。その間に雲が風にながされるなどして、きえてしまうのです。
 2つ目は、小さな雲が雨をふらせる場合です。雨は積乱雲などの大きな雲がふらせるイメージがありますが、ときどきこのような小さな雲が一定の地域に集中して雨をふらせることがあります。
2つ目は、小さな雲が雨をふらせる場合です。雨は積乱雲などの大きな雲がふらせるイメージがありますが、ときどきこのような小さな雲が一定の地域に集中して雨をふらせることがあります。
 3つ目は、雨が風によってとばされてくる場合です。よその雨雲からふった雨が、上空の強い風ではこばれ、はれている場所におちてくるのです。
3つ目は、雨が風によってとばされてくる場合です。よその雨雲からふった雨が、上空の強い風ではこばれ、はれている場所におちてくるのです。
天気雨のふるしくみ
 雨がふったあと雲がなくなる。
雨がふったあと雲がなくなる。
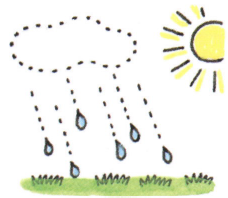
 小さな雲が雨をふらせる。
小さな雲が雨をふらせる。

 風で雨がとばされる。
風で雨がとばされる。

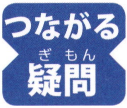 深海にはどんな生き物がいるの?
深海にはどんな生き物がいるの?
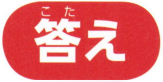 陸上の生物とは見た目も体のつくりもちがう生き物がいます
陸上の生物とは見た目も体のつくりもちがう生き物がいます
 深海は、世界中の海の90%以上をしめています。海は深いほど水圧が高く、太陽の光がとどかないため暗く、温度も低く、酸素もうすくなります。
深海は、世界中の海の90%以上をしめています。海は深いほど水圧が高く、太陽の光がとどかないため暗く、温度も低く、酸素もうすくなります。
そのようなきびしい環境なので、昔は生き物はあまりいないとかんがえられてきました。しかし研究がすすむにつれて実際にはたくさんの生き物がいることがわかり、多く発見されています。
 マリアナ海溝のチャレンジャー海淵で発見されたカイコウオオソコエビは、海底にしずんだ木や植物をこうりつよく分解できる新しい種類のセルラーゼとよばれる酵素をもっており、えさの少ない深海の環境でもくらすことができます。
マリアナ海溝のチャレンジャー海淵で発見されたカイコウオオソコエビは、海底にしずんだ木や植物をこうりつよく分解できる新しい種類のセルラーゼとよばれる酵素をもっており、えさの少ない深海の環境でもくらすことができます。
陸上の生物とはちがう、深海の環境にあう体のつくりをしているのです。
 煮付けなどの料理がおいしいキンメダイも、水深100~800にくらす深海魚。
煮付けなどの料理がおいしいキンメダイも、水深100~800にくらす深海魚。

228
酸性雨って何?
 排気ガスなどの中の成分がとけている雨です
排気ガスなどの中の成分がとけている雨です
 雨は、ふってくる途中で空気中のよごれなどがくっつきます。よごれはほこりやちりだったり、植物の花粉だったりさまざまです。
雨は、ふってくる途中で空気中のよごれなどがくっつきます。よごれはほこりやちりだったり、植物の花粉だったりさまざまです。
 その中でも、工場からでるけむりや、自動車からでる排気ガスの中にふくまれるイオウ酸化物や窒素酸化物などの成分が雨にとけてふってくるのが酸性雨です。
その中でも、工場からでるけむりや、自動車からでる排気ガスの中にふくまれるイオウ酸化物や窒素酸化物などの成分が雨にとけてふってくるのが酸性雨です。
 酸性雨は、川や湖の水質をかえて、生き物のすむ環境にわるい影響をあたえます。
酸性雨は、川や湖の水質をかえて、生き物のすむ環境にわるい影響をあたえます。
原因となる物質が酸性雨となってふってくるまでに数百から数千
を移動することもあります。そこで、世界気象機関(WMO)のもと、ヨーロッパや北アメリカを中心に世界各国およそ200か所で酸性雨の成分の観測がおこなわれるなど、酸性雨に対するとりくみがおこなわれています。
 酸性雨が発生するしくみ。
酸性雨が発生するしくみ。
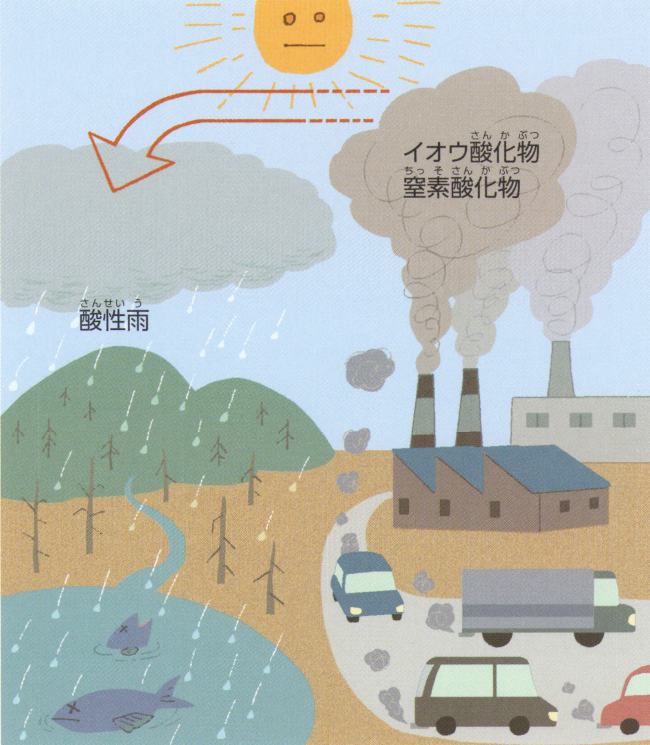
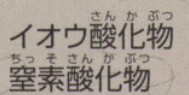
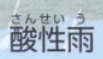
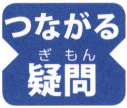 酸性雨でどんなことがおこるの?
酸性雨でどんなことがおこるの?
 森林の木がかれるなどの影響があります
森林の木がかれるなどの影響があります
 酸性雨がふることで、地上ではさまざまな影響があります。
酸性雨がふることで、地上ではさまざまな影響があります。
たとえば、川や湖の水質をかえたり、土の性質を酸性にかえたりして、そこにいる生き物や植物の生態系にも影響をあたえます。
 そのほかにも、金属がさびて変化したり、コンクリートがもろくなったりする原因となる場合もあります。歴史的な建物や彫刻が酸性雨の被害にあうことも少なくありません。
そのほかにも、金属がさびて変化したり、コンクリートがもろくなったりする原因となる場合もあります。歴史的な建物や彫刻が酸性雨の被害にあうことも少なくありません。
 酸性雨の影響でかれた木と、表面がへんかした石像。
酸性雨の影響でかれた木と、表面がへんかした石像。
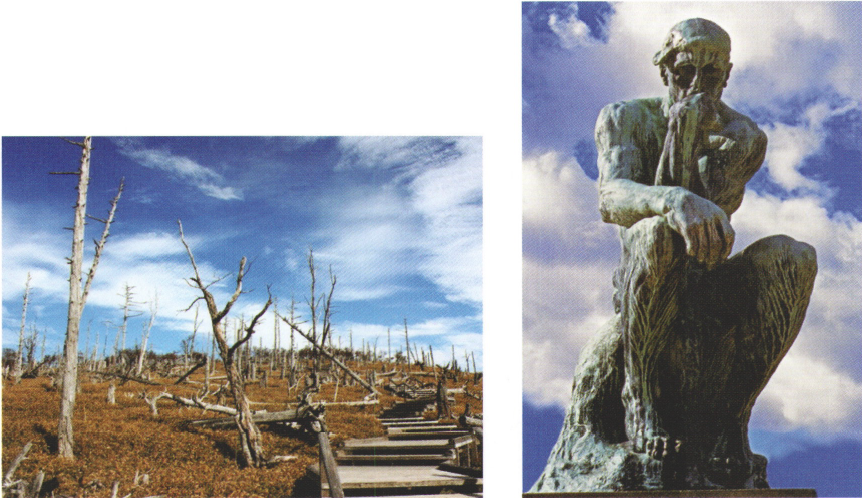
229
台風はどうしてできるの?
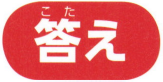 熱帯地方の低気圧が発達すると台風になります
熱帯地方の低気圧が発達すると台風になります
 空気はあたためられるとふくらんで軽くなり、上空へ上がることで上昇気流がおきます。
空気はあたためられるとふくらんで軽くなり、上空へ上がることで上昇気流がおきます。
 太平洋の赤道に近い南の地域は熱帯性のあたたかい気候です。海水の温度が高いため、上昇気流ができやすく低気圧(熱帯低気圧)になります。この熱帯低気圧によってできた積乱雲があつまり、そこにむかって風がふきこむと積乱雲は回転しはじめ、小さな空気のうずになります。これが台風のもとです。
太平洋の赤道に近い南の地域は熱帯性のあたたかい気候です。海水の温度が高いため、上昇気流ができやすく低気圧(熱帯低気圧)になります。この熱帯低気圧によってできた積乱雲があつまり、そこにむかって風がふきこむと積乱雲は回転しはじめ、小さな空気のうずになります。これが台風のもとです。
この後台風のもとはいきおいが弱まると、きえてしまいます。反対にいきおいが強まって大きな空気のうずになり、中心あたりの最大風速が秒速17.2
以上になったものを台風とよびます。
 台風の中心を台風の目とよびます。その直径は20~200とさまざまで、小さくはっきりみえるほど台風のいきおいは強いとされています。
台風の中心を台風の目とよびます。その直径は20~200とさまざまで、小さくはっきりみえるほど台風のいきおいは強いとされています。
 台風の断面図…台風は下のほうでは反時計回りに、上のほうでは時計回りに回転しながら噴出する。
台風の断面図…台風は下のほうでは反時計回りに、上のほうでは時計回りに回転しながら噴出する。
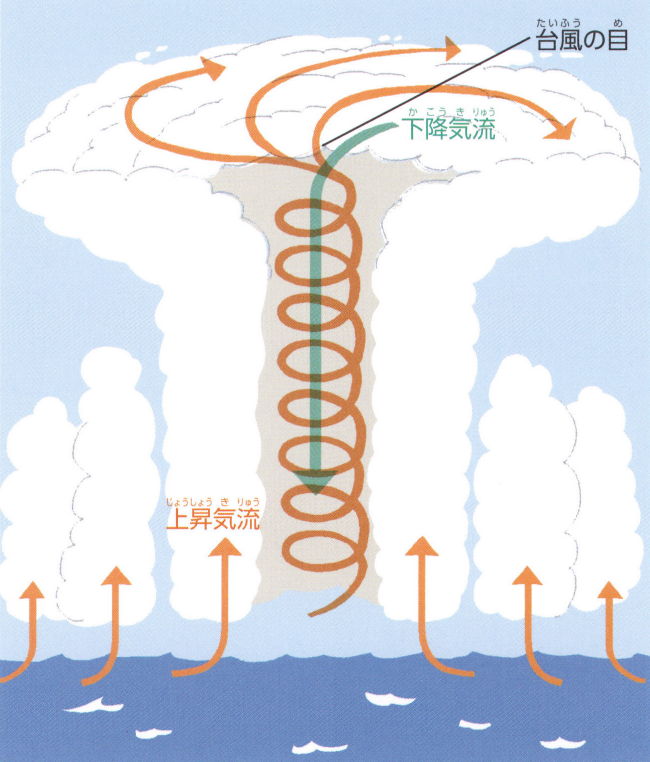

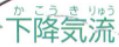
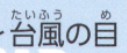
230
春夏秋冬があるのはなぜ?
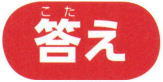 地球の公転と自転が春夏秋冬をうんでいます
地球の公転と自転が春夏秋冬をうんでいます
 地球の運動には、地球自体が1日に1回転する自転と、太陽のまわりを1年間かけて1周する公転があります。
地球の運動には、地球自体が1日に1回転する自転と、太陽のまわりを1年間かけて1周する公転があります。
地球が自転するときの軸は、垂直ではなく約23.4度かたむいています。このかたむきのまま公転することによって、日の長さにさがうまれます。
 夏は北極側が太陽をむくため、日本では昼の時間のほうが長く、太陽の高度も高いため、暑くなります。冬は南極側が太陽をむくので、日本では夜の時間のほうが長く、太陽の高度も低くなり、寒くなります。
夏は北極側が太陽をむくため、日本では昼の時間のほうが長く、太陽の高度も高いため、暑くなります。冬は南極側が太陽をむくので、日本では夜の時間のほうが長く、太陽の高度も低くなり、寒くなります。
春と秋はちょうど昼夜の時間が同じような長さになるので、寒暖のさも少ないすごしやすい季節になります。
 このように地球の自転と公転の組み合わせによって、季節の変化がうまれているのです。
このように地球の自転と公転の組み合わせによって、季節の変化がうまれているのです。
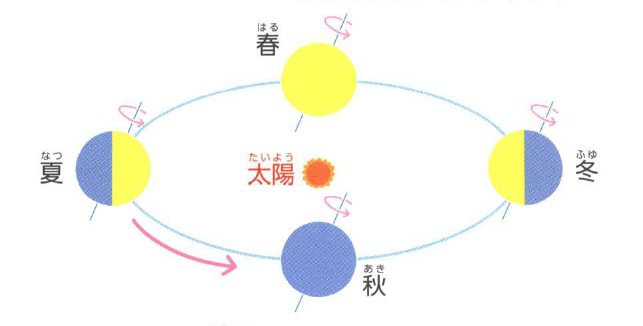





 夏の太陽
夏の太陽
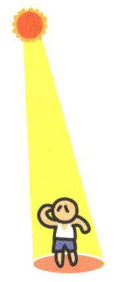
高度が高く、昼間の時間が長くなるので、暑い。
 冬の太陽
冬の太陽

高度が低く、昼間の時間が短くなるので、寒い。
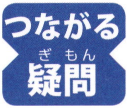 世界でも季節のうつりかわりは同じなの?
世界でも季節のうつりかわりは同じなの?
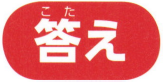 北半球と南半球では、春夏秋冬が反対になります
北半球と南半球では、春夏秋冬が反対になります
 地球は赤道を境に北を北半球、南を南半球とよびます。地球の軸がかたむいていることによって、北半球と南半球の春夏秋冬のうつりかわりもちがいます。
地球は赤道を境に北を北半球、南を南半球とよびます。地球の軸がかたむいていることによって、北半球と南半球の春夏秋冬のうつりかわりもちがいます。
北半球に太陽の光が上のほうからあたる夏の季節は、南半球は太陽の高度が低く冬になります。反対に、南半球が夏のときは、北半球は太陽の高度が低く冬になります。
 日本は北半球にあります。日本では寒い冬のイベントとしてもりあがるクリスマスですが、南半球のオーストラリアなどでは、真夏にあたります。そのため、サンタクロースがサーフィンや水上ボートでやってくるなど、日本とはちがったクリスマスがたのしめます。
日本は北半球にあります。日本では寒い冬のイベントとしてもりあがるクリスマスですが、南半球のオーストラリアなどでは、真夏にあたります。そのため、サンタクロースがサーフィンや水上ボートでやってくるなど、日本とはちがったクリスマスがたのしめます。
 北半球と南半球では季節が反対になりますが、赤道に近い地域では昼と夜の長さが1年をとおしてあまりかわりません。そのため季節の変化もほとんどなく、1年中夏のような日がつづきます。
北半球と南半球では季節が反対になりますが、赤道に近い地域では昼と夜の長さが1年をとおしてあまりかわりません。そのため季節の変化もほとんどなく、1年中夏のような日がつづきます。
 日本が冬のとき、オーストラリアは夏。
日本が冬のとき、オーストラリアは夏。
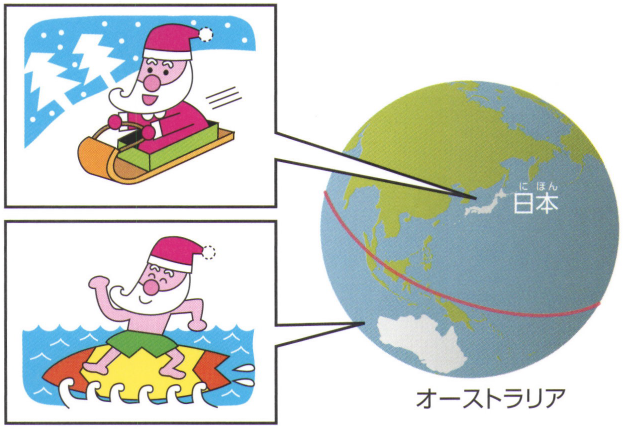


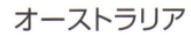

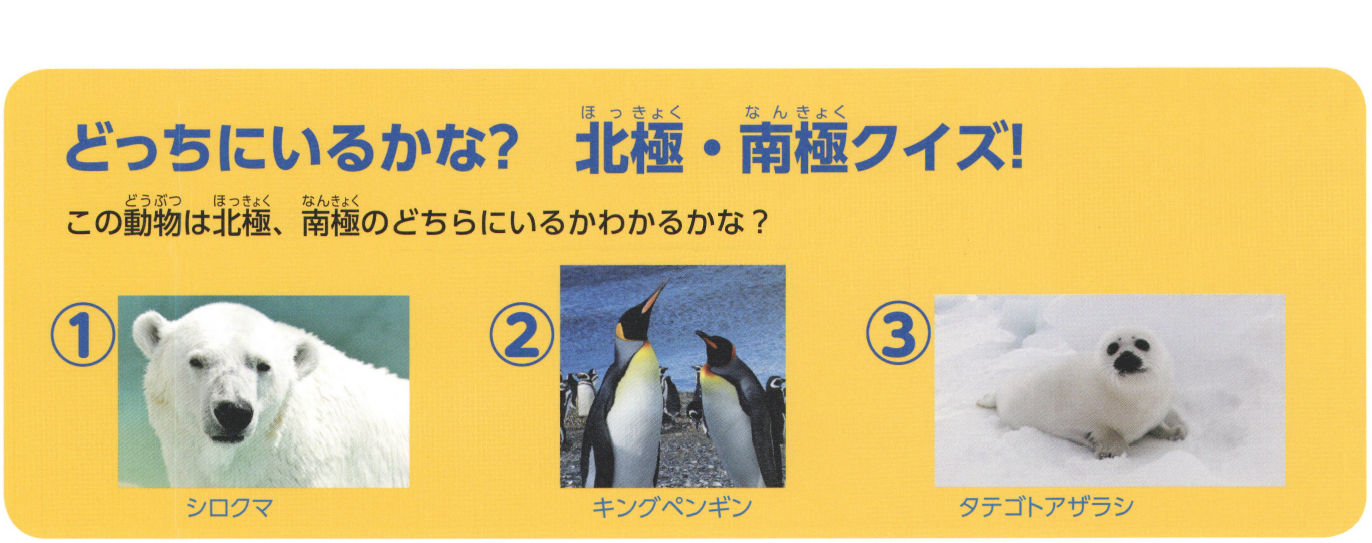

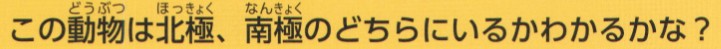
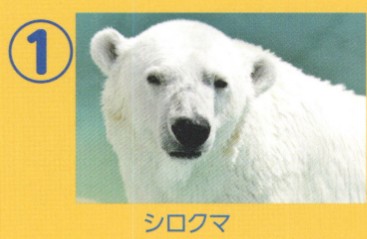
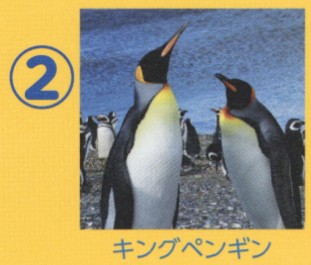
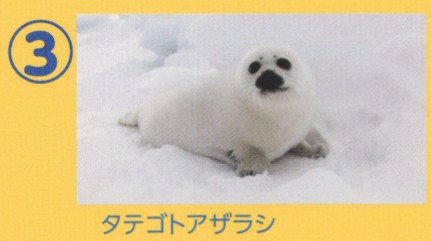

①北極
②南極
③北極
232
地球の温暖化って何?
 地球全体の気温が高くなってしまうことです
地球全体の気温が高くなってしまうことです
 地球のまわりの空気には、二酸化炭素、フロンやメタンといったガスがふくまれています。これを温室効果ガスといいます。
地球のまわりの空気には、二酸化炭素、フロンやメタンといったガスがふくまれています。これを温室効果ガスといいます。
温室効果ガスは、太陽の光はとおしますが、太陽によってあたためられた地表の熱(赤外線)を吸収する性質があります。温室効果ガスは、適度にたもたれれば地球全体の気温もあがることはありません。しかし、温室効果ガスの量がふえることによって、太陽からの熱が地球の外へ放出されにくくなり、余分な熱が地球にこもってしまいます。
このこもった熱が地球全体の気温を少しずつ上昇させていると考えられる現象が温暖化です。
 温室効果ガスの主な原因となる二酸化炭素は、工場や自動車からでる排気ガスなどにふくまれ、電気やガソリンなどを利用することによってうみだされたということもできます。
温室効果ガスの主な原因となる二酸化炭素は、工場や自動車からでる排気ガスなどにふくまれ、電気やガソリンなどを利用することによってうみだされたということもできます。
 また、植物は二酸化炭素を吸収し、酸素をつくりだすはたらきをもっていますが、世界的に森林の破壊がすすんでいることも、二酸化炭素のふえる原因とかんがえられています。
また、植物は二酸化炭素を吸収し、酸素をつくりだすはたらきをもっていますが、世界的に森林の破壊がすすんでいることも、二酸化炭素のふえる原因とかんがえられています。
 昔の地球。
昔の地球。
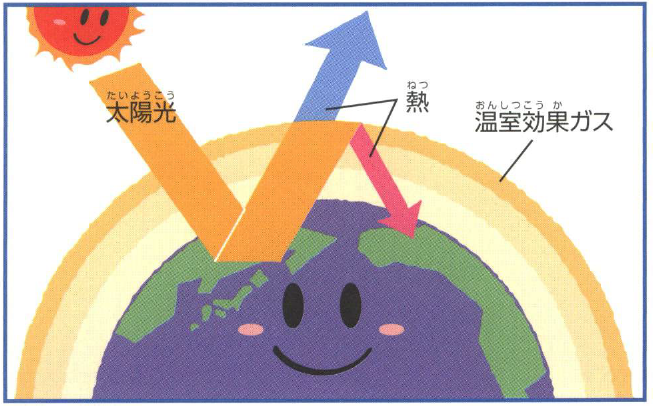
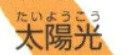

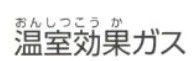

 現在の地球。
現在の地球。
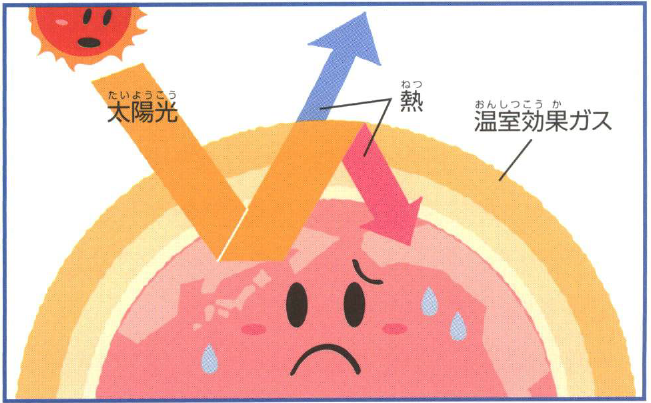
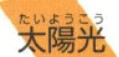

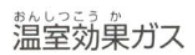
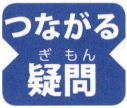 温暖化がつづくとどうなるの?
温暖化がつづくとどうなるの?
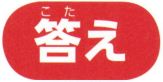 異常気象が発生しやすくなるなどの影響があります
異常気象が発生しやすくなるなどの影響があります
 温暖化によって地球全体の気温があがってしまうと、世界中でさまざまな影響があるとかんがえられています。
温暖化によって地球全体の気温があがってしまうと、世界中でさまざまな影響があるとかんがえられています。
たとえば、かんばつによる水不足がおきたり、野生生物のくらす自然がうしなわれたり、異常気象によって高潮や洪水がおきたりするなどの予測もあります。
そこで、2015年にフランスでおこなわれた地球温暖化問題の対策会議では、世界の196か国全体で気温上昇が1.5℃未満になるよう努力するという目標をきめました。

233
化石はどうやってできるの?
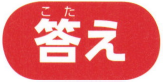 大昔の生き物などが土にうまりそのままのこされてできます
大昔の生き物などが土にうまりそのままのこされてできます
 化石とは、大昔の生き物が死んですなやどろの中にうまり、ほぞんされたものをいいます。多くの学者はおよそ1万年前よりも古い生物の死体について化石とよぶようです。
化石とは、大昔の生き物が死んですなやどろの中にうまり、ほぞんされたものをいいます。多くの学者はおよそ1万年前よりも古い生物の死体について化石とよぶようです。
 化石の多くはほねなどがみつかります。生き物にはやわらかいところとかたいところがあり、死んだ生き物のやわらかい部分はほかの生き物にたべられたり、微生物などによって分解されたりしてしまいます。ほねやかいなどはかたくのこりやすいので、化石になりやすいのです。
化石の多くはほねなどがみつかります。生き物にはやわらかいところとかたいところがあり、死んだ生き物のやわらかい部分はほかの生き物にたべられたり、微生物などによって分解されたりしてしまいます。ほねやかいなどはかたくのこりやすいので、化石になりやすいのです。
化石はすなやどろの地層の中にうまっていますが、発掘調査によって地層がほりおこされたり、自然に地層がけずられたり、くずれたりしてあらわれます。
 つみかさなった地層から、どの時代のものかをしらべれば、発見した化石の生き物がくらしていた環境もわかるというわけです。
つみかさなった地層から、どの時代のものかをしらべれば、発見した化石の生き物がくらしていた環境もわかるというわけです。
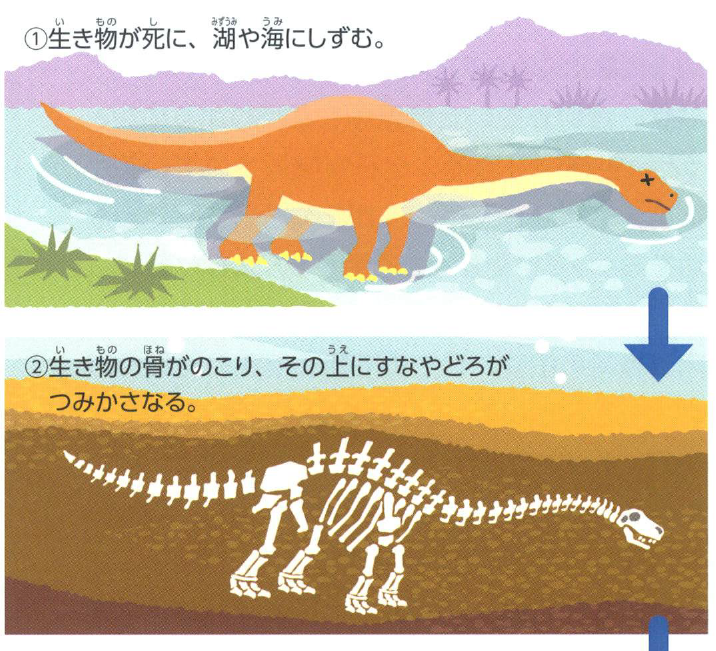

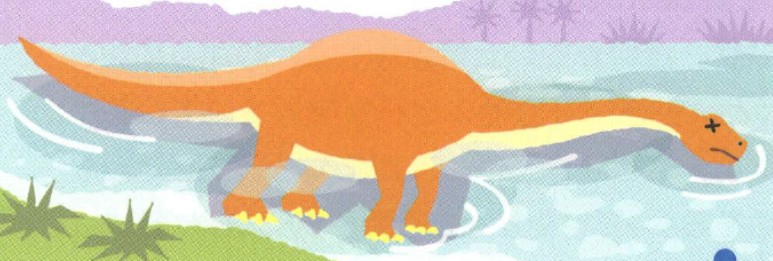
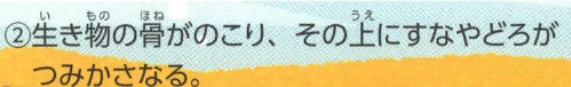
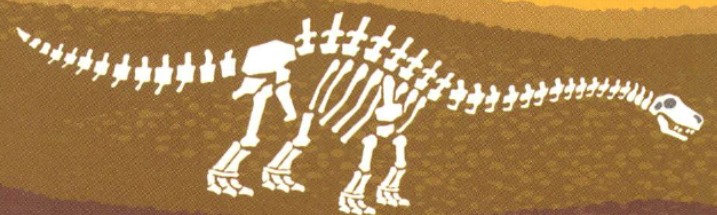
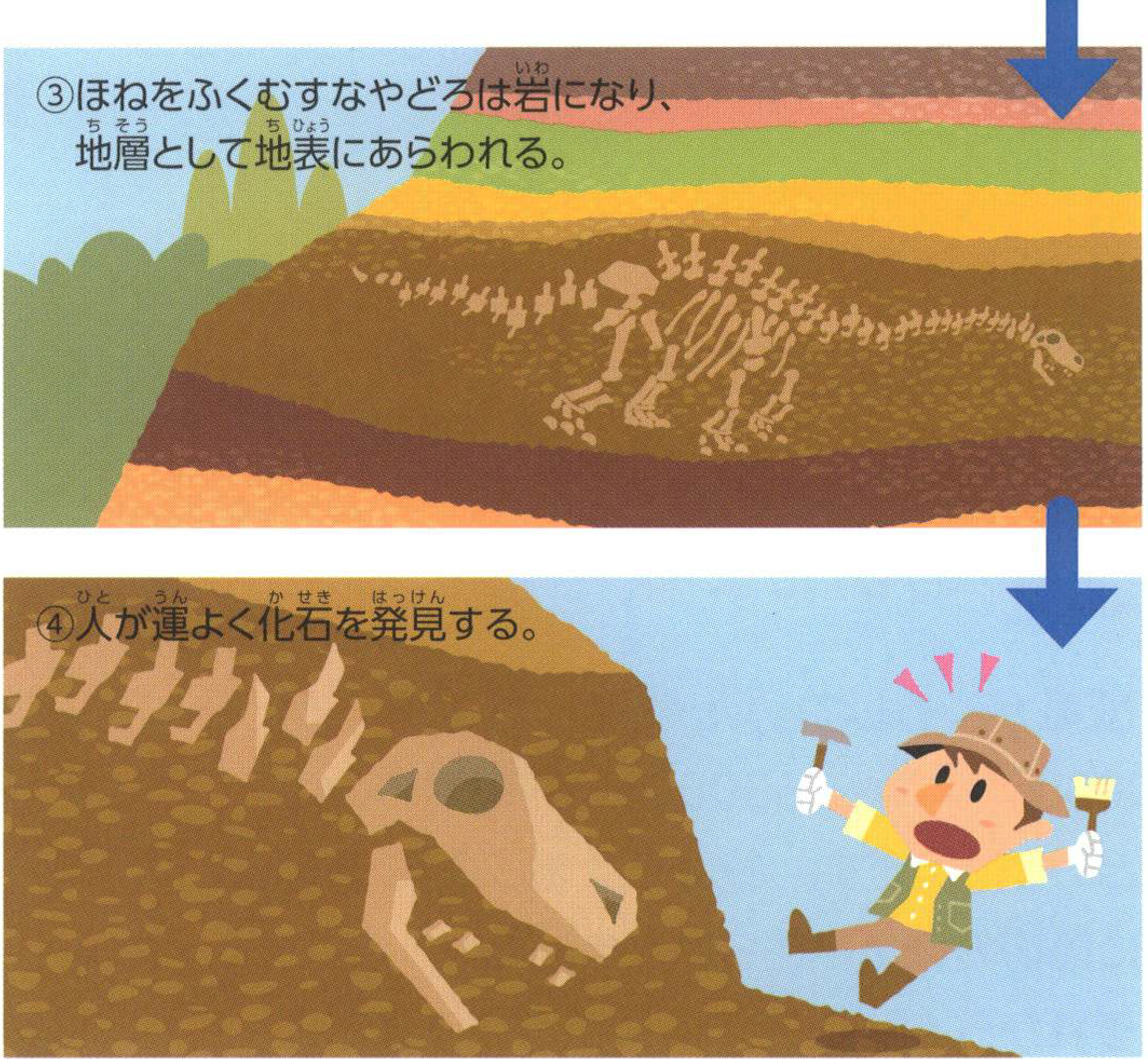
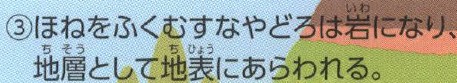
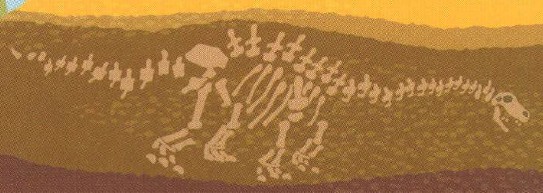
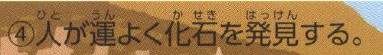

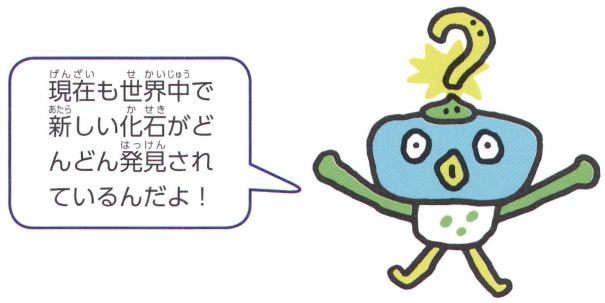
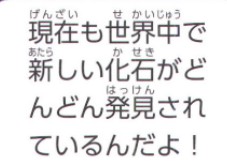
建物の素材としてもつかわれる大理石という種類の石に、生き物の化石がはいりこんでいる場合があります。百貨店など、大理石が多くつかわれている建物でみつけることができます。
 大理石にうまったアンモナイトの化石。
大理石にうまったアンモナイトの化石。

234
恐竜って本当にいたの?
 世界中で恐竜の化石が発見されています
世界中で恐竜の化石が発見されています
 今からおよそ2億5000万年~6500万年前、地球上にはたくさんの恐竜がくらしていました。
今からおよそ2億5000万年~6500万年前、地球上にはたくさんの恐竜がくらしていました。
なぜ、昔いきていた恐竜のことがわかるのかというと、世界中で恐竜の化石が発見されているからです。化石は、恐竜のすがたや形、どのような生活をおくっていたかをしる手がかりになります。
 歯の化石ひとつとっても、ティラノサウルスなどの肉食恐竜の歯は、えものであるほかの恐竜の肉をくいちぎるために、するどくとがっています。
歯の化石ひとつとっても、ティラノサウルスなどの肉食恐竜の歯は、えものであるほかの恐竜の肉をくいちぎるために、するどくとがっています。
一方、トリケラトプスなどの草食恐竜は、植物をたべるために細かい歯をもちます。このように、化石からたべていたものまでわかるのです。
 日本でもたくさんの恐竜の化石が発見されており、昔は日本にも恐竜がくらしていたことがわかっています。
日本でもたくさんの恐竜の化石が発見されており、昔は日本にも恐竜がくらしていたことがわかっています。
 発掘された恐竜の化石は、博物館などでみることができる。
発掘された恐竜の化石は、博物館などでみることができる。

235
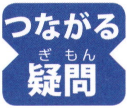 恐竜の名前はどうやってつけているの?
恐竜の名前はどうやってつけているの?
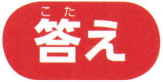 恐竜の特徴などをもとに名前がつけられています
恐竜の特徴などをもとに名前がつけられています
 生き物や植物には学名という名前がつけられます。学名は、生物の特徴をあらわしていて、ほかのどのような生物のなかまとするかがわかるようになっています。また、世界中の研究者や学者が共通でつかえるようにラテン語がつかわれています。恐竜も同じように名前がつけられます。
生き物や植物には学名という名前がつけられます。学名は、生物の特徴をあらわしていて、ほかのどのような生物のなかまとするかがわかるようになっています。また、世界中の研究者や学者が共通でつかえるようにラテン語がつかわれています。恐竜も同じように名前がつけられます。
たとえば、肉食恐竜の王者といわれるティラノサウルスは、ティラノ(あばれんぼう)とサウルス(とかげ)がくっついた名前です。
 多くの恐竜の名前にサウルスがつくのは、恐竜の祖先がとかげなどのは虫類だからです。
多くの恐竜の名前にサウルスがつくのは、恐竜の祖先がとかげなどのは虫類だからです。
ステゴサウルスは、背中にある板のようなほねが特徴です。名前もその見た目にあわせてステゴサウルス(屋根とかげ)とつけられています。
 ティラノサウルス(あばれんぼうとかげ)
ティラノサウルス(あばれんぼうとかげ)
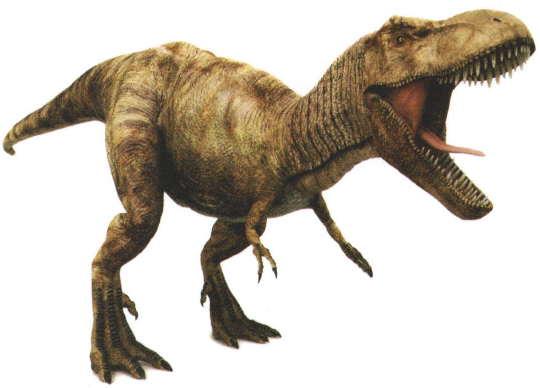
 ステゴサウルス(屋根とかげ)
ステゴサウルス(屋根とかげ)

 ブラキオサウルス(うでとかげ)
ブラキオサウルス(うでとかげ)
後ろあしより前あしのほうが長いことから名前がついた。

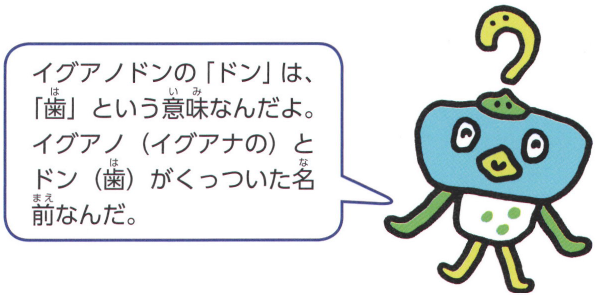
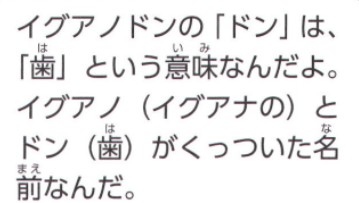
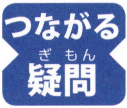 恐竜はどうしてほろびたの?
恐竜はどうしてほろびたの?
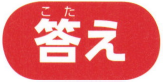 いん石の落下や火山の噴火など、さまぎまな説があります
いん石の落下や火山の噴火など、さまぎまな説があります
 恐竜は数10ほどの小さなものから、数10にもなる大きなものまで、さまざまな種類がいました。しかし、恐竜は絶滅してしまい現在はみることができません。
恐竜は数10ほどの小さなものから、数10にもなる大きなものまで、さまざまな種類がいました。しかし、恐竜は絶滅してしまい現在はみることができません。
 恐竜が絶滅した原因にはいくつかの説があります。地球に大きないん石が落下したという説や、火山が爆発したという説、急激に気候が変化して寒さにたえられなかったなどの説もありますが、はっきりとした絶滅の理由はわかっていません。
恐竜が絶滅した原因にはいくつかの説があります。地球に大きないん石が落下したという説や、火山が爆発したという説、急激に気候が変化して寒さにたえられなかったなどの説もありますが、はっきりとした絶滅の理由はわかっていません。
恐竜は絶滅しましたが、その後ほ乳類や鳥類、は虫類などの生きのこったものは、進化をかさね今につづいています。また、鳥類は、恐竜の進化したものであるといわれています。
 大きないん石が地球に落下し、恐竜が絶滅したという説もある。
大きないん石が地球に落下し、恐竜が絶滅したという説もある。

236
天の川って何?
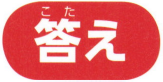 たくさんの星が帯状にひろがり川のようにみえるところです
たくさんの星が帯状にひろがり川のようにみえるところです

 天の川とはその名前のとおり、夜空を横切るかのように星の帯がひろがるところです。
天の川とはその名前のとおり、夜空を横切るかのように星の帯がひろがるところです。
地球は太陽を中心とした太陽系という天体のあつまりの中にあります。太陽はおよそ2000億こもの星があつまったさらに大きな銀河系の中のひとつの星です。
 銀河系は、上からみるとうずをまいているような形をしていますが、横からみると円盤型です。地球から銀河の反対側の方向をみたとき、遠くの星はかさなりあって白いおびのようにみえます。このすがたがまるで星の川のようにみえることから、天の川とよばれます。
銀河系は、上からみるとうずをまいているような形をしていますが、横からみると円盤型です。地球から銀河の反対側の方向をみたとき、遠くの星はかさなりあって白いおびのようにみえます。このすがたがまるで星の川のようにみえることから、天の川とよばれます。
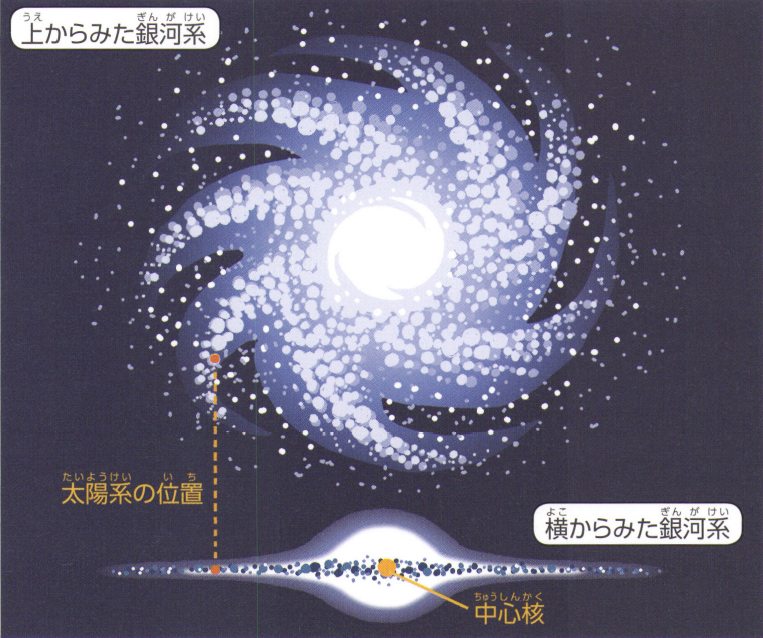
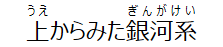
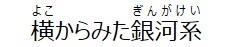
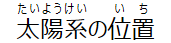
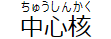
宇宙はいつできたの?
 今から138億年前におきたビッグ・バンによりはじまったとかんがえられています
今から138億年前におきたビッグ・バンによりはじまったとかんがえられています
 宇宙がどうやってできたのかは、まだはっきりとしたことはわかっていません。しかし、地上の大型望遠鏡や宇宙望遠鏡による観測などによって、少しずつ宇宙のことがわかり、推測ができるようになってきました。
宇宙がどうやってできたのかは、まだはっきりとしたことはわかっていません。しかし、地上の大型望遠鏡や宇宙望遠鏡による観測などによって、少しずつ宇宙のことがわかり、推測ができるようになってきました。
 およそ138億年前、宇宙が誕生した直後、ビッグ・バンとよばれる大爆発がおきました。これが現在の宇宙へとつながります。
およそ138億年前、宇宙が誕生した直後、ビッグ・バンとよばれる大爆発がおきました。これが現在の宇宙へとつながります。
ビッグ・バンによってできた水素などから星がうまれ、星のまわりにちりがあつまって惑星ができ、星があつまることで銀河がつくられ、やがて今の宇宙ができあがったとかんがえられています。
 現在も宇宙はひろがりつづけていて、このまま永遠にひろがりつづけるのか、ある時点でとまったり変化するかなどは、結論はいまだにわかっていませんが、どんどんひろがりかたが加速しているという結果がでています。
現在も宇宙はひろがりつづけていて、このまま永遠にひろがりつづけるのか、ある時点でとまったり変化するかなどは、結論はいまだにわかっていませんが、どんどんひろがりかたが加速しているという結果がでています。
 ビッグ・バンのあと、宇宙はひろがりつづけている。
ビッグ・バンのあと、宇宙はひろがりつづけている。
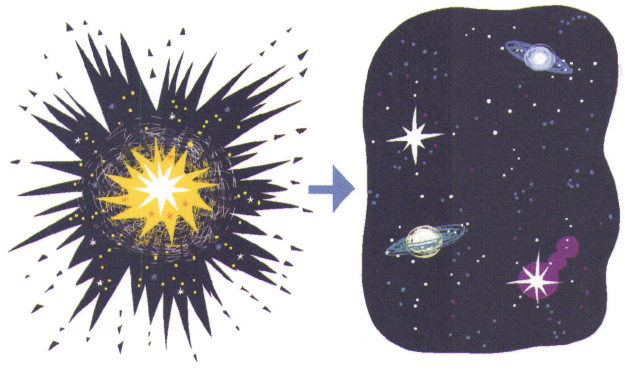
237
ブラックホールって何?
 光さえもすいこんでしまう重力のとても強い天体のこと
光さえもすいこんでしまう重力のとても強い天体のこと
 星には重いものと軽いものがあります。重い星は寿命をむかえるとばくはつをおこし、中心部分は重力の強い天体へと変化し、近づくものは何でもすいこんでしまうブラックホールになることがあります。光さえもでていくことができないため、ブラックホールをみることはできません。ブラックホールのブラックは、ブラックホール自体が黒い色をしているというわけではなく、目にみえないことをたとえてつけられているのです。
星には重いものと軽いものがあります。重い星は寿命をむかえるとばくはつをおこし、中心部分は重力の強い天体へと変化し、近づくものは何でもすいこんでしまうブラックホールになることがあります。光さえもでていくことができないため、ブラックホールをみることはできません。ブラックホールのブラックは、ブラックホール自体が黒い色をしているというわけではなく、目にみえないことをたとえてつけられているのです。
しかし、ブラックホールの中に物質がすいこまれるときにでるX線や強い電波などを観測することによって、ブラックホールのことがわかります。
ブラックホールにすいこまれたものは、中心にむかっておち、顕微鏡でもみえないほど小さくばらばらにされてしまうという考えかたがあります。
 夏の星座を代表する白鳥座の中のX‐1という星は、ブラックホールであるといわれています。
夏の星座を代表する白鳥座の中のX‐1という星は、ブラックホールであるといわれています。
 ブラックホールのイメージ。すいこまれたものはでられないとかんがえられている。
ブラックホールのイメージ。すいこまれたものはでられないとかんがえられている。

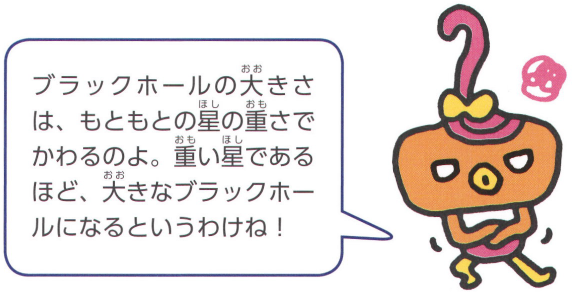
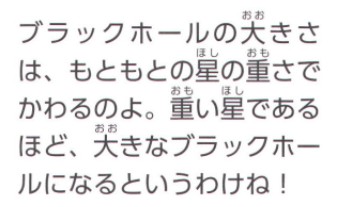
宇宙人はいるの?
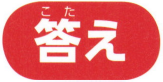 今のところ、宇宙人がいるかどうかはわかっていません
今のところ、宇宙人がいるかどうかはわかっていません
 わたしたちのくらす太陽系には、地球以外に惑星や衛星があります。しかし、地球のように生物のくらしやすい環境の天体はないとかんがえられています。
わたしたちのくらす太陽系には、地球以外に惑星や衛星があります。しかし、地球のように生物のくらしやすい環境の天体はないとかんがえられています。
宇宙探査の技術が進歩していてもそのしらべられる範囲はほんのわずかで、広大な宇宙にはまだまだわからないことがたくさんあります。太陽系の天体では宇宙人はいないとかんがえられていますが、宇宙には太陽系以外にも多くの天体があり、もしかすると未来は宇宙人がいる天体がみつかるかもしれません。
 NASA(アメリカ航空宇宙局)は、1972~73年にうちあげた惑星探査機パイオニア10号と11号に、人類や太陽系をえがいた金属板を、地球外生命へのメッセージとして機体にとりつけました。
NASA(アメリカ航空宇宙局)は、1972~73年にうちあげた惑星探査機パイオニア10号と11号に、人類や太陽系をえがいた金属板を、地球外生命へのメッセージとして機体にとりつけました。
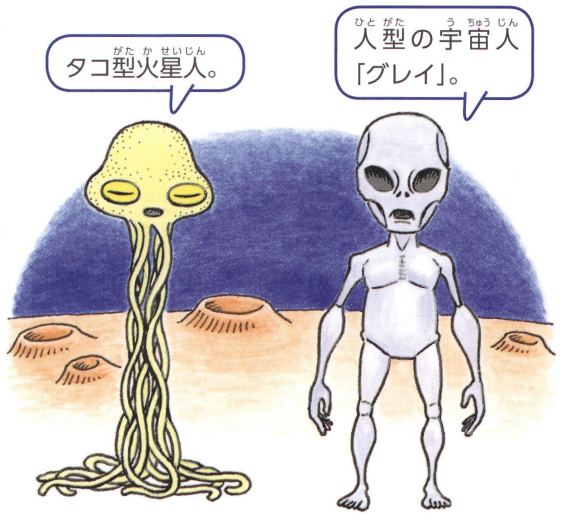

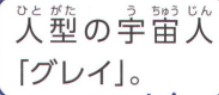
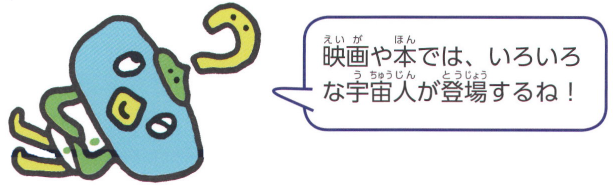
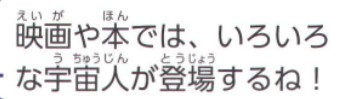
238
しんきろうはどうしてできるの?
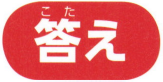 温度のちがう空気の層で光がまげられるから
温度のちがう空気の層で光がまげられるから
 しんきろうとは、水平線あたりの遠くの景色が空中にういてみえたり、上下にのびてみえる現象です。しんきろうは、光と空気のぐうぜんのくみあわせでおきます。
しんきろうとは、水平線あたりの遠くの景色が空中にういてみえたり、上下にのびてみえる現象です。しんきろうは、光と空気のぐうぜんのくみあわせでおきます。
 空気の温度が高い層と低い層がある時、そのさかい目で光がまがることでしんきろうがおきるのです。
空気の温度が高い層と低い層がある時、そのさかい目で光がまがることでしんきろうがおきるのです。
 しんきろうには2つの種類があります。1つ目は上位しんきろうといって、空気の層の下がつめたく上があたたかいときにできます。実物の上に、ひっくりかえったしんきろうがみえるため、長くのびたようにみえます。
しんきろうには2つの種類があります。1つ目は上位しんきろうといって、空気の層の下がつめたく上があたたかいときにできます。実物の上に、ひっくりかえったしんきろうがみえるため、長くのびたようにみえます。
2つ目は下位しんきろうといって、空気の層の下があたたかく上がつめたいときにできます。実物の下にひっくりかえったしんきろうができることで、遠くのものが下にむかってのびたり、空中にういたように見えます。
 上位しんきろうのみえ方。
上位しんきろうのみえ方。
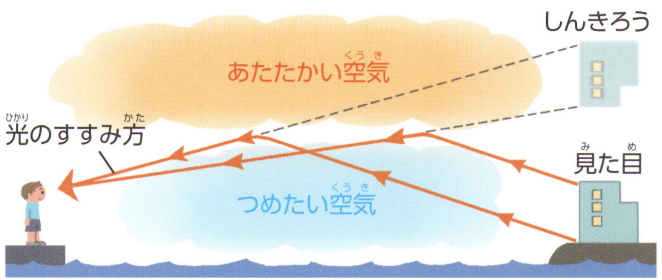
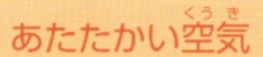
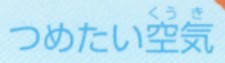
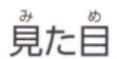
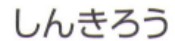
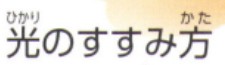
 上位しんきろうのようす。海の上にういたようにみえる。
上位しんきろうのようす。海の上にういたようにみえる。

 下位しんきろうのみえ方。
下位しんきろうのみえ方。
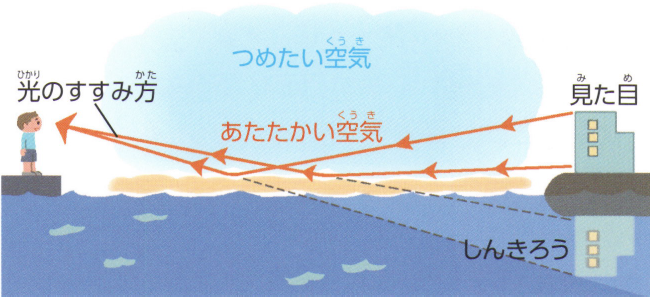
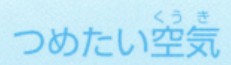
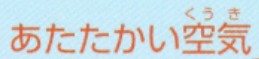
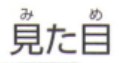
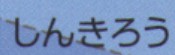
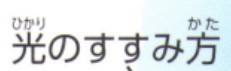
うずしおって何?
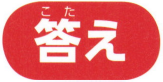 海水がうずをまいてながれることです
海水がうずをまいてながれることです
 うずしおは、潮のみち引きによるはげしい潮流がひきおこす、うずをまく水の流れです。日本では瀬戸内海の鳴門のうずしおが有名です。
うずしおは、潮のみち引きによるはげしい潮流がひきおこす、うずをまく水の流れです。日本では瀬戸内海の鳴門のうずしおが有名です。
鳴門海峡は、イタリアのメッシーナ海峡、カナダのセイモア海峡にならぶ世界三大潮流のひとつで、潮流の速さは最大で時速20ほどにもなります。
鳴門海峡は、はばが1.3とせまくなっているため、外へと一気に海水がながれだし、潮の速いながれとおそいながれがうまれます。それらがぶつかることでうずができるのです。
 とくに、1か月に2回、満月と新月のときに潮のみちひきのさが最大になる大潮をむかえると、迫力のあるうずしおがみられます。
とくに、1か月に2回、満月と新月のときに潮のみちひきのさが最大になる大潮をむかえると、迫力のあるうずしおがみられます。

 鳴門海峡のうずしおの流れ。
鳴門海峡のうずしおの流れ。
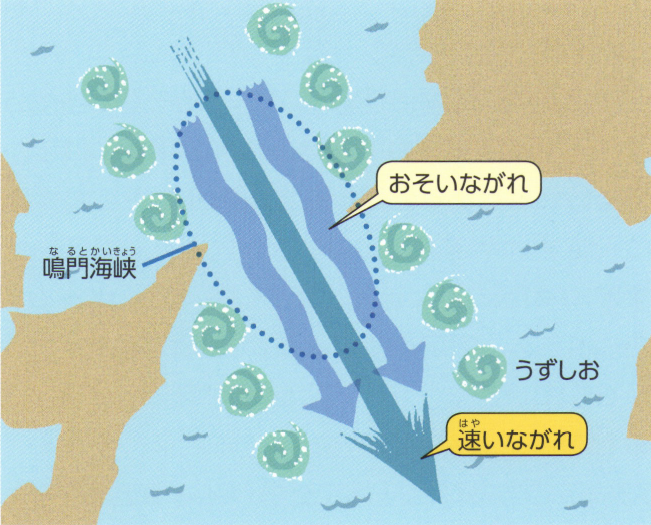
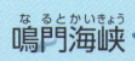
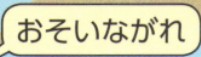
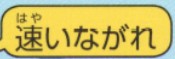
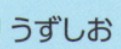
239
海の水はどうしてしおからいの?
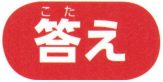 塩のもとになる成分が海の水にとけこんでいるから
塩のもとになる成分が海の水にとけこんでいるから
 海水にはさまざまな成分がとけこんでいますが、その85%をしめるのが塩素とナトリウムという成分です。この2つがむすびつくと、塩の主成分(塩化ナトリウム)になります。
海水にはさまざまな成分がとけこんでいますが、その85%をしめるのが塩素とナトリウムという成分です。この2つがむすびつくと、塩の主成分(塩化ナトリウム)になります。
 およそ46億年前に地球が誕生したとき、小天体の衝突によって高温になりました。しばらくすると空気中の水蒸気はひえて雨になって、地上にふりそそぎ、陸地の低いところへどんどんたまっていきました。これが海の始まりです。
およそ46億年前に地球が誕生したとき、小天体の衝突によって高温になりました。しばらくすると空気中の水蒸気はひえて雨になって、地上にふりそそぎ、陸地の低いところへどんどんたまっていきました。これが海の始まりです。
火山ガスの中の塩酸ガスが雨にふくまれていたため、岩石の中のナトリウムがとけだしました。水の中で塩素とナトリウムがむすびつき、しおからい海の水ができあがったのです。
 地球全体の海水にとけている塩のりょうは3万4700兆
。地球全体をその塩でおおうと、東京タワーが半分くらいまでうまります。
地球全体の海水にとけている塩のりょうは3万4700兆
。地球全体をその塩でおおうと、東京タワーが半分くらいまでうまります。
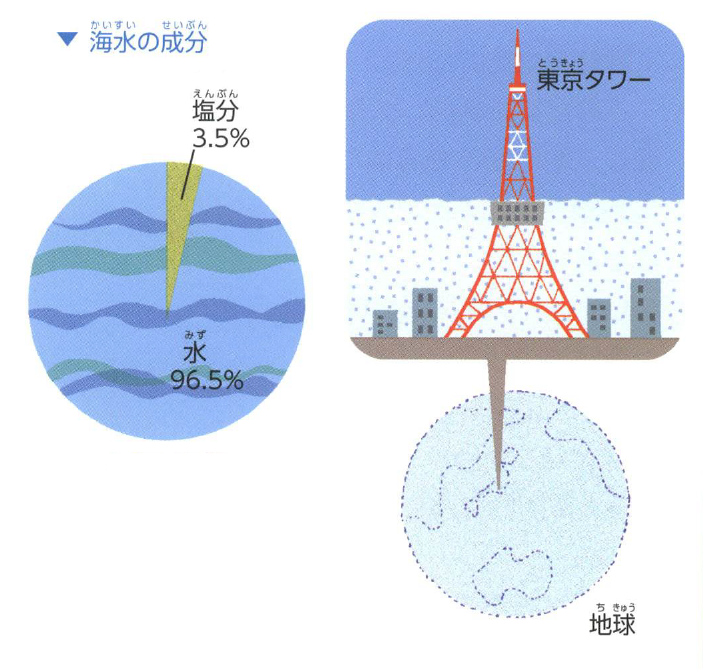

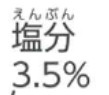
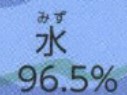

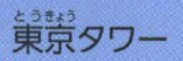
240
オゾン層って何?
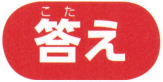 太陽からの有害な紫外線から地球をまもる空気の層です
太陽からの有害な紫外線から地球をまもる空気の層です
 地球をおおう空気は、高さによっていくつかの層にわかれています。地上からおよそ10~50の成層圏では、オゾンという物質が層になって地球全体をおおっています。
地球をおおう空気は、高さによっていくつかの層にわかれています。地上からおよそ10~50の成層圏では、オゾンという物質が層になって地球全体をおおっています。
このオゾン層は、太陽からの有害な紫外線を吸収し、地球をまもるはたらきがあります。有害な紫外線がふえると、人体や自然へのさまざまな影響があります。
 しかし、フロンなどの化学物質によってこのオゾン層が減少しています。フロンは自然界には存在しない人工的な物質で、冷暖房器具や冷蔵庫、工場などでつかわれてきました。フロンが上空にのぼると成層圏に達し、オゾン層をこわしてしまうのです。
しかし、フロンなどの化学物質によってこのオゾン層が減少しています。フロンは自然界には存在しない人工的な物質で、冷暖房器具や冷蔵庫、工場などでつかわれてきました。フロンが上空にのぼると成層圏に達し、オゾン層をこわしてしまうのです。
オゾン層が1%こわれると有害な紫外線がおよそ2%増加するといわれており、北極や南極では、オゾン層に穴のあく「オゾンホール」という現象がおきています。
 このオゾンホールがひろがったり数がふえたりしないためにも、世界中でフロンの使用を禁止したり、使用を規制したりするなどのルールがきめられています。
このオゾンホールがひろがったり数がふえたりしないためにも、世界中でフロンの使用を禁止したり、使用を規制したりするなどのルールがきめられています。
 有害な紫外線から地球を守るオゾン層のやくわり。
有害な紫外線から地球を守るオゾン層のやくわり。

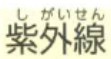
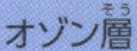
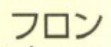
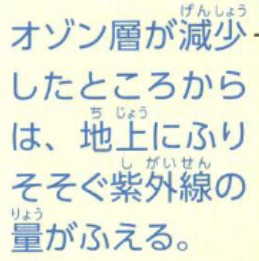
温泉はどうしてわくの?
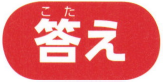 地下にたまった水があたためられて地上にあがってきたり、穴をほってくみあげられたりします
地下にたまった水があたためられて地上にあがってきたり、穴をほってくみあげられたりします
 温泉は、熱い湯がつぎつぎにわきでてきます。温泉は大きくわけて2つあり、どちらも地下にたまった水があたためられたものです。
温泉は、熱い湯がつぎつぎにわきでてきます。温泉は大きくわけて2つあり、どちらも地下にたまった水があたためられたものです。
1つ目は火山性温泉で、火山のマグマだまりの中の熱水や火山ガスの熱によってあたためられた地下水が、断層のすきまからわきでたり、穴をほることでわきでたりしたものです。
2つ目は非火山性温泉で、地熱であたためられた地下水を、地下深くに穴をほってくみあげる温泉です。しかし、どこをほっても温泉がでてくるというわけではなく、地下に豊富な地下水がたくわえられていることが条件です。
温泉を勝手にほることは禁じられていて、許可が必要です。
 火山性温泉のしくみ。
火山性温泉のしくみ。
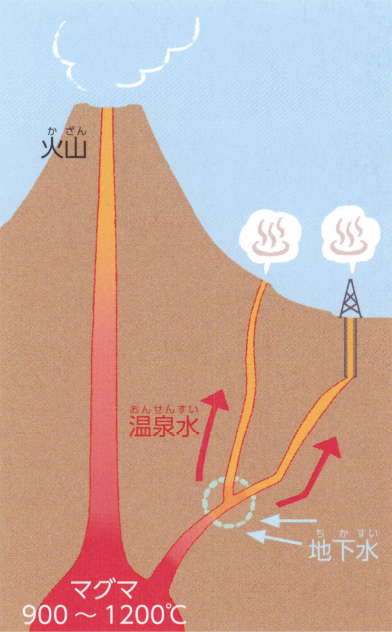

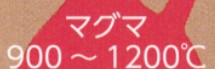

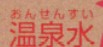

 非火山性温泉のしくみ。
非火山性温泉のしくみ。
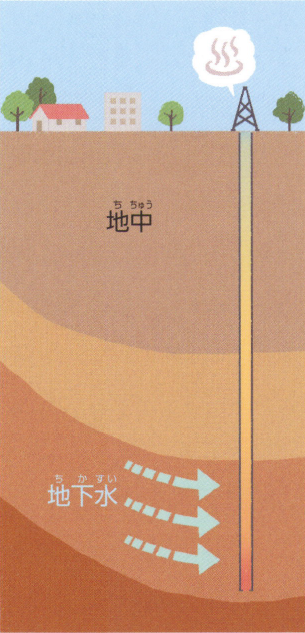

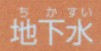

242
科学でつかわれるむずかしい用語を解説しています。
慣性の法則
乗り物にのっているとき、急にはしりだすとすすむ方向とは反対側に体がたおれそうになります。これは「慣性」という力がはたらいているからです。ものは、外から力をくわえられないかぎり、とまっているものは、とまったままでいようとし、うごいているものはうごきつづけようとする性質があります。これが「慣性」です。慣性は、ものが重くなるほど大きくはたらきます。
地球上では、うごいているものはいつかうごきがとまってしまいます。それは、空気におされたり、地面との摩擦がじゃまをしてうごきをとめてしまうからです。
 慣性の法則がよくわかる「だるまおとし」。
慣性の法則がよくわかる「だるまおとし」。

気圧
地球をおおっている空気にも重さがあり、すべてのものを上や横などあらゆる方向からおしています。空気がものをおす力を「気圧」といい、hPa(ヘクトパスカル)という単位であらわします。
気圧は、つみかさなった空気の量によってかわるので、高いところほど低くなります。また、場所や時間によってもかわります。
新聞やテレビの天気予報でみる天気図には、円やまがりくねった線がかかれています。これは「等圧線」といって、同じ気圧の地点をむすんだものです。
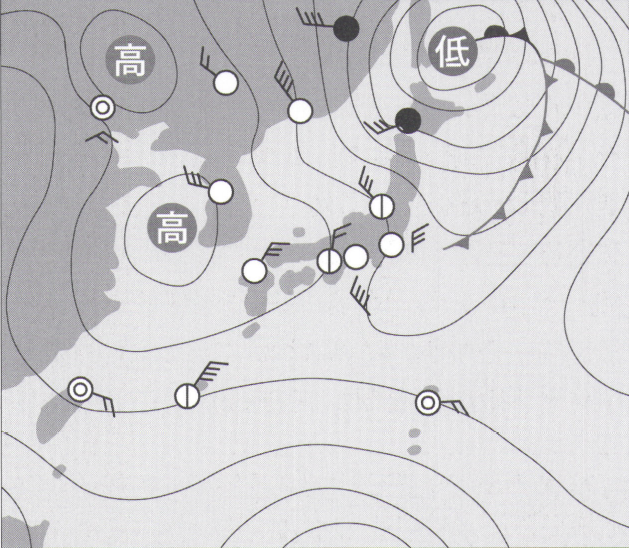
屈折
光は、空気や水、ガラスなどすきとおったものの中ではまっすぐにすすみます。しかし、空気と水、水とガラスといったように、ちがう物質にまたがってすすむときは、そのさかい目でまがる性質があります。これを「光の屈折」といいます。
水のはいったコップにストローをさすと、ストローがおれたようにまがってみえます。これは、水の中と外からでは光のすすむ角度がかわって、わたしたちの目にはいってくるからです。
また、同じ空気でも温度のちがう空気の間では屈折がおこります。それがしんきろうをつくりだすのです。
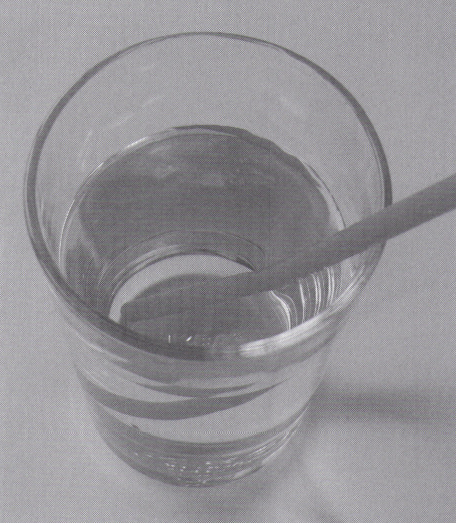
243
鉱物
道ばたにおちている石を虫めがねで拡大してみると、小さなつぶがたくさんならんでいるのがわかります。このつぶは「鉱物」とよばれる小さな結晶です。たとえば、ビルや墓石につかわれる「花こう岩」という石は、「石英」や「長石」、「雲母」などの鉱物があつまってできています。
鉱物は4000以上の種類があり、鉱物を多くふくむ岩石を「鉱石」といいます。鉱石からとりだされた鉱物は、わたしたちのくらしにやくだてられています。
 石英。きれいな形に結晶になったものを「水晶」とよぶ。
石英。きれいな形に結晶になったものを「水晶」とよぶ。

細胞
人の体はとても小さな「細胞」があつまってできています。細胞には形や大きさ、はたらきがちがうものがあり、それぞれがあつまって、「組織」をつくります。そして、いくつかの組織があつまって、骨や皮膚、筋肉、内臓などの器官ができます。
人の体をつくっている細胞はなんと60兆こにもなります。ほとんどの細胞には寿命があり、つねに死んだりつくられたりして、新しい細胞にいれかわっています。
人だけでなく、動物や植物などすべての生き物は細胞からできています。また、アメーバやゾウリムシなど、1つの細胞だけでできている生き物もいます。
244
重力
空中でものをおとすと、ものは下におちます。これは、「重力」という力がはたらいているからです。わたしたちがふわふわとうかばずに地面にたっていたり、ものが下におちたりするのは、地球の中心にむかってひっぱる重力がはたらいているからです。ものに重さがあるのも、重力があるからです。
2つのものの間にはかならず、おたがいにひっぱりあう、目にみえない「引力」という力がはたらきます。重力は、地球の引力と、地球の自転による遠心力があわさった力です。ものが大きくなればなるほど、引力が大きくなります。地球はとても大きいので引力も大きいのです。
 ものの重さは重力がつくりだしている。
ものの重さは重力がつくりだしている。

電磁波
電気や磁気がおたがいに影響しあってつくられる波を「電磁波」といいます。電磁波は周波数(1秒間の波の数)によっていくつかの種類にわけられます。周波数をあらわす単位「1Hz(ヘルツ)」は、1秒間に1回振動するという意味です。
目に見える光「可視光線」や、肌を黒くする「紫外線」、リモコンにつかわれる「赤外線」、レントゲンにつかわれる「エックス線」、電子レンジにつかわれる「マイクロ波」、これらもすべて電磁波です。また、ラジオやテレビ、携帯電話などの通信にも電磁波が利用されています。よくつかわれる「電波」というのは、電磁波の中でも光よりも周波数が低いもののことをいいます。
 飛行機や船の通信や気象観測につかわれるレーダーは、高周波をつかう。
飛行機や船の通信や気象観測につかわれるレーダーは、高周波をつかう。
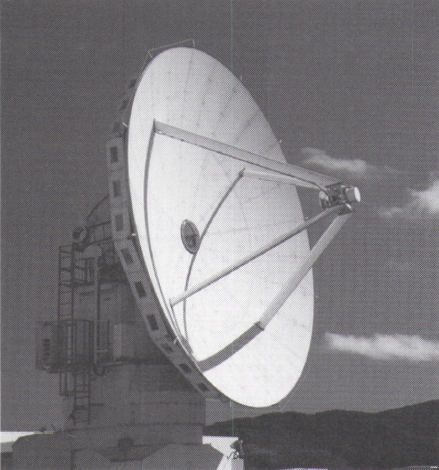
245
反射
光は、じゃまをするものがなければどこまでもまっすぐにすすむ性質があります。ところが、ものにぶつかるとはねかえります。これを「光の反射」といいます。
鏡のように、表面がつるつるしたものは光をよく反射し、布などのざらざらしたものはあまり反射しません。
鏡にものがうつるのも、鏡に反射した光がみえるからです。鏡にまっすぐにあたった光は、まっすぐに反射しますが、ななめにあたった光は同じ角度で反対側に反射します。この性質を利用すると、目にみえない場所もみることができます。自動車のバックミラーや道路のコーナーミラーも反射を利用しています。
 運転手からみえない曲がり角をうつしてくれるコーナーミラー。
運転手からみえない曲がり角をうつしてくれるコーナーミラー。
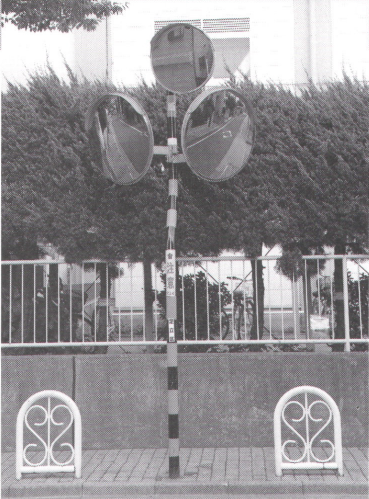
分子
物質をどんどん細かくわけていくと、その物質が性質をたもっていられる最小のつぶとなります。このつぶを「分子」といいます。分子をさらにわけて、それ以上わけることができなくなった小さなつぶを「原子」といいます。原子にわけるとその物質の性質はなくなります。原子の種類やならび方、大きさがちがうと、まったく別の物質になるのです。
たとえば水の分子は、1つの酸素原子(O)と2つの水素原子(H)でできています。また、プラスチックは、炭素を中心としたとても長い分子でできています。
変態
昆虫はほかの動物とちがって、子どもと親のすがたがまったくちがうものがいます。昆虫の成長のしかたを「変態」といいます。
たとえばチョウは、たまごからかえった小さな幼虫が、何度か脱皮をして大きな幼虫になり、やがてさなぎになります。さなぎの間はまったくうごかず、何もたべませんが、さなぎの中では大きな変化がおこっています。そして、1月ほどたつと、さなぎから親と同じ姿になった成虫がでてきます。
たまご→幼虫→さなぎ→成虫という成長のしかたを「完全変態」といいます。チョウ・ハチ・カブトムシなどがこのタイプです。一方、バッタ・カメムシ・セミなどは、さなぎにはならず、幼虫が脱皮をくりかえして成虫になります。これを「不完全変態」といいます。
あ
アイスクリーム頭痛……131
アイスランド貝……33
アイナメ……62
亜鉛……136
アオマツムシ……31
あか……114
アカウミガメ……35
アカゲラ……50
赤ちゃん……39, 40, 94, 95, 101
アカマツ……70
秋……31
あくび……97
アゲハチョウ……20, 74
アゲハモドキ……74
アサギマダラ……54
朝日……221
足, あし……14, 76, 79, 96
味……91
アシダカグモ……22
味の対比効果……201
アスタキサンチン……202
汗……38, 98, 114, 168
アニメーション……155
油……186-187
アブラゼミ……25
アフリカゾウ……36
アマガエル……55
天の川……236
アミメハギ……61
アミロペクチン……200
雨……220
アメンボ……14
アリ……16
アルカリ性……176
アルカリ電池……136
アルコール……202
アンコウ……60
アントシアニン……177
い
胃……13, 77, 98, 123, 129
イースト菌……202
イカ……57
息……112, 199
生き物……35-36
石……205
イシダイ……60
石目……205
異常気象……232
イソギンチャク……58
一次電池……136
イチョウ……69
遺伝子……99, 104
イナゴ……18
イヌ……34, 44, 102
イネ……63
イノコヅチ……67
イボイノシシ……100
イボウミウシ……57
イルカ……56, 100
イルミネーション……139
インコ……50
インフルエンザウイルス……203
引力……186, 244
う
ウイルス……102, 103, 105, 110, 130, 203
ウォンバット……39
羽化……29
ウグイス……51
ウサギ……34, 41
ウシ……77
右心室……84
右心房……84
うずしお……238
打ち水……204
宇宙……236-237
宇宙人……237
ウツボ……60
ウツボカズラ……81
うどん……181
ウナギ……61
右脳……115
ウマ……109
うまれかわり……197
海の水……239
梅……66
うんち……34, 39, 43, 114, 120
え
永久歯……108
栄養……68, 78, 101, 117, 120
液化プラント……141
液体……152, 168, 170-171, 243
エコーロケーション……56
エコマーク……144
S極……154, 167, 239
X染色体……99
N極……154, 167, 239
エビ……202
エビングハウス錯視……88
LED……139
LNGタンカー……141
LNGタンク……141
炎色反応……162
遠心力……146
エンマコオロギ……31
お
横隔膜……107, 112
オウム……75
オオウチ錯視……89
オオカミ……45, 94
オオスズメバチ……13
オオハクチョウ……54
オオヨシキリ……53
247
オーロラ……239
オガサワラオオコウモリ……35
おしっこ……44, 114, 124
おしべ……72, 81
おしり……79
オシロイバナ……65
オゾン層……240
オナモミ……67
おなら……118
おねしょ……124
おふろ……114, 151
オポッサム……39
おもち……200
温室効果ガス……232
温泉……240
温暖化……232
オンブバッタ……18
か
カ(蚊)……19
ガ(蛾)……72, 74
海王星……210, 213
皆既月食……209
皆既日食……209
外骨格……32
外耳道……90
カイツブリ……53
回転……164
界面活性剤……187
海綿動物……33
カエデ……69
化学反応……136
かき氷……131
核(体)……116
核(地球)……167
角質層……109, 114, 130
覚醒中枢……121
角膜……86
家系図……195
カゲロウ……29
下弦の月……208
化合物……162
火山性温泉……240
ガス……141
ガス田……141
ガスホルダー……141
かぜ(風邪)……102, 110
火星……210
化石……233, 234
家族……195
顎下腺……110
カッコウ……53
カニ……202
カニッツァの三角形……89
カバ……38
カビ……64, 189, 192
カフェウォール錯視……89
カブトムシ……26
花粉……13, 72, 130
花粉症……130
カマキリ……18, 26
髪……92
紙……48, 144-145
カミキリムシ……26, 74
紙識別マーク……144
雷……64,216
髪の毛……74, 106, 114, 125
紙パック識別マーク……144
カメノコテントウ……27
カメムシ……20
カメレオン……55
カモガヤ……130
カラス……34, 53
ガラス……156
カラスウリ……72
火力発電……138
カレイ……55
カワウソ……94
カワゲラ……29
カワニナ……30
カンガルー……39
慣性……198, 242
慣性の法則……147, 242
カンタン……31
かんてん……190-191
感電……199
乾電池……136-137
甘味料……201
き
気圧……225, 242
気温……172, 232
気化器……141
帰化植物……65
気孔……71
擬死……78
気体……152, 168, 170-171, 204, 222, 243
キタオポッサム……20
キツツキ…50, 71
キツネ……100
キノコ……64
木の実……66
キビタキ…51
キュウセン……61
恐怖心……194
共鳴室……24
恐竜……234-235
キョクアジサシ……54
キリン……34
銀河系……236
金環日食……209
金魚……62
金星……210
金属……162
緊張……193, 194
筋肉……95, 97, 107, 126, 129
菌類……35, 64
248
く
空気……168, 174‐175
空気砲……175
クエン酸……176
くしゃみ……102
クジラ……40
クスサン……74
屈折……218, 242
くっつき虫……67
クマ……94
クマゼミ……25
クマノミ……61
クマムシ……36
クモ……18,21
雲……173, 216, 218, 222-223
クモザル……100
クライミングクレーン……163
クリ……70
グリーンマーク……144
グルタミン酸……182
グルテン……181, 202
クレーン……163
グンタイアリ……36
け
毛……47, 49
蛍光灯(蛍光ランプ)……139
ケイブ・クレイフィッシュ……33
消しゴム……166
血液……104, 129
血液型……104
ゲッカビジン……72
血管……105, 109
結晶体……156
血小板……105
月食……209
ゲップ……118
けづめ……79
月齢……208
結露……171
巻雲……222-223
ゲンゴロウ……29
ゲンジボタル……30
原子力発電……138
巻積雲……222-223
巻層雲……222-223
こ
コアジサシ……53
コアラ……39
コイ……33, 60
コイル……138
甲殻類……23, 58
光合成……68, 69, 71, 81
虹彩……92
高積雲……222-223
酵素……185, 191
高層雲……222-223
紅茶……176
公転……230
硬度……160
コウノトリ……35, 41
鉱物……160, 243
酵母菌……202
コウモリ……94
紅葉……69
声……24, 124, 127
氷……152-153, 172-173, 222
五感……91
ゴキブリ……22
呼吸……193
コゲラ……50, 53
こし……181
古紙パルプ……144
コジュケイ……51
固体……152, 168, 243
5大栄養素……117, 120
骨格……32, 95
ことば……75
小鳥……51
コノハミドリガイ……69
ゴマダラカミキリ……74
ゴマモンガラ……60
ごみ……114
ゴム……150
ゴリラ……41
昆虫……32
こんにゃく……205
さ
サイ……94
細菌……103, 105, 114, 123, 130, 182, 192, 203
サイクロン……229
再生可能エネルギー……138
再生紙……144
細胞……55, 68, 99, 103, 116, 125, 184, 188, 203, 243
細胞膜……116
魚……60, 61, 62
サギ……50
錯視……88
朔望月……208
サケ(鮭)……59
左心室……84
左心房……84
錯覚……221
砂糖……192, 201
ザトウクジラ……40
左脳……115
砂漠……71, 78
さび……165
サボテン……71
サメ……60, 62
酸化……185
酸化鉄……165
249
サンシュユ……66
サンショウ……70
酸性……176
酸性雨……228
酸素……68, 84, 97, 101, 112, 165, 192-193
残像……203
ザンダー錯視……88
産卵……18, 31, 59
し
死……197
ジェットコースター……146
シェパード錯視……88
塩……184, 201, 239
しおふき……40
塩水……142, 185
シカ……94
紫外線……87, 92, 128, 240, 244
耳下線……110
耳管……90
視交叉上核……121
脂質……117
磁石……138, 154, 167
視神経……86
舌……45, 91, 110
実視等級……215
湿度……189, 220
しっぽ……79, 100
自転……230
自転車……138, 143, 147, 148
磁場……167
脂肪……78
シマウマ……42, 87, 121
シマスカンク……20
シマリス……42
しもばしら……152
指紋……119
視野……87
シャチ……36, 41
しゃっくり……107
シャボン玉……12
ジャム……192
ジュウシチネンゼミ……25
臭腺……20
重力……244
シュガーレス……201
樹氷……152
寿命……196
春夏秋冬……230
上弦の月……208
条件反射……110
小腸……123, 129
蒸発……168, 188, 204, 243
常緑樹……69
食虫植物……81
植物性炭水化物……190
食物繊維……120
触角……74
しらが……125
磁力……154, 167, 239
シロツメクサ……65
しわ……130
深海……227
新幹線……159
しんきろう……238
神経……90, 109
新月……208
信号機……139
心臓……84, 193
振動……158
心拍数……85
す
巣……12, 16, 21, 50, 53, 71
スイカ……201
水蒸気……152, 170-171, 172-173, 199, 200, 220, 222, 226
すい星……212
水生昆虫……29
水生植物……73
水滴……171, 199
水溶液……176
水力発電……138
スーパーボール……150
スギ……130
スズムシ……31
スズメ……51
スズメガ……72
スズメバチ……41
ストレス……193, 194
スピーカー……158
すべり台……143
すみ……57
スリックタイヤ……161
せ
正座……131
声帯……124
セイタカアワダチソウ……65
成虫……29
静電気……134-135
セイヨウタンポポ……65
せき……102
積雲……222-223
赤外線……198, 232, 244
せきつい動物……35
積乱雲……216, 222-223, 226
セーター……134
舌下線……110
接眼レンズ……157
赤血球……105
セミ……24-25
ゼラチン……190-191
染色体……99
前線……225
センダイムシクイ……51
センダングサ……67
250
線路……204
そ
ゾウ……34, 77, 85
層雲……222-223
ゾウガメ……33
草食動物……34, 38
層積雲……222-223
爪半月……109
爪母……109
ゾウムシ……26
ソーマトロープ……155
ソメンヤドカリ……58
た
体液……116
体積……151, 153
大腸……123, 129
大脳……115, 121, 122
台風……229
タイフーン……229
対物レンズ……157
タイヤ……161
ダイヤモンド……160, 205
太陽……208-209, 210, 212, 214, 217, 218, 219, 221, 230, 236, 239, 240
太陽系……210, 213, 236
太陽光発電……138
太陽風……239
対流……151
だ液……19
唾液腺……110
竹……43
タコ……55, 57
タチウオ……60
ダチョウ……52
ダツ……60
タヌキ……78
タヌキモ……81
たね……67, 80
たまご……18, 29, 59
たまご(鶏卵)……178-179
タマネギ……180
たん……102, 114
単位電池……136
たんこぶ……125
ダンゴムシ……23
淡色野菜……120
炭水化物……117
弾性……150
炭素……160
たんぱく質……104, 117, 118, 178
田んぼ……63
段ボール製容器包装マーク……144
タンポポ……65
ち
血……19, 84, 103, 105, 125, 131
チーター……100
地球……208-209, 210-211, 212, 230, 239
チャバネアオカメムシ……20
チャレンジャー海淵……227
中性……176
チョウ……26, 74
腸……98, 118, 123, 129
超音波……90
チョウチョウウオ……61
チンパンジー……102
つ
月……208-209
ツキミソウ……72
ツクツクボウシ……25
土ふまず……96
つば……110
ツバメ……53, 54
ツマグロヒョウモン……74
爪……47, 109
梅雨……220
つらら……152
て
テアフラビン……176
DNA……99
低気圧……225, 229
鉄……142, 154, 165
電解液……136
電気……134-135, 136-137, 138-139, 199, 216
天気雨……226
天気記号……225
天気図……225
天気予報……224-225
電光掲示板……139
電磁波……244
電車……198, 204
電子レンジ……140
電線……199
天然ガス……141
でんぷん……200
と
等圧線……225, 242
トウガラシ……22
等級……215
糖質……117
動物性たんぱく質……190-191
動脈……113
とげ……70, 71
土星……210, 213
凸レンズ……157
トビウオ……57
251
トラ……42
トラウツボ……62
鳥……50, 52, 53, 66, 75
鳥はだ……126
トンボ……28, 29
な
内骨格……32
長生き……33
流れ星……211, 212
鳴き声……25, 31, 51, 94
ナスニン……177
納豆……182
ナナカマド……66
ナナホシテントウ……27
涙……93, 97, 127
ナミテントウ……27
南極……231, 239, 240
ナンテン……66
に
ニイニイゼミ……25
ニカド電池……136
二酸化炭素……68, 84, 202, 232
にじ……217, 218-219
二次電池……136
ニジュウヤホシテントウ……27
日食……209
ニホンタンポポ……65
ニホンミツバチ……13
乳酸菌……123, 182
乳歯……108
ニワトリ……52, 76
ね
ネコ……46
熱帯低気圧……229
熱中症……128
ねむり……47, 61, 121-122
年表……195
の
ノアザミ……70
脳……86, 88, 90, 93, 96, 97, 110, 111, 115, 121
脳幹……121, 122
ノンレム睡眠……122
ノンレム睡眠中枢……121, 122
は
歯……37, 60, 108
葉……68-69
肺……112
梅雨前線……220
バイオマス発電……138
廃棄物発電……138
パイナップル……80
ハエトリグサ……81
白衣……203
白熱電球……139
ハゲブダイ……61
ハチドリ……50
発音筋……24
発音膜……24
白血球……103, 105
発酵……182-183, 202
発酵食品……183
発光ダイオード……139
発電所……138
鼻……44, 62, 91
鼻くそ……114
花火……162
鼻水……102, 114
ハニカム構造……12
ハムスター……34, 85
バラ……70
バラスト……204
ハリケーン……229
ハリセンボン……57
波力発電……138
パン……202
半規管……90, 111
半月……208
反射……156, 169, 218, 245
パンダ……43, 94
半透膜……184
ハンノキ……130
ひ
ピーナッツ(→落花生)
非火山性温泉……240
光……169, 216-217, 238
光のスペクトル……86
ヒグラシ……25
ひげ……46
飛行機雲……173
非晶体……156
微生物……192, 202, 233
ビタミン……117, 120
左利き……115
ビッグ・バン……236
ヒツジ……48
ひづめ……109
ヒバリ……53
皮膚……32, 38, 55, 76, 92, 106, 109, 114, 119, 125, 126, 130
ビフィズス菌……123
ヒメクロゴキブリ……22
ヒメジョオン……65
日やけ……128
病気……42, 103, 105
氷山……153
表面温度……215
表面張力……12, 14
ヒヨドリ……53
ピラニア……60
252
ふ
風向……225
風力……225
ブーメラン……148-149
風力発電……138
ふきガラス……156
複眼……28
副交感神経……93
フクロウ……75
ブタクサ……65, 130
沸騰……170, 243
ふとん……168
船……142
腐敗菌……182
部分月食……209
フラクタン……182
ブラックホール……237
フラミンゴ……50, 76
プリズム……218
浮力……142
フレア……210
フロアクライミング方法……163
分子……140, 152-153, 156, 200, 245
へ
ヘイケボタル……30
へそ……101
ヘッピリムシ……20
ベニクラゲ……33
ヘビ……79
ヘモグロビン……105
ペリカン……50
Hz(ヘルツ)……90, 244
変化球……164
ペンギン……52, 94
変態……245
ほ
方位磁石……167
望遠鏡……157
膀胱……124
胞子……189
膨張……151
放電……134, 216
ホオジロ……51
ボール……150
ボールペン……166
ほくろ……126
保護色……55
星(花火)……162
星……214-215, 236
ホソムギ……130
ホタル……30
ボタン電池……136
北極……49, 231, 239, 240
ホッキョククジラ……33
ホッキョクグマ……49
ポップコーン……200
ホトトギス……51
ほ乳類……35, 40, 101
骨……32, 96, 100, 125
ポリフェノール……185
ポリブタジエン……150
ま
マーキング……44
マイクロ波……140, 244
マグナス効果……164
マグロ……61
摩擦……140, 143
摩擦熱……143, 161
マストクライミング方法……163
マッコウクジラ……36
マツムシ……31
マツモムシ……29
マツヨイグサ……72
まばたき……127
真水……142
マリアナ海溝……227
マンガン電池……136
満月……208
マンボウ……61
み
ミイデラゴミムシ……20
三日月……208
右利き……115
水……152-153, 170-171, 172, 185, 186, 188, 199, 204, 222
ミツバチ……12-13
ミツロウ……13
ミトコンドリア……116
ミネラル……117
ミノカサゴ……57
耳……46, 62, 90, 111
耳あか……114
脈……85
ミュラー・リヤー錯視……88
ミント……22
ミンミンゼミ……25
む
ムカシトカゲ……33
虫……31
虫歯……37, 108, 110
虫めがね……157
ムンカー錯視……89
め
目……47, 75, 86, 92, 97, 111
めしべ……72, 81
目の錯覚……88
253
メラニン色素……92, 125, 126, 128
も
毛幹……92
毛球……106, 125
モウセンゴケ……81
網膜……86
モース硬度……160
木星……210, 213
木炭電池……137
や
ヤギ……48, 94
ヤゴ……29
野菜……120
ヤドカリ……58
ヤマボウシ……66
ヤモリ……79
ゆ
有袋類……39
夕立……226
夕日……221
夕焼け……217
雪……172
雪雲……172
雪の結晶……152, 172
湯気……152, 170, 172, 199
輸血……104
指……130
ゆめ……122
よ
揚力……148
葉緑素……68
葉緑体……68
ヨーグルト……123
予防接種……103
ヨモギ……130
ら
ライオン……94
ライオンゴロシ……67
ラクダ……78
落葉樹……69
落花生……80
ラミーカミキリ……74
乱層雲……222-223
り
リクイグアナ……71
リサイクル……144
リチウムイオン電池……136
リトマス試験紙……176
リモコン……198
流星群……212
硫化アリル……180
緑黄色野菜……120
リンゴ……185
リンパ液……90, 111
る
涙腺……93, 97
涙のう……97
れ
冷凍……188
レッドデータブック……35
レム睡眠……122
レム睡眠中枢……121, 122
レモン……22, 176
連結器……159
レンコン……73
レンズ……157
わ
Y染色体……99
渡り鳥……54
【主な参考文献】
『ふしぎ! なぜ? 大図鑑―宇宙・地球・人間』(主婦と生活社)
『こどもおもしろ学習館』(主婦と生活社)
『人間を科学する事典―心と身体のエンサイクロペディアー』(東京堂出版)
『もっと知りたい、おなかの赤ちゃんのこと』(赤ちゃんとママ社)
『トコトンやさしい血液の本』(日刊工業新聞社)
『データでわかる人間のカラダ』(明治書院)
『面白いほどよくわかる人体のしくみ』(日本文芸社)
『決定版 知ってビックリ! 人体のヒミツ大全』(宝島社)
『毎日小学生新聞 マンガで理科! きょうのなぜ 自然現象のなぞ21』(偕成社)
『食べものを科学する パート1(身のまわりのふしぎサイエンス1)』(岩崎書店)
『ギモンかいけつ! 天達さんのお天気教室』(文化出版局)
日本科学協会 http://www.jss.or.jp/fukyu/kagaku/data/744.html
WWF http://www.wwf.or.jp/biodiversity/
環境省 https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/index.html#index
キノコの不思議 http://kenko-shien.com/ohga/rabo.html
宇宙科学研究所キッズサイト ボクら宇宙かがく大好き!ウチューンズ http://www.kids.isas.jaxa.jp/
JAXA宇宙情報センター http://Spaceinfo.jaxa.jp/
JSTバーチャル科学館 http://www.jst.go.jp/csc/virtual/
自然科学研究機構国立天文台 http://www.nao.ac.jp/
気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html
国立研究開発法人 海洋研究開発機構 JAMSTEC http://www.jamstec.go.jp/j/
山田養蜂場ミツバチ研究支援サイト http://www.bee-lab.jp/hobeey/
254
――保護者のみなさんヘ――
子どもたちの「なぜ!?」を上手にサポート
中島千恵子(千葉経済大学短期大学部子ども学科教授)
体験を通して知る喜び・わかる楽しさは学習の基盤になります
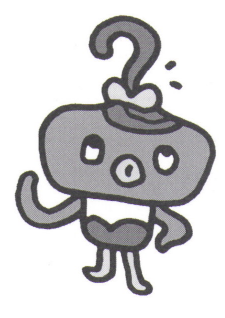
お子さんが小さい時に、「○○って何?」「何で?」と質問責めにあった時期があったことを覚えていますか? 子どもたちの興味・関心、好奇心がありとあらゆるものに向けられていた時期がありましたね。不思議なこと・驚くことに気づき、それらを知る喜びが子どもの学びの原点になっていたのです。
大きくなるにつれて、何気なく行ってしまうこと、気づかずに過ぎてしまうことが多くなっていきます。世の中の動きも速く、時間ややることに追われ、心の余裕がない生活になってきていることがあるのかもしれません。だからこそ今、周囲の環境にちょっと目を向けていってください。そこには子どもの「なぜ?」を思わせる様々なことがあふれているはずです。急がずにゆっくりと見てください。あれあれ? 何でそうなのか、わからないこと・不思議なことがたくさん見えてきますね。
子どもの「なぜ?」が素直に表現できるように、まず聞く姿勢を示してください。つまらない、くだらないとすぐに否定しないようにしましょう。忙しいから後でと先送りして結局対応しないですますというのもいけません。その場で疑問をしっかりと受けとめて、是非親子で一緒に考える時間を作ってください。
子どもから質問された時、正解を言わなくてはならないと思い、わからないことを質問されてつい素っ気ない対応になってしまいませんか。子どもの疑問や言葉に正解を与えることが良いのではなく、疑問を持ったこと自体を「よく気づいたね」としっかりと認めることが大切なことです。そして、子どもと同じ方向を向いて一緒に調べたり試したりしていきましょう。体験を通して知る喜び・わかる楽しさは学習の基盤となり、生涯の学びにつながっていきます。
また、知識の多さを競うのではなく、実際にやってみて実感してわかることがとても大切なことです。大人が知らないことやわからないこともあります。大事なことは、ともに歩み、ともに学びを楽しんでいくという親の姿勢なのです。そして、思ったことを表現しあうことで、親子のコミュニケーションも密になり、豊かになり、絆もさらに深くなっていくことでしょう。「調べてみようか」「ちょっとやってみようか」と気軽に声をかけてあげましょう。そんな一押しが子どもたちの心の支えと希望なのです。
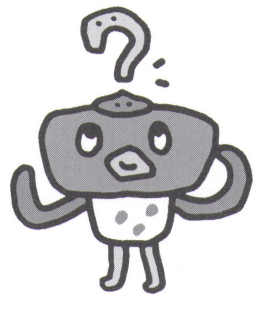
255
●生き物のなぜ?
子どもたちは生き物が好きですね。興味・関心が高いことでしょう。身近な生き物の存在から子どもたちは命の不思議さや驚異・神秘を実感していきます。
生き物の各々の個体には特有の形態や生態があります。見て不思議、動いて不思議、自分と比べての生活の不思議など、疑問はたくさんでてくることでしょう。どんな生き物にも、その存在に意味があります。そして、環境に適応してきた生きるための知恵がたくさんあります。生きる力について是非多くのことを親子で話し合っていってください。
また、肉眼では見られないことや見過ごすこともありますので、一緒に調べてよく見て考える姿勢を育てていきましょう。そして、すべての生き物が必要であること、環境にとって大切なことを考えていけるとよいですね。親御さんの中には虫が苦手な方もいると思いますが、まずは大人から、生き物自体を理解していく姿勢を示してください。家の中、庭先で、歩く道で、身近なところから「なぜ?」を考え始めましょう。
●体のなぜ?
人体の神秘は奥深いものですね。自分の体の中で何がどのように機能しているのかということはなかなか理解することができませんが、表にあらわれる現象や症状などを通して必要なことが自分の体で起こっているということを探ることができます。各々が必要な働きをして生命を維持していることは本当に驚異なのです。
子どもたちが自分なりに理解できる範囲で、自分の体に関心を持つこと、健康で過ごせるように意識して生活することは生きるためにとても重要なことです。頭のてっぺんから足の先まで、自分の体で感じる疑問を一緒に考えていきましょう。それが、体を大事にしていく気持ち、他の人の生命や体を大事に思う気持ちへとつながっていきます。
学校では健康教育や食育が重要視され、学年に応じた内容で実践されています。家庭では素朴なふれあいから感じること・疑問をいろいろ話し合ってください。そして、人間って素晴らしいと実感してくださいね。
●身の回りのなぜ?
生活の中には不思議がたくさんあります。家の中を見回すと、台所のガス台、戸棚、冷蔵庫の中や食材にも発見があることでしょう。目の前になぜだろうと思うことがたくさんある宝の山ですね。むしろ自分のごく近いところにある事柄だからこそ、関心を持ち、知りたい思いが高まるのではないでしょうか。改めて「どうして?」と聞かれるとわからないことも多いですし、昔から何気なく見てきたこと・やってきたことにも説明できる答えがあることがわかりますね。
現代の人々の生活は忙しく、早くいろいろなことをすることが良いように思われがちです。でも、今子どもの立ちどまった素朴な疑問や考えを大事に受けとめてください。そして、子どもと一緒に小さな疑問から大きな驚きを味わってください。ちょっとした実験を通して、そうだったのかと理解を深め、生活を楽しんでいきましょう。
●地球・宇宙のなぜ?
夜空に輝く満天の星を見てそれぞれの星座の話を聞き、月にはうさぎがいると思っていた子ども時代を過ごした方もいることでしょう。今や、人類は月に足を踏み入れ、その様子を映像で見ることができるようになりました。科学の進歩は日進月歩、想像と浪漫の世界だったものの謎がひとつずつ解き明かされていきます。宇宙飛行士は、将来の職業として実現可能な夢になっているのです。憧れの気持ちと今現実にわかっていることを子どもと一緒に考えていきましょう。
また、自然は人々の暮らしに多大な影響を及ぼします。天気予報というごく身近なかかわりから、自然現象、温暖化など様々なことをしっかり理解していければ、未来に向かって大事な財産を子どもたちに残していけると思います。少し難しいことがあるかもしれませんが、一緒に調べたり話し合ったりしていくことで、自然との大切な絆を感じ、自然への敬虔な思いをもっていけることでしょう。
●協力
西村聡―(株式会社サイエンスエンタテイメント)
村上渡、関野剛、板垣喜子、市岡元気、田中由香里
海老谷浩(米村でんじろうサイエンスプロダクション)
●写真提供(五十音順)
アドベンチャーワールド(p43)
海野和男(p87)
かみね公園管理事務所(p79)
下関市しものせき水族館海響館(p33)
スティングレイ・ジャパン(p33)
長崎バイオパーク(p39)
広島市衛生研究所(p203)
横浜市野毛山動物園(p37)
●執筆
宇川静
渋谷典子
とりごえこうじ
栗田芽生(グループ・コロンブス)
橋本千絵(グループ・コロンブス)
●キャラクターデザイン
法嶋かよ
●本文イラスト
かわむらふゆみ
末藤久美子
鶴田一浩
とりごえこうじ
吉見礼司
●装丁
cycledesign
●本文デザイン
坂田良子
●構成・編集
グループ・コロンブス(石井立子)
●編集人
畠山健一(辰巳出版)
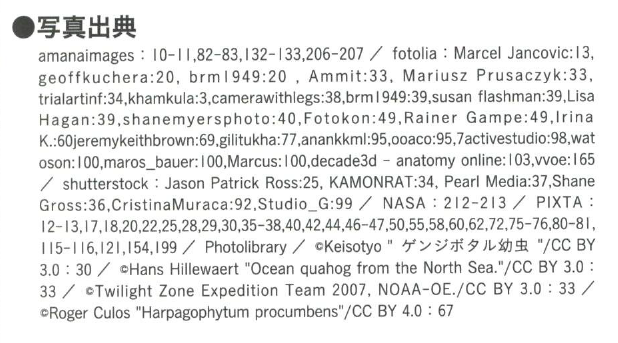
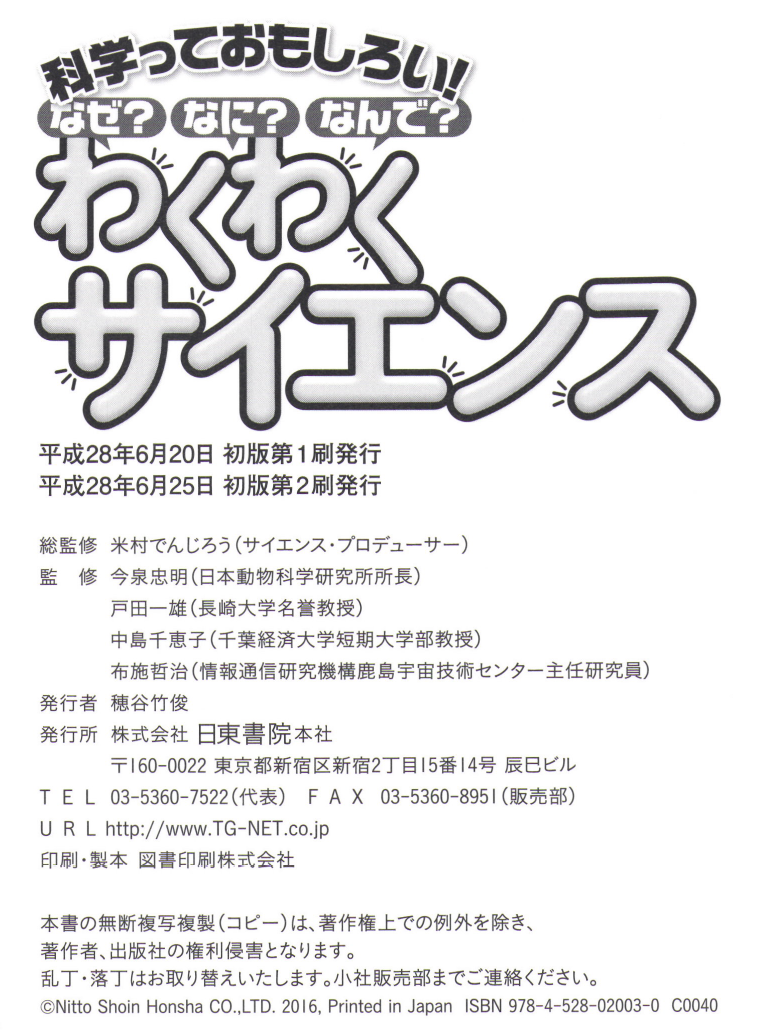

![]()
![]()


![]()
![]()




![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
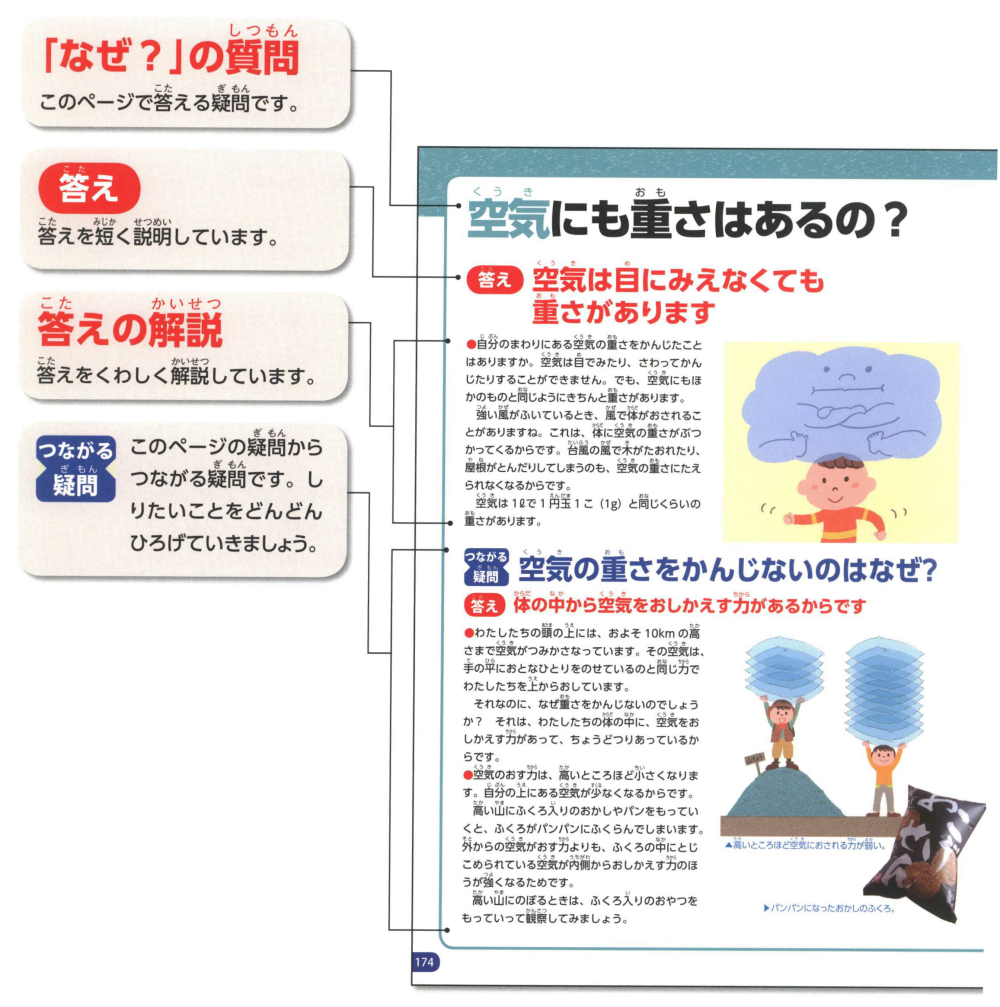
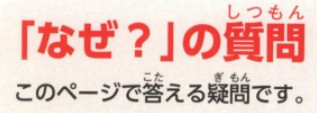
![]()
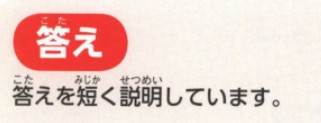
![]()
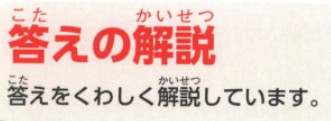
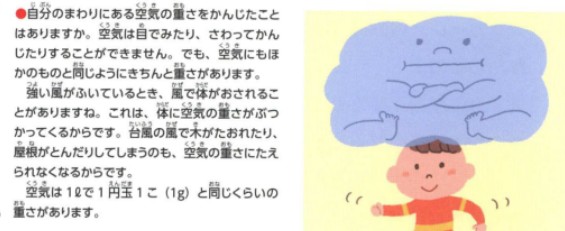
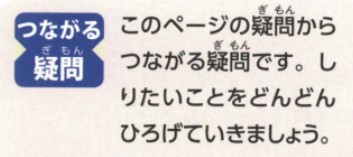
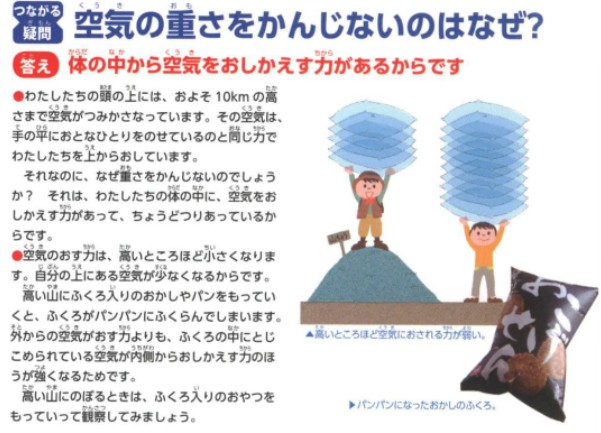
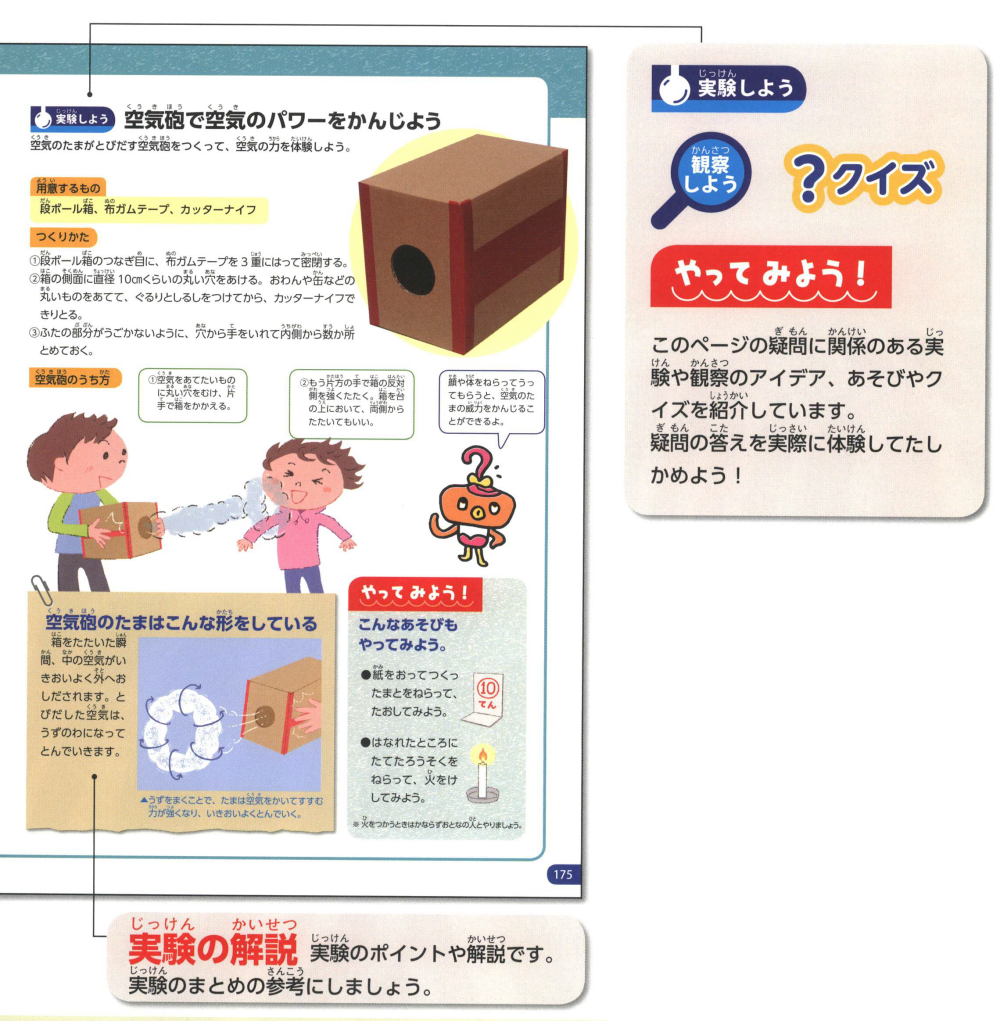
![]()
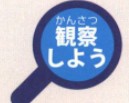
![]()
![]()
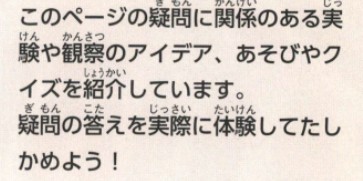
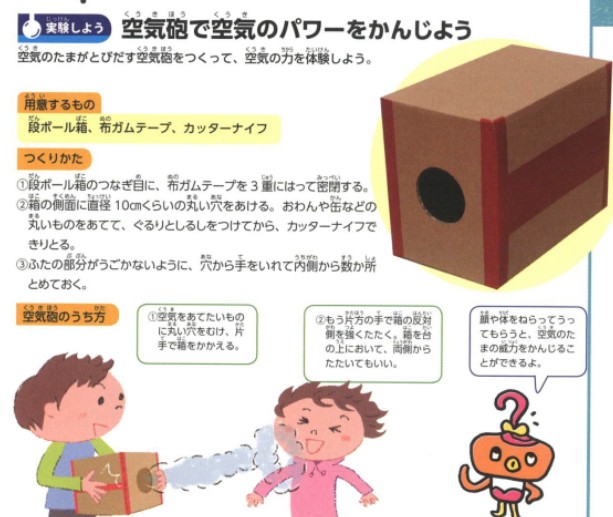
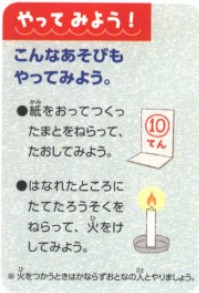
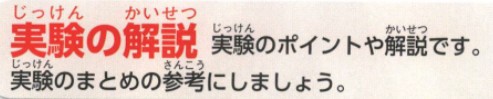
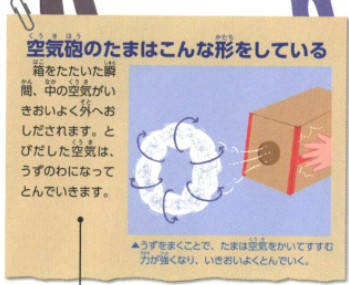

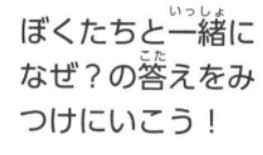
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
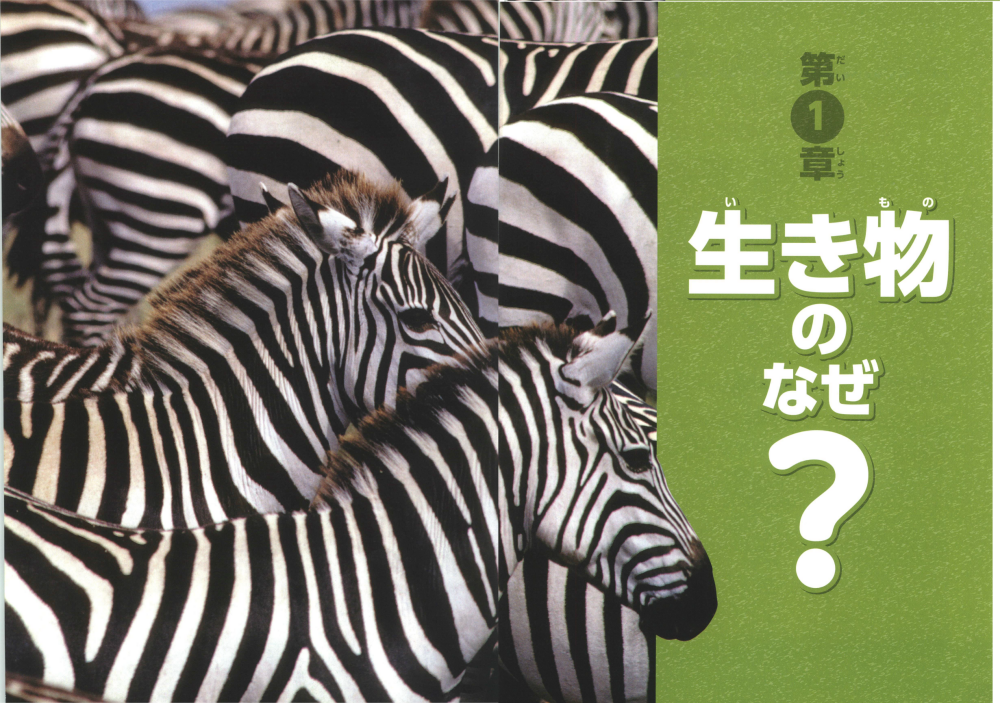
![]()
![]()
![]()

![]()
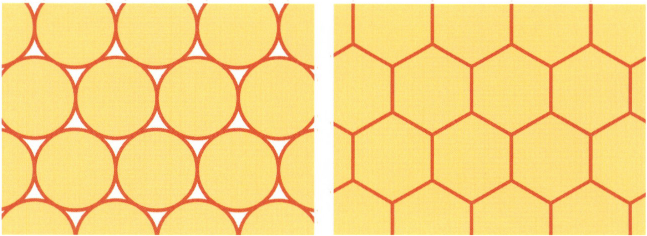
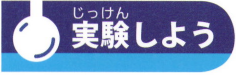
![]()
![]()
![]()
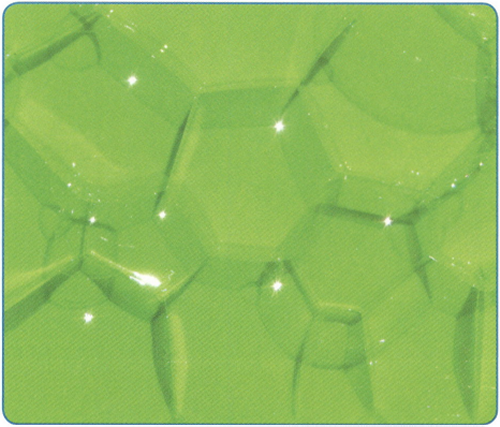

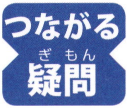
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()

![]()
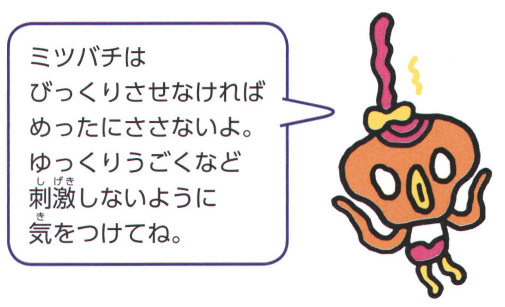
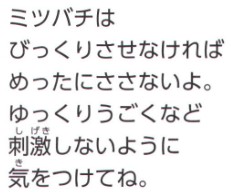
![]()
![]()

![]()
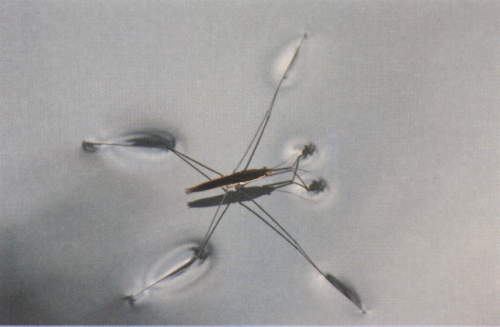
![]()
![]()
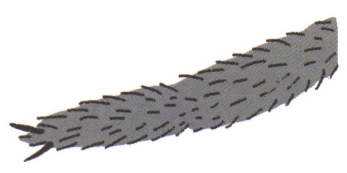
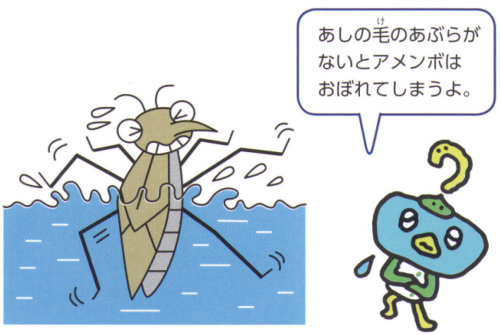
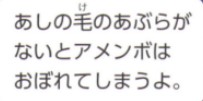

![]()
![]()
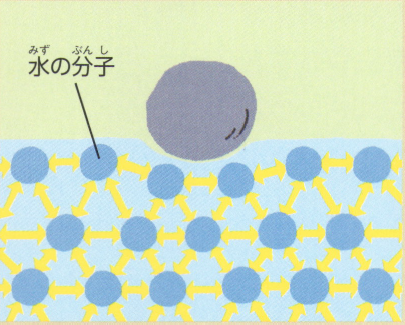
![]()
![]()
![]()
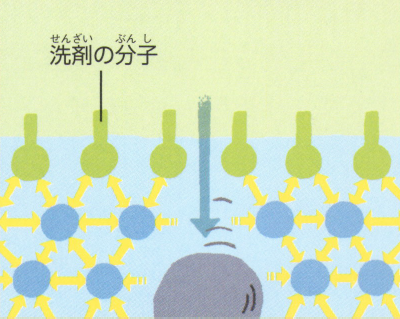
![]()
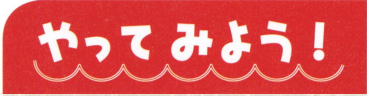
![]()
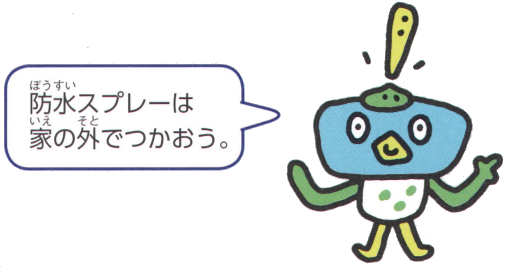
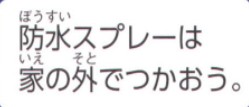
![]()
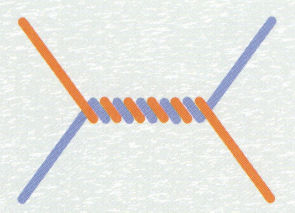
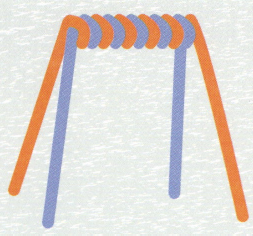
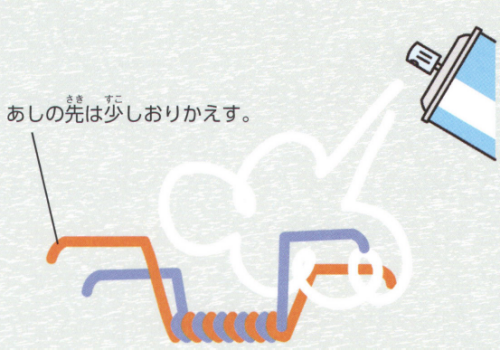
![]()
![]()
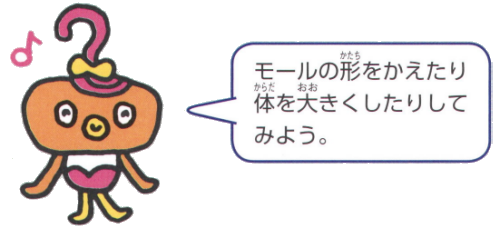
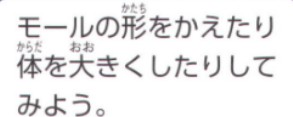
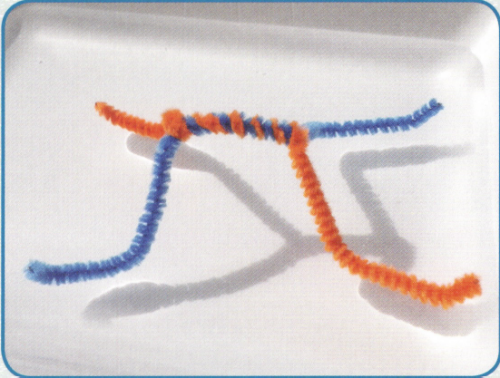
![]()
![]()
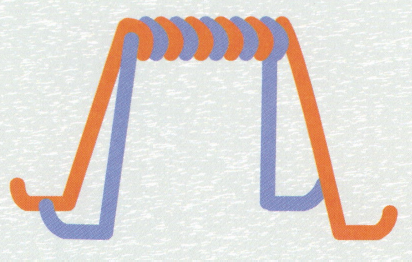
![]()
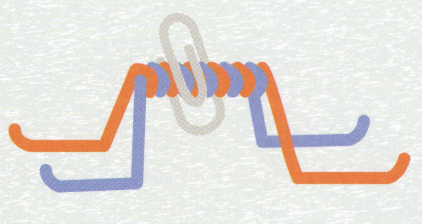
![]()
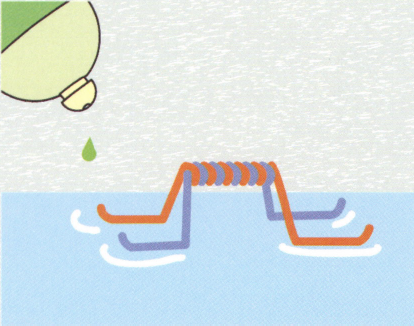
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
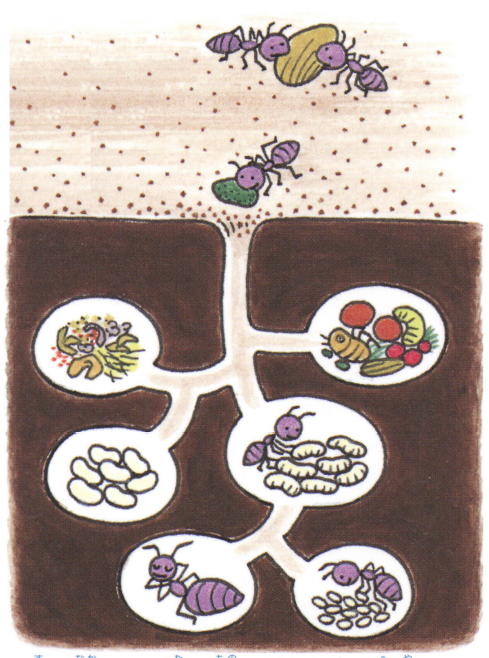
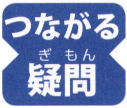
![]()
![]()
![]()


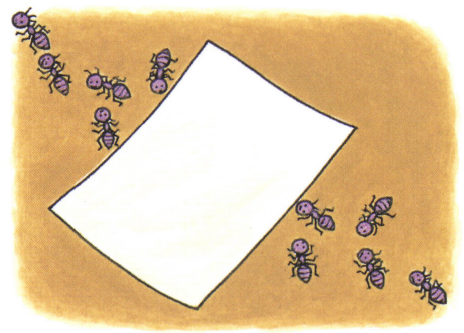
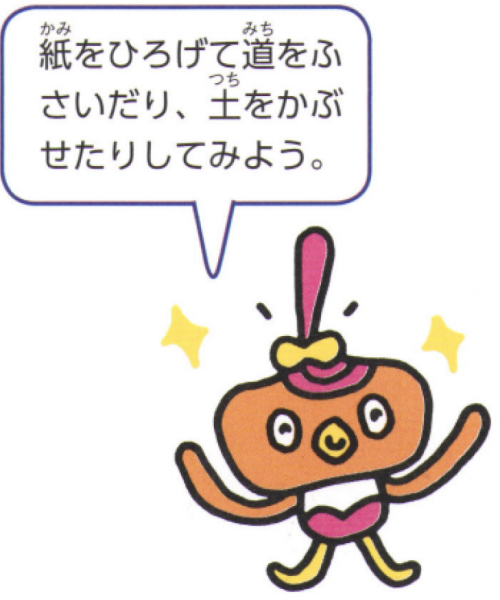
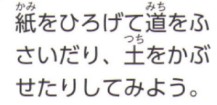
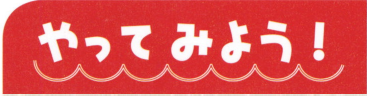
![]()
![]()
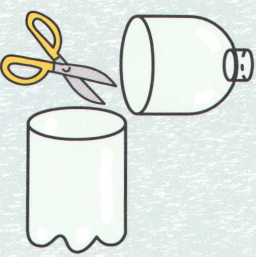

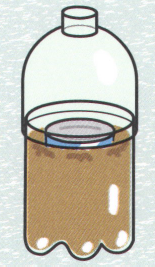
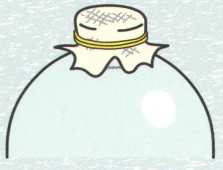
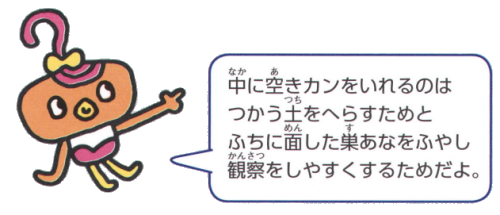
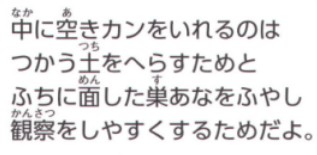


![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

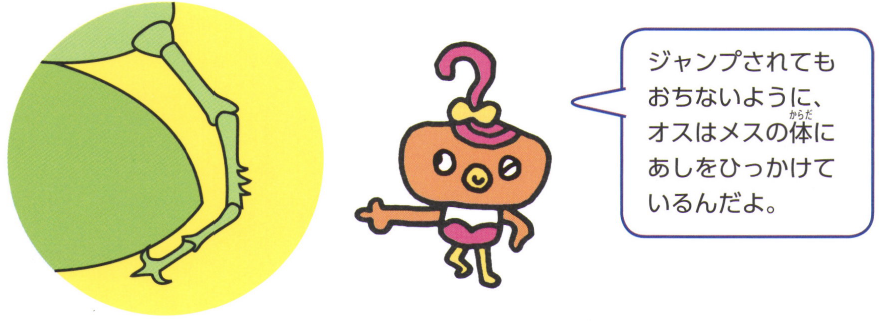
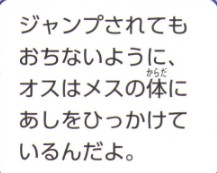
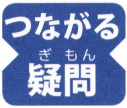
![]()
![]()
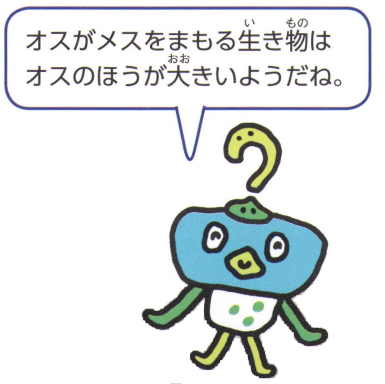
![]()
![]()
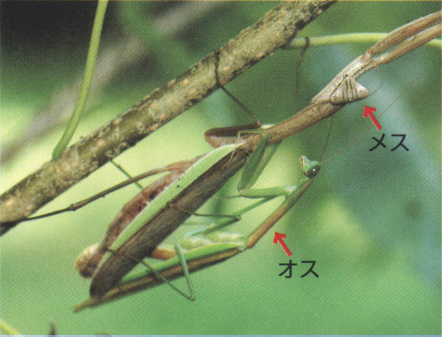
![]()
![]()
![]()
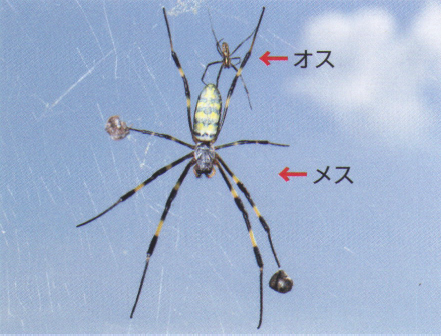
![]()
![]()
![]()
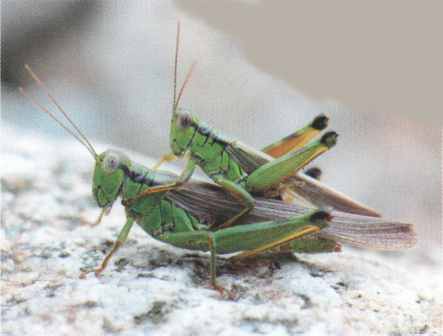
![]()
![]()
![]()

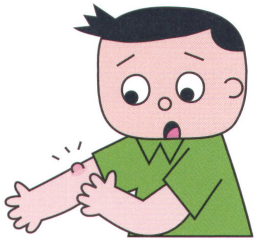
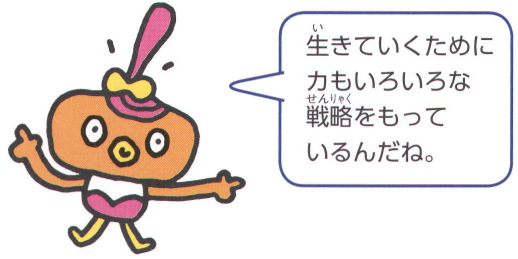
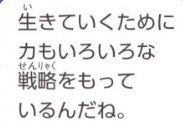
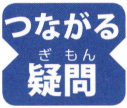
![]()
![]()
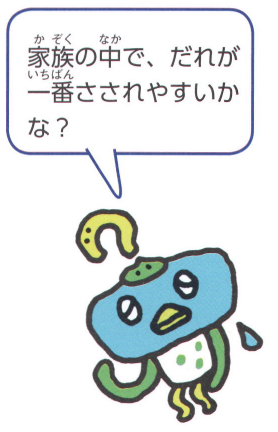
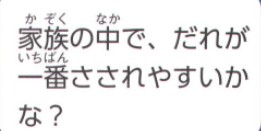

![]()
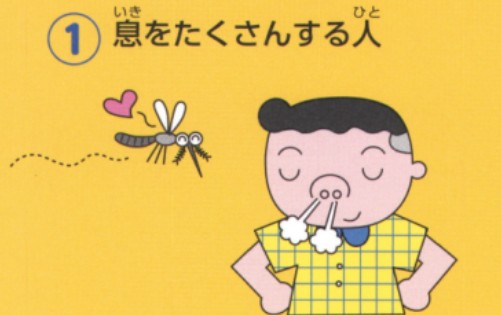
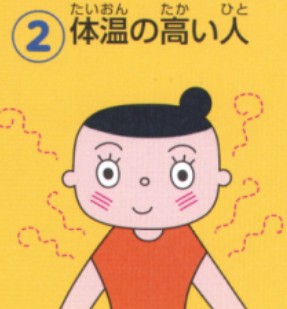
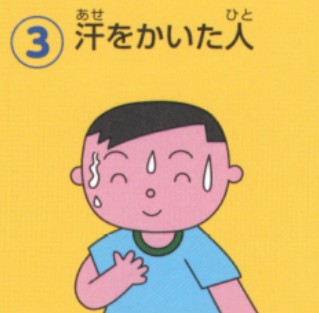
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

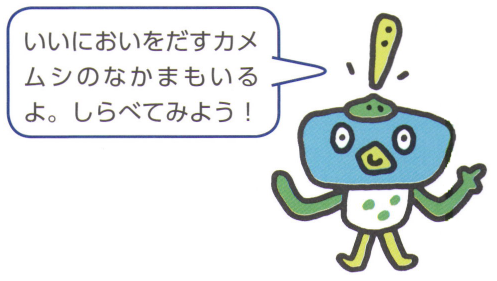
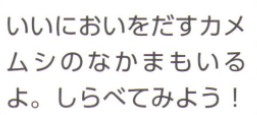
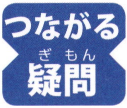
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

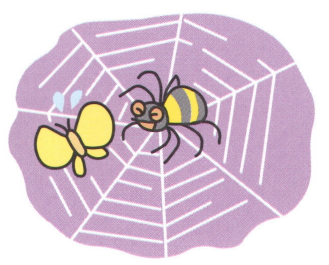
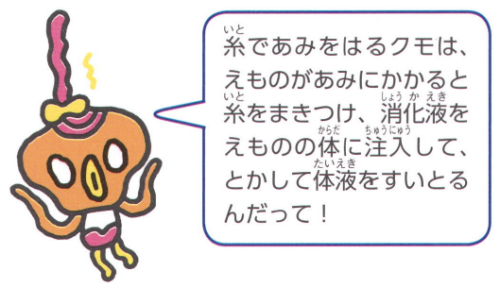
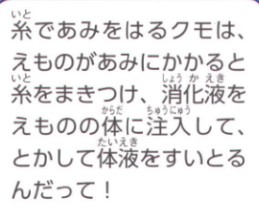
![]()
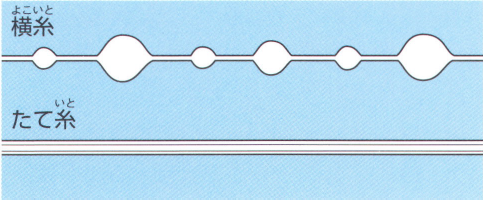
![]()
![]()

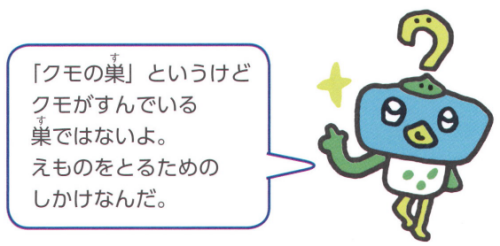
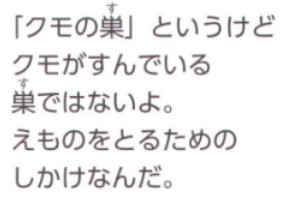
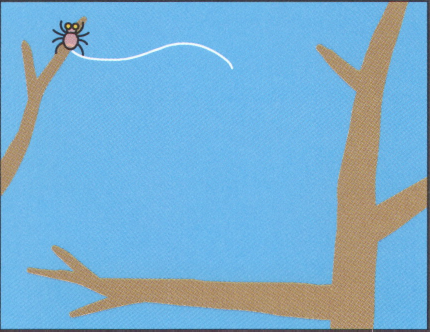
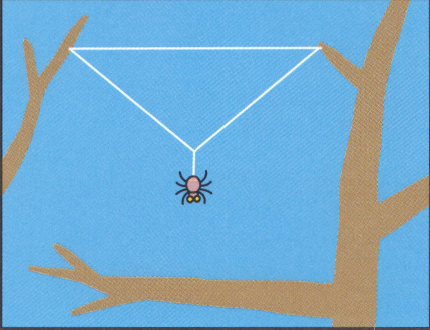
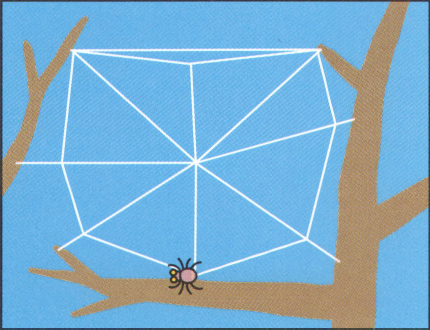
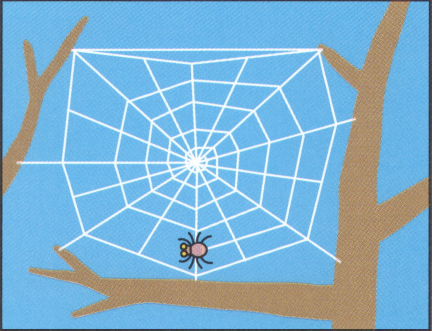
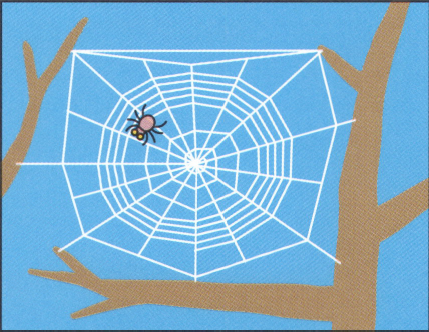
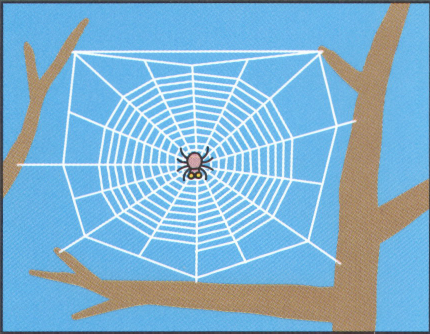
![]()
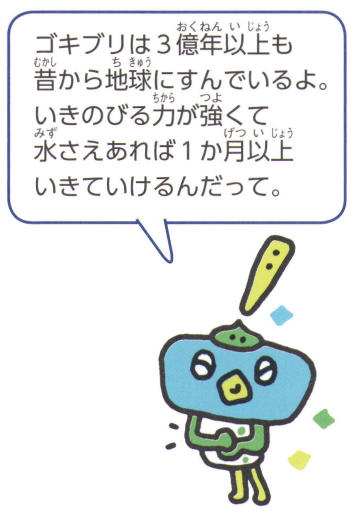
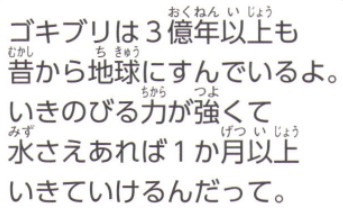
![]()
![]()

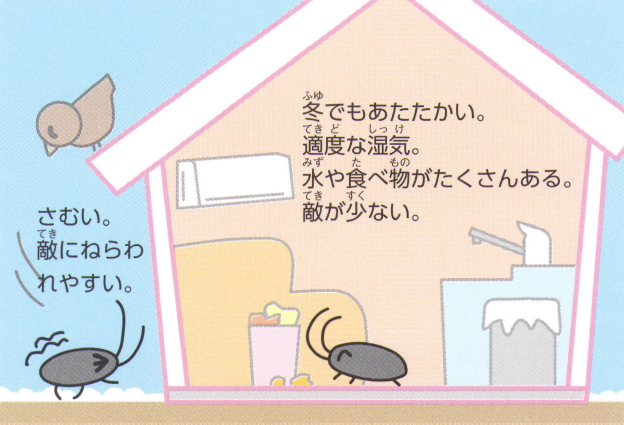
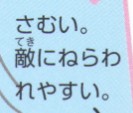
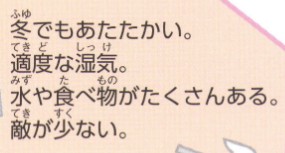
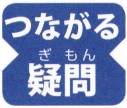
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
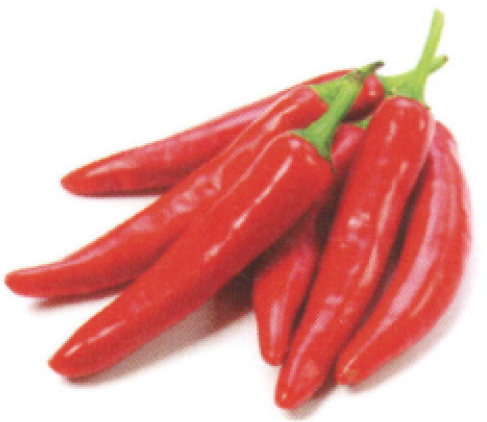
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
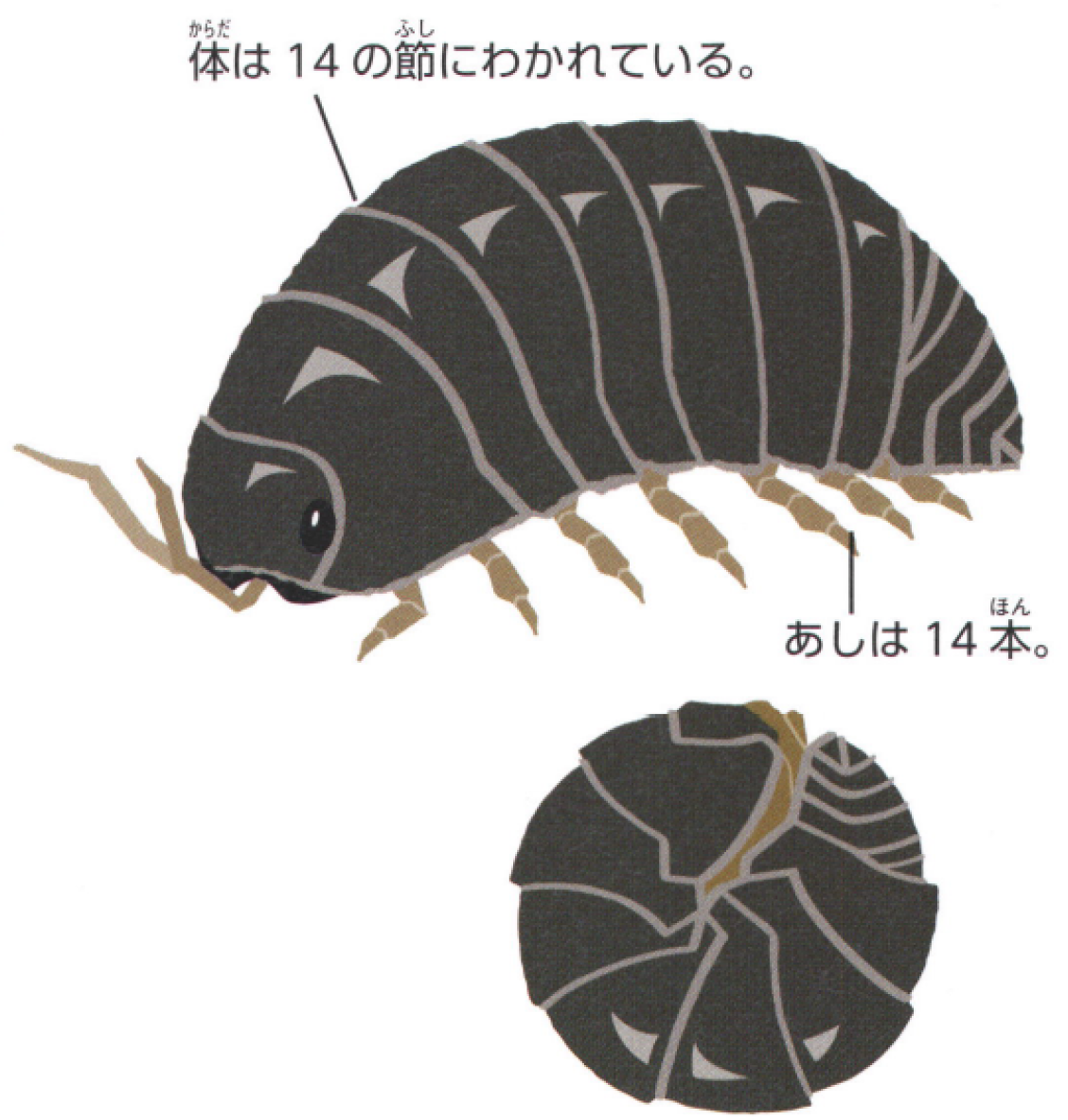
![]()
![]()
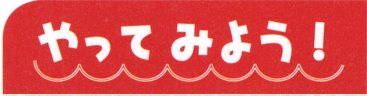
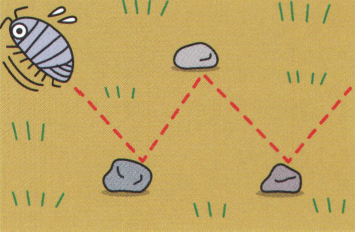
![]()
![]()
![]()
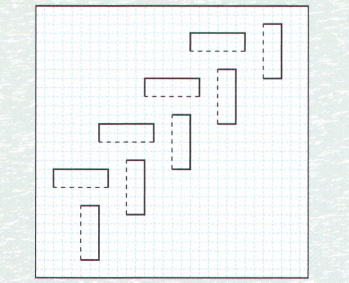
![]()
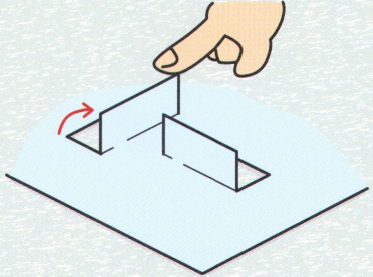
![]()
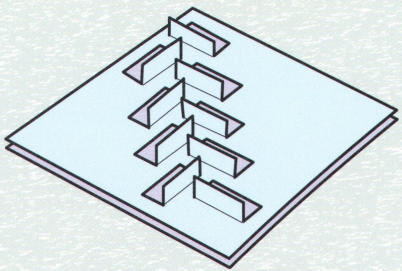
![]()
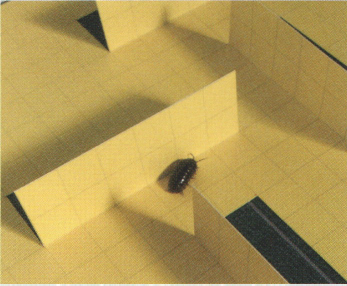
![]()
![]()
![]()

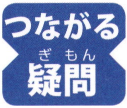
![]()
![]()
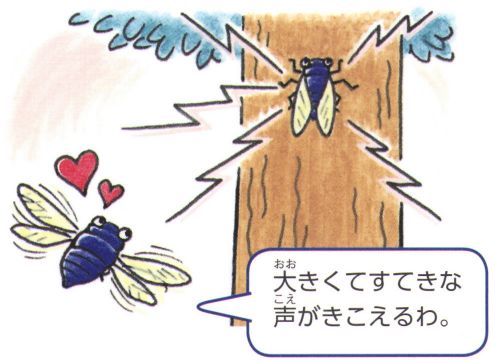
![]()
![]()
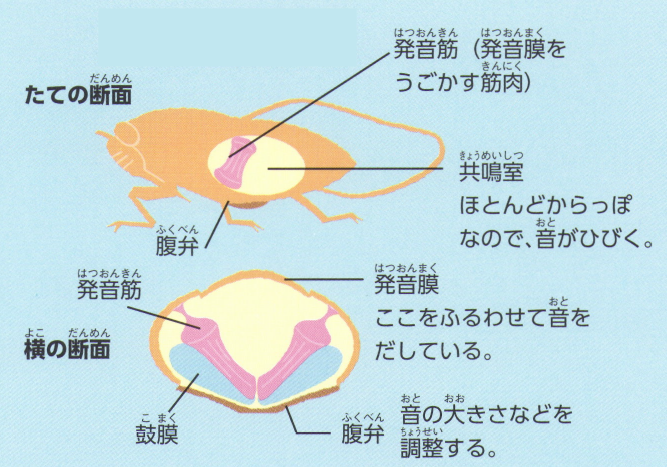
![]()
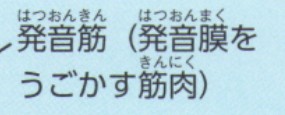
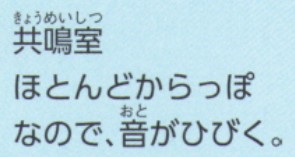
![]()
![]()
![]()
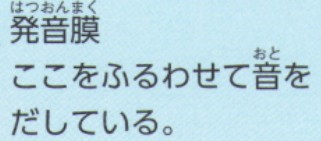
![]()
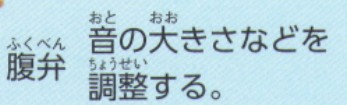
![]()
![]()
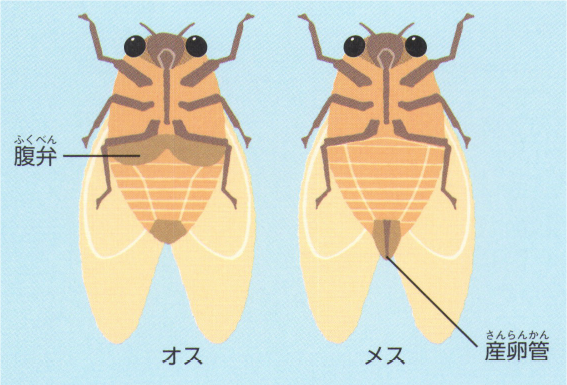
![]()
![]()
![]()
![]()
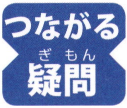
![]()
![]()
![]()
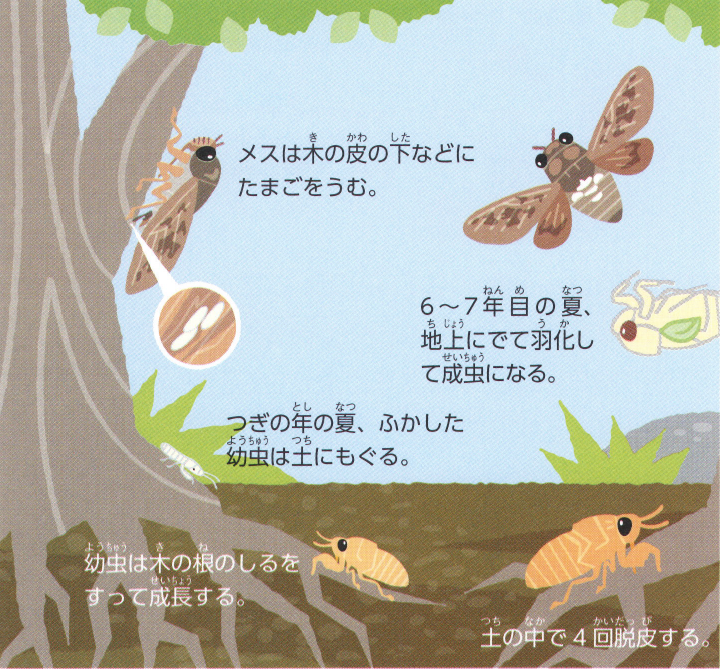
![]()
![]()
![]()
![]()
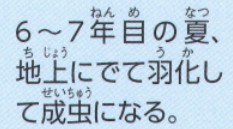


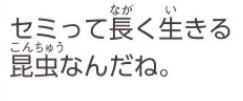

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
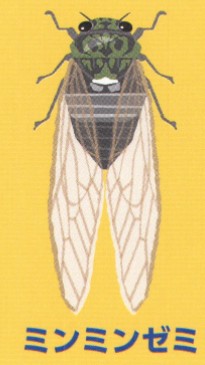

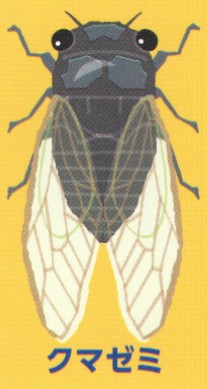


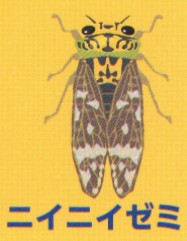
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()


![]()
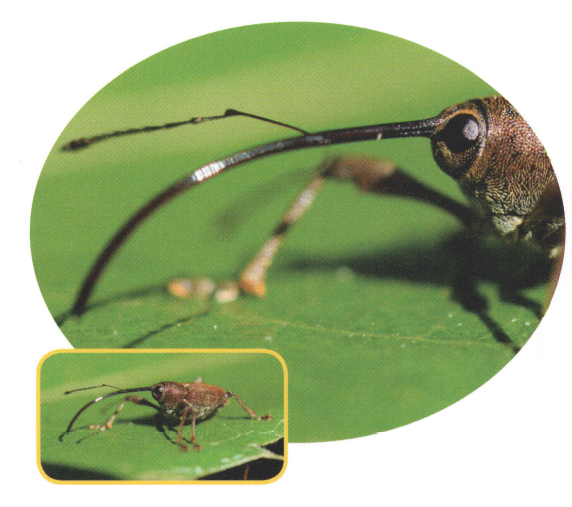
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
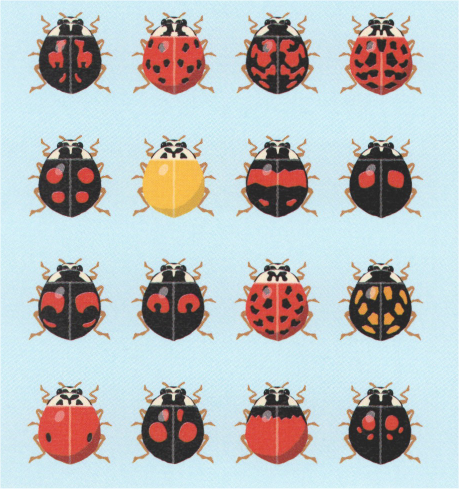
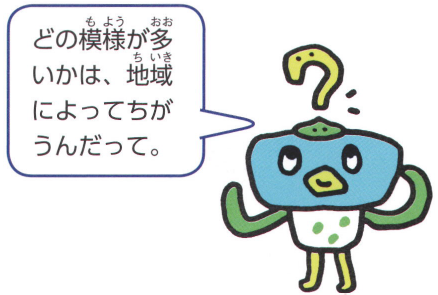
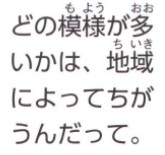

![]()

![]()

![]()

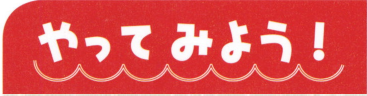
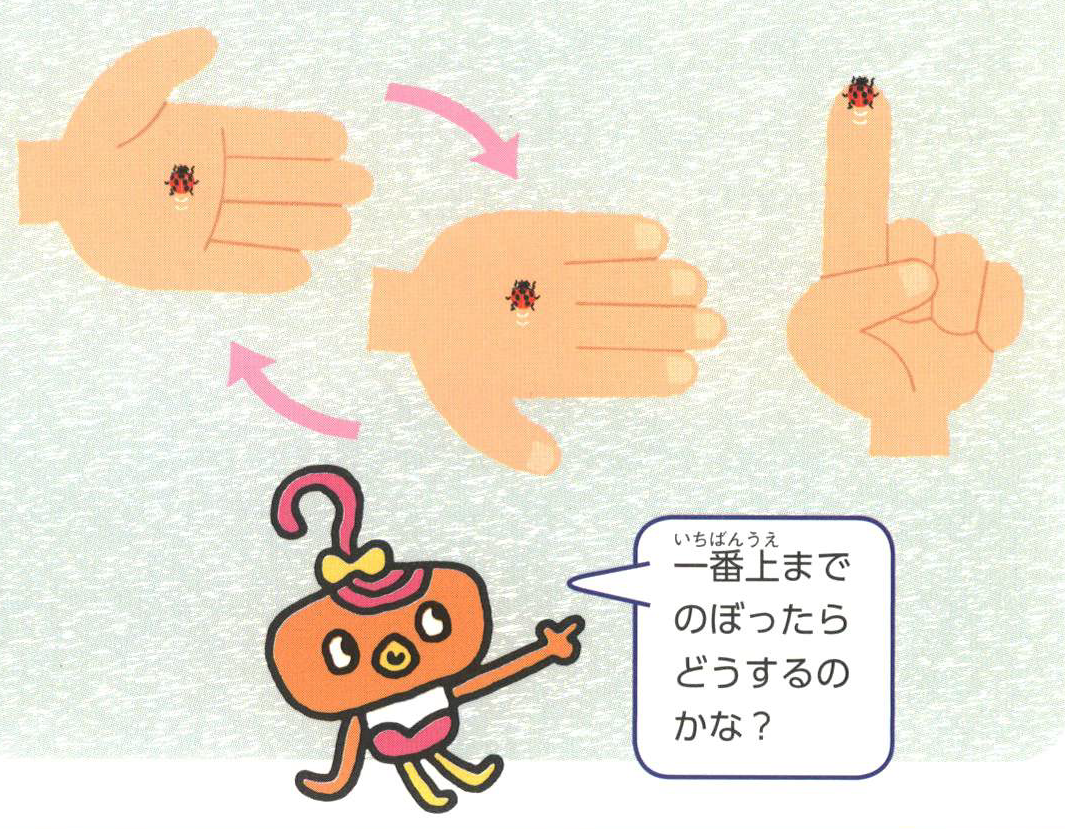
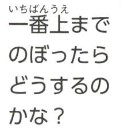
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
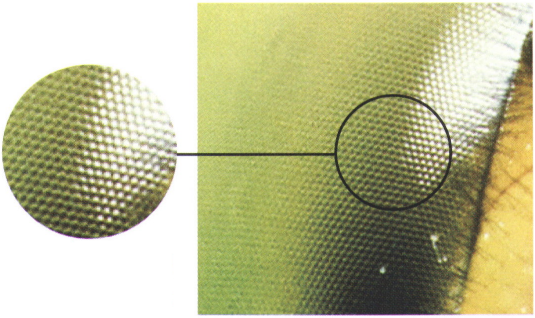
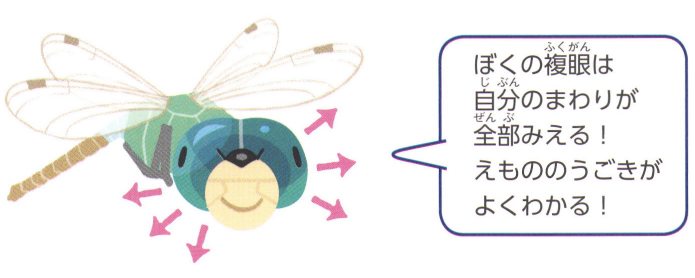
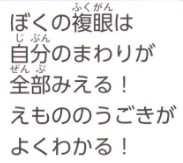
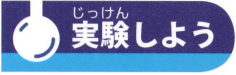
![]()
![]()
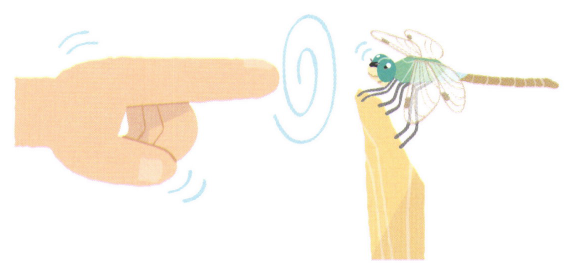
![]()
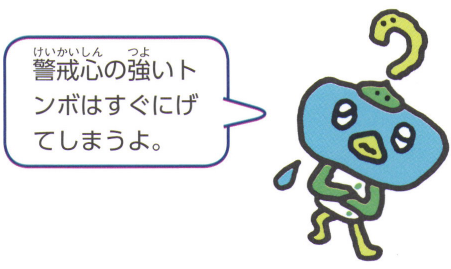
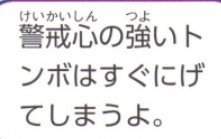
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
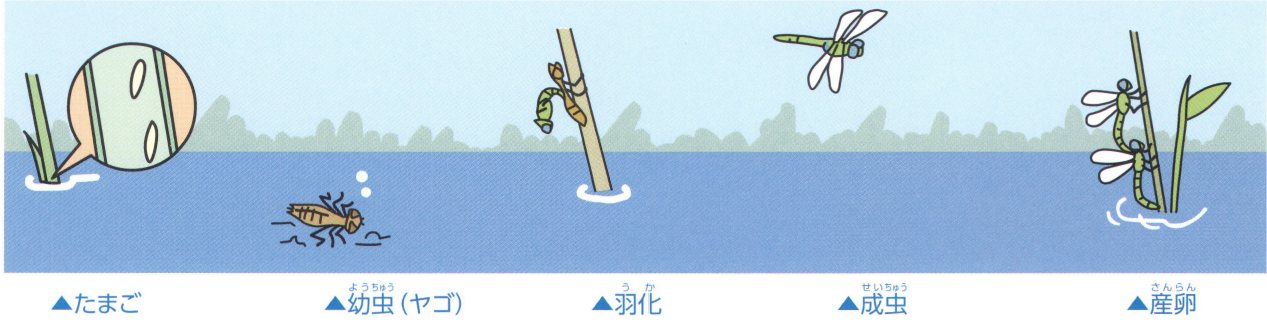
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

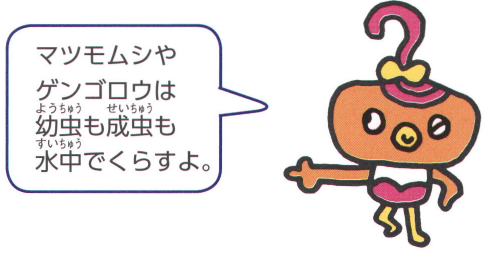
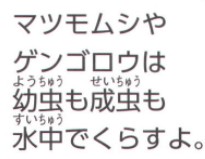
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

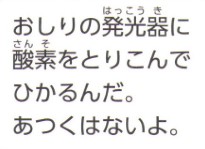
![]()
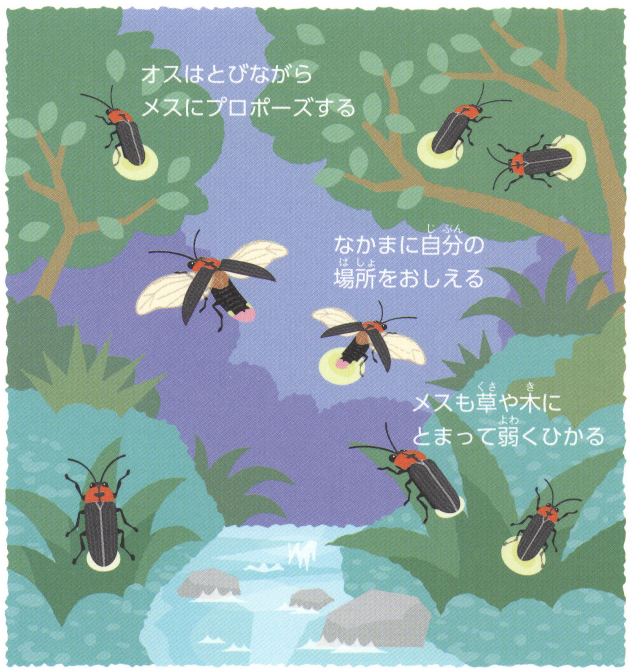
![]()
![]()
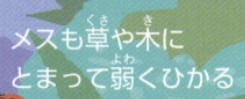
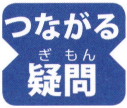
![]()
![]()

![]()
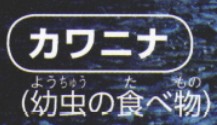
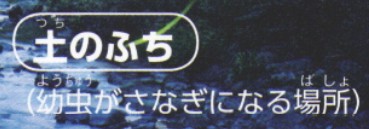
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()


![]()

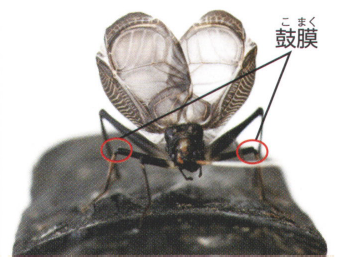
![]()

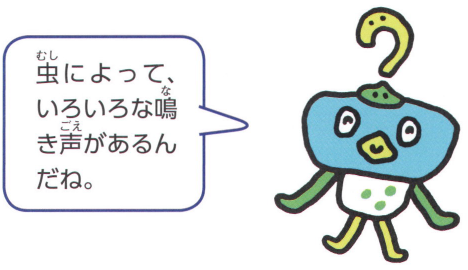
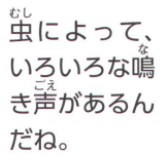
![]()
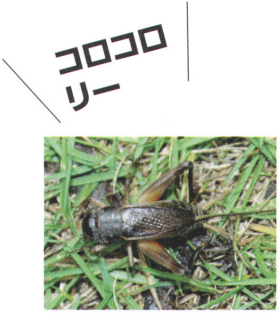

![]()


![]()
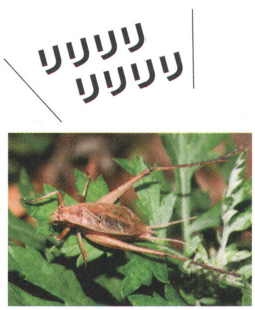

![]()
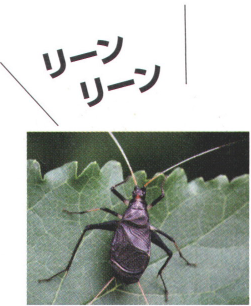
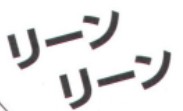
![]()

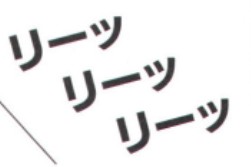
![]()
![]()
![]()
![]()
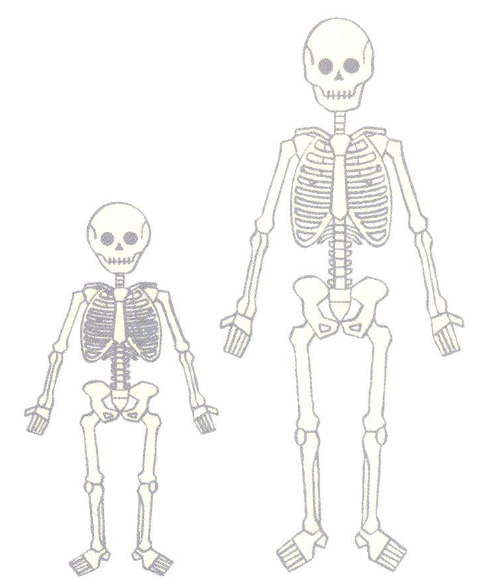
![]()
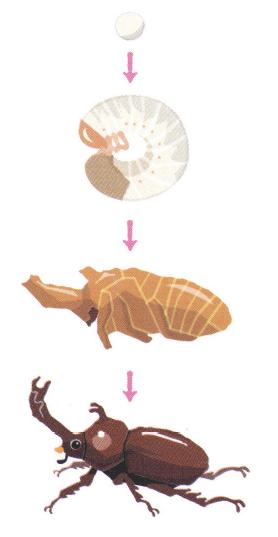
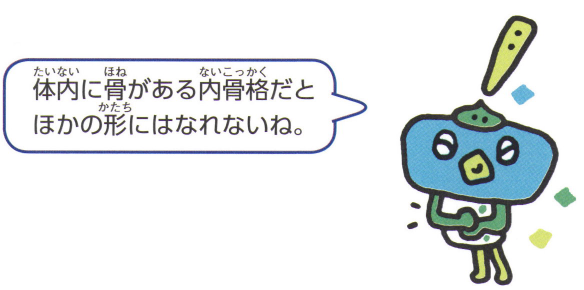
![]()

![]()
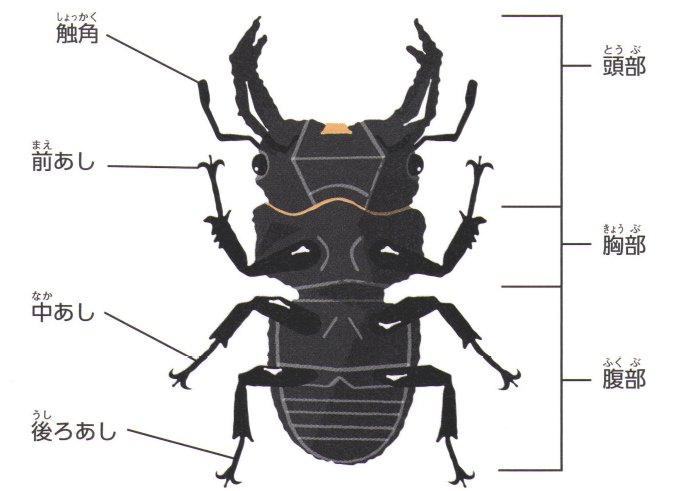
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
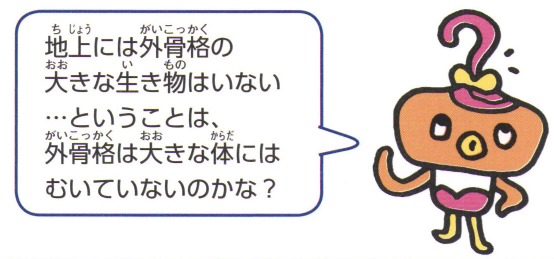
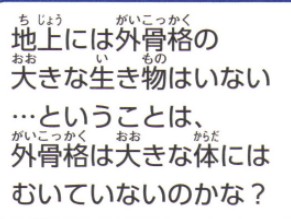
![]()
![]()
![]()


![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
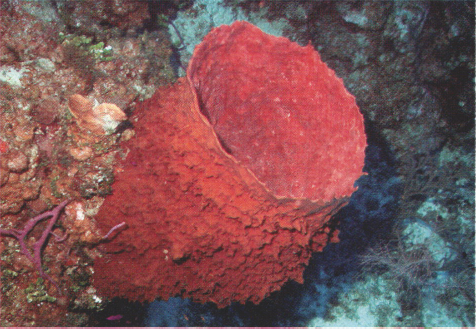
![]()


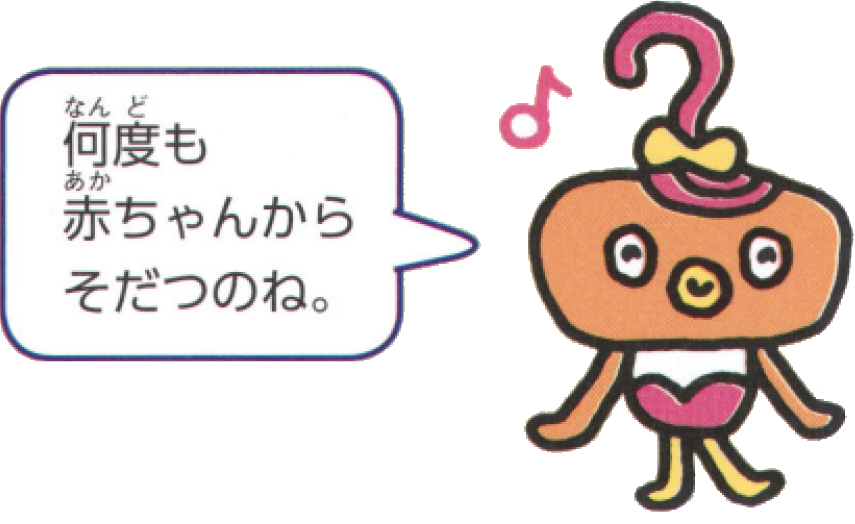
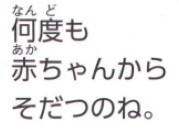
![]()
![]()
![]()
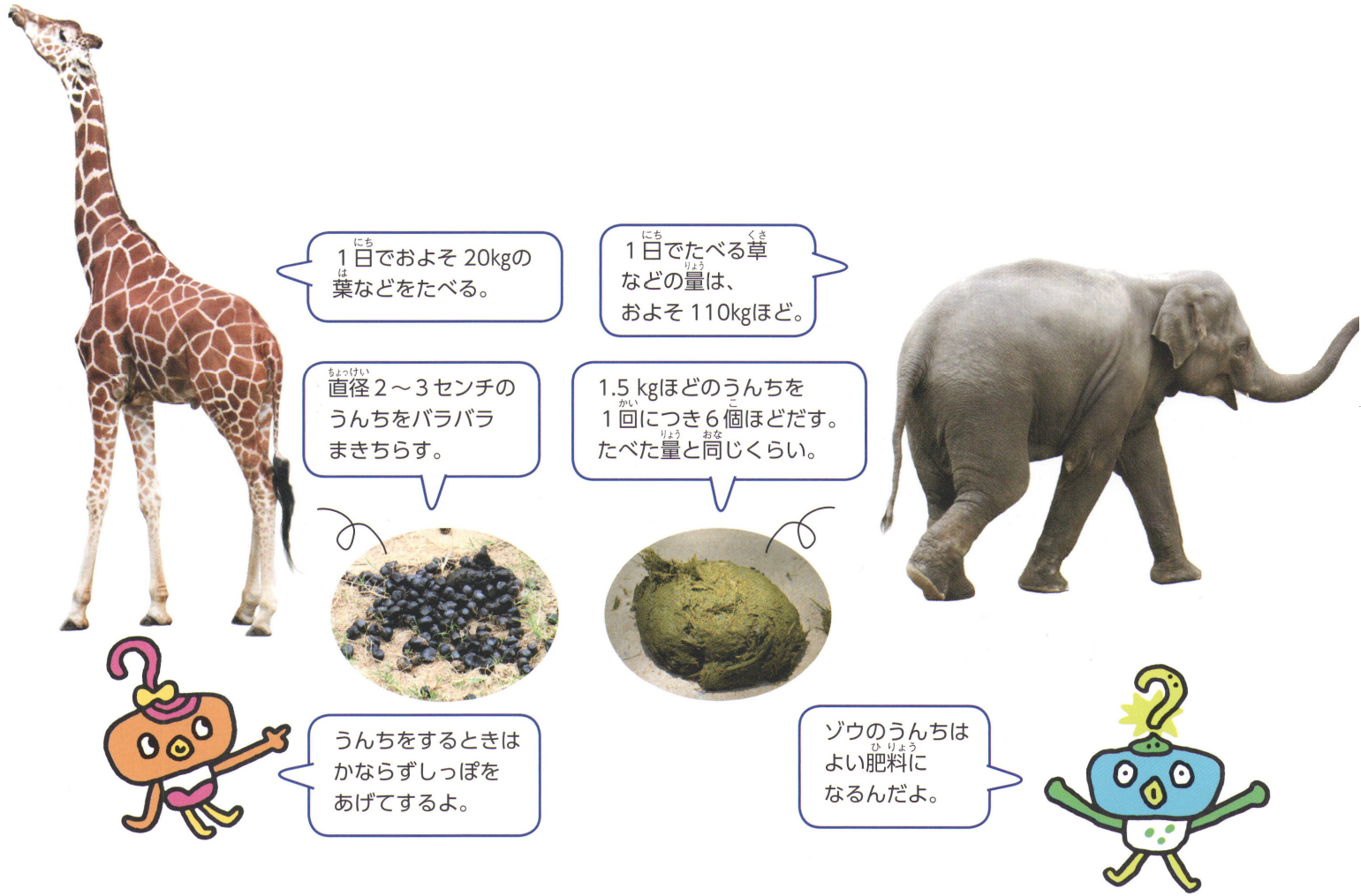
![]()
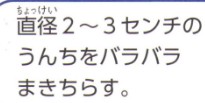
![]()
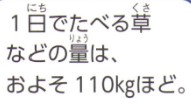
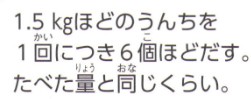
![]()
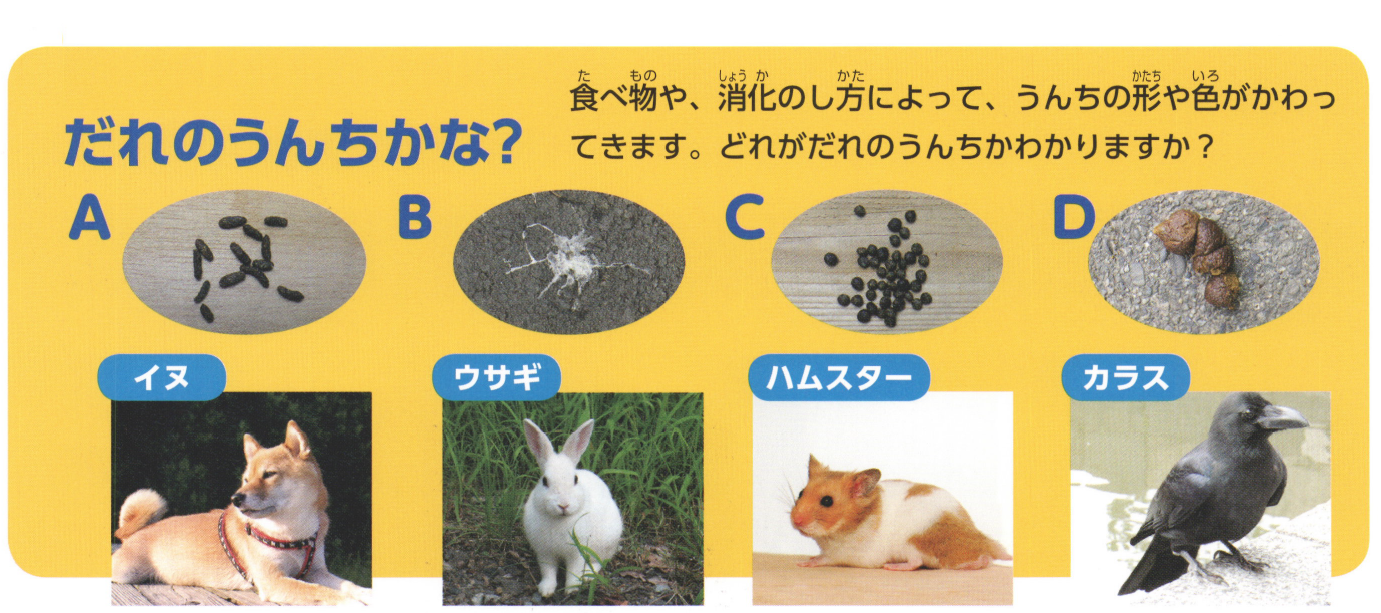
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
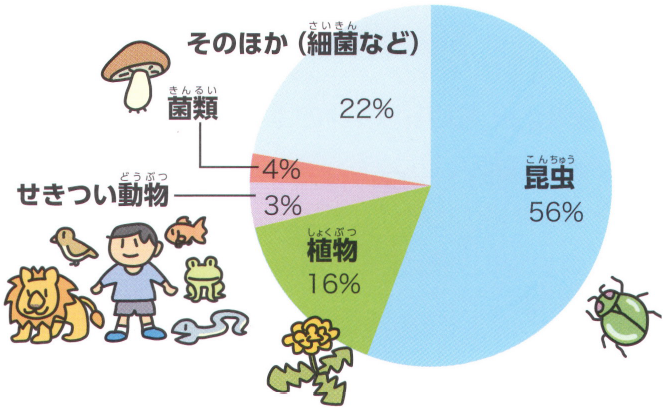
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
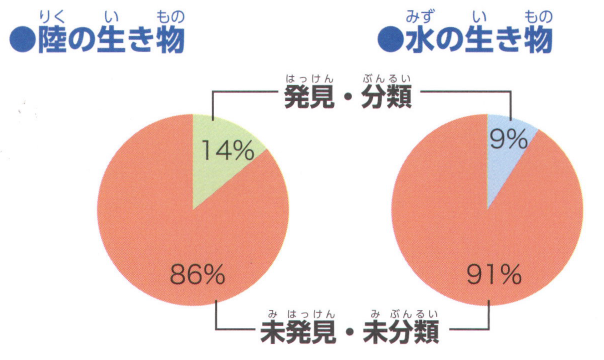
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
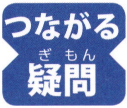
![]()
![]() 大昔に
大昔に
![]()
![]()

![]()
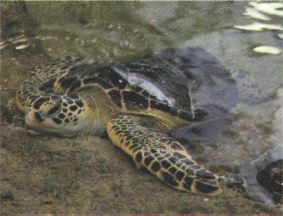
![]()

![]()
![]()
![]()


![]()


![]()

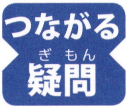
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

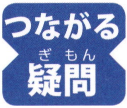
![]()
![]()
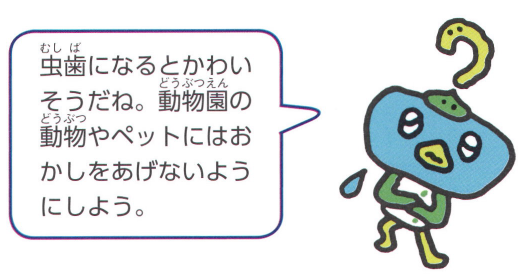
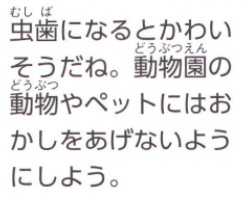
![]()
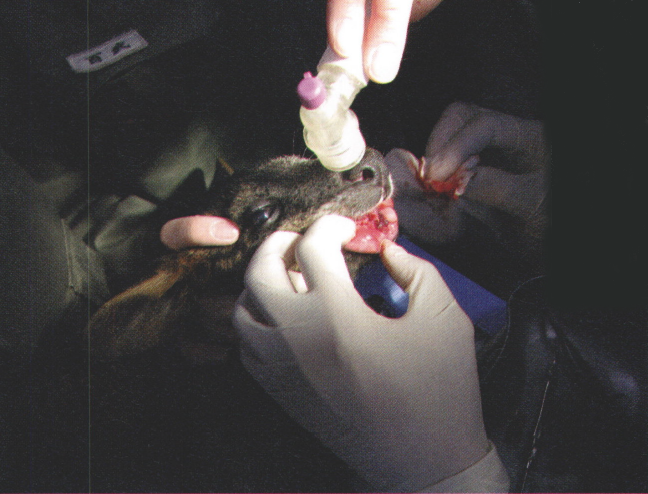
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


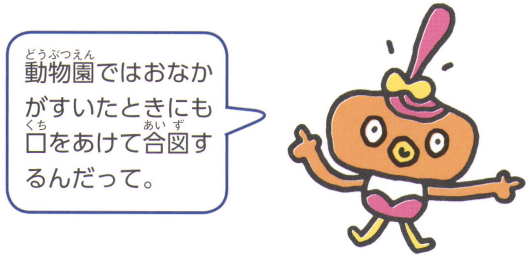
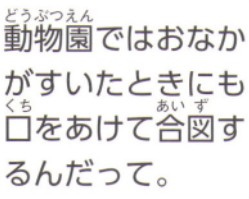
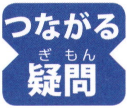
![]()
![]()
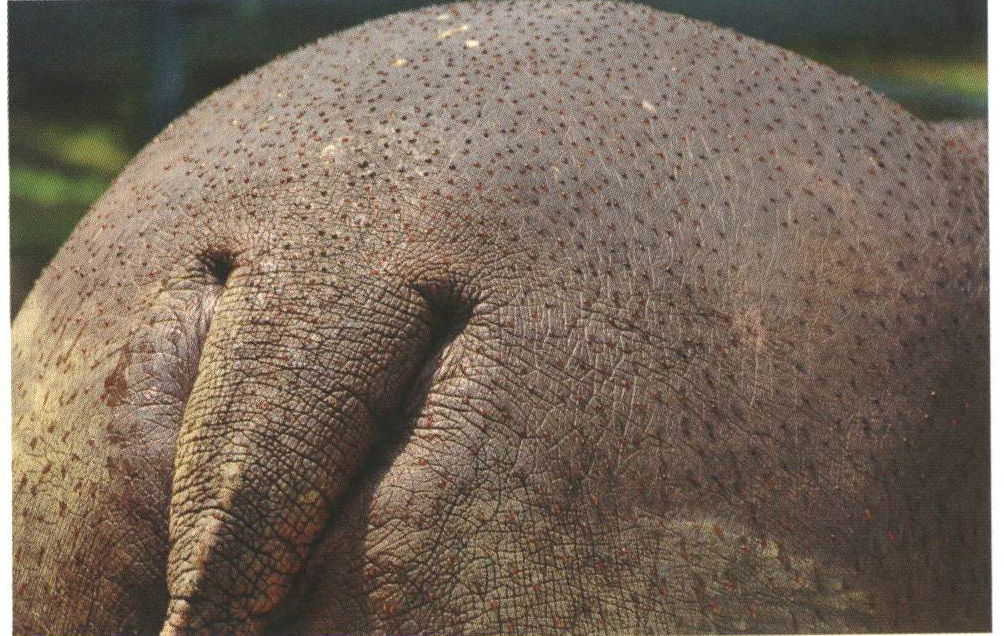
![]()
![]()
![]()

![]()

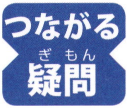
![]()
![]()


![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
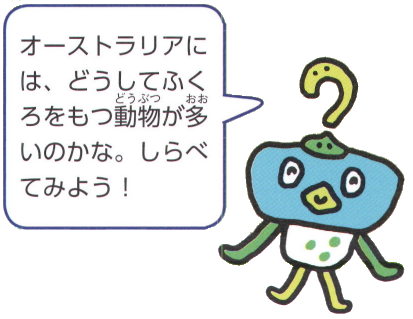
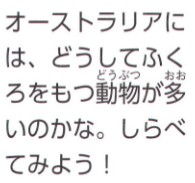
![]()
![]()
![]()
![]()

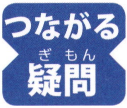
![]()
![]()
![]()
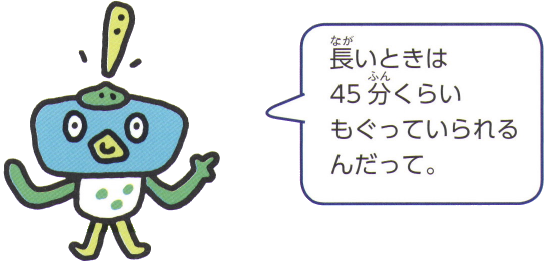
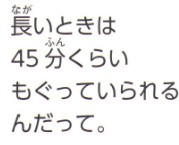
![]()


![]()
![]()
![]()
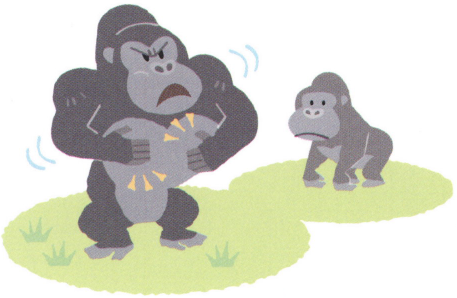
![]()

![]()

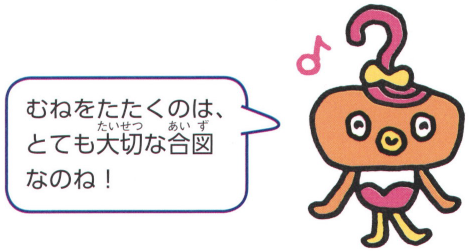
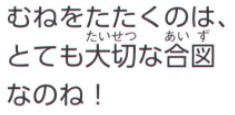

![]()
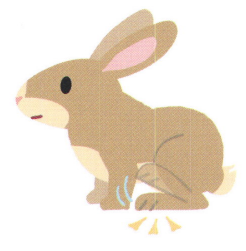
![]()
![]()

![]()
![]()
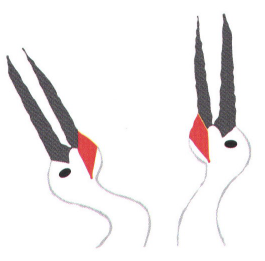
![]()
![]()
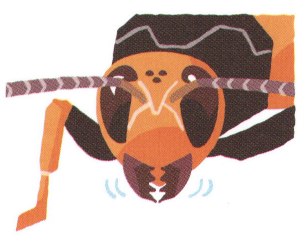
![]()
![]()
![]()
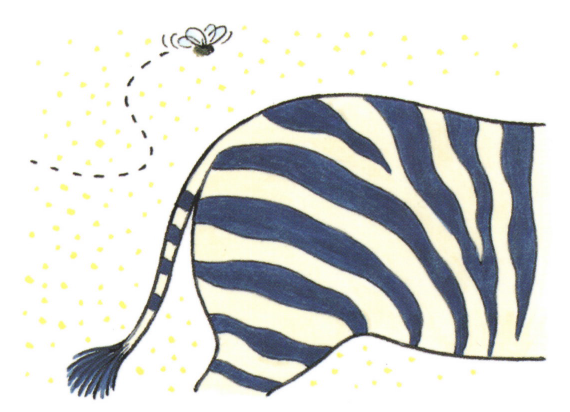
![]()
![]()

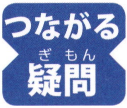
![]()
![]()
![]()




![]()
![]()
![]()

![]()

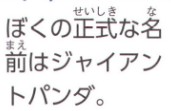
![]()
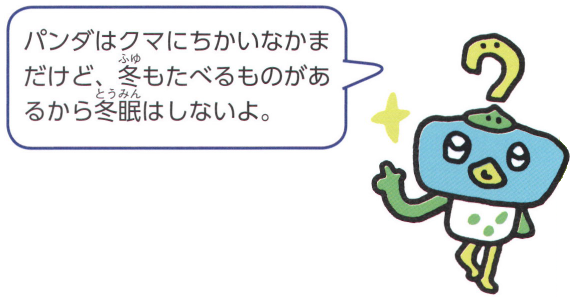
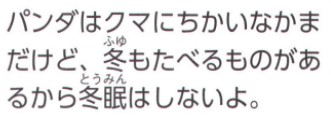
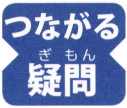
![]()
![]()
![]()

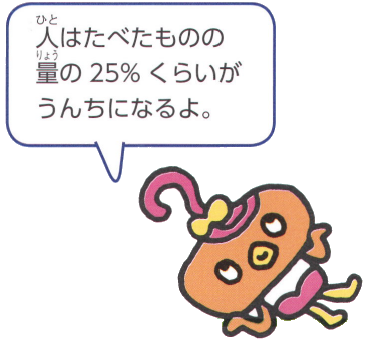
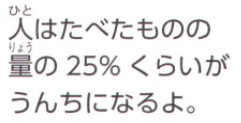
![]()
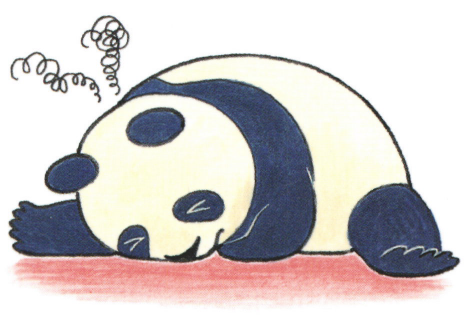
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
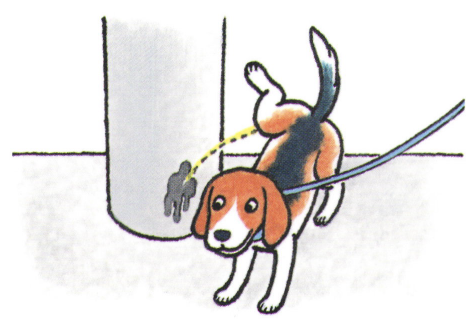
![]()
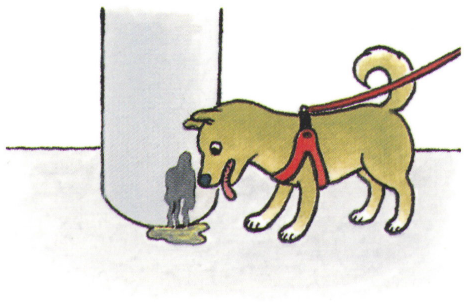
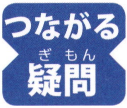
![]()
![]()
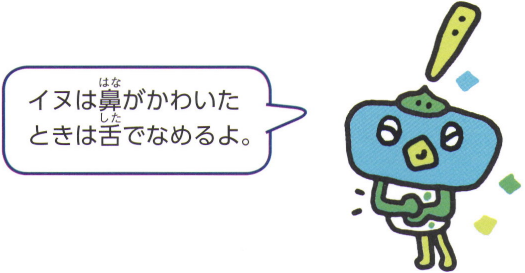
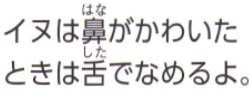
![]()

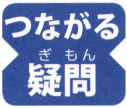
![]()
![]()
![]()

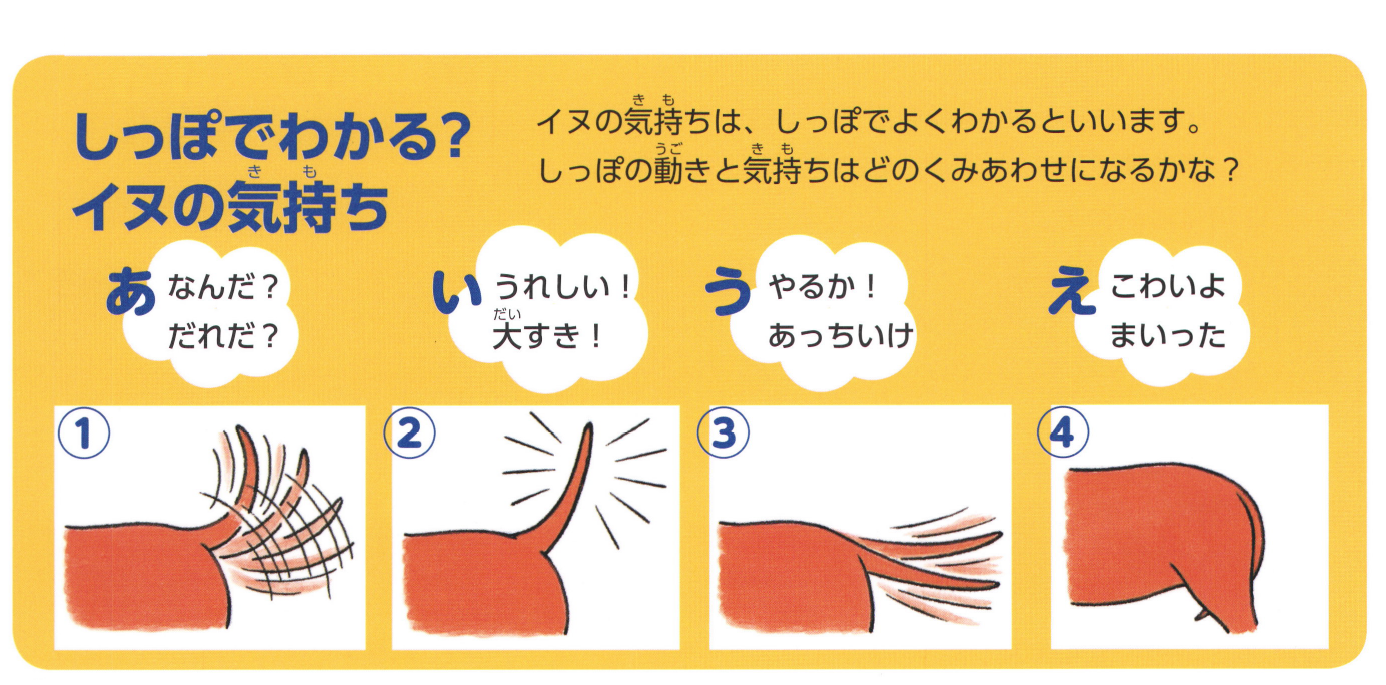
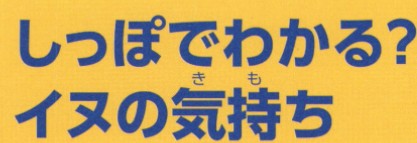
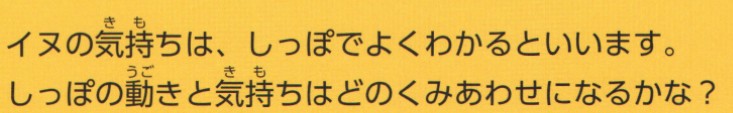
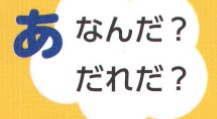
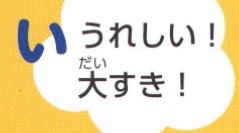
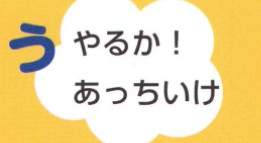
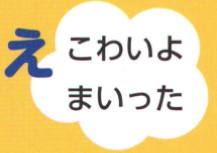
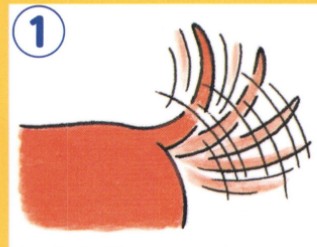
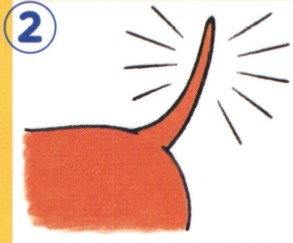
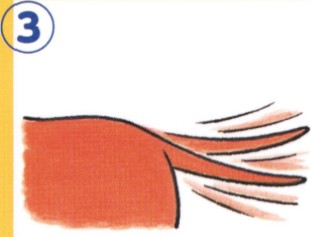
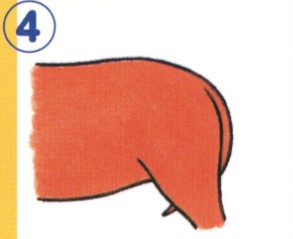
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
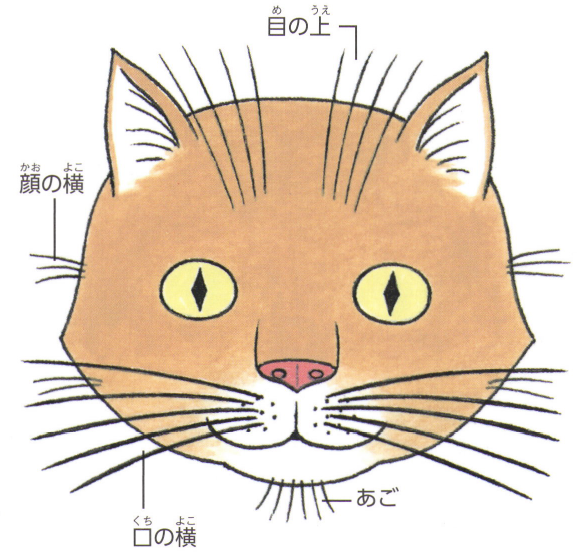
![]()
![]()
![]()
![]()

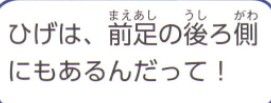

![]()
![]()
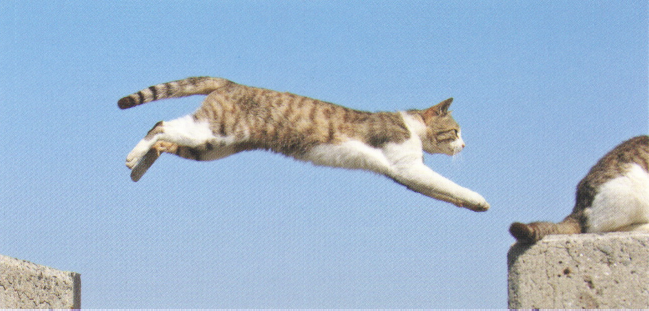
![]()
![]()

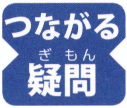
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
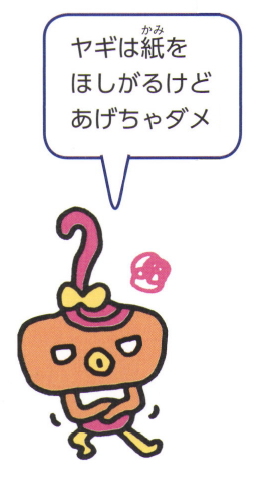
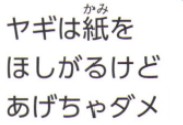
![]()

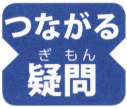
![]()
![]()
![]()
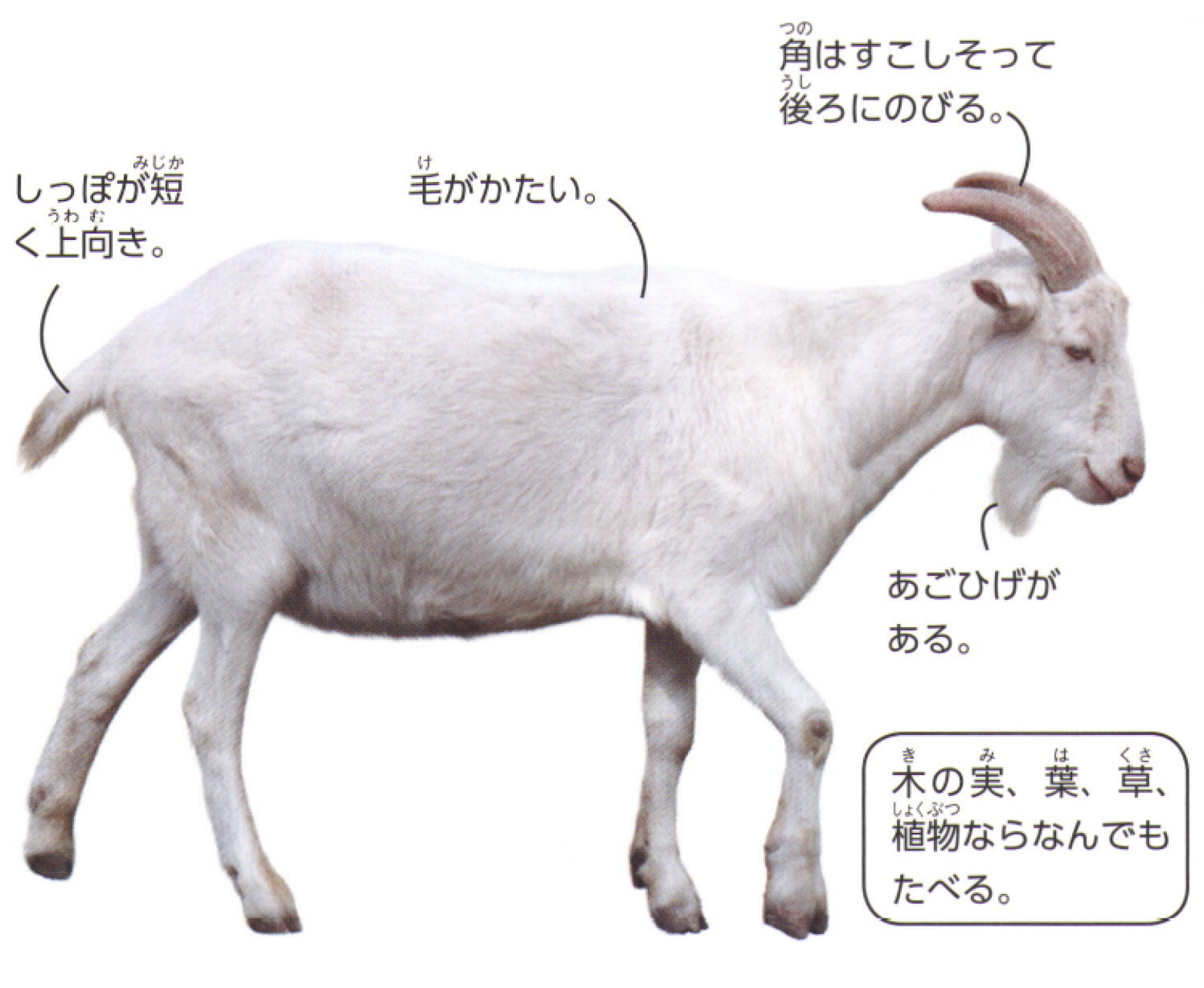
![]()
![]()
![]()
![]()
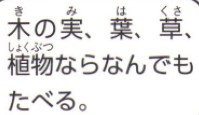
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
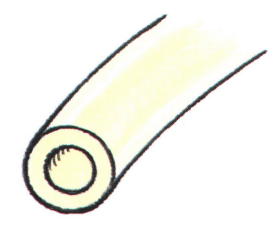
![]()
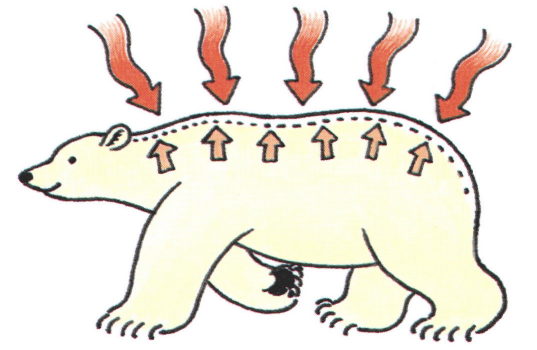
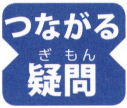
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

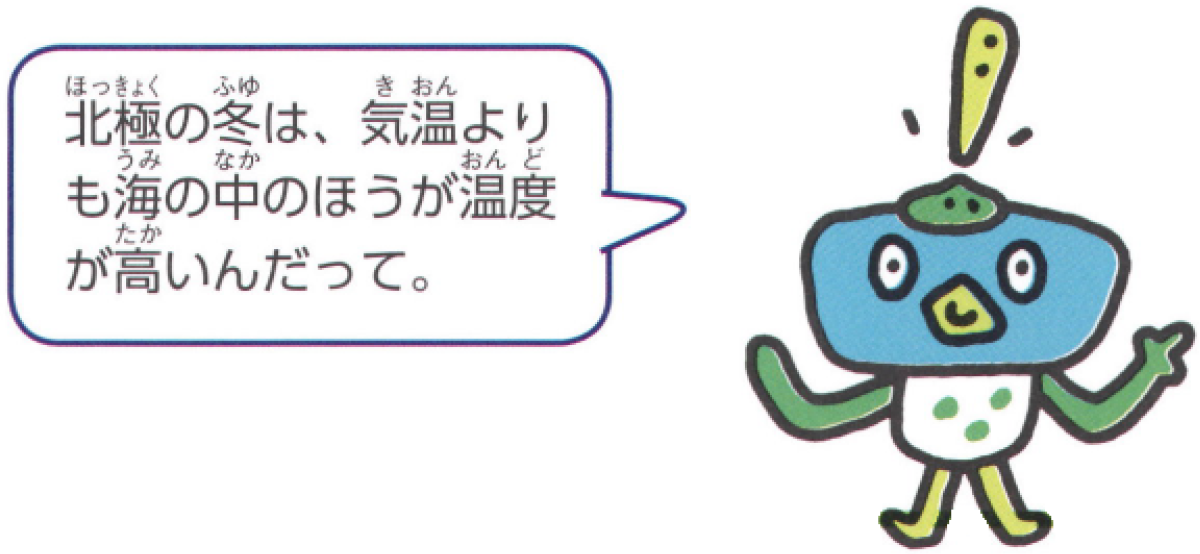
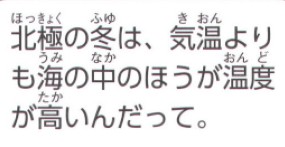
![]()
![]()
![]()
![]()
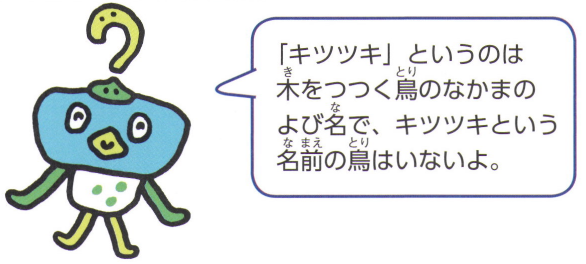
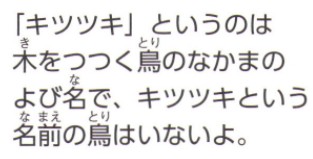
![]()

![]()

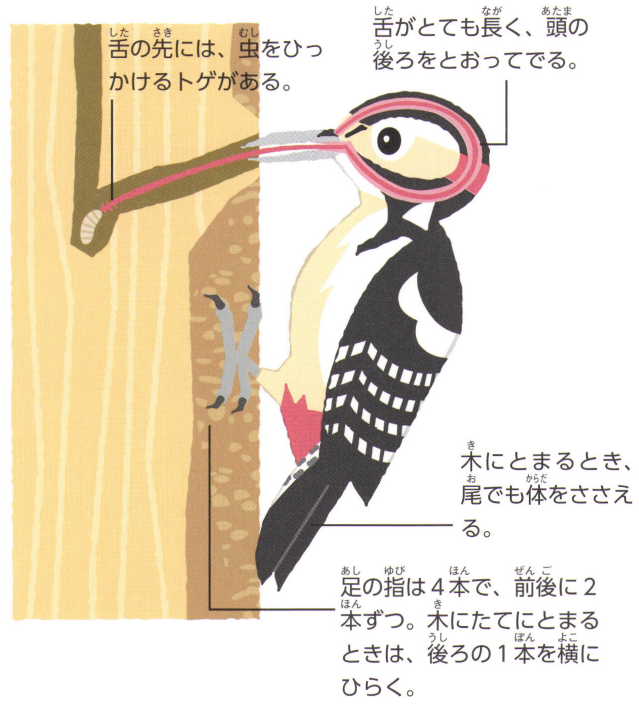
![]()
![]()
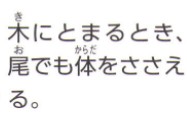
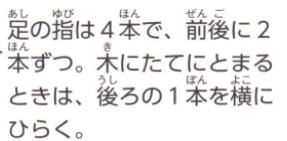

![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
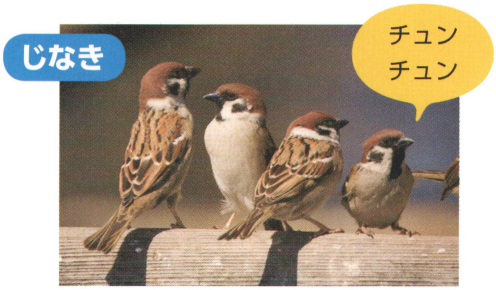
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
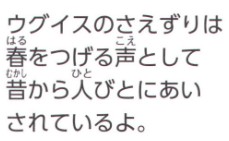
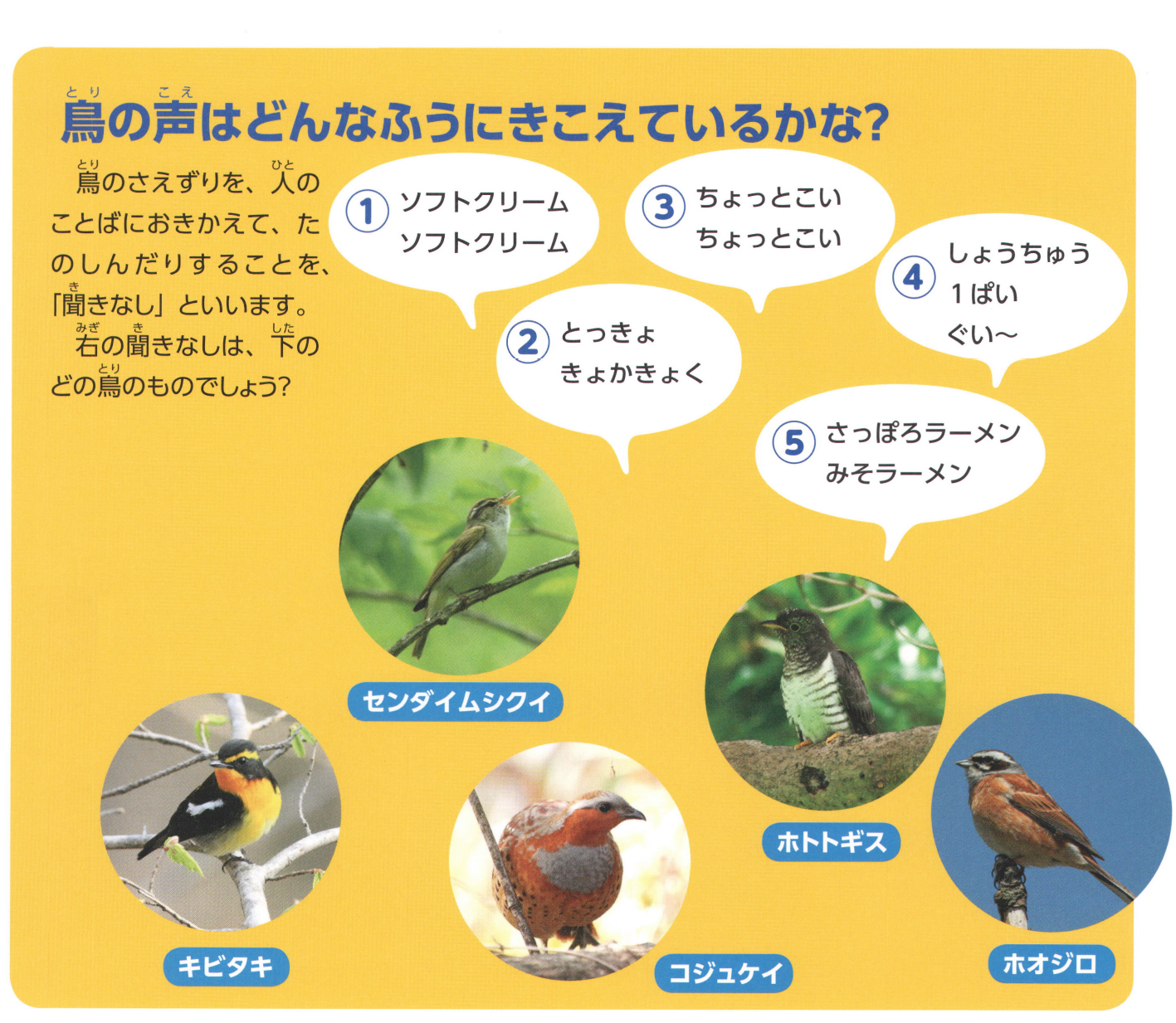
![]()
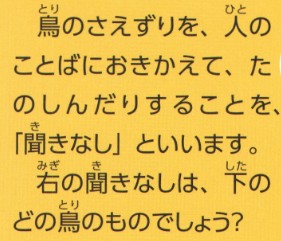
![]()
![]()
![]()
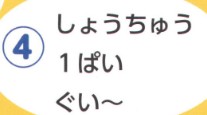
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

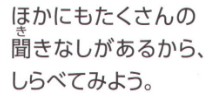
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
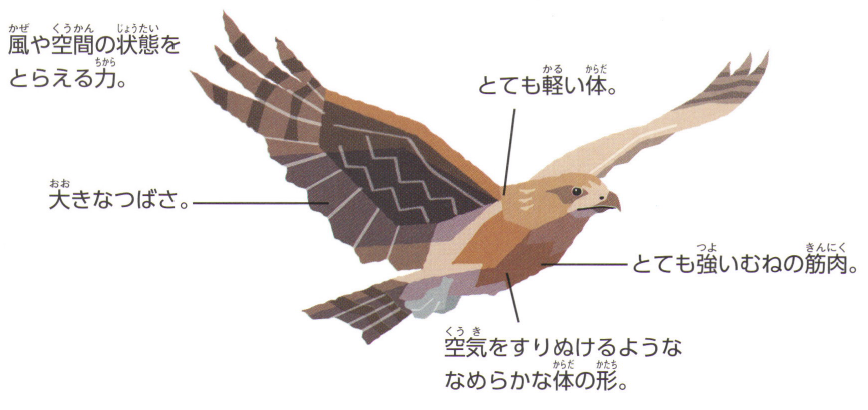
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
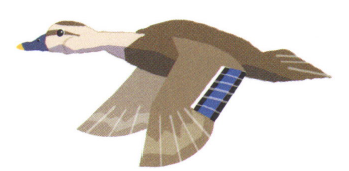
![]()

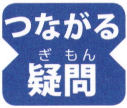
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
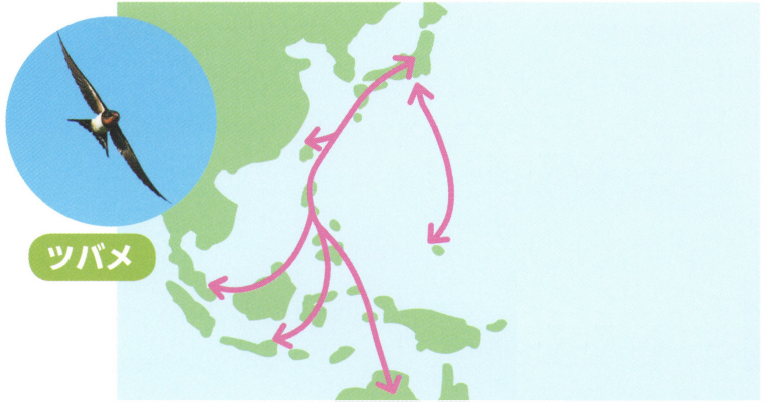
![]()

![]()
![]()

![]()
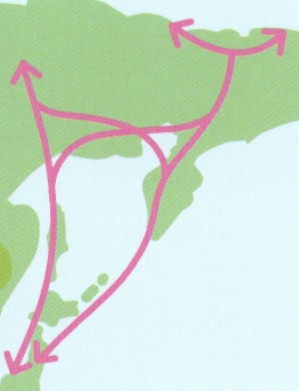
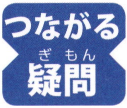
![]()
![]()
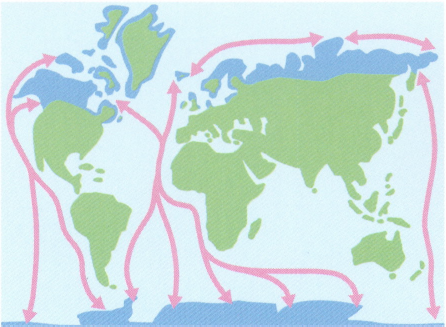



![]()
![]()
![]()


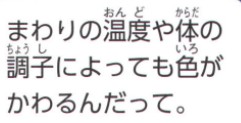
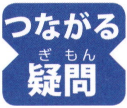
![]()
![]()
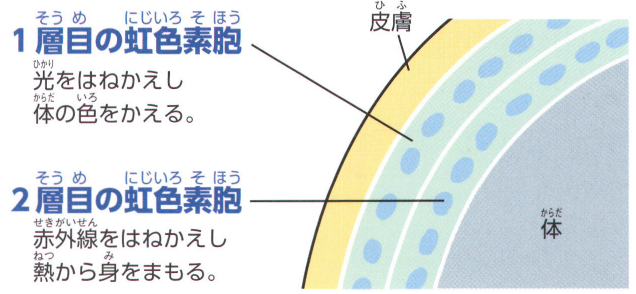
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
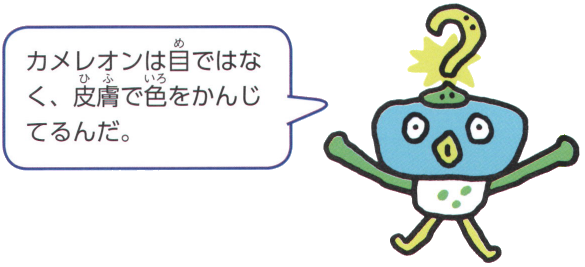
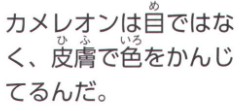

![]()
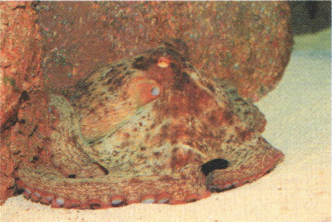
![]()
![]()
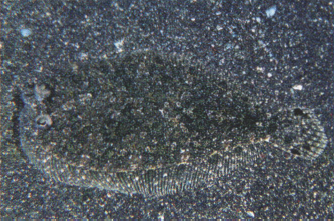
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

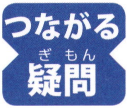
![]()
![]()
![]()
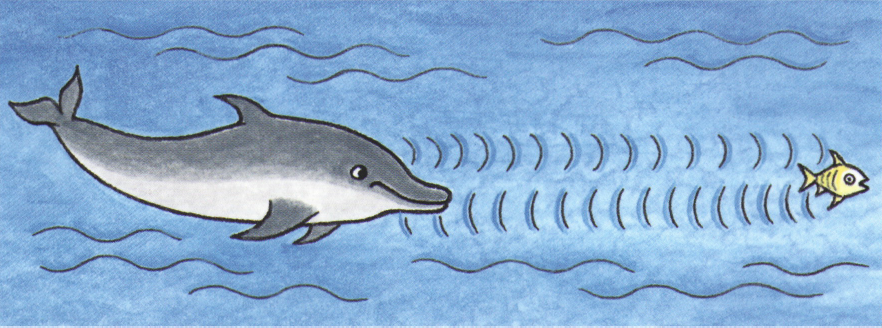
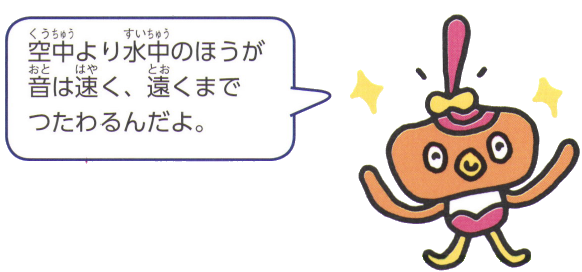
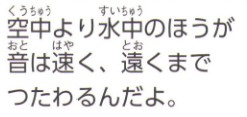
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
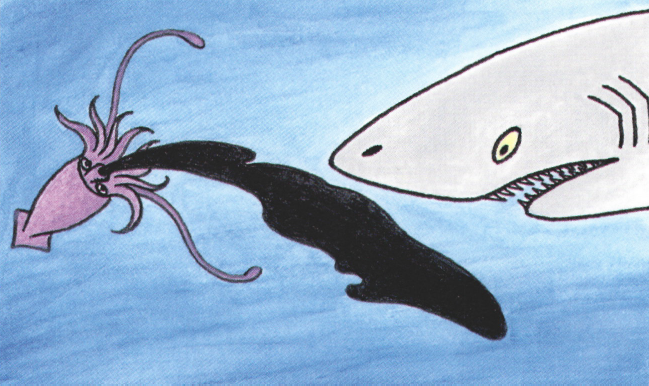
![]()


![]()
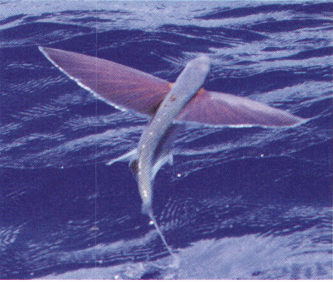
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
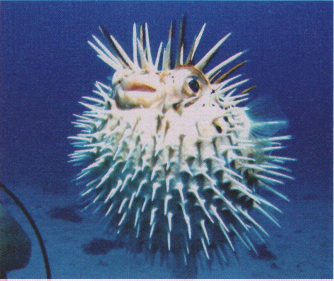
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
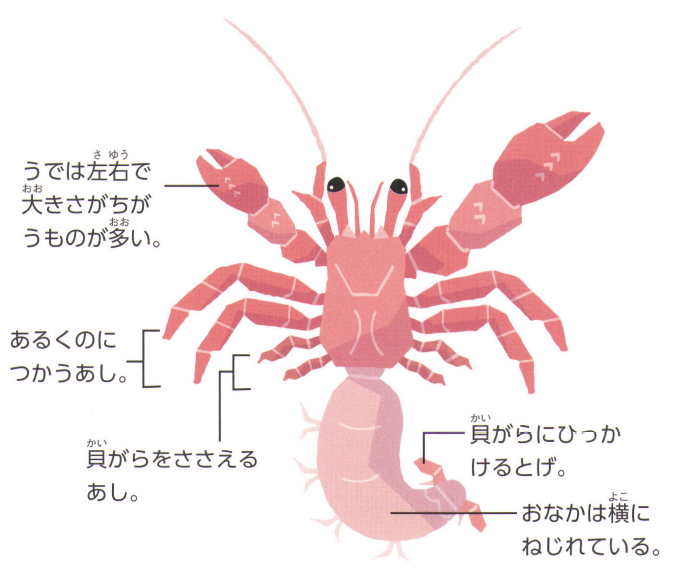
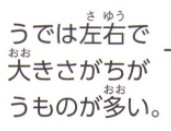
![]()
![]()
![]()
![]()


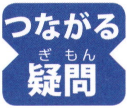
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
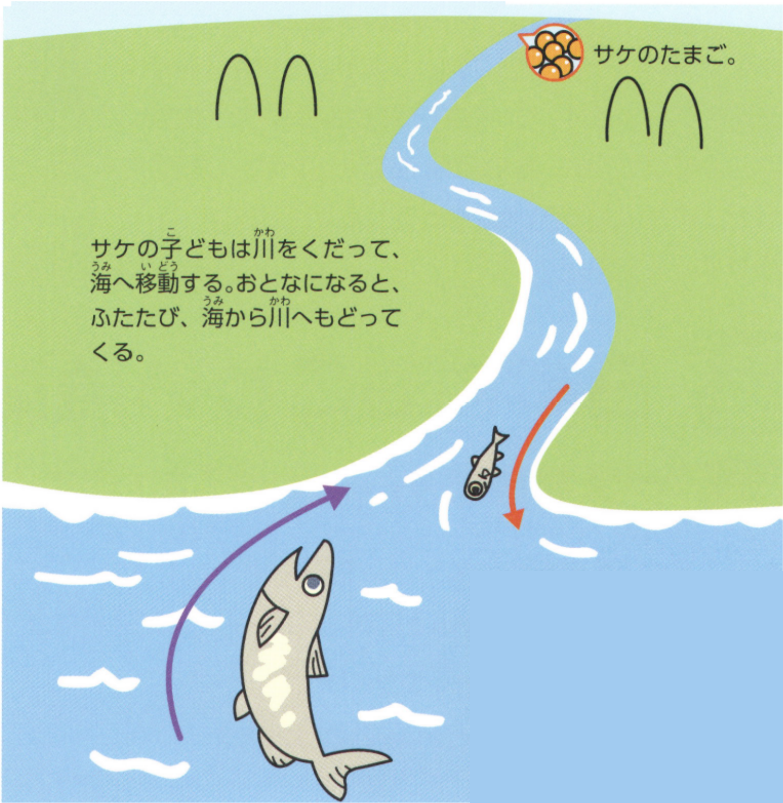
![]()
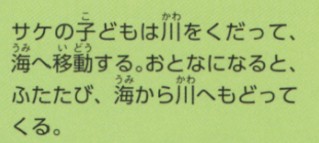
![]()
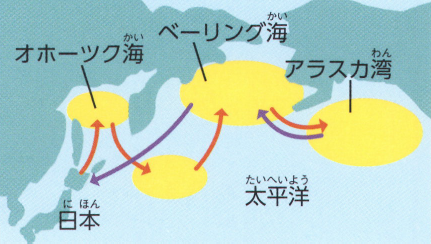
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
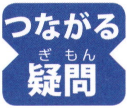
![]()
![]()
![]()
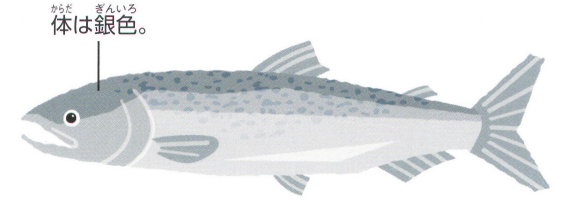
![]()
![]()
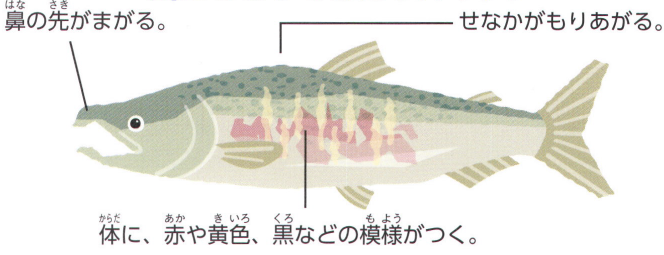
![]()
![]()
![]()
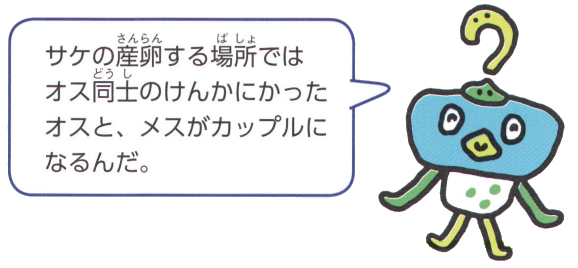
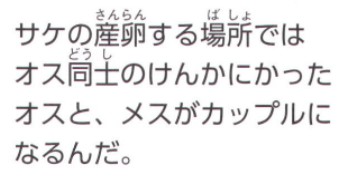
![]()
![]()
![]()

![]()

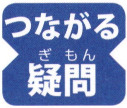
![]()
![]()
![]()

![]()
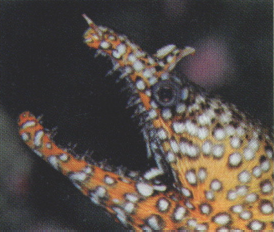
![]()


![]()

![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
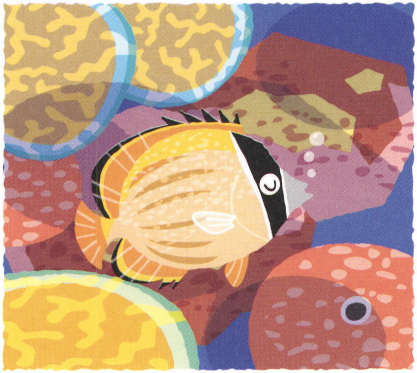
![]()
![]()
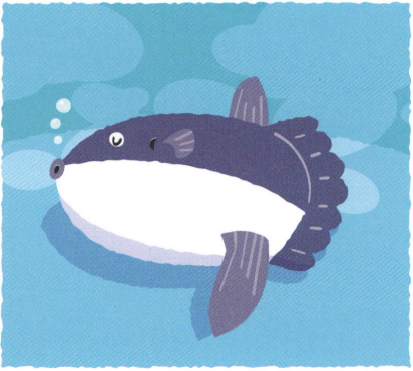
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
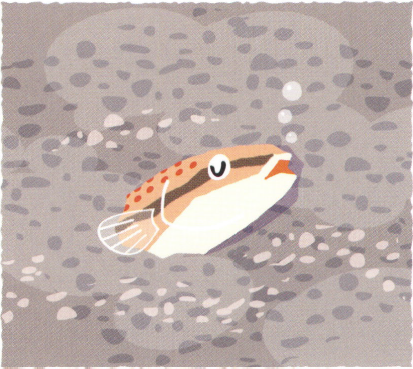
![]()
![]()
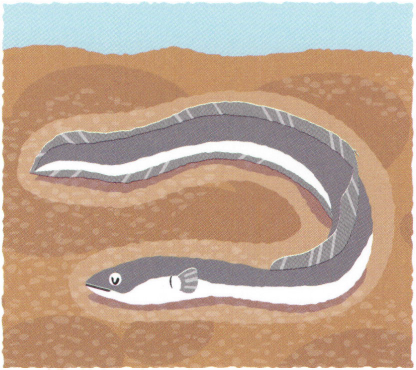
![]()
![]()
![]()
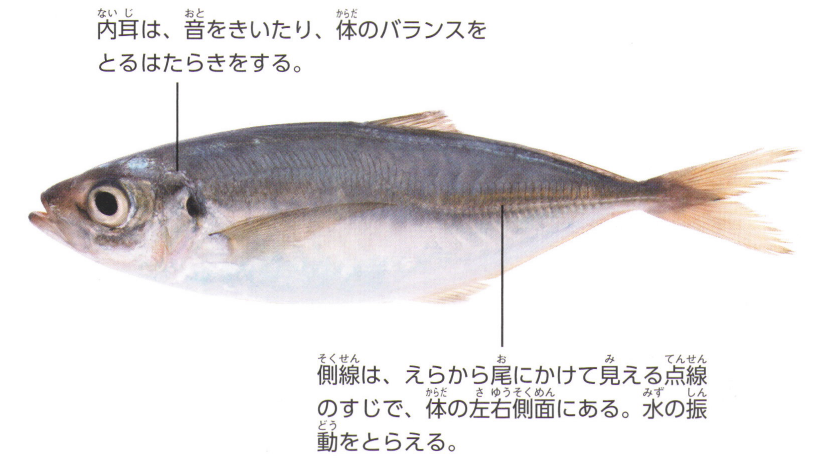
![]()
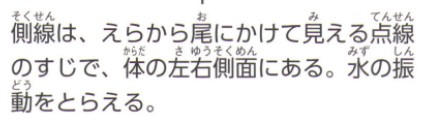
![]() 魚にも
魚にも![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
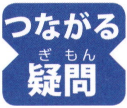
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
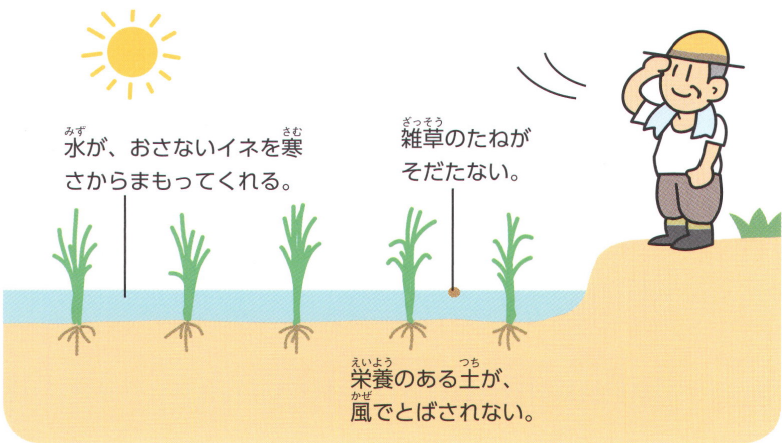
![]()
![]()
![]()
![]()
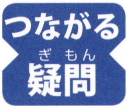
![]()
![]()
![]()
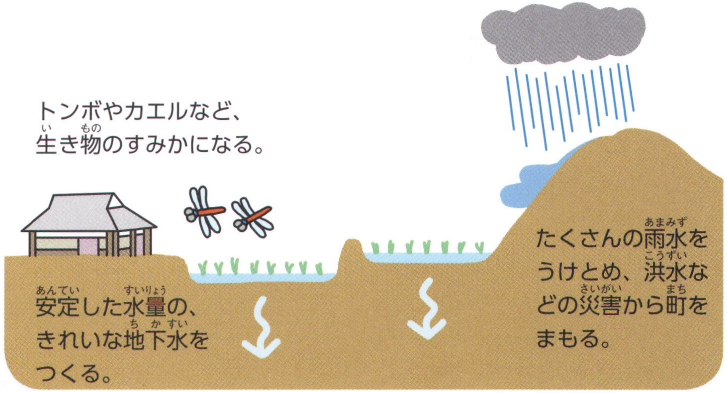
![]()
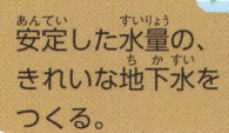
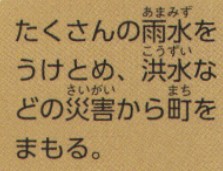
![]()
![]()
![]()


![]()
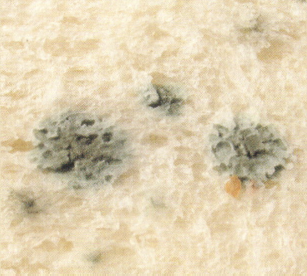
![]()

![]()

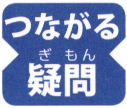
![]()
![]()
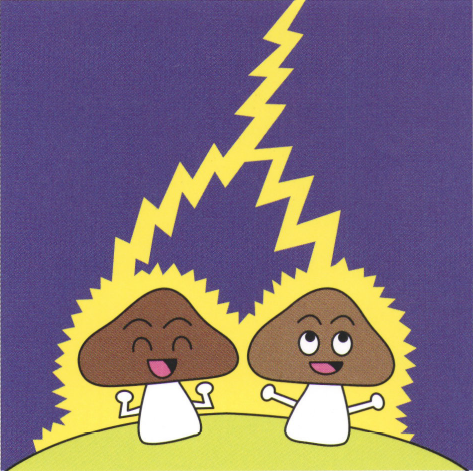
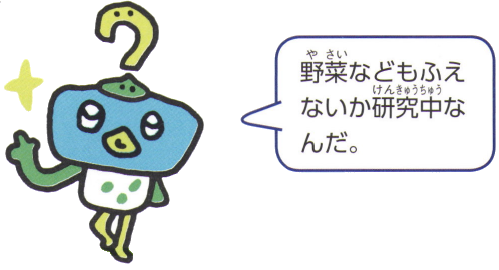
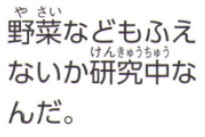
![]()
![]()
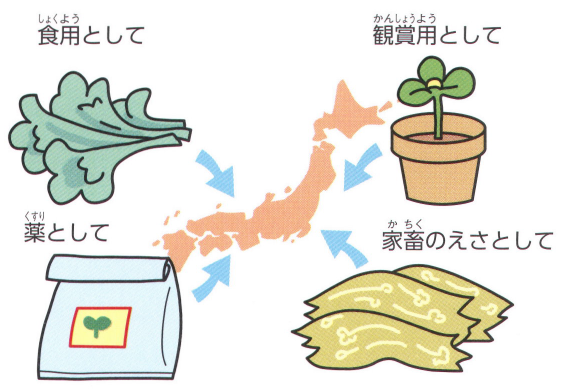
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()

![]()
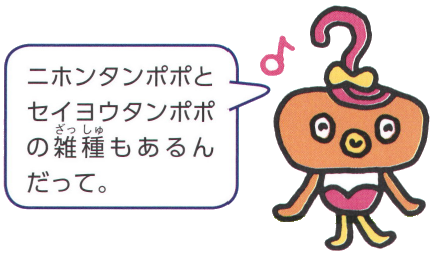
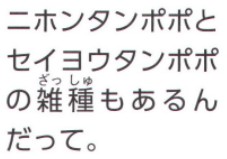
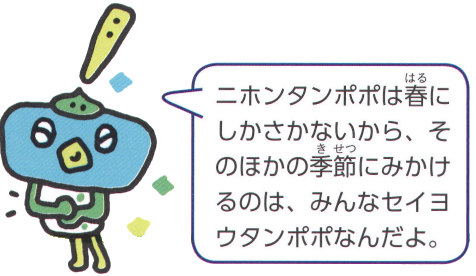
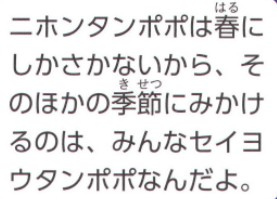
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

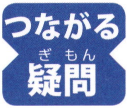
![]()
![]()


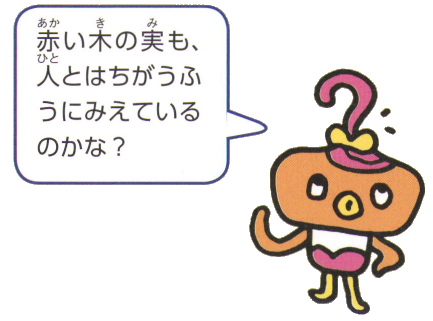
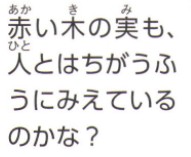
![]()
![]()
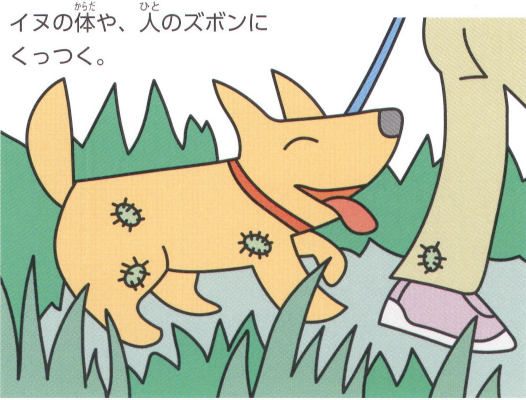
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
![]()

![]() ライオンゴロシの
ライオンゴロシの

![]()
![]()
![]()
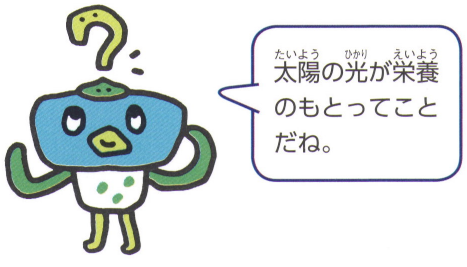
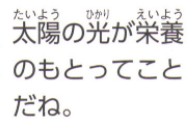
![]()
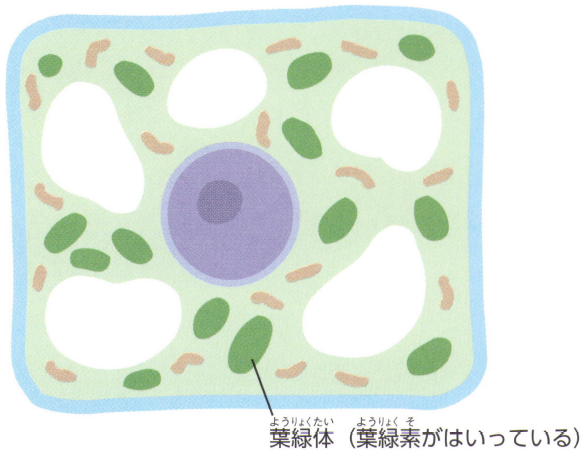
![]()
![]()
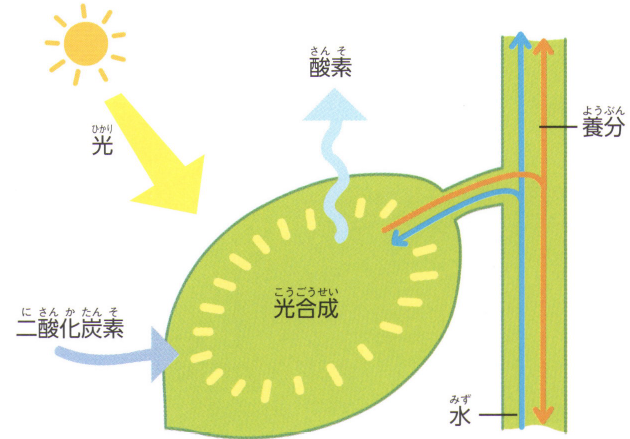
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
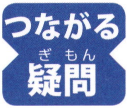
![]()
![]()
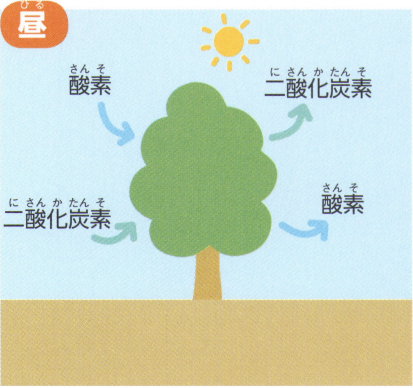
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
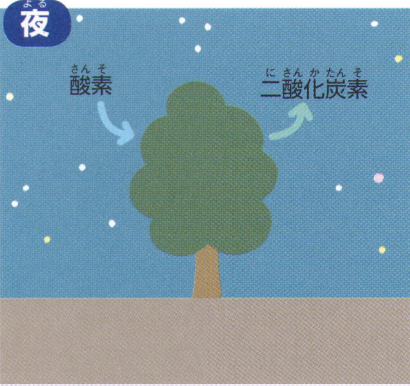
![]()
![]()
![]()

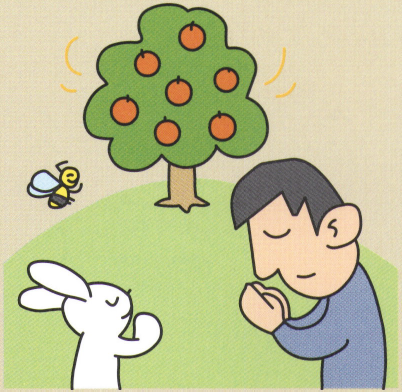
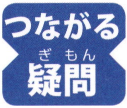
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
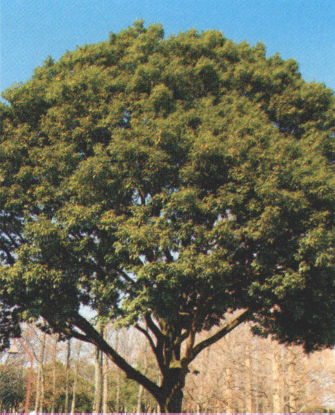
![]()
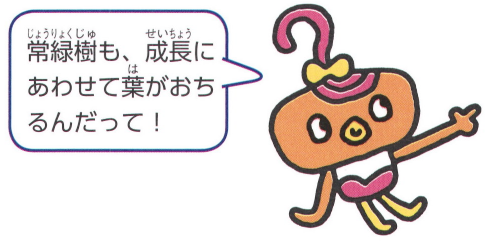
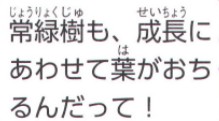
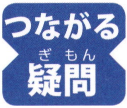
![]()
![]()
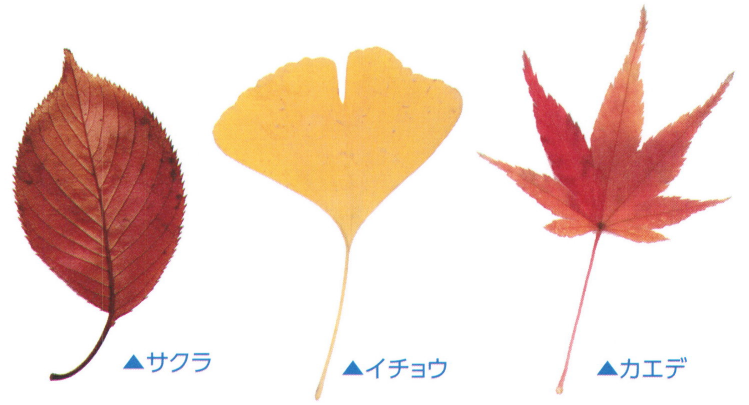
![]()
![]()
![]()

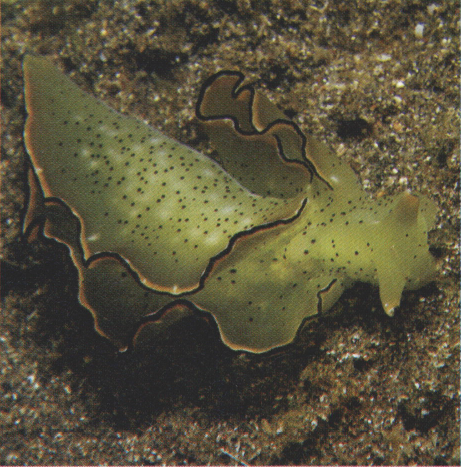
![]()
![]()
![]()
![]()
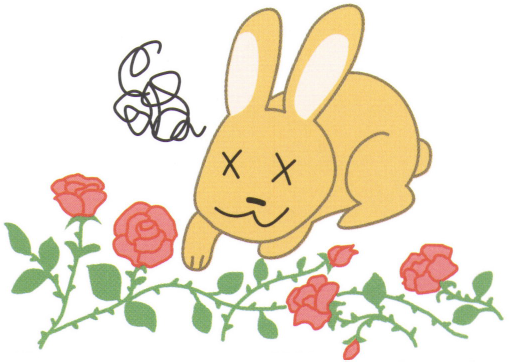
![]()
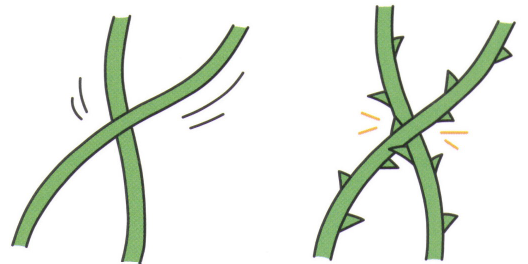

![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

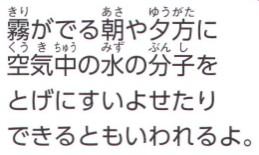
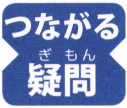
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()


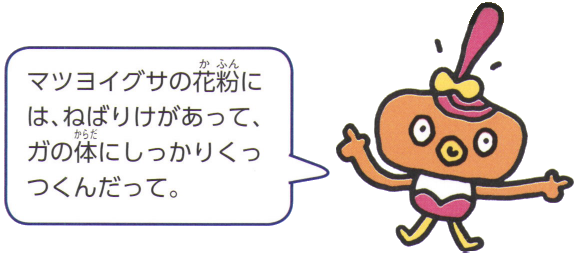
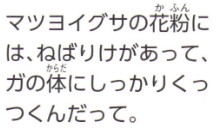


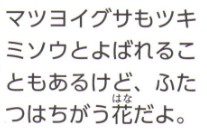
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
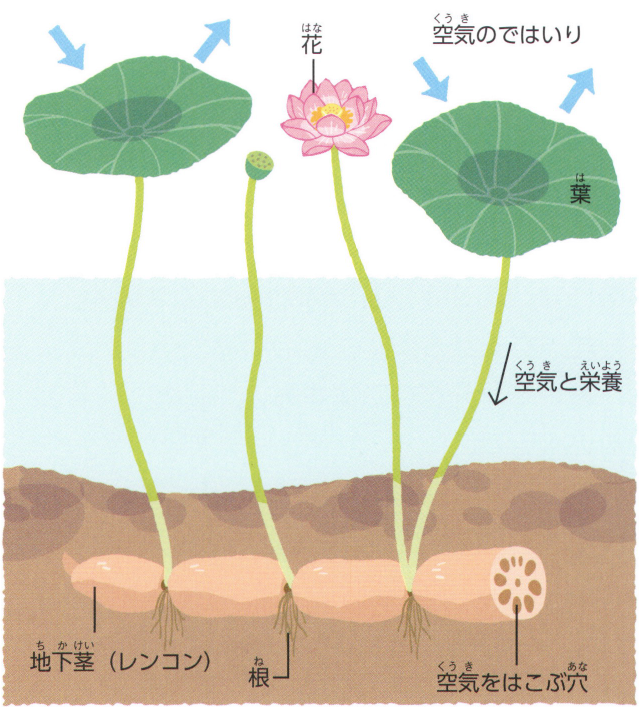
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
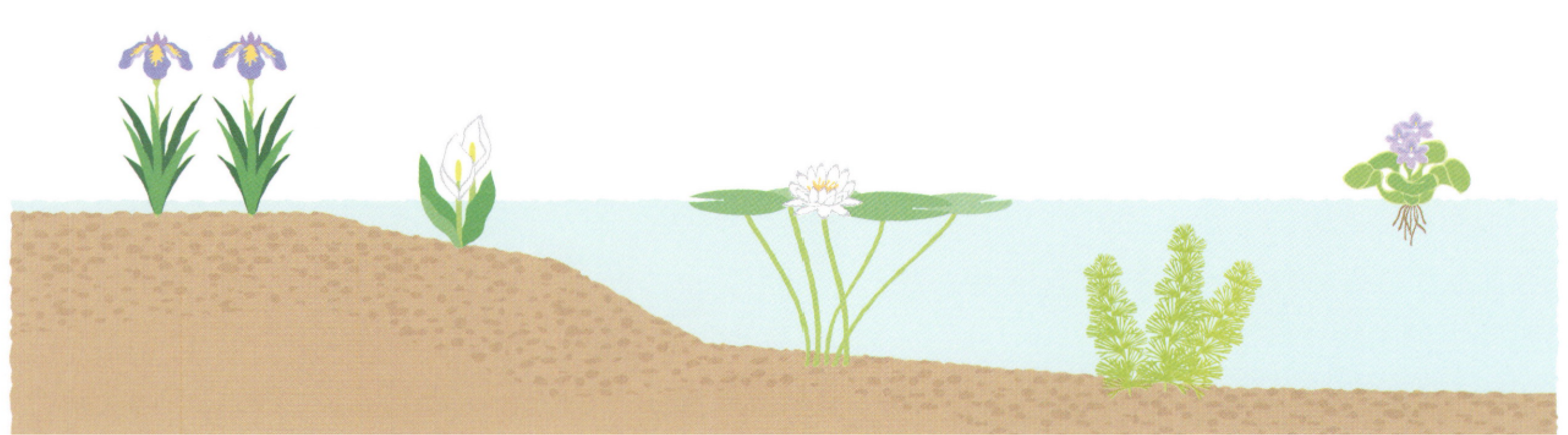
![]()

![]()

![]()

![]()
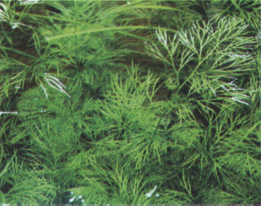
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
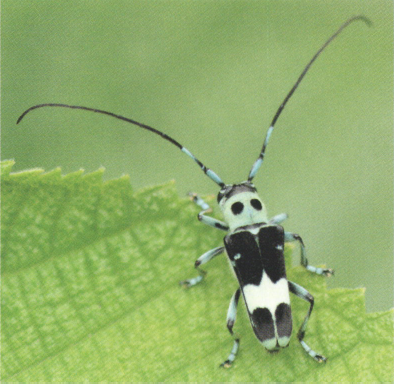
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() アゲハチョウ
アゲハチョウ
![]() ツマグロ
ツマグロ
![]()
![]() アゲハ
アゲハ
![]() クスサン
クスサン
![]()
![]()
![]()
![]()
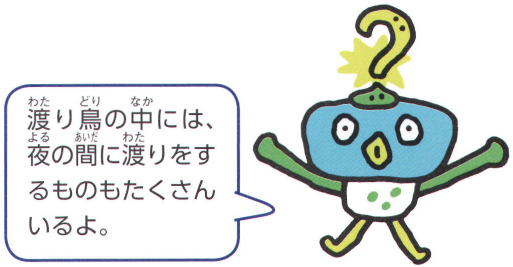
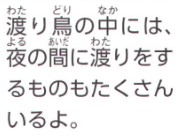
![]()
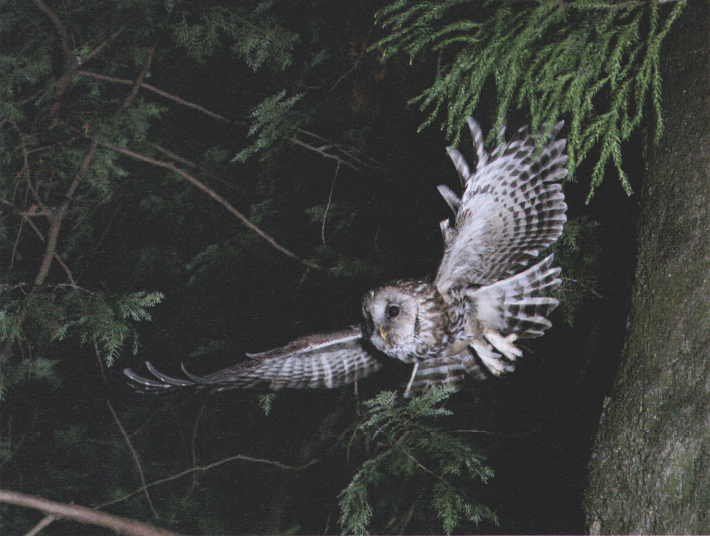
![]()
![]()
![]()
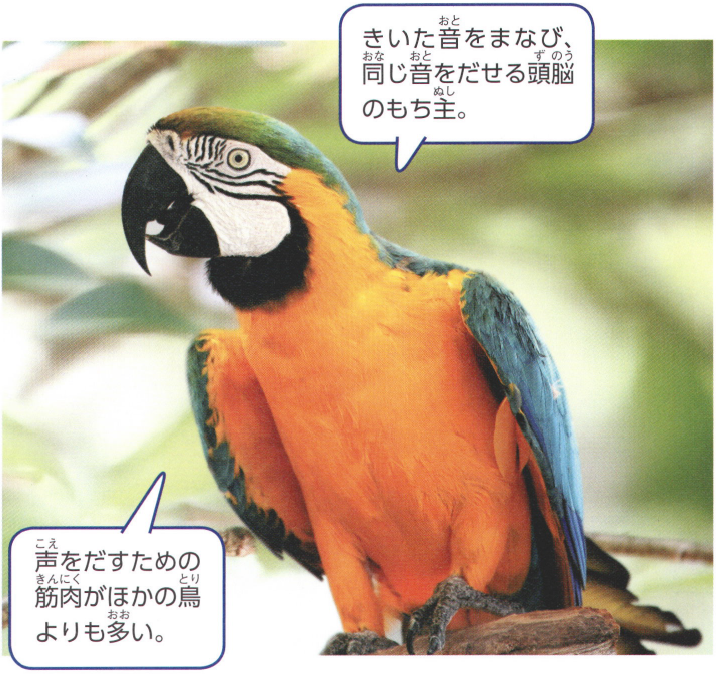
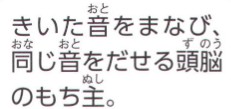
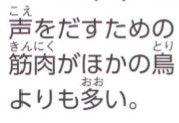
![]()
![]()

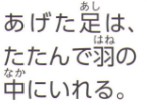
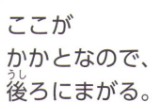
![]()
![]()
![]() ねて
ねて
![]()
![]()
![]()
![]()
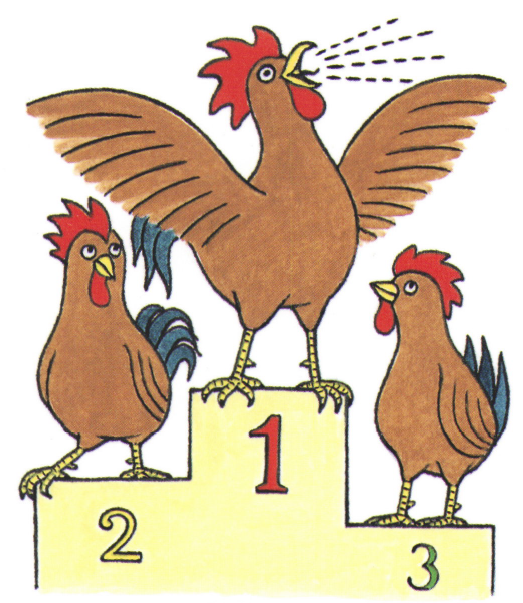
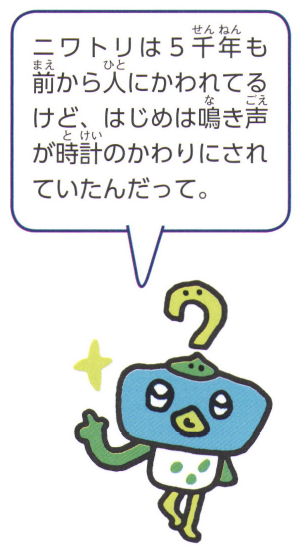
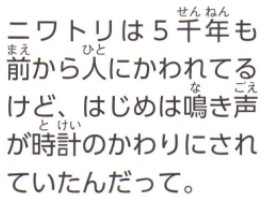
![]()
![]()
![]()
![]()
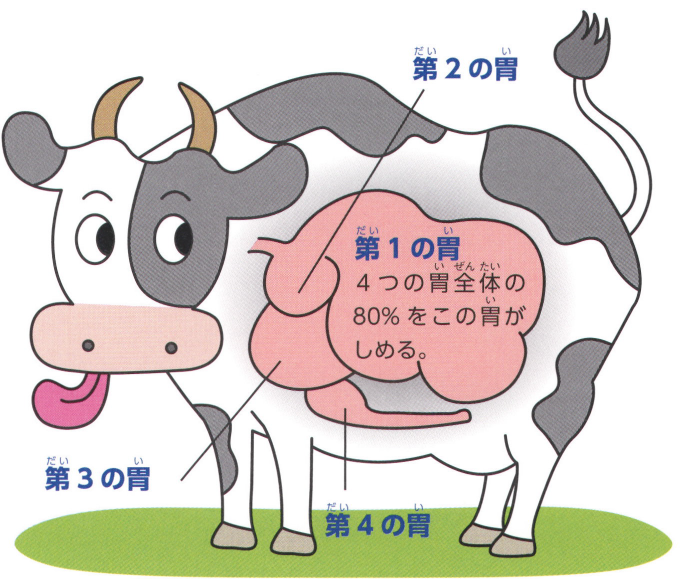
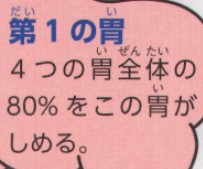
![]()
![]()
![]()
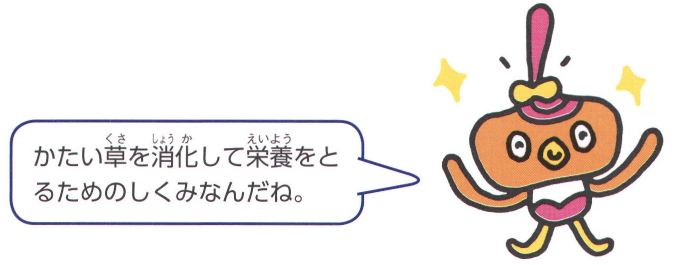
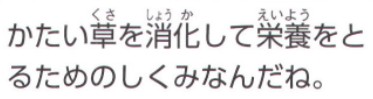
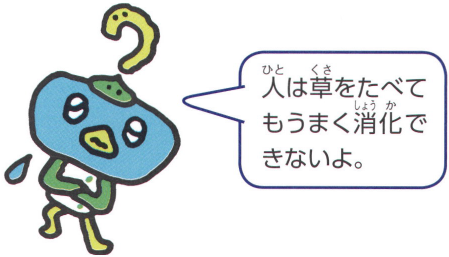
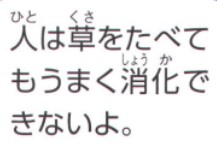
![]()
![]()
![]()

![]()
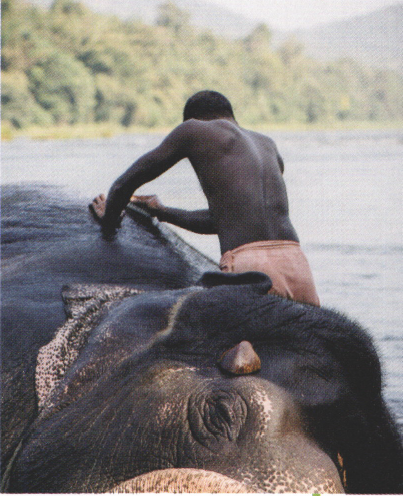
![]()
![]()
![]() 砂漠に
砂漠に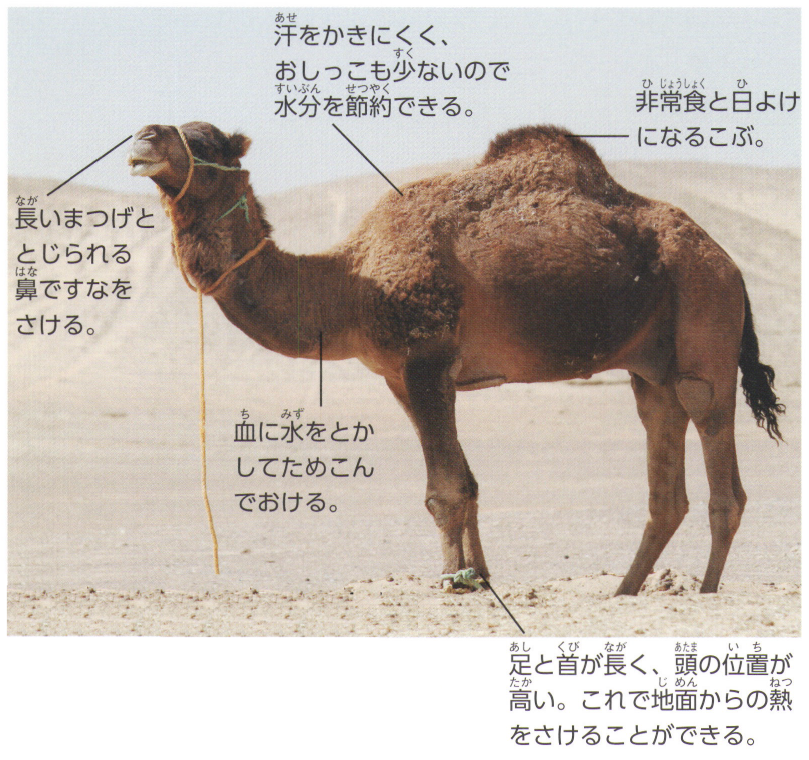
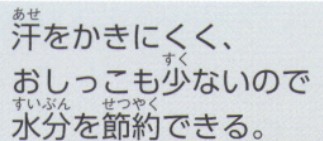
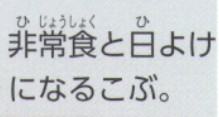
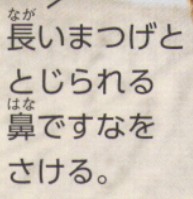
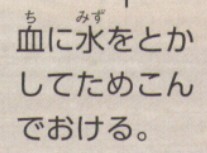
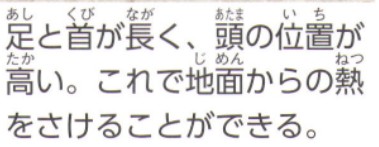
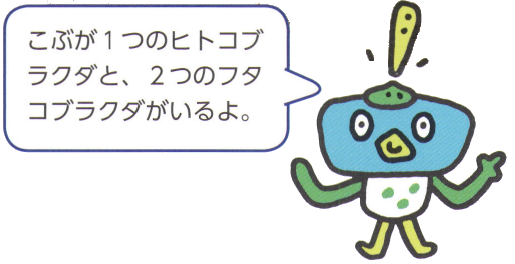
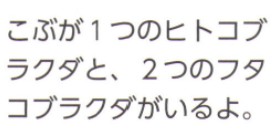
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

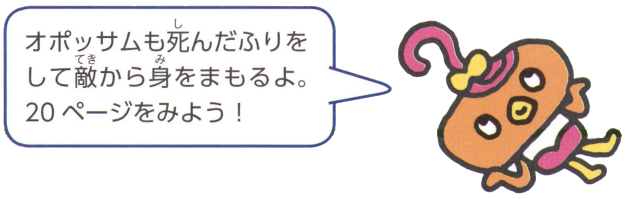
![]()
![]()
![]()
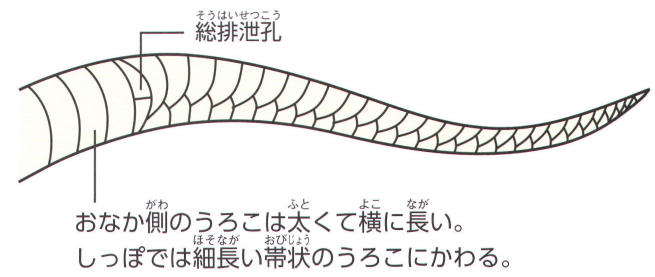
![]()
![]()
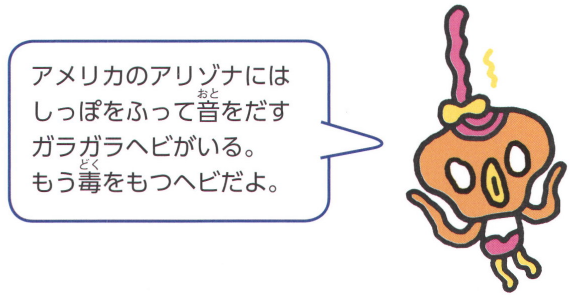
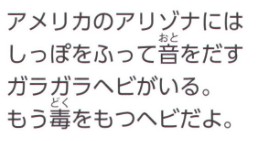

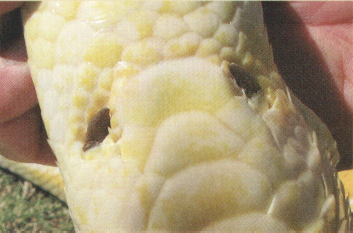
![]()
![]()
![]()

![]()

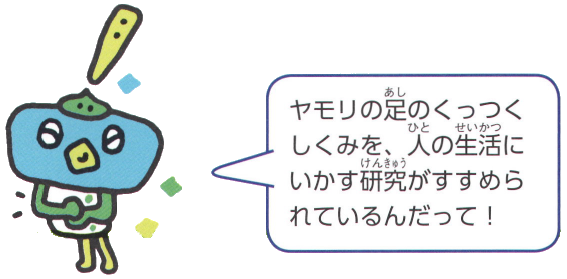
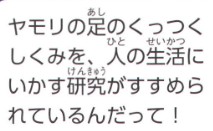
![]()
![]()
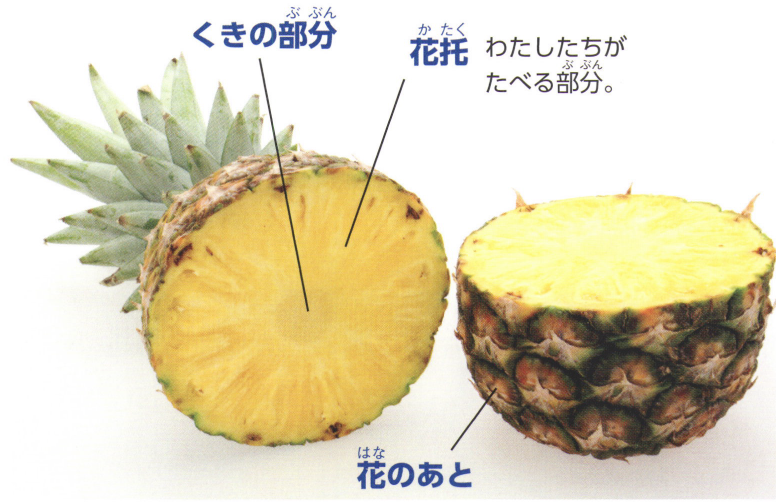
![]()
![]()
![]()
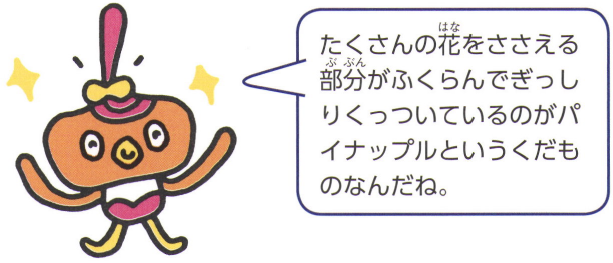
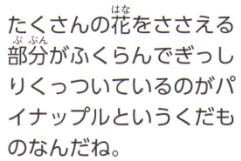
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

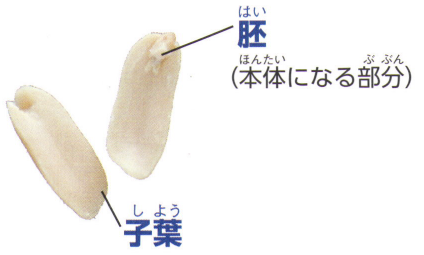
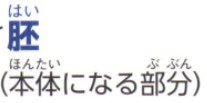
![]()
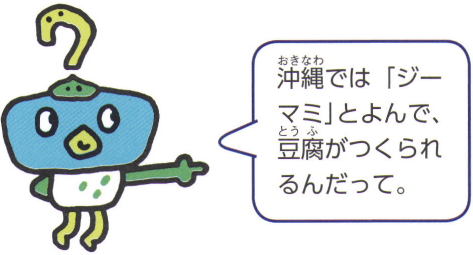
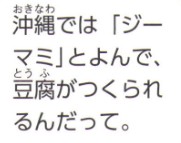
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
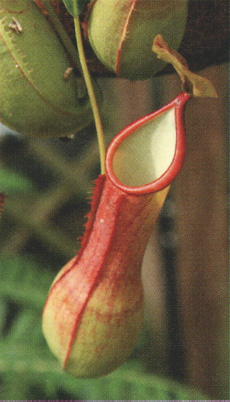
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()


![]()


![]()
![]()


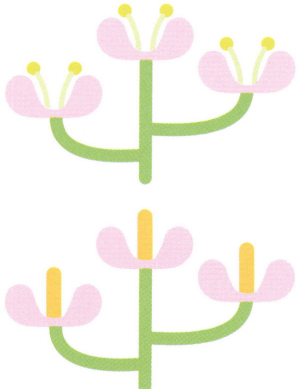
![]()

![]()
![]()
![]()
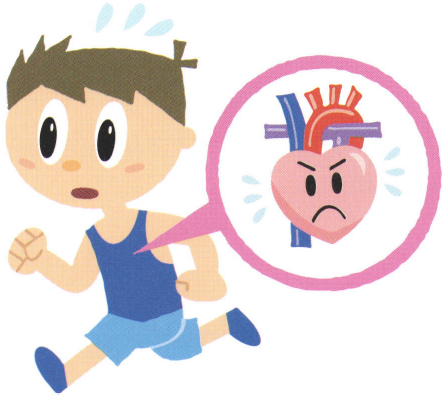
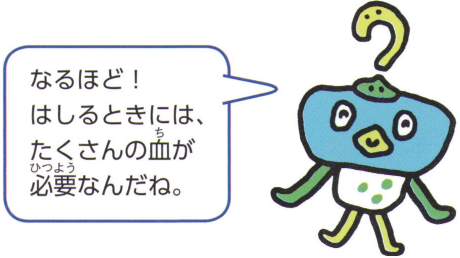
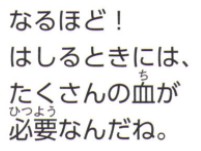
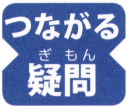
![]()
![]()
![]()
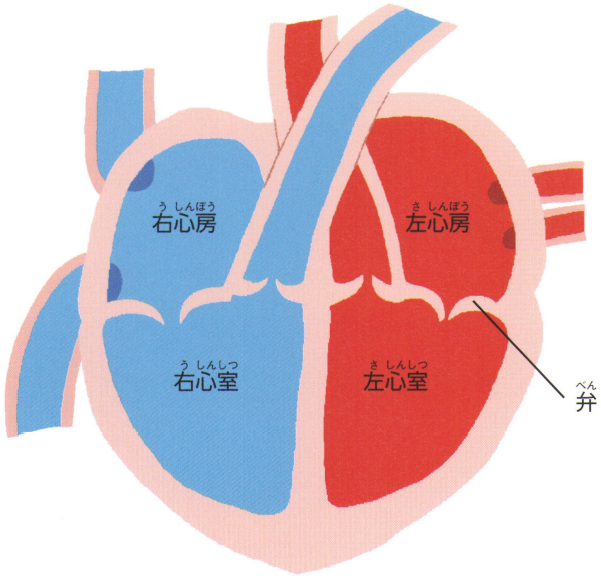
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
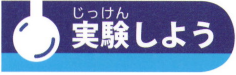


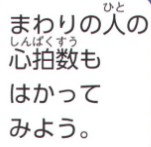
![]()
![]()
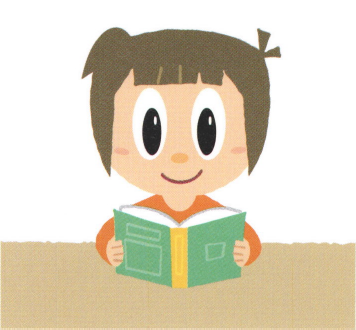
![]()
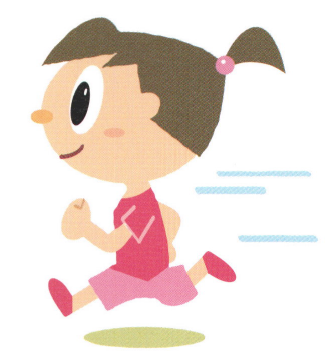
![]()
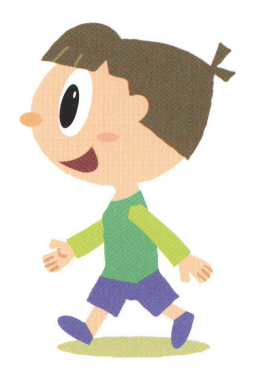

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
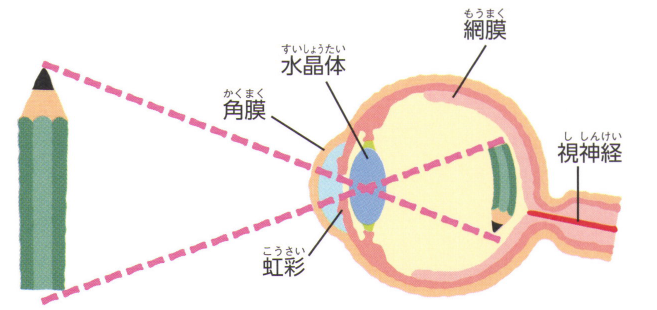
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
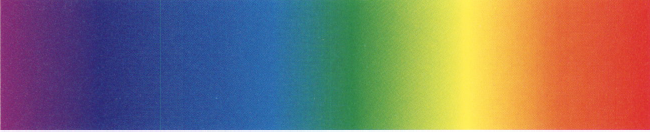

![]()


![]()
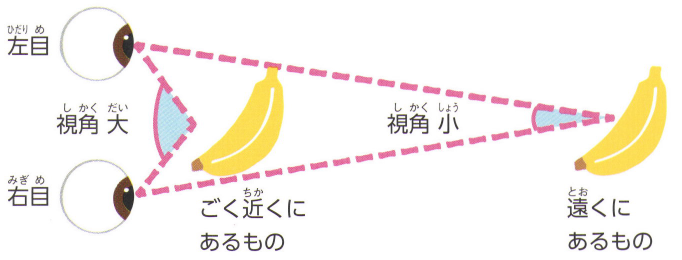
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
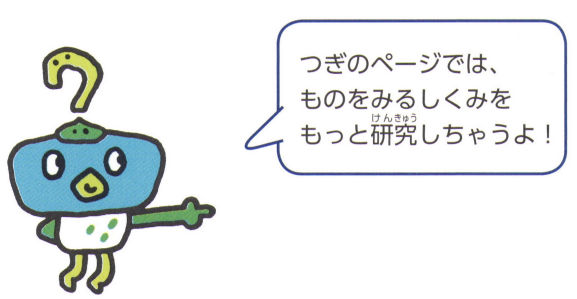
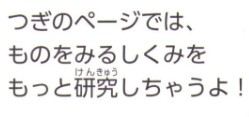
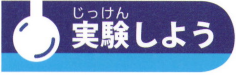
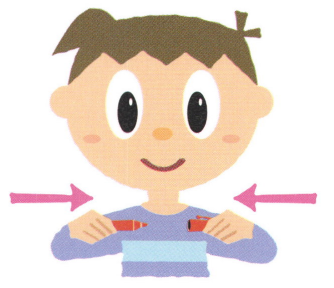
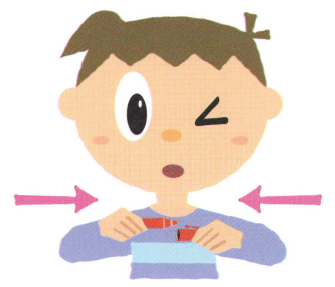
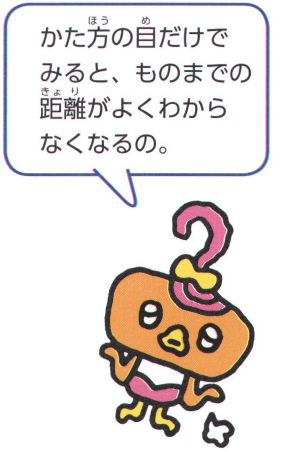
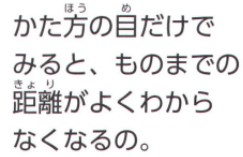
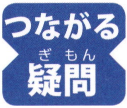
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

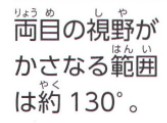
![]()
![]()

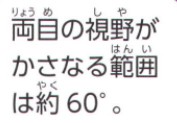
![]()
![]()
![]()
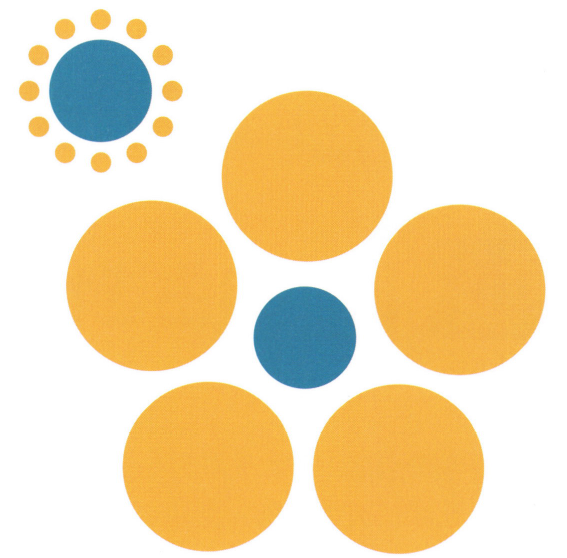
![]()
![]()
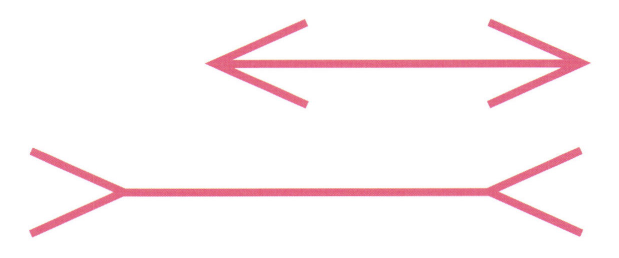


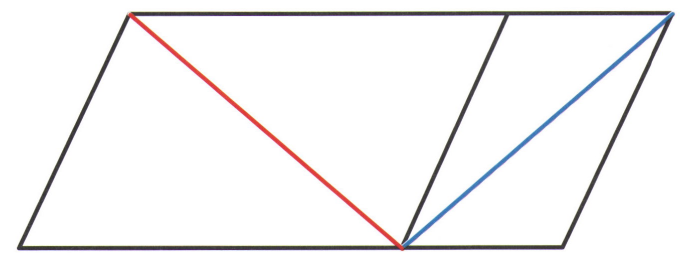
![]()

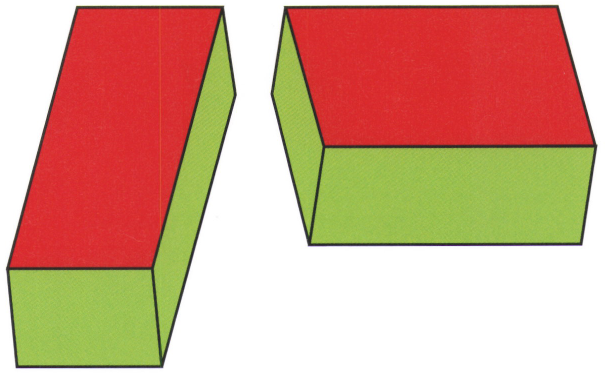
![]()

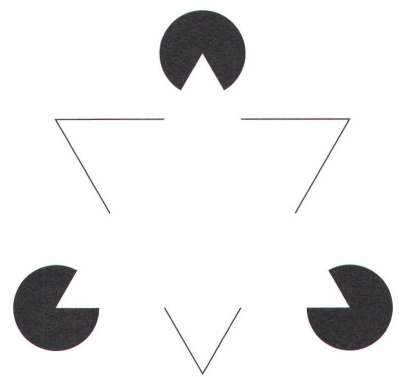
![]()

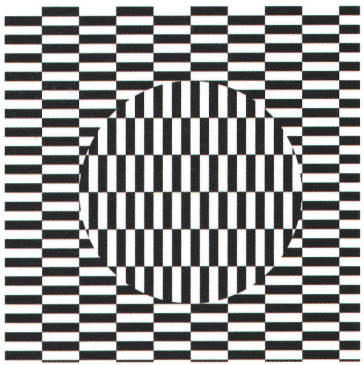
![]()

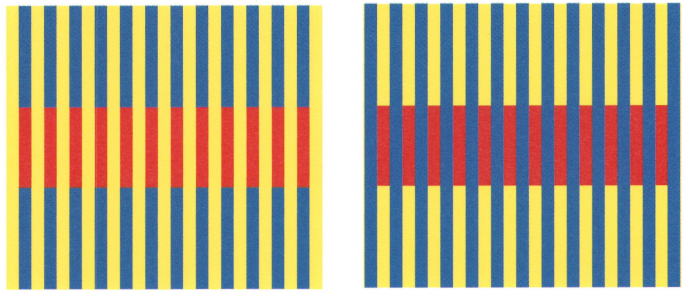
![]()

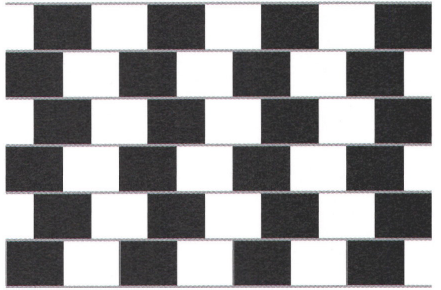
![]()

![]()
![]()
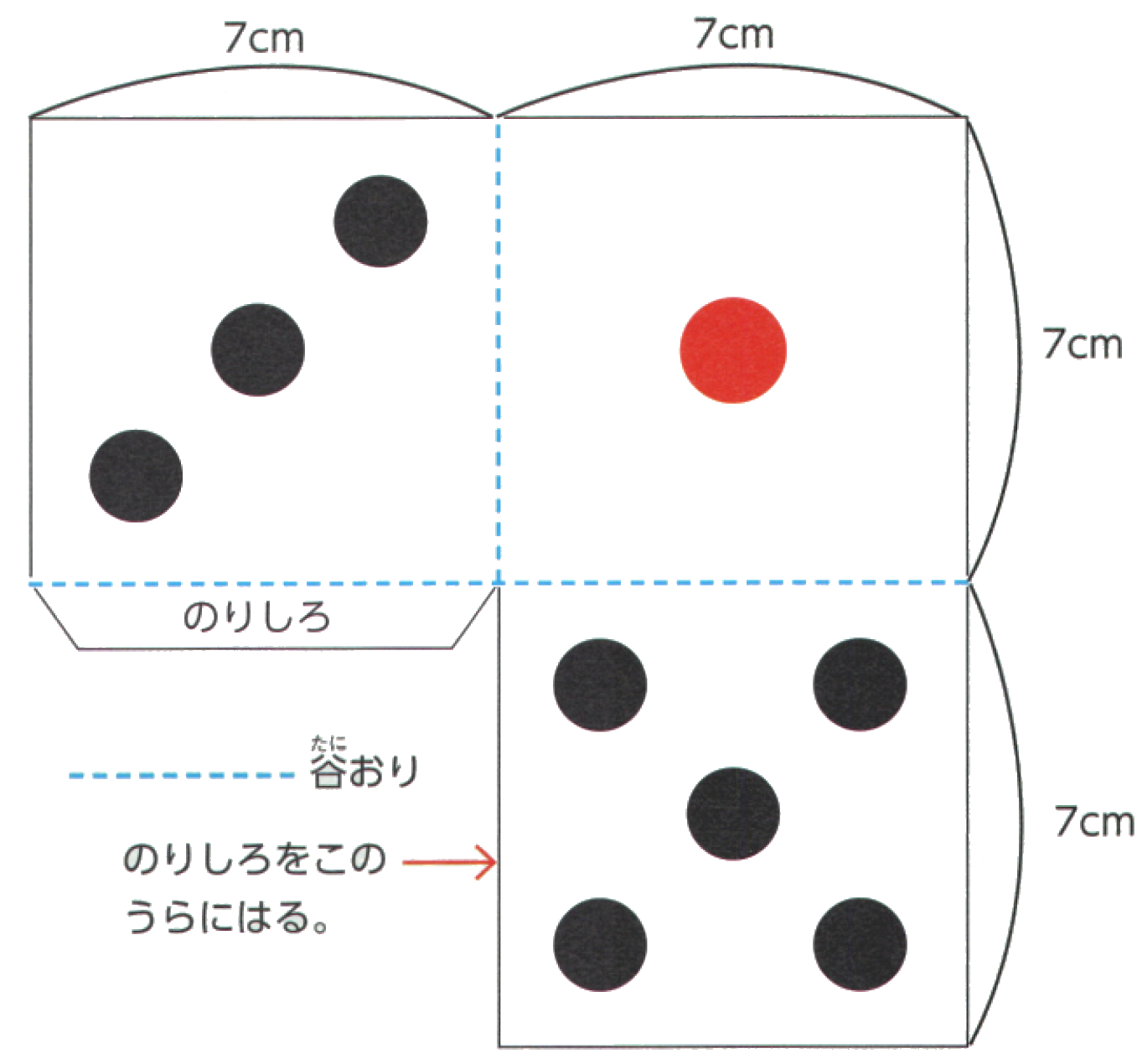
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
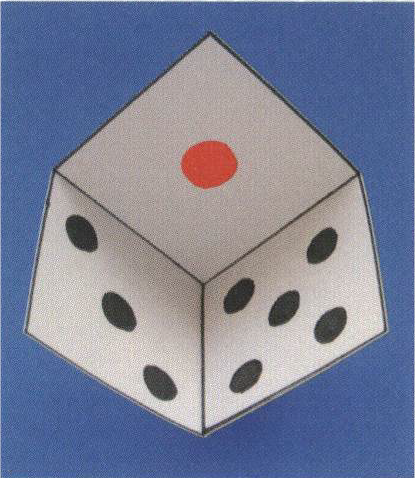

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
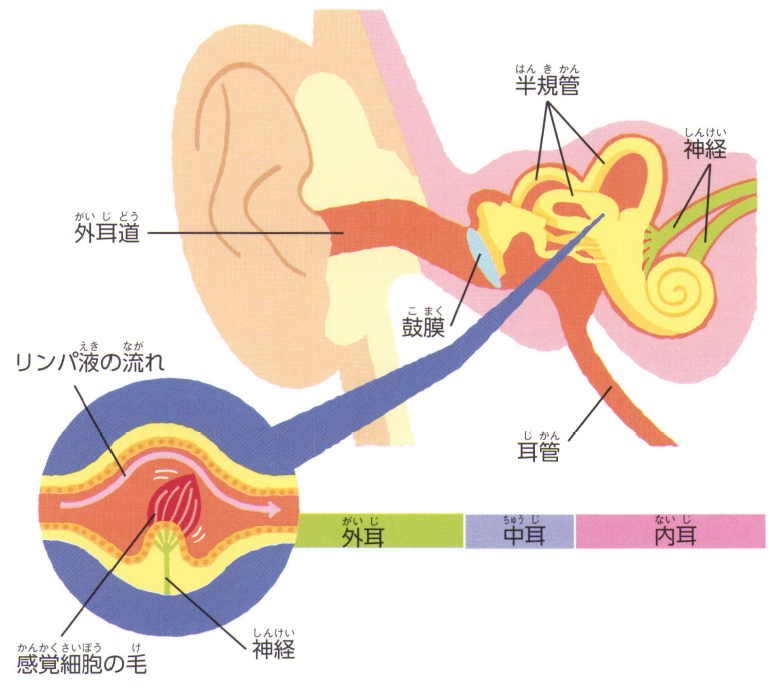
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
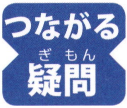
![]()
![]()
![]()
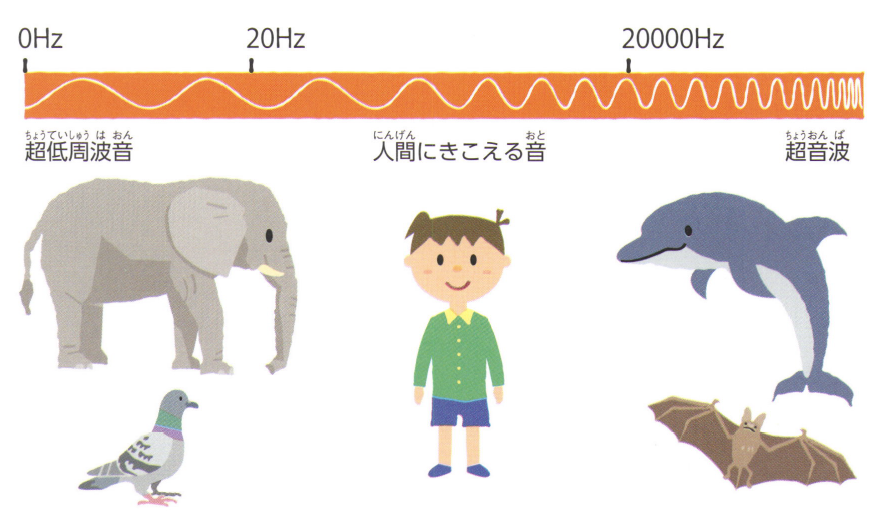
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
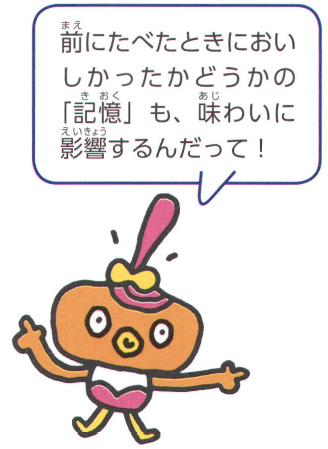
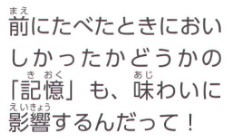
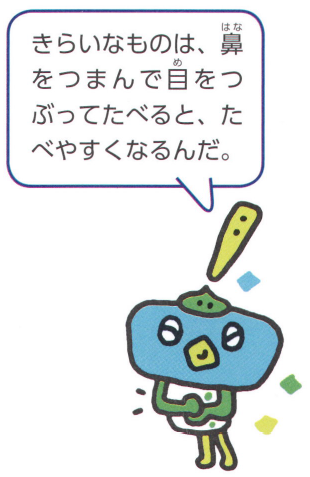
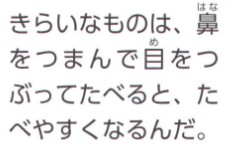
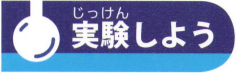
![]()
![]()
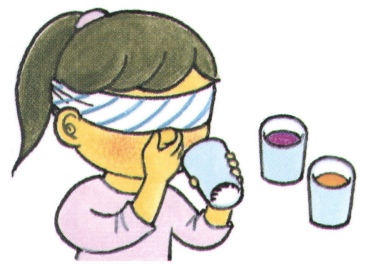
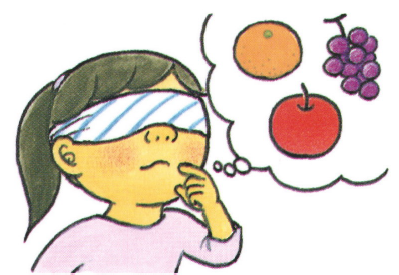
![]()

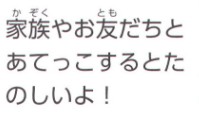
![]()
![]()
![]()
![]()

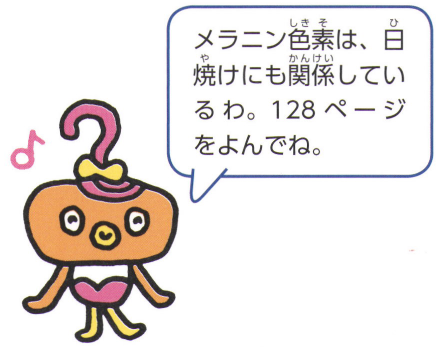
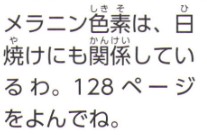
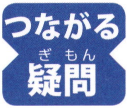
![]()
![]()
![]()
![]()

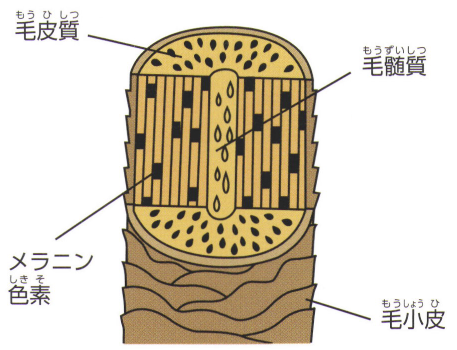
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

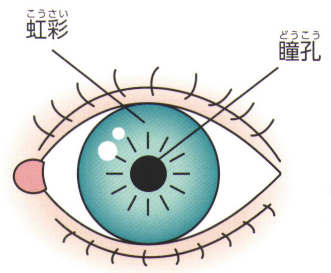
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
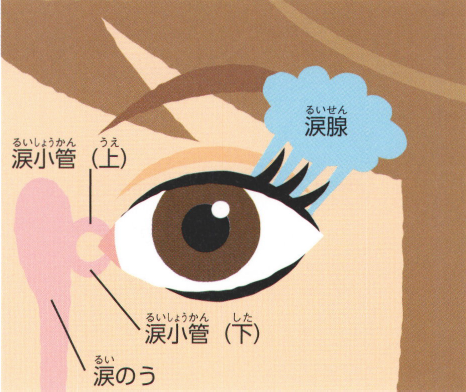
![]()
![]()
![]()
![]()
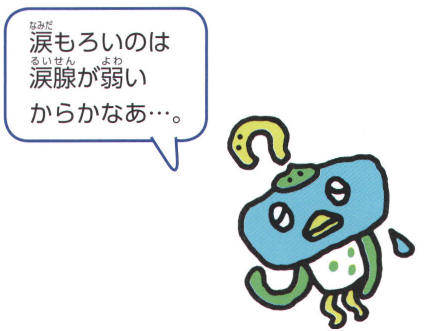
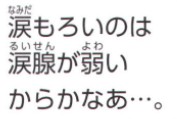

![]()

![]()

![]()

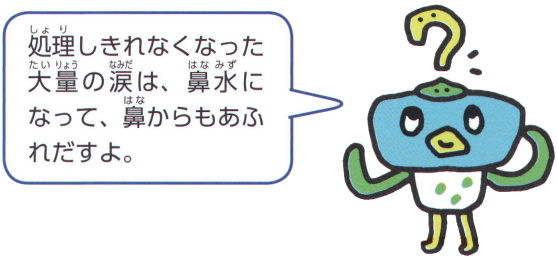
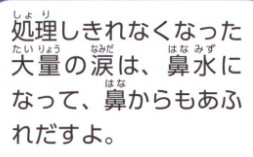
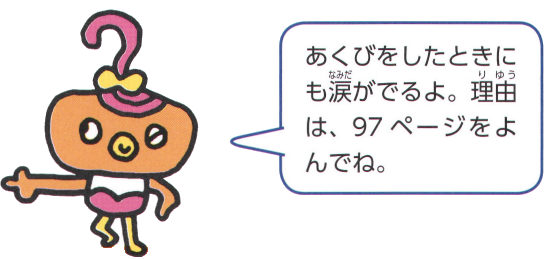
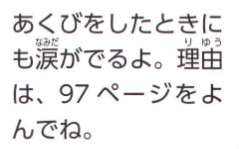
![]()
![]()
![]()
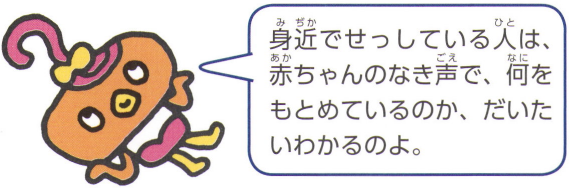
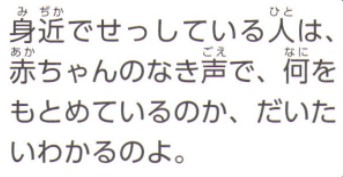

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
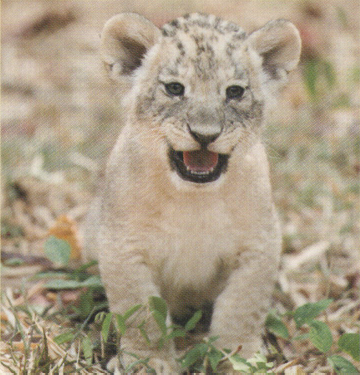

![]()
![]()
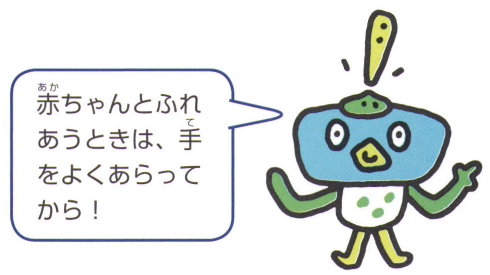
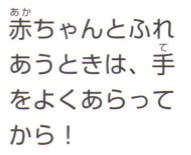
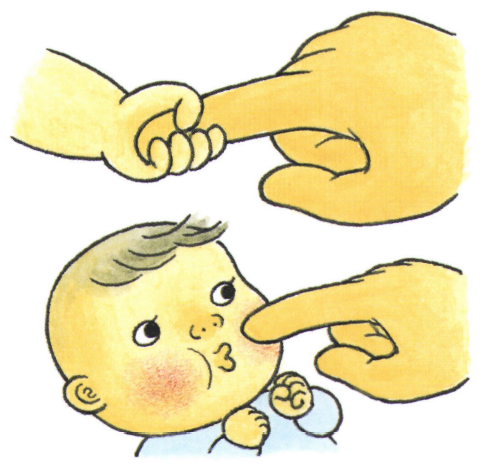
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
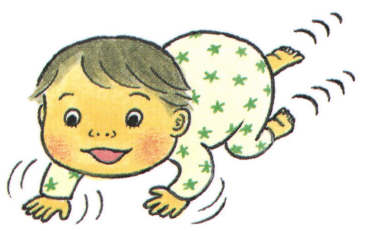
![]()
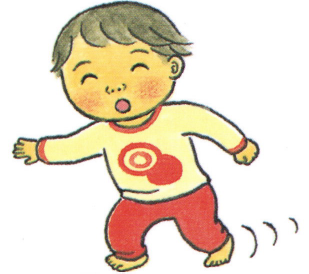

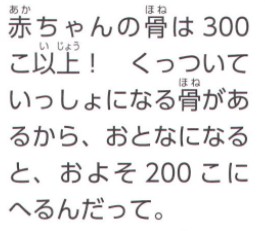
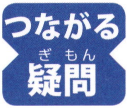
![]()
![]()
![]()
![]()
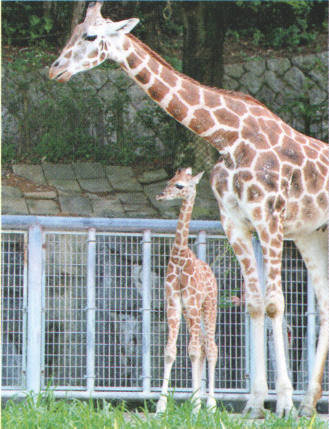
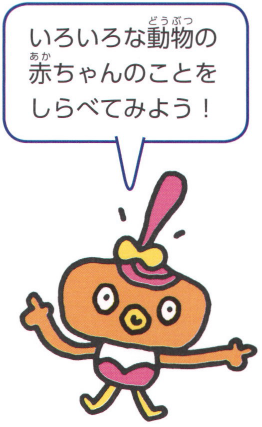
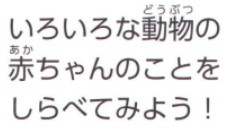
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
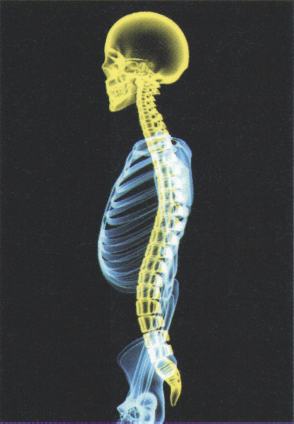
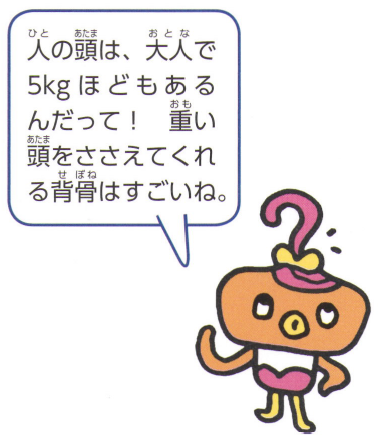
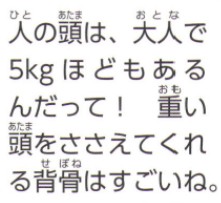
![]()

![]()
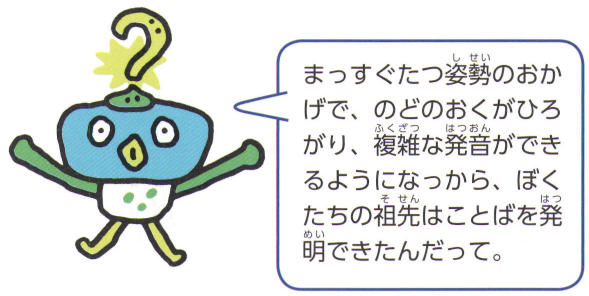
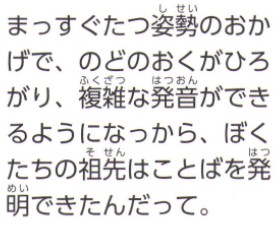


![]()
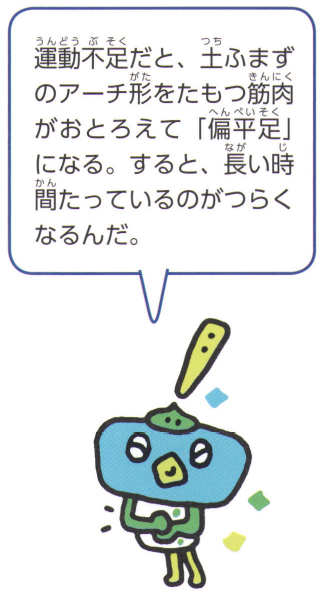
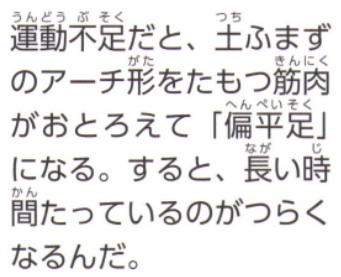
![]()
![]()
![]()
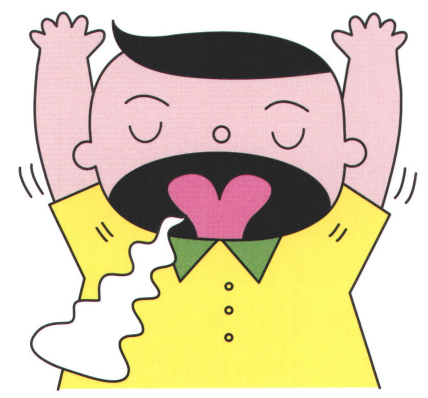
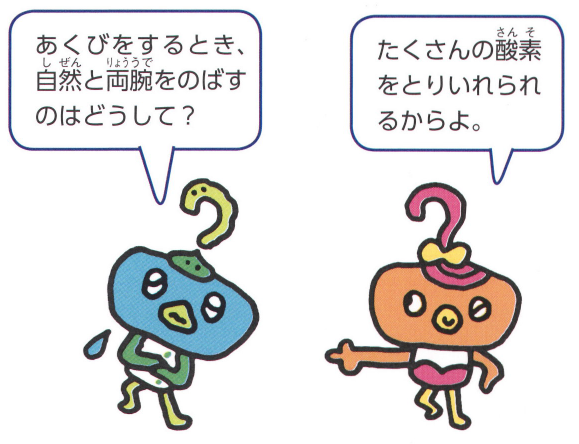
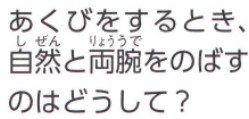
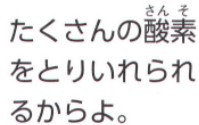
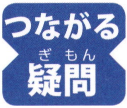
![]()
![]()

![]()
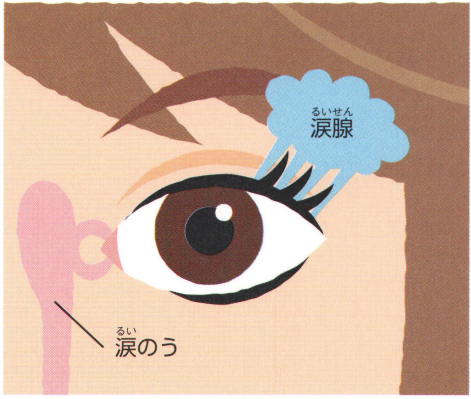
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

![]() 運動を
運動を
![]() 熱が
熱が
![]() 気温が
気温が
![]() 緊張
緊張
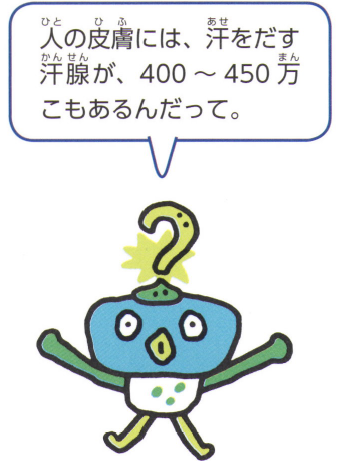
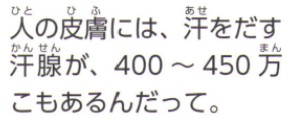
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

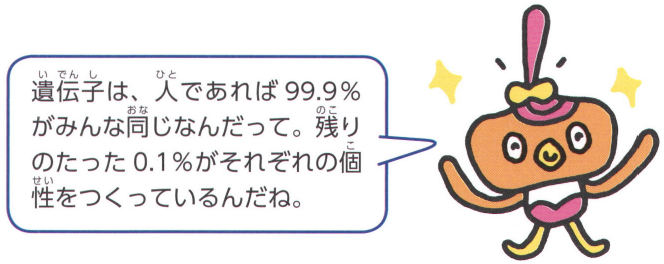
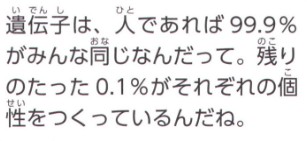
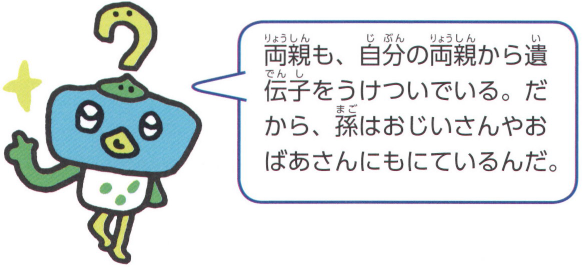
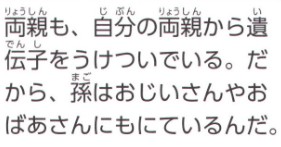
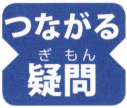
![]()
![]()
![]()
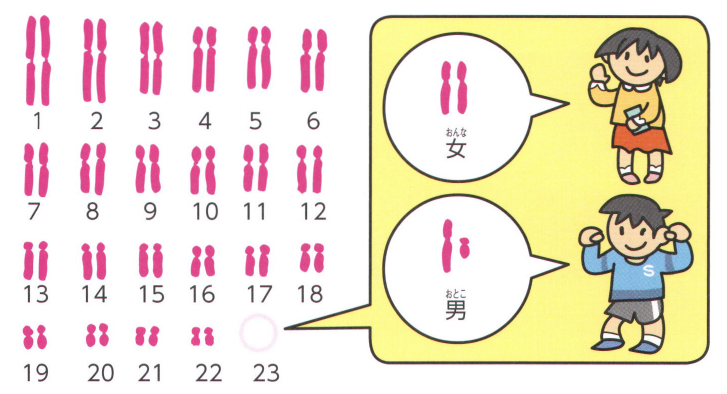
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
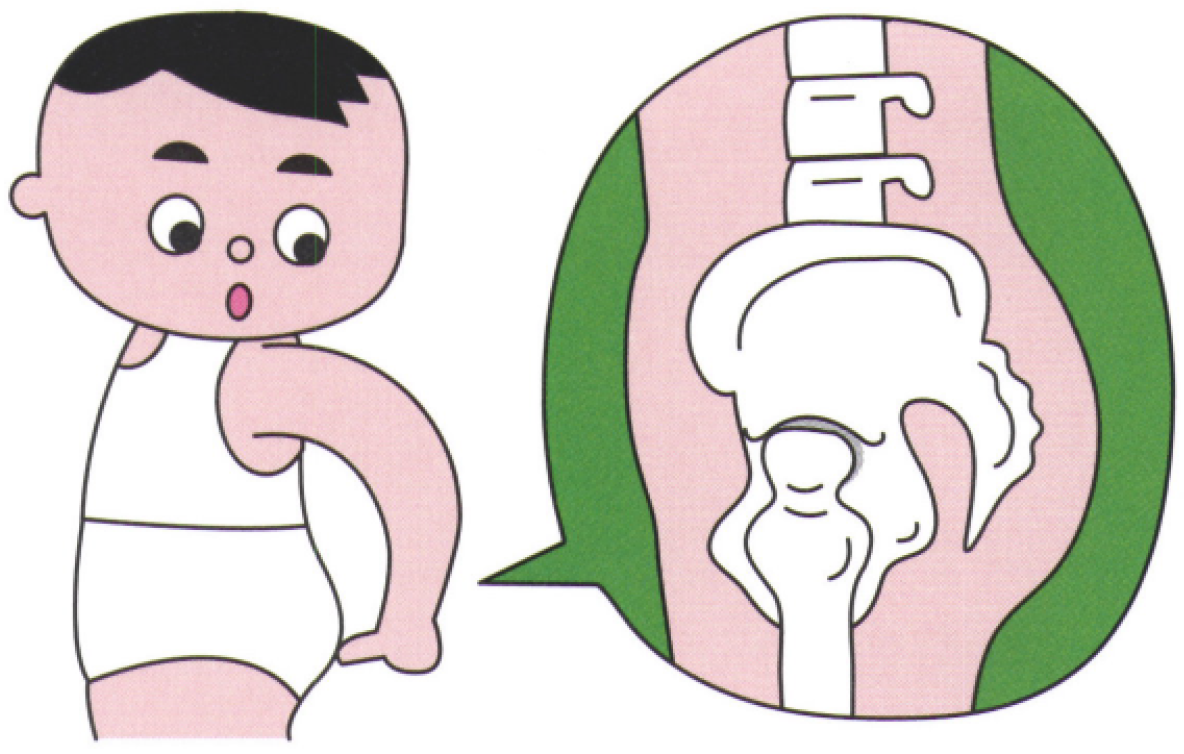
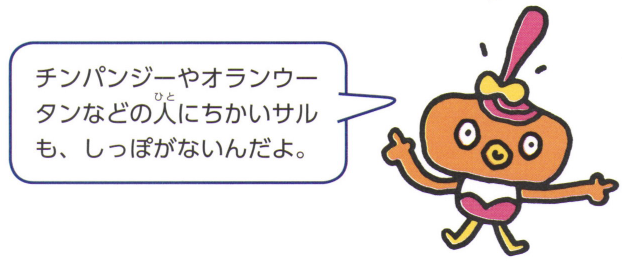
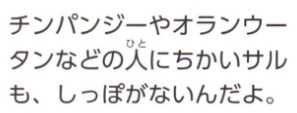

![]()
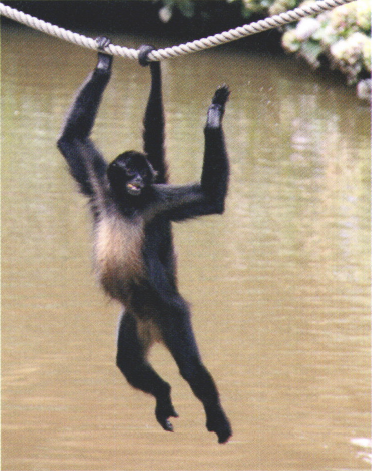
![]()

![]()

![]()

![]()

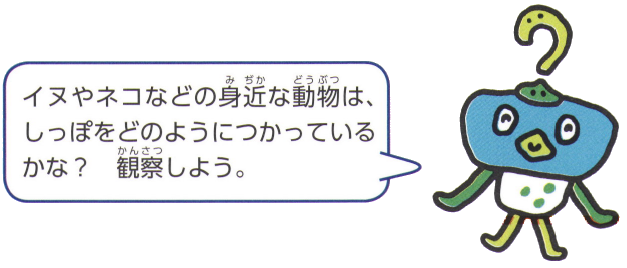
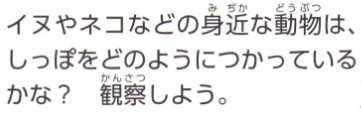
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
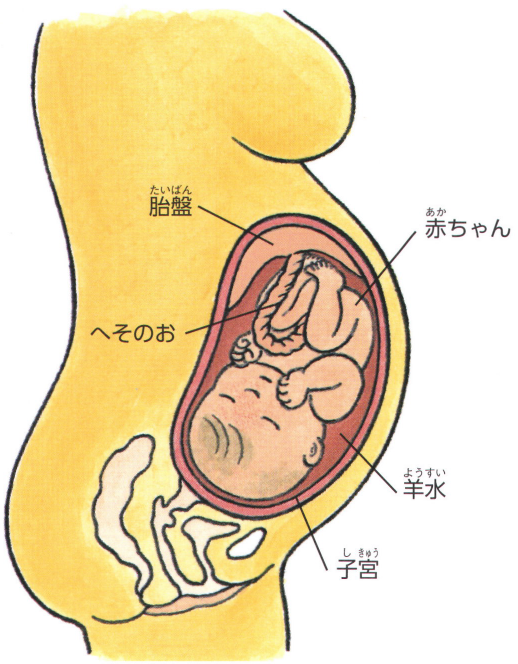
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
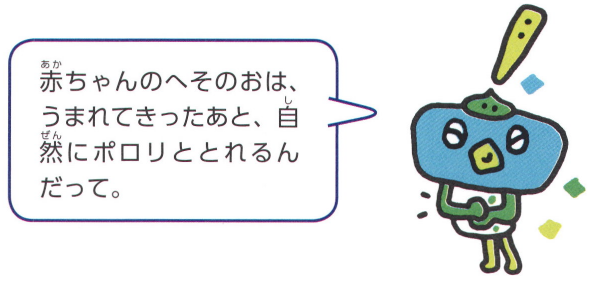
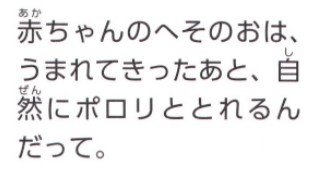
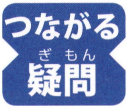
![]()
![]()
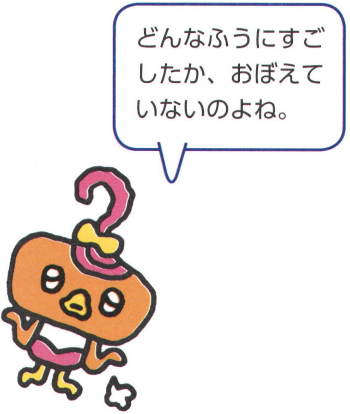
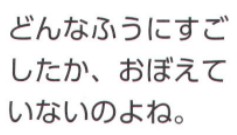
![]()
![]()
![]()
![]()
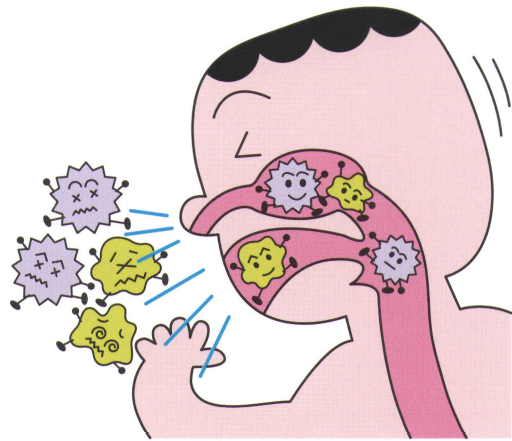

![]()
![]()
![]()
![]()
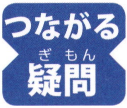
![]()
![]()
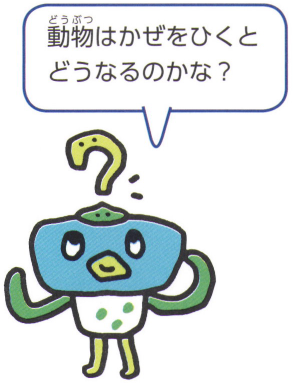
![]()
![]()
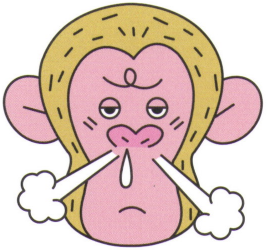
![]()
![]()
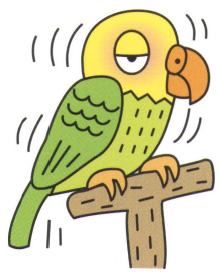
![]()
![]()
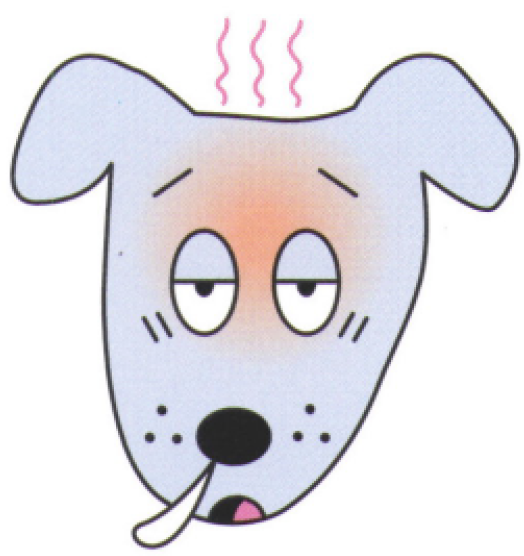
![]()
![]()
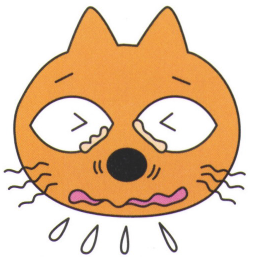
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
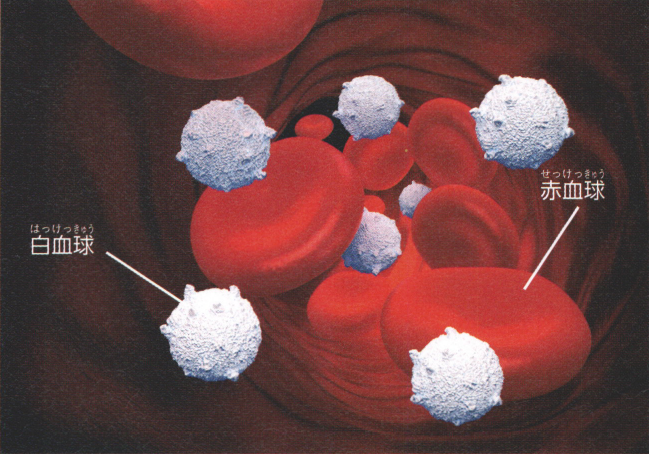
![]()
![]()
![]()
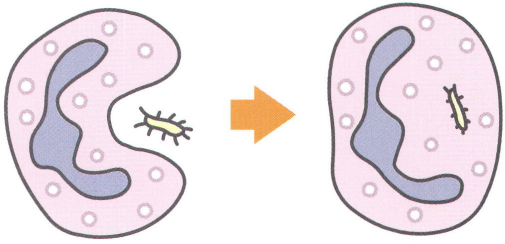
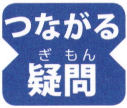
![]()
![]()
![]()
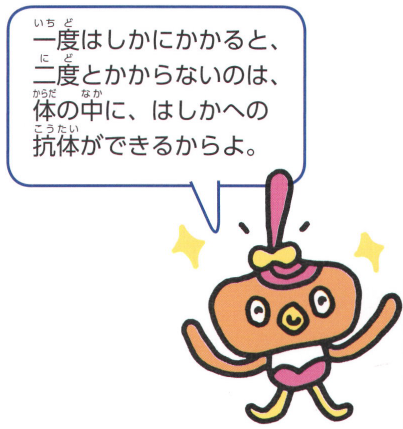
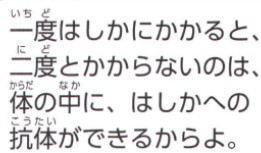
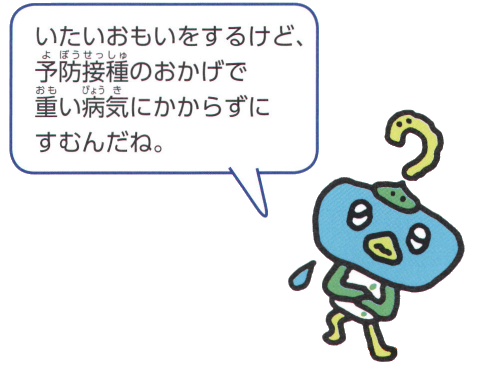
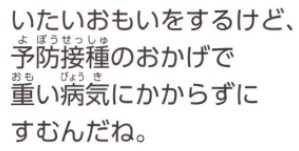
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
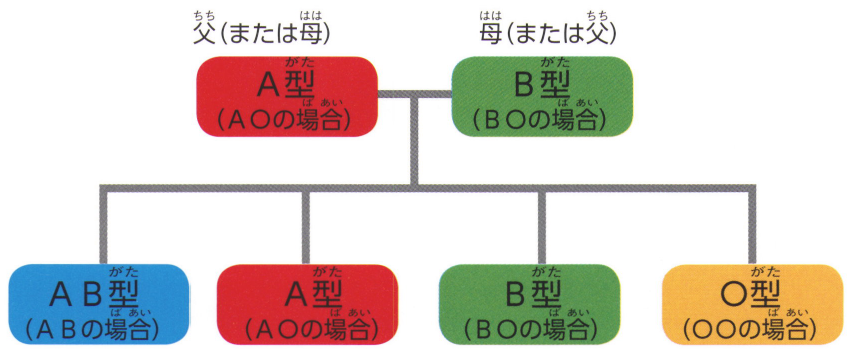
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
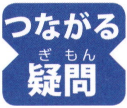
![]()
![]()
![]()
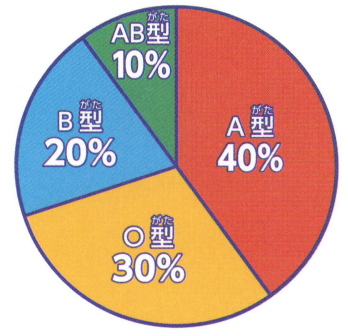
![]()
![]()
![]()
![]()
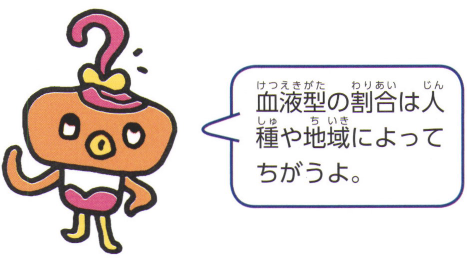
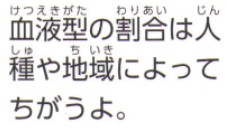
![]()
![]()
![]()
![]()
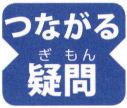
![]()
![]()
![]()
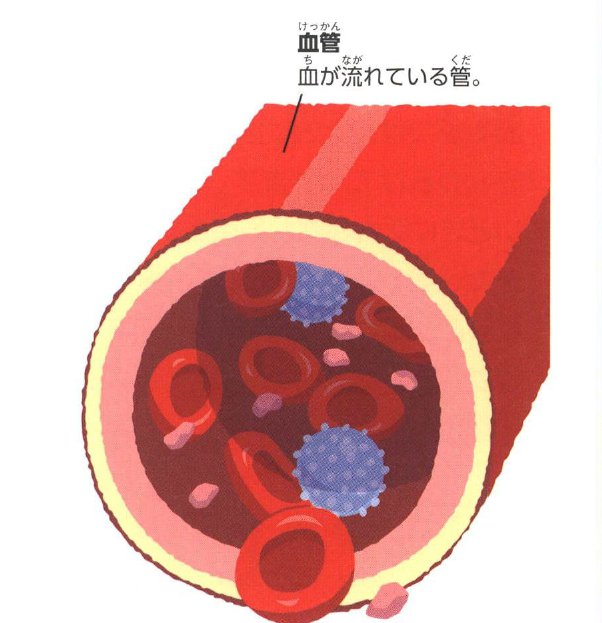
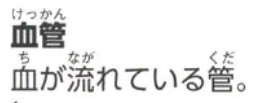
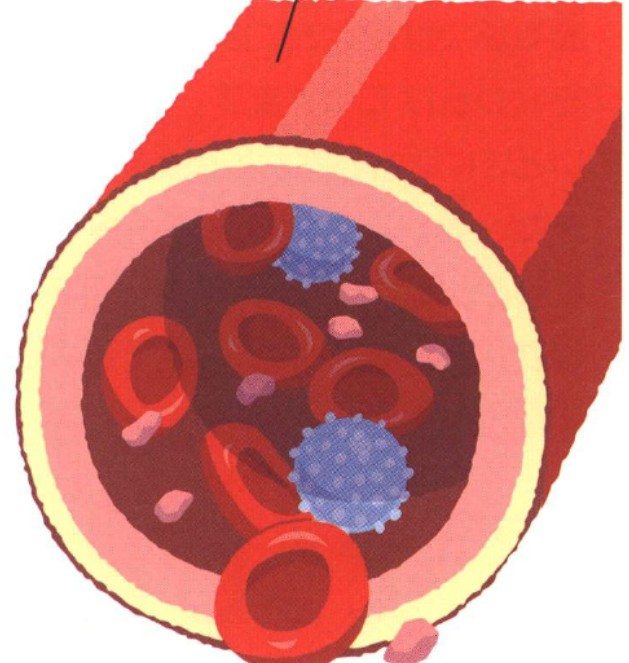
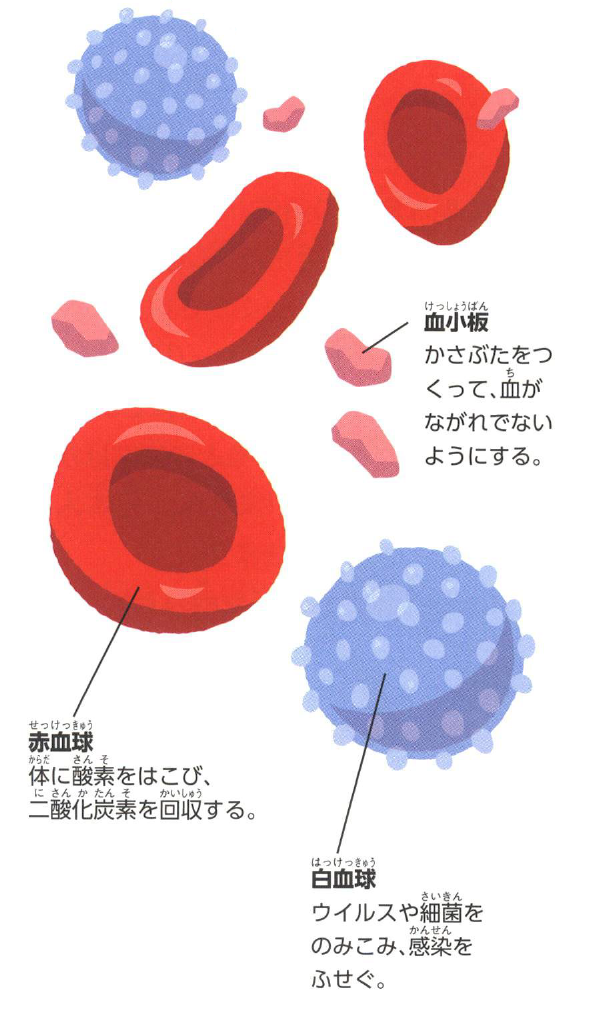
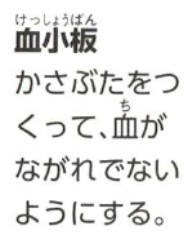
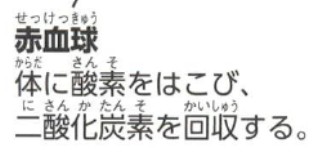
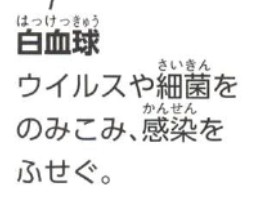
![]()
![]()
![]()
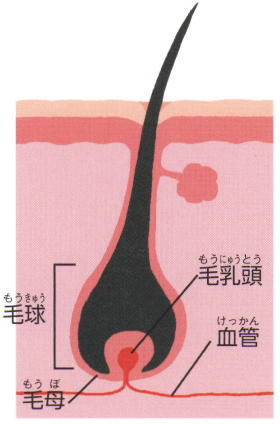
![]()
![]()
![]()
![]()
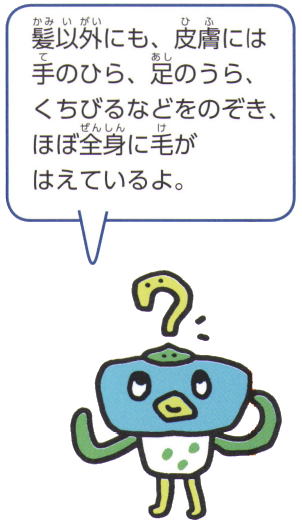
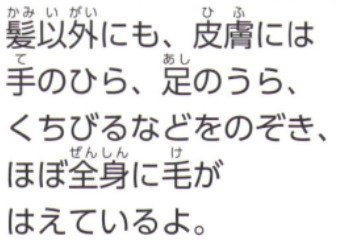
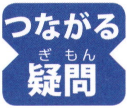
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
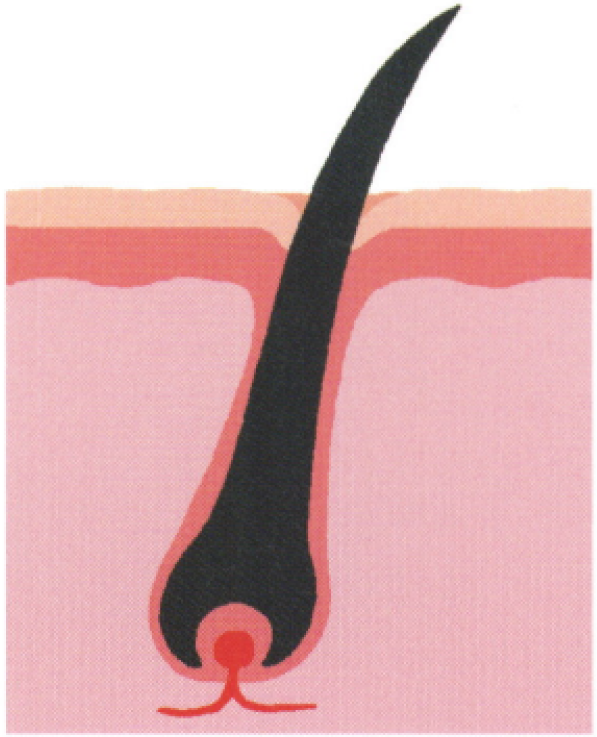
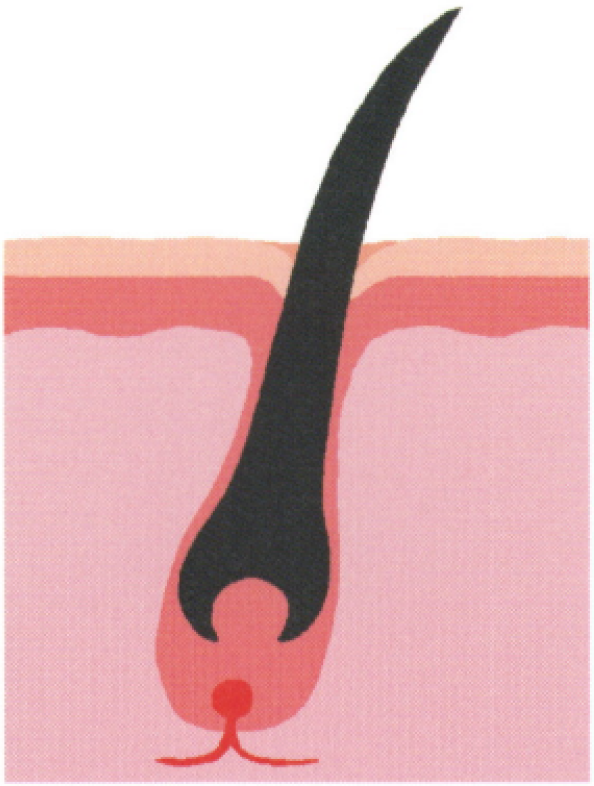
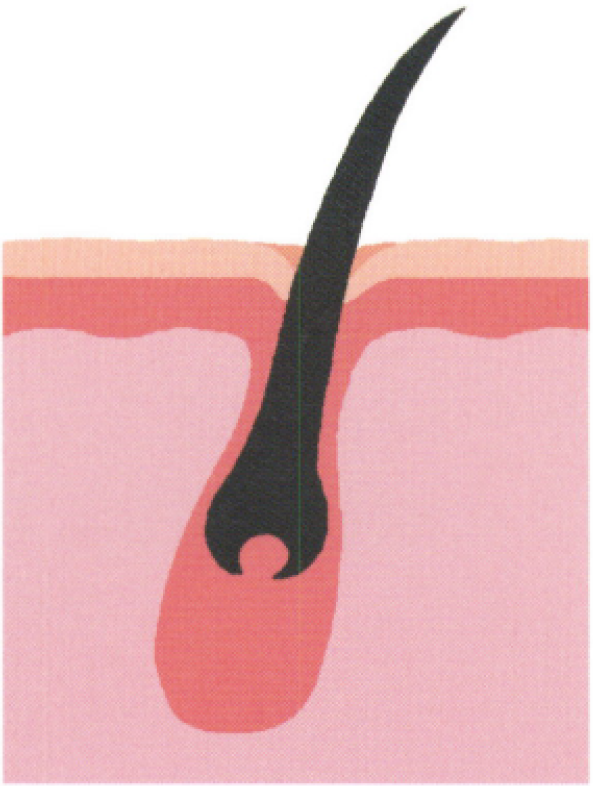
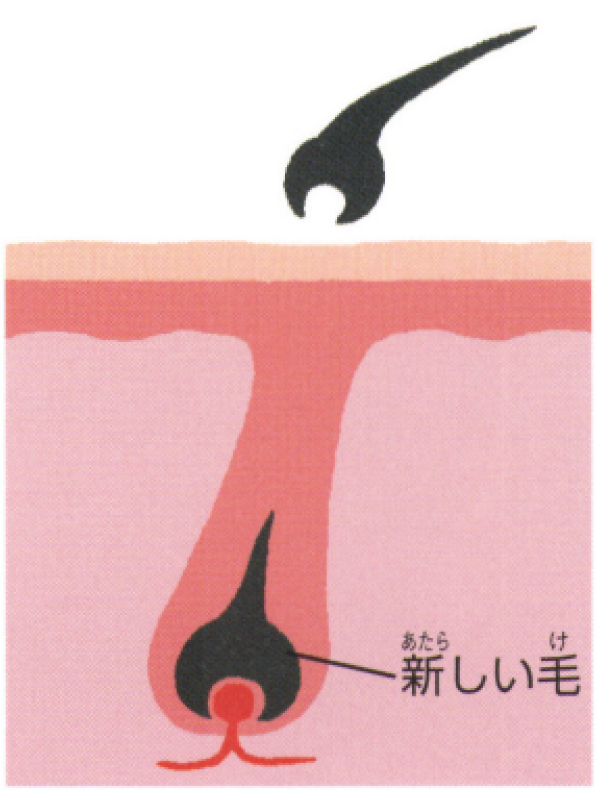
![]()
![]()
![]()
![]()
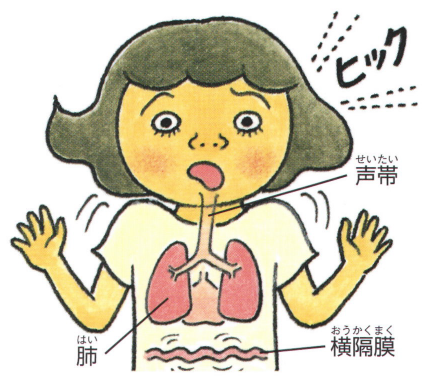
![]()
![]()
![]()
![]()
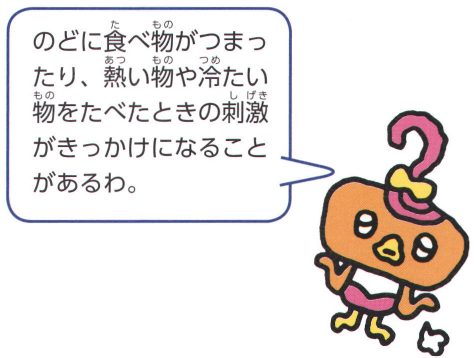
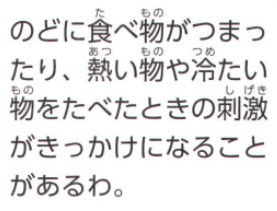
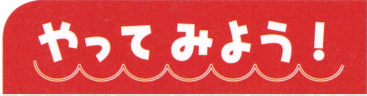
![]()
![]()
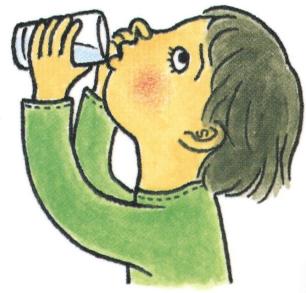
![]()
![]()

![]()
![]()



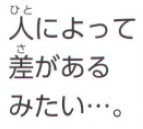
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
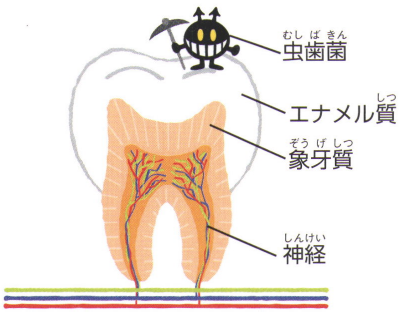
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
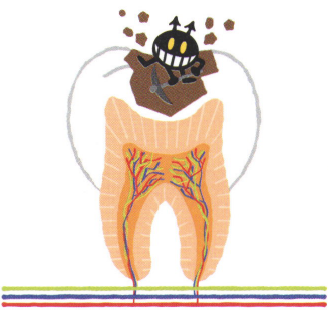
![]()
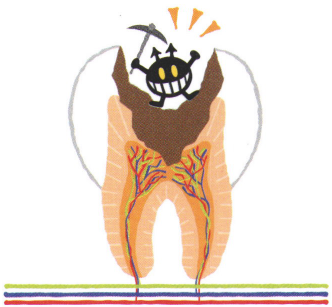
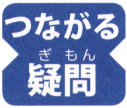
![]()
![]()
![]()
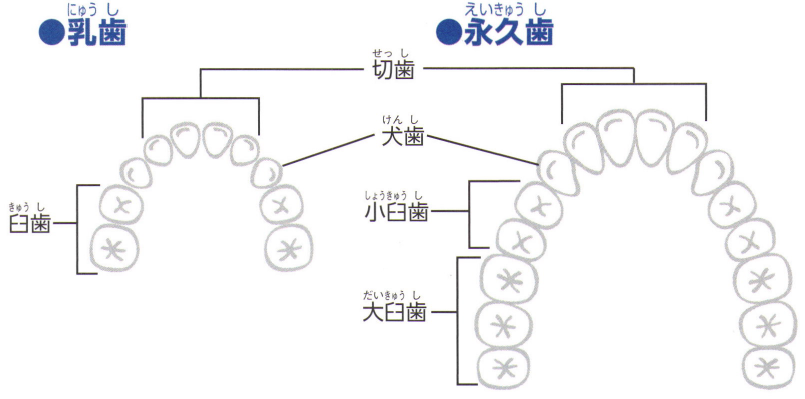
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
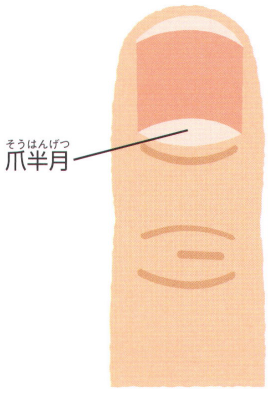
![]()
![]()
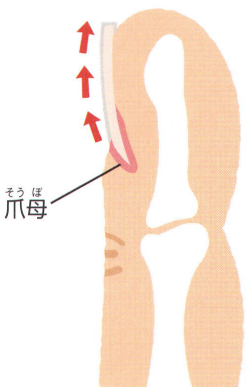
![]()
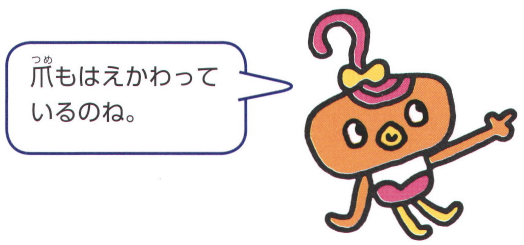
![]()
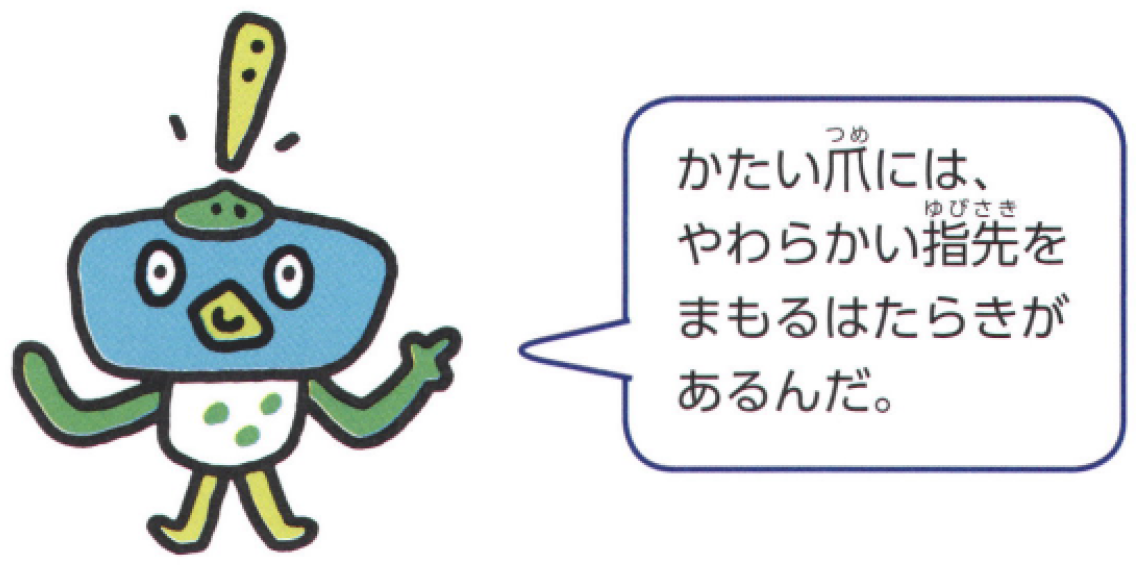
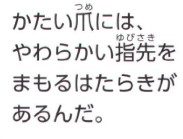
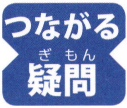
![]()
![]()
![]()

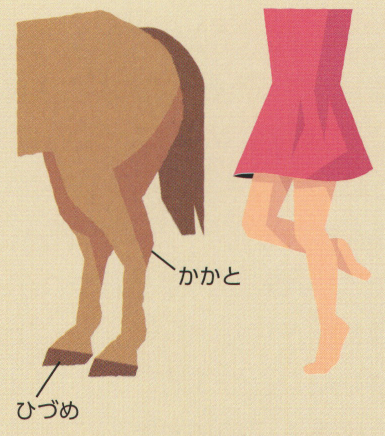
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
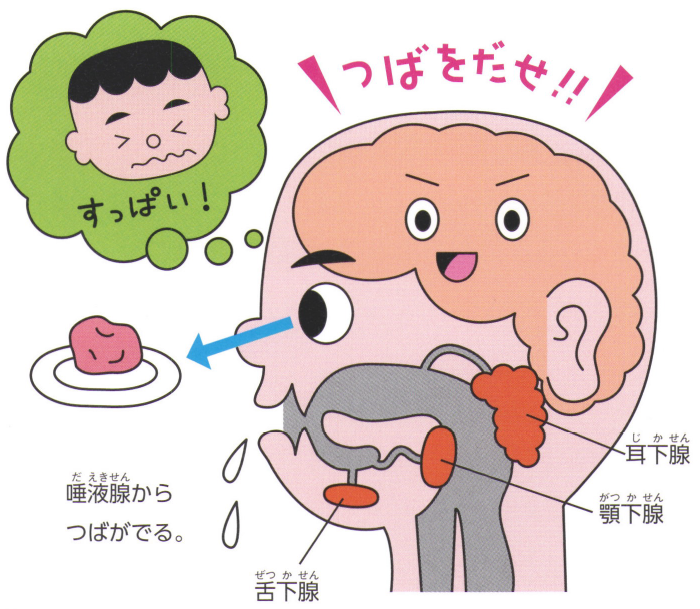
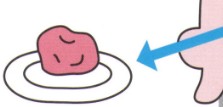
![]()
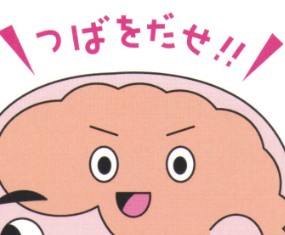
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
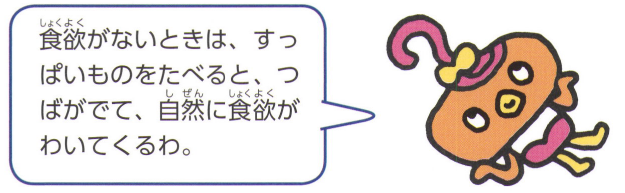
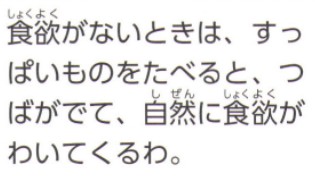
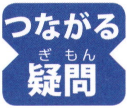
![]()
![]()
![]()
![]()
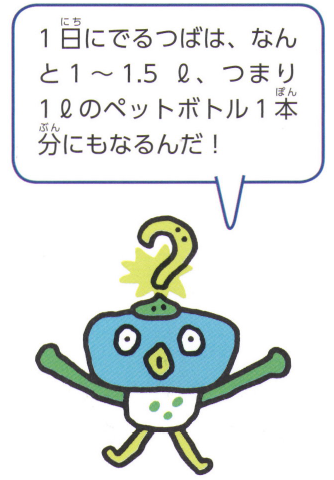
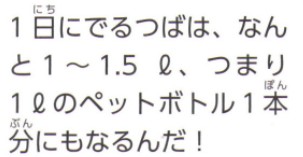
![]()
![]()
![]()
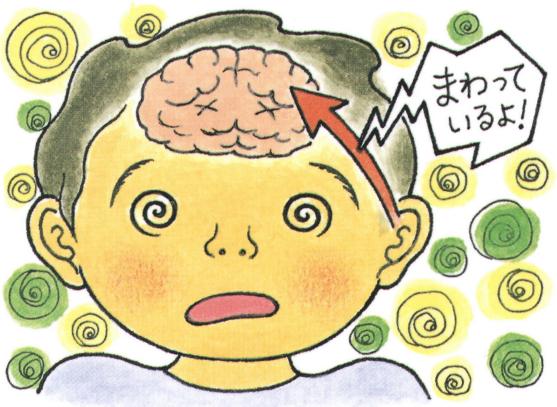
![]()
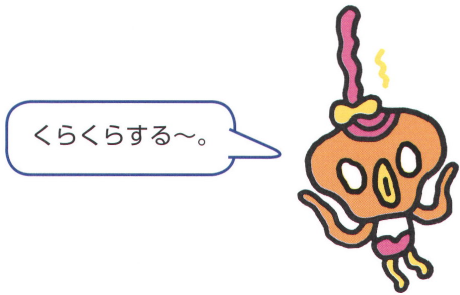
![]()
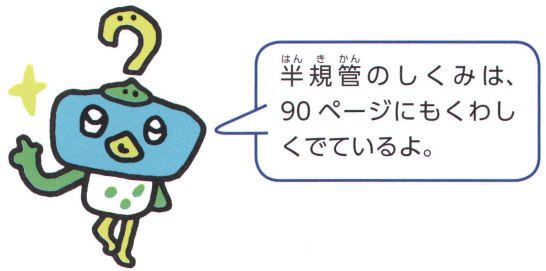
![]()
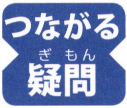
![]()
![]()
![]()
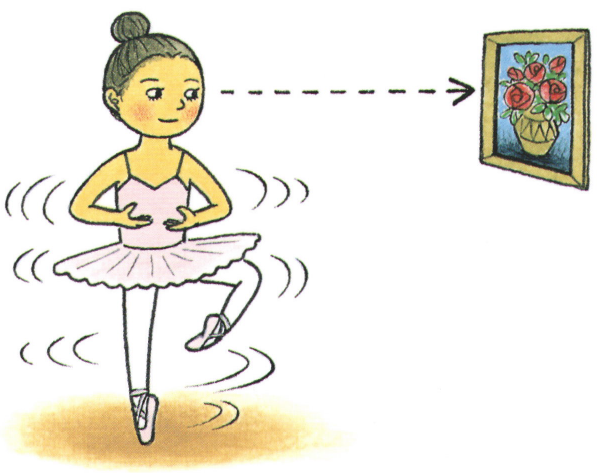
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
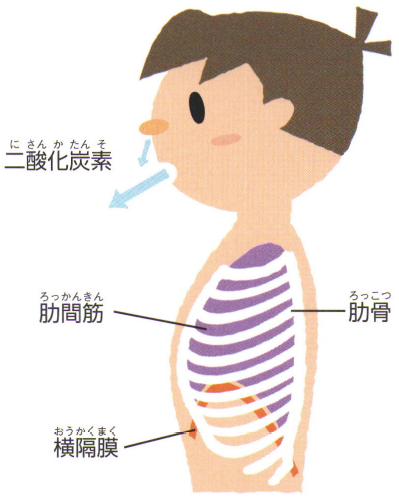
![]()
![]()
![]()
![]()
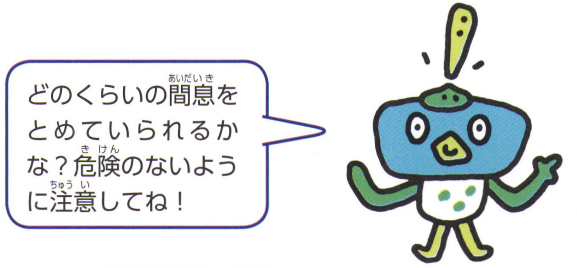
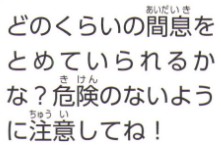
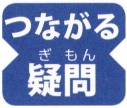
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
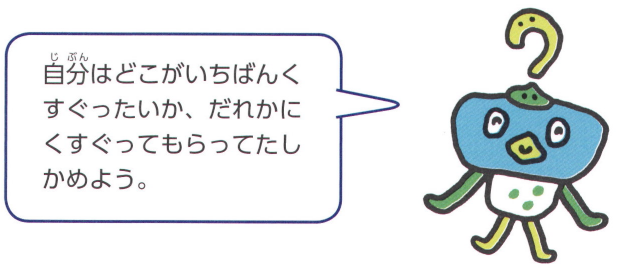
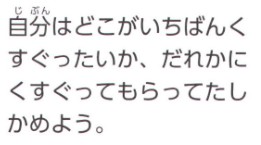
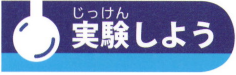
![]()
![]()
![]()

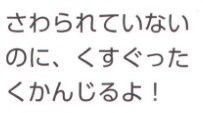
![]()
![]()
![]()
![]()
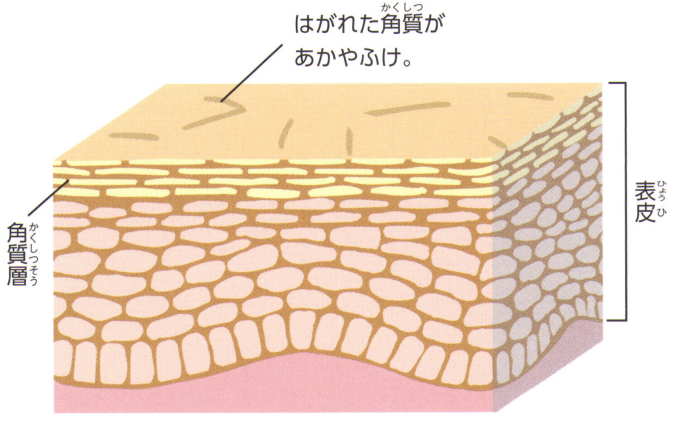
![]()
![]()
![]()



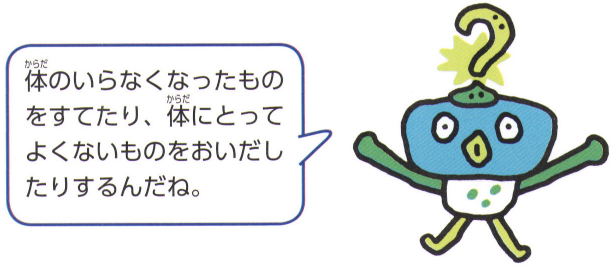
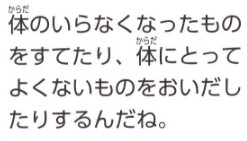
![]()
![]()
![]()
![]()
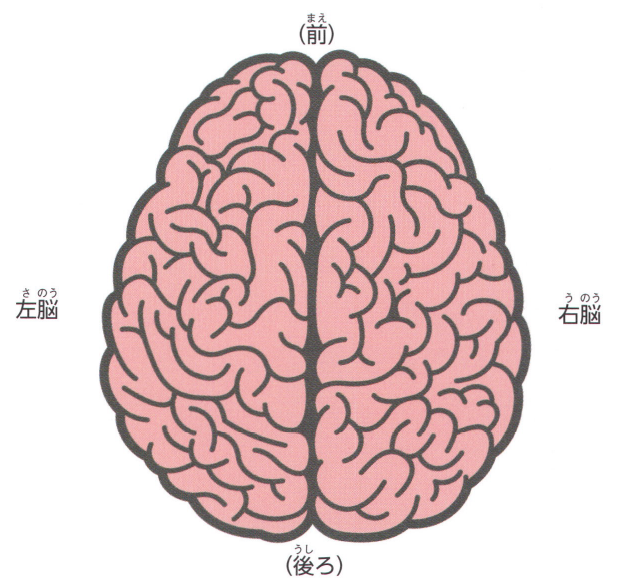
![]()
![]()
![]()
![]()
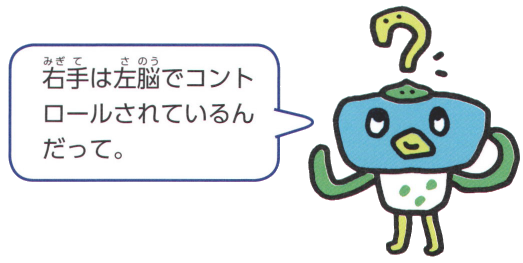
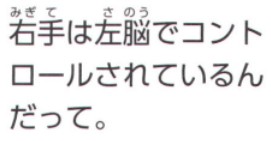

![]()
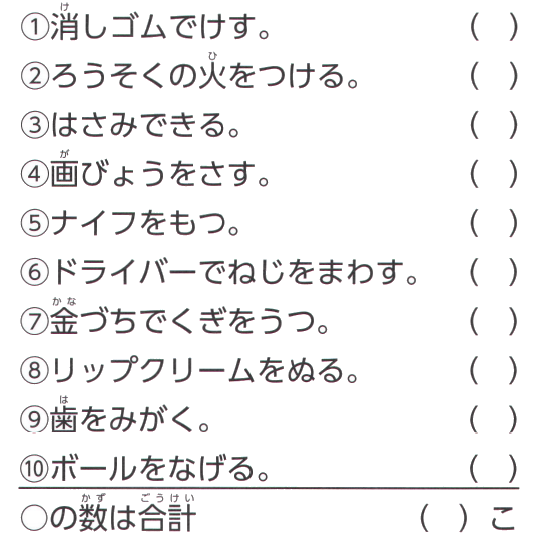
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
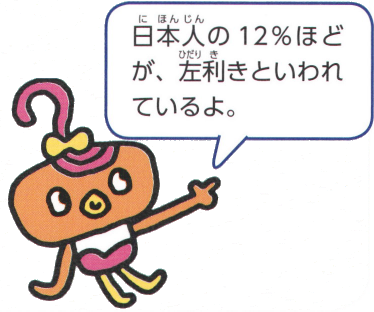
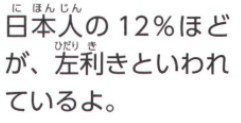
![]()
![]()
![]()
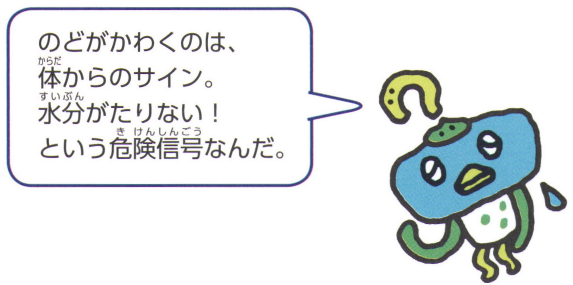
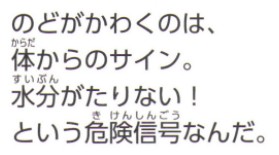

![]()
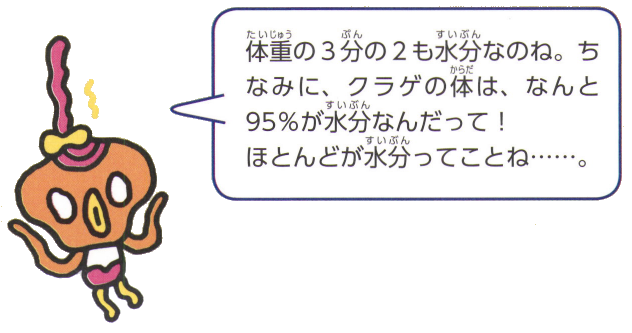
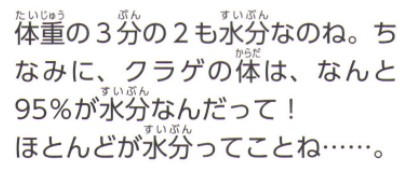
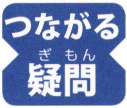
![]()
![]()

![]()
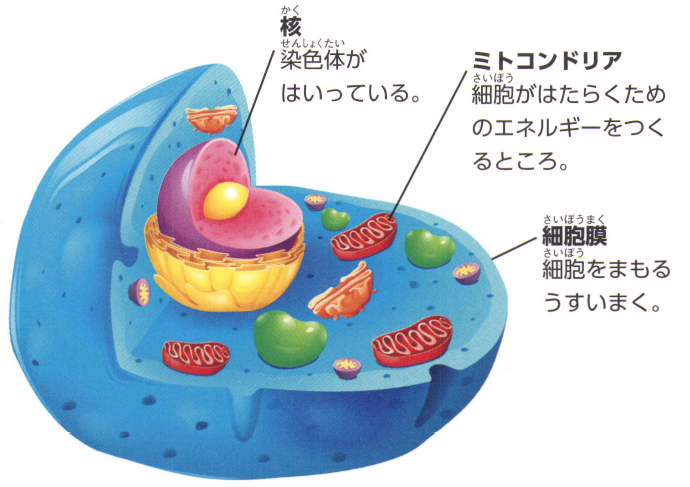
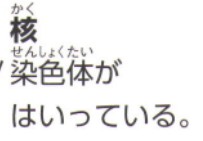
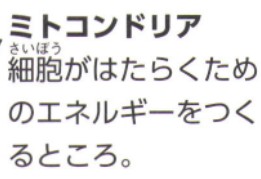
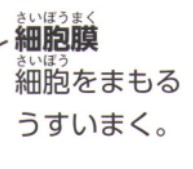
![]()
![]()
![]()
![]()
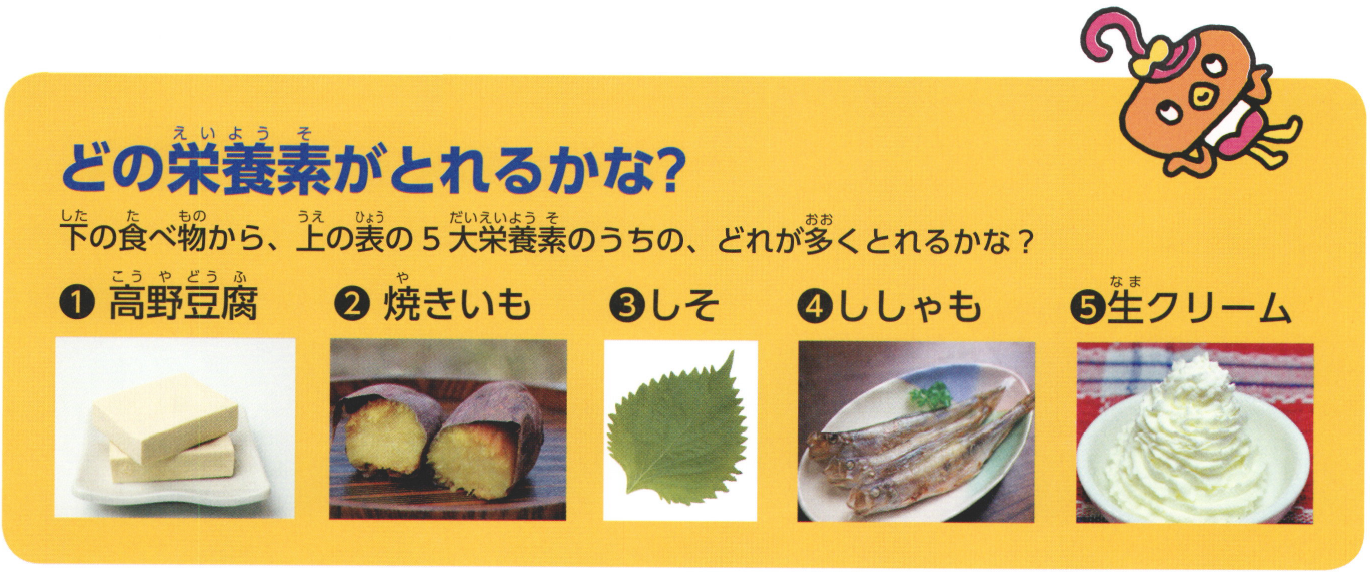
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
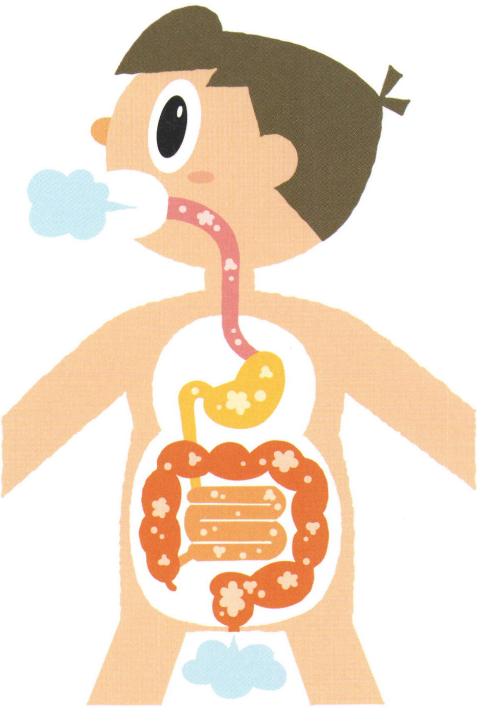

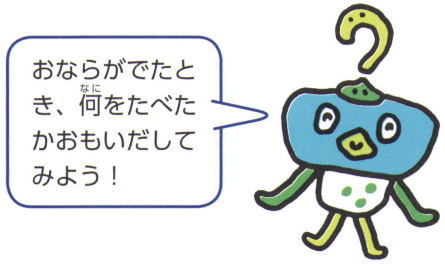
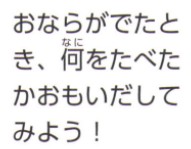
![]()
![]()
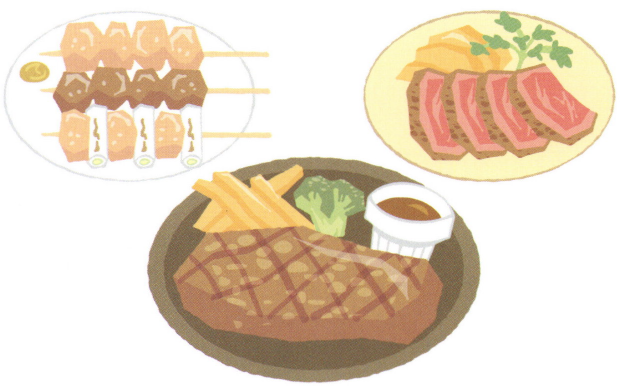
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
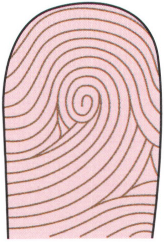
![]()
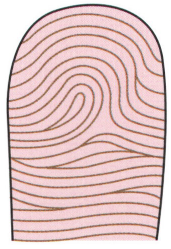
![]()
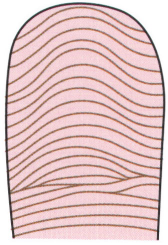
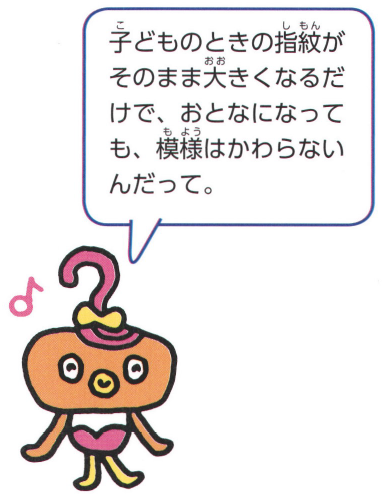
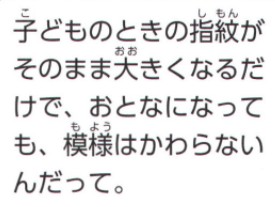
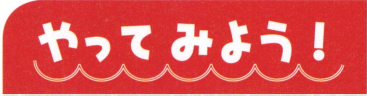
![]()
![]()

![]()


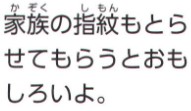
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

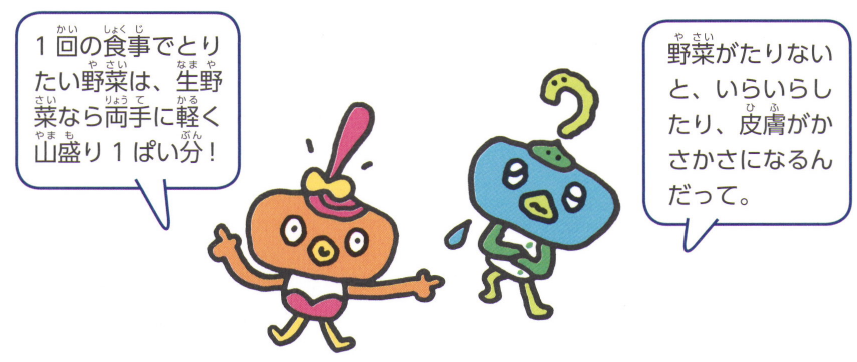
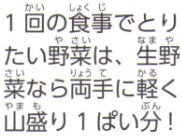
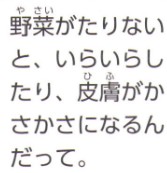
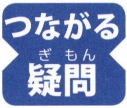
![]()
![]()
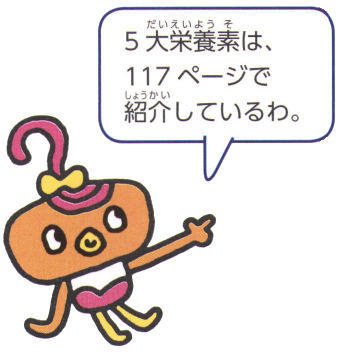
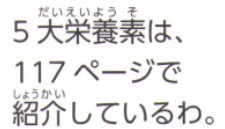
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
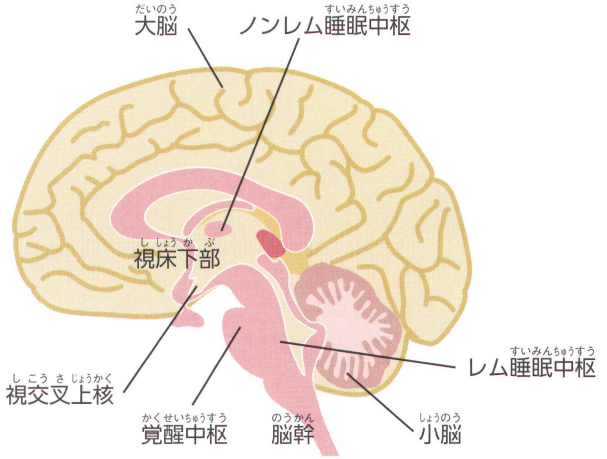
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
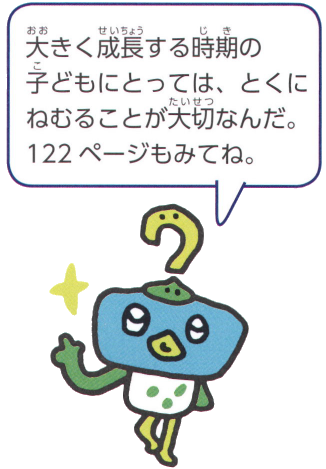
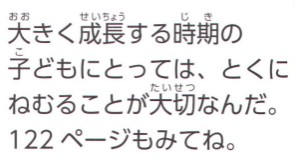
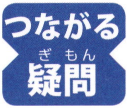
![]()
![]()
![]()
![]()

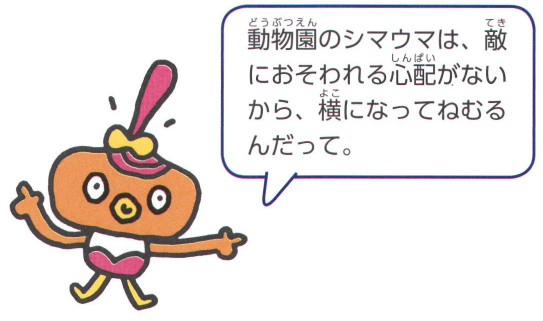
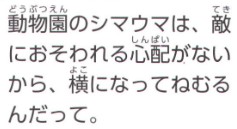
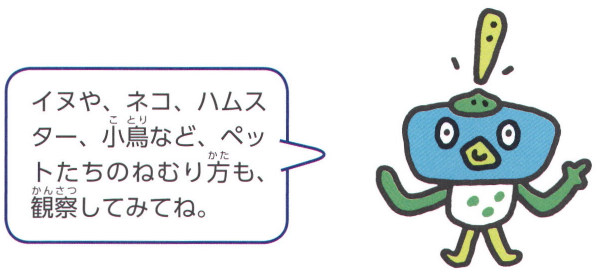
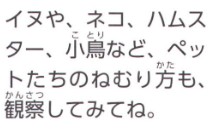
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
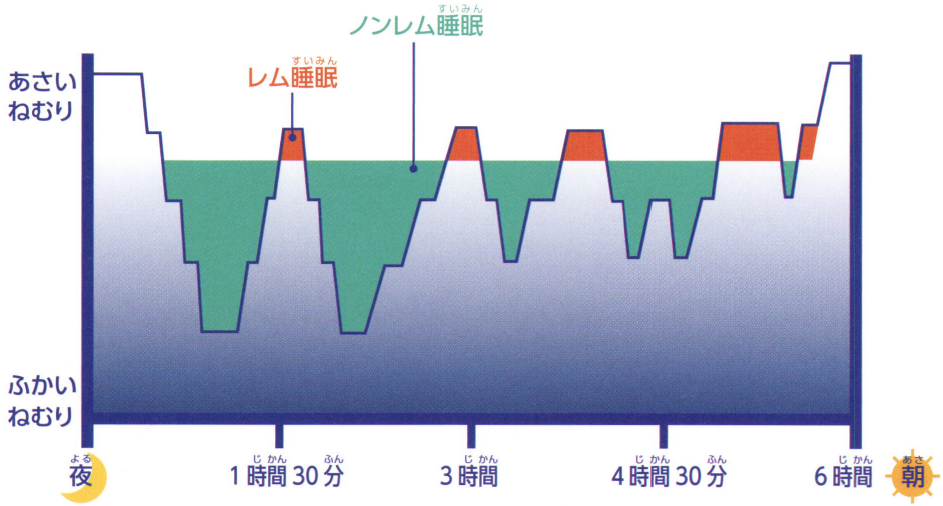
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
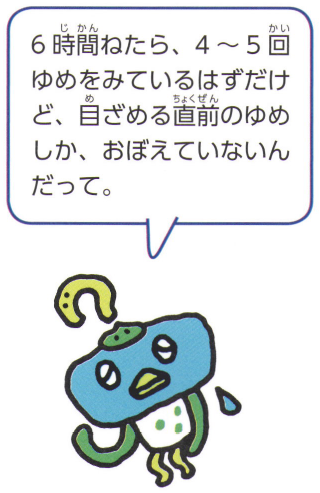
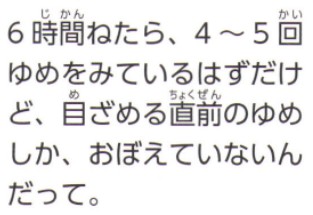
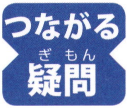
![]()
![]()
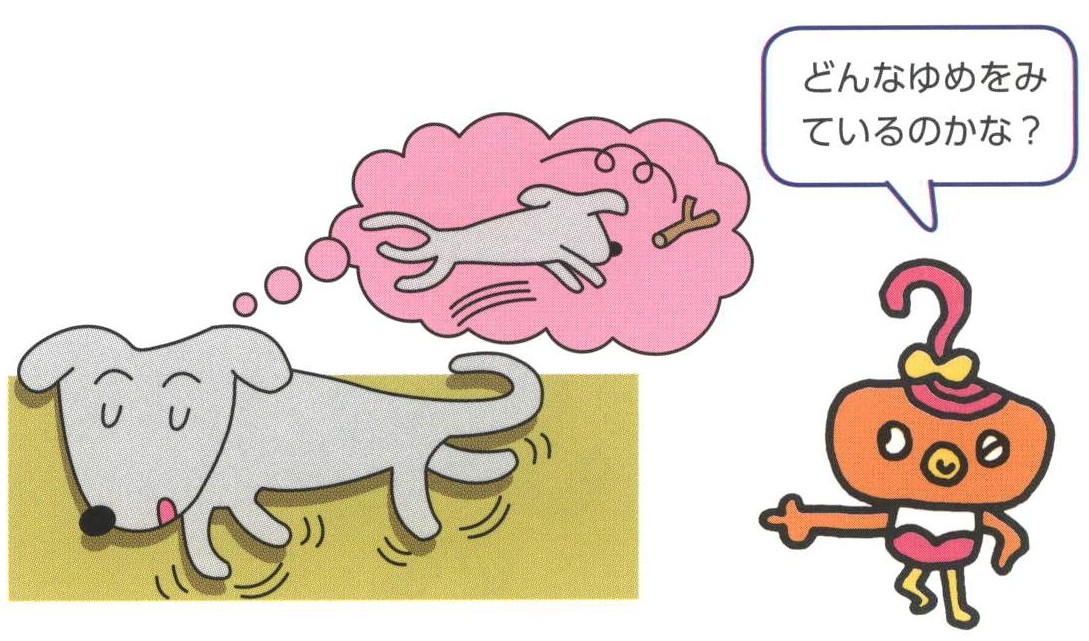
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
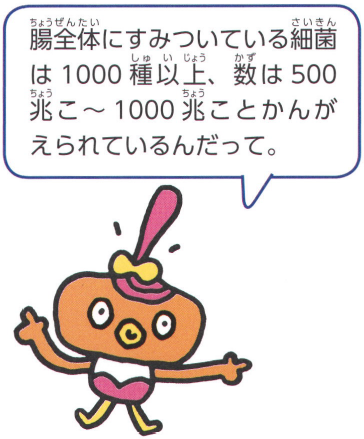
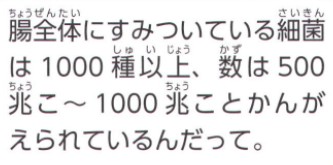
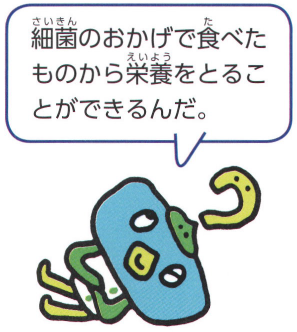
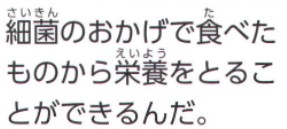
![]()

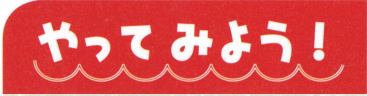
![]()
![]()
![]()
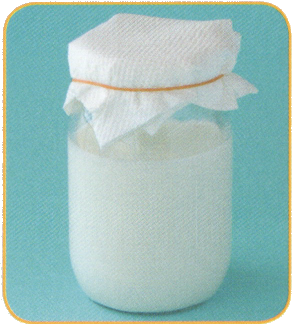

![]()

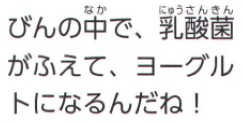
![]()
![]()
![]()
![]()
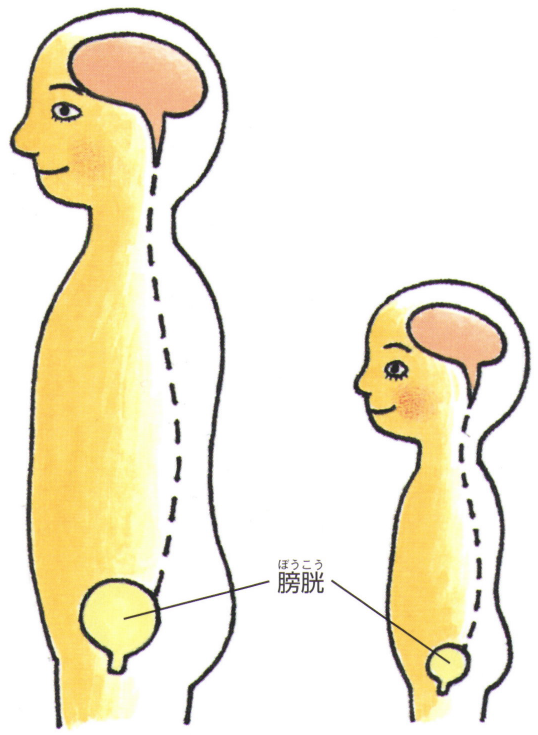
![]()
![]()
![]()
![]()
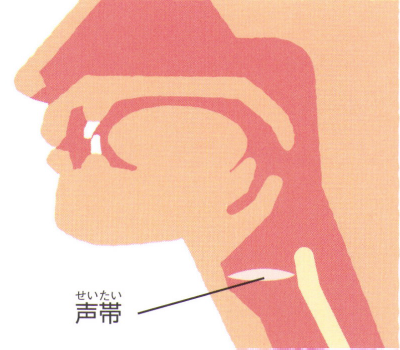
![]()
![]()
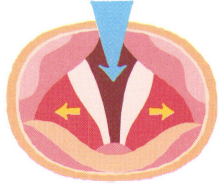
![]()
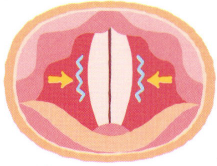
![]()
![]()
![]()
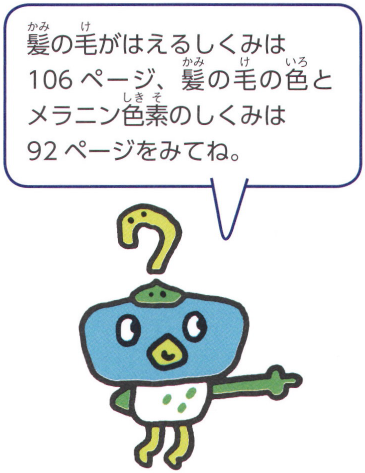
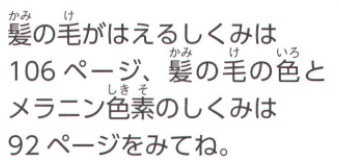
![]()
![]()
![]()
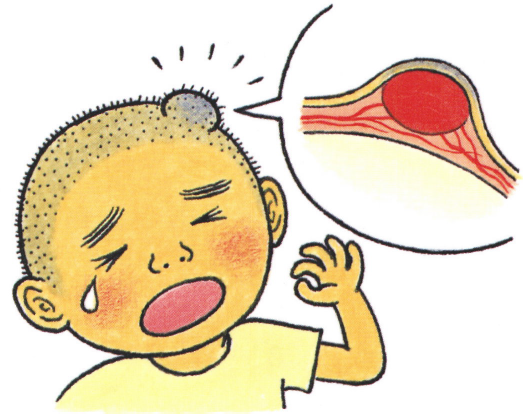

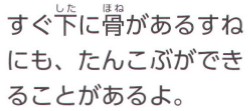
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
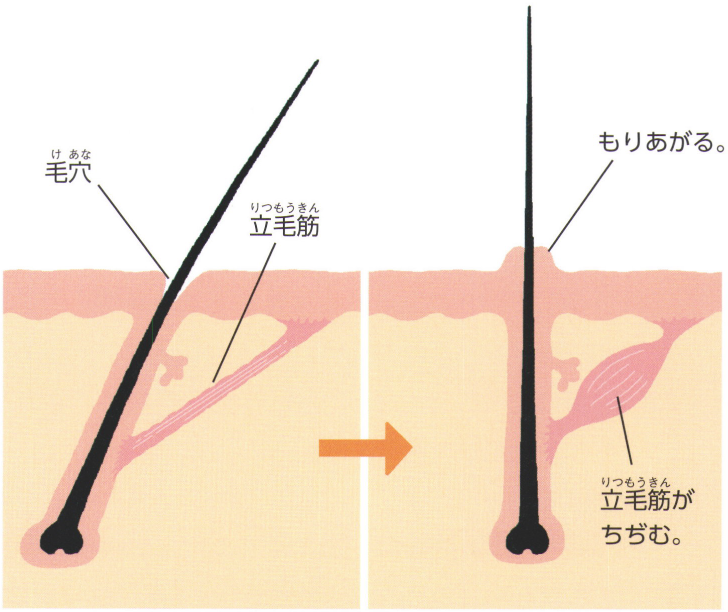
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
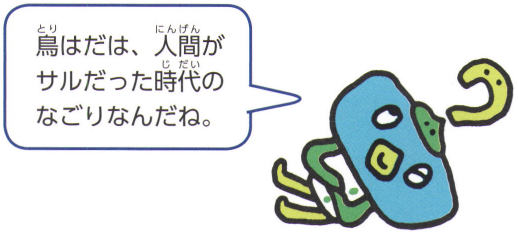
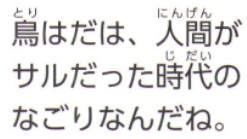
![]()
![]()
![]()
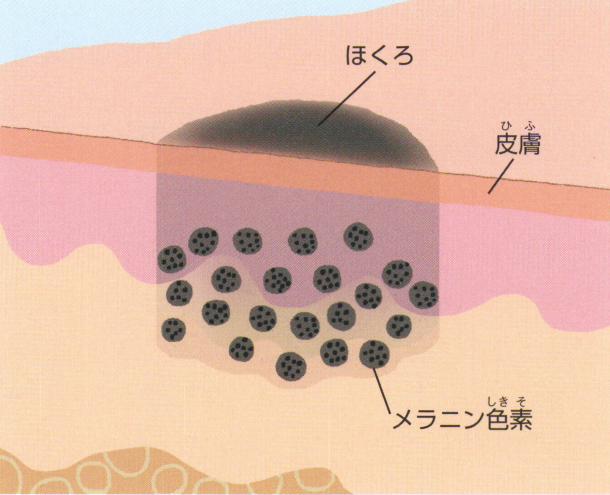
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
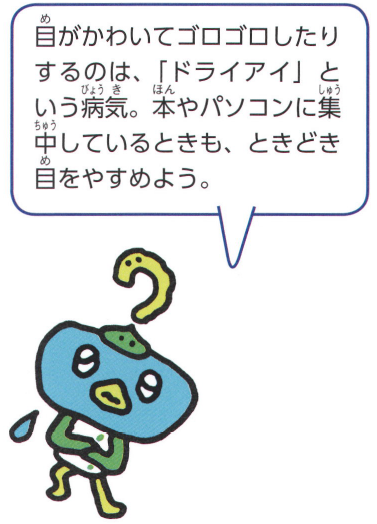
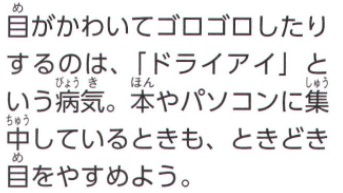
![]()
![]()
![]()
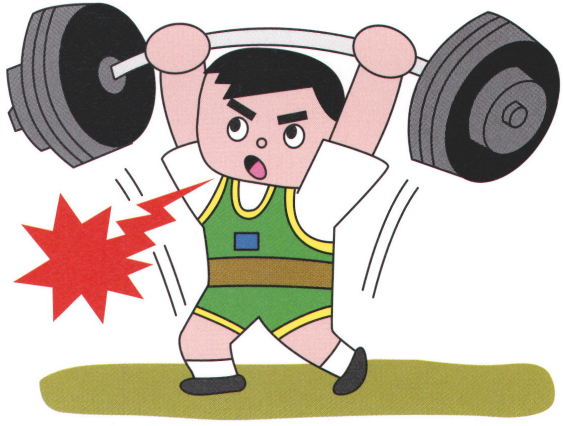
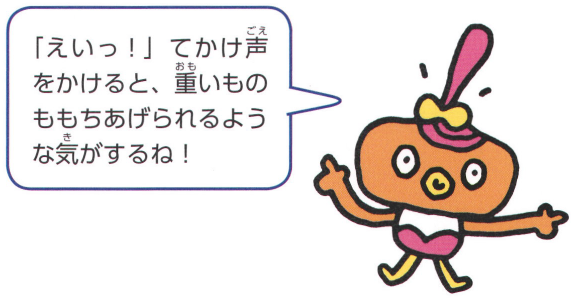
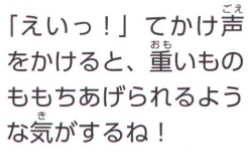
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
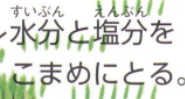
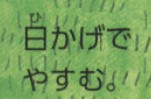
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
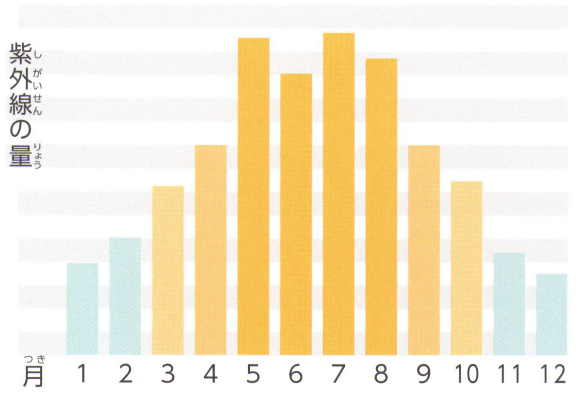
![]()
![]()
![]()
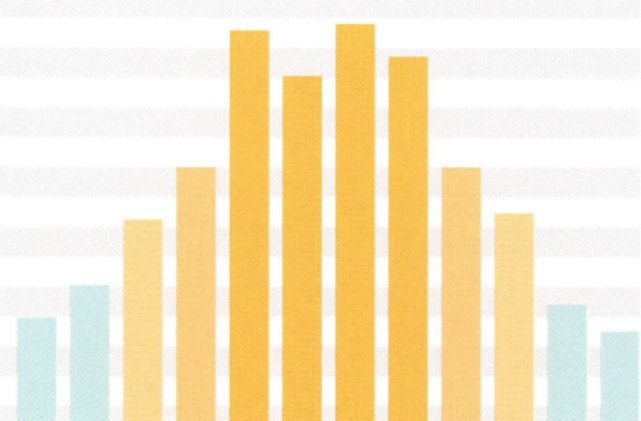
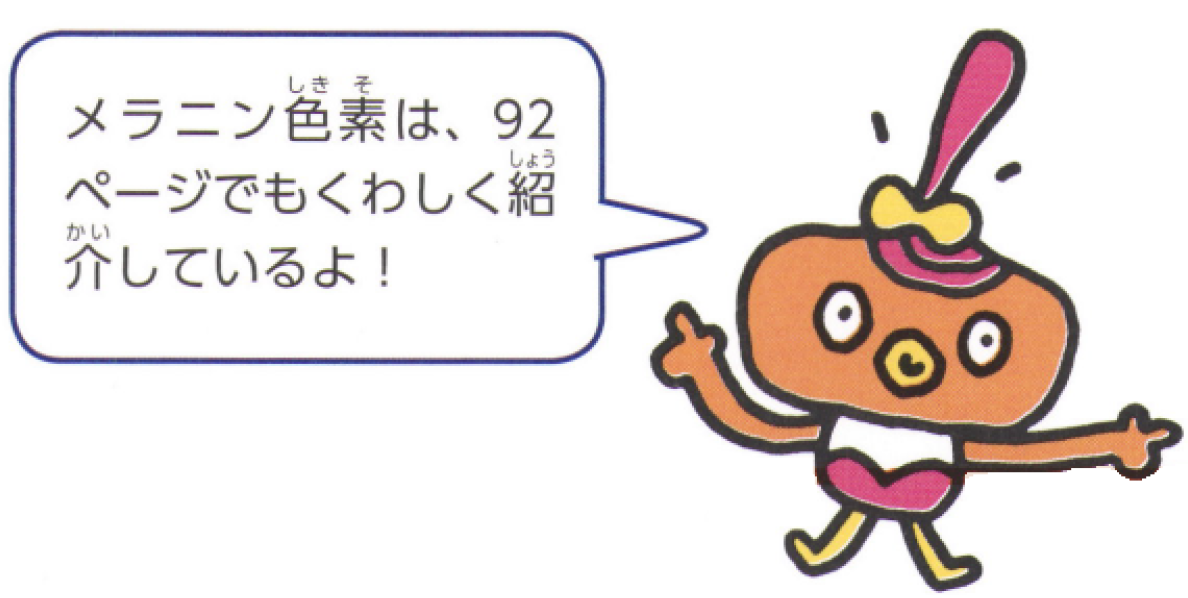
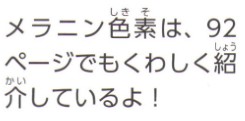
![]()
![]()
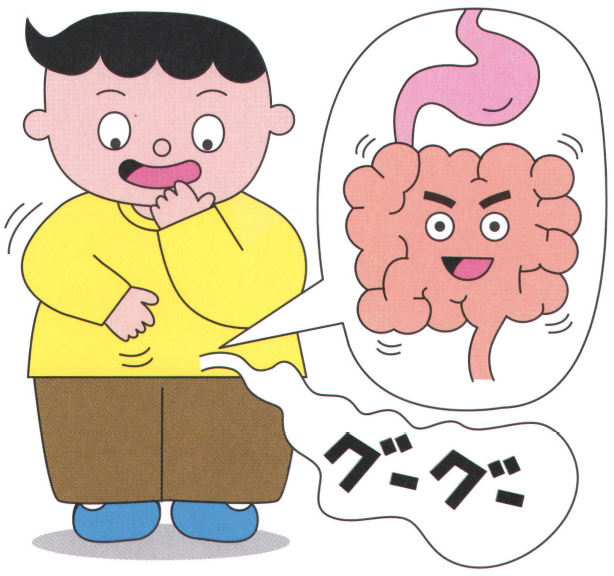
![]()
![]()
![]()
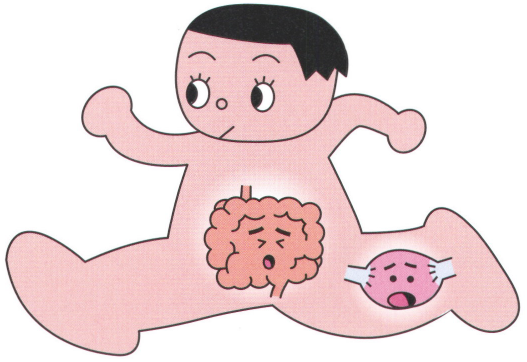
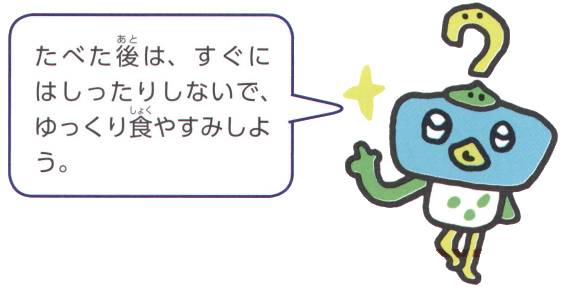
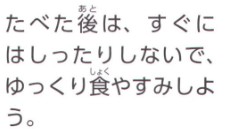
![]()
![]()
![]()
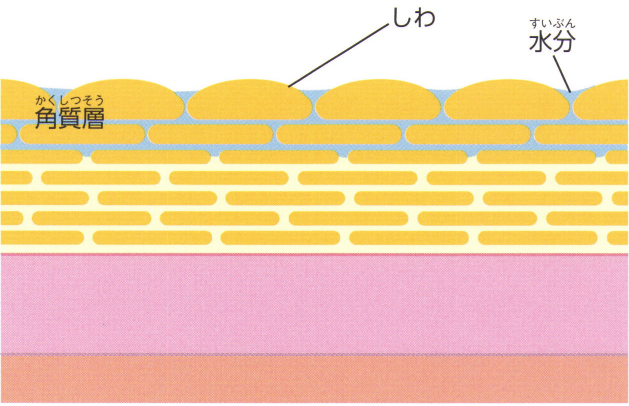
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
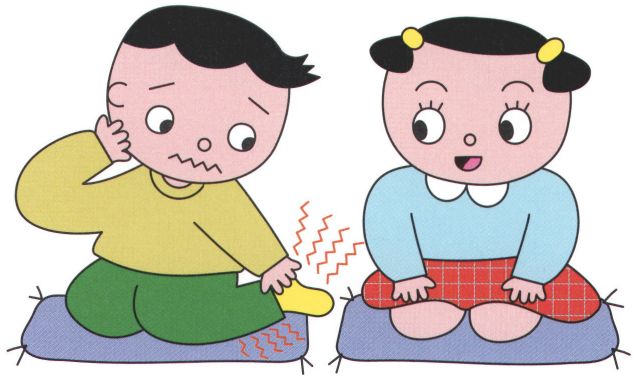
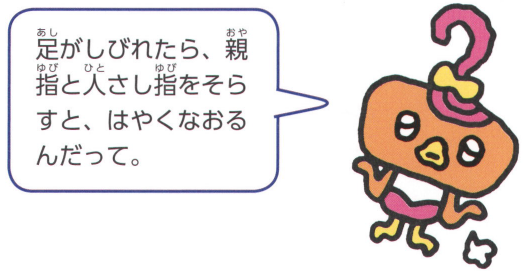
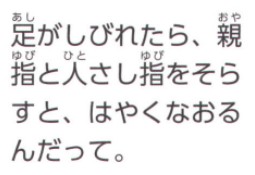
![]()
![]()
![]() アイス
アイス

![]()
![]()
![]()
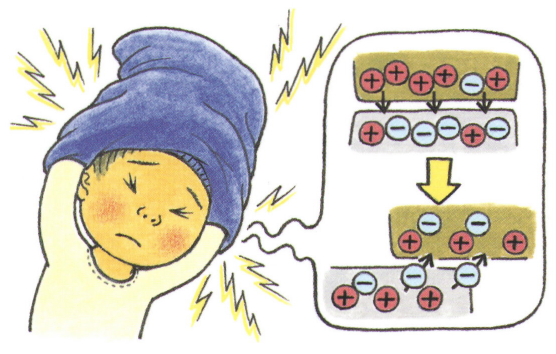
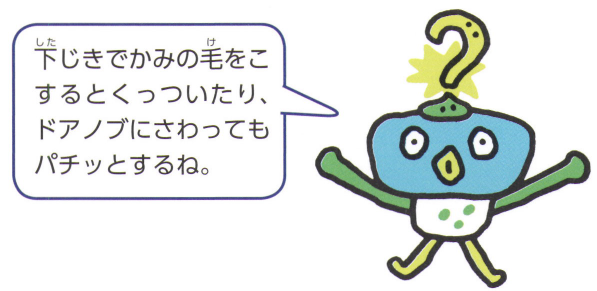
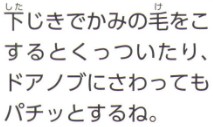

![]()
![]()
![]()
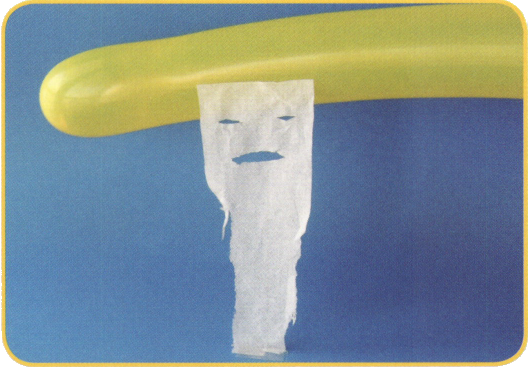

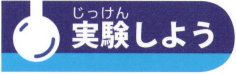
![]()

![]()
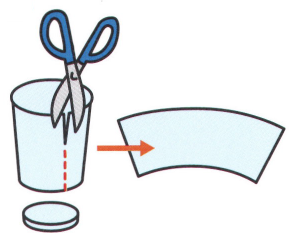

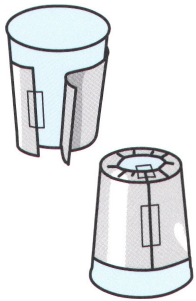
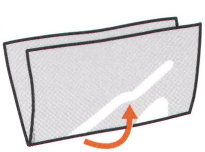
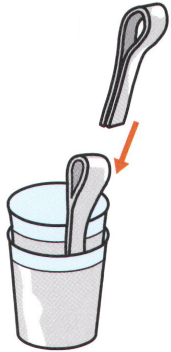
![]()
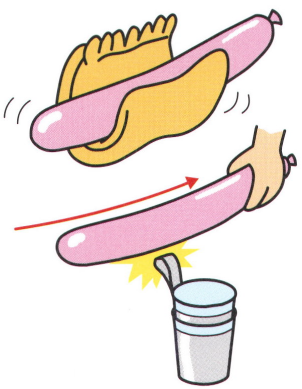



![]()
![]()
![]()

![]()
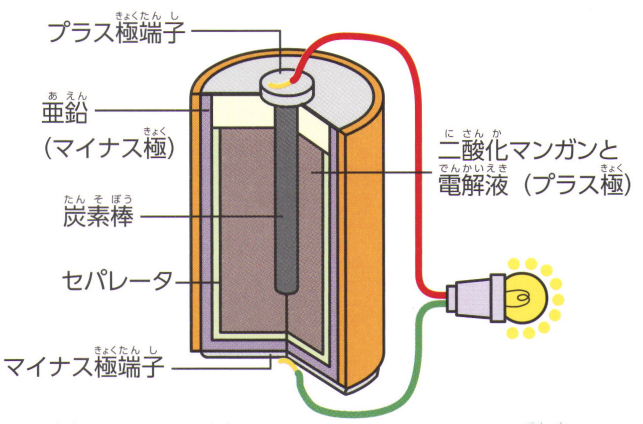
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
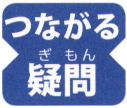
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
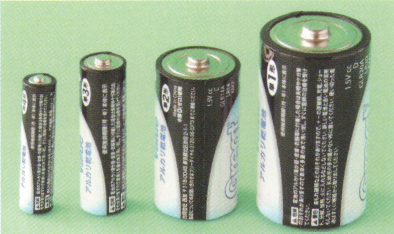
![]()

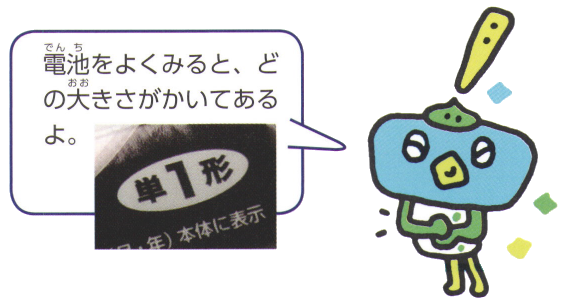
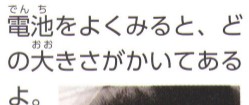
![]()
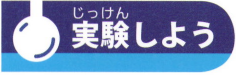
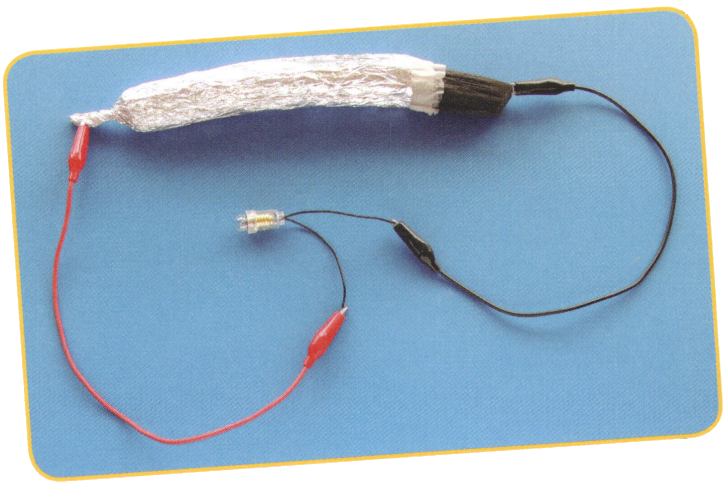
![]()
![]()
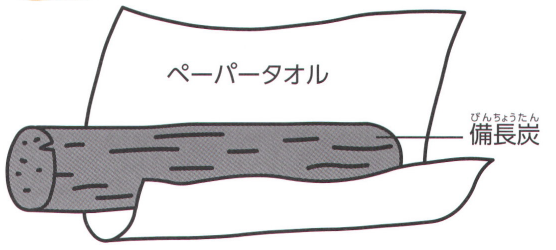
![]()
![]()
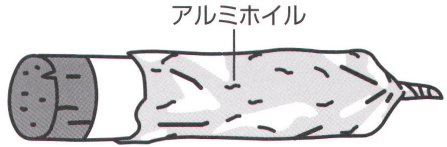
![]()
![]()
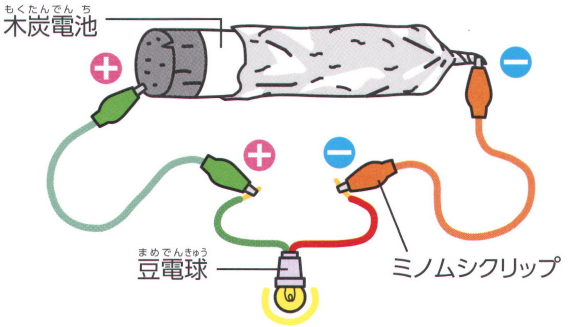
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
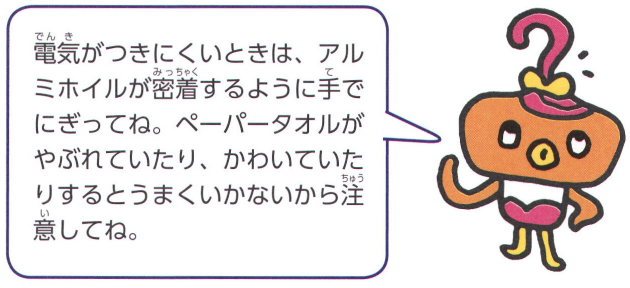
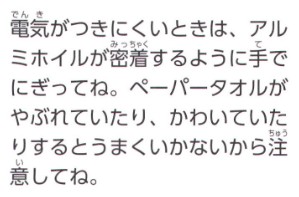

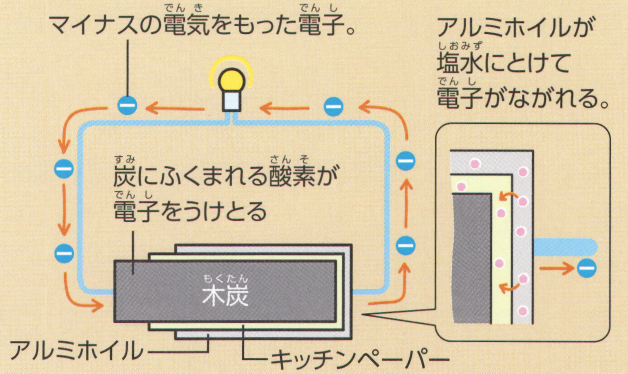
![]()
![]()
![]()
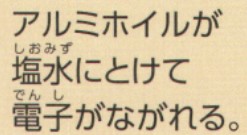
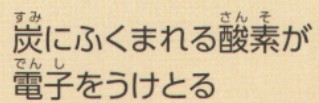
![]()
![]()
![]()
![]()
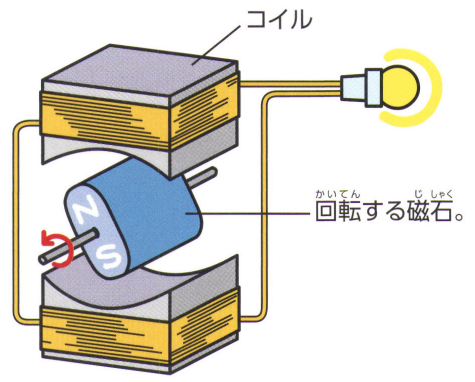
![]()
![]()
![]()

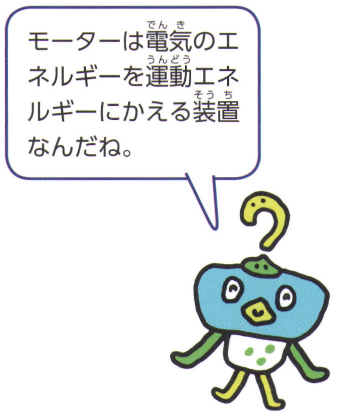
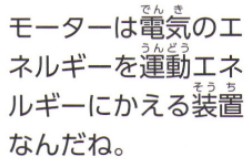
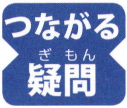
![]()
![]()
![]()
![]()
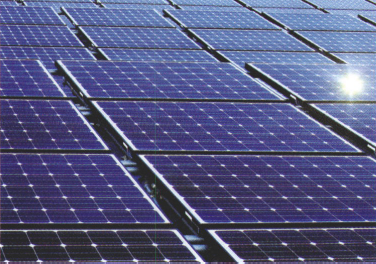
![]()
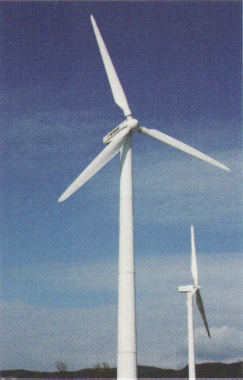
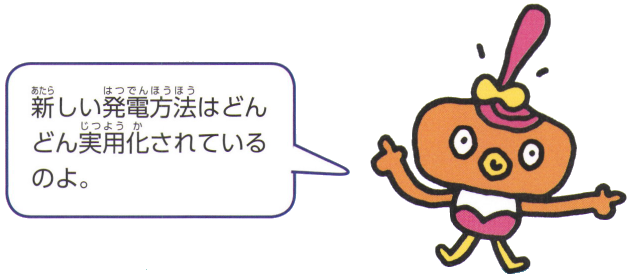
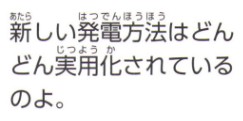
![]()
![]()
![]()
![]()
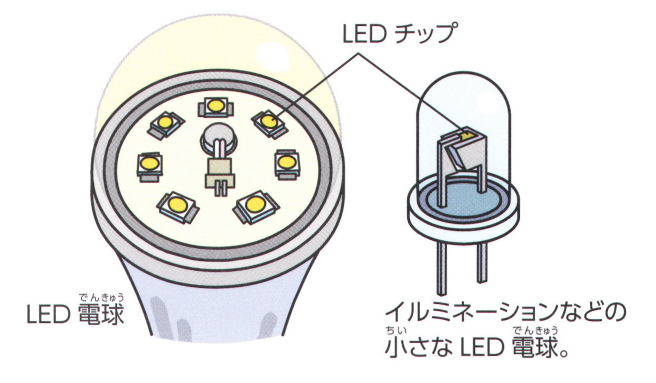
![]()
![]()
![]()
![]()
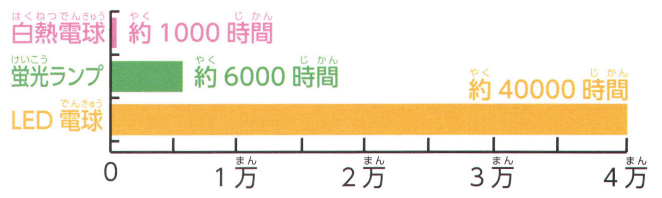
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
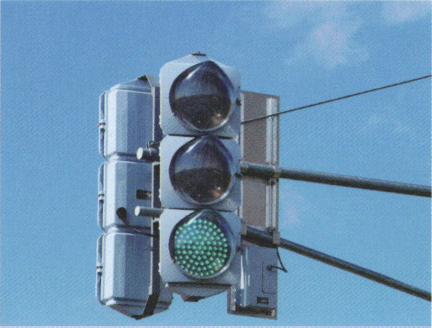
![]()

![]()

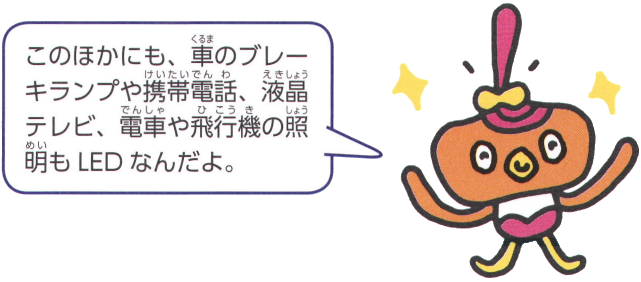
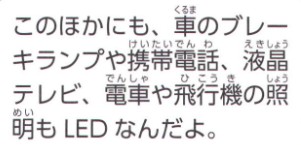
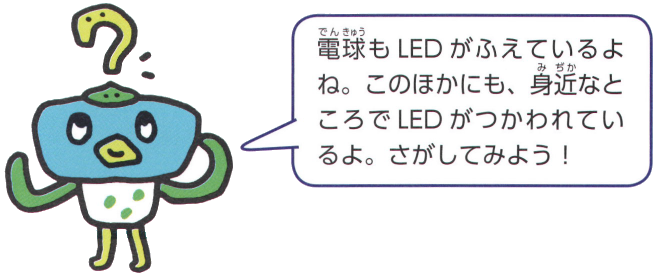
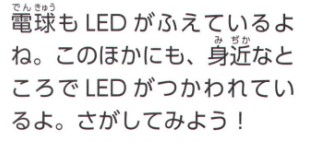
![]()
![]()
![]()
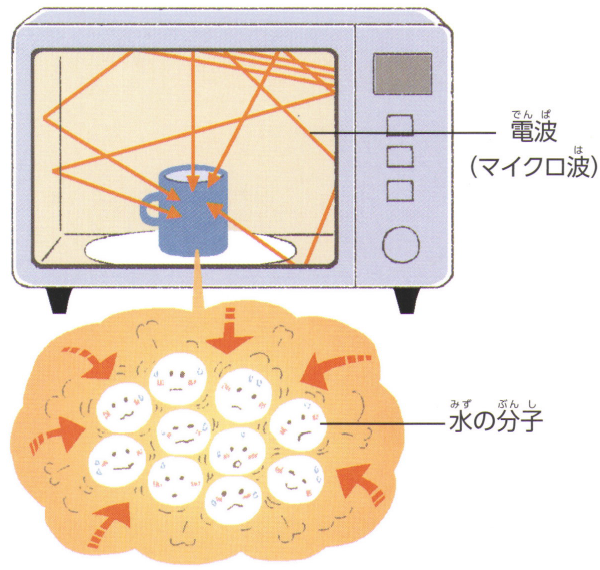
![]()
![]()
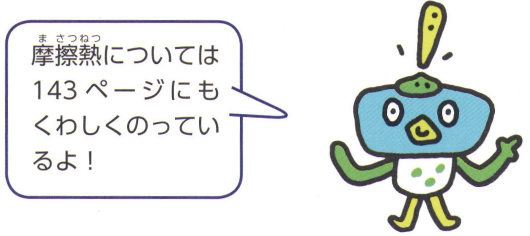
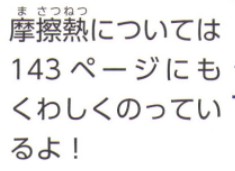
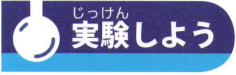
![]()
![]()
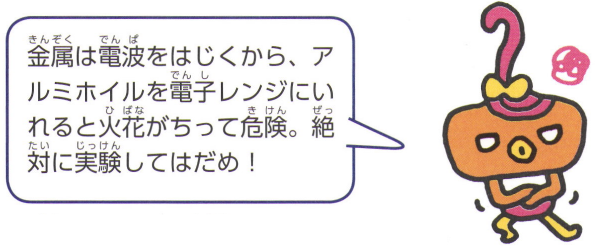
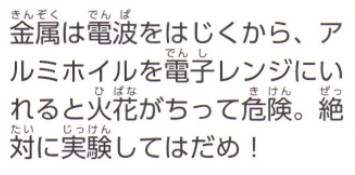

![]()
![]()
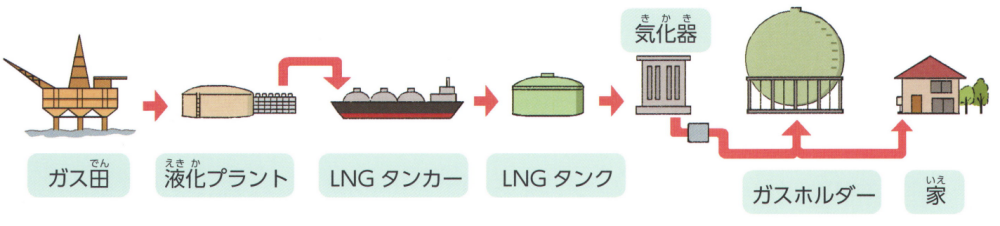
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
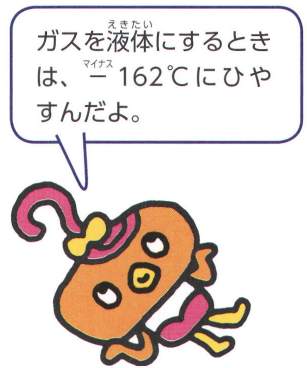
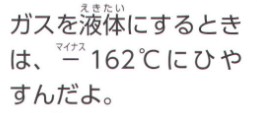
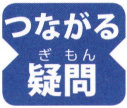
![]()
![]()
![]()
![]()
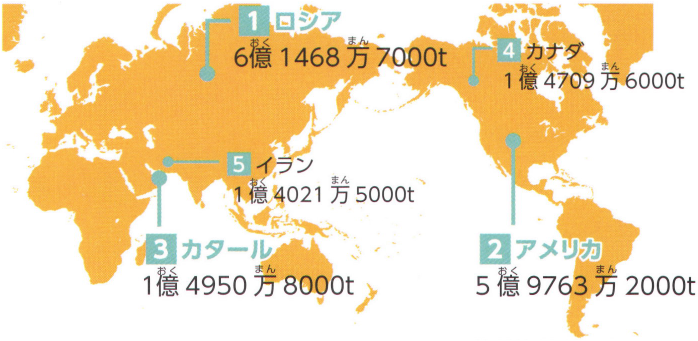
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
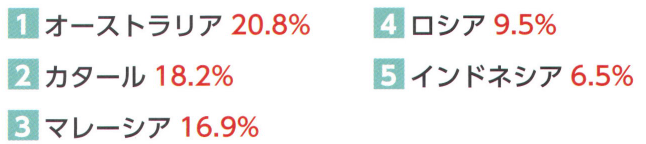
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
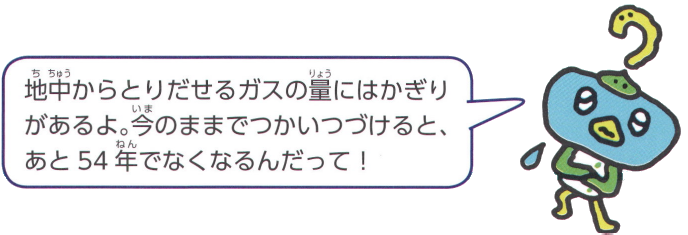
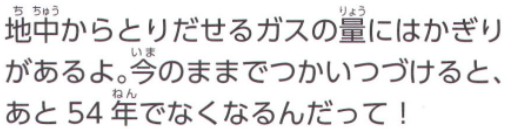
![]()
![]()
![]()
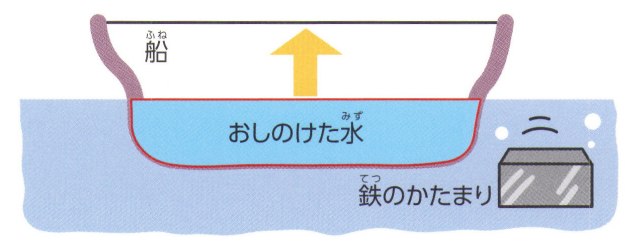
![]()
![]()
![]()
![]()
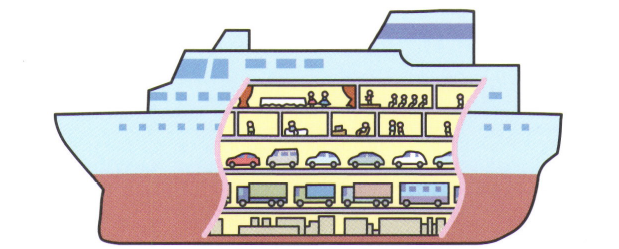
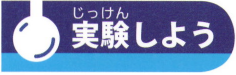
![]()
![]()
![]()
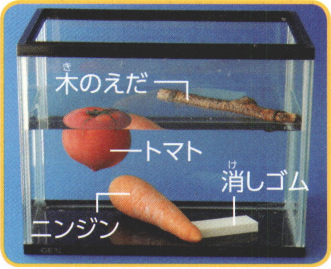
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
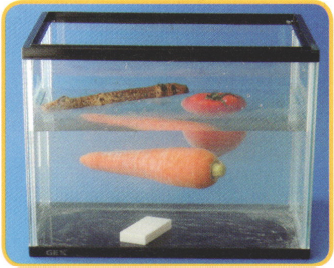
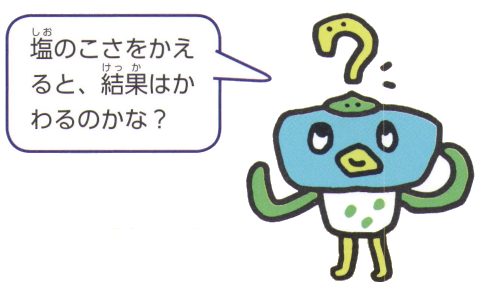
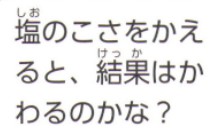

![]()
![]()
![]()
![]()
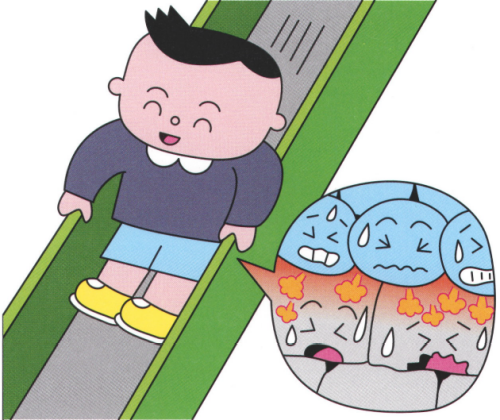
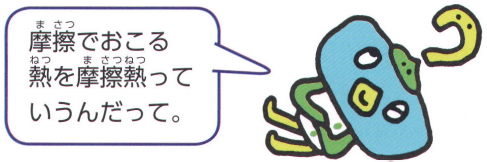
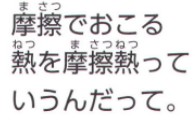
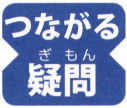
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
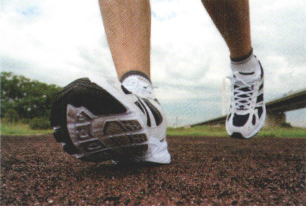
![]()

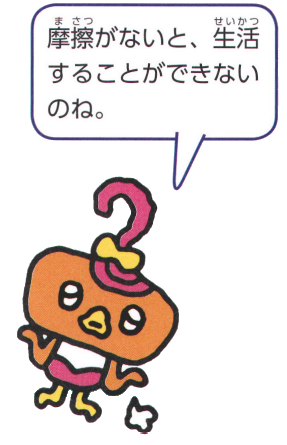
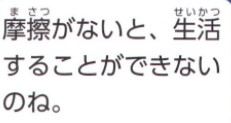
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
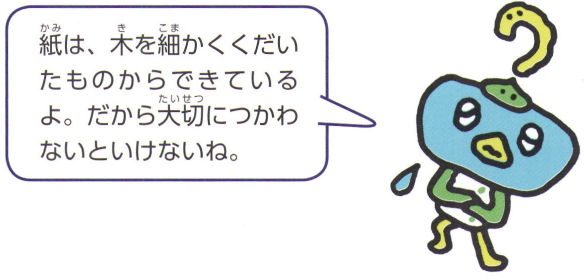
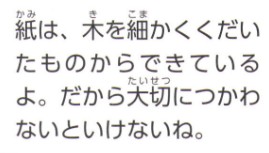

![]()

![]()
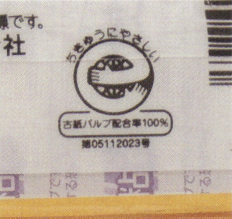
![]()
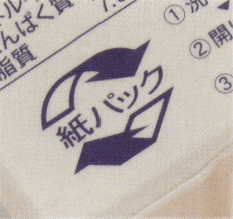
![]()

![]()
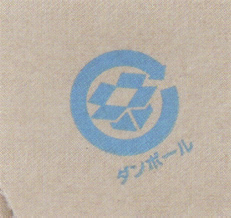

![]()
![]()

![]()
![]()
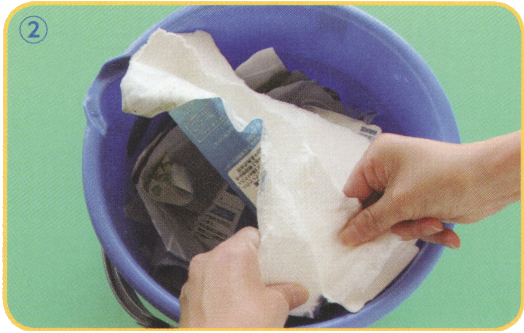
![]()

![]()


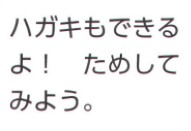
![]()
![]()
![]()
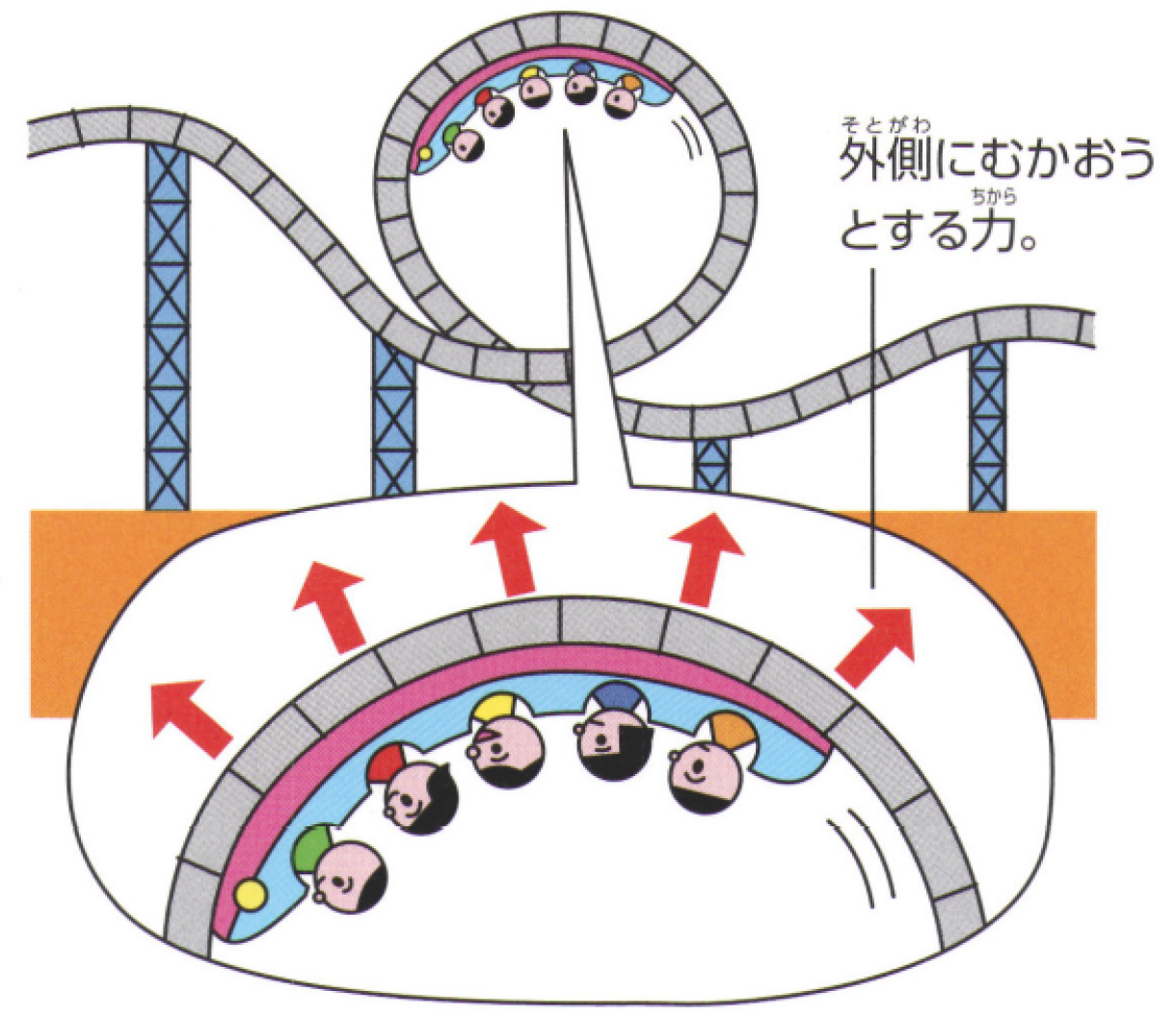
![]()
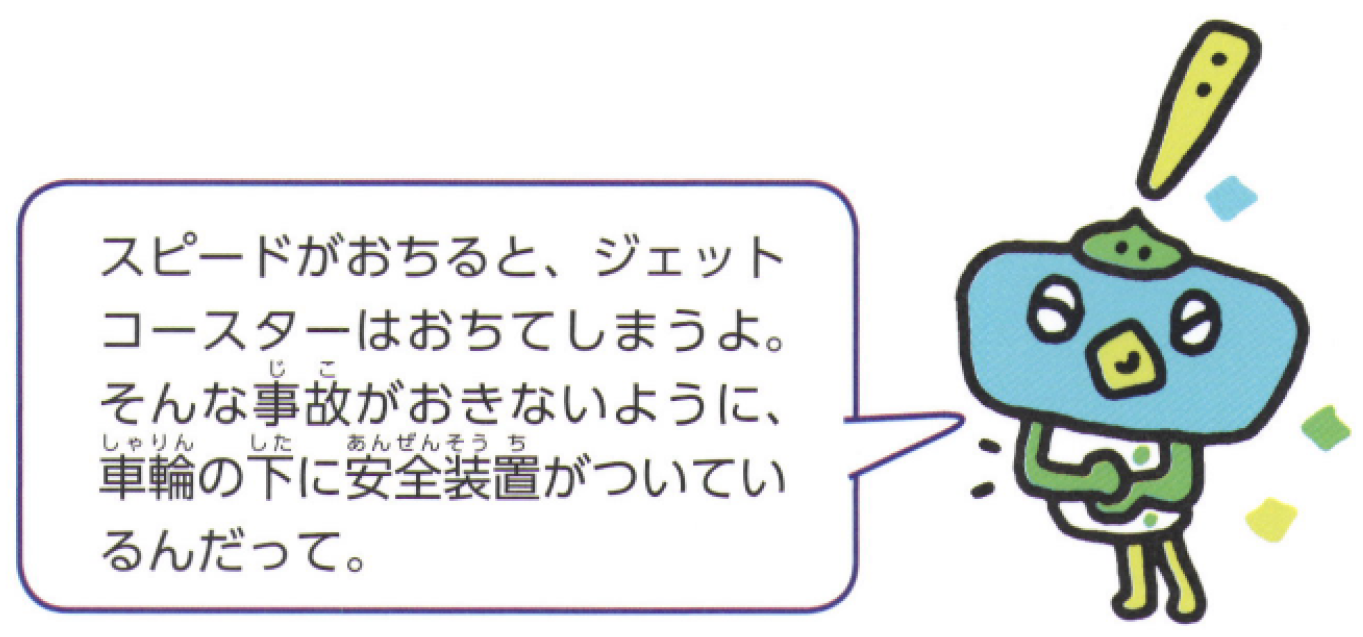
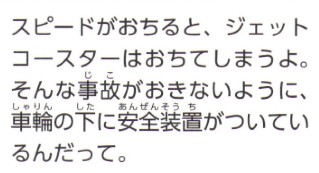

![]()
![]()

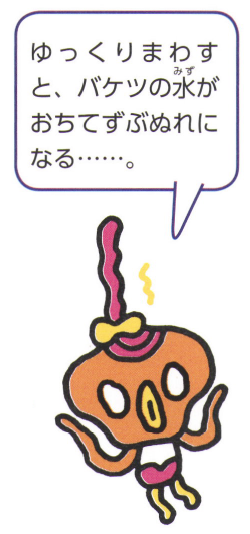
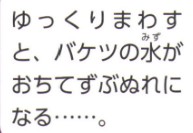

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
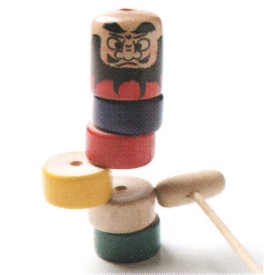
![]()

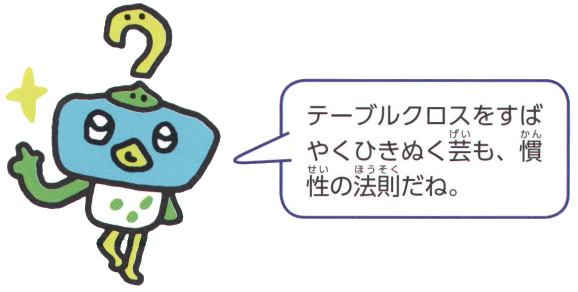
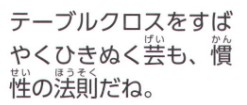
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
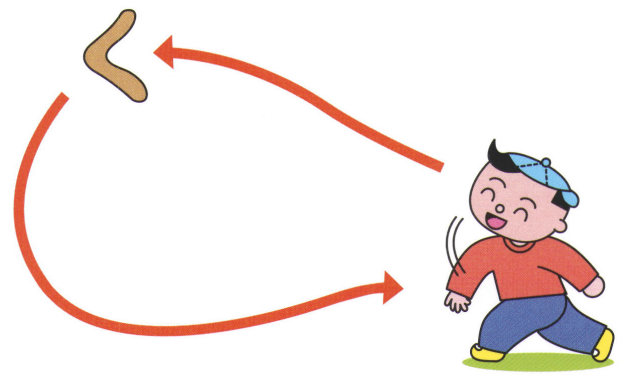
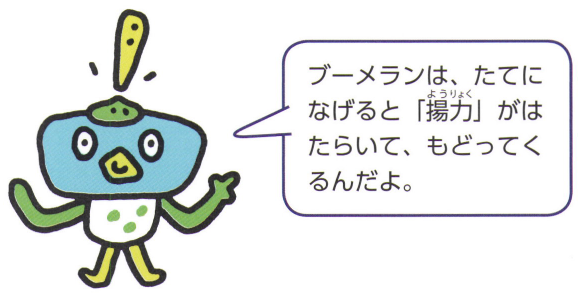
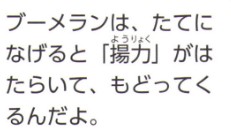
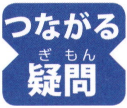
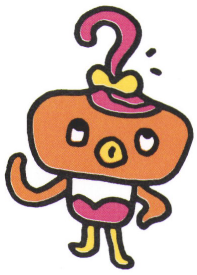
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
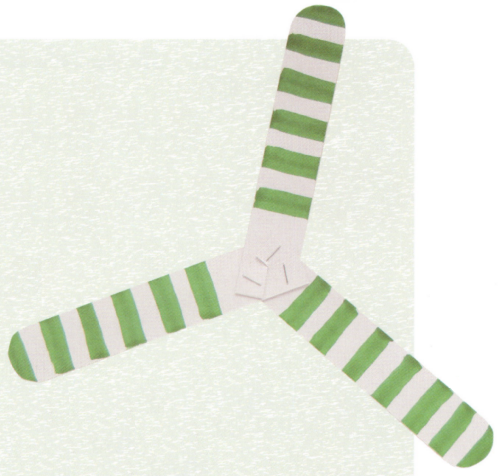
![]()
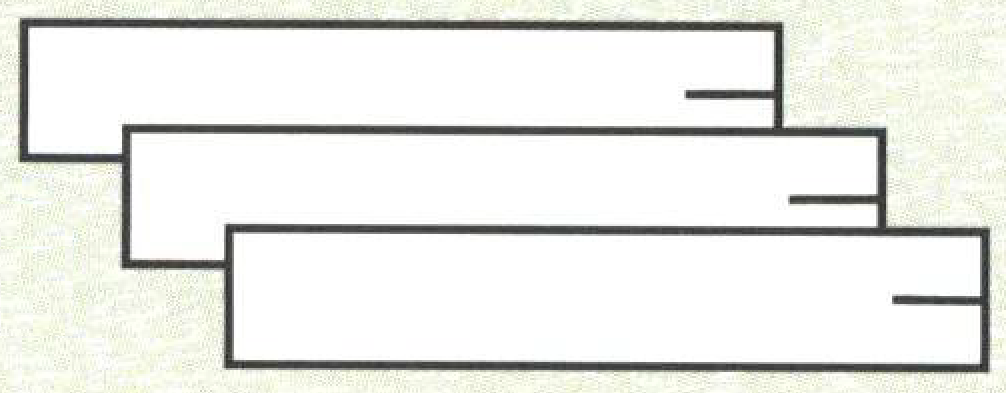
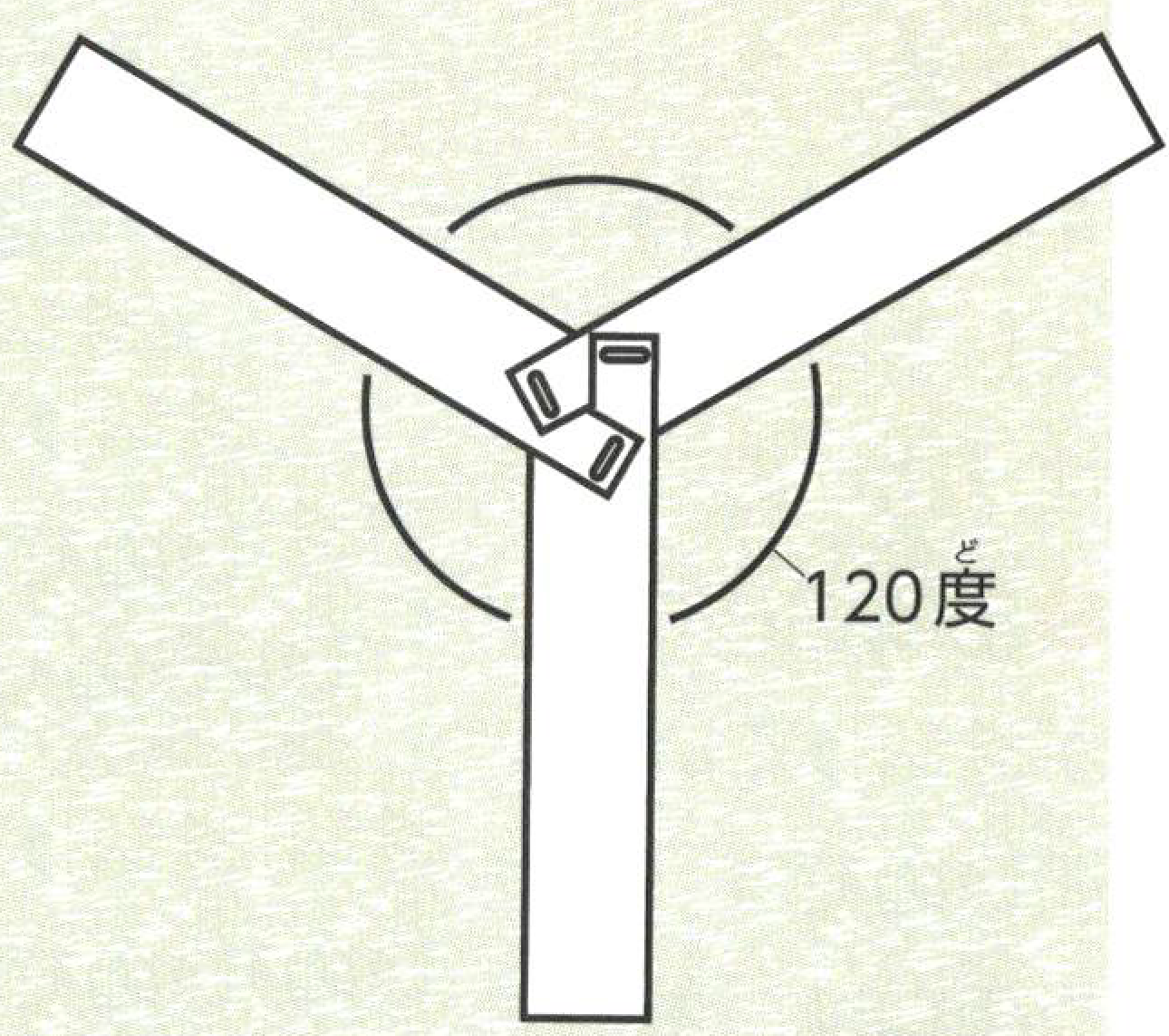
![]()
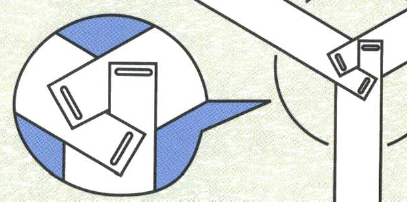

![]()
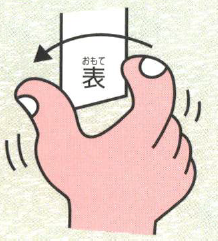
![]()
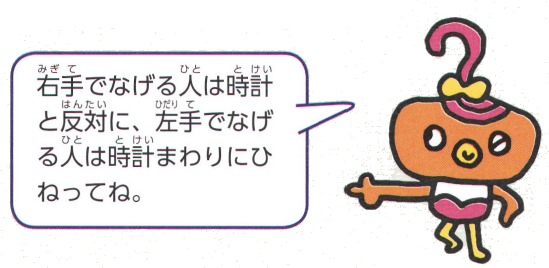
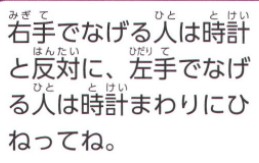
![]()
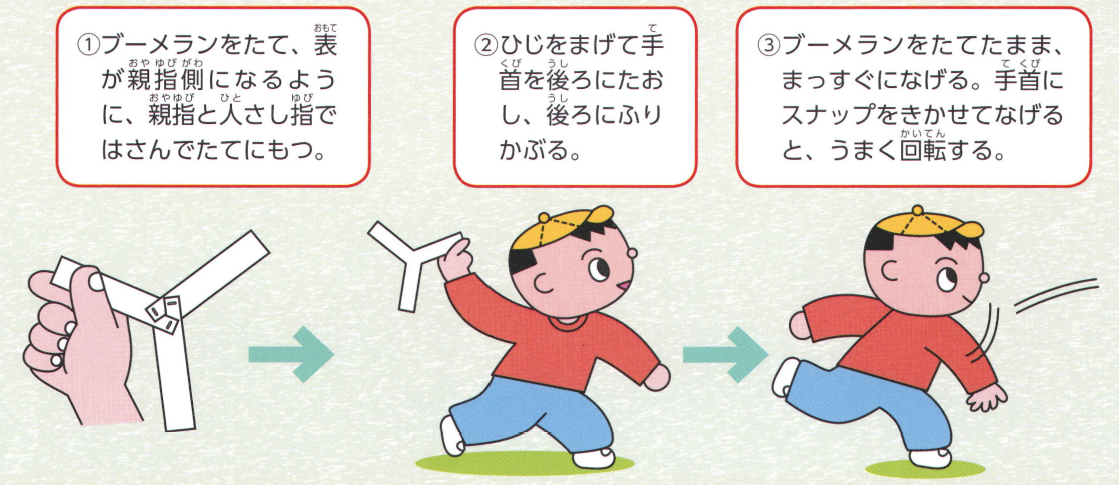
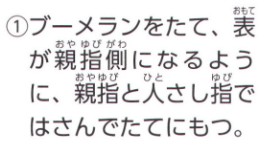
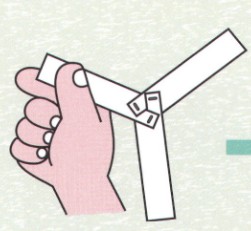
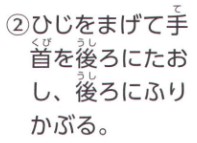
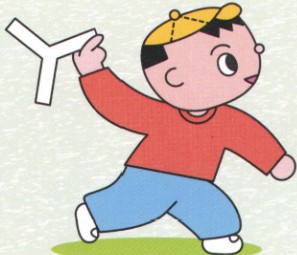
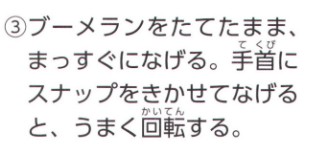


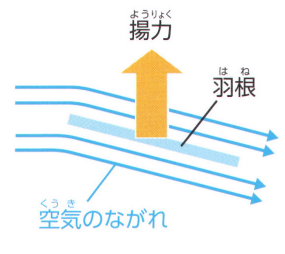
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
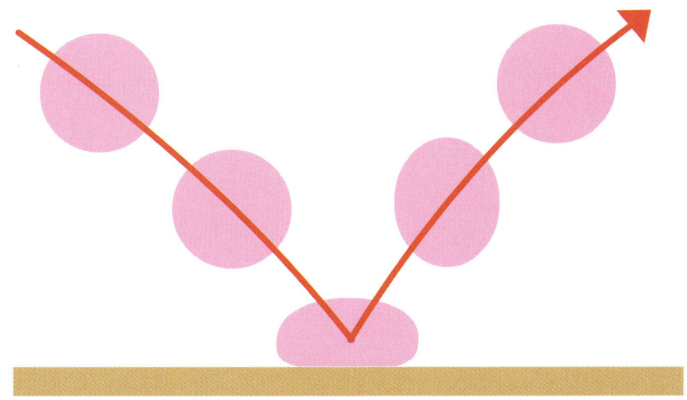
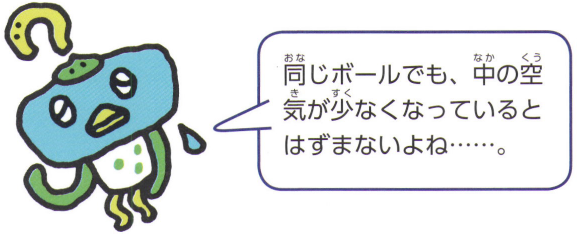
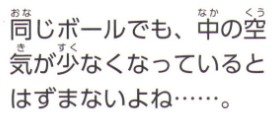
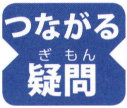
![]()
![]()
![]()
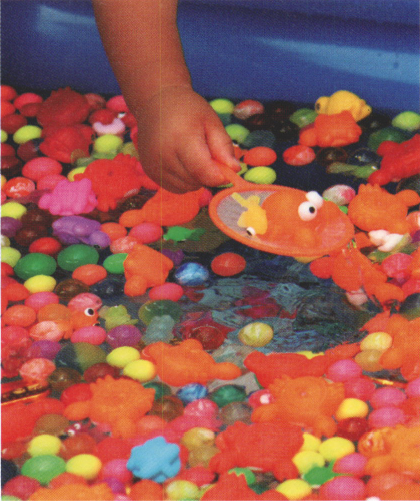
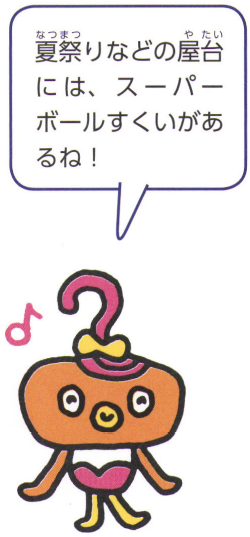
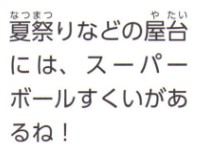
![]()
![]()
![]()
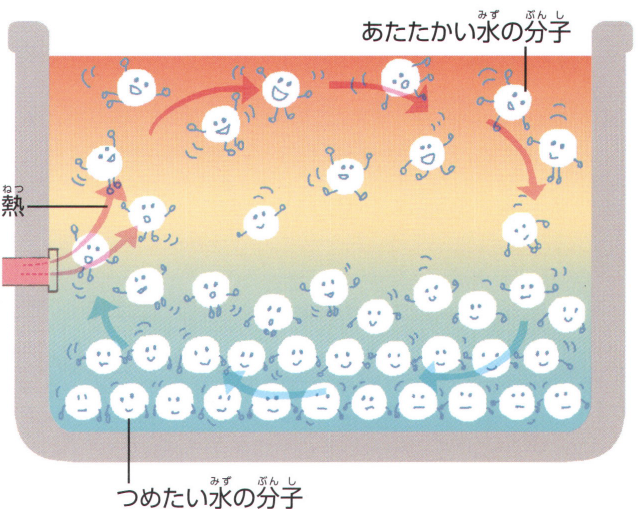
![]()
![]()
![]()
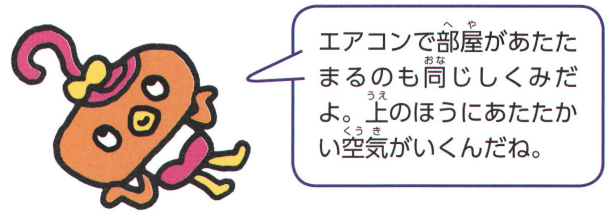
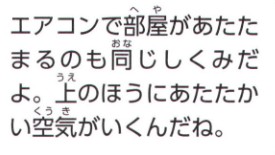

![]()
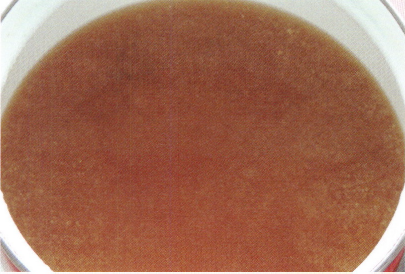
![]()

![]()
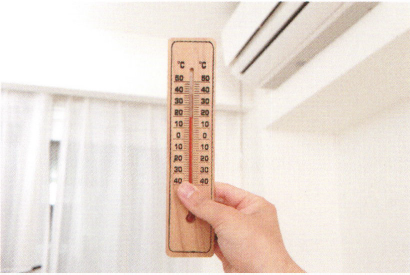
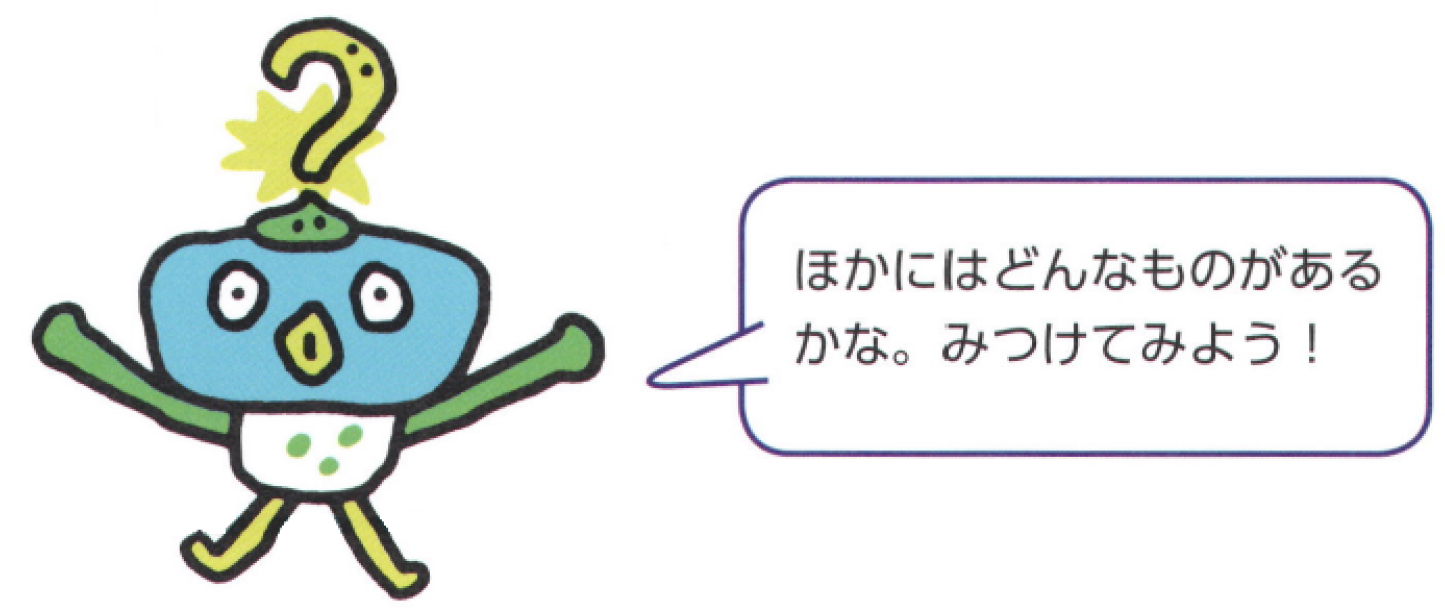
![]()
![]()
![]()
![]()
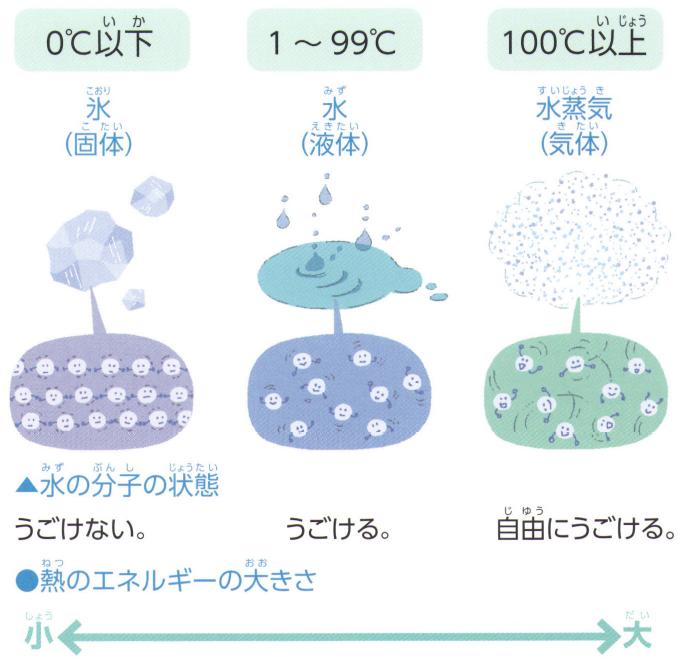
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
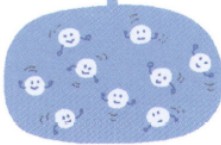
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()


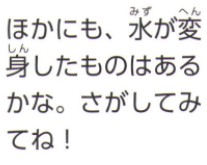
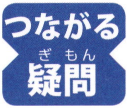
![]()
![]()
![]()
![]()
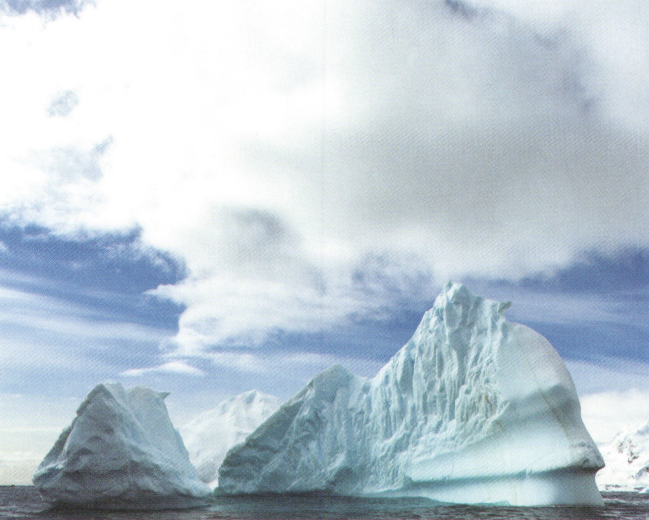
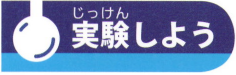
![]()
![]()
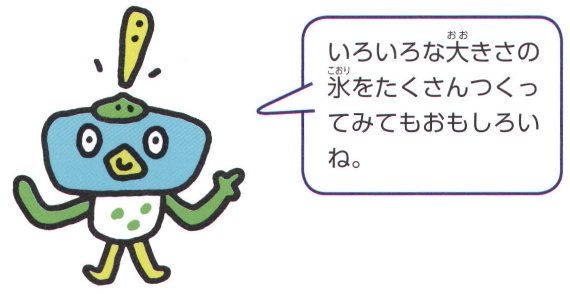
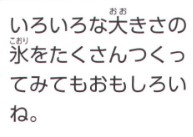

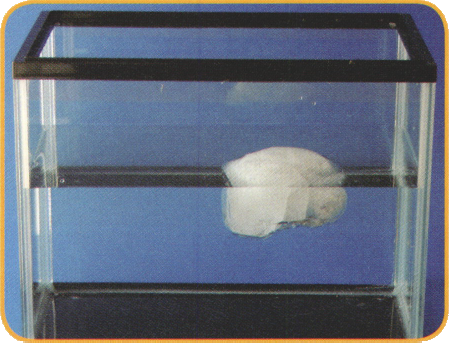
![]()
![]()
![]()
![]()
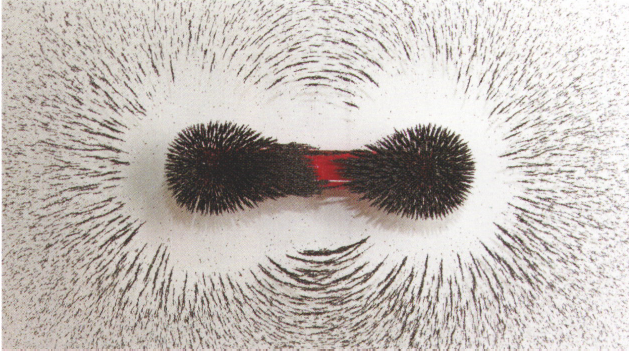
![]()
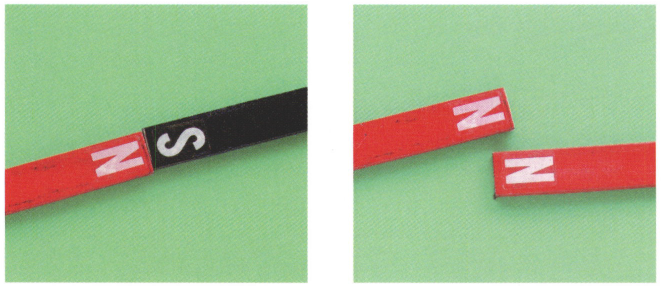
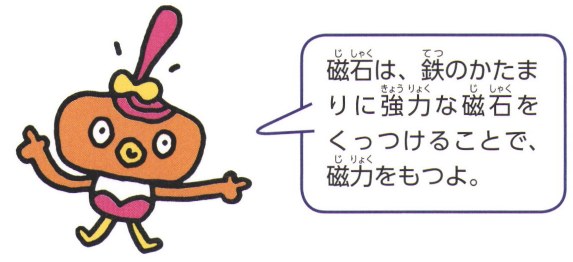
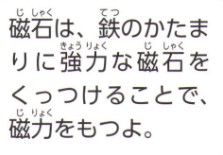
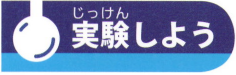
![]()
![]()

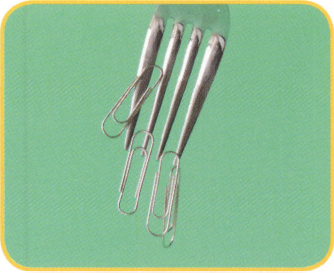

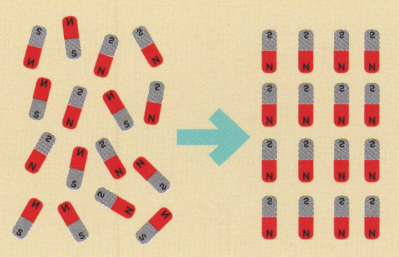
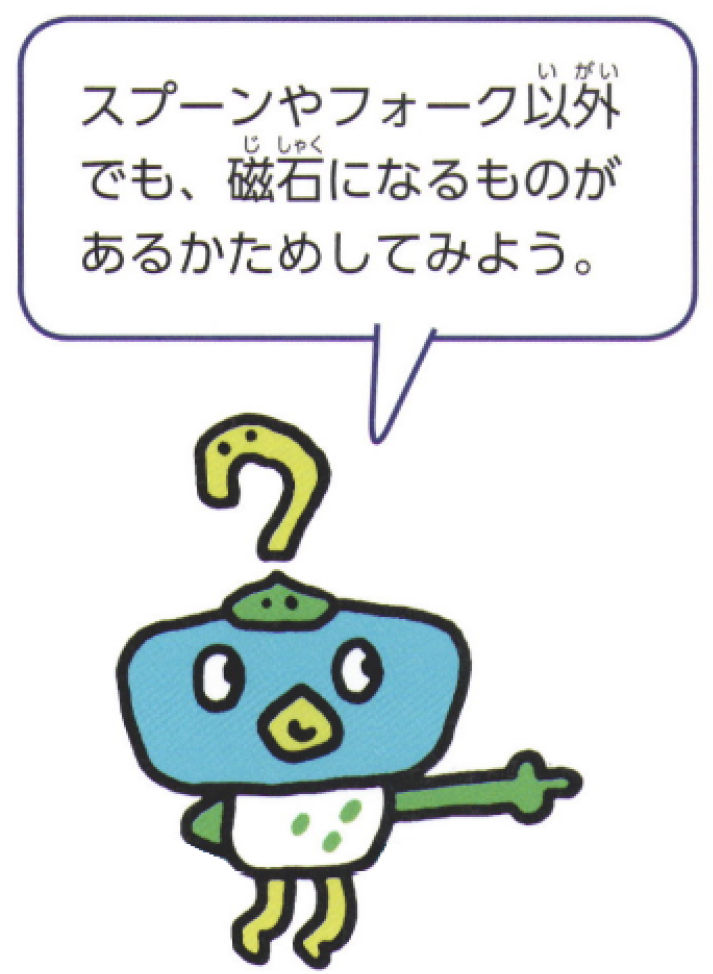
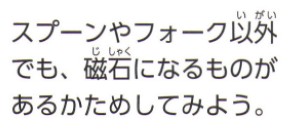
![]()
![]()
![]()
![]()
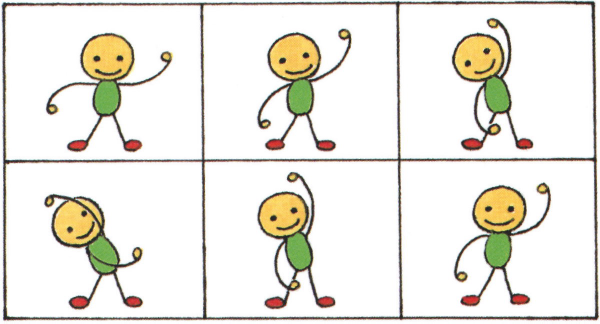
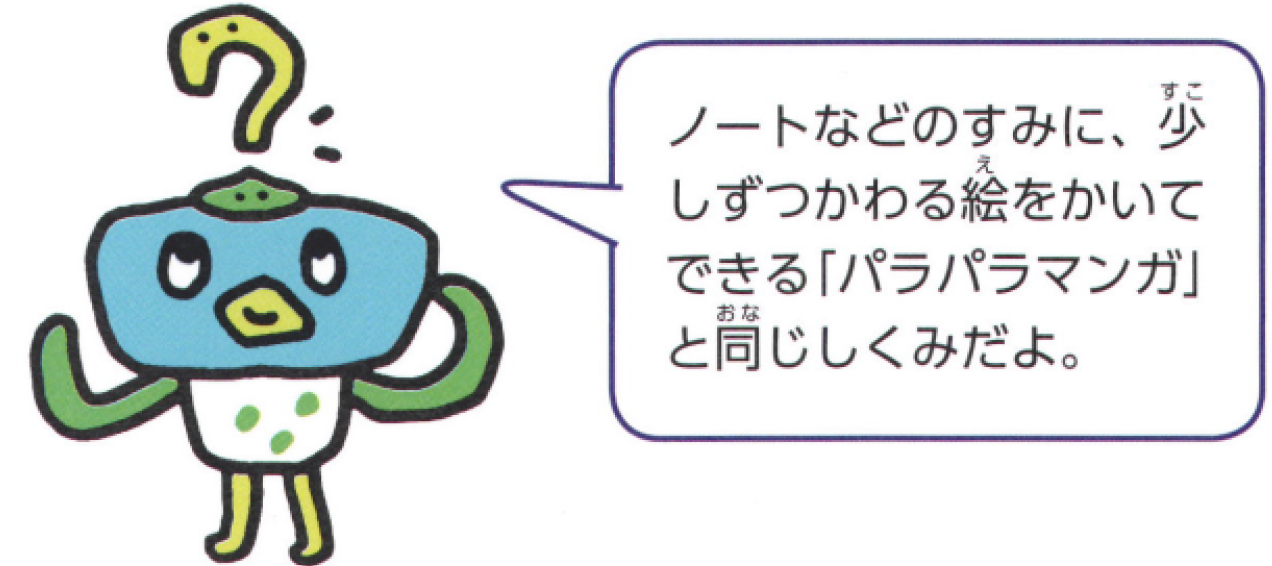
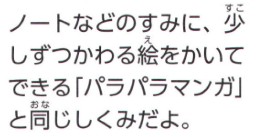

![]()
![]()
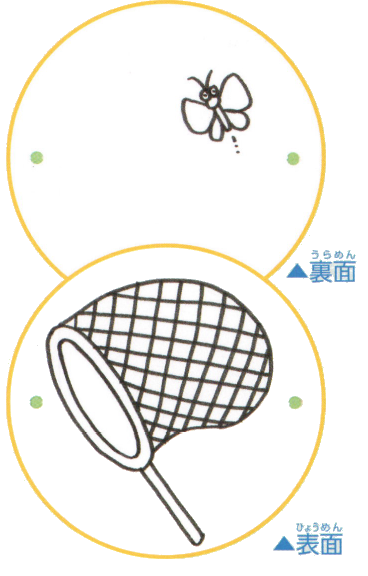
![]()
![]()
![]()
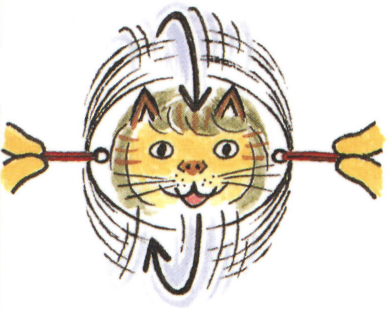
![]()
![]()
![]()
![]()
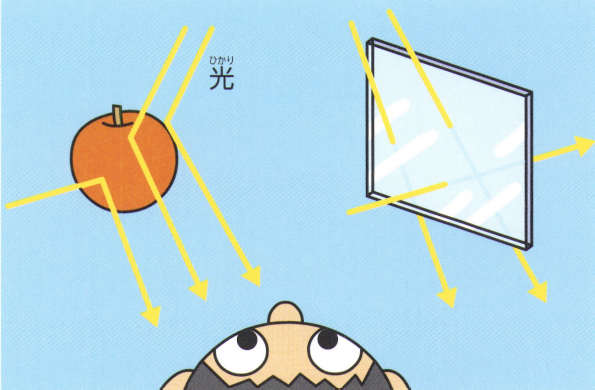
![]()
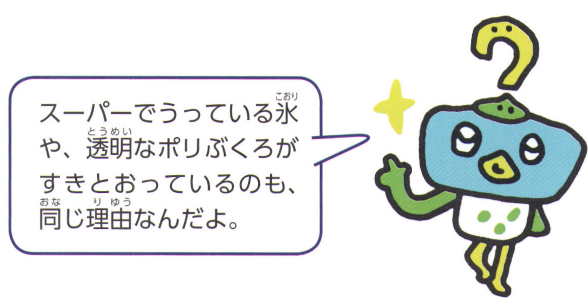
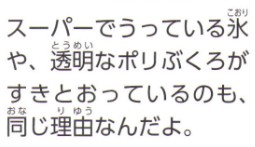
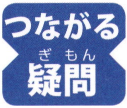
![]()
![]()
![]()
![]()
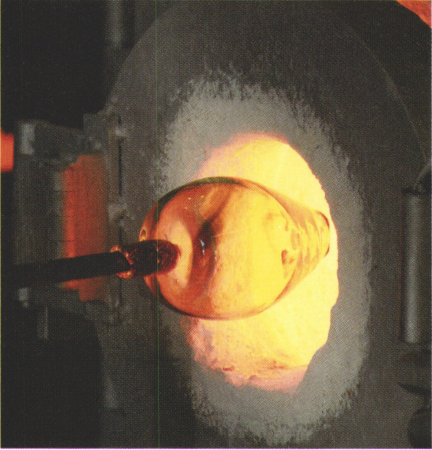

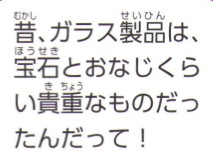
![]()
![]()
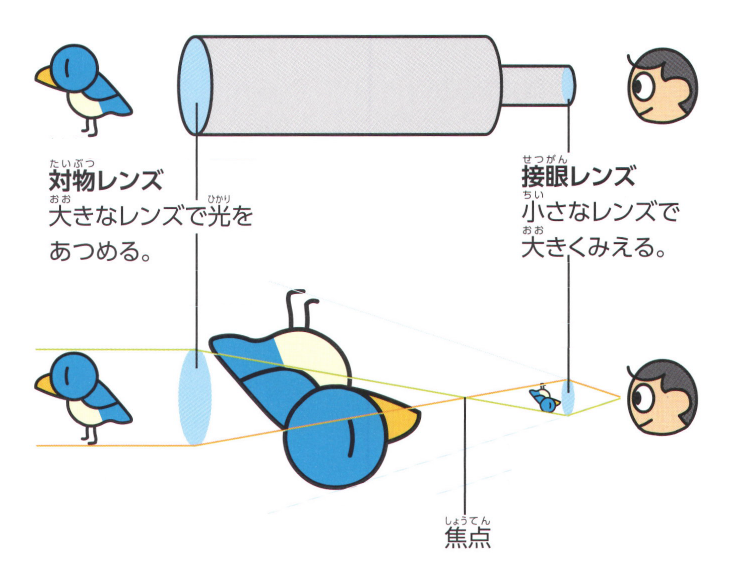
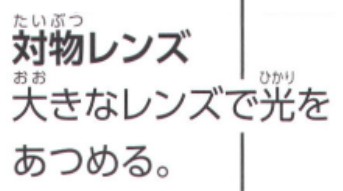

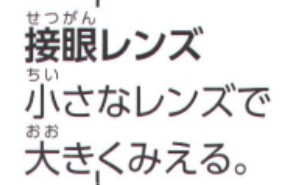
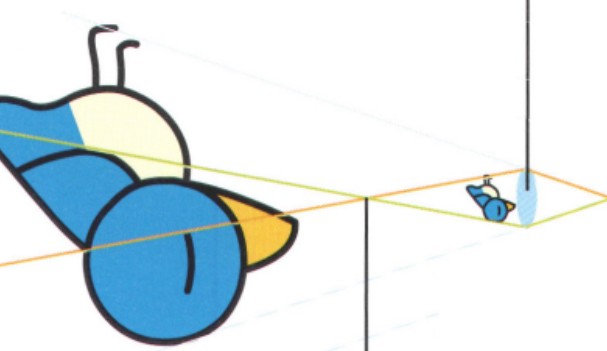
![]()
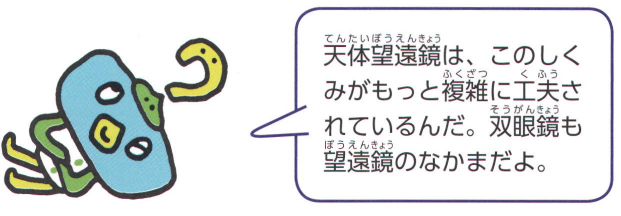
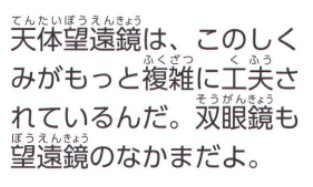
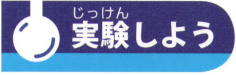
![]()
![]()
![]()

![]() 目から
目から

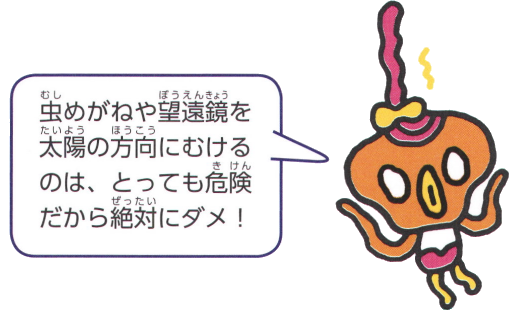
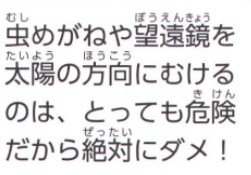
![]()
![]()
![]()
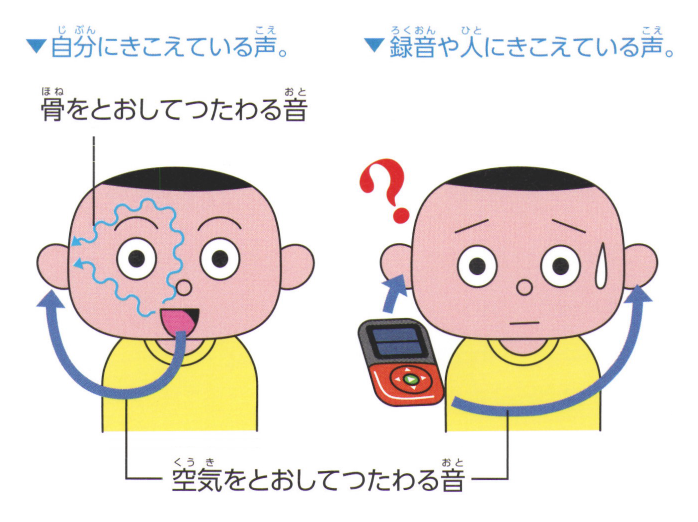
![]()
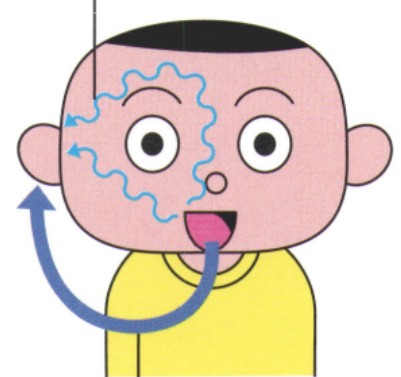
![]()
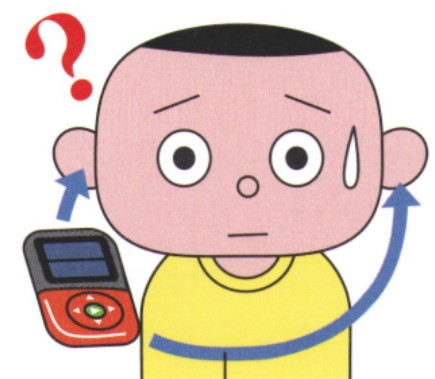
![]()
![]()
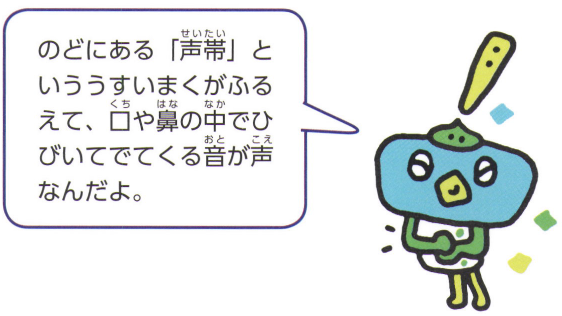
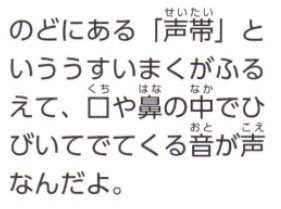
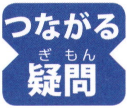
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
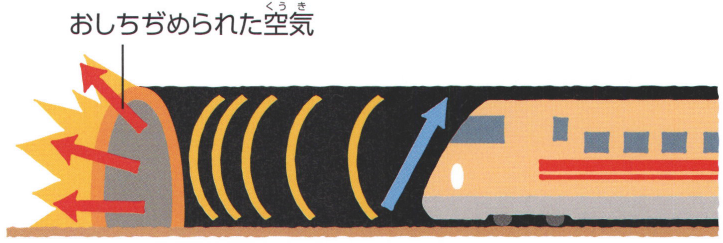
![]()
![]()

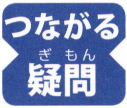
![]()
![]()
![]()

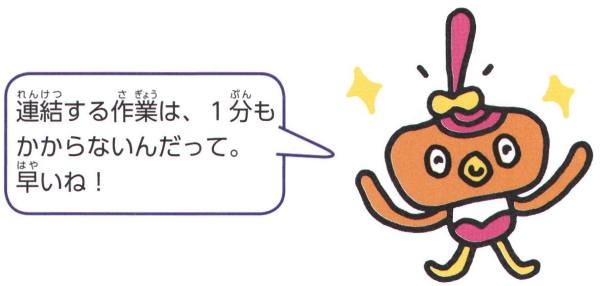
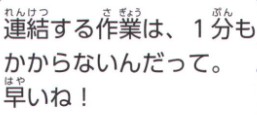
![]()
![]()
![]()
![]()
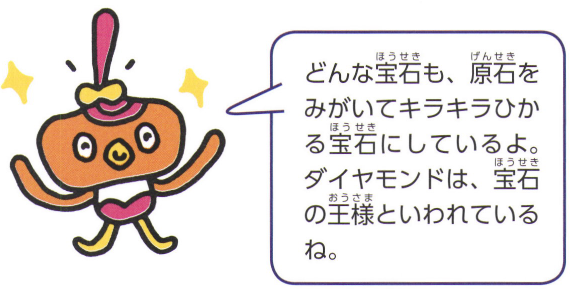
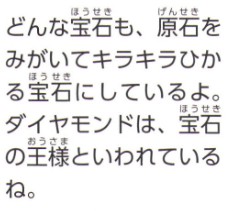
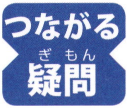
![]()
![]()
![]()
![]()


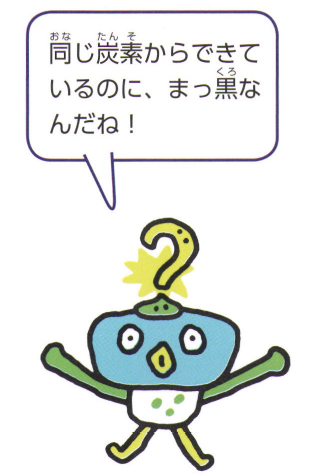
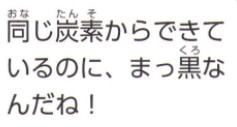
![]()
![]()
![]()
![]()
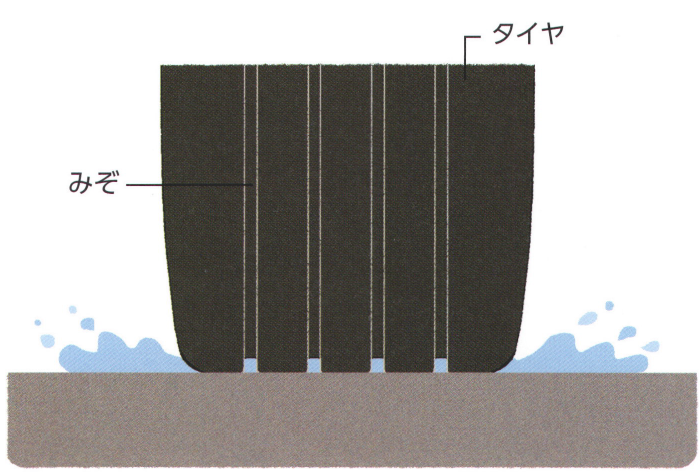
![]()
![]()
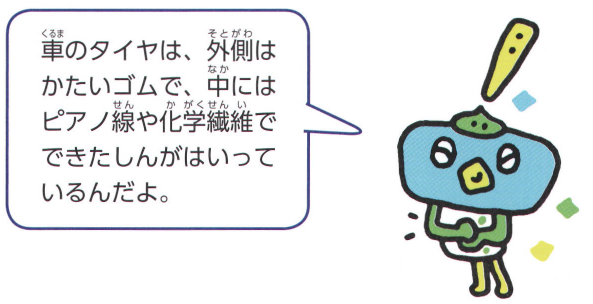
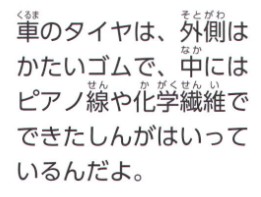
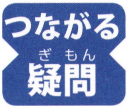
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
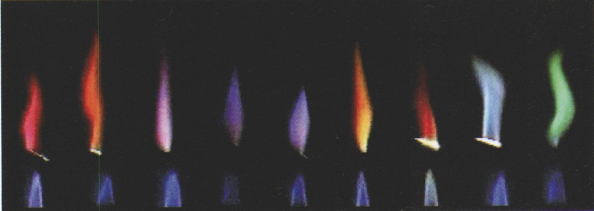
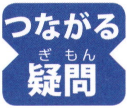
![]()
![]()

![]()
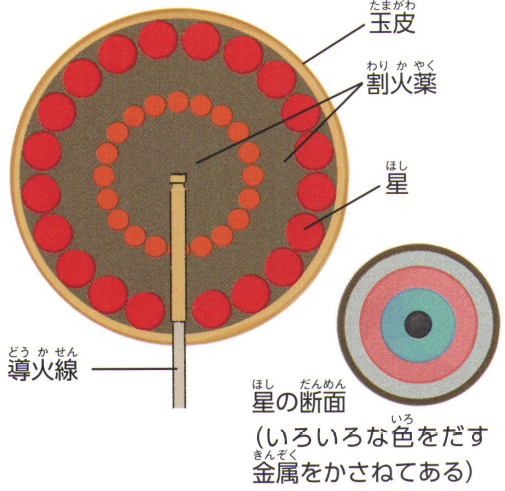
![]()
![]()
![]()
![]()
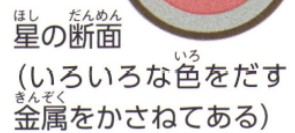
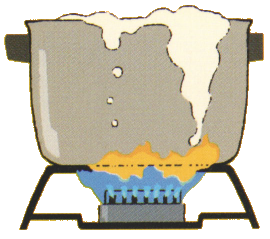
![]()
![]()
![]()
![]()

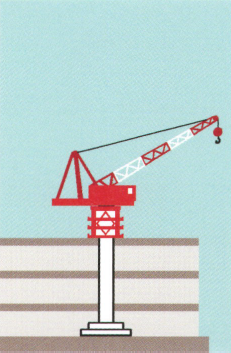
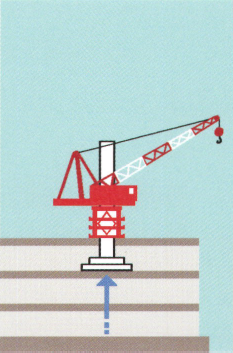
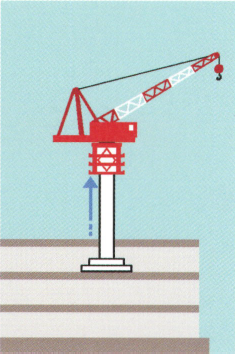
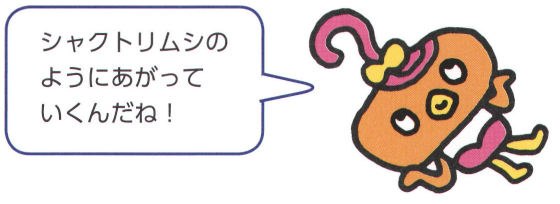
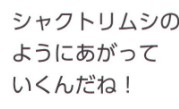
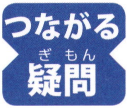
![]()
![]()
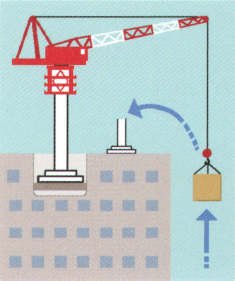
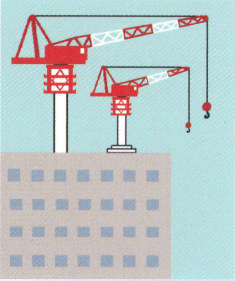
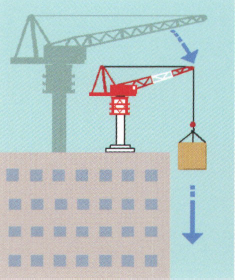
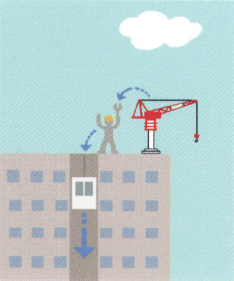
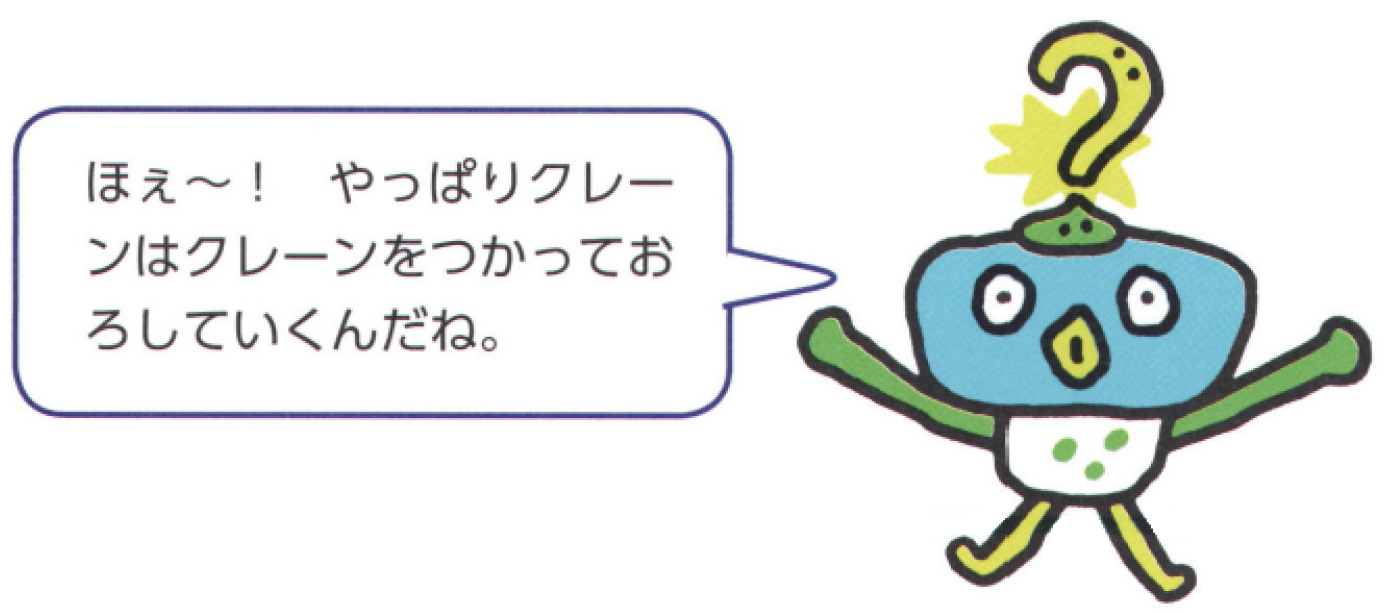
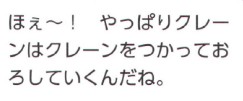
![]()
![]()
![]()
![]()
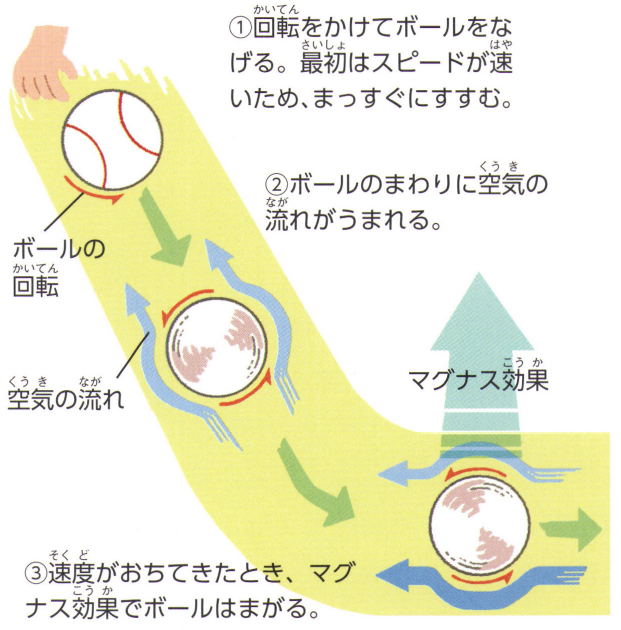
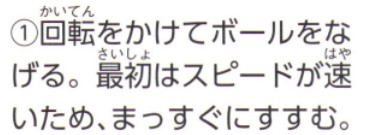
![]()
![]()
![]()
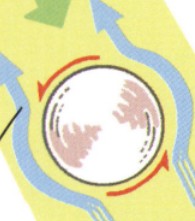
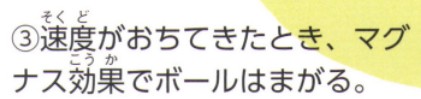
![]()
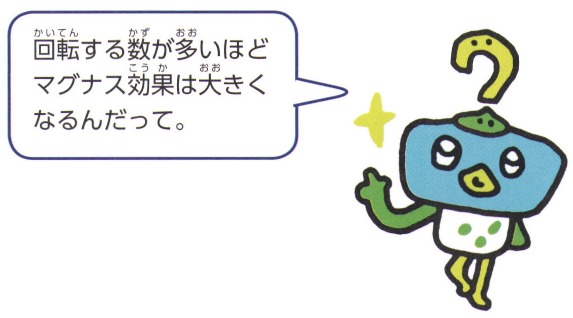
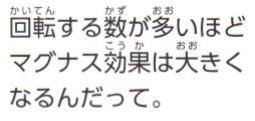
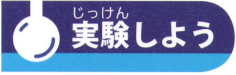
![]()
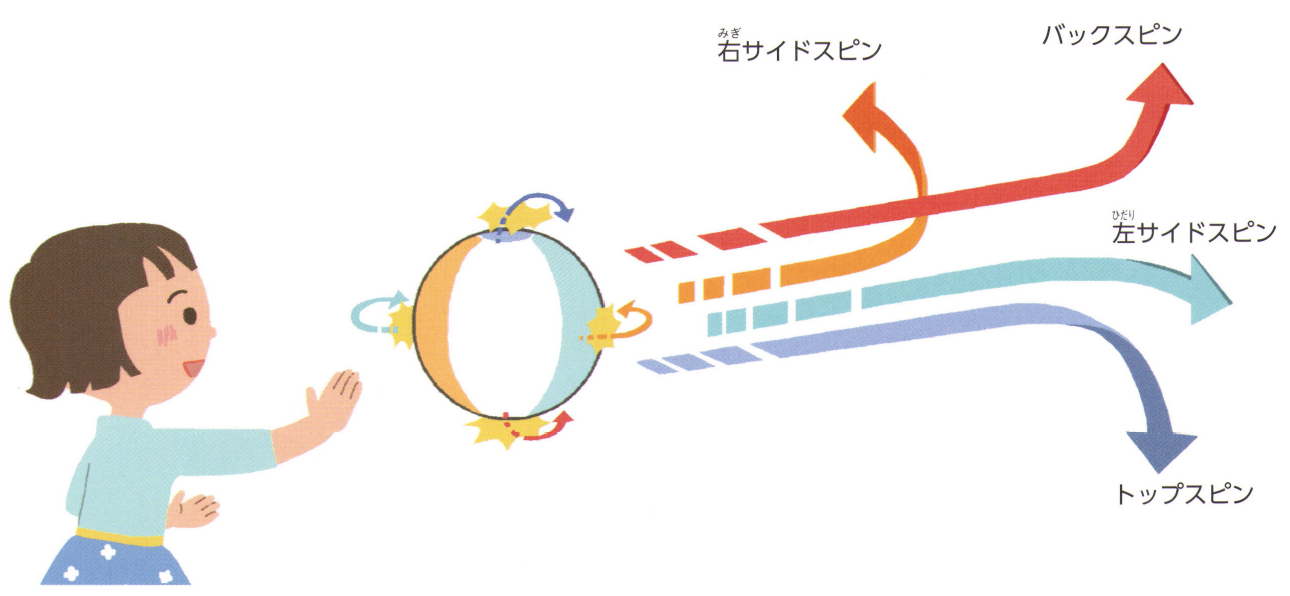
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()


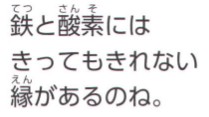
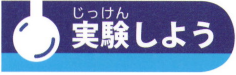
![]()
![]()

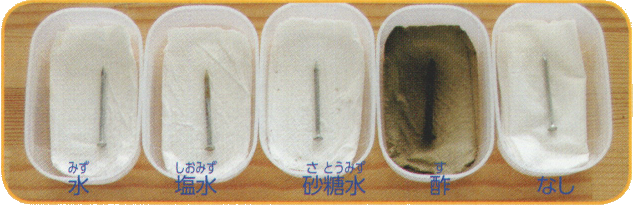
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
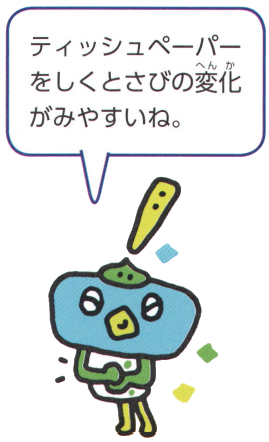
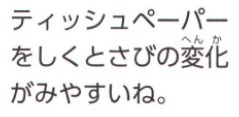
![]()
![]()
![]()
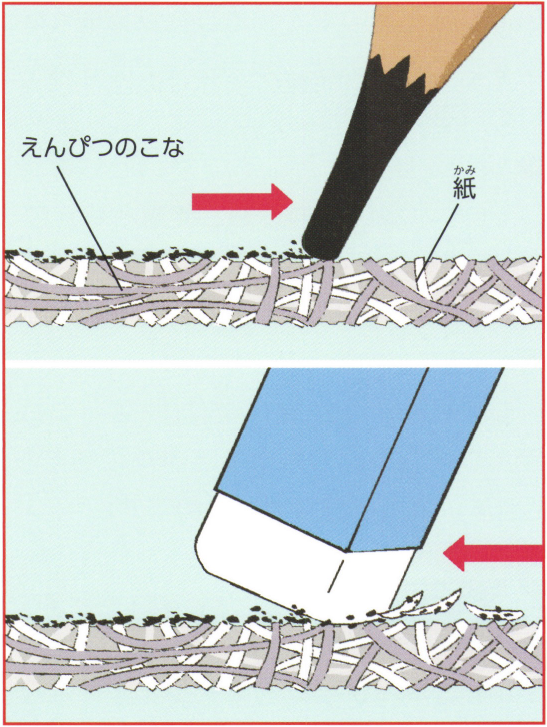
![]()
![]()

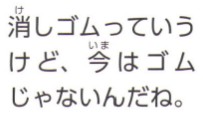
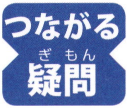
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
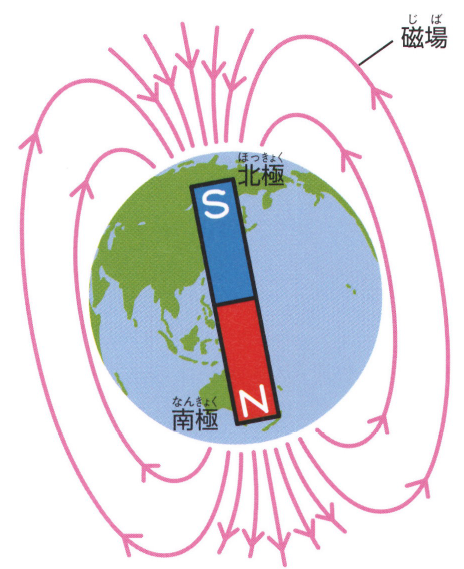
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
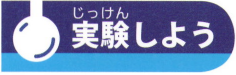
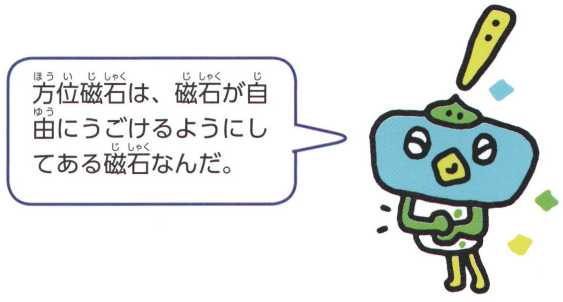
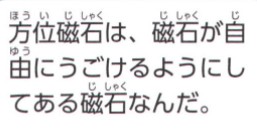
![]()
![]()
![]()
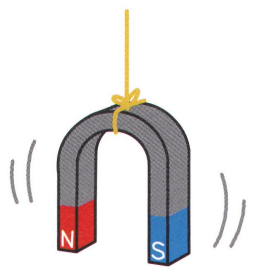
![]()
![]()
![]()
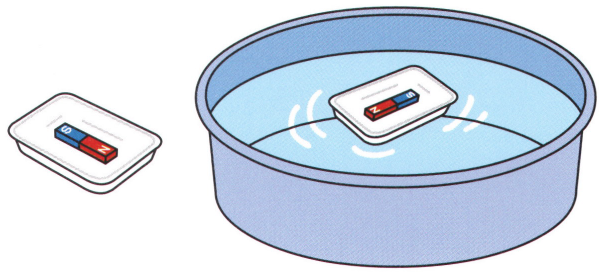
![]()
![]()
![]()
![]()
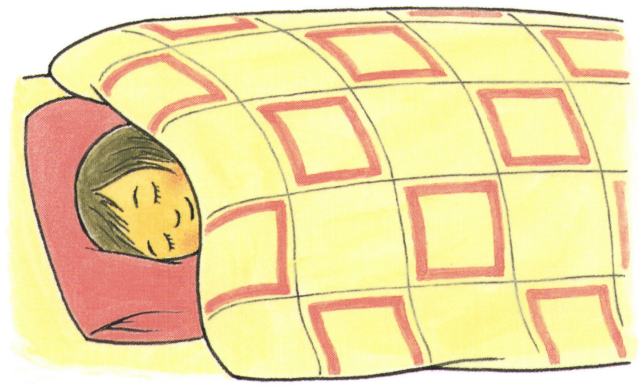
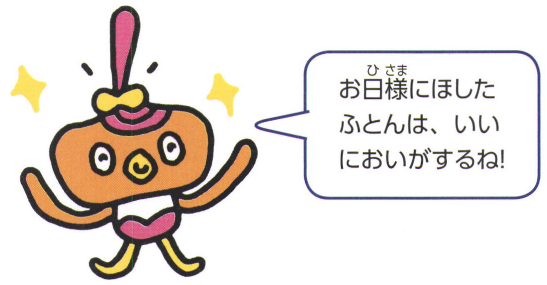
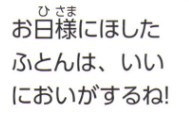
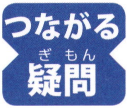
![]()
![]()
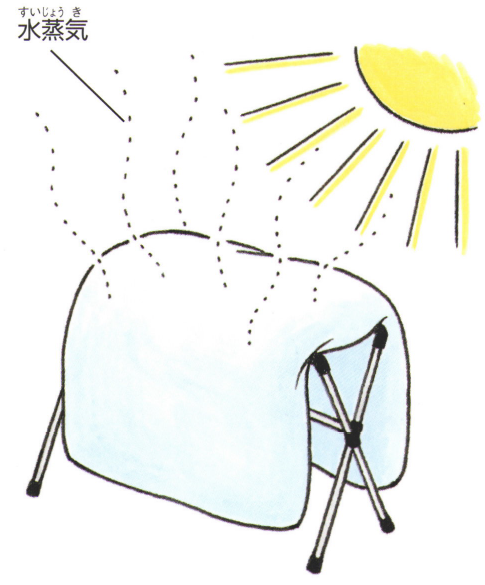
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
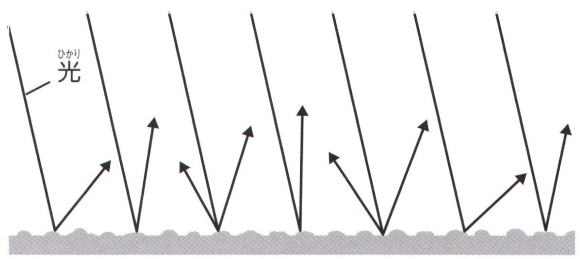
![]()
![]()
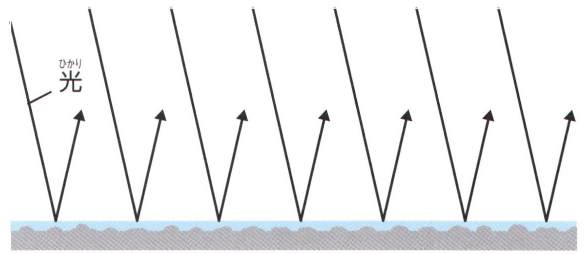
![]()
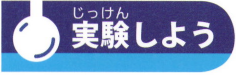
![]()
![]()

![]()
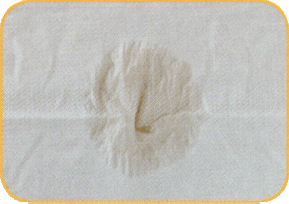
![]()

![]()
![]()
![]()
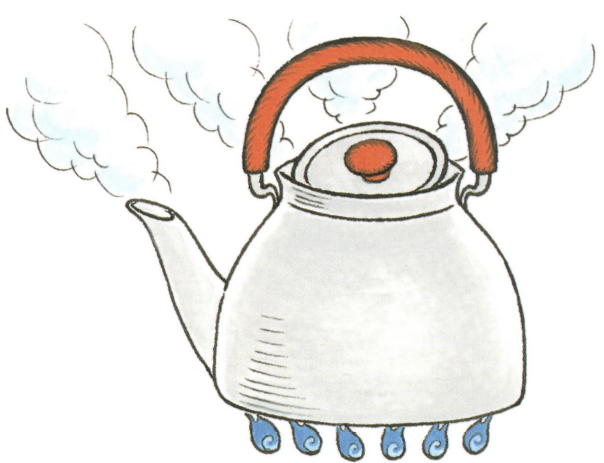

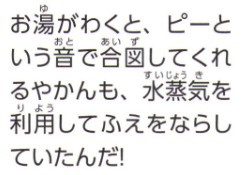
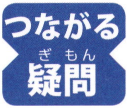
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

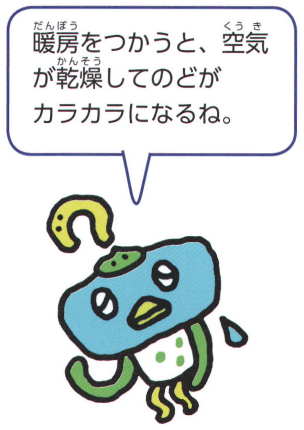
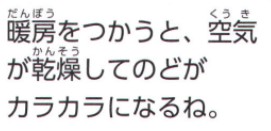
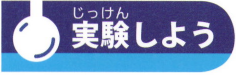
![]()
![]()

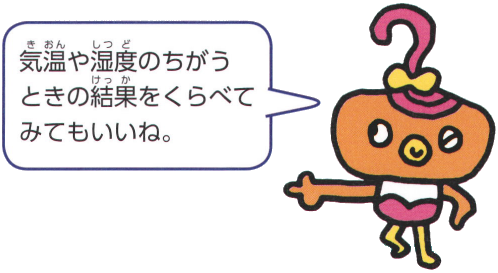
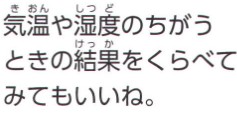
![]()
![]()
![]()
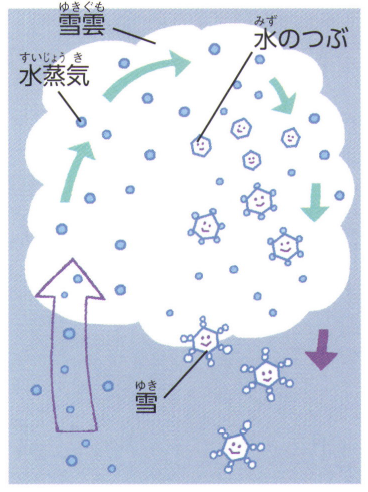
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
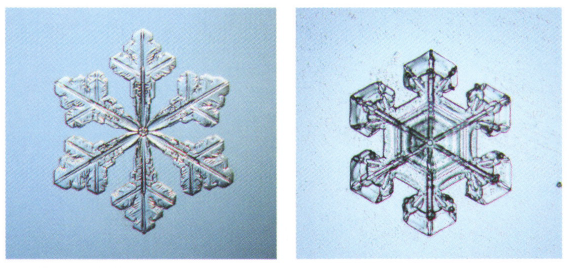
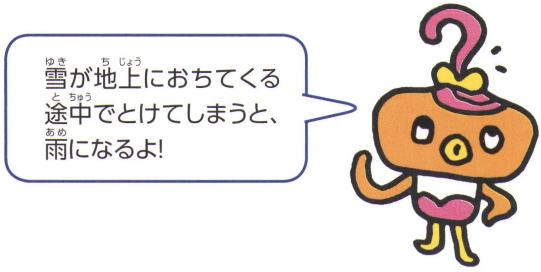
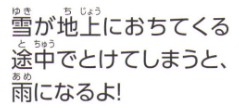
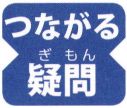
![]()
![]()
![]()
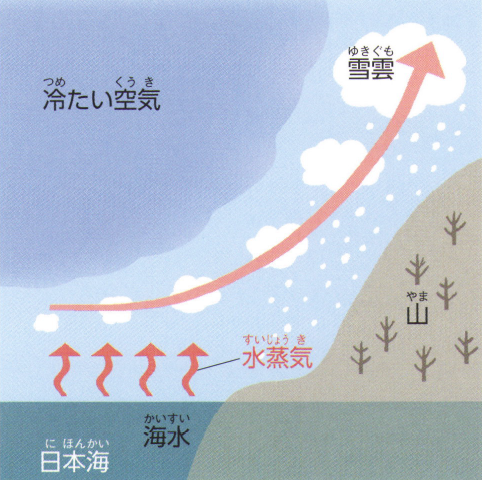
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
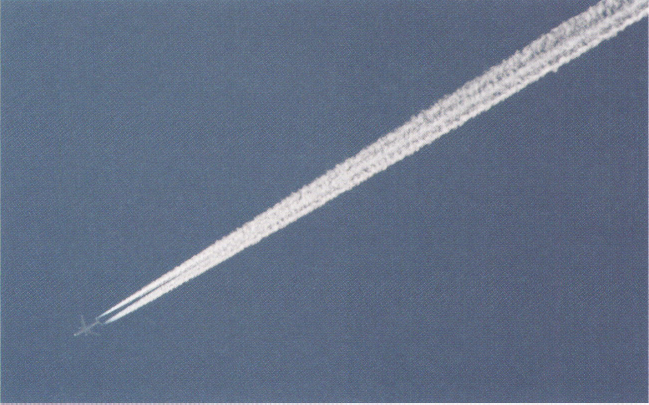
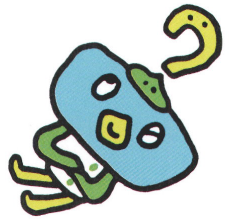
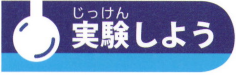

![]()
![]()

![]()
![]()
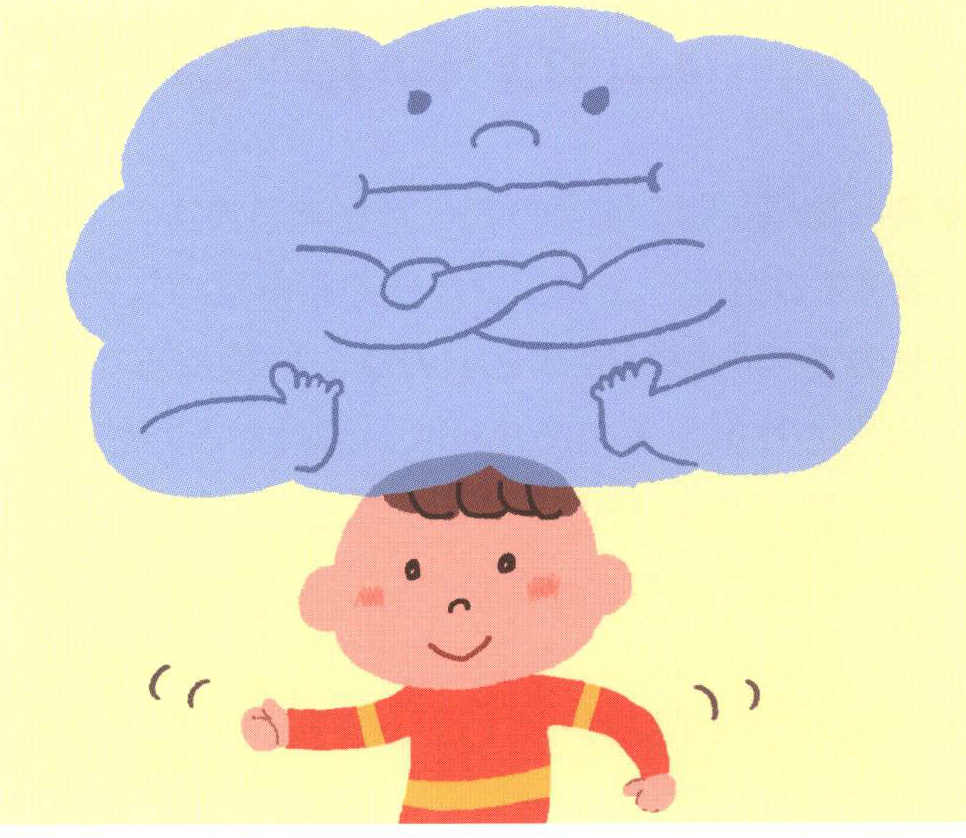
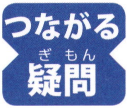
![]()
![]()
![]()
![]()
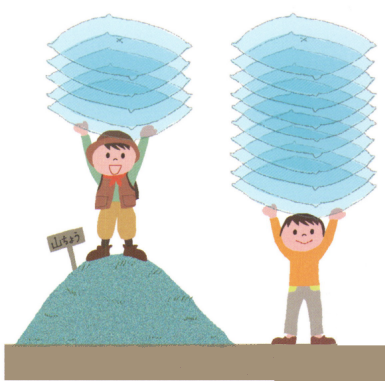
![]() パンパンに
パンパンに
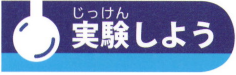
![]()
![]()
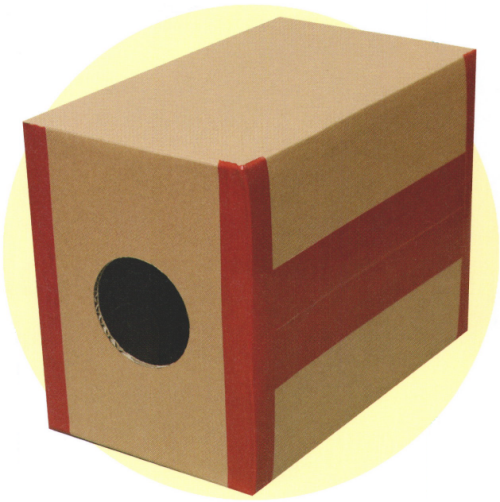
![]()


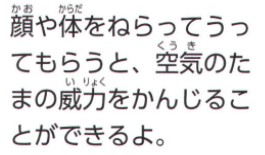

![]()
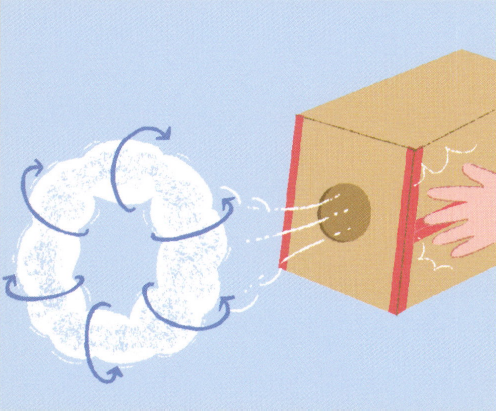
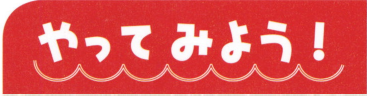
![]()
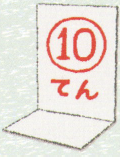
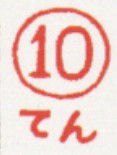
![]()
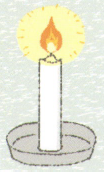
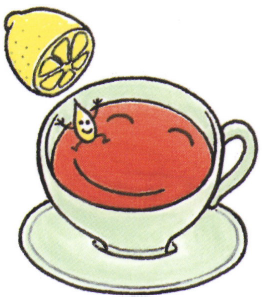
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()


![]()
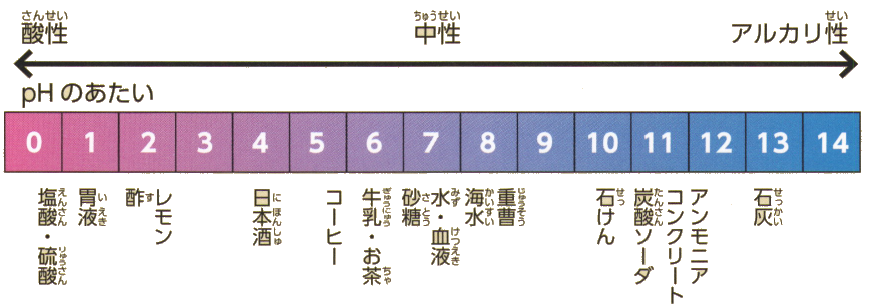
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
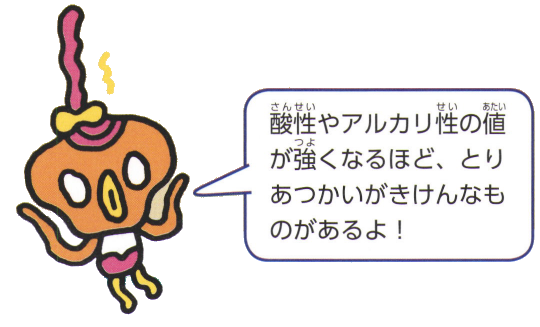
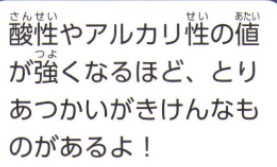
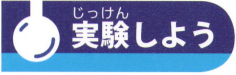
![]()
![]()
![]()
![]()
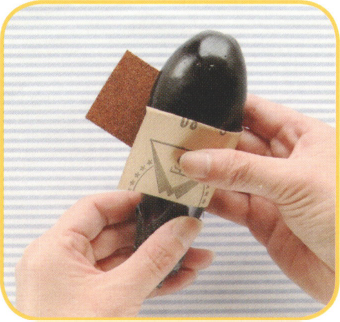

![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
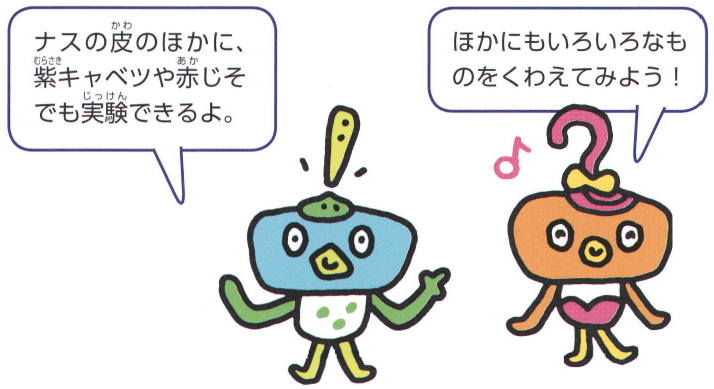
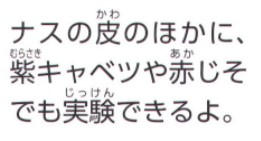
![]()

![]()
![]()
![]()


![]()
![]()
![]()

![]()

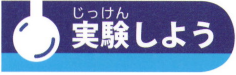
![]()
![]()
![]()
![]()
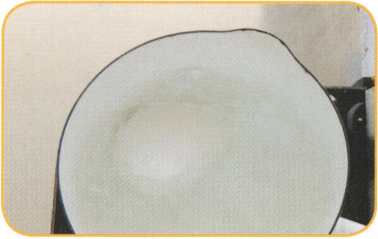
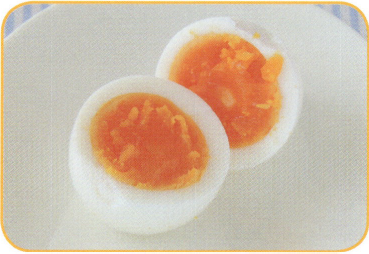
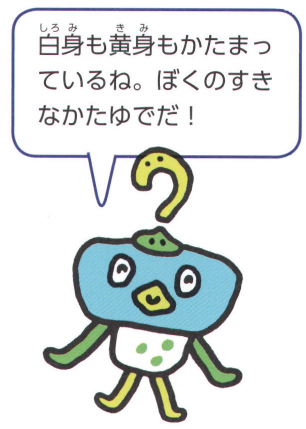
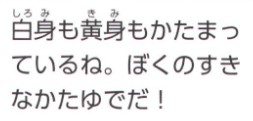
![]()
![]()
![]()
![]()

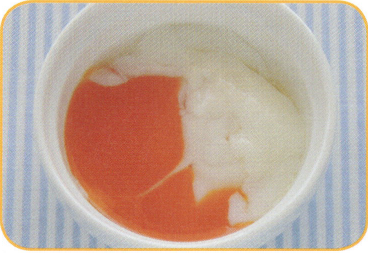

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
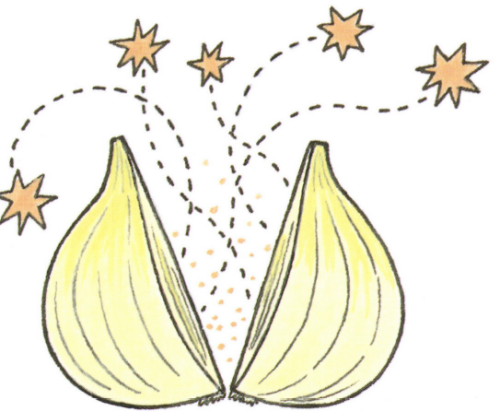
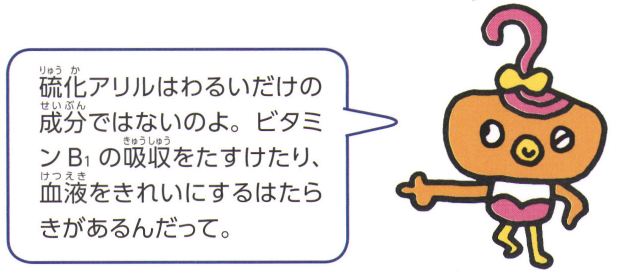
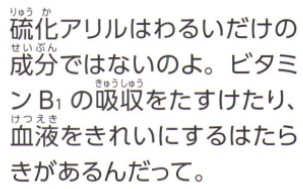
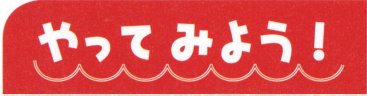
![]()
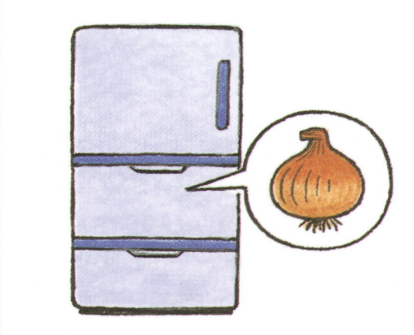
![]()
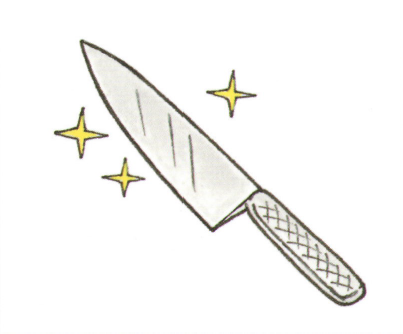
![]()
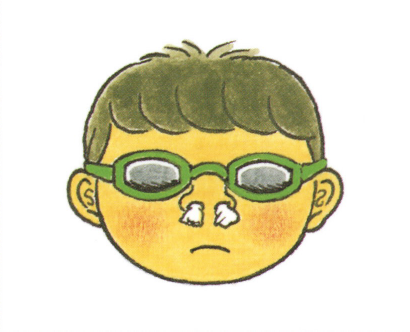
![]()
![]()
![]()
![]()
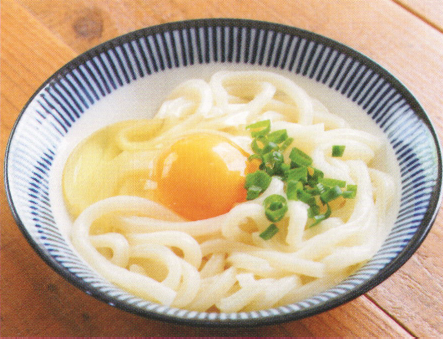
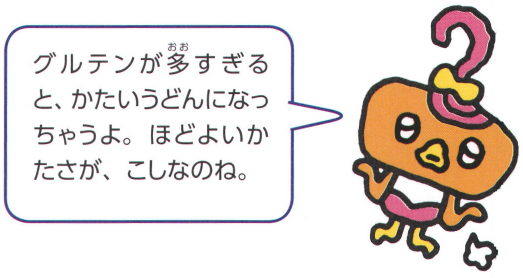
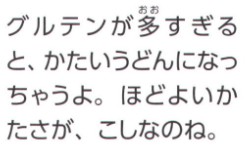

![]()

![]()
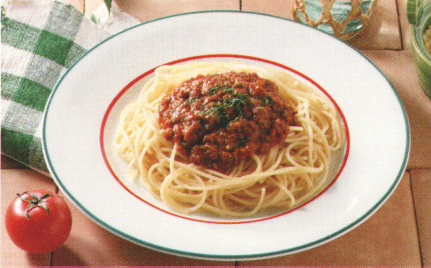
![]()

![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
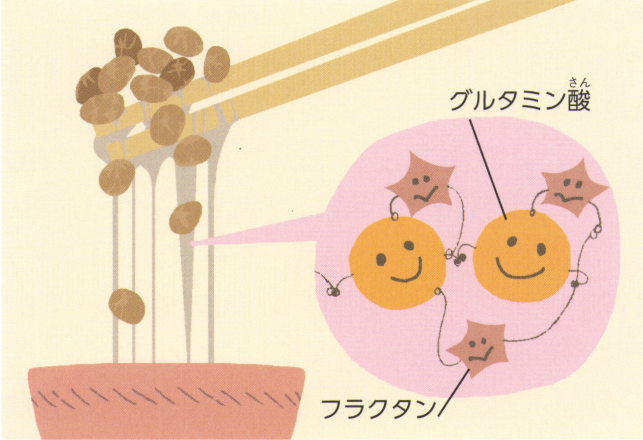
![]()
![]()
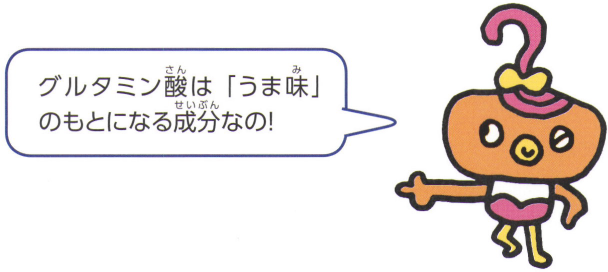
![]()
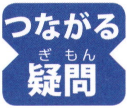
![]()
![]()
![]()
![]()

![]() くさる
くさる

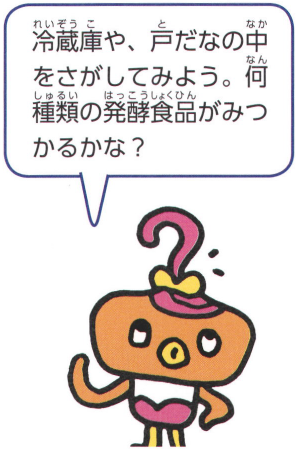
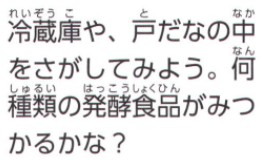
![]()
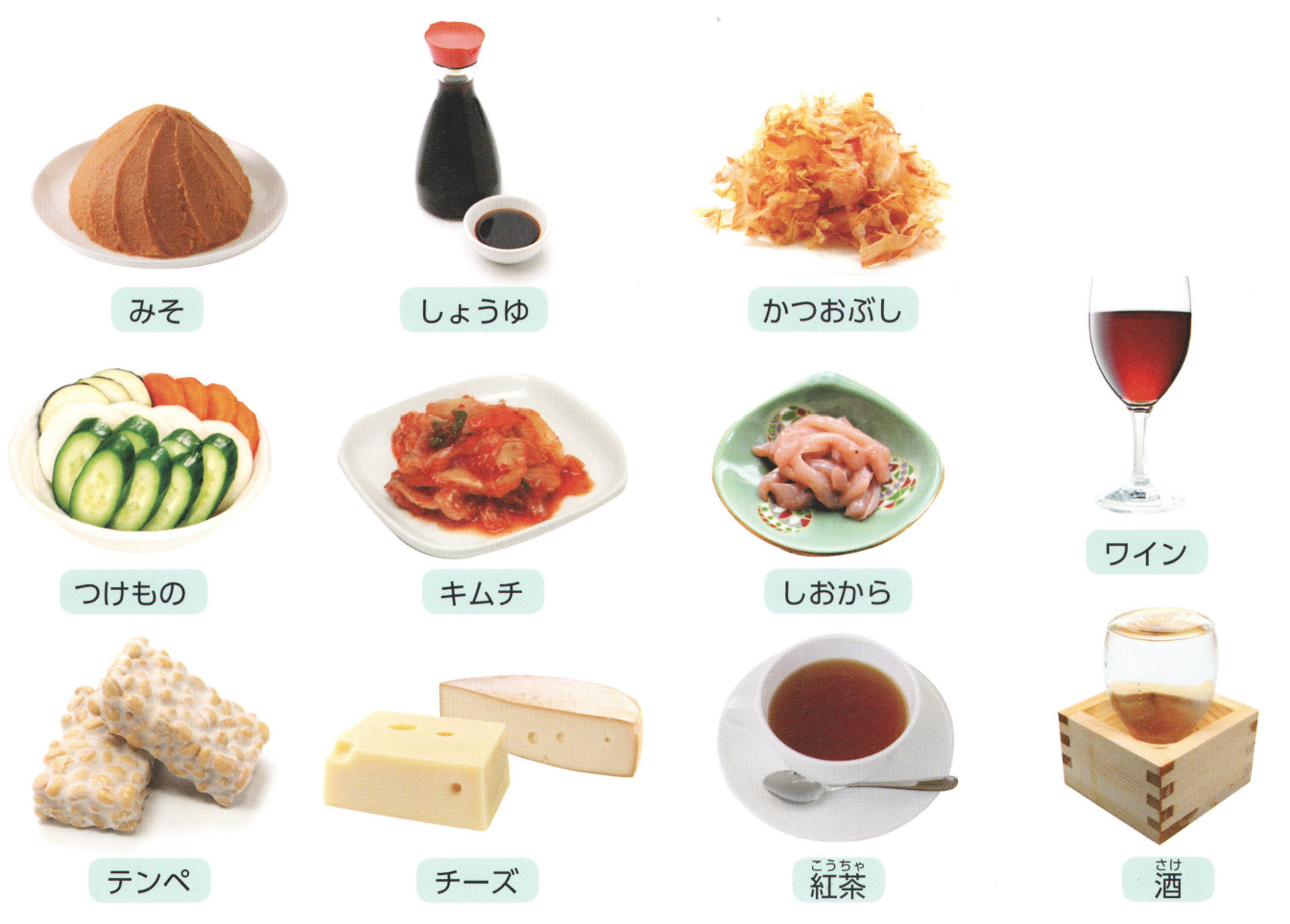
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
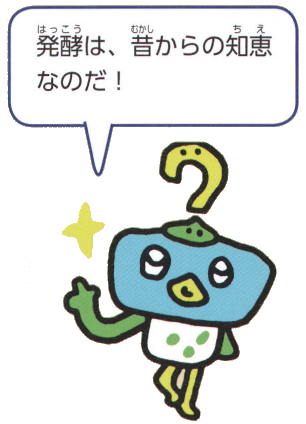
![]()
![]()
![]()
![]()
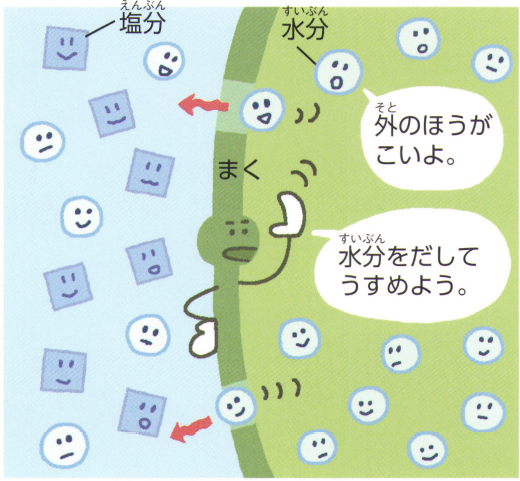
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
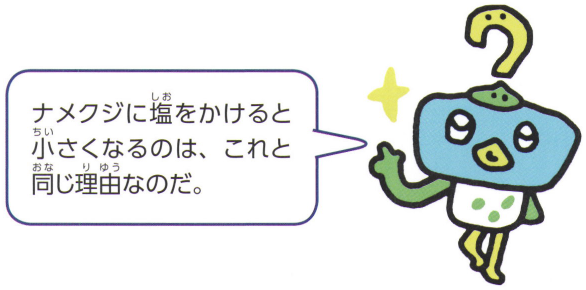
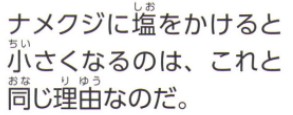
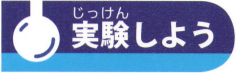
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
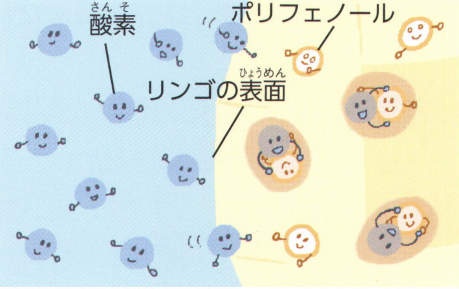
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
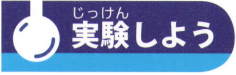
![]()
![]()
![]()
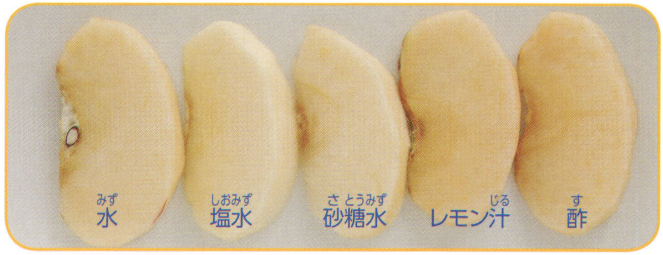
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
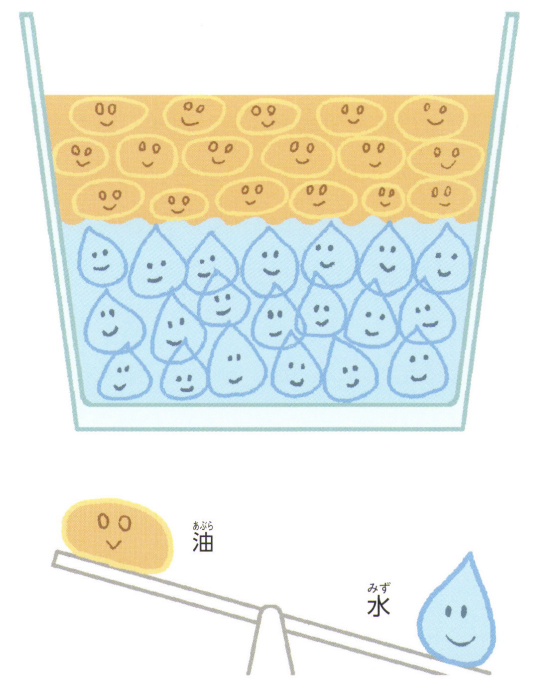
![]()
![]()
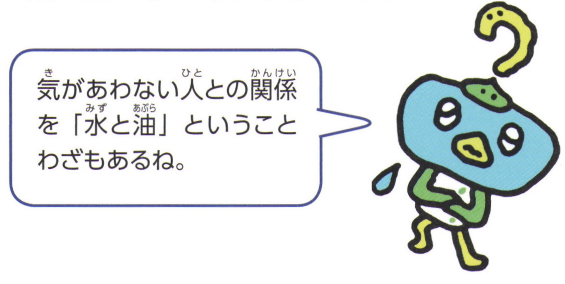
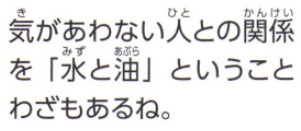

![]()
![]()
![]()

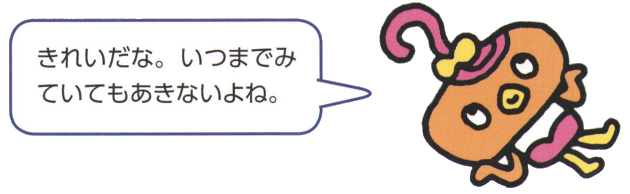
![]()
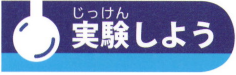
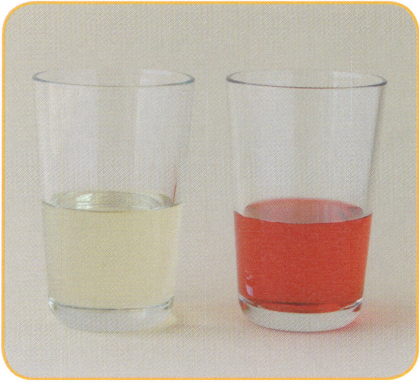
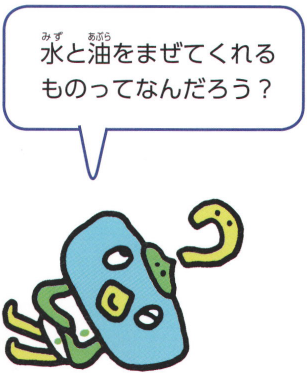
![]()
![]()
![]()
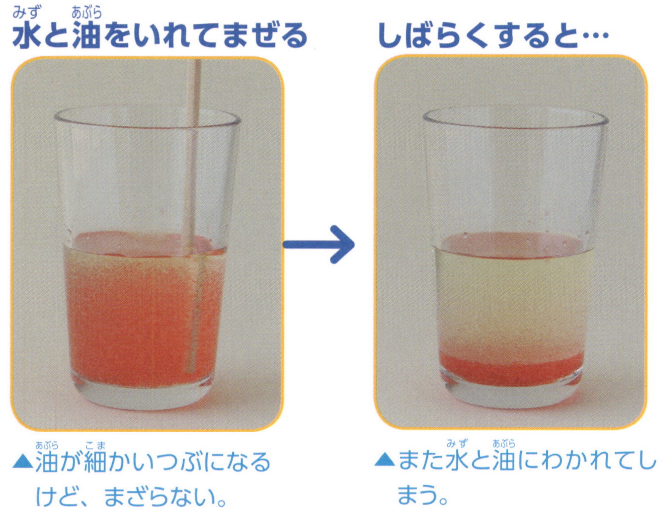
![]()
![]()
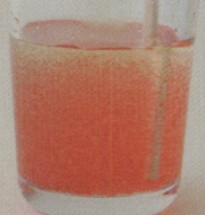
![]()
![]()
![]()
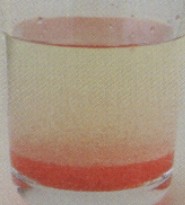
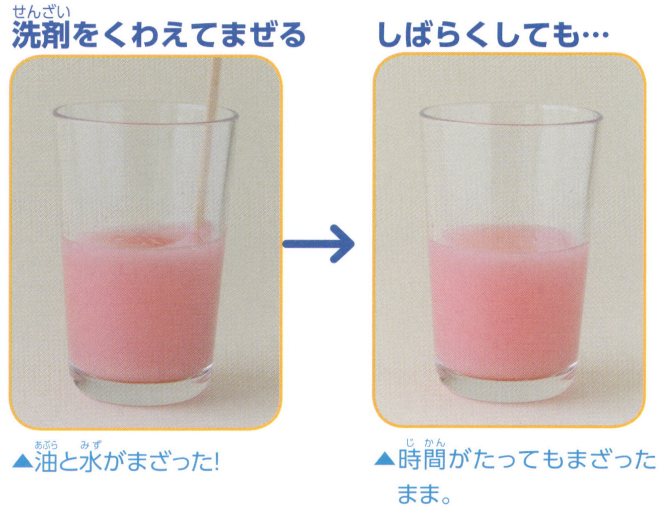
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()


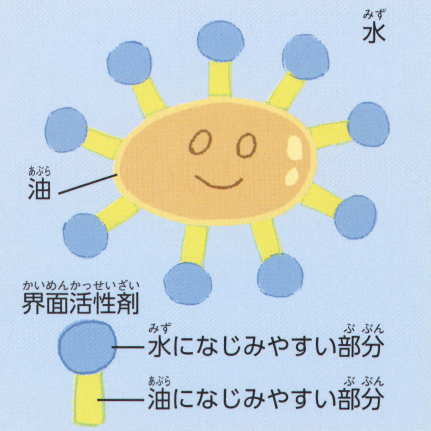
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

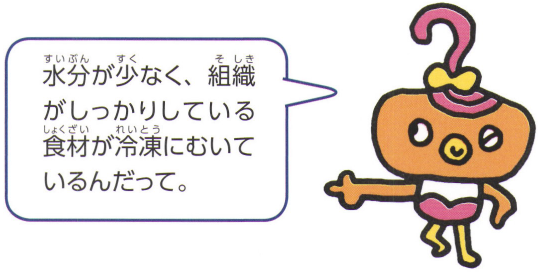
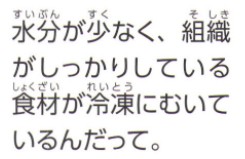
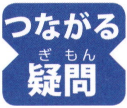
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
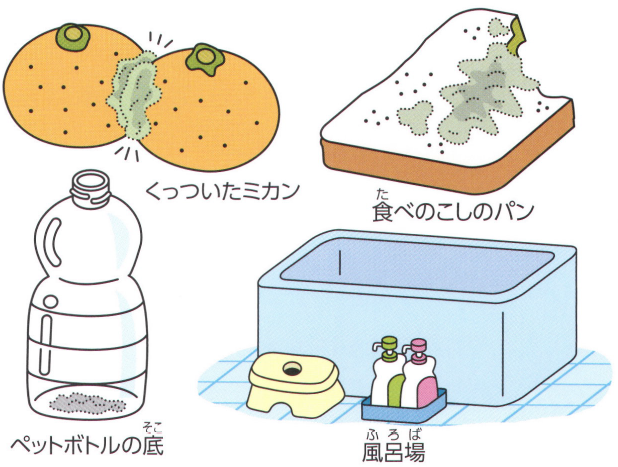
![]()
![]()
![]()
![]()
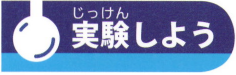
![]()
![]()
![]()
![]()
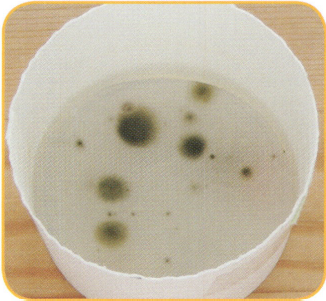

![]()
![]()
![]()
![]()
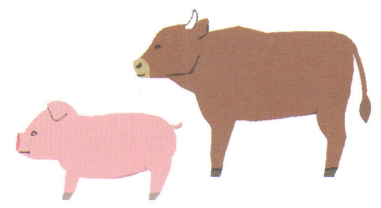
![]()
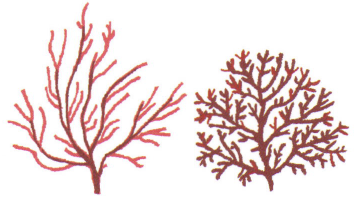
![]()
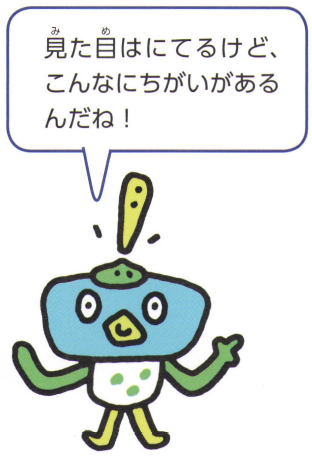
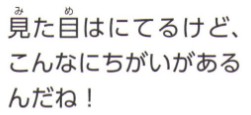

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
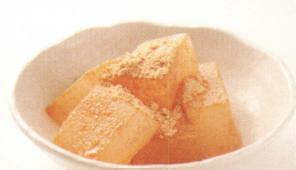
![]()
![]()

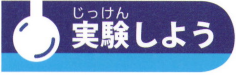
![]()
![]()
![]()

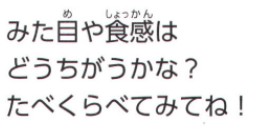
![]()
![]()
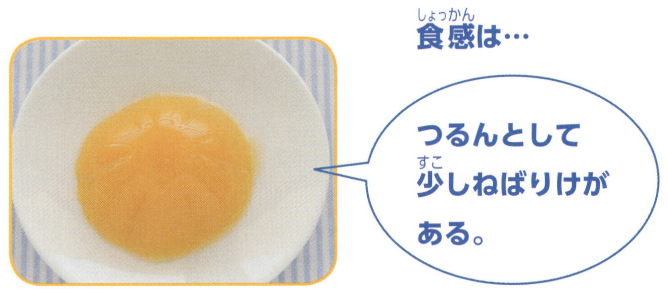
![]()
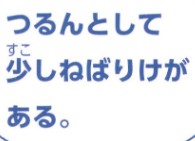
![]()
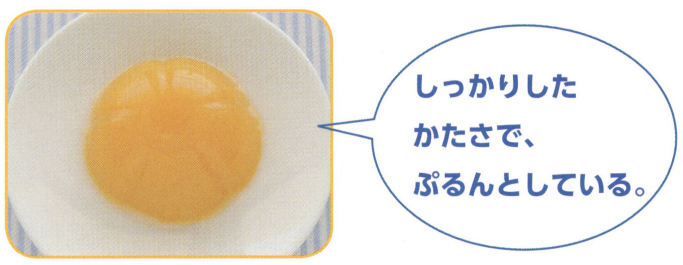
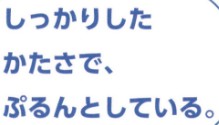
![]()
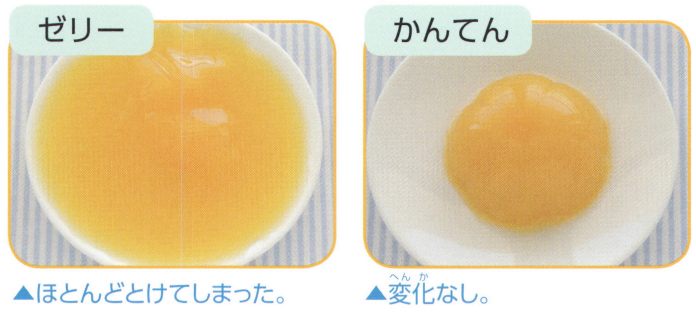
![]()
![]()
![]()
![]()
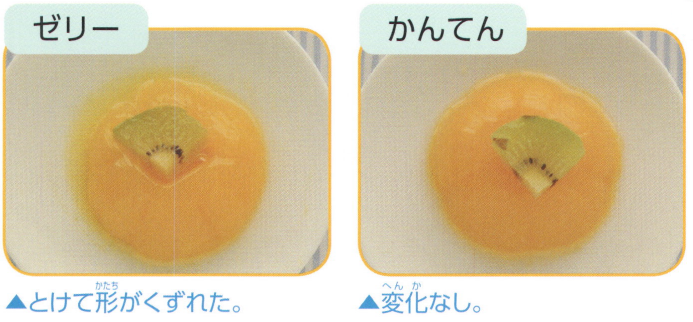
![]()
![]()
![]()
![]()

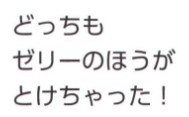

![]()
![]()
![]()
![]()
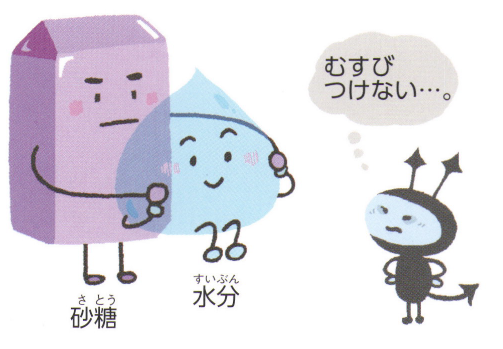
![]()
![]()
![]()
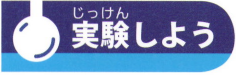
![]()
![]()
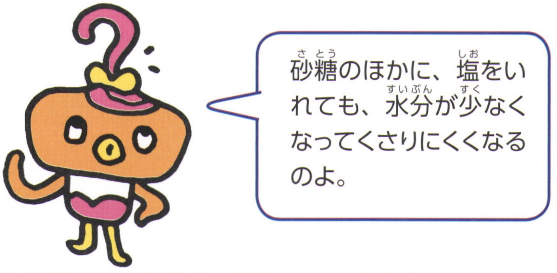
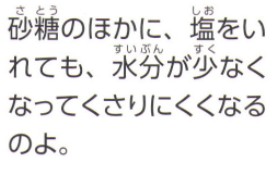

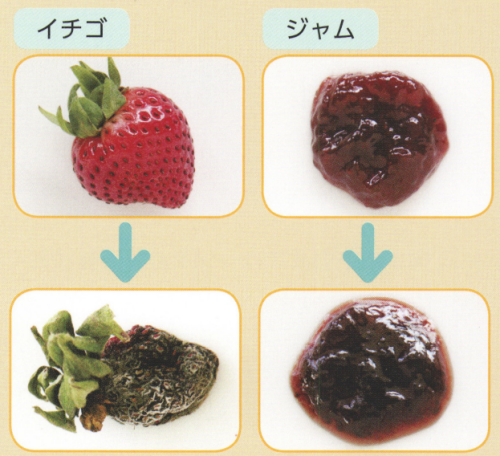
![]()
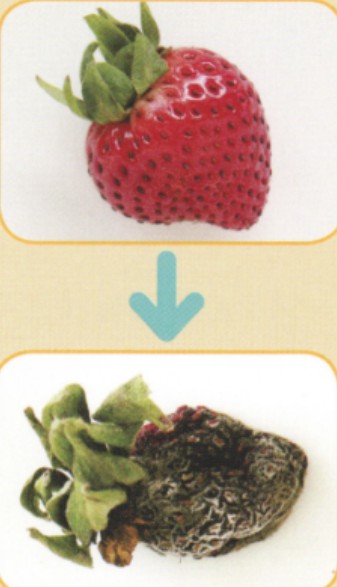
![]()
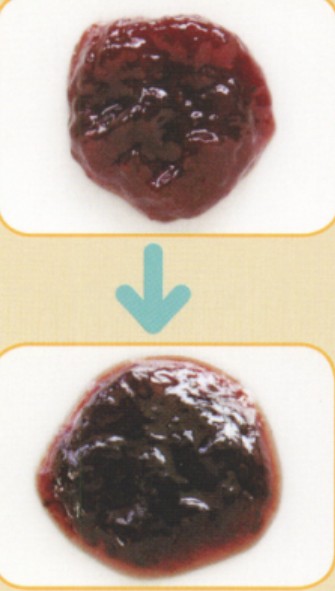
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


![]()

![]()
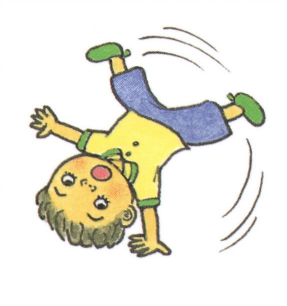
![]()

![]()
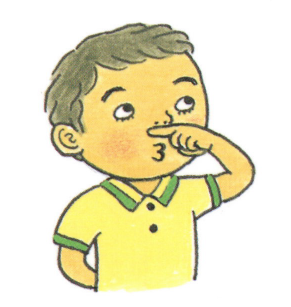
![]()
![]()
![]()
![]()
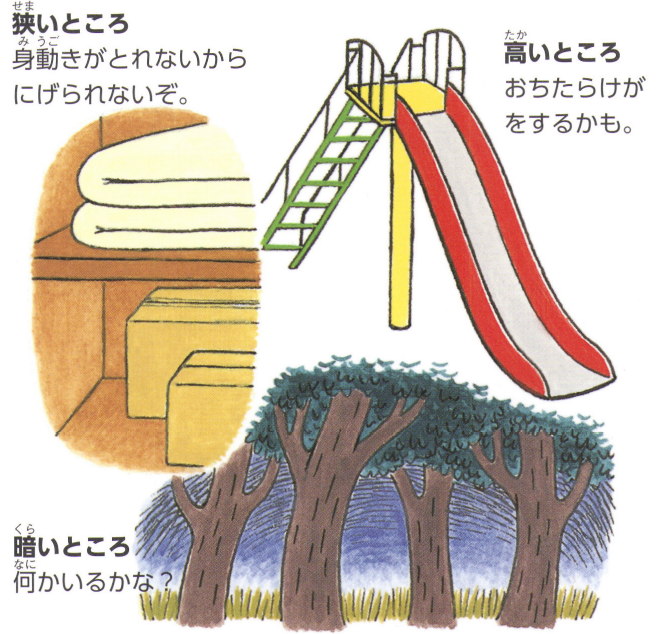
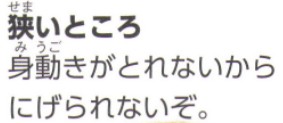
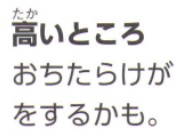
![]()
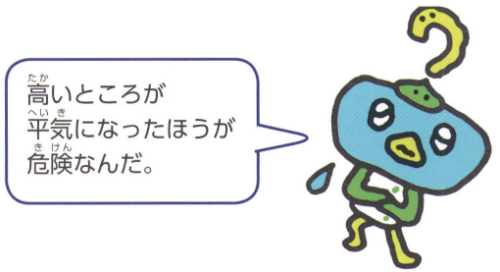
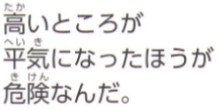
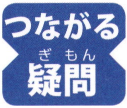
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
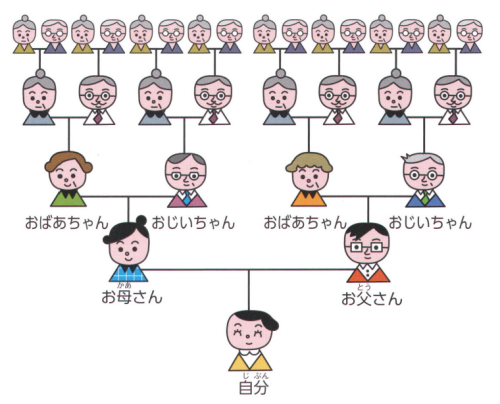
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
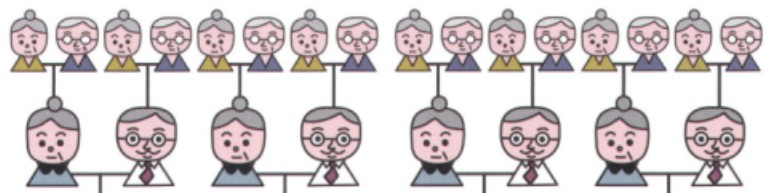
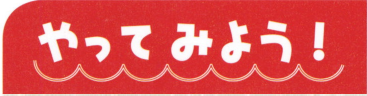
![]()
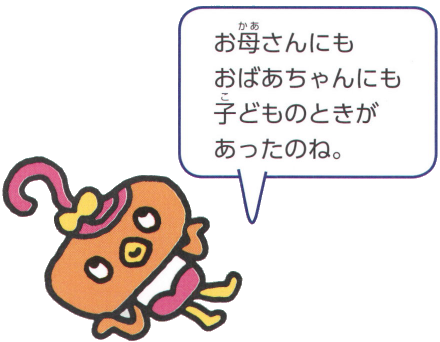
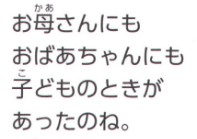
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
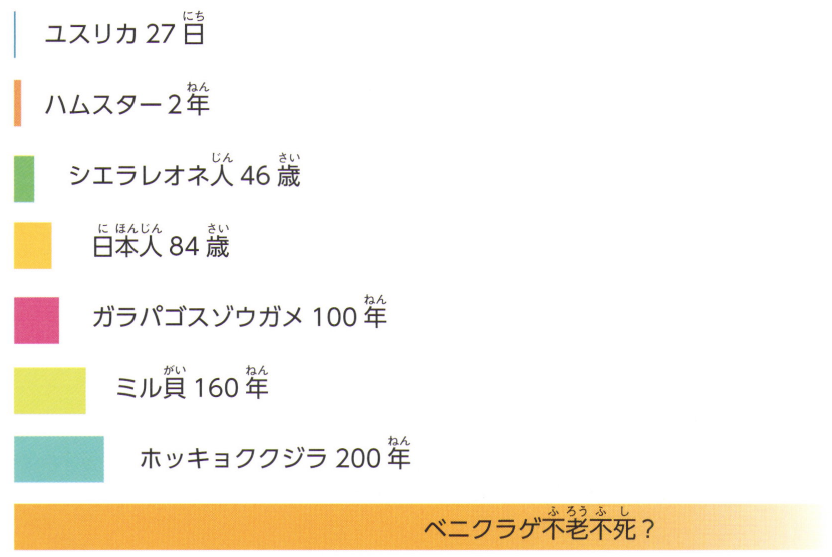
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

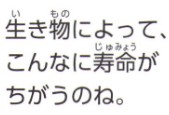
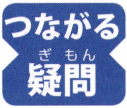
![]()
![]()
![]()
![]()
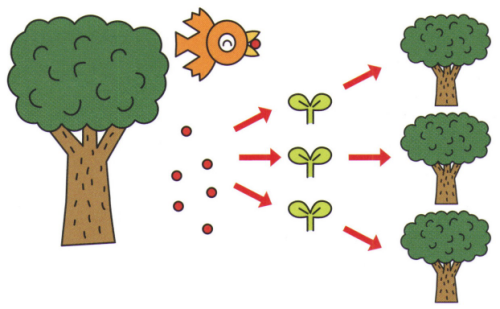
![]()
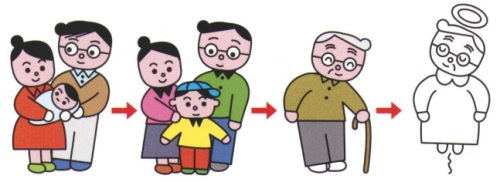
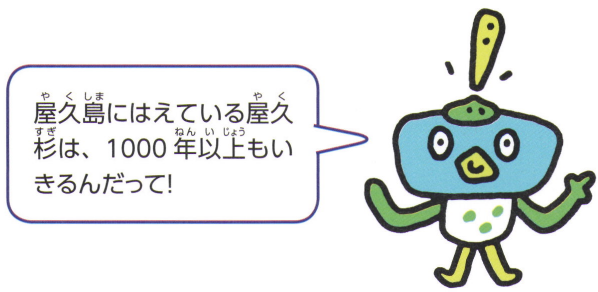
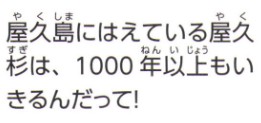
![]()
![]()
![]()
![]()
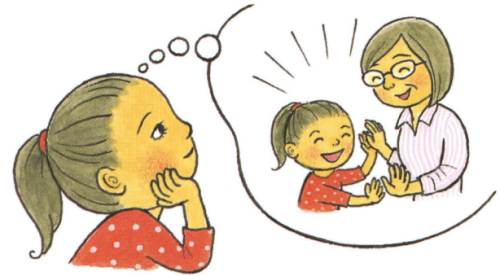
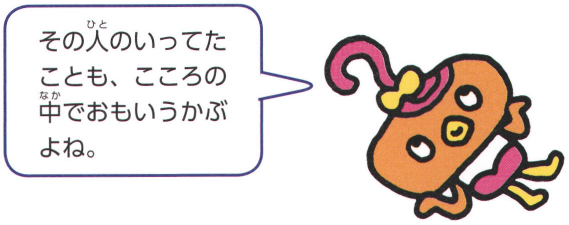
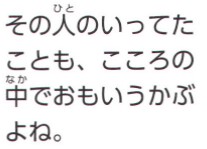
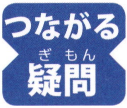
![]()
![]()
![]()
![]()
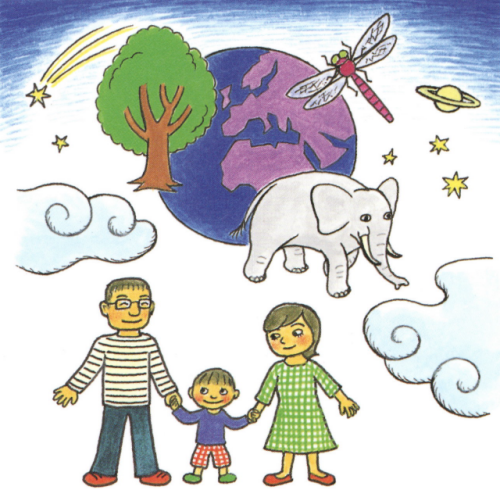
![]()
![]()
![]()
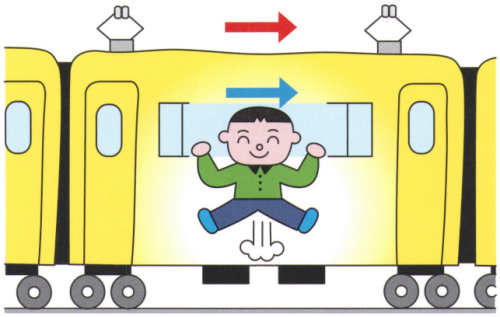
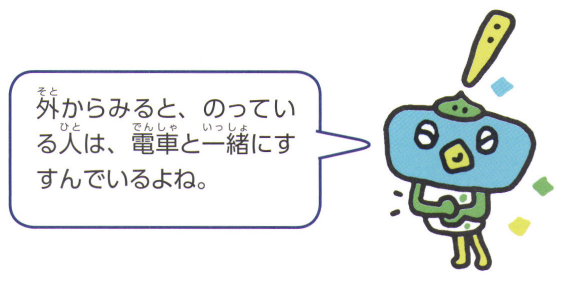
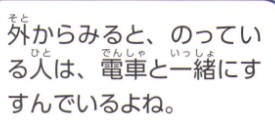
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
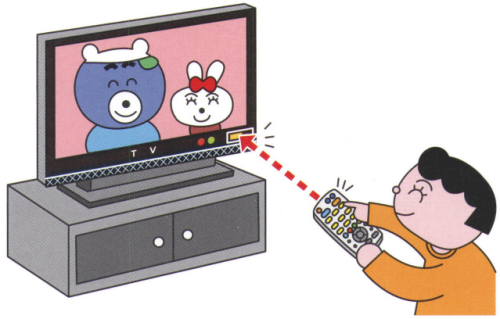
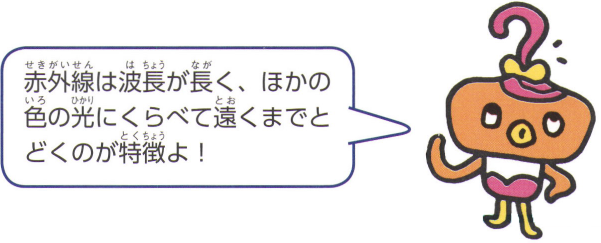
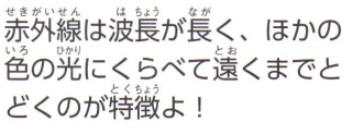
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
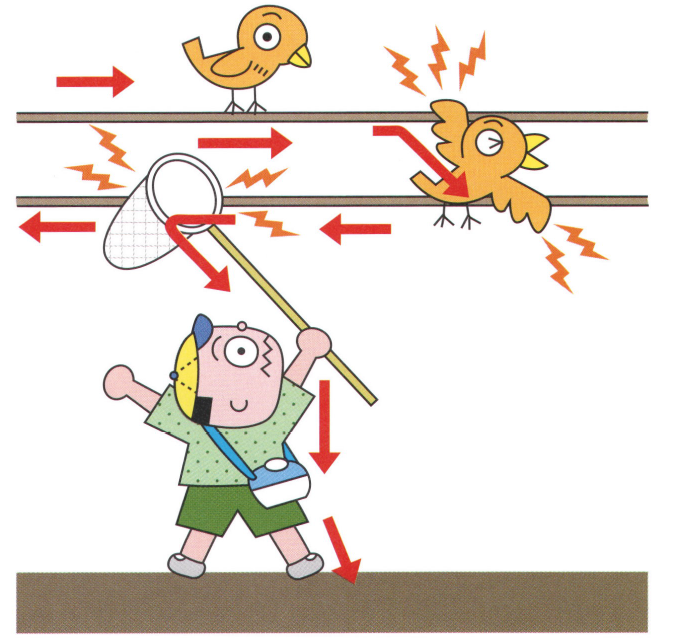
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
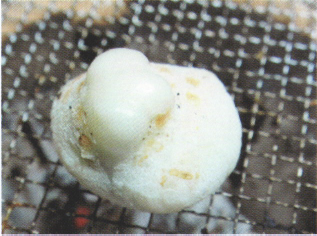
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
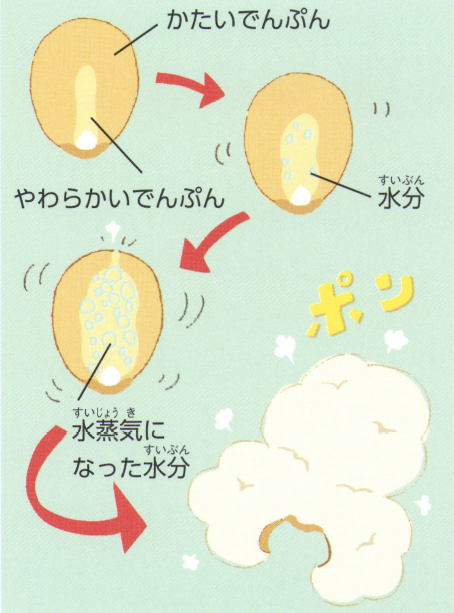
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
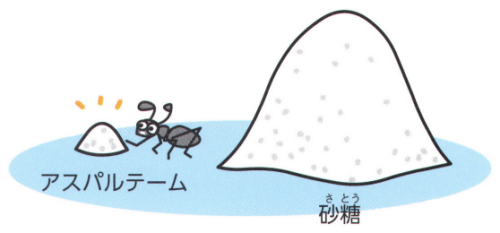
![]()
![]()
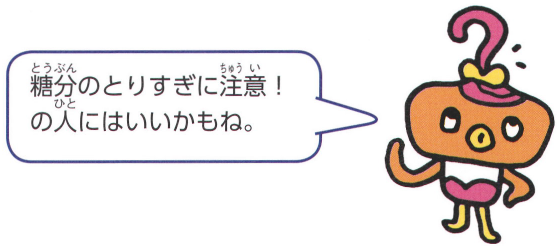
![]()
![]()
![]()
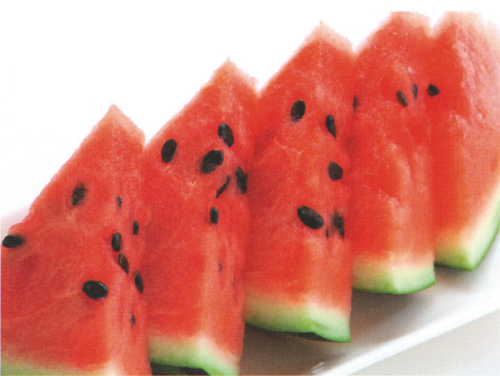
![]()
![]()
![]()
![]()
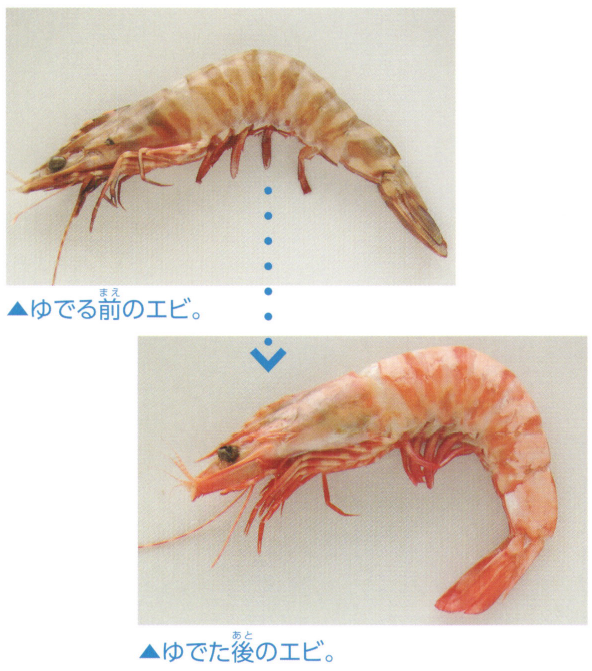
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
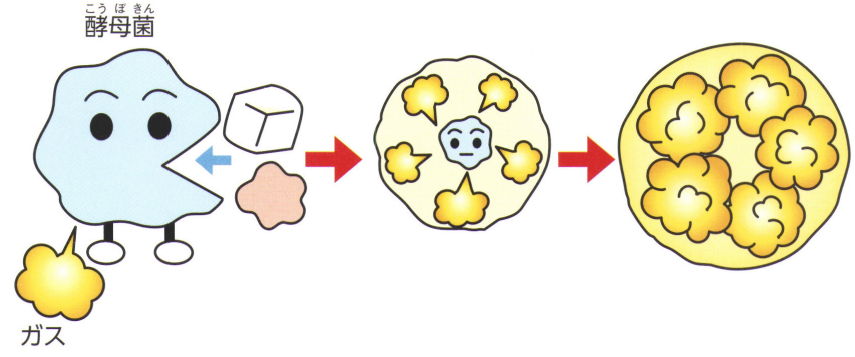
![]()
![]()
![]()
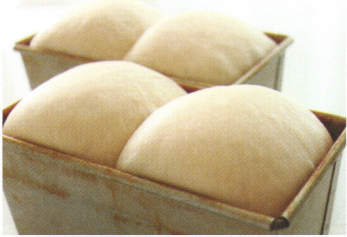
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
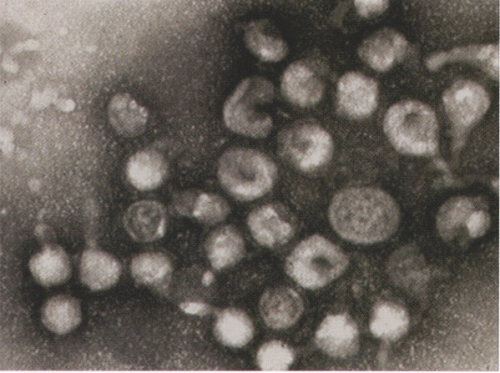
![]()
![]()
![]()
![]()
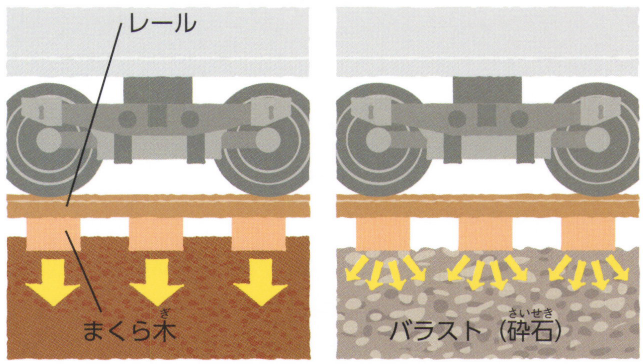
![]()
![]()
![]()
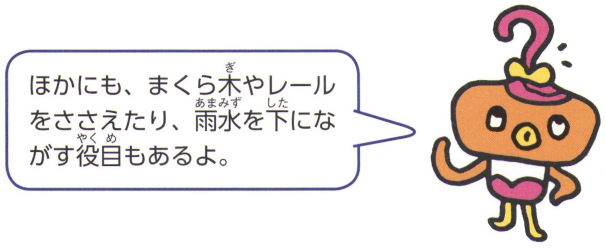
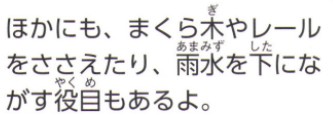
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

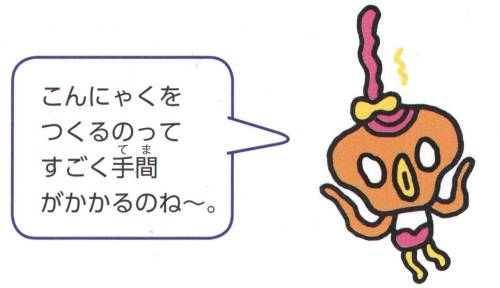
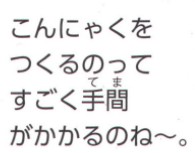
![]()
![]()
![]()
![]()



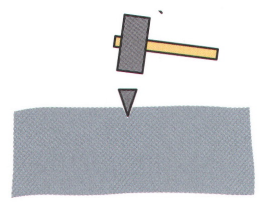
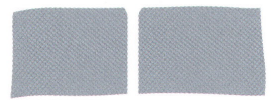
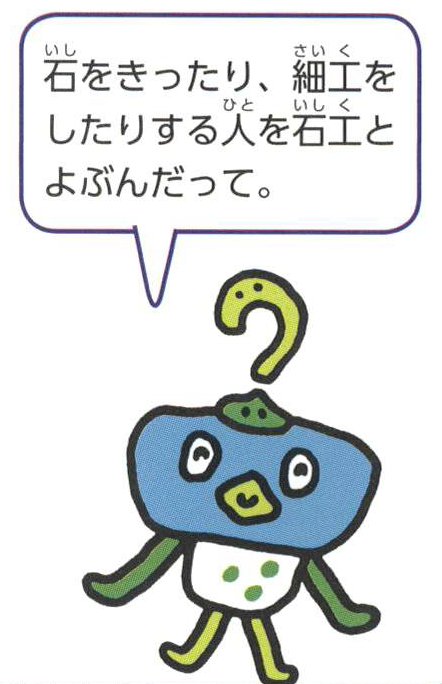
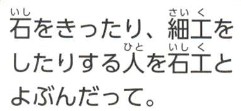
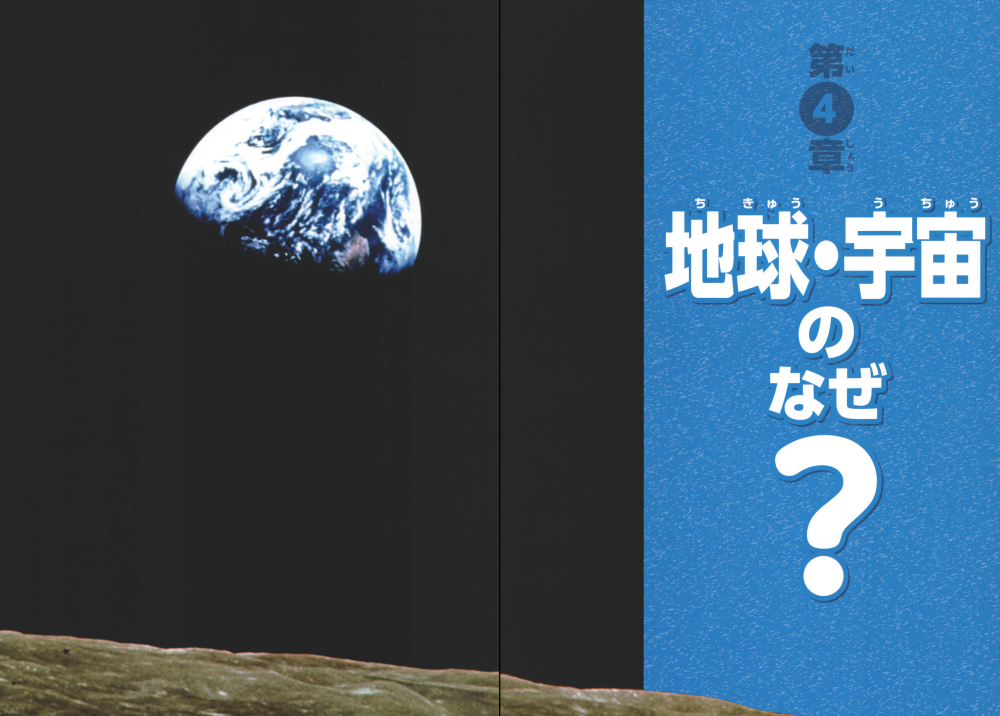
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
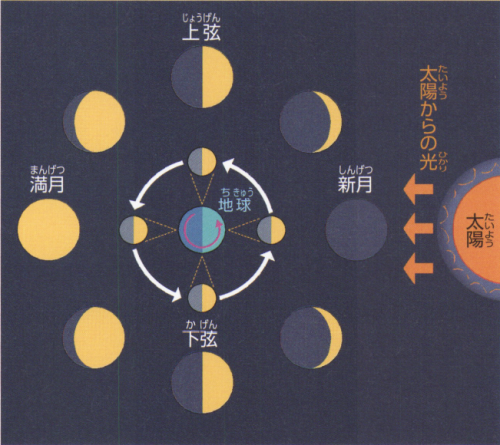
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






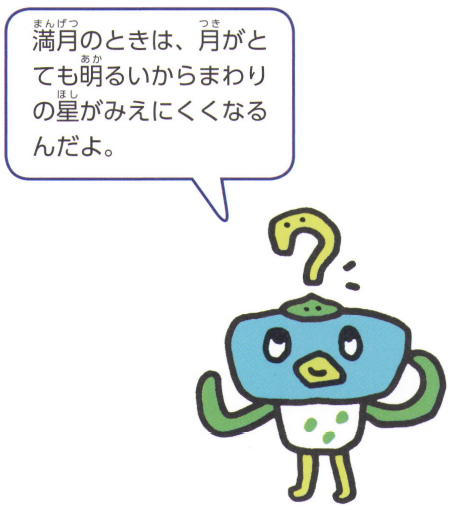
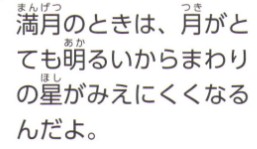
![]()

![]()
![]()
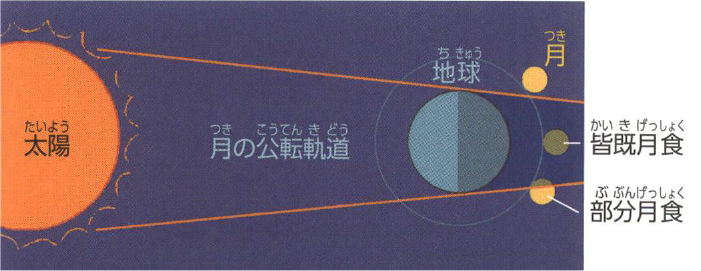
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
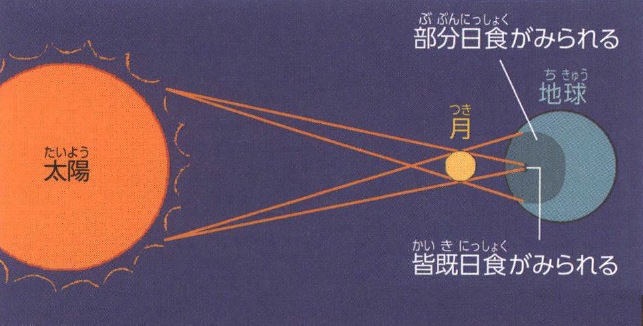
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

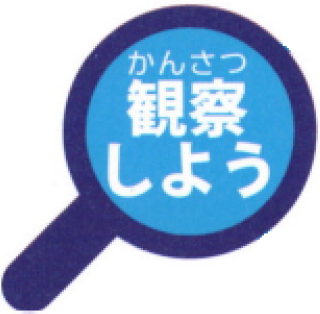
![]()
![]()
![]()
![]()
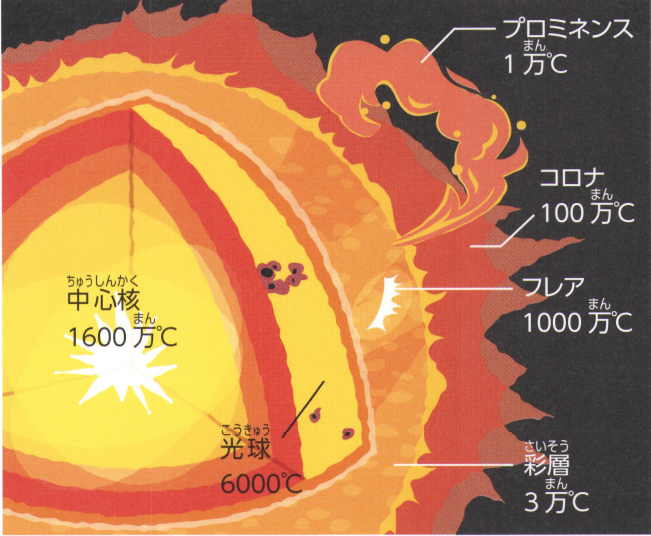
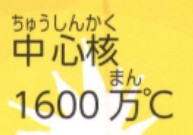
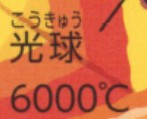
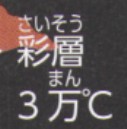
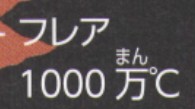
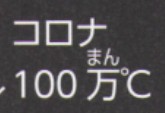
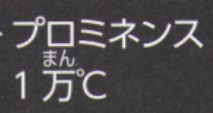
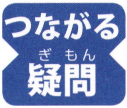
![]()
![]()
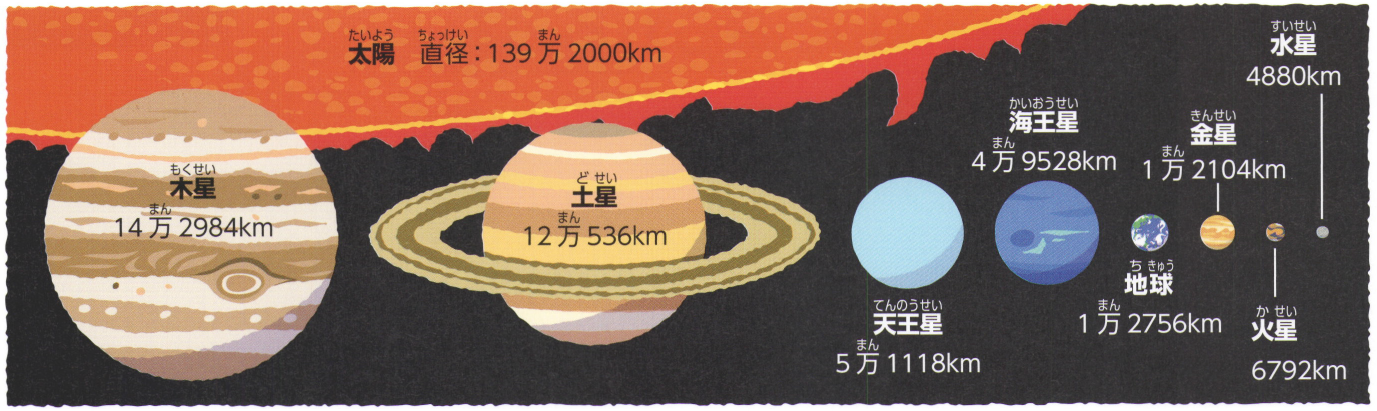
![]()
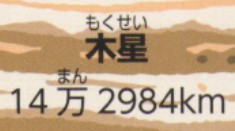
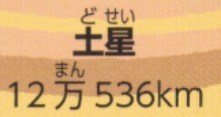
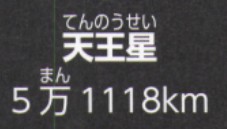
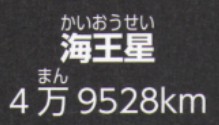
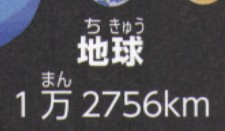
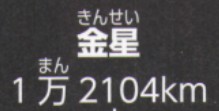
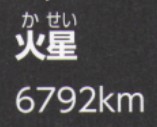
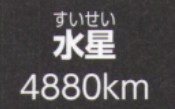
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
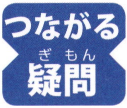
![]()
![]()
![]()
![]()
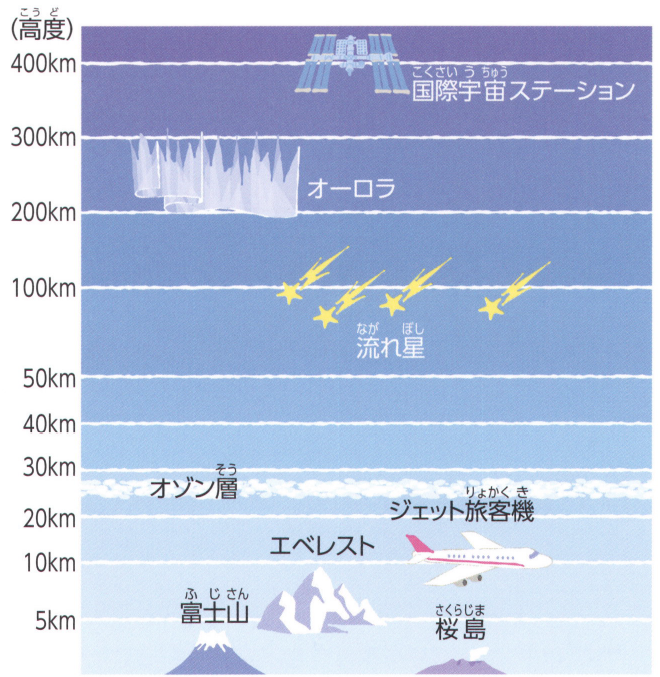
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
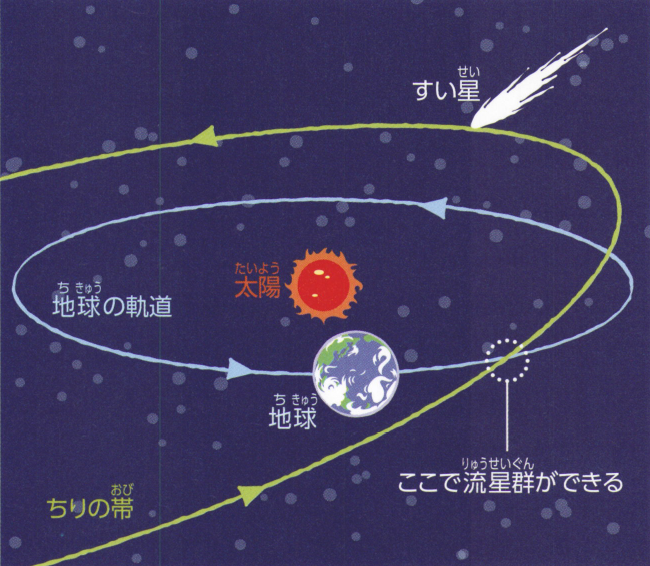
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
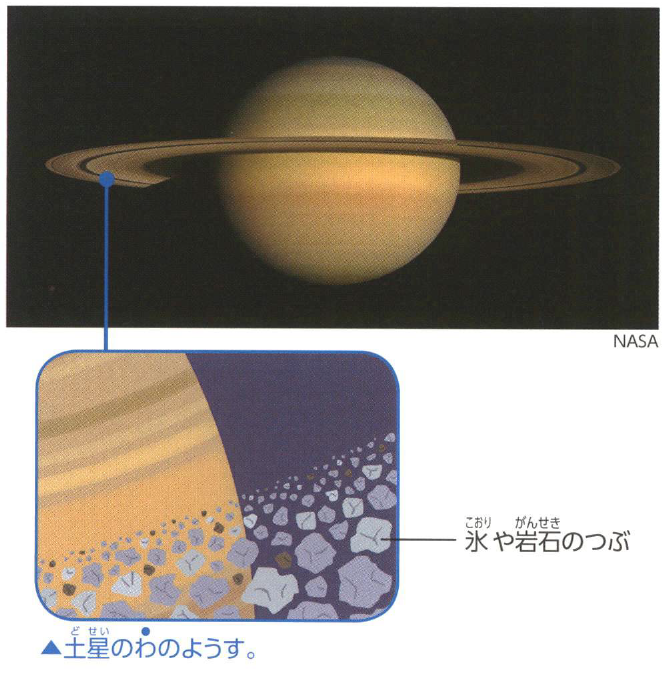
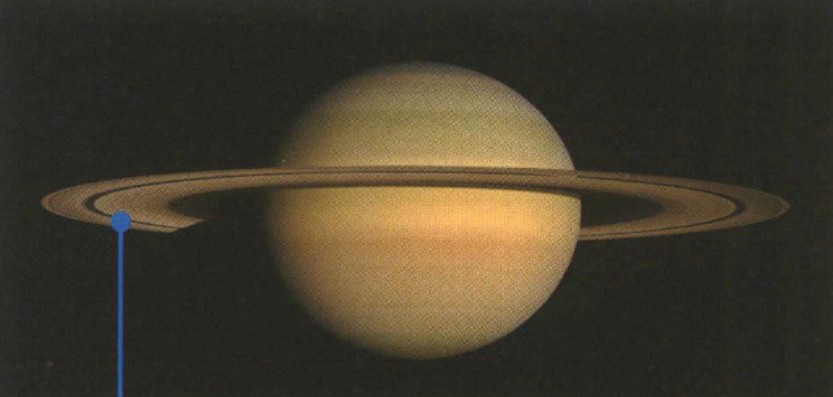
![]()
![]()
![]()
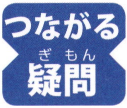
![]()
![]()
![]()
![]()
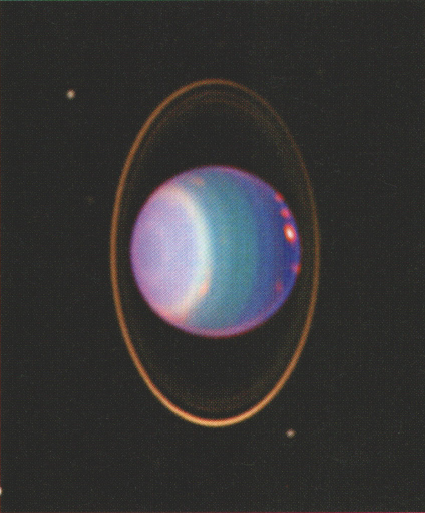
![]()
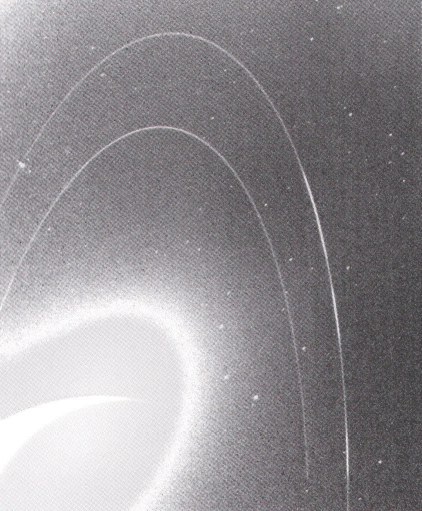
![]()
![]()
![]()
![]()
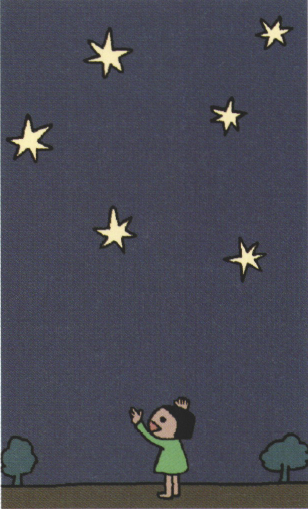
![]()

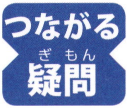
![]()
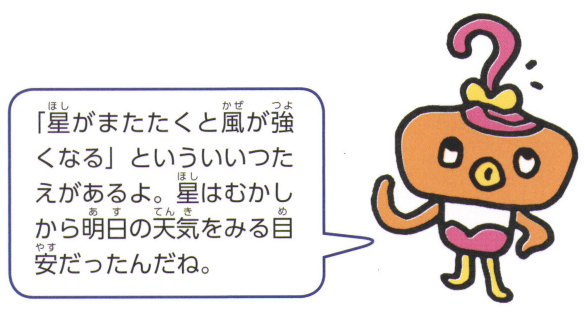
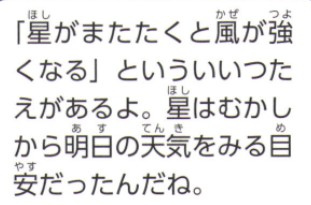
![]()
![]()
![]()
![]()
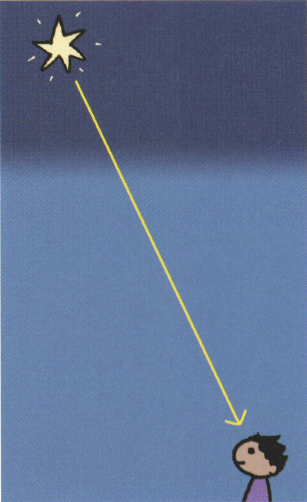
![]()
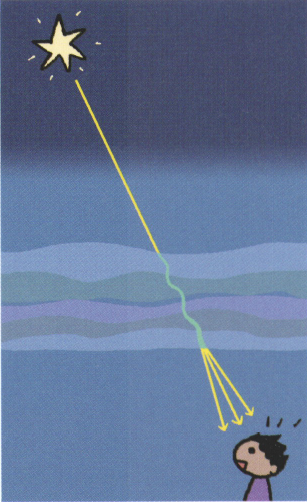
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
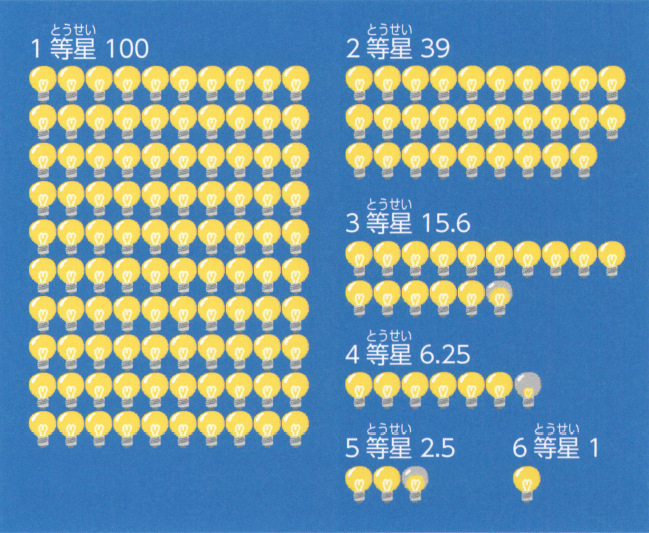
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
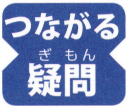
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
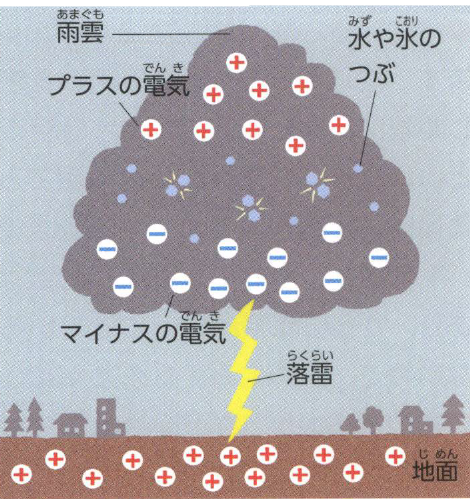
![]()
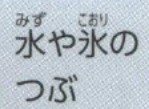
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
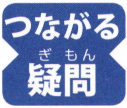
![]()
![]()
![]()

![]()
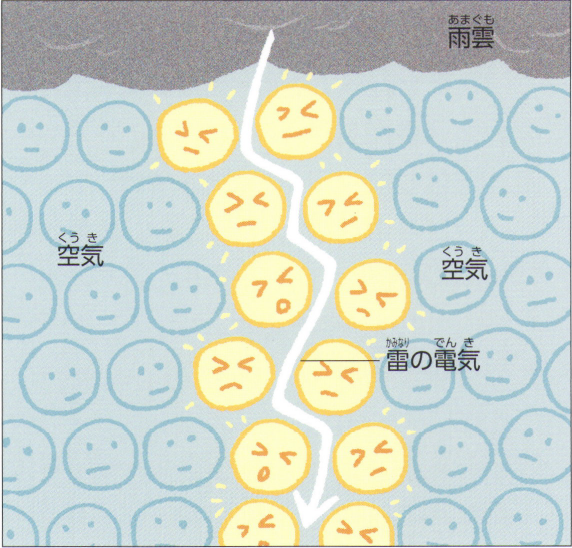
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
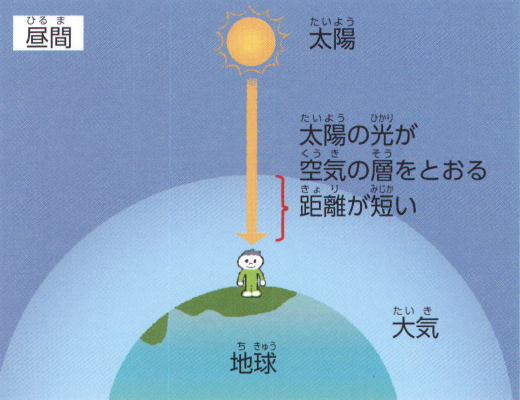
![]()
![]()
![]()
![]()
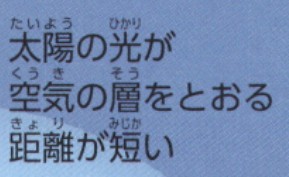
![]()
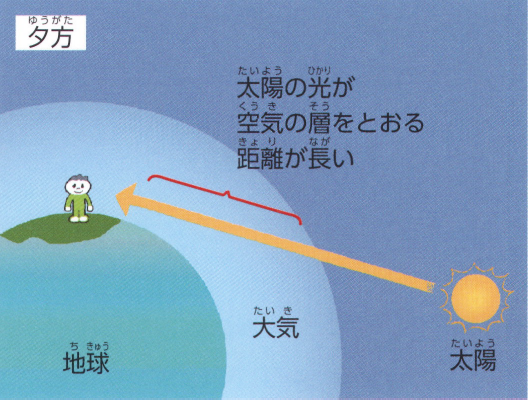
![]()
![]()
![]()
![]()
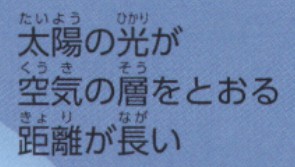
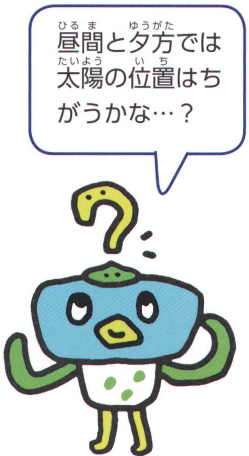
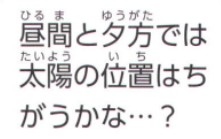
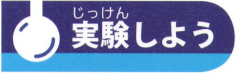
![]()
![]()
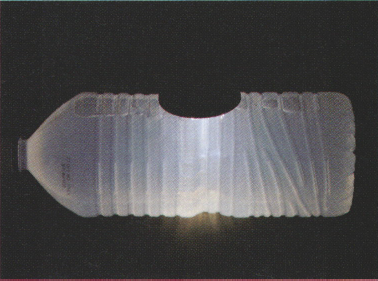
![]()
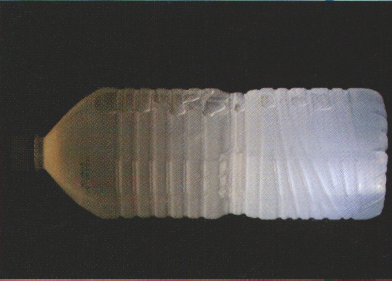
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
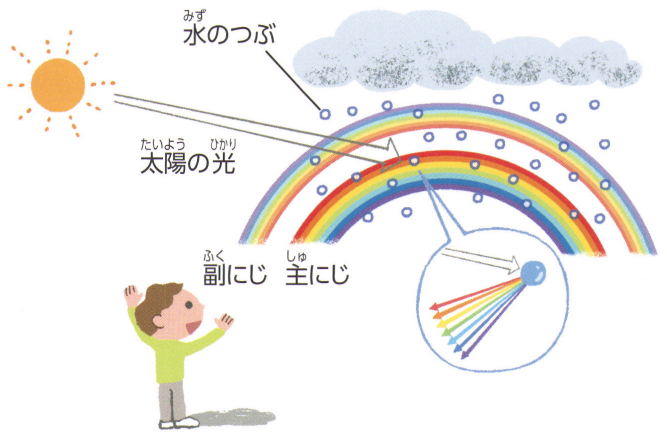
![]()
![]()
![]()
![]()

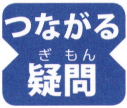
![]()
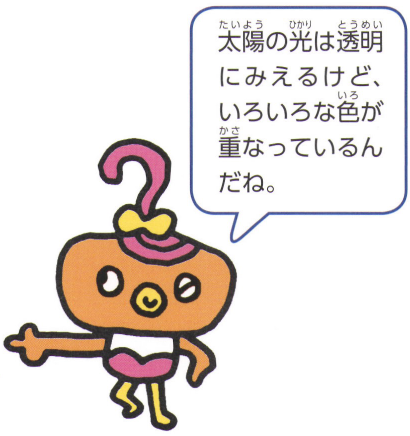
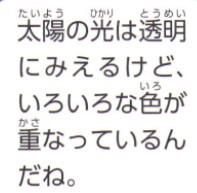
![]()
![]()
![]()
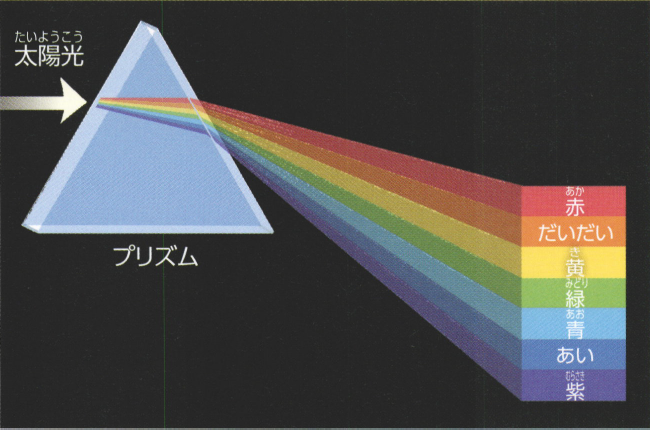
![]()
![]()

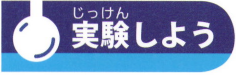
![]()
![]()

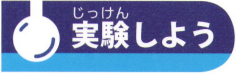
![]()
![]()
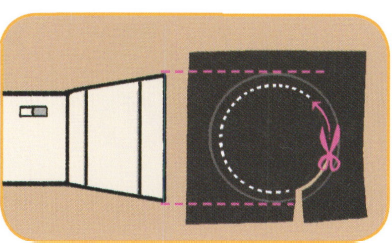
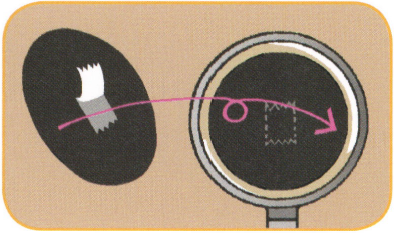
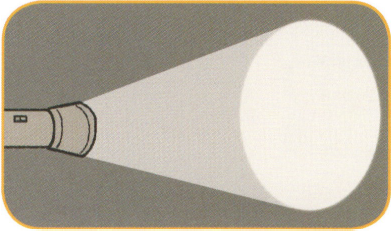
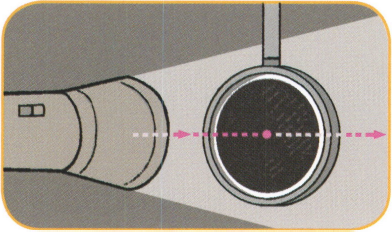
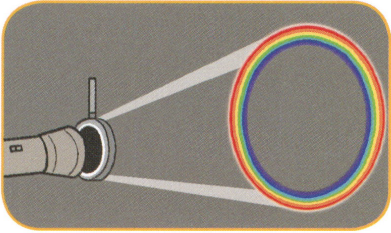
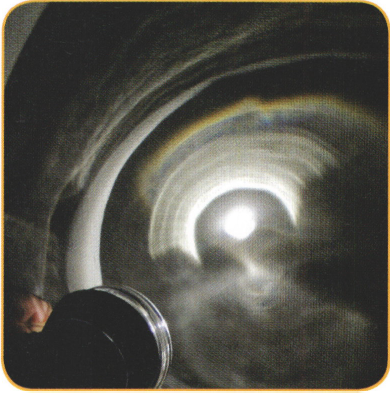
![]()
![]()
![]()
![]()
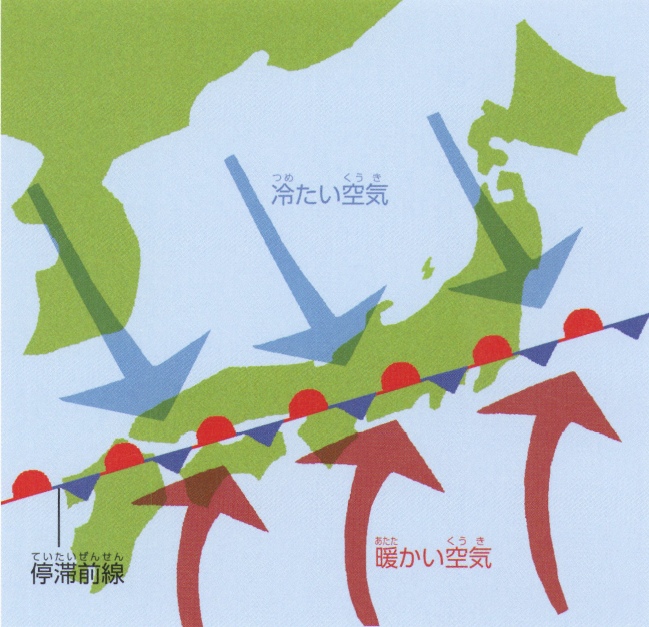
![]()
![]()
![]()
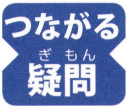
![]()
![]()
![]()
![]()
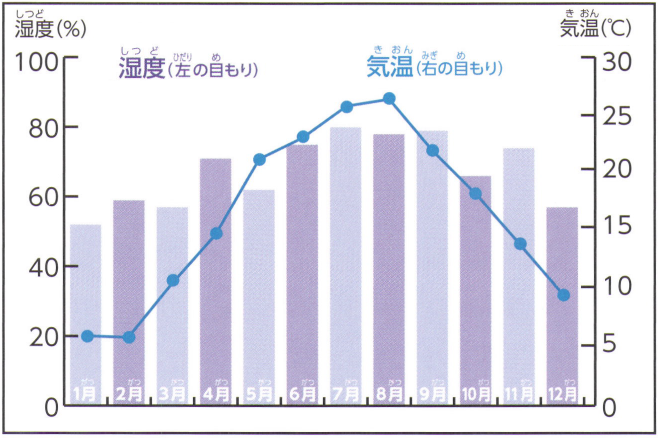
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
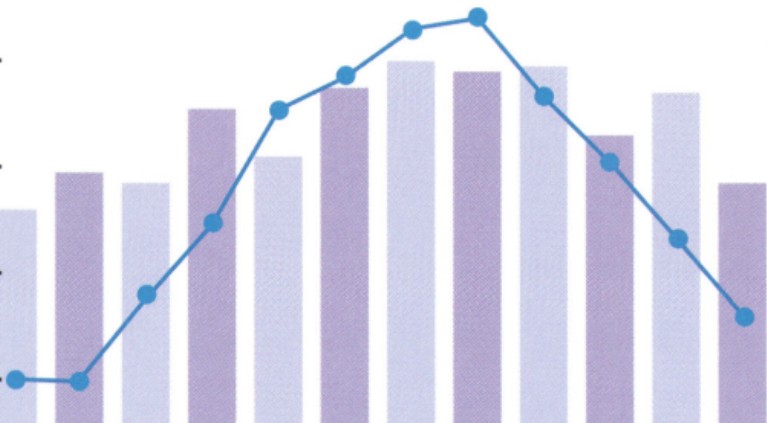
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

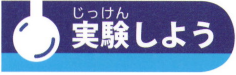
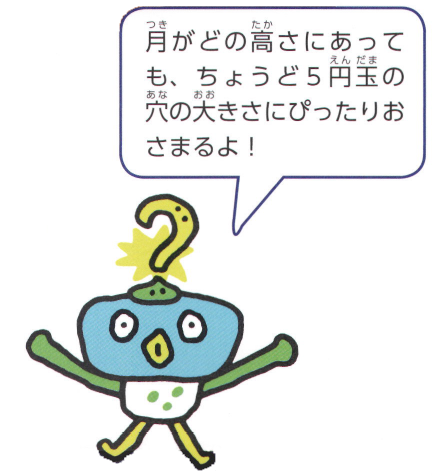
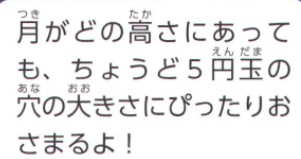
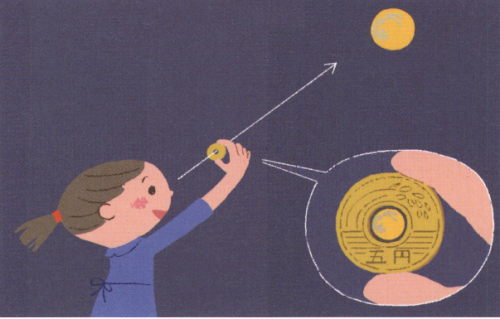
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
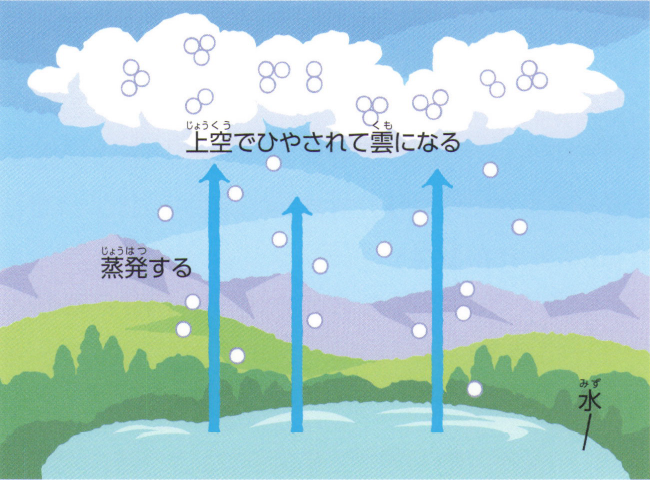
![]()
![]()
![]()
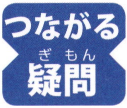
![]()
![]()
![]()
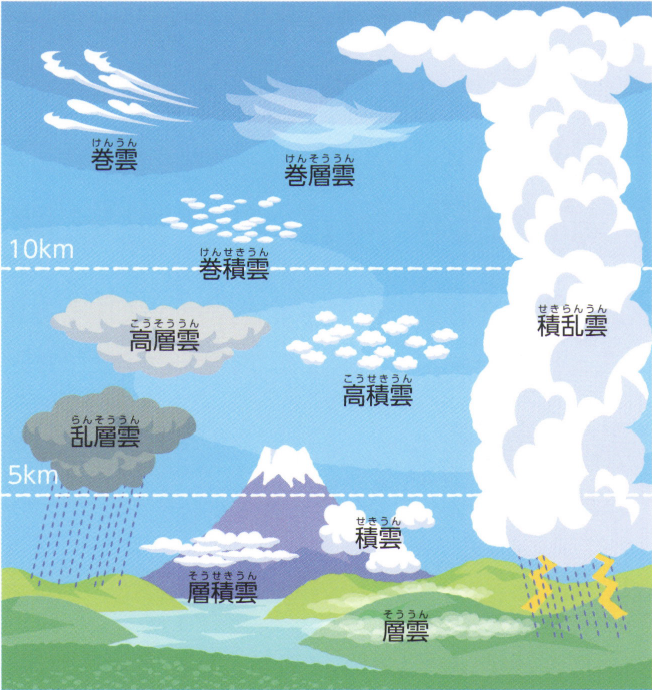
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
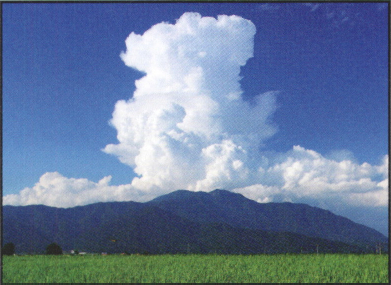
![]()

![]()

![]()
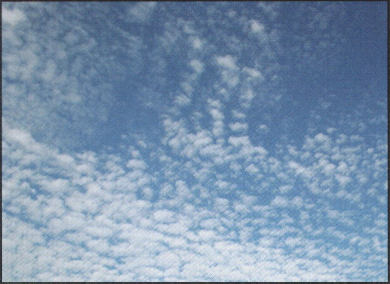
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

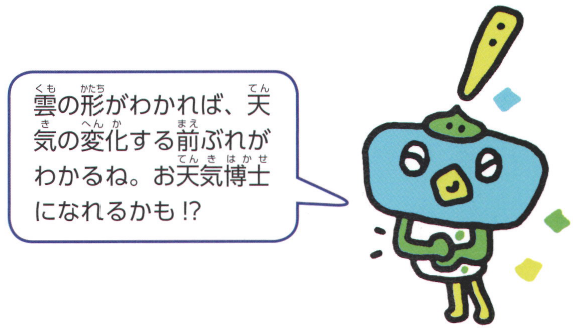
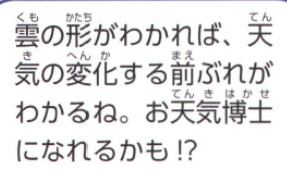
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
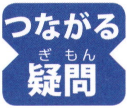
![]()
![]()
![]()
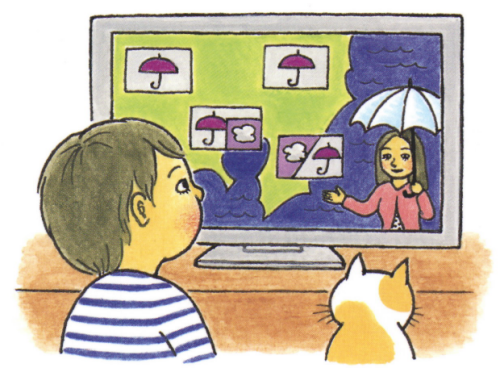


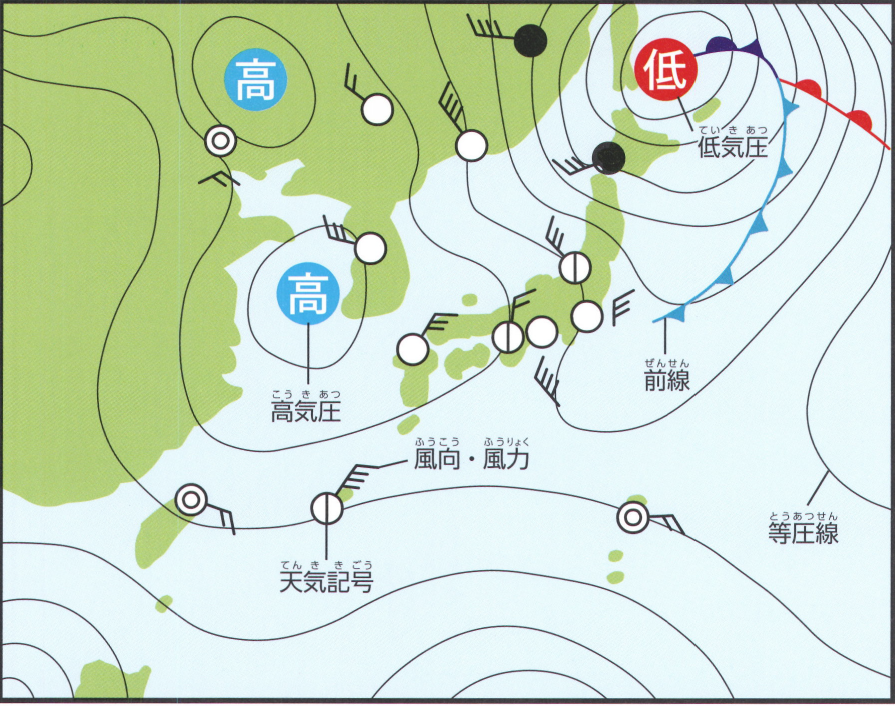
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


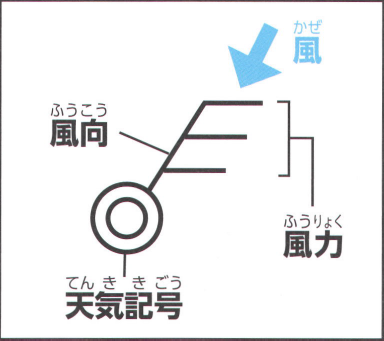
![]()
![]()
![]()
![]()

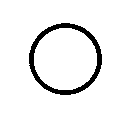 快晴
快晴
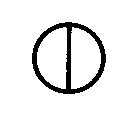 晴れ
晴れ
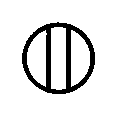 薄曇り
薄曇り
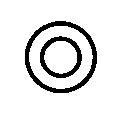 曇り
曇り
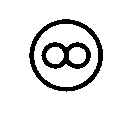 煙霧
煙霧
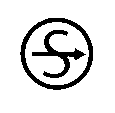 砂じん あらし
砂じん あらし
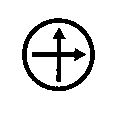 地ふぶき
地ふぶき
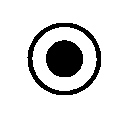 霧
霧
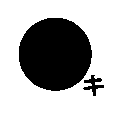 霧雨
霧雨
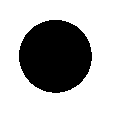 雨
雨
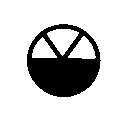 みぞれ
みぞれ
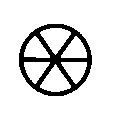 雪
雪
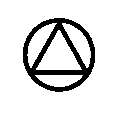 あられ
あられ
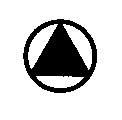 ひょう
ひょう
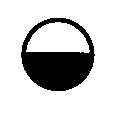 雷
雷


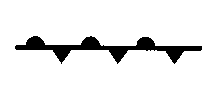
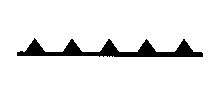
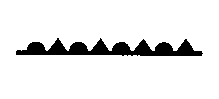

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
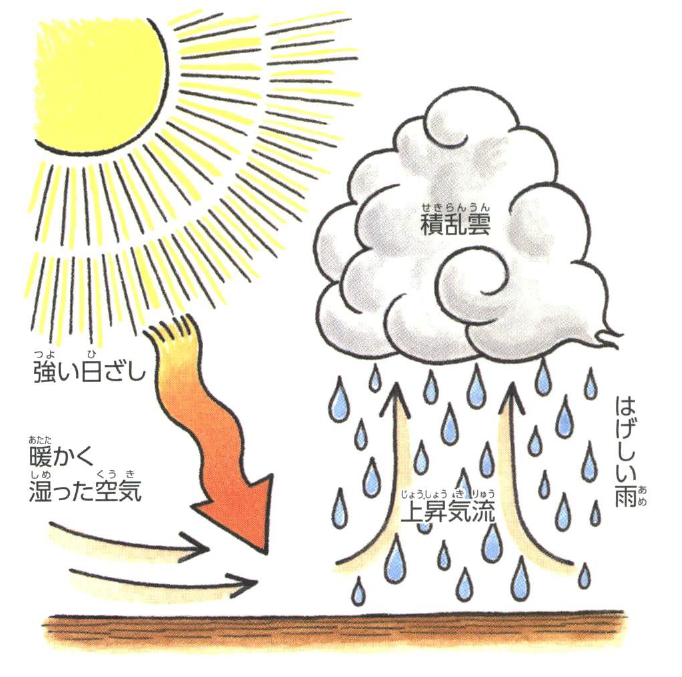
![]()
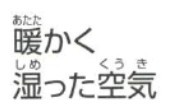
![]()
![]()
![]()
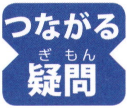
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
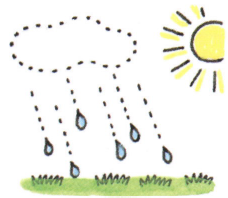
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() が
が
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
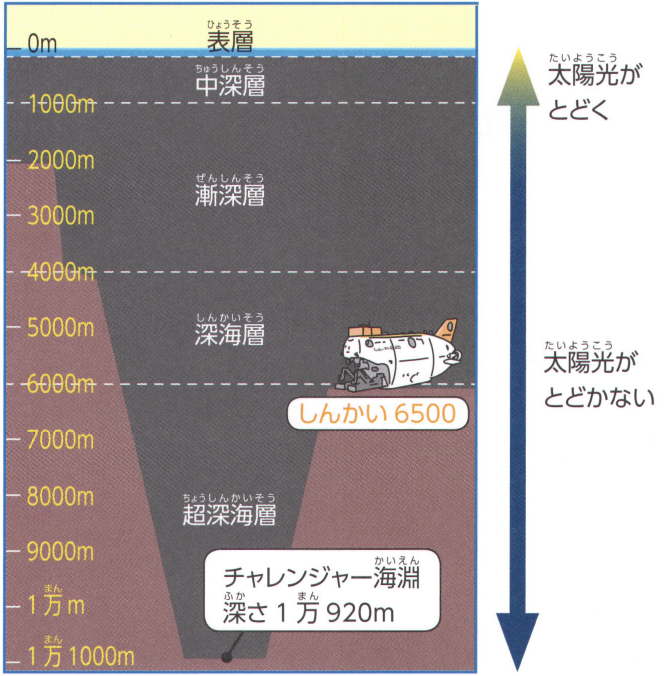
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
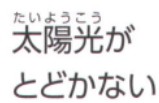
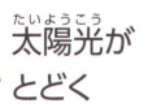
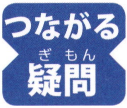
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
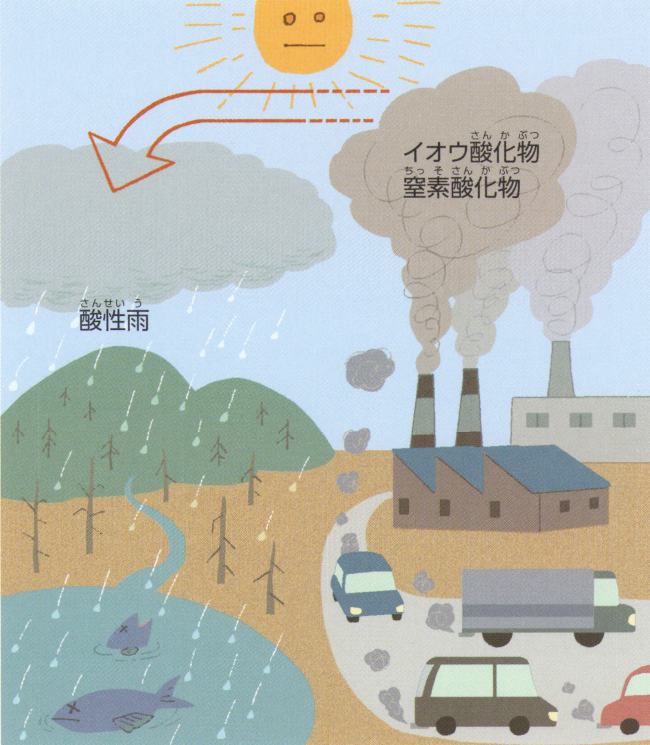
![]()
![]()
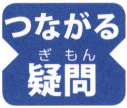
![]()
![]()
![]()
![]()
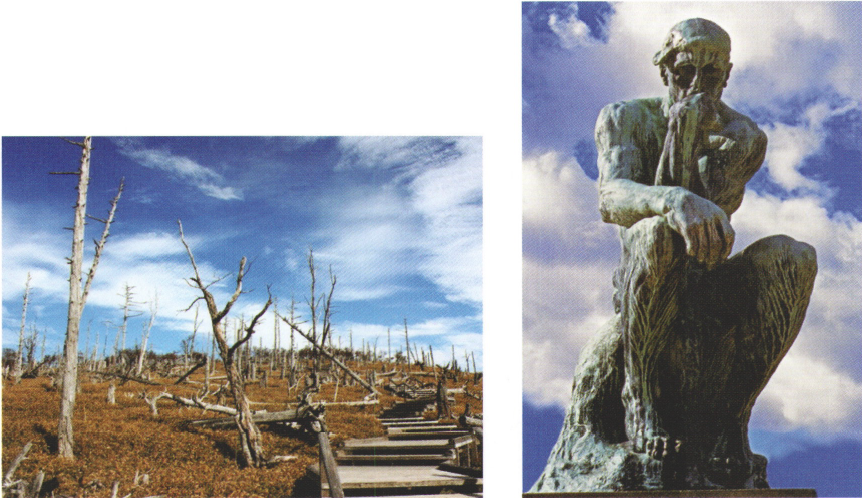
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
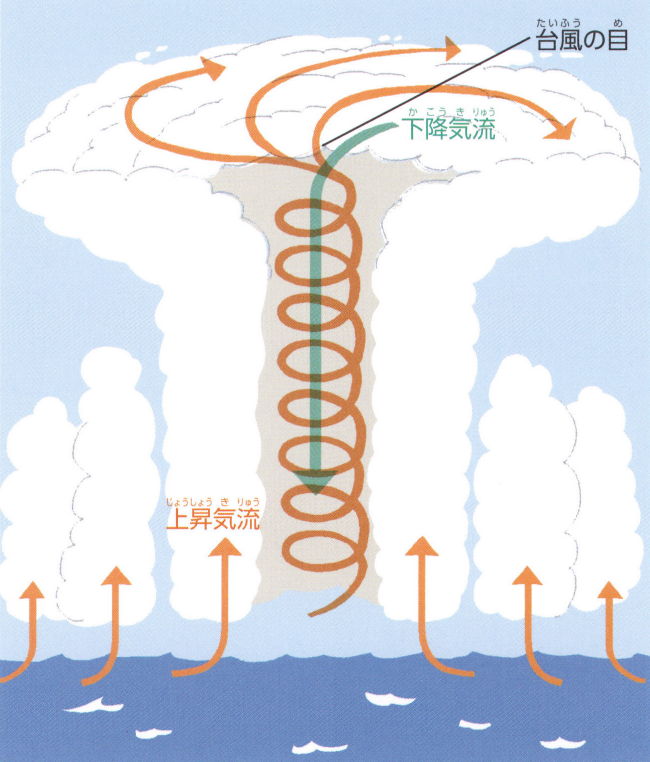
![]()
![]()
![]()
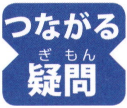
![]()
![]()
![]()
![]()
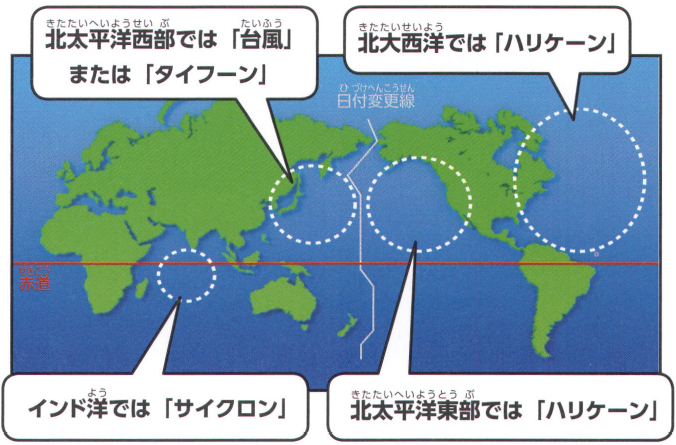
![]()
![]()
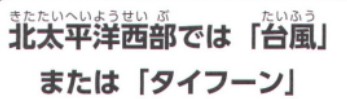

![]()
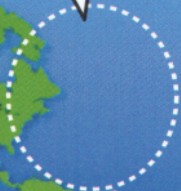
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
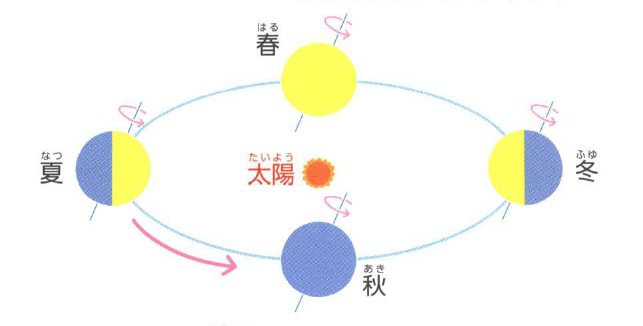
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
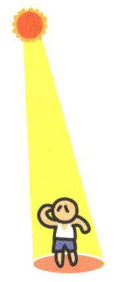
![]()

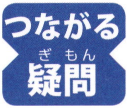
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
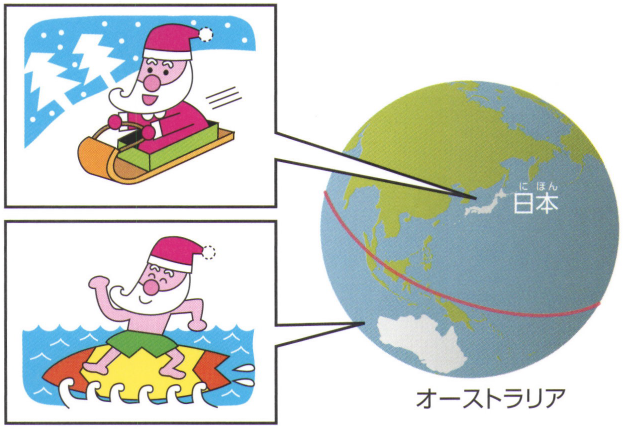
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
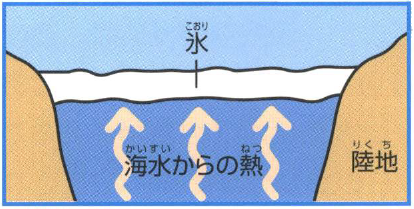
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
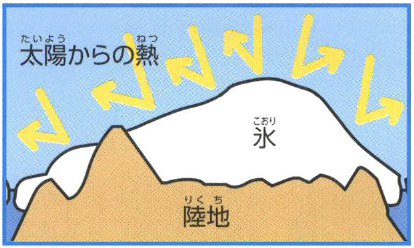
![]()
![]()
![]()
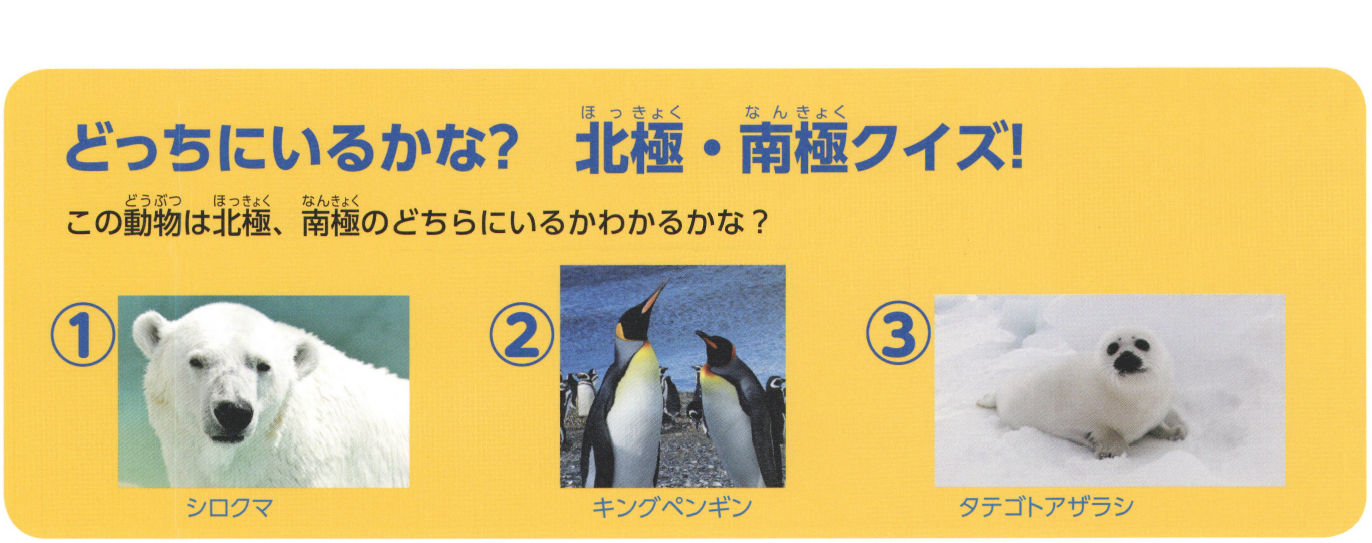
![]()
![]()
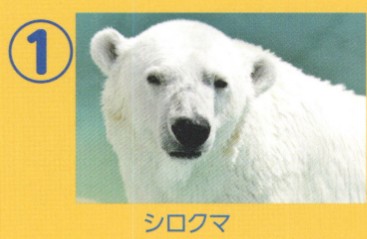
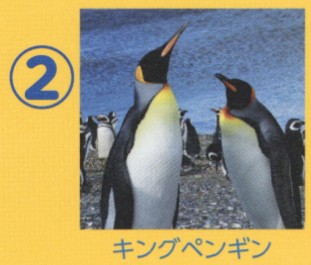
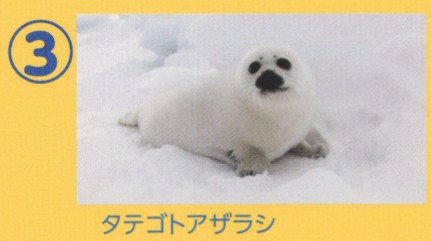
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
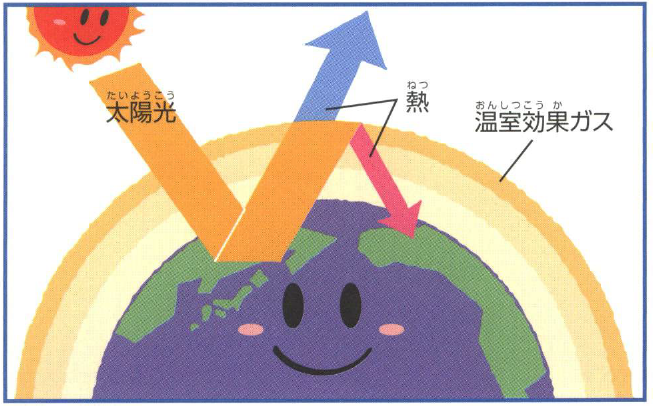
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
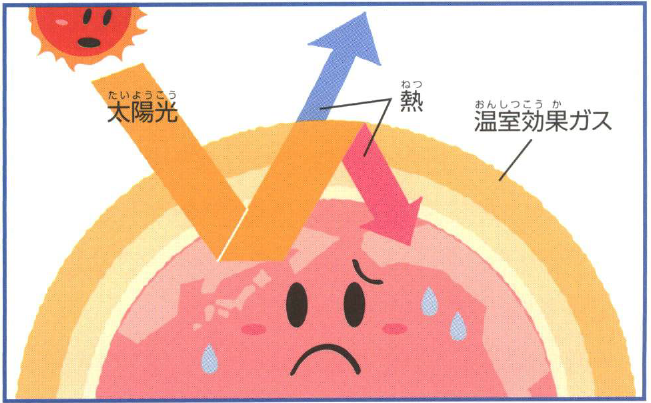
![]()
![]()
![]()
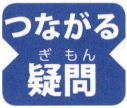
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
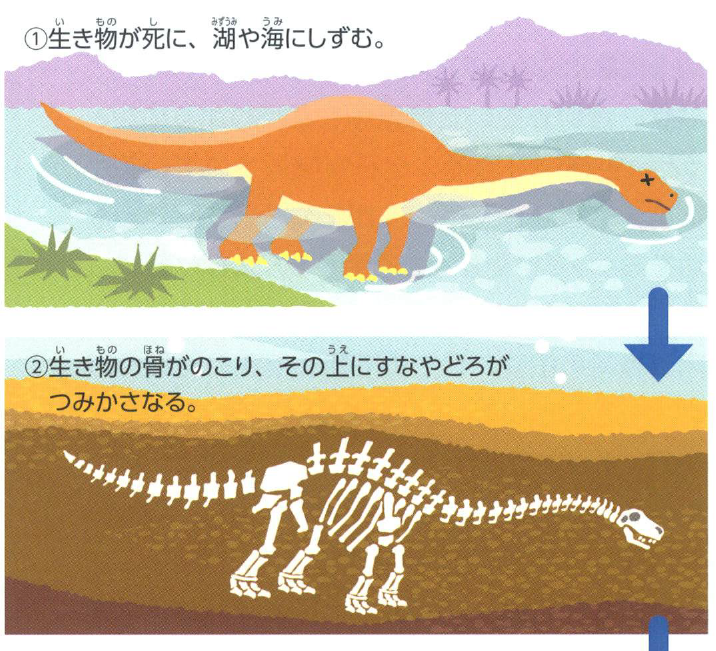
![]()
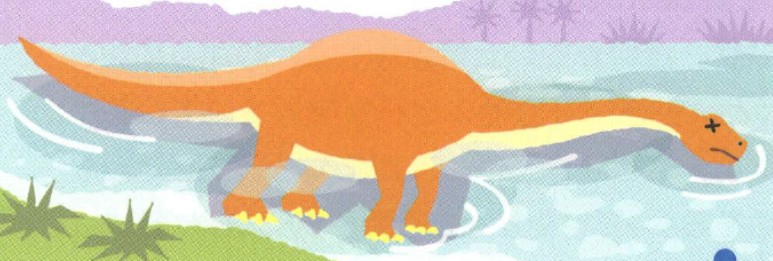
![]()
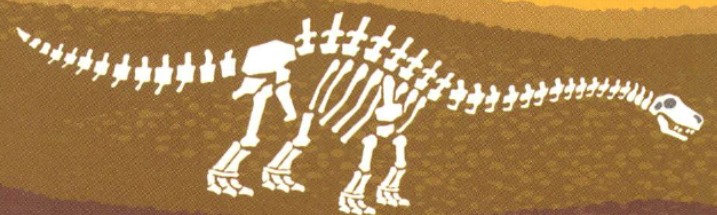
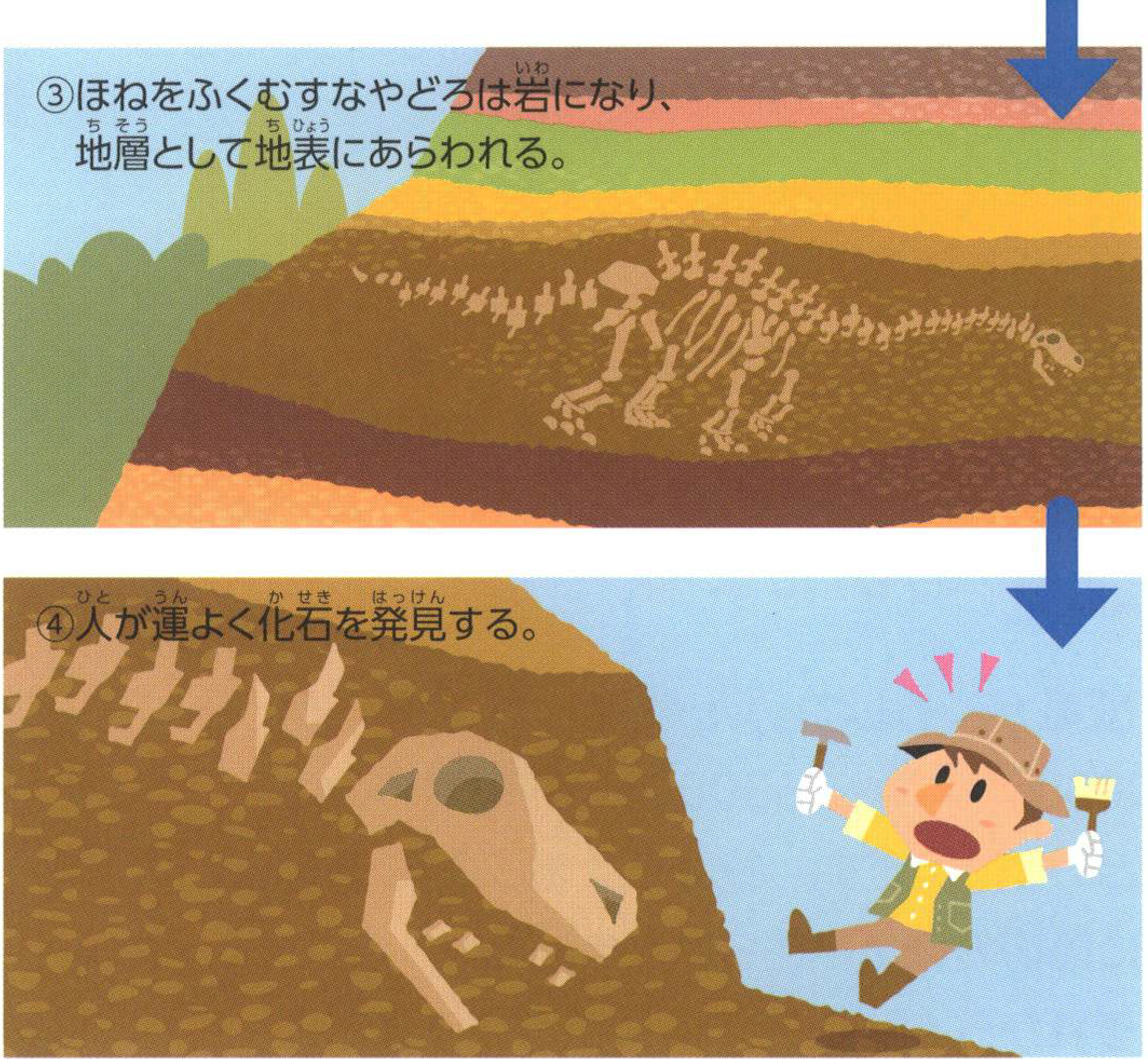
![]()
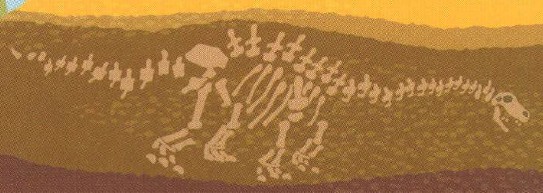
![]()

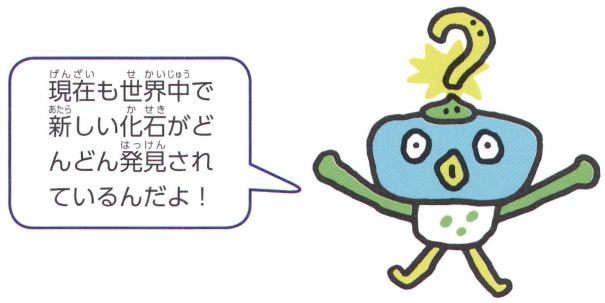
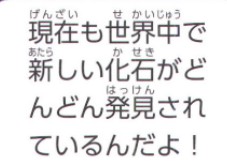
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

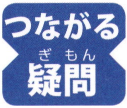
![]()
![]()
![]()
![]()
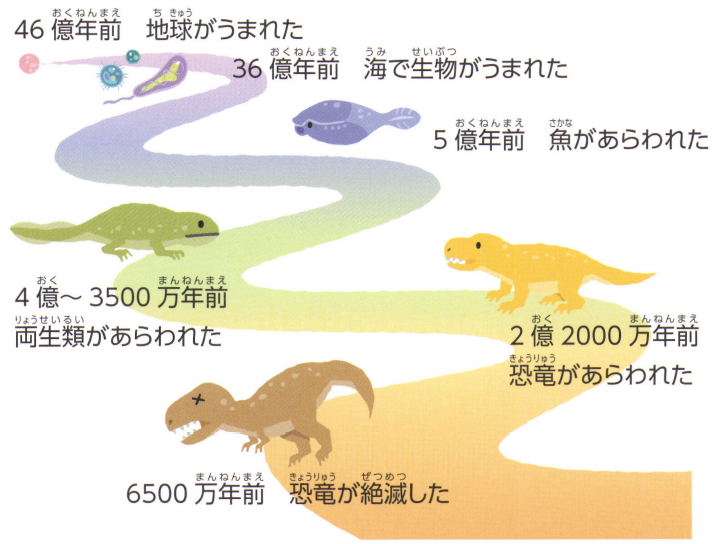
![]()
![]()
![]()
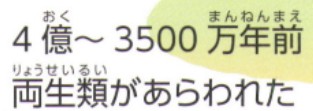
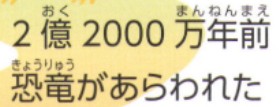
![]()
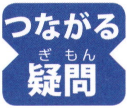
![]()
![]()
![]()
![]()
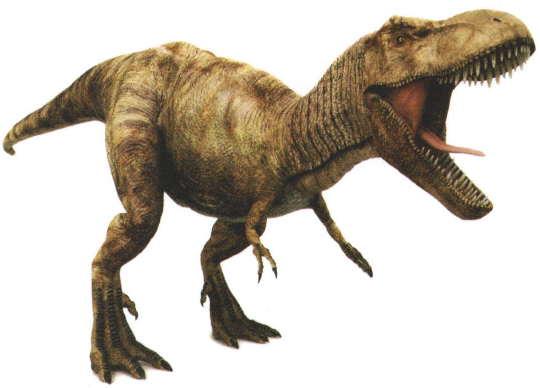
![]()

![]()

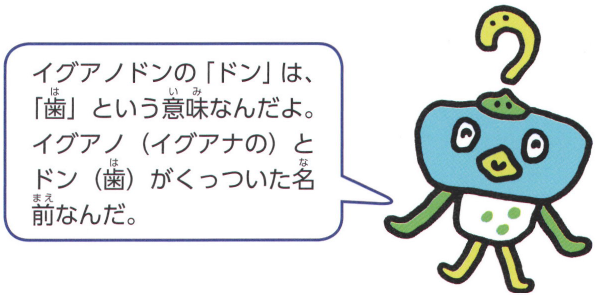
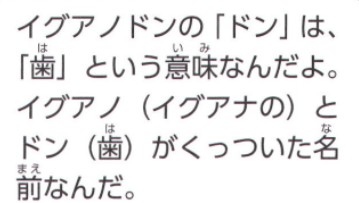
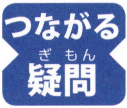
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
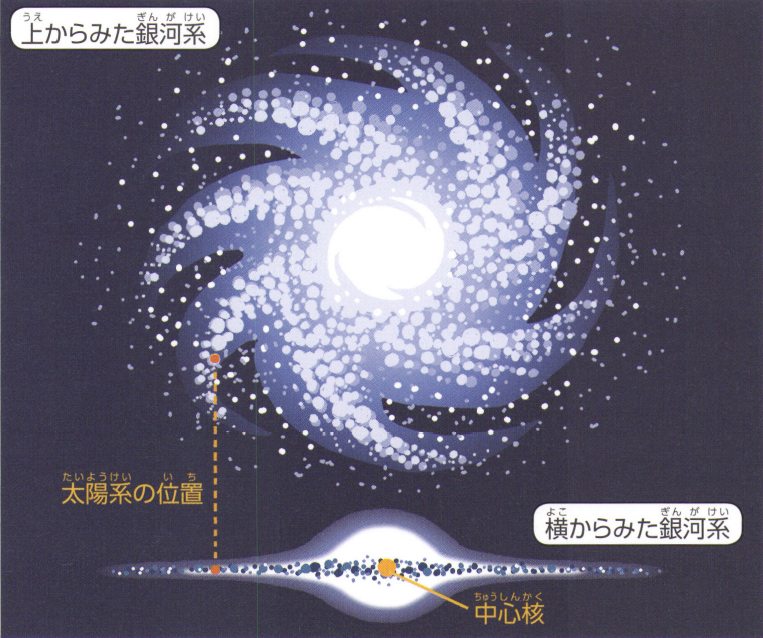
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
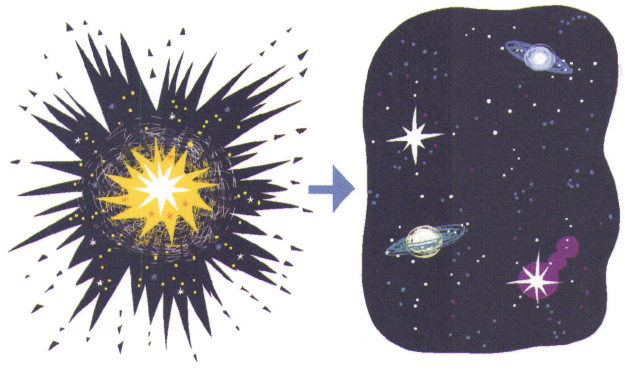
![]()
![]()
![]()
![]()

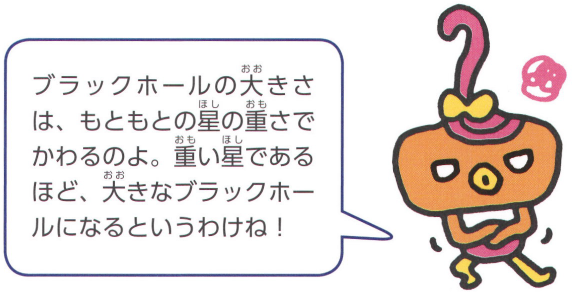
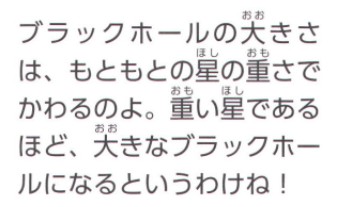
![]()
![]()
![]()
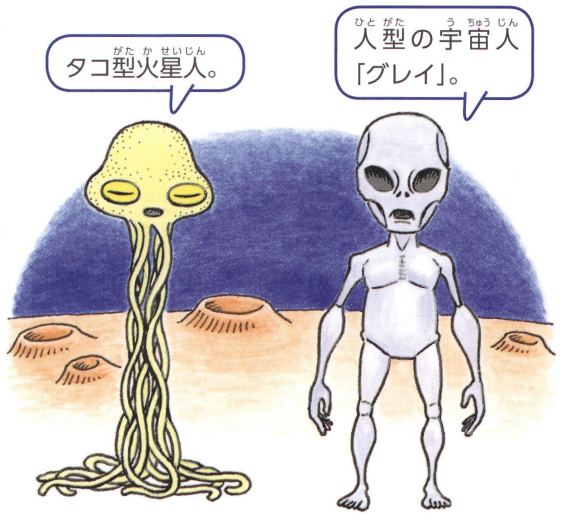
![]()
![]()
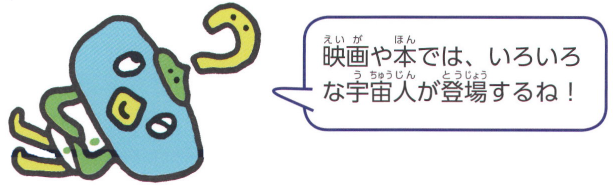
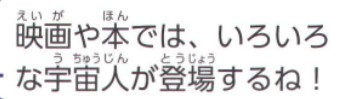
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
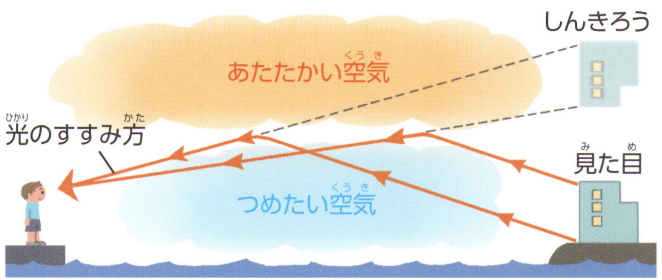
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
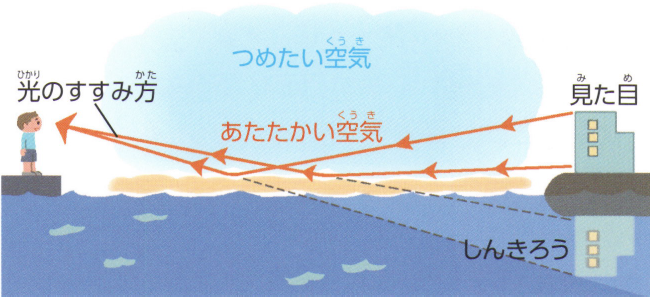
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
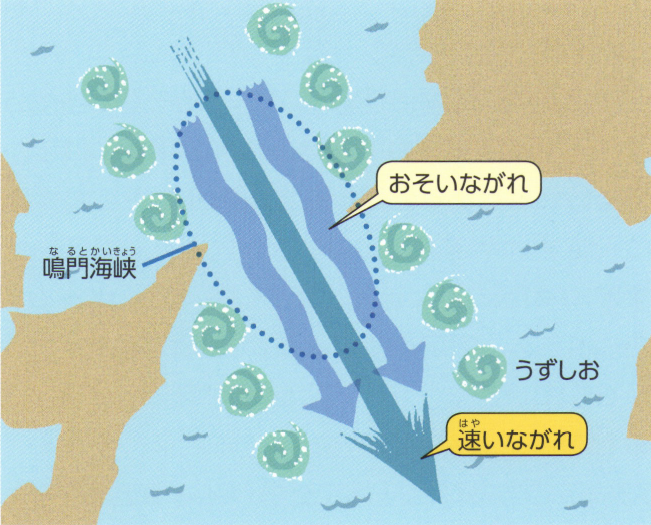
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
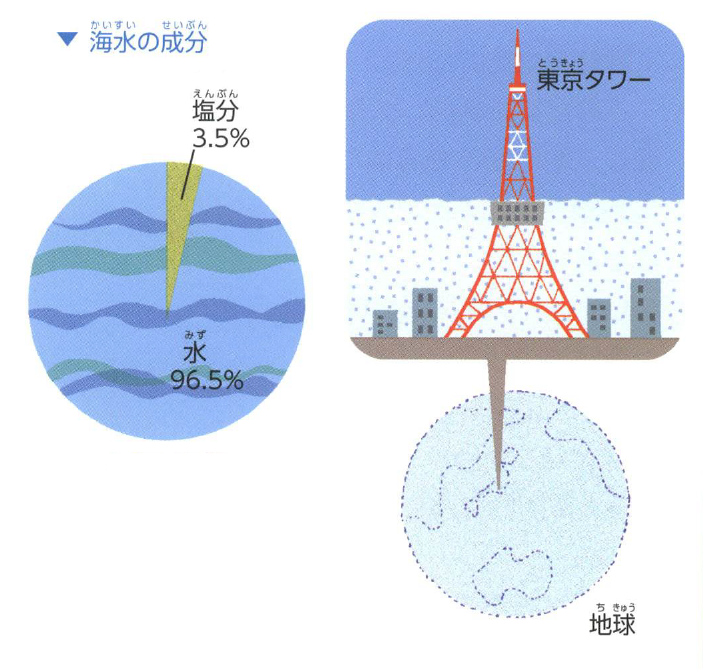
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
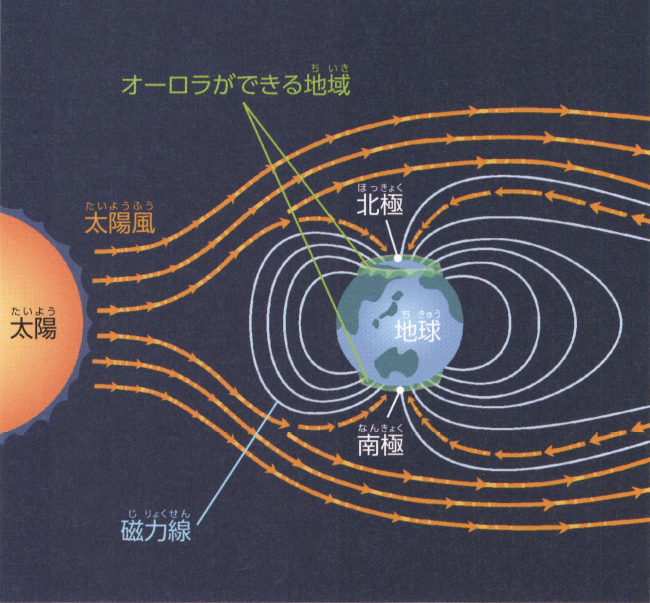
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
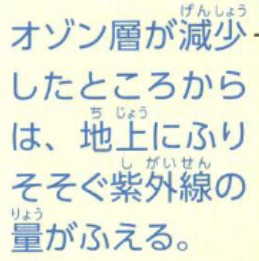
![]()
![]()
![]()
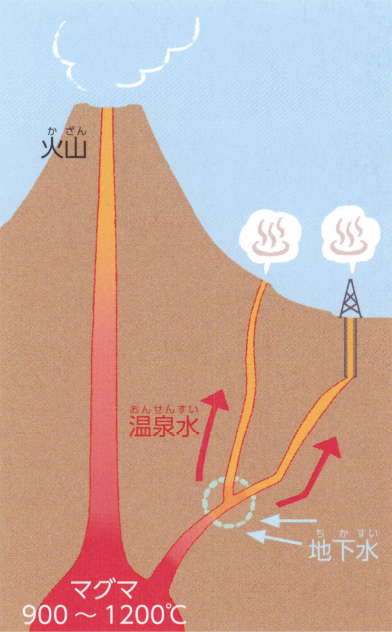
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
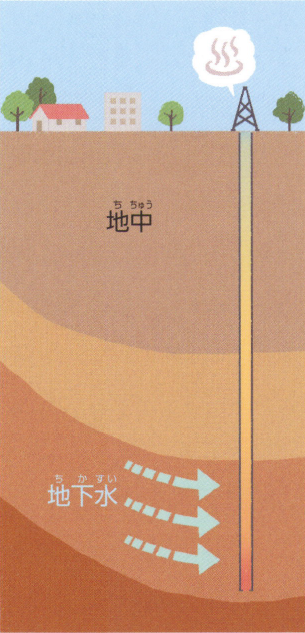
![]()
![]()

![]()

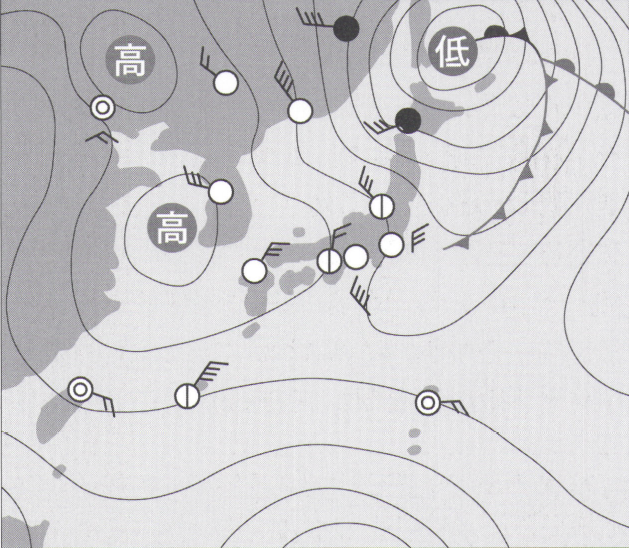
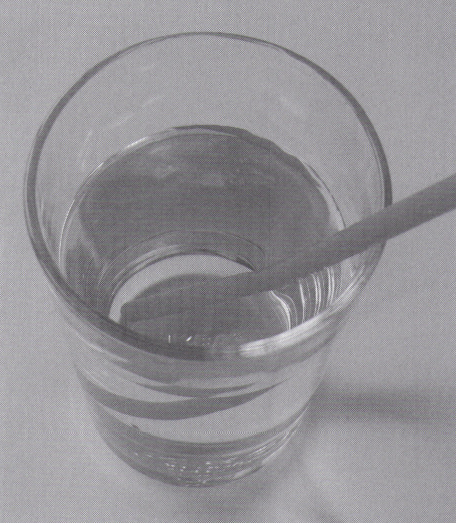
![]()

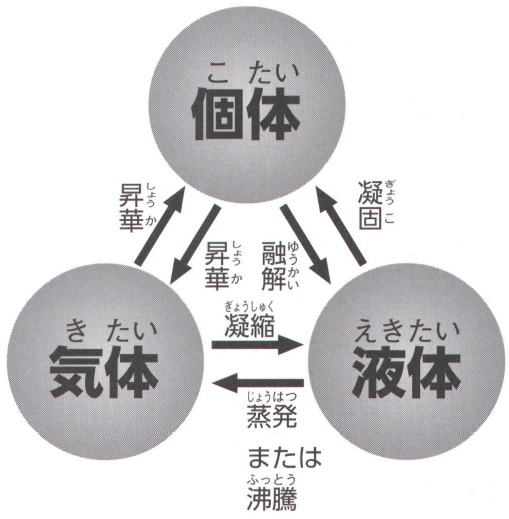
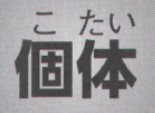
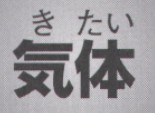
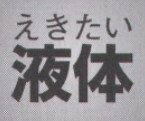
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

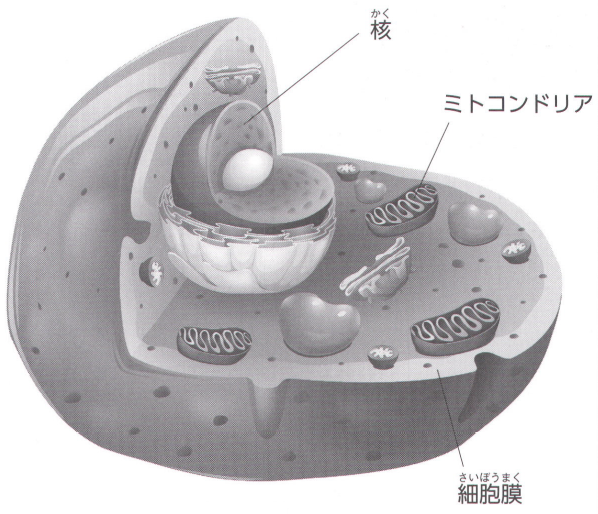
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
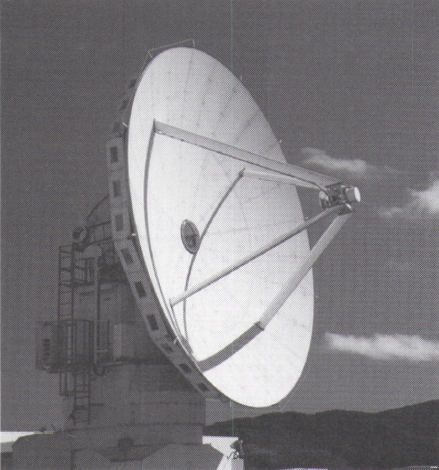
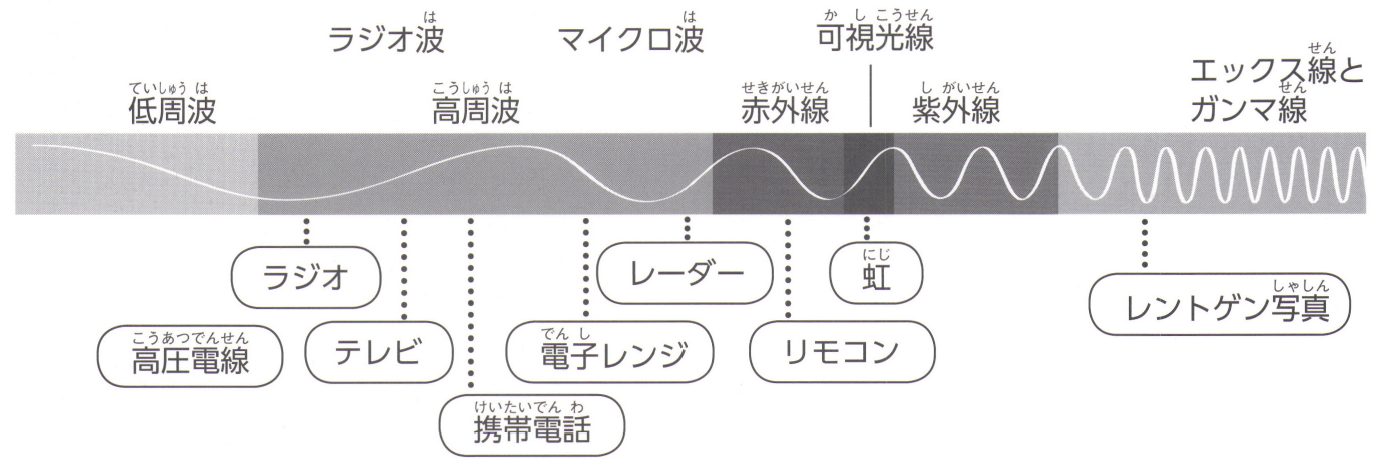
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
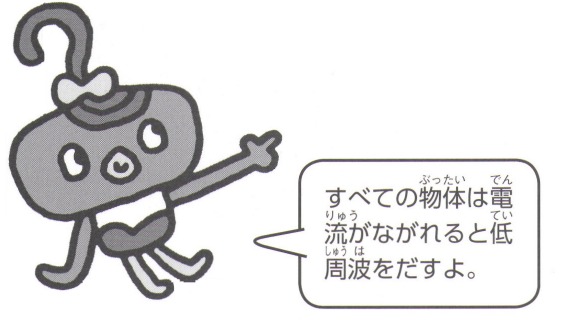
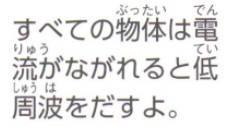
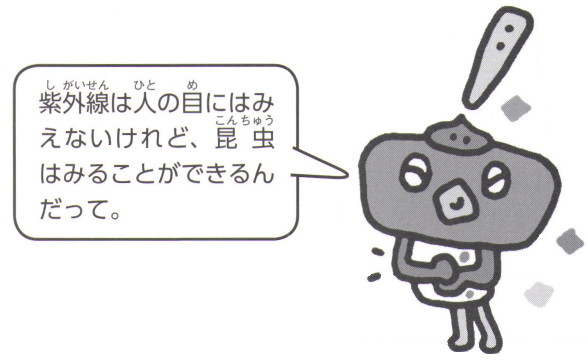
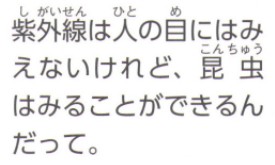
![]()
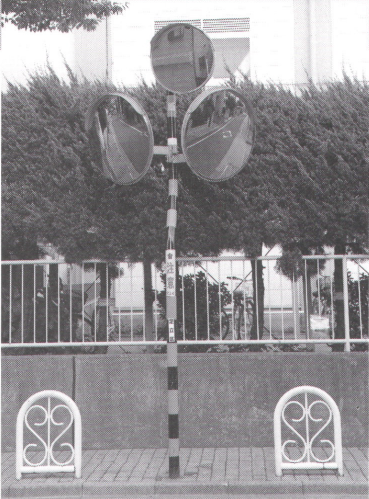

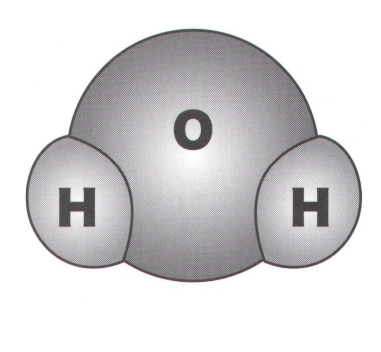
![]()
![]()
![]()

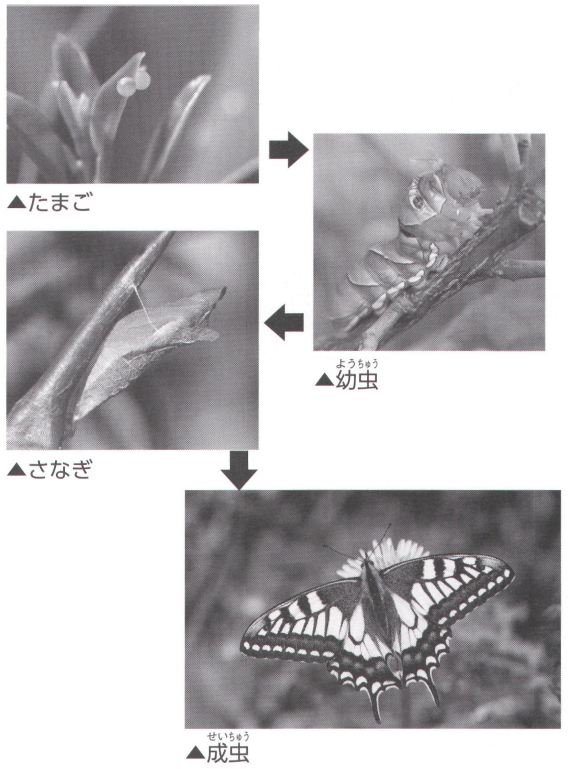
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()