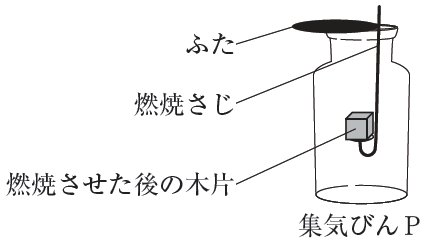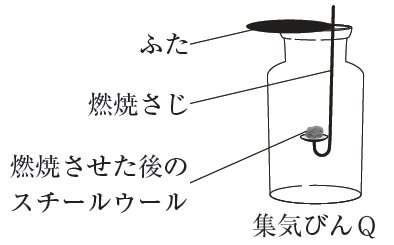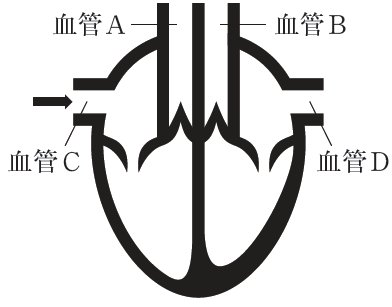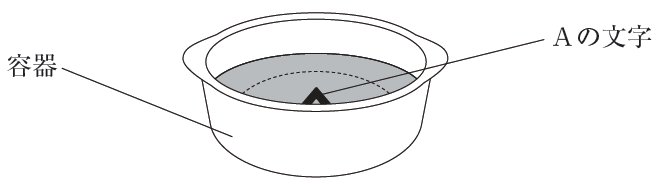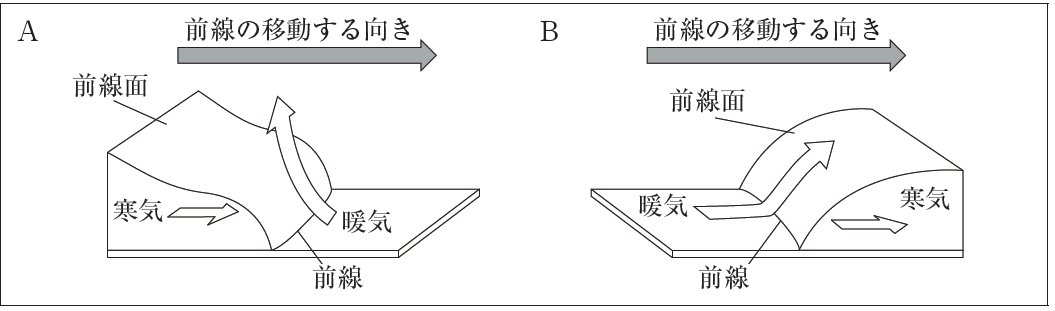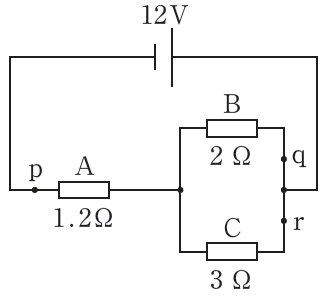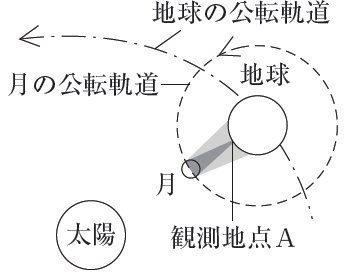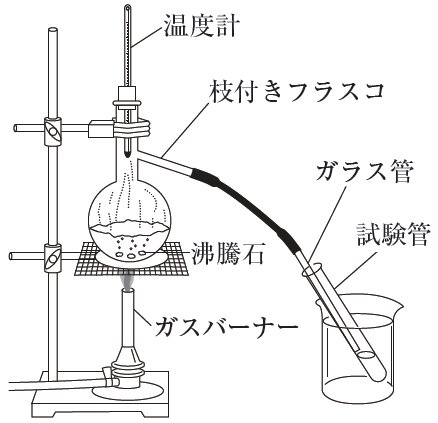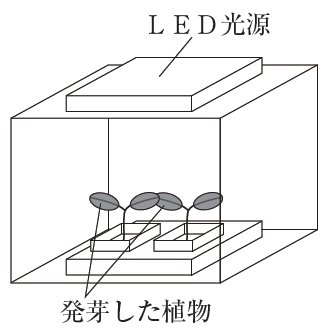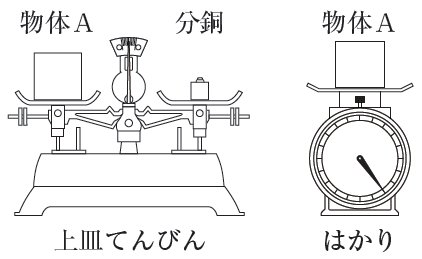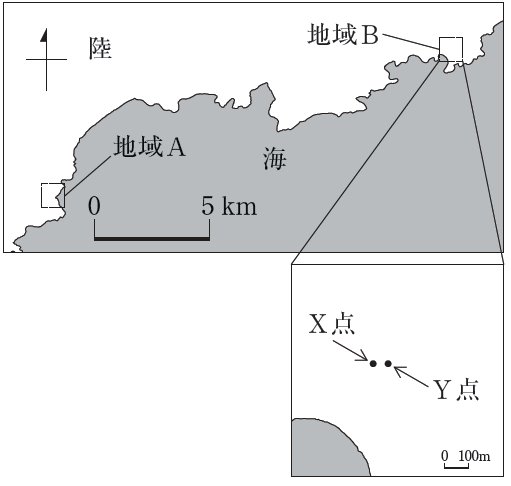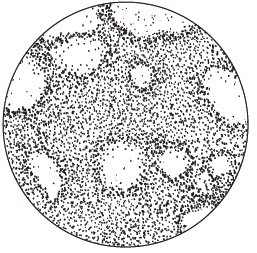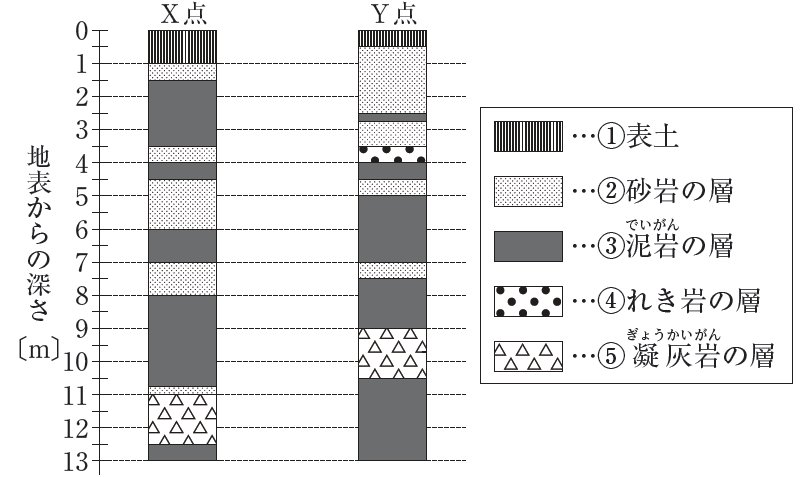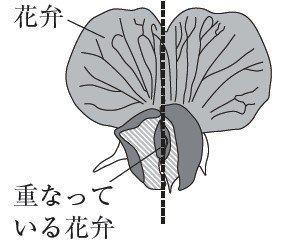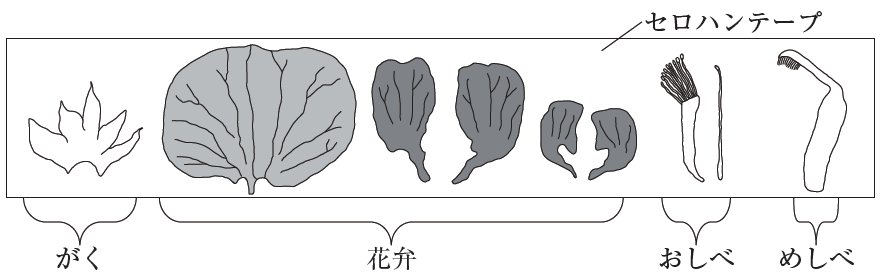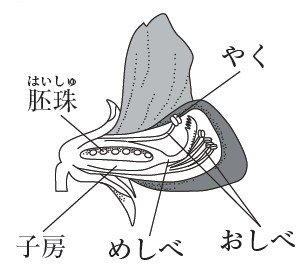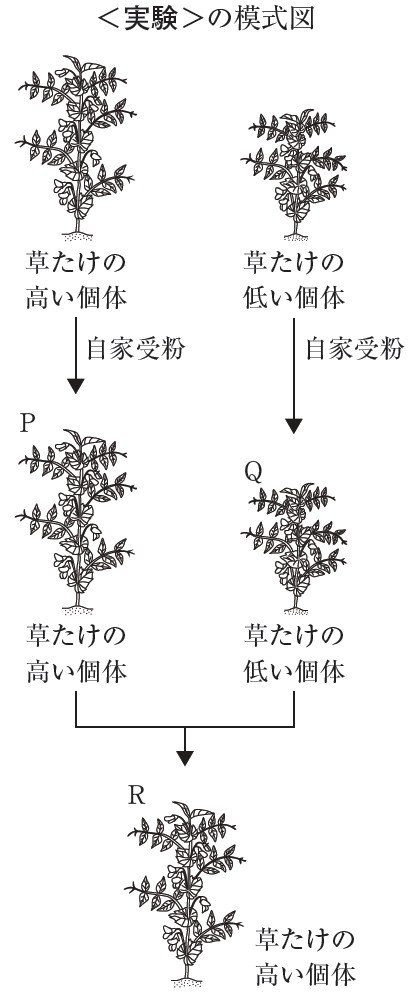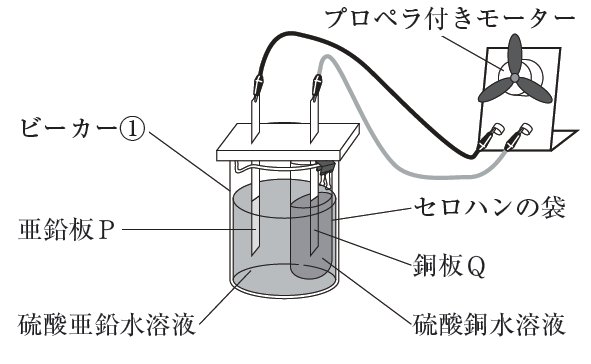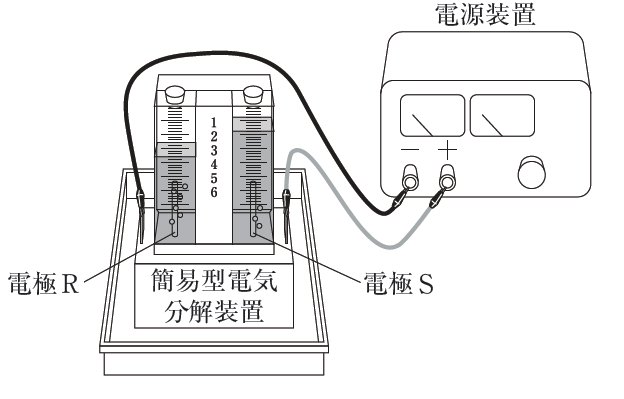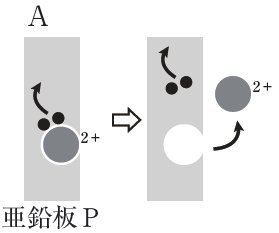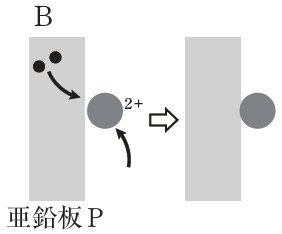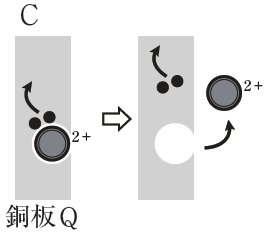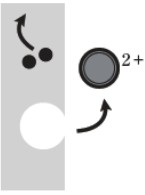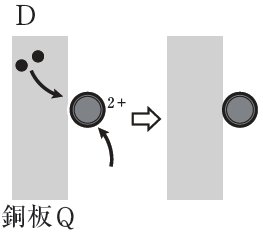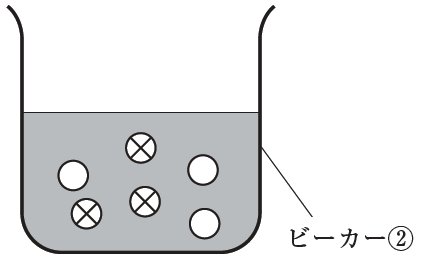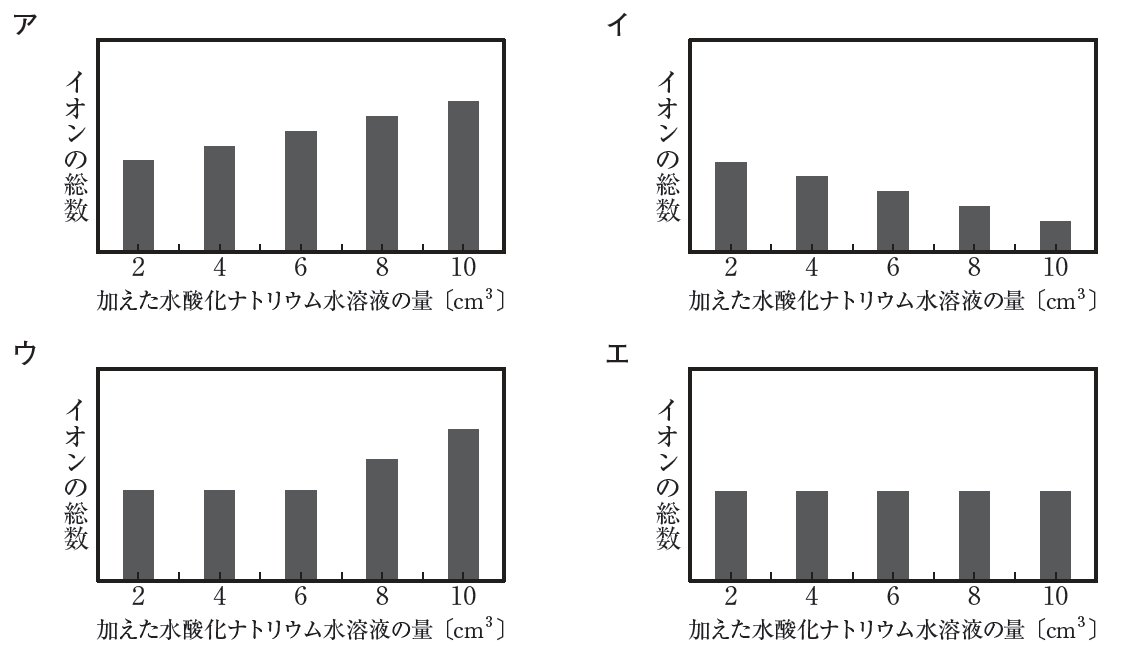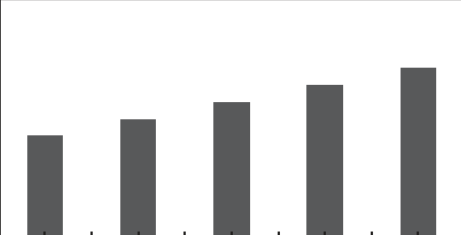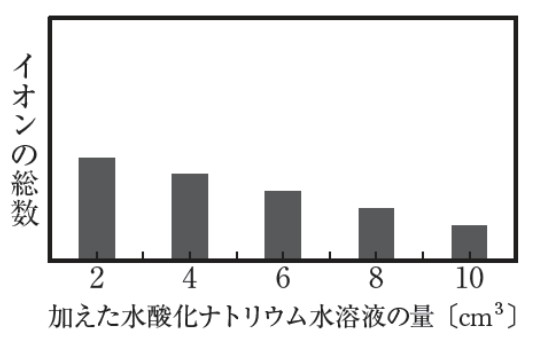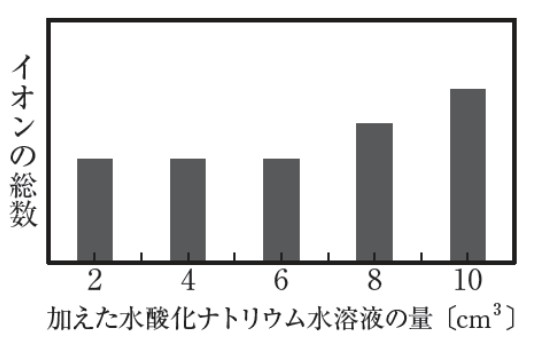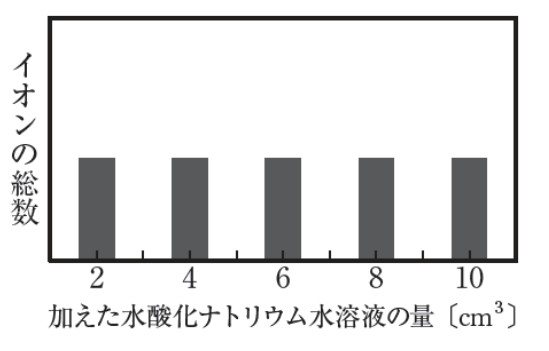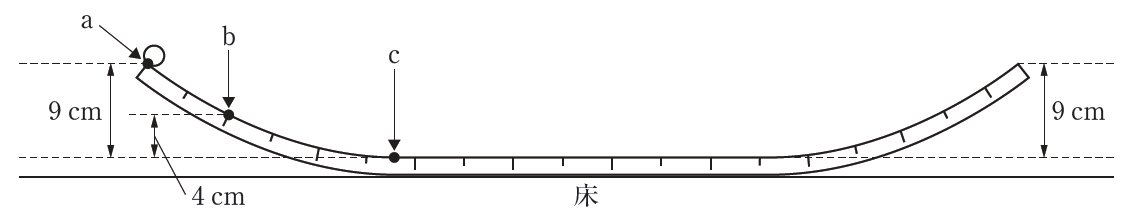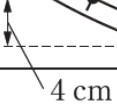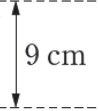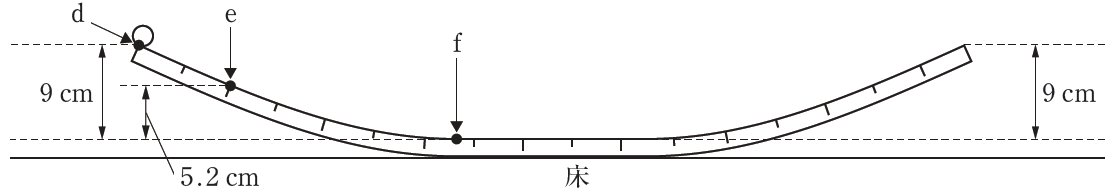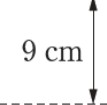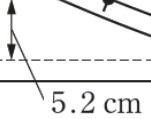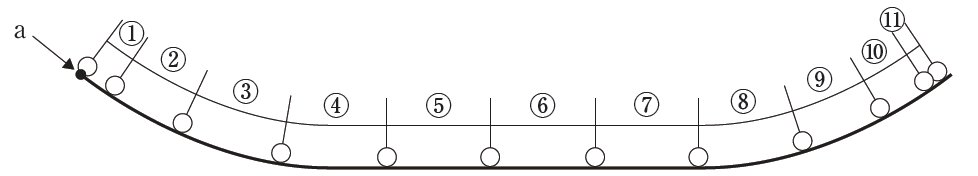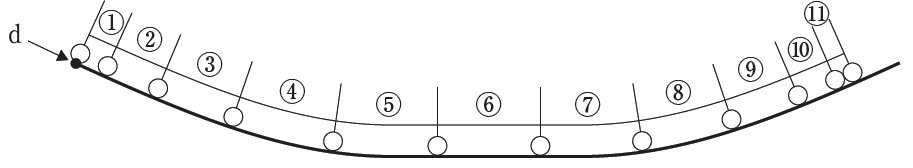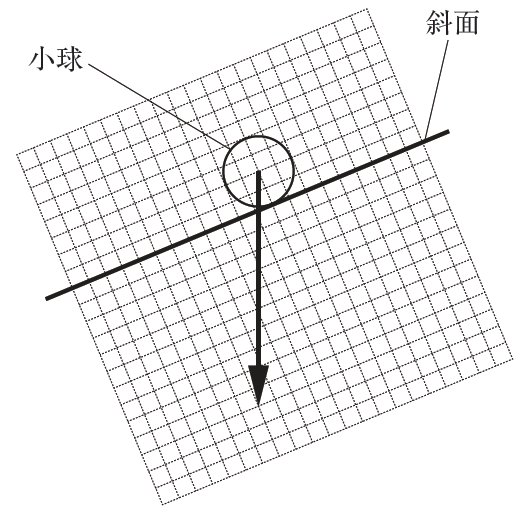令和
理科
注意
| 1 | 問題は |
| 2 | 検査 |
| 3 | 声を |
| 4 | 計算が |
| 5 | 答えは |
| 6 | 答えは |
| 7 | 答えを |
| 8 | 答えを |
| 9 | 受検 |
| 10 | 解答 |
問題は
1
次の
〔問1〕 図1は,質量を
燃焼
燃焼
図1
図2
|
|
燃焼 |
石灰水が |
|---|---|---|
|
ア |
木片 |
集気びんP |
|
イ |
スチールウール |
集気びんP |
|
ウ |
木片 |
集気びんQ |
|
エ |
スチールウール |
集気びんQ |
〔問2〕 図3は,ヒトの![]() )は
)は
血管A〜
図3
|
|
動脈 |
動脈血が |
|---|---|---|
|
ア |
血管Aと |
血管Bと |
|
イ |
血管Aと |
血管Aと |
|
ウ |
血管Cと |
血管Bと |
|
エ |
血管Cと |
血管Aと |
〔問3〕 図4は,平らな
図4
|
|
水中から |
「A」の |
|---|---|---|
|
ア |
屈折角より |
容器の |
|
イ |
屈折角より |
容器の |
|
ウ |
入射角より |
容器の |
|
エ |
入射角より |
容器の |
〔問4〕 前線が![]() )で
)で
暖気と
密度が
ア A,C イ A,D ウ B,C エ B,D
〔問5〕 図5は,の
図5
ア
イ
ウ
エ
2
生徒が,国際
<レポート1> 日食に
金環
日食が
図1
〔問1〕 <レポート1>から,図1の
|
|
真南の |
1週間後に |
|---|---|---|
|
ア |
12時 |
上弦の |
|
イ |
18時 |
上弦の |
|
ウ |
12時 |
下弦の |
|
エ |
18時 |
下弦の |
<レポート2> 国際
国際
蒸留により
表1
|
蒸発 |
観察 |
|---|---|
|
水溶液A |
結晶が |
|
液体B |
結晶が |
図2
〔問2〕 <レポート2>から,結晶に
|
|
結晶に |
水溶液Aの |
|---|---|---|
|
ア |
混合物 |
より |
|
イ |
化合物 |
より |
|
ウ |
混合物 |
より |
|
エ |
化合物 |
より |
<レポート3> 国際
国際
植物の
図3
〔問3〕 <レポート3>から,上下に
|
|
上下に |
光合成で |
|---|---|---|
|
ア |
光が |
道管 |
|
イ |
光が |
師管 |
|
ウ |
光が |
道管 |
|
エ |
光が |
師管 |
<レポート4> 月面での
国際
地球上で
また,重力の
図4のような
図4
〔問4〕 <レポート4>から,図4のような
|
|
上皿 |
はかりに |
|---|---|---|
|
ア |
の |
約 |
|
イ |
の |
約 |
|
ウ |
の |
約 |
|
エ |
の |
約 |
3
岩石や
<観察>を
<観察>
図1は,岩石の
図1
| (1) | 地域Aでは,特徴的な |
| (2) | 岩石Pと |
| (3) | 地域Bに |
| なお,X点の |
<結果>
(1) <観察>の
表1
|
|
岩石P |
岩石Q |
|---|---|---|
|
スケッチ |
|
|
|
特徴 |
全体的に |
全体的に |
|
教科書や |
無色 |
丸い |
(2) 図2は
〔問1〕 <結果>の
|
|
岩石Pと |
れき岩を |
|---|---|---|
|
ア |
岩石Pは |
角が |
|
イ |
岩石Pは |
角ばった |
|
ウ |
岩石Pは |
角が |
|
エ |
岩石Pは |
角ばった |
〔問2〕 <結果>の
|
|
岩石Qが |
同じ |
|---|---|---|
|
ア |
魚類と |
アンモナイト |
|
イ |
魚類と |
三葉虫 |
|
ウ |
鳥類が |
アンモナイト |
|
エ |
鳥類が |
三葉虫 |
〔問3〕 <結果>の
| ア | 流水で |
| イ | 流水で |
| ウ | 流水で |
| エ | 流水で |
〔問4〕 <結果>の
X点の
ア 高く イ 低く ウ 高く エ 低く
4
植物の
<観察>を
<観察>
| (1) | メンデルの |
| (2) | (1)から |
| (3) | (1)から |
図1
<結果1>
| (1) | <観察>の |
図2
| (2) | <観察>の |
図3
次に,<実験>を
<実験>
| (1) | 校庭で |
| (2) | 草たけが |
| (3) | 草たけが |
| (4) | (2)で |
| (5) | (3)で |
| (6) | (4)で |
| (7) | (6)の |
| (8) | (7)で |
<結果2>
| (1) | <実験>の |
| (2) | <実験>の |
| (3) | <実験>の |
図4
〔問1〕 <結果1>の
|
|
子葉の |
胚珠が |
|---|---|---|
|
ア |
1枚 |
被子 |
|
イ |
1枚 |
裸子 |
|
ウ |
2枚 |
被子 |
|
エ |
2枚 |
裸子 |
〔問2〕 <実験>の
|
|
花粉管の |
受精卵 |
|---|---|---|
|
ア |
卵 |
7本 |
|
イ |
卵 |
14本 |
|
ウ |
卵細胞 |
7本 |
|
エ |
卵細胞 |
14本 |
〔問3〕 <結果2>の
| ア | 草たけの |
| イ | 草たけの |
| ウ | 全て |
| エ | 全て |
〔問4〕 メンデルが
ただし,エンドウの
<モデル
| (1) | 親の |
| (2) | 子の |
<考察>
<モデル
<考察>の
ア AAと
5
イオンの
<実験1>を
<実験1>
| (1) | 図1のように,ビーカー①に |
図1
| (2) | 図2のように,簡易型 |
図2
<結果1>
| (1) | <実験1>の |
| (2) | <実験1>の |
〔問1〕 <結果1>の![]() ,亜鉛
,亜鉛![]() ,銅
,銅![]() ,銅
,銅![]() ,電子
,電子![]() と
と
ア A,C イ A,D ウ B,C エ B,D
〔問2〕 <結果1>の
|
|
合わせた |
合わせた |
電極Rで |
電極Sで |
|---|---|---|---|---|
|
ア |
増える。 |
減る。 |
空気より |
水に |
|
イ |
増える。 |
増える。 |
空気より |
水に |
|
ウ |
増える。 |
減る。 |
空気より |
水に |
|
エ |
減る。 |
増える。 |
空気より |
水に |
|
オ |
減る。 |
減る。 |
空気より |
水に |
|
カ |
減る。 |
増える。 |
空気より |
水に |
次に,<実験2>を
<実験2>
| (1) | ビーカー②に |
図3
| (2)水酸化 | |
| (3)(2)の | |
| (4)(3)の | |
| (5)緑色に |
<結果2>
スライドガラスには,塩化ナトリウムの
〔問3〕 <実験2>の
ただし,<化学
<化学
〔問4〕 <実験2>の
6
物体の
<実験>を
<実験>
| (1) | 形が |
| (2) | レールA上の |
| (3) | (2)で |
| (4) | ストロボ |
| (5) | レールBに |
| (6) | レールAと |
図1
レールA
レールB
図2
レールA
レールB
<結果>
|
区間 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
⑩ |
⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時間 [s] |
0- |
0.1- |
0.2- |
0.3- |
0.4- |
0.5- |
0.6- |
0.7- |
0.8- |
0.9- |
1.0- |
|
レールAに |
3.6 |
7.9 |
10.4 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
10.8 |
10.6 |
9.0 |
5.6 |
1.7 |
|
レールBに |
3.2 |
5.6 |
8.0 |
10.5 |
10.9 |
10.9 |
10.6 |
9.5 |
6.7 |
4.2 |
1.8 |
〔問1〕 <結果>から,レールA上の
ア
イ
ウ
エ
〔問2〕 <結果>から,小球が
| ア力の | |
| イ力の | |
| ウ力の | |
| エ力の |
〔問3〕 図3の
図3
〔問4〕 <実験>の
|
|
点bと |
点cと |
|---|---|---|
|
ア |
点bの |
点fの |
|
イ |
点bの |
ほぼ |
|
ウ |
ほぼ |
点fの |
|
エ |
ほぼ |
ほぼ |