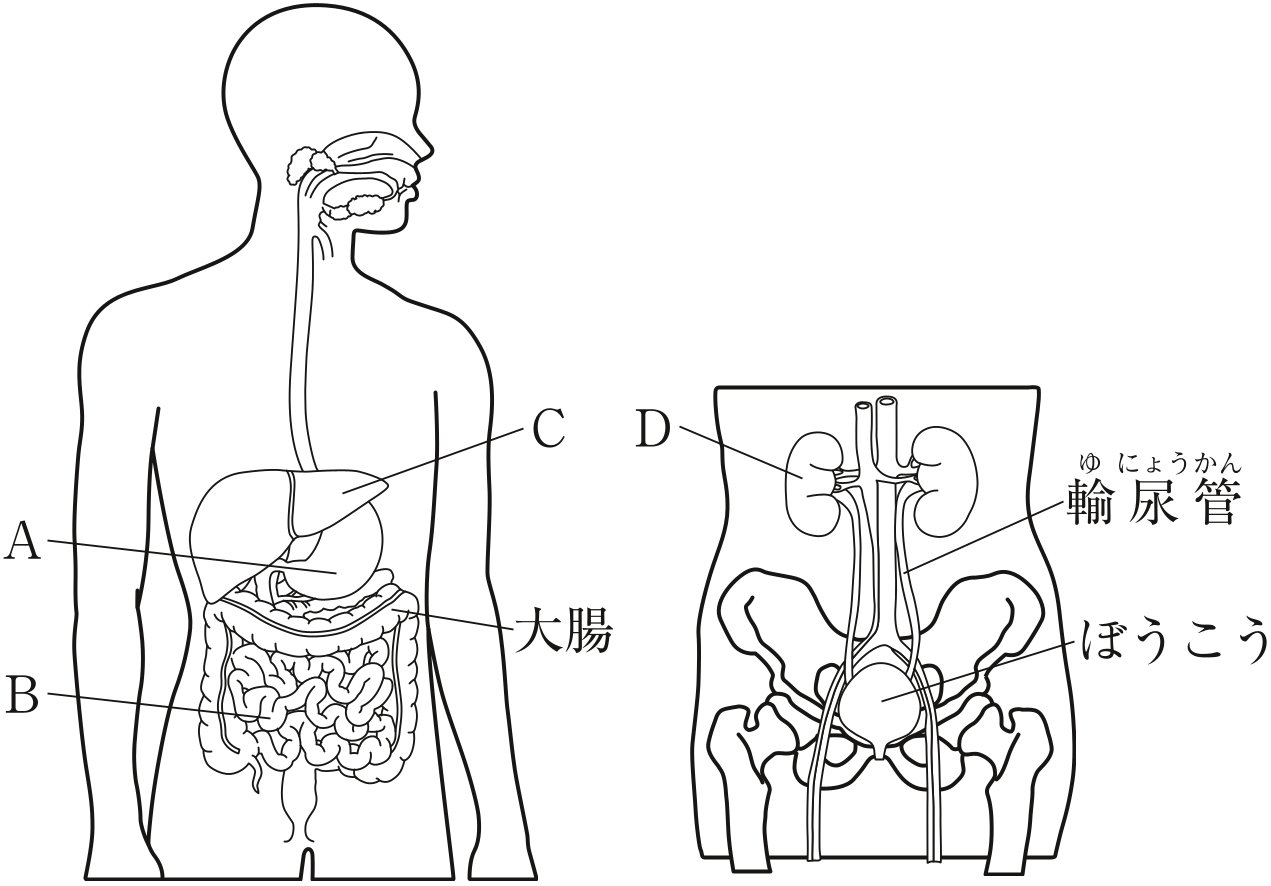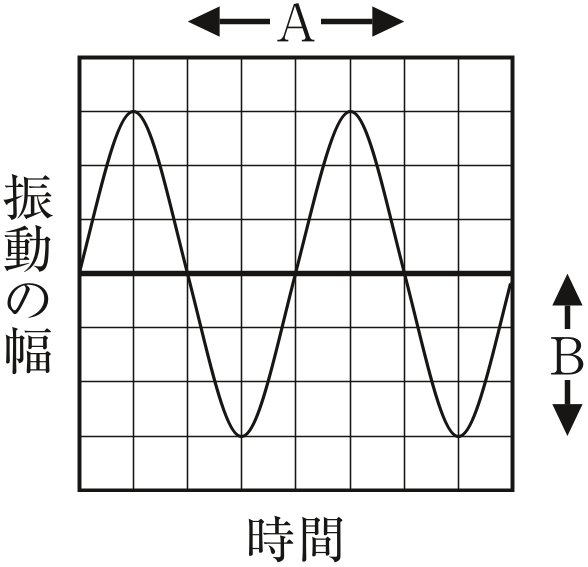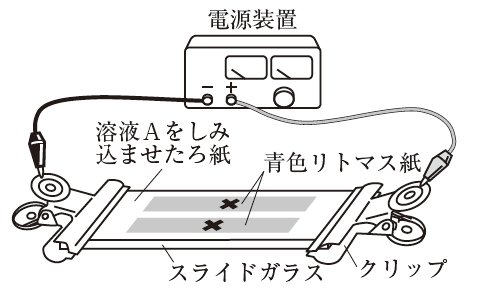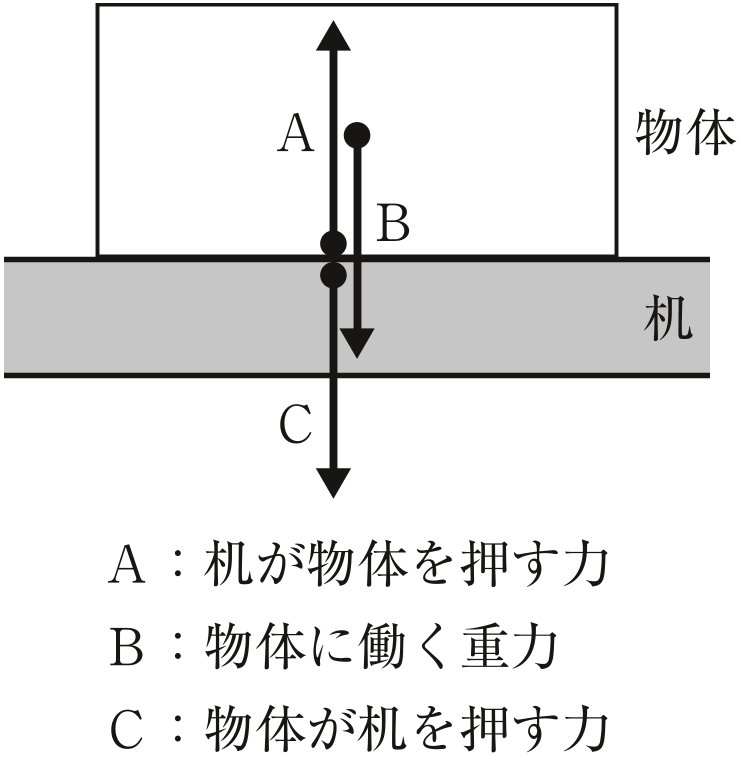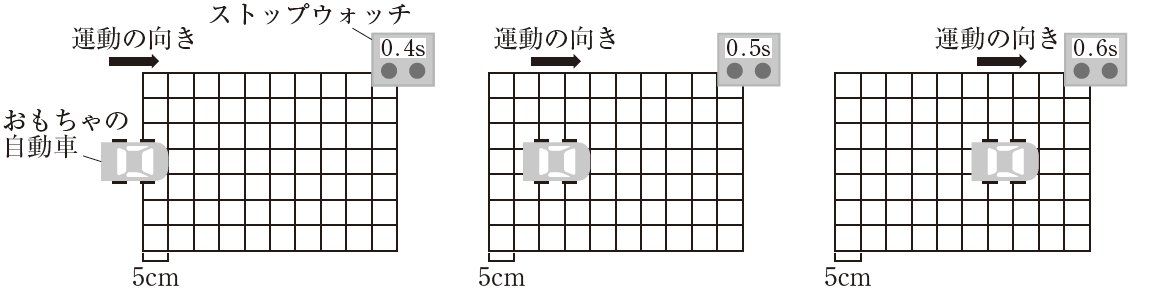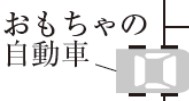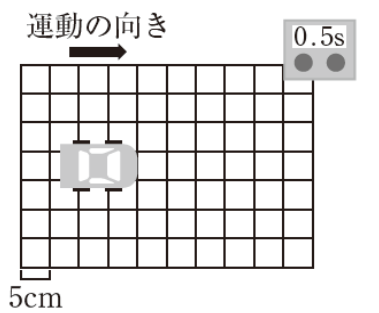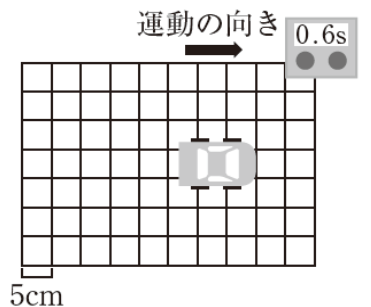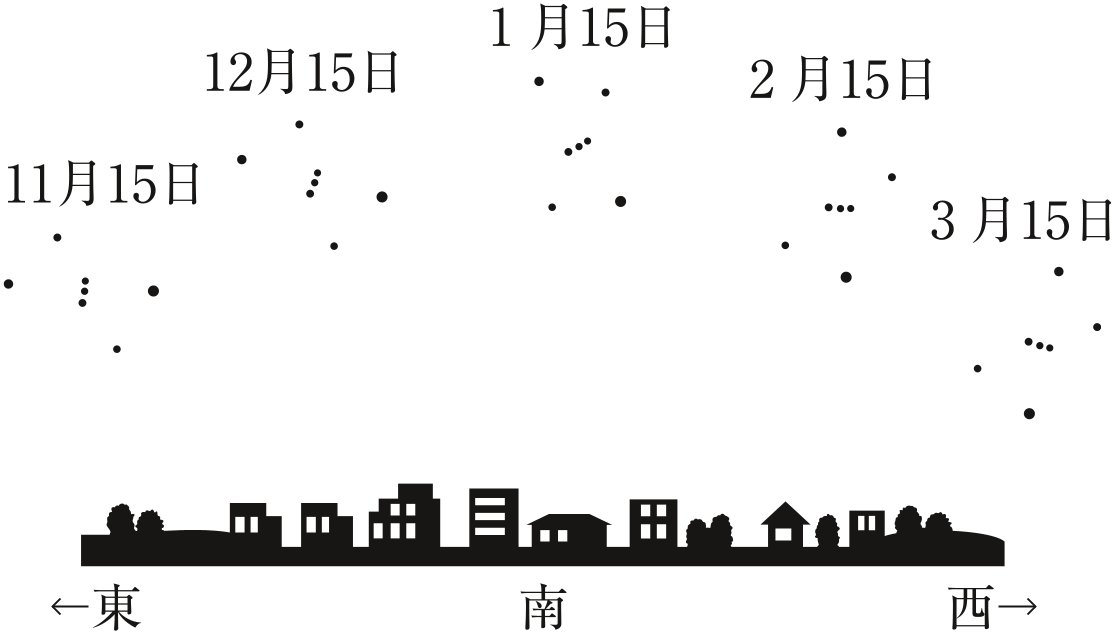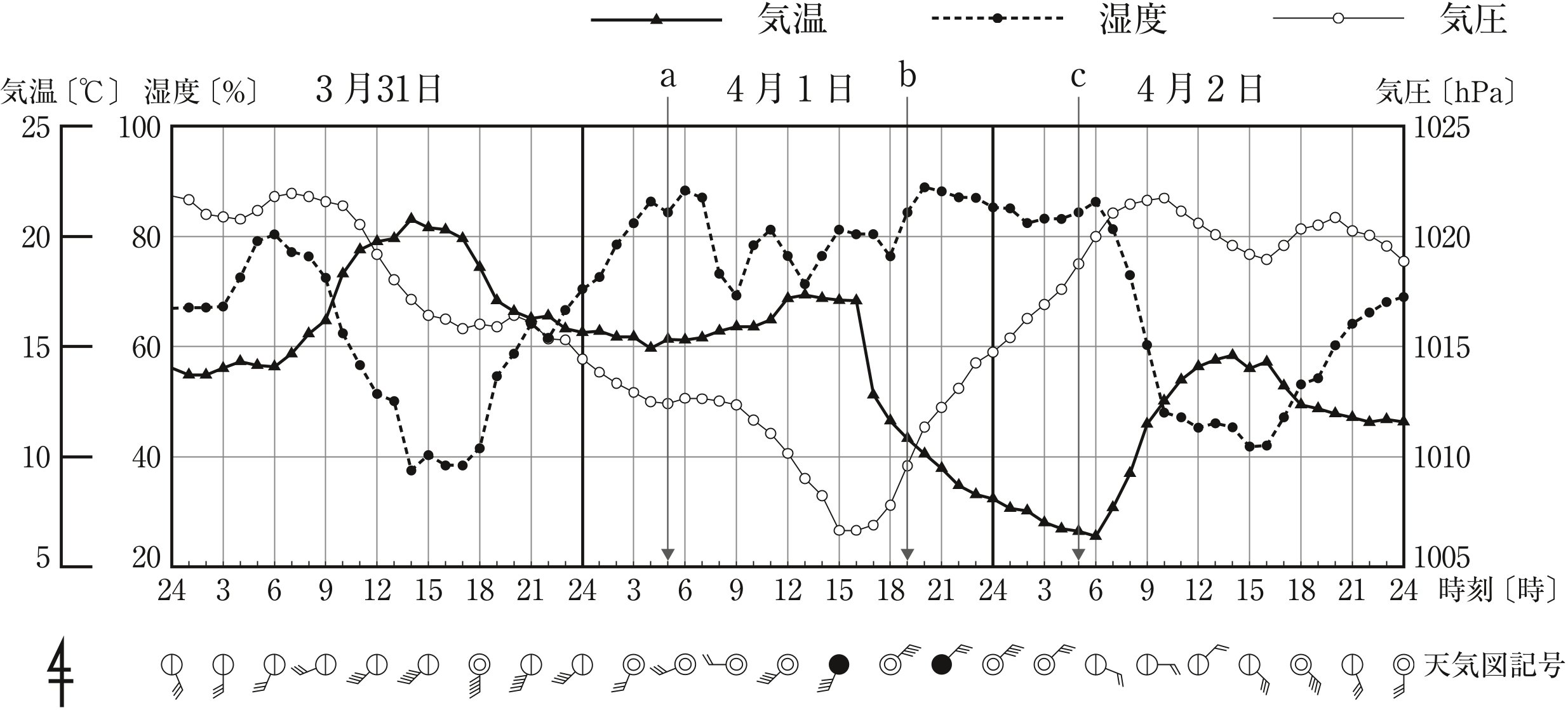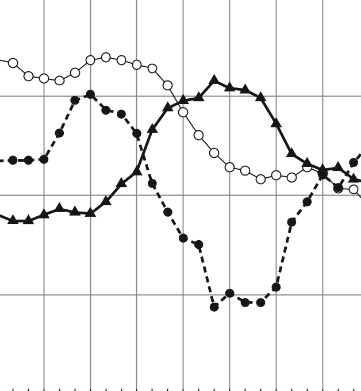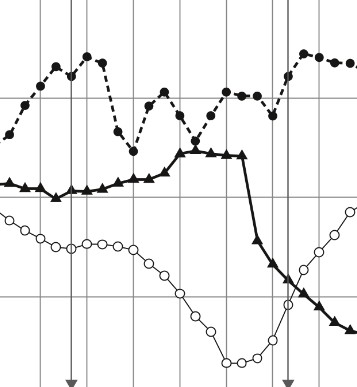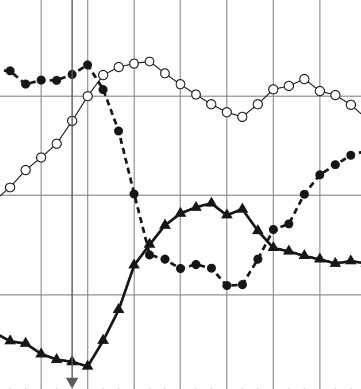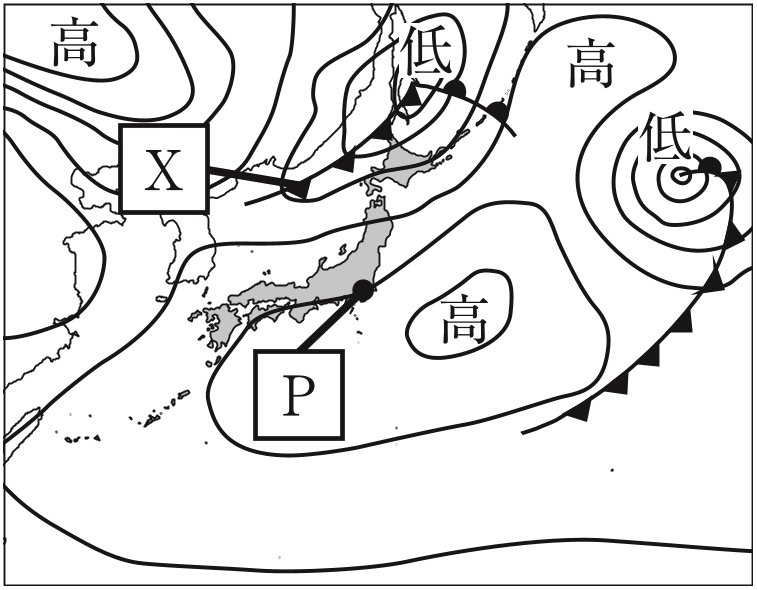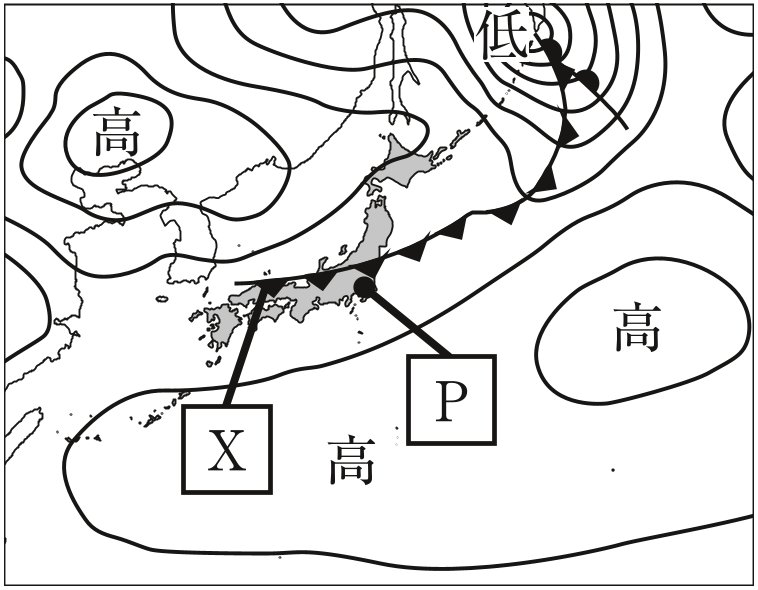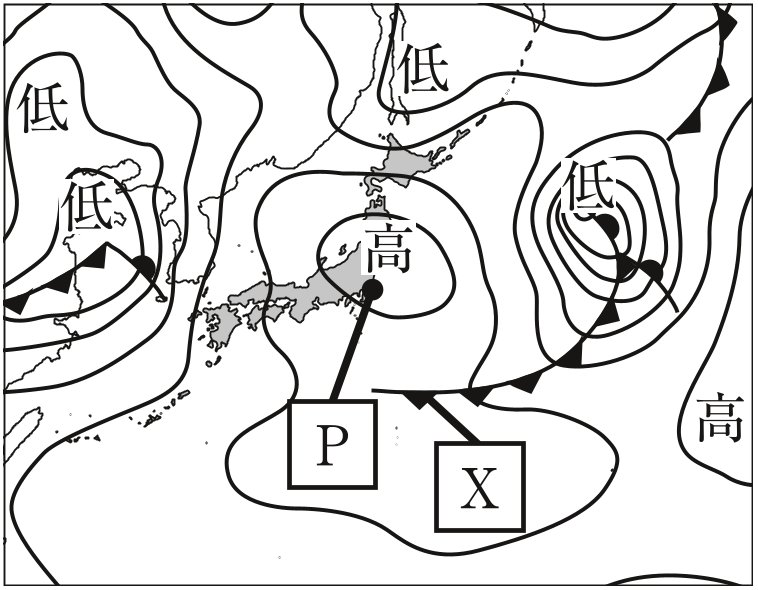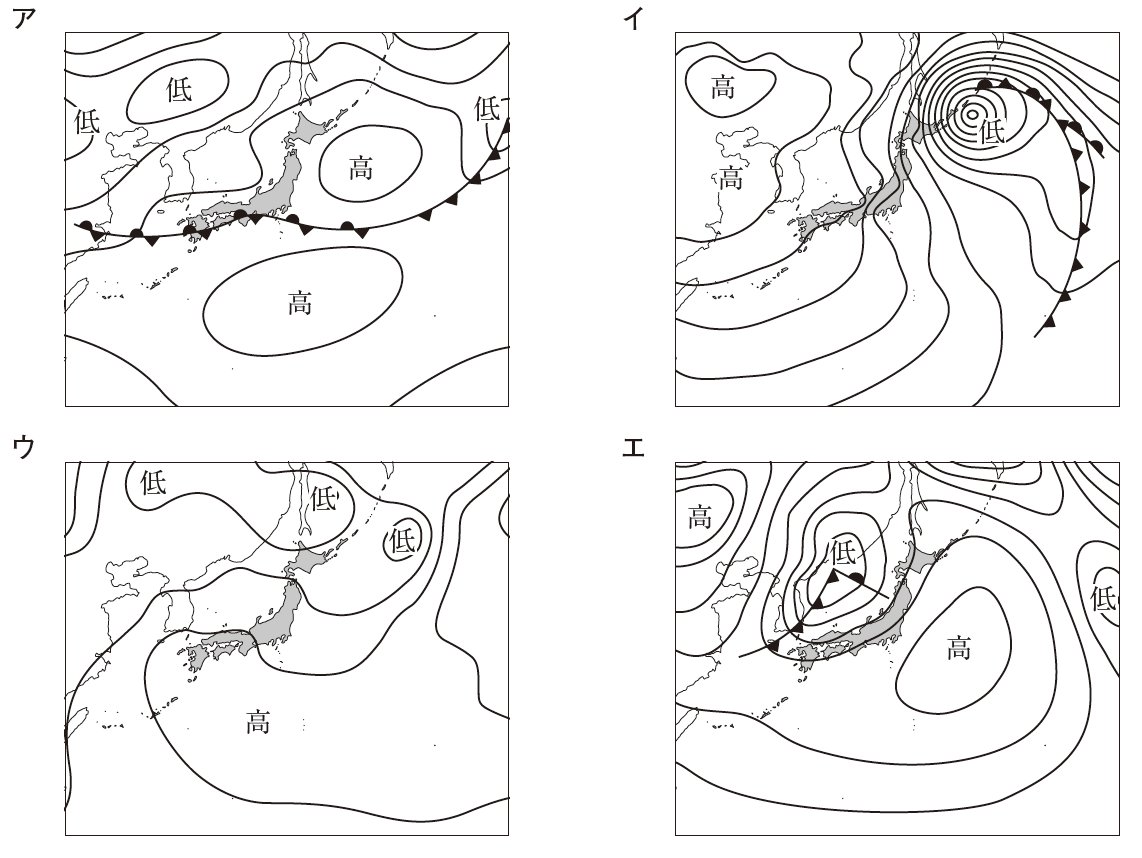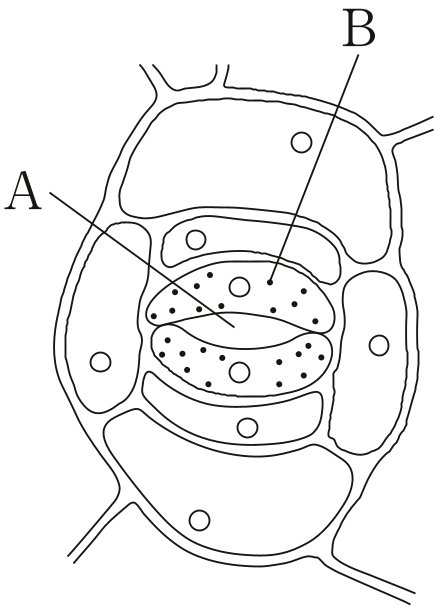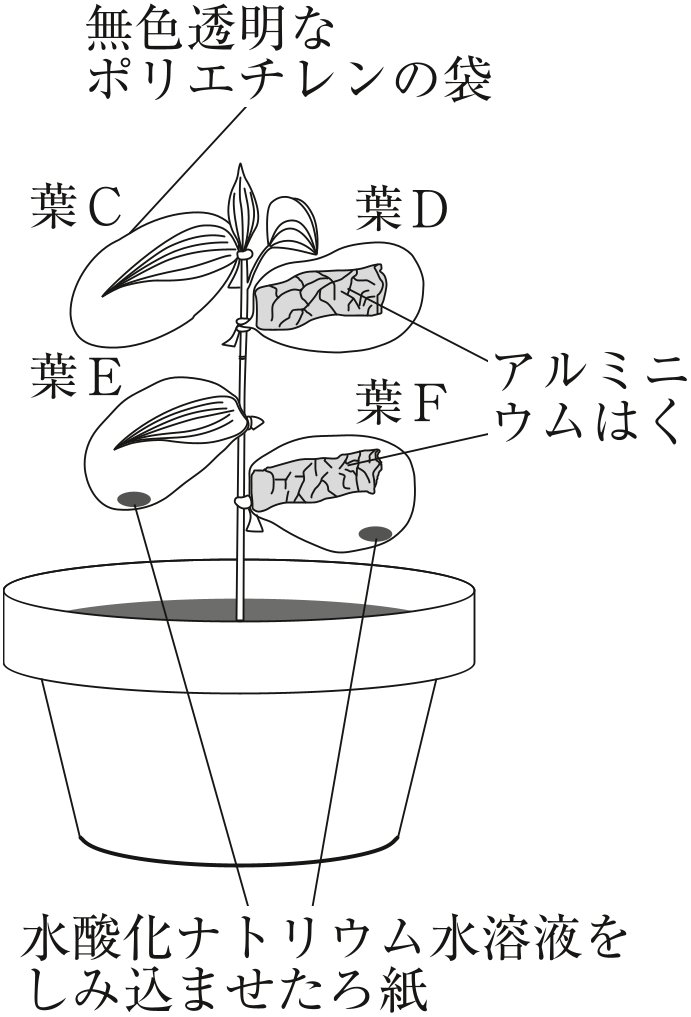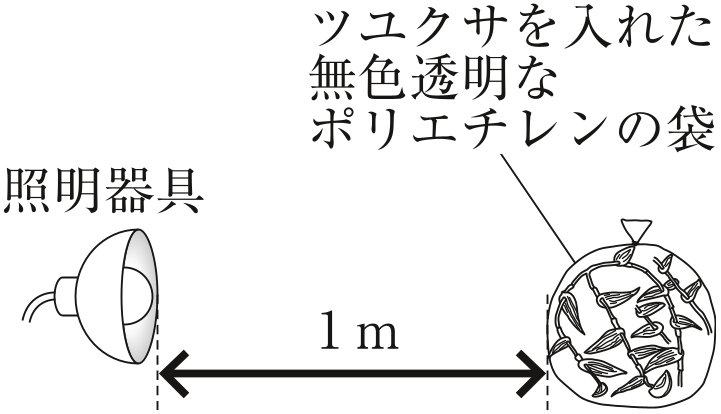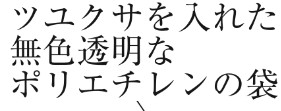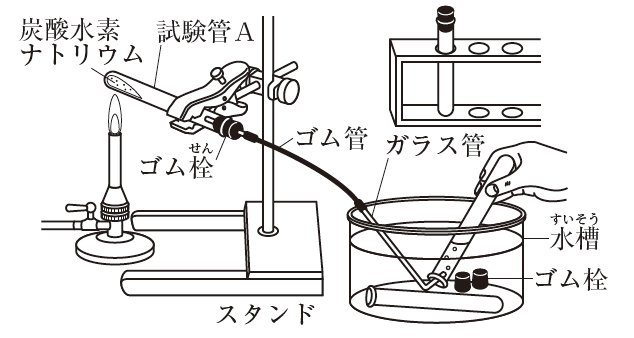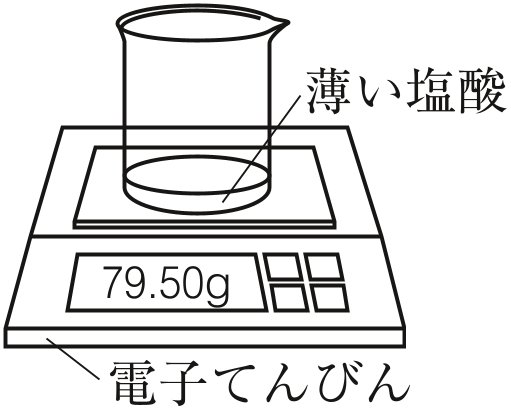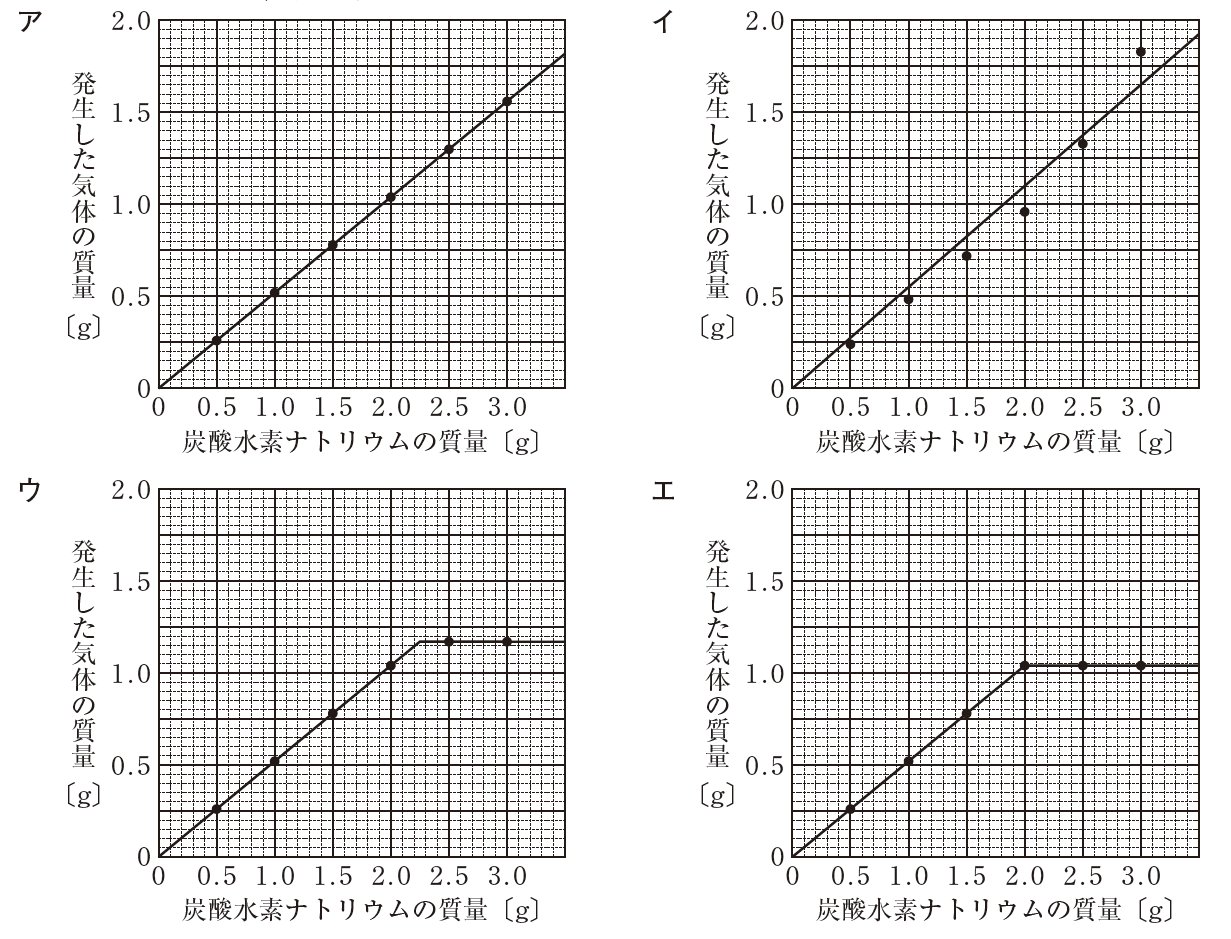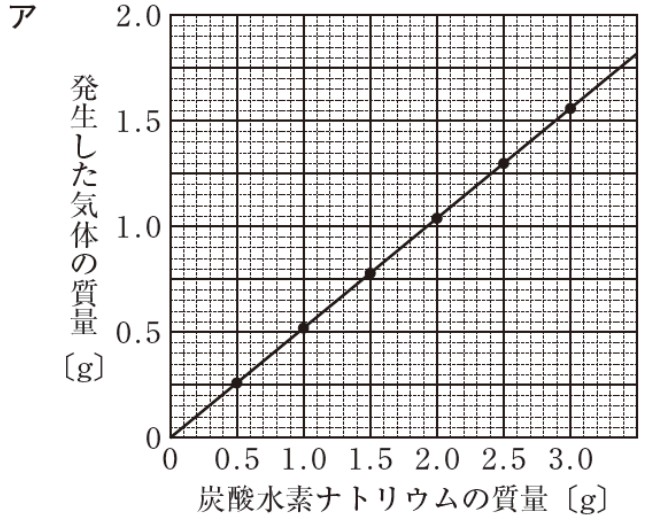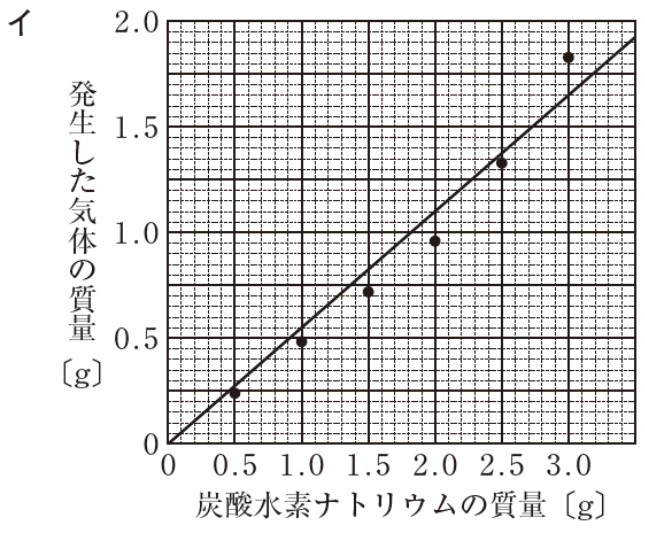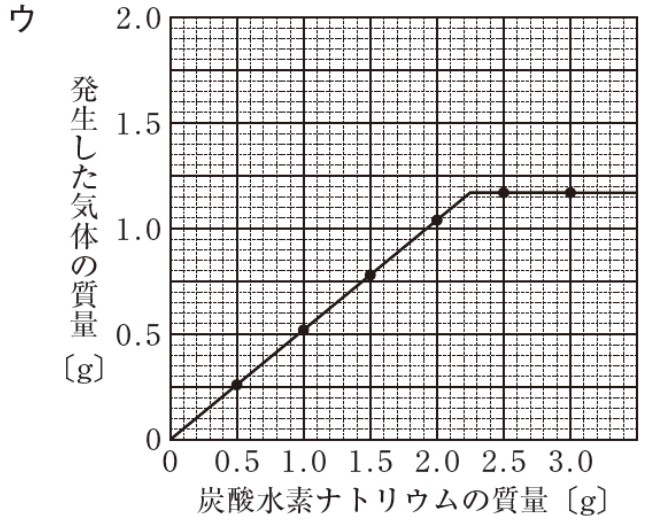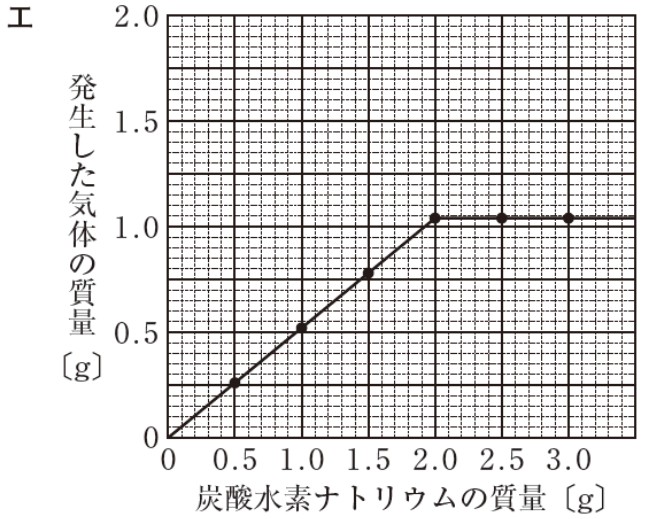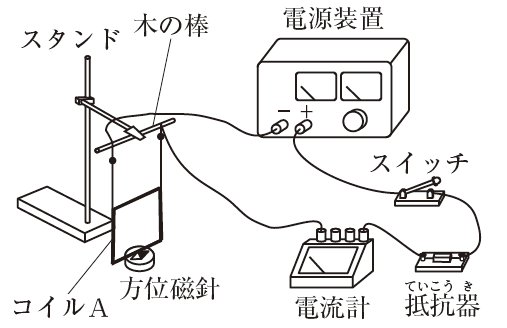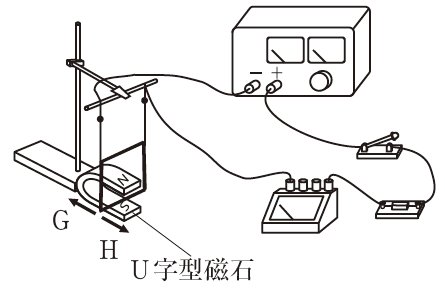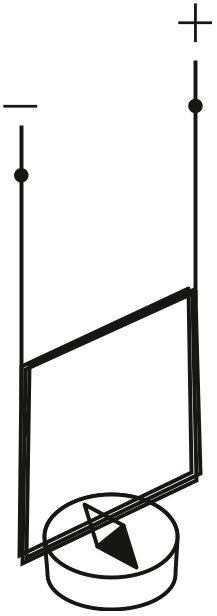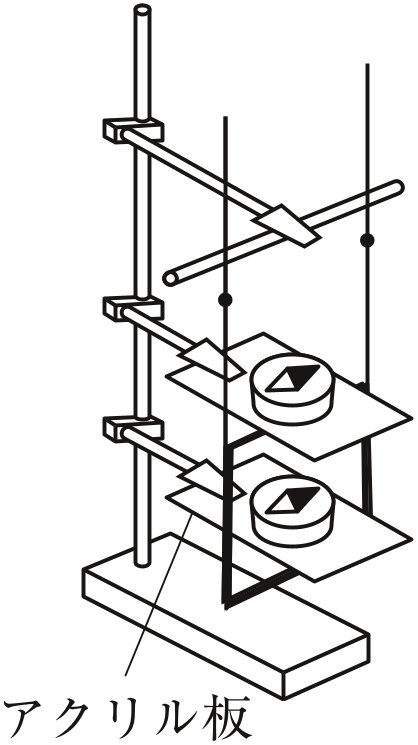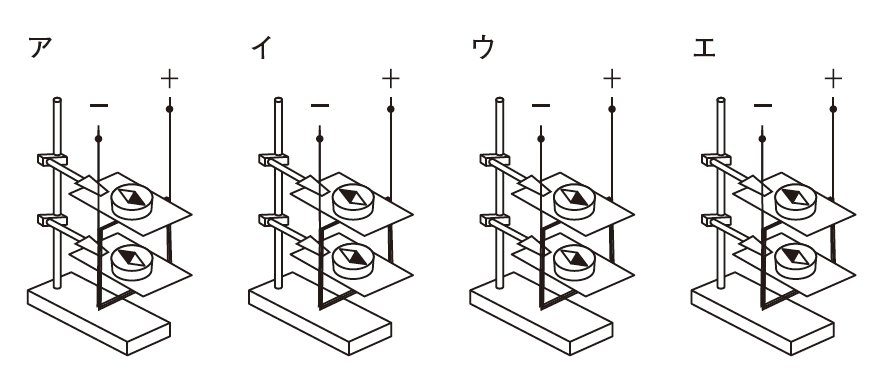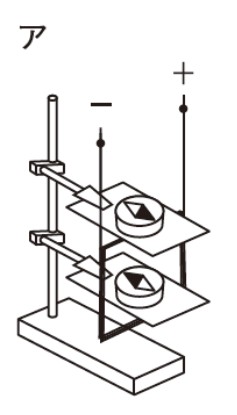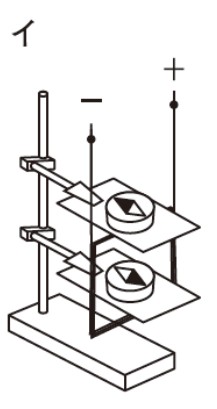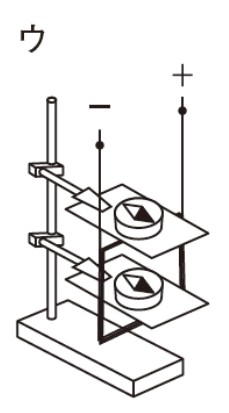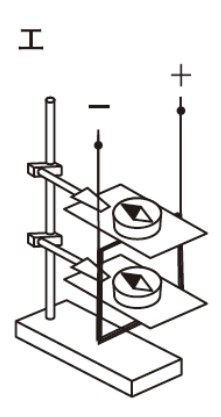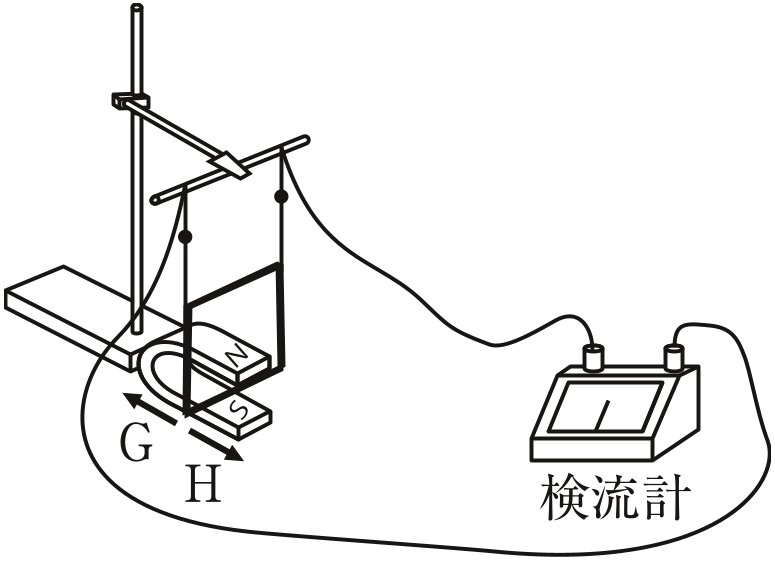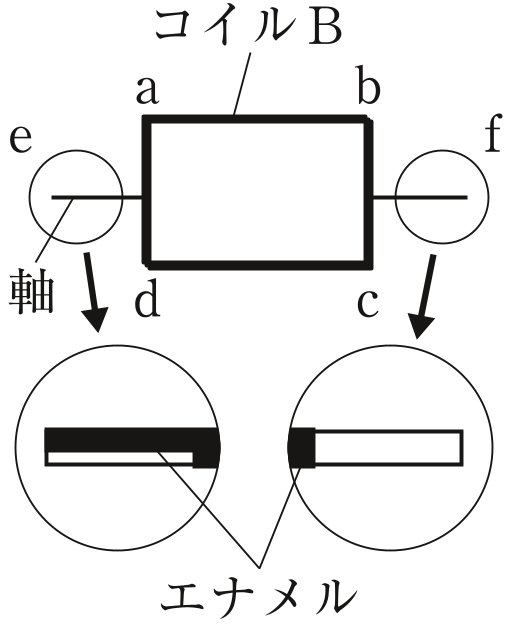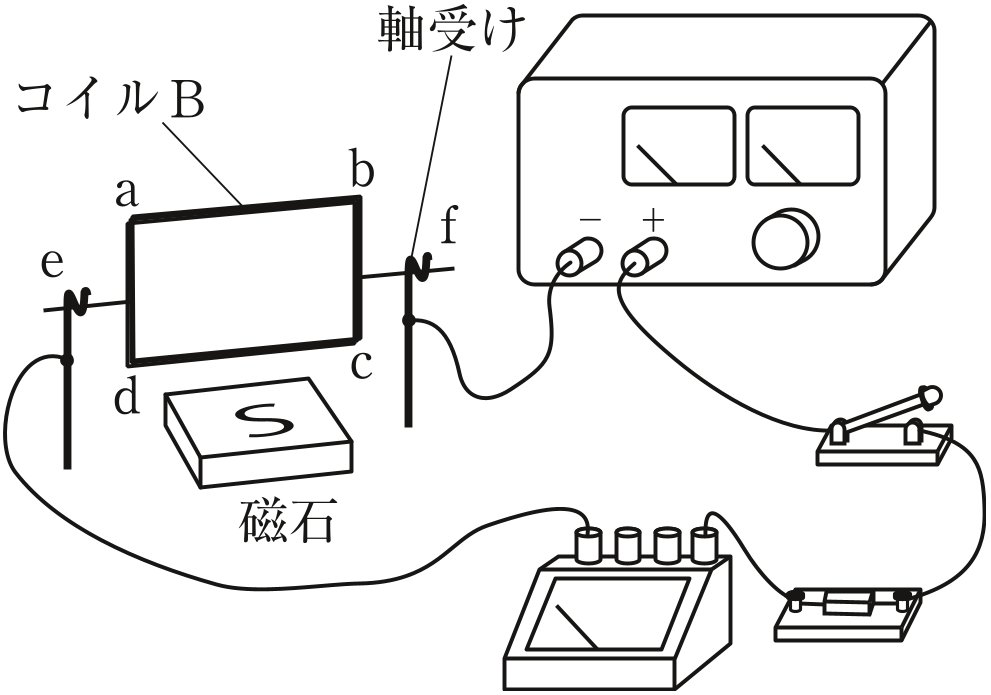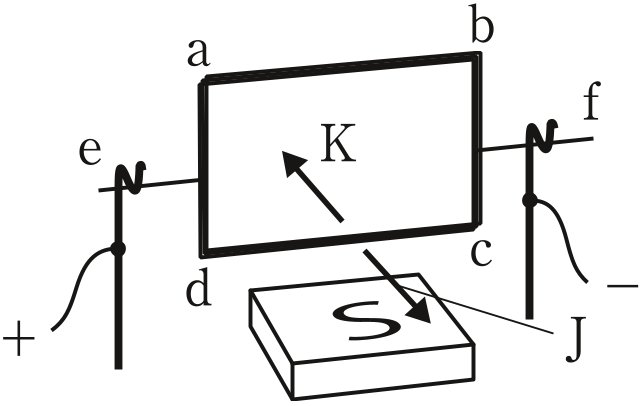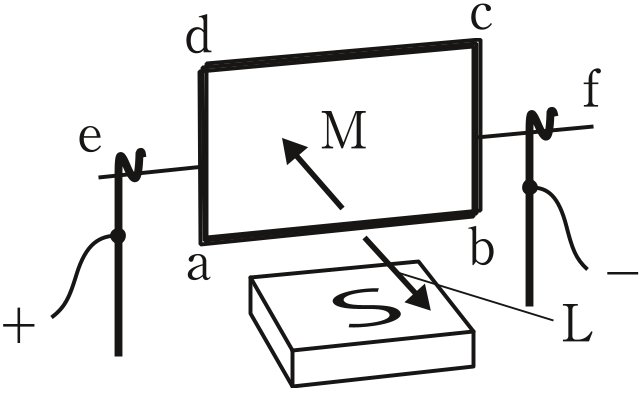令和
注意
| 1 | 問題は |
| 2 | 検査 |
| 3 | 声を |
| 4 | 計算が |
| 5 | 答えは |
| 6 | 答えは |
| 7 | 答えを |
| 8 | 答えを |
| 9 | 受検 |
| 10 | 解答 |
問題は
1
次の
〔問1〕 図1は,ヒトの
図1
ア A,C
イ A,D
ウ B,C
エ B,D
〔問2〕 音さXと
図2
| ア | Aは |
| イ | Aは |
| ウ | Aは |
| エ | Aは |
〔問3〕 表1は,ある
ただし,地震の
表1
|
観測地点 |
震源からの距離 |
初期微動の始まった時刻 |
主要動の始まった時刻 |
|---|---|---|---|
|
A |
|
10時 |
10時 |
|
B |
|
10時 |
10時 |
|
C |
|
10時 |
10時 |
ア 10時
イ 10時
ウ 10時
エ 10時
〔問4〕 スライドガラスの
図3
| ① | ア エタノール |
| ② | ア イ ウ エ |
〔問5〕 エンドウの
ただし,種子の
ア AAと
イ AAと
ウ Aaと
エ Aaと
〔問6〕 図4の
ただし,図4では
図4
|
|
力のつり合いの関係にある2力 |
作用・反作用の関係にある2力 |
|---|---|---|
|
ア |
Aと |
Aと |
|
イ |
Aと |
Aと |
|
ウ |
Aと |
Aと |
|
エ |
Aと |
Aと |
2
生徒が,毎日の
<レポート1> しらす
食事の
しらす漁の
表1
|
グループ |
生物 |
|---|---|
|
A |
イワシ・ |
|
B |
エビ・ |
|
C |
タコ・ |
|
D |
二枚貝の |
〔問1〕 <レポート1>から,生物の
表1の
| ① | ア A イ Aと |
| ② | ア C イ D ウ Cと |
<レポート2> おもちゃの
ぜんまいで
ストップウォッチの
図1
〔問2〕 <レポート2>から,おもちゃの
ア イ ウ エ
<レポート3> プラスチック
ペットボトルを
水
また,ペットボトルに
表2
|
プラスチックの |
密度 |
|---|---|
|
ポリエチレン |
|
|
ポリスチレン |
|
|
ポリエチレン |
|
|
ポリプロピレン |
|
〔問3〕 <レポート3>から,食塩水に
ただし,ラベルは
ア ポリエチレン
イ ポリスチレン
ウ ポリエチレン
エ ポリプロピレン
<レポート4> 夜空に
毎日
方位
図3
〔問4〕 <レポート4>から,2月
ア 午前
イ 午前
ウ 午後
エ 午後
3
天気の
<観測>を
<観測>
天気の![]() )は
)は
<結果>
図1
図2 3月
図3 4月
図4 4月
〔問1〕 <結果>の
ア
イ
ウ
エ
〔問2〕 <結果>の
日中の
| ① | ア 快晴 イ 晴れ ウ くもり |
| ② | ア 東寄りの |
| ③ | ア 気温 イ 湿度 ウ 気圧 |
〔問3〕 <結果>から,4月
①
| ア | 気温が |
| イ | 気温が |
| ウ | 気温が |
| エ | 気温が |
②
| ア | 地上から |
| イ | 地上から |
| ウ | 上空から |
| エ | 上空から |
〔問4〕 日本には,季節の
4
ツユクサを
<観察>を
<観察>
| (1) | ツユクサの |
| (2) | (1)の |
| (3) | (1)の |
| (4) | (3)の |
<結果1>
| (1) | <観察>の |
図1
| (2) | <観察>の |
〔問1〕 <結果1>で
|
|
Aに |
Bに |
|---|---|---|
|
ア |
酸素,二酸化 |
植物の |
|
イ |
酸素,二酸化 |
植物の |
|
ウ |
細胞の |
植物の |
|
エ |
細胞の |
植物の |
次に,<実験1>を
<実験1>
| (1) | 無色 |
| (2) | 図2のように,葉D,葉Fは,それぞれ |
図2
| (3) | <実験1>の |
| (4) | <実験1>の |
| (5) | 切り取った |
<結果2>
|
|
色の |
|---|---|
|
葉C |
青紫色に |
|
葉D |
変化 |
|
葉E |
変化 |
|
葉F |
変化 |
〔問2〕 <実験1>の
①
| ア | 葉に |
| イ | 葉に |
| ウ | 葉に |
②
| ア | 葉Cと |
| イ | 葉Cと |
| ウ | 葉Dと |
次に,<実験2>を
<実験2>
| (1) | 明るさの |
| (2) | 袋G〜 |
| (3) | 袋Gは,暗室に |
| (4) | 袋Hは,図3のように,照明 |
図3
(5)袋Iは,図3のように,照明
<結果3>
|
|
暗い → 明るい | |||
|---|---|---|---|---|
|
袋G |
袋H |
袋I | ||
|
二酸化 |
実験前 |
|
|
|
|
実験後 |
|
|
| |
〔問3〕 <結果3>から,袋Hと
①
| ア | 呼吸に |
| イ | 呼吸に |
| ウ | 袋Hも |
②
| ア | デンプンなどの |
| イ | デンプンなどの |
| ウ | 袋Hと |
5
物質の
<実験1>を
<実験1>
| (1) | 乾いた |
図1
| (2) | 図1のように,試験管 |
| (3) | ガラス管を |
| (4) | 気体を |
| (5) | 加熱後の |
| (6) | 水 |
<結果1>
塩化
| …… | 青色から |
火の
| …… | 線香の |
火の
| …… | 変化 |
石灰水の
| …… | 白く |
加熱後の
| …… |
水への
| …… | 炭酸 |
〔問1〕 <実験1>の
①
| ア | 試験管 |
| イ | 試験管 |
| ウ | 試験管 |
| エ | 試験管 |
②
| ア | 炭酸 |
| イ | 炭酸 |
| ウ | 炭酸 |
〔問2〕 <実験1>の
①
| ア | 酸化銀を |
| イ | マグネシウムを |
| ウ | 鉄と |
| エ | 鉄粉と |
図2
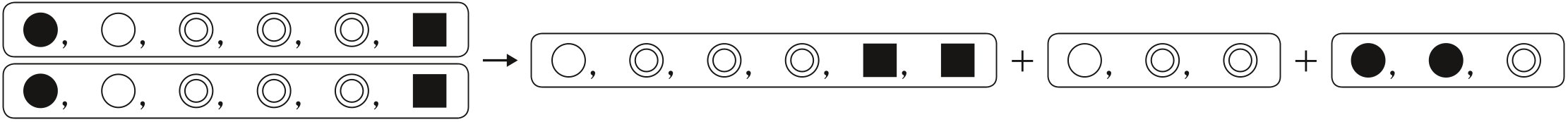
② ア ● イ ○ ウ ◎ エ ■
次に,<実験2>を
<実験2>
| (1) | 乾いた |
図3
| (2) | 炭酸 |
| (3) | <実験2>の |
<結果2>
|
反応前の |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
炭酸 |
|
|
|
|
|
|
|
反応後の |
|
|
|
|
|
|
〔問3〕 <結果2>から,炭酸
〔問4〕 <実験2>で
ただし,発生
6
電流と
<実験1>を
<実験1>
| (1) | 木の |
| (2) | コイルAの |
| (3) | 電源 |
図1
| (4) | <実験1>の |
図2
<結果1>
| (1) | <実験1>の |
図3
| (2) | <実験1>の |
〔問1〕
図4
次に,<実験2>を
<実験2>
| (1) | 図5のように |
図5
| (2) | コイルAを |
<結果2>
コイルAを
〔問2〕 <結果2>から,コイルAに
次に,<実験3>を
<実験3>
| (1) | 図6に |
| なお,図6の |
図6
| (2) | 図7のように,磁石の |
図7
<結果3>
コイルBは,同じ
〔問3〕 <実験3>の
ア の
イ の
ウ の
エ の
〔問4〕 <結果3>に
図8
図9
図8の
①
| ア | c→dの |
| イ | d→cの |
| ウ | 電流が |
②
| ア | Jの |
| イ | Kの |
| ウ | 力を |
③
| ア | a→bの |
| イ | b→aの |
| ウ | 電流が |
④
| ア | Lの |
| イ | Mの |
| ウ | 力を |